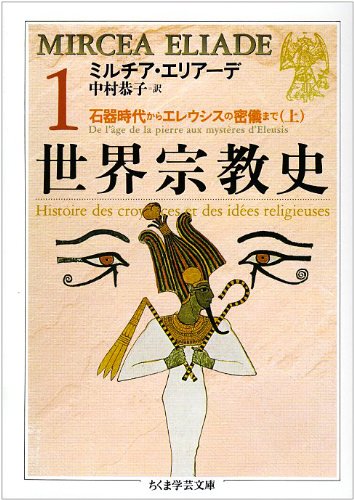- 著者
- 竹中 哲夫
- 出版者
- Brewing Society of Japan
- 雑誌
- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)
- 巻号頁・発行日
- vol.104, no.11, pp.858-865, 2009 (Released:2016-02-15)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 1
味噌,醤油,納豆製造時に副生する蒸煮廃液(大豆煮汁)は排水処理にコストがかかるので,その有効利用が求められている。そこで,著者は大豆煮汁に含まれるアンギオテンシンI変換酵素(ACE)阻害物質として,ニコチアナミンを分離・同定した。さらに,このニコチアナミンを高血圧自然発症ラット(SHR)に投与して,降圧作用を認めた。したがって,大豆煮汁は脂質やタンパク質などの夾雑物が少ないので,ニコチアナミンの供給源として期待できるので解説いただいた。
1 0 0 0 IL-5の好酸球に対する延命効果とテオフィリンによるその抑制効果
近年、気管支喘息は、慢性剥離性好酸球性気管支炎とも呼ばれ、気道の慢性炎症において好酸球が重要な役割を演じていると言われている。好酸球が、その機能を十分に発揮するためには、遊走して来た局所における寿命の延長が重要で、気管支喘息の治療戦略においても、遊走して来た局所における好酸球の寿命を抑制することは有用な治療手段である。本研究では、サイトカインのなかで好酸球に対して最も強力に作用するIL-5を用いて、IL-5による好酸球寿命延長効果を確認するとともに、既存の抗喘息薬としてテオフィリンを取り上げ、IL-5の好酸球寿命延長効果に対するテオフィリンの抑制効果の有無を検討し、さらに、そのメカニズムにapoptosisが関与してるかどうかをDNAのfragmentationを指標にして検討を加えた。1.IL-5による好酸球寿命延長効果:末梢血より分離した好酸球に培養液のみを加えたコントロール群と、好酸球にIL-5(10ng/ml)のみを加えたIL-5単独群で好酸球の生存細胞数の推移を検討した。その結果、コントロール群の生存細胞は、day4において24.4%まで急減し、dya7で全ての好酸球が死滅した。一方、IL-5単独群では、day7での生存細胞数は94.2%とやや低下したが、day10においてさえも%生存細胞数は83.8%維持されていた。以上の結果により、IL-5は、好酸球の寿命を著明に延長し、IL-5が好酸球寿命延長効果を有することを確認した。2.IL-5の好酸球寿命延長効果に対するテオフィリンの抑制効果:好酸球に、IL-5を加えたIL-5単独群のday4における%生存細胞数を100%として生存率を計算したところ、IL-5+テオフィリン群のday4における%生存細胞数は、63.1±3.4%(mean±SEM)で両者間に明らかな有意差(t<0.005)を認め、テオフィリンは、IL-5の好酸球寿命延長効果に対して抑制効果があることが判明した。3.テオフィリンによるIL-5の好酸球寿命延長効果に対する抑制機構の検討-apoptosisの関与について:テオフィリンは、IL-5の好酸球寿命延長効果を抑制したが、その機構がapoptosisによるものかどうかを調べるために、IL-5単独、コントロール、IL-5+テオフィリン、IL-5+dibutyryl-cAMP(d-cAMP)、IL-5+デキサメタゾンの好酸球から抽出したDNAのfragmentationを指標にしてapoptosisの関与を検討した。その結果、IL-5+テオフィリン、IL-5+d-cAMP、IL-5+デキサメタゾンでDNAのfragmentationが見られ、これらの薬剤によるapoptosisの誘導が示唆された。IL-5+テオフィリンとIL-5+d-cAMPでDNAのfragmentationが見られたことは、テオフィリンによるIL-5の好酸球寿命延長効果に対する抑制機構にapoptosisが関与し、さらにテオフィリンは、その薬理作用の中で細胞内cAMP上昇を介することにより好酸球に対してapoptosisを誘導していると考えられた。
1 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1905年01月26日, 1905-01-26
1 0 0 0 OA DPP-4阻害薬(シタグリプチン)による薬剤熱が疑われた1例
- 著者
- 阿武 孝敏 柱本 満 田邊 昭仁 中嶋 久美子 岡内 省三 亀井 信二 松木 道裕 宗 友厚 加来 浩平
- 出版者
- 一般社団法人 日本糖尿病学会
- 雑誌
- 糖尿病 (ISSN:0021437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.5, pp.292-297, 2013 (Released:2013-06-07)
- 参考文献数
- 15
2009年に上市されたDipeptidyl peptidase-4(DPP-4)阻害薬は,2型糖尿病薬物療法の選択肢の一つとして,その使用が急速に拡大している.一方,DPP-4はリンパ球やマクロファージ上に発現しているCD26と同一分子であるため,DPP-4阻害薬が免疫系に影響する可能性が以前より指摘されていた.今回我々はシタグリプチン投与が原因と疑われる薬剤熱の症例を経験した.発熱と同期して初期の炎症マーカー(IL-1β,IL-6,TNF-α)とCRPの上昇を認め,シタグリプチン投与が,マクロファージを介して初期の炎症性サイトカイン産生を亢進させ,薬剤熱を発症した可能性が示唆された.
1 0 0 0 OA シミュレーテッド・アニーリング法を用いた板取計画の最適化
- 著者
- 松田 浩一 高井 幸秀 吉田 耕作 西村 勝 松山 峯雄 澤田 泰明
- 出版者
- The Society of Instrument and Control Engineers
- 雑誌
- 計測自動制御学会論文集 (ISSN:04534654)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.5, pp.544-552, 1995-05-31 (Released:2009-03-27)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 1 2
This paper describes about cutting stock scheduling system using simulated annealing method. The cutting stock problem is that of combinatorial optimization. The following functions are needed for the cutting stock scheduling system.1) Balance adjusting function for productivity, yield rate and delivery time.2) The results of scheduling have to satisfy constraint condition of coil cutting machine.3) There is time limitation for making cutting stock schedule. To overcome these problem, we realize new cutting stock scheduling system through following methods.1) Weights for each evaluated item are introduced and sum of these items are minimized by simulated annealing.2) The new neighborhood structure is developed for this problem which can satisfy constraint condition of coil cutting machine.3) The adjusting parameter for calculation time is newly introduced for Huang's annealing schedule, so that we can select best solution under the limit of calculation time.This cutting stock scheduling system is applied to plate plant and used as one of production planning system.
1 0 0 0 IR 横光利一における「父なるもの」
- 著者
- 日置 俊次
- 出版者
- 青山学院大学
- 雑誌
- 青山学院大学文学部紀要 (ISSN:05181194)
- 巻号頁・発行日
- no.46, pp.19-39, 2004
- 著者
- 髙柳 春希
- 出版者
- 日本湿地学会
- 雑誌
- 湿地研究 (ISSN:21854238)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.177-181, 2018 (Released:2019-04-01)
- 参考文献数
- 17
スクミリンゴガイは国内外で問題視されている外来生物の一つである.スクミリンゴガイの防除策の一つとして,卵塊の掻き落とし作業が行われるが,卵塊の分布特性を理解せずして効率的な作業は望めない.そこで本研究では滋賀県野洲市の水路を対象に,スクミリンゴガイ卵塊の分布様式を調査した.調査の結果,卵塊は集中分布を示した.さらに卵塊は水路の水深が深くなるにつれ減少し,水路の幅が広くなるほど多くなることが判明した.これらの情報はスクミリンゴガイを駆除する上で重要な手がかりになると示唆された.
1 0 0 0 OA 大腿骨頸部骨折入院時の熱発
- 著者
- 萩尾 慎二 黒佐 義郎 小島 秀治 相澤 充 青山 広道 前原 秀二 三宅 諭彦 藤田 浩二 多川 理沙 佐藤 智哉
- 出版者
- 一般社団法人 日本農村医学会
- 雑誌
- 日本農村医学会学術総会抄録集 第54回日本農村医学会学術総会 (ISSN:18801749)
- 巻号頁・発行日
- pp.256, 2005 (Released:2005-11-22)
高齢の大腿骨頸部骨折患者が入院時に熱発を呈することをしばしば経験する。また大腿骨頸部骨折患者の主な合併症として肺炎や尿路感染症が挙げられる。今回、入院時に採取した尿の細菌培養を行ない熱発と尿路感染(腎盂腎炎)との関係を調査した。【方法】大腿骨頸部骨折患者を入院時熱発群(術前最高体温38.0以上)と非熱発群に分け年齢、性別、入院時血液検査(白血球数、CRP、好中球%)、尿沈渣による白血球数、尿培養結果、入院時胸部レントゲン像による肺炎の有無、術後最高体温との関連を調査した。【結果】調査数15症例(平均82歳、男性1例、女性14例)のうち術前38.0度以上の熱発が見られたのは4例(全て女性、平均78.8歳)だった。熱発群ではCRPが平均3.5と上昇していた(非熱発群は平均1.6)。血液検査の白血球数、尿沈渣による白血球数、胸部レントゲン写真による肺炎像の有無、術後最高体温については非熱発群との差を認めなかった。尿培養では熱発群2例(50%)、非熱発群4例(36.4%)で陽性であり計7例中大腸菌が3例で検出された。【考察】大腿骨頸部骨折患者は大多数が高齢者であり、複数の合併症を有することが多い。入院後患者が熱発したとき、その原因として(1)骨折自体による熱発 (2)肺炎 (3)腎盂腎炎などが考えられる。受傷後、臥位が続けば肺炎、腎盂腎炎を併発するリスクは高くなると予想されるが、今回の調査では入院時検査において発熱群と非発熱群との差を認めなかった。その理由として(1)感染症の併発の有無を問わず骨折自体による熱発が多くの症例でみられる (2)入院後早期に手術が施行(平均手術待機日数1.5日)され、その際に使用される抗生剤により感染症が治癒したと考えた。尿培養では一般的に言われているように大腸菌が検出されることが多かった。我々の施設では術後抗生剤としてセファメジンα(セファゾリンナトリウム:第一世代セフェム)を使用しているが、今回の調査中に培養で検出された6菌種のうちセファメジンに感受性がなかったのは1菌種のみであった。 熱発がないにも関わらず尿培養陽性だった例(無症候性細菌尿)が多くみられたことより、熱発時に細菌尿を認めたからといって熱源の探索を怠ると他の原因の見落としにつながる危険性が十分にあると思われた。
1 0 0 0 OA 東北電力沼沢沼発電所
- 著者
- 亀ヶ森 恵司
- 出版者
- 一般社団法人 ターボ機械協会
- 雑誌
- ターボ機械 (ISSN:03858839)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.5, pp.336-338, 1994-05-10 (Released:2011-07-11)
1 0 0 0 龍樹、無著、世親の到達した階位に關する諸傳承
- 著者
- 船山 徹
- 出版者
- 東方学会
- 雑誌
- 東方学 (ISSN:04957199)
- 巻号頁・発行日
- vol.105, pp.134-121, 2003-01
1 0 0 0 OA "いじめ"行為の発生要因に関する実証的研究
This article aims to review and verify some causal hypotheses on "Ijime" behavior. In the mid 1980's many articles presented the results of surveys analysis, and the interpretation on "Ijime" behavior. We have as yet no conclusive evidence on the cause of the occurrence of "Ijime" behavior. First, I review the preceding studies, classify the hypotheses and extract five hypotheses - 1 : Personality of the assailant and the sufferer causes occurrences, 2 : Vulnerability of the sufferer gives occasion to occurrences, 3 : Unsuitability of the assailant to school life causes occurrences, 4 : Lack of the moral norm of the assailant accelerates occurrences, 5 : Lack of the moral norm of the witness accelerates occurrence. Secondly, I verify these hypotheses using the data from the questionnaire survey administered to the panel samples for three years. The results of verification are as follows ; 1 : Personality hypothesis is rejected. 2 : Vulnerability hypothesis is accepted. 3 : Unsuitability hypothesis is accepted. 4 : Moral lacking hypothesis in the assailant is partly accepted. 5 : Moral lacking hypothesis in the witness isn't rejected or accepted. These results imply that the assailant in unsuitability does "Ijime" behavior to the person characterized by vulnerability, the psychological cnaracteristics of the assailant are a reflection of their unsuitability and not their personality, the psychological characteristics of sufferers stem from their vulnerability and not their personality, and moral lacking of the assailant sometimes accelerates their behavior.
1 0 0 0 OA 前期中世(西暦0.6-1.0千年)の気温変動と世界史 : 完新世の人類学 (13)
- 著者
- 佐々木 明
- 出版者
- 信州大学人文学部
- 雑誌
- 人文科学論集. 人間情報学科編
- 巻号頁・発行日
- vol.45, pp.165-188, 2011-03-15
The temperature-culture change parallelism during the period 0.6-1.0k A.D., of which description is the purpose of this paper, is summarized as (1) the 610 A.D. warming and succeeding microhypsithermal improved the middle and high latitudinal agriculture and economy and increased polarward migration, though desiccation in the low and middle latitudinal dry zones damaged the regional development, especially in the Fertile Crescent, resulting in the Islam expansion, (2) the 740 A.D. cooling and following microhypothermal mildly disordered the middle and high latitudinal societies, augmenting equatorward migration, but disdesiccation in the Fertile Crescent led the Islam empire to the zenith, (3) the 800 A.D. warming and subsequent microhypsithermal revived the middle and high latitudinal development, while nominalizing the droughty Islam empire, and (4) the 900 A.D. cooling, having started the medieval hypothermal, disordered the middle-high latitudinal cultures, and caused semiglobal changes in the low-middle latitudinal areas which the temperature oscillation would have affected minimally, if the equatorward migrants from the polarwardly adjoining areas had not increased, but the low-middle latitudinal dry zones experienced favorable disdesiccation, the trans-Sahara trade prosperity being the typical example. In the terminal paragraphs are outlined the construction and deterioration of the Japanese kingdom (18.7), the inseparable premodern complex of small population, militarism and discrimination (18.8), and the Subboreal palaeotemperature (18.9).本論の目的は前稿(佐々木,2010)に続く 4 百年間の気温変動と世界史の相関的記述にある。当期は全体的には高温期だったが,8c. 後半は軽度の低温期,10c. は中世低温の開始期だった。やや詳しく述べると冒頭の約10年間に先行期末の低温が続いた後に (i) 急激な温暖化があり,弱い寒冷化傾向はあったが,先行期にはなかった本格的高温が続いた。(ii) 740 年代の寒冷化で軽度の低温が出現したが,(iii) 800年頃の温暖化で本格的な高温が戻った。8c. 後半の低温が軽度で,長く続かなかったので,ここまでは巨視的には高温期だったが,(iv) 900 年頃の寒冷化が中世低温期を開始させた。本論の末尾では日本列島の状況 (18.7),前近代人口の小規模性と好戦主義,差別 (18.8),Subboreal期の気温変動 (18.9) を論じる。
1 0 0 0 根冠による土壌の摩擦抵抗の減少効果 : 粘液と境界細胞の貢献度
- 著者
- 飯嶋 盛雄 樋口 俊文 BARLOW Peter BENGOUGH A. Glyn
- 雑誌
- 根の研究 = Root research (ISSN:09192182)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.2, 2002-06-26
1 0 0 0 世界宗教史
- 著者
- ミルチア・エリアーデ著 中村恭子訳
- 出版者
- 筑摩書房
- 巻号頁・発行日
- 2000
1 0 0 0 OA 対話型ロボットを利用したプログラミング的思考の「教えることによる学習」
- 著者
- 林 雄介 福井 昌則 平嶋 宗
- 出版者
- 一般社団法人 CIEC
- 雑誌
- コンピュータ&エデュケーション (ISSN:21862168)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, pp.38-45, 2019-06-01 (Released:2019-12-01)
コンピュテーショナル・シンキング,日本では「プログラミング的思考」という言葉をキーとしてプログラミング教育に注目が集まっている。そして,日本では既存の教科の中にプログラミング教育を組み込むクロスカリキュラムとなっているため,どのようにプログラミング教育を実施していくかが問題となっている。本稿では,ベン図,Yes/Noチャート,ビジュアルプログラミング言語,対話型ロボットを利用したプログラミング的思考の育成モデルを紹介し,その実践事例やそれに基づく学習環境を紹介する。この特徴は,分類を対象として教科の中で学習する内容の理解を深めることを目標としてプログラミングを行うこと,プログラムという抽象的なものをロボットとのインタラクションという具体的なものにすることである。
1 0 0 0 OA 憲法発布五十年を回顧して
1 0 0 0 OA 大日本帝国憲法 : 帝国憲法制定の精神 欧米各国学者政治家の評論
1 0 0 0 OA 帝国憲法制定の精神・欧米各国学者政治家の評論
- 著者
- 金子堅太郎 著
- 出版者
- 東京日日新聞発行所[ほか]
- 巻号頁・発行日
- 1935