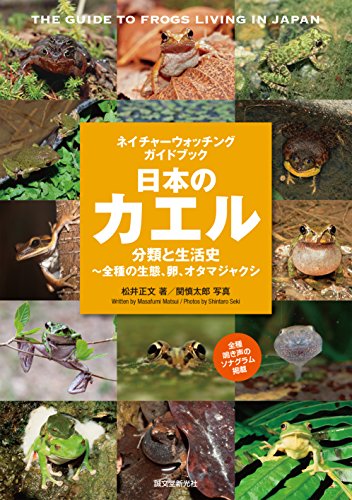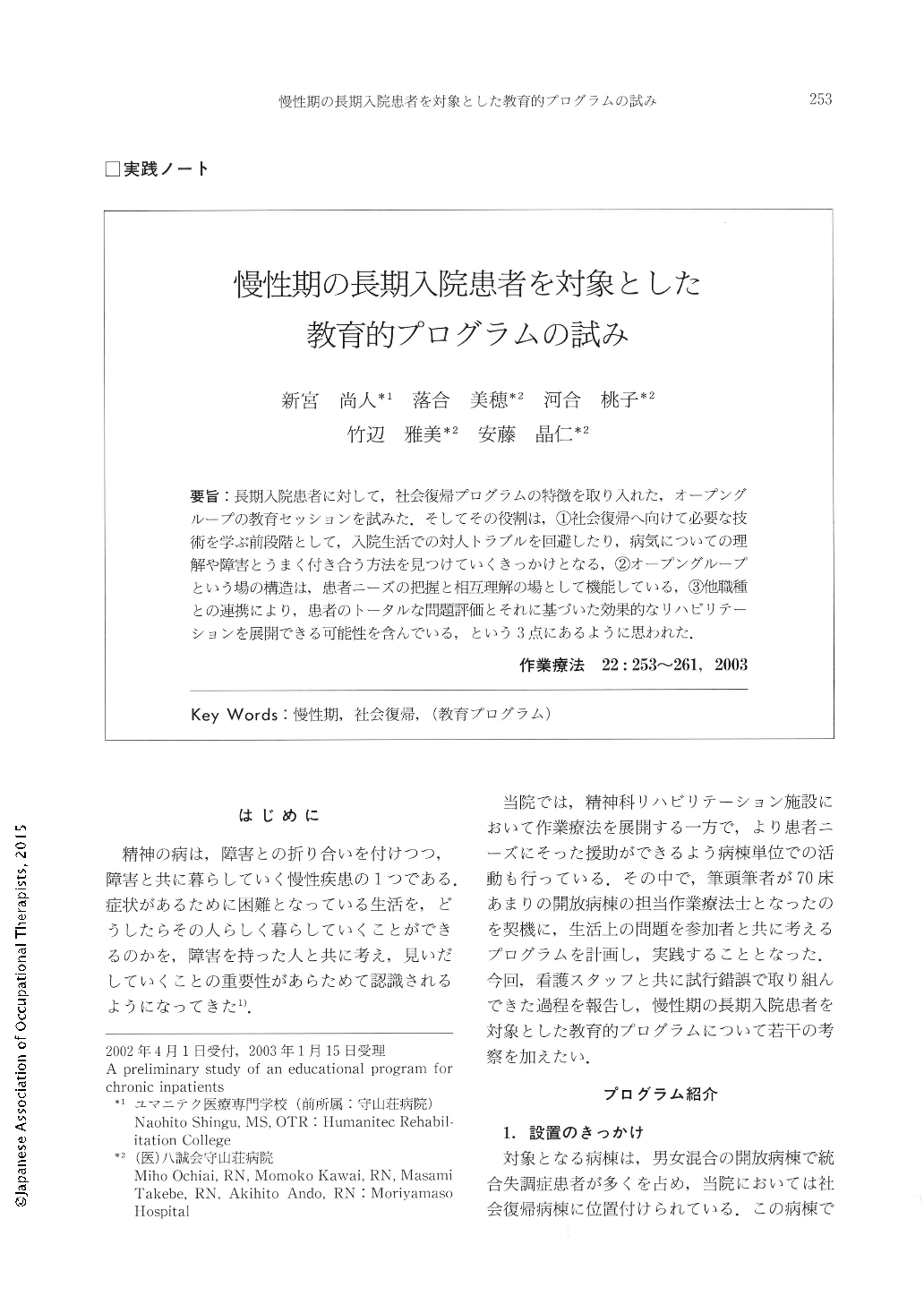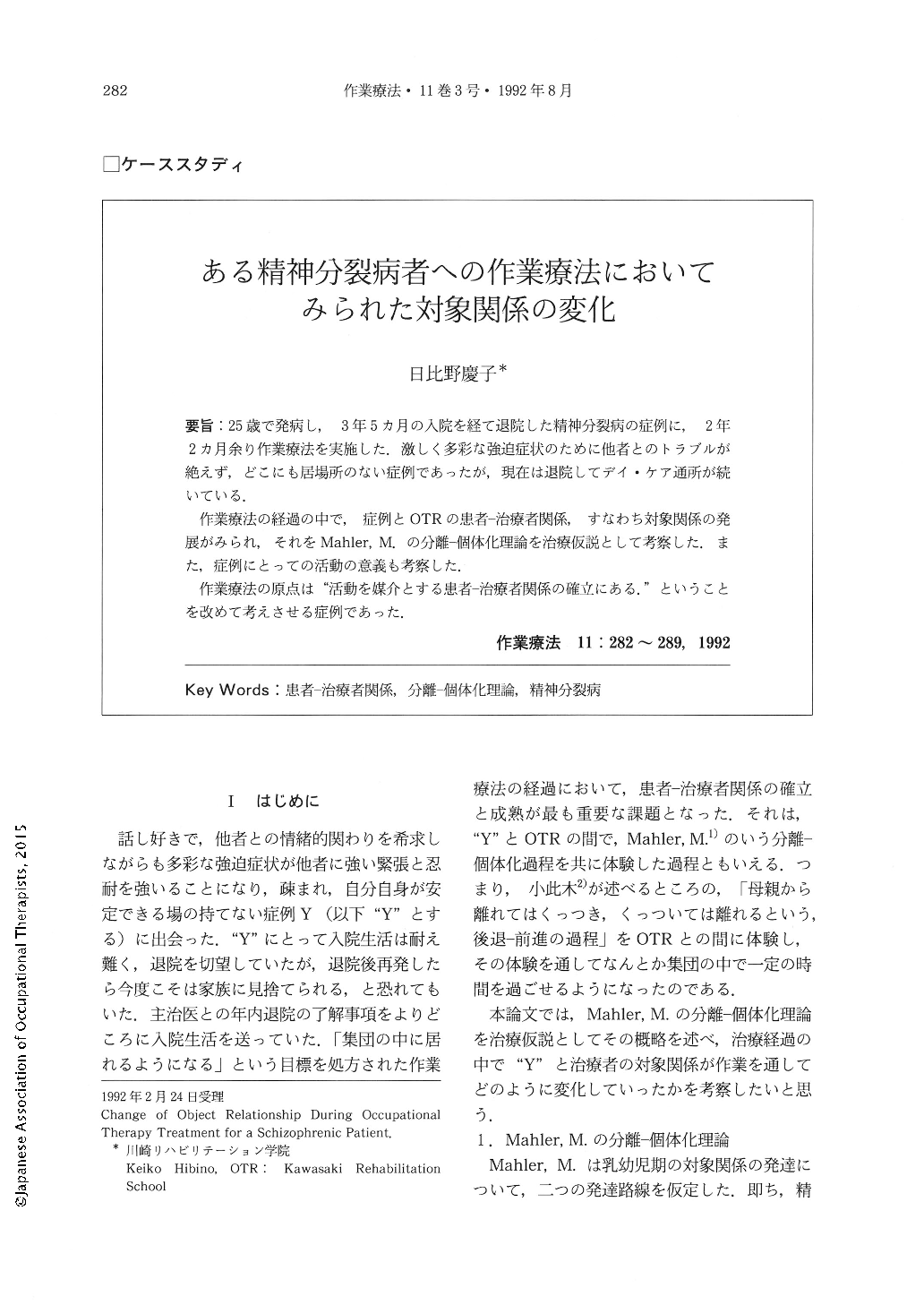1 0 0 0 日本のカエル : 分類と生活史〜全種の生態、卵、オタマジャクシ
1 0 0 0 OA 脳卒中既往患者における開腹手術のリスク評価
- 著者
- 田中 恒夫 真次 康弘 松田 正裕 石本 達郎 香川 直樹 中原 英樹 福田 康彦
- 出版者
- Japan Surgical Association
- 雑誌
- 日本臨床外科学会雑誌 (ISSN:13452843)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.7, pp.1477-1482, 2006-07-25 (Released:2009-01-22)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1 1
目的:脳卒中既往患者における開腹手術のリスク評価を検討した.方法: 2002年1月から3年間に脳卒中で入院歴を有し,開腹手術を行った77例を対象とした.手術のリスク評価のために術後合併症のあり群(n=33)となし群(n=44)に分けて,術前因子,血液検査,手術因子, POSSUMの比較を行った.結果:入院死亡は4例(5.2%)であった.術前因子,検査では年齢,脳出血後,呼吸器障害あり, performance status 2以上,アルブミン値,コリンエステラーゼ値の6項目で有意差が認められた.手術因子では緊急手術と出血量で, POSSUMでは3項目で有意差が認められた.結論:脳卒中既往症例の開腹手術における術前リスク評価の指標として, performance statusとPOSSUMは有用であった.
1 0 0 0 OA イスラム宗教史を読む
- 著者
- 中村 廣治郎 Kojiro NAKAMURA
- 雑誌
- 国際学レヴュー = The Review of international studies (ISSN:09162690)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.69-89, 2006-03-31
A great number of studies have been done so far on the history of Islam in the various fields of discipline. Among others, Oriental History has done a major contribution to the study, while very few by Comparative Religion, or the History of Religions. This article is an attempt to read the history of Islam in terms of the History of Religions, by which I mean to study religions by applying the general theories of religions. The theories I make use of in this article are "Holy Community" by J. Kitagawa, typology of religions "Prophetic" and "Mystic" by F. Heiler and "Fundamentalism."
1 0 0 0 慢性期の長期入院患者を対象とした教育的プログラムの試み
要旨:長期入院患者に対して,社会復帰プログラムの特徴を取り入れた,オープングループの教育セッションを試みた.そしてその役割は,①社会復帰へ向けて必要な技術を学ぶ前段階として,入院生活での対人トラブルを回避したり,病気についての理解や障害とうまく付き合う方法を見つけていくきっかけとなる,②オープングループという場の構造は,患者ニーズの把握と相互理解の場として機能している,③他職種との連携により,患者のトータルな問題評価とそれに基づいた効果的なリハビリテーションを展開できる可能性を含んでいる,という3点にあるように思われた.
- 著者
- 矢野 由起
- 出版者
- 日本家庭科教育学会
- 雑誌
- 日本家庭科教育学会誌 (ISSN:03862666)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.4, pp.290-301, 2015-02-01 (Released:2017-11-17)
小学校家庭科における食の安全に関する学習内容の変遷と課題を明らかにするため,小学校家庭科教科書の記述を分析した。結果は次の通りである。(1)学習指導要領で調理実習題材に指定することによって,調理技能を身に付けるだけではなく,その食品の選び方や扱い方についても同時に学んできた。(2)教科書における野菜の洗い方に関する記述は,野菜の栽培方法,野菜の食べ方,中性洗剤の安全性に対する評価などの変化に応じて書き換えられてきた。(3)小学校家庭科教科書における食の安全に関する記述は,それぞれの時代における問題や課題に応じて,また,新しい科学的知見を取り入れながら,書き換えられてきた。(4)食品の安全な選び方や扱い方を学ぶためには,食の安全に関する内容を調理の目的として,あるいは食の文化として学習指導要領に位置づけることも考えられる。
1 0 0 0 OA 視覚教材としての教育掛図
- 著者
- 牧野 由理
- 出版者
- 美術科教育学会
- 雑誌
- 美術教育学:美術科教育学会誌 (ISSN:0917771X)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.289-300, 2018 (Released:2020-04-02)
- 参考文献数
- 36
本研究は,明治期の旧開智学校において使用していた教育掛図や備品台帳を対象とし,視覚教材として掛図が与えた影響について検討したものである。明らかになったことは以下3点である。 (1)明治43(1910)年の備品台帳の分析によれば,1,244点の掛図を所蔵していた。10分類のうち最も多い掛図は「地理部」であり,次いで「修身部」,「歴史部」,「動物部」,「国語部」の順である。 (2)備品台帳の「著作者又ハ発売者」の集計によれば,「職員」が198点(16%)の掛図を作成していた。「職員」による掛図は信州地域の地図や歴史,産業など地域に密着していたことや,「松本教育品博覧会」の影響を受けていたことがわかった。 (3)「歴史部」の掛図の一部には,日本画家である岡倉秋水や女子高等師範学校図画講師の森川清が図を手掛けていたものが含まれていた。他教科の教育掛図を通して間接的ではあるが画家の絵に美的感受を受けていたことが示唆される。
1 0 0 0 ある精神分裂病者への作業療法においてみられた対象関係の変化
要旨:25歳で発病し,3年5ヵ月の入院を経て退院した精神分裂病の症例に,2年2カ月余り作業療法を実施した.激しく多彩な強迫症状のために他者とのトラブルが絶えず,どこにも居場所のない症例であったが,現在は退院してデイ・ケア通所が続いている. 作業療法の経過の中で,症例とOTRの患者—治療者関係,すなわち対象関係の発展がみられ,それをMahler, M.の分離—個体化理論を治療仮説として考察した.また,症例にとっての活動の意義も考察した. 作業療法の原点は“活動を媒介とする患者—治療者関係の確立にある.”ということを改めて考えさせる症例であった.
1 0 0 0 OA 伊能忠敬の測量事業にともなった学術的交流
- 著者
- 鈴木 純子
- 出版者
- 公益社団法人 東京地学協会
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.129, no.2, pp.161-179, 2020-04-25 (Released:2020-05-12)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 3
The accomplishments of the survey projects of Inoh Tadataka in early 19th century Japan should not be evaluated merely from the visible results of his maps of the country. The latest surveying technologies and instruments, as well as his knowledge of the astronomical almanac, had a wide range of influences upon the surveying skills and astronomical knowledge of local surveyors and scholars. Inoh's Sokuryo-nikki (Survey diary) and records of local counterparts preserved in throughout Japan are reviewed and connections are evaluated. The records have been unearthed in recent years by historians editing regional histories and local history researchers. These investigations are important aspects of recent studies of Inoh's projects and supplement basic research of Otani (1917) and Hoyanagi (1974). During his journeys to survey Japan over seventeen years, Inoh kept a daily journal. It records some 12,000 people who attended or guided Inoh's team. However, his journal lacks details of connections among them. Local records contain extensive practical information concerning the project. Generally, officials of local lords or village officials accompanied the team of surveyors. They would learn on the job. According to their records and letters, some made and improved upon Inoh's surveying instruments. Others wanted to become students of Inoh and later attended private classes in Edo. Still others discussed calendrical calculations, trigonometric functions, and logarithm. Subsequently, some returned to their home regions and took charge of local surveys. As a result, we can recognize the wide range of influences the surveying project of Inoh Tadataka had.
1 0 0 0 OA アナログメモリーを使ったテレビジョン方式変換装置の開発
- 著者
- 谷村 洋 日下 秀夫
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.7, pp.985-989, 2005-07-01 (Released:2011-03-14)
- 参考文献数
- 4
1 0 0 0 OA Her Tastes
- 著者
- 竹ノ内 ひとみ 宮本 道人 森尾 貴広 安藤 英由樹 矢代 真也 Takahiro MORIO
- 出版者
- HITE-Media
- 巻号頁・発行日
- pp.1-39, 2020-04-01
編集:矢代真也デザイン:島影南美作画協力:橋本公司丸
1 0 0 0 OA 「現代プロダクトデザインの役割とは?」
- 著者
- 松坂 洋三
- 雑誌
- 大分県立芸術文化短期大学研究紀要 = Bulletin of Oita prefectural College of Arts and Culture (ISSN:13466437)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, pp.1-20, 2020-03-13
この論文は、プロダクトデザインの役割についての考察である。戦後から今日に至るまでに、プロダクトデザインの役割とデザイナーの仕事は多様化した。プロダクトデザインは、さまざまな産業でその活躍の場を広げてきた。日本のデザイン教育は山脇巌氏や水谷武彦氏らが留学したドイツ「バウハウス」のインターナショナルなデザイン教育をルーツとしており、現代では、従来のインダストリアルデザインの定義だけでは学生への説明が不十分と感じていた。かつてどこにも属さないようなカテゴリーの価値を持った製品をプロダクトデザイナーが創作しているからだ。すなわちプロダクトデザイナーが役割の新しい解釈や可能性を広げて、プロダクトデザイナー自身が自らの領域の可能性を広げているのだ。今日そのような仕事を生んでいるのはデザインスタジオnendoの佐藤オオキ氏や吉岡徳仁デザイン事務所の吉岡徳仁氏のような傑出した人たちであり、また彼らのクリエイティビティ―に刺激を受けたプロダクトデザイナーたちだ。それは例えば「動詞のデザイン」「関係のデザイン」「意味のデザイン」といったような新しい定義であり、人間中心の発想でデザインすることである。バウハウスの時代のものが、「もの発想」であるのなら「ユーザーの行動、理解を発想」したデザインなのだ。例えば、佐藤オオキ氏が最近デザインしたカップヌードルのフォークとカルピスのグラスは、動詞と振舞いのデザインである。 これらのデザインの役割は、新しい価値の創造であり、プロダクトデザイナー自身が開発した。プロダクトデザインには17の役割が必要だと分析した。This Paper is thinking of role of present-day product design. The role of product design and designerʼs job has been diversified after war until today. Product design has expanded contribute field at each industry after war. The Japanese design education roots were international style of BAUHAUS, studied abroad by Mr.Iwao Yamawaki and Mr.Takehiko Mizutani, however, it is not enough to define modern product designʼs role today. Reason why, product designers are designing products which are not belongs any category ever now.It is meaning that product designers are expanding new definition of role and possibilities by themselves. Today, such a job is doing by Mr.Sato or Mr.Yoshioka and young designers who were influenced them. For example, it is essential new definition of “verbs design” ,”relate deign” or “meaning design”, otherwise designing by way of human-centered. If BAUHAUS way is products idea origin, their way is behavior or understanding idea origin. For example, CUPNOODLEsʼ folk and Calpis glass designed by Mr.Sato approaches verbʼs and behaviorʼs design. These roles of approach are new value creation and developed by product designer. What is role of design? I think that we need 17 roles of product design.
1 0 0 0 OA 抗原決定基(エピトープ)
- 著者
- 橘田 和美
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品科学工学会
- 雑誌
- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.7, pp.399, 2006-07-15 (Released:2007-07-15)
- 参考文献数
- 2
花粉症をはじめとする様々なアレルギー症状を持つ人が年々増加し,今や我が国の国民の3人に1人が何らかのアレルギーを持っているといわれている.このアレルギーを引き起こす物質をアレルゲンと呼ぶが,アレルギー症状を引き起こす免疫システムと,アレルゲンのもつ化学構造のインターフェースとなっているのが抗原決定基(エピトープ)である.即ち,アレルゲンのみならず,ある物質がそれに対する抗体を誘発する場合,免疫システムによって認識される部位がエピトープである.アレルゲンをはじめとし,抗体産生を誘発する抗原はその分子内にいくつものエピトープを持っている.これらエピトープは生体内で抗体産生に携わるT細胞によって認識されるT細胞エピトープと,B細胞によって認識され,また抗体の結合部位になるB細胞エピトープとに分類されている.抗体等によって認識される構造単位であるエピトープであるが,タンパク質中の特定のアミノ酸配列だけでなく,糖鎖の一部,低分子物質なども含まれる.糖鎖抗原としてはABO式血液型抗原が有名であり,アレルゲンに関してもミツバチ毒ホスホリパーゼA2,オリーブ花粉アレルゲン等のB細胞エピトープは糖鎖部分であることが示唆されている.T細胞に抗原が認識される場合,まず抗原はマクロファージ,B細胞等の抗原提示細胞に取り込まれペプチドまで分解される.処理されたペプチドは抗原提示細胞上に発現するMHCクラスII分子とともにT細胞レセプターに提示され,これによって抗原情報がT細胞へと伝達され,T細胞の活性化が起きる.このとき,T細胞レセプターはMHCと複合体を形成した線状のエピトープとしか反応しない.従って,T細胞エピトープは熱変性など一次構造に影響しない処理に対しては安定であるが,酵素処理のような一次構造を切断するような処理に対しては影響を受けやすい.一方,B細胞エピトープは,線状に並んだ一次構造から形成されるエピトープだけでなく,タンパク質の立体構造に依存したエピトープを形成する場合もある.従って,B細胞エピトープの場合,T細胞エピトープのように一次構造の変化を伴わない処理に対して影響を受け難いものもある一方,立体構造に依存するエピトープは加熱変性のように三次元構造に変化を引き起こす処理によっても容易に影響を受け,B細胞及び抗体から認識されなくなってしまう.卵一つとってみても,卵白中のオボムコイドは加熱処理に対して安定であるが,オボアルブミンは不安定であるなど,エピトープの構造の違いが調理などによるアレルゲン性の消長に影響を及ぼしている.ところで,花粉症や食物アレルギーなどのアレルギー患者の増加に伴い,その治療法も多くの研究の対象となっている.アレルギーの治療法としては,抗アレルギー剤,ステロイド等,種々の薬剤による対症療法が一般的である.また,少量の抗原をアレルギー患者に長期にわたり繰り返し投与する減感作療法は,花粉,動物,ダニ等の吸入性アレルギーの治療に長く使われてきた.しかし,現行の減感作療法はIgE結合部位を含む抗原を投与することからアレルギー症状を惹起する危険性も否定できない.そこで,ペプチド免疫療法など新たな治療の試みも検討されている.これは完全長のタンパク質分子を用いるのではなく,T細胞エピトープを含むペプチド断片を用いて行われるものである.これらのペプチド断片はアレルギー反応の惹起に必要なIgEの結合及びその架橋形成はできないが,T細胞の不応答を引き起こすとされている.実用化には至っていないが,花粉症のアレルギー症状の緩和を目指したスギ花粉症緩和米はこの現象を利用したものである.具体的には,遺伝子組換えの技術を利用し,スギ花粉症抗原タンパク質の中から7種の主要なT細胞エピトープを選び,これらを連結したエピトープペプチドをコメの胚乳部分に特異的かつ高度に蓄積させたものである1).その他にも,B細胞エピトープのアミノ酸を一つ置換したリコンビナントペプチドを用いた変異タンパク免疫療法も研究されている.T細胞活性化能を保持しながらもIgE結合能が減弱したアミノ酸置換リコンビナントをモデルマウスに投与した実験では,アナフィラキシー発症の頻度及び程度の軽減が認められている2).このようにエピトープの解明は非常に重要であるが,一部の主要アレルゲンを除き,多くのアレルゲンにおいてはエピトープの解明は十分ではない.今後のエピトープ解析の進展が強く望まれる.
1 0 0 0 OA ストレスフルな体験の反すうと意味づけ──主観的評価と個人特性の影響──
- 著者
- 上條 菜美子 湯川 進太郎
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- pp.85.13047, (Released:2014-10-01)
- 参考文献数
- 53
- 被引用文献数
- 7 2
This study examined the factors that influence meaning making and rumination related to stressful events. Six hypothetical scenarios were used, all of which were contextualized stressful events. Participants (N = 779) completed a questionnaire about one of the six scenarios, which assessed the possibility of preventing the event, the probability of the event occurring, the perceived threat of the event, the frequency of rumination, and meaning making. They completed a scale that assessed self-rumination and self-reflection as a way of thinking, and a scale that assessed executive function. Executive function and self-rumination were negatively correlated. Furthermore, self-rumination positively correlated with the frequency of rumination on the event. The perceived threat was high when the probability of the event occurring was low and the possibility of preventing the event was high. Although the perceived threat of the event inhibited meaning making, this was promoted by mediating the frequency of rumination. Self-reflection also directly promoted meaning making. Therefore, this study highlighted a number of factors that affect rumination and meaning making.
1 0 0 0 OA 大豆食品と健康
- 著者
- 難波 文男
- 出版者
- 日本食生活学会
- 雑誌
- 日本食生活学会誌 (ISSN:13469770)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.4, pp.225-229, 2018 (Released:2018-04-28)
- 参考文献数
- 33
A part of the bone is always dissolved and absorbed by osteoclast (bone resorption). And osteoblasts form a new bone (osteoplasty). When this balance collapses, it leads to the disease called the bone metabolism abnormality symptom, and the most common example is osteoporosis. In male and female, the bone mass reaches maximum in mid-30 years old and decreases gradually with aging afterward. It is revealed that estrogen greatly participates in maintaining a bone mass. Because in the women in particular, the sudden decrease in bone mass happens for postmenopausal 5-10 years, and there is knowledge such as there being fewer losses of the bone mass than the woman who is irregular in the women who are stable in their menstrual cycle. It is known that the soy isoflavone has weak estrogen-like activity. The effects of isoflavones on bone are confirmed not only in vitro examination but also in animal experiment and a clinical trial. It is thought that these effects act by mechanism same as bone resorption restraint action of estrogen. Black soybean, a type of soybean with a black seed coat, has been widely used as a nutritionally rich food in Asia. Black soybean has been utilized as a traditional Chinese medicine for preventing of cardiovascular diseases, improving aging liver and kidney functions, and for accelerating diuretic action. Black soybean seed coat contains numerous bioactive compounds including proanthocyanidins and anthocyanins. These compounds have activity as radical scavengers, anti-diabetic and anti-inflammatory agents, and for improving the fluidity of blood. These multiple activities may have some effects on endothelial function.
- 著者
- 佐藤 有貴
- 出版者
- 日記文学会
- 雑誌
- 日記文学研究誌 (ISSN:13449249)
- 巻号頁・発行日
- no.18, pp.60-72, 2016-06
1 0 0 0 OA R.シュタイナーの「道徳的想像力」の構造
- 著者
- 小林 裕明
- 出版者
- 新潟大学大学院現代社会文化研究科
- 雑誌
- 現代社会文化研究 = 現代社会文化研究 (ISSN:13458485)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, pp.89-106, 2010-03
R. Steiner's The Philosophy of Freedom(die Philosophie der Freiheit) puts moral imagination (die moralische Phantasie) at its center. This moral imagination is the intuition of individual idea. By this, the human is freedom, and individual. In this ideal intuition, the idea is mediated through the representation (Vorstellung) to the perception (Wahrnehmung), in such a way that the representation mediates as a motive between the feeling (Gefuhl) and the perception. Under this structure of the duple mediation, the idea and the action are mediated and conjoined through the motive according to the moral idea. Without the unity of idea and action, it isn't in the right, and the action without the mediation through the motive isn't free. In this way, freedom is all human self-development of (individual) Idea which corresponds to love. This structure of moral imagination necessarily leads to the weltanschauung of triple worlds, material-, soul- and spiritual world in his later works on the science of the spirit (Geisteswissenschaft). Because individual idea that is the core of human freedom is true actual only as the unity of these triple worlds, namely as the self that penetrates samsaras. The content of moral imagination is the necessity of samsaras (karma)=idea of the individual, and what is more, the idea of the nation and the age that flows in it. On the other hand, the form of moral imagination is faith. By faith, the human is freedom, and by freedom, the human loves the others.
1 0 0 0 OA 近代北京における町屋の変容過程に関する史的研究
- 著者
- 笠井 健
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.683, pp.237-246, 2013-01-30 (Released:2013-05-30)
This study, focusing on the urban space of the old Beijing city which is a legacy of the pre-modern period, deals with the development of its modern commercial district and historical evolution of town houses. The results are as follows.The commercial district reflected the social background and urban structure of the pre-modern period, and the evolution of the town houses reflected the land use and site conditions of the commercial district. This evolution could be seen in their facades and spatial compositions. For example, there were Chinese Baroque and Art deco style facades. With regards to spatial composition, multi-storey buildings, atriums, and staircases for each story were used to ensure effective use of the land. By applying these three construction methods, new commercial facilities were also constructed.
1 0 0 0 OA 冷風乾燥法による肉、魚、および野菜のセミドライ食品開発
- 著者
- 福永 淑子 船山 敦子 高崎 寿江 永嶋 久美子 臼井 照幸 蓮沼 良一
- 出版者
- 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会大会研究発表要旨集 平成20年度日本調理科学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.11, 2008 (Released:2008-08-29)
【目的】 冷蔵庫を用いて強性通風した庫内において肉、魚および野菜を低温で乾燥させることより新鮮さを保ちつつ保存性が高まった美味しいセミドライ食品製造する方法を開発した。セミドライ食品は一般には野外の通風のよい所にさせるものであるが、本開発技術では冷蔵庫内の低温乾燥した空気より食材を乾燥させてセミドライ食品を製造する方法であり、この方法を冷風乾燥法と名づけた。 【実験】 材料としては、肉類、魚類、野菜類、キノコ類および果物類を選び、その効果を検討した。今回は市販(日立R-SF60XM型)に強制通風させて8~12℃に設定した、約25cm×15cm×12cmのプラスチック性箱を製作し、この中に網棚を設けた。上記の食材をこの網棚に並べ約一日から二日間乾燥させた。 【結果および考察】 この操作により、個々の食材によって風味や色および味が異なるが、従来の常温乾燥セミドライものと比べて全体的に以下のような優れた特徴を持つ食品を製造できることが明らかになった。_丸1_常温乾燥のものと比べて、全体的にも元の生の色に近く、肉類については特に透明感と光沢感が強いこと、_丸2_特に肉類では生臭みはなくなり、野菜類ではその特有の風味が強まること、_丸3_一部の食材では熟成作用もあることが感じられ、果物と野菜では濃縮した美味しい味とともに、テクスチャーが変わり、新たな食感の食品となること、_丸4_キノコ類では水で戻すと速やかに旨味成分が溶出し、しかも濃いだしがとれること、エノキ茸ではそのまま食すると非常に美味しい新たな食品となることが、わかった。以上のように低温乾燥セミドライ法により新しい特徴を持った加工食品・食材が製造できることがわかった。
1 0 0 0 OA 養護教諭がおこなった感染症対策に関する研究 : 新型インフルエンザ対策の実態調査より
- 著者
- 筒井 康子 上田 千尋
- 出版者
- 九州女子大学 :
- 雑誌
- 九州女子大学紀要 (ISSN:18840159)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.1, pp.113-127, 2011