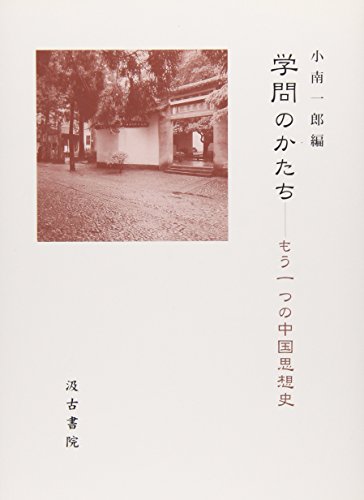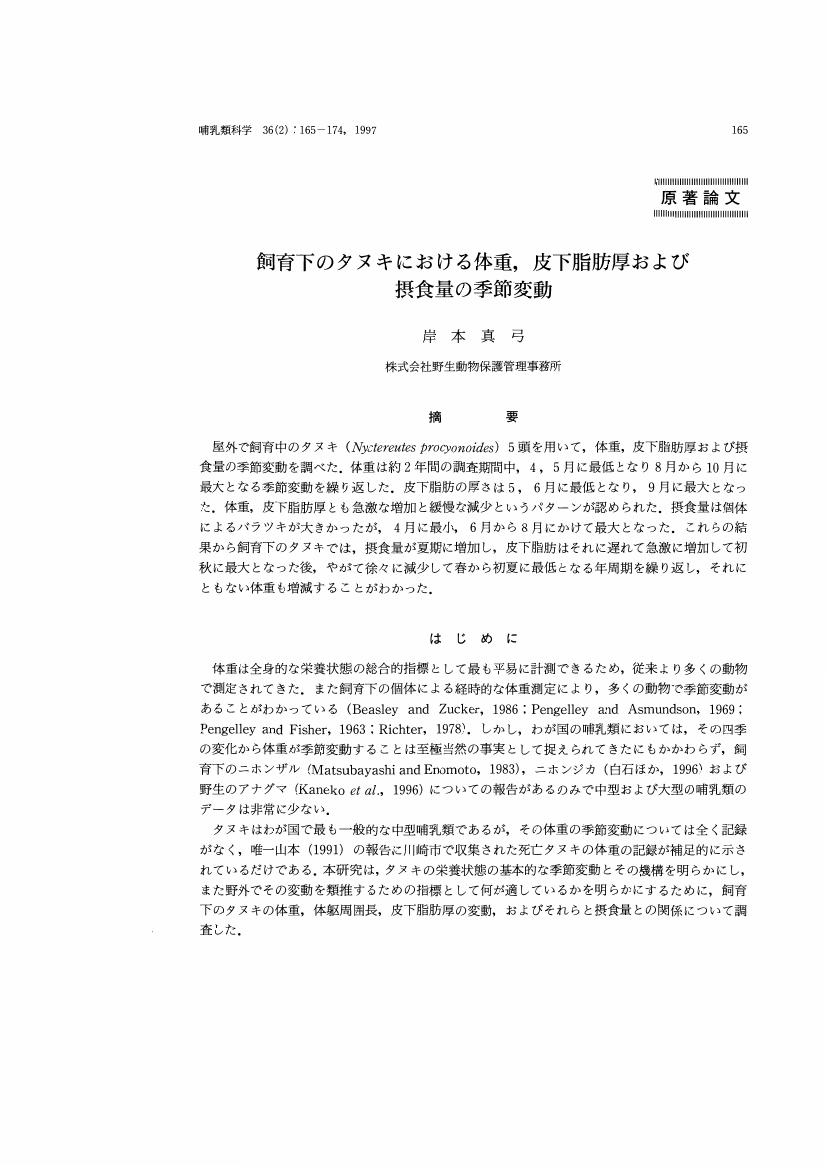- 著者
- 菊池 良和 梅崎 俊郎 山口 優実 佐藤 伸宏 安達 一雄 清原 英之 小宗 静男
- 出版者
- 日本音声言語医学会
- 雑誌
- 音声言語医学 (ISSN:00302813)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.1, pp.35-39, 2013 (Released:2013-04-03)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 2 1
成人の吃音患者に,社交不安障害(social anxiety disorder,以下SAD)が40%以上もの高い確率で合併する(Blumgartら,2010).SADにおいては,人と接する場面で強い不安を覚えるばかりでなく,社会生活上に大きな支障を及ぼす可能性があり,精神科・心療内科で薬物療法を行われることが多い.しかし,吃音にSADが合併している場合は,吃音をよく知っている言語聴覚士とも協力したほうがSADから回復し,従来の生活に戻れる可能性が高まる.症例は16歳男性,授業で本読みをすることに恐怖を感じ,不登校となった.心療内科でSADと診断され薬物療法を受けるが,本読みのある授業は欠席していた.耳鼻咽喉科に紹介され,環境調整,言語療法,認知行動療法を併用した結果,3週間後に授業を欠席せず登校可能となり,通常の高校生活に戻ることができた.吃音症にSADが合併した症例は,医師による薬物療法だけではなく,耳鼻咽喉科医・言語聴覚士の積極的介入が有用であると考えられた.
7 0 0 0 OA 大規模コーパスに基づく日本語教育語彙表の作成
- 著者
- 本田 ゆかり ホンダ ユカリ Honda Yukari
- 出版者
- 本田ゆかり
- 巻号頁・発行日
- 0000
PDF/A形式により利用可能 アクセス:WWWによる 東京外国語大学大学院総合国際学研究科博士 (学術) 論文 (2016年3月) 博甲第208号 参考文献: p158-166
7 0 0 0 学問のかたち : もう一つの中国思想史
7 0 0 0 讖緯思想の綜合的研究
7 0 0 0 ゼロ・ビットの世界
- 著者
- 清水哲郎 [ほか] 著
- 出版者
- 岩波書店
- 巻号頁・発行日
- 1991
7 0 0 0 OA 厚生省の優良多子家庭表彰竝附帯調査
- 出版者
- 国立社会保障・人口問題研究所
- 雑誌
- 人口問題研究
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.3, 1940-06
7 0 0 0 OA スウィンバーンと<ファム・ファタル>神話―メアリ・ゴードンをめぐって
- 著者
- 上村 盛人
- 出版者
- 奈良教育大学
- 雑誌
- 奈良教育大学紀要. 人文・社会科学 (ISSN:05472393)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.69-80, 1977-11-15 (Released:2017-02-24)
In Swinburne's poetry we find many remarkable femme fatale characters : Dolores, Faustine, Venus, Mary Stuart, and Atalanta are all typical femmes fatales, to give a few examples. He was almost possessed with the femme fatale image, and in fact, he became the first to introduce to the Victorian England the "fatal woman" imagery, which was indeed the representative iconography in the fin de siecle European art. Mary Gordon was Swinburne's closely related cousin and was also his bosom friend who had shared the romantic make-believe world of their own since their childhood. Mary's sudden announcement to marry a soldier was a shock to the poet, to whom perhaps it meant destruction of their cherished private world. Swinburne had been interested in the femme fatale theme since his boyhood, and in his imagination the "fatal woman" image had already taken shape, waiting only for a chance to be actually written down as a poem. Mary's engagement announcement gave him such a chance, and now he could set out to become a chief actor in his‘monodrama', in which he was to be tormented by cruel femmes fatales. Swinburne was a poet who was extremely conscious of his poetic art as a‘maker' of poetry. Almost all his poetry can possibly be said‘meta-poetry', that is, poetry about poetry. To achieve his aim to embody‘l'art pour l'art' in his poems, he made use of surprisingly many poetic forms and themes. And his femme fatale myth was one of such themes and his‘lost love' to Mary Gordon gave a good chance to start him writing femme fatale poems.
7 0 0 0 IR 文部省唱歌『ふるさと』100 年の変遷を辿る
- 著者
- 宮島 幸子 伏見 強 Sachiko MIYAJIMA Tsuyoshi FUSHIMI 京都文教短期大学非常勤 京都文教短期大学 Kyoto Bunkyo Junior College Kyoto Bunkyo Junior College
- 出版者
- 京都文教短期大学
- 雑誌
- 京都文教短期大学研究紀要 = The Kenkyu kiyo (ISSN:03895467)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, pp.123-130, 2015-03-13
日本人なら誰でも知っている文部省唱歌『ふるさと』は尋常小学校で児童に歌われ始めて今年で100年になる。1914年(大正3年)という年になぜ文部省唱歌として尋常小学唱歌集6年生用に掲載されたのか。社会状況が目まぐるしく変化する中で100年経てもなおも歌い続けられる文部省唱歌『ふるさと』について、時代と『ふるさと』の変遷を辿り、文部省唱歌『ふるさと』を歌う意味、役割を考察した。
7 0 0 0 OA 「ポスト構築主義」としての「プレ構築主義」
- 著者
- 北田 暁大
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.3, pp.281-297, 2004-12-31 (Released:2010-04-23)
- 参考文献数
- 29
「過去 (歴史) は記述者が内在する〈現在〉の観点から構築されている」という歴史的構築主義のテーゼは, 公文書の検討を通じて歴史命題の真偽を探究し続けてきた実証史学に, 少なからぬインパクトを与えた.「オーラル・ヒストリーをどう位置づけるか」「過去の記憶をめぐる言説はことごとく政治的なものなのではないか」「記述者の位置取り (positioning) が記述内容に及ぼす影響はどのようなものか」といった, 近年のカルチュラル・スタディーズやポストコロニアリズム, フェミニズム等で焦点化されている問題系は, 構築主義的な歴史観と密接なかかわりを持っている.もはや構築主義的パースペクティヴなくして歴史を描き出すことは不可能といえるだろう.しかしだからといって, 私たちは「理論的に素朴な実証史学が, より洗練された言語哲学・認識論を持つ構築主義的歴史学にとってかわられた」と考えてはならない.社会学/社会哲学の領域において, 構築主義が登場するはるか以前に, きわめて高度な歴史方法論が提示されていたことを想起すべきである.以下では, WeberとPopperという2人の知の巨人の議論 (プレ構築主義) に照準しつつ, 「因果性」「合理性」といった構築主義的な歴史論のなかであまり取り上げられることのない-しかしきわめて重要な-概念のアクチュアリティを再確認し, 「構築主義以降」の歴史社会学の課題を指し示していくこととしたい.
- 著者
- 建部 正義
- 出版者
- 中央大学商学研究会
- 雑誌
- 商学論纂 = The journal of commerce (ISSN:02867702)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.5, pp.317-349, 2017-03
- 著者
- Masahiro Ito Tetiana Bogdanova Liudmyla Zurnadzhy Vladimir Saenko Tatiana Rogounovitch Norisato Mitsutake Hisayoshi Kondo Shigeto Maeda Masahiro Nakashima Mykola Tronko Shunichi Yamashita
- 出版者
- (社)日本内分泌学会
- 雑誌
- Endocrine Journal (ISSN:09188959)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.12, pp.1221-1228, 2014 (Released:2014-12-25)
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 5
Geographic differences have been reported to affect the morphological and molecular features of papillary thyroid carcinomas (PTCs). The area around Chernobyl is well-known to be iodine-deficient in contrast to Japan, an iodine-rich country. We reviewed histological differences in adult PTC between Ukraine and Japan. In total, 112 PTCs from age- and sex-matched adults (Ukraine 56, Japan 56) were evaluated histologically for several factors including tumor size, capsulation, tumor components (papillary, follicular, solid, trabecular), lymph node metastasis, extrathyroid invasion, lymphocytic infiltration, oxyphilic metaplasia, and MIB-1 index. We demonstrated that tumors were smaller (1.56 vs. 2.13 cm, p<0.05) and more solid and that lymph node metastasis was less frequent (14.3% vs. 48.2%, p<0.001) in Ukrainian cases. PTC subtype distribution was significantly different between the two groups. Solid variant (8.9% vs. 1.8%) and mixed subtypes with solid components were more frequent in Ukrainian patients. In contrast, classical papillary carcinomas were more frequent in Japanese cases (10.7% vs. 50.0%, p<0.001). Marked oxyphilic metaplasia was more common in Ukrainian cases (33.9 % vs. 8.9 %, p<0.001). MIB-1 index was significantly higher in Ukrainian cases (2.9% vs. 1.8%, p<0.001). However, the frequencies of tumor capsule formation and background lymphoid follicle formation around the tumor were similar between groups. Morphological differences in adult PTCs were similar to those in pediatric PTCs as reported previously, suggesting that morphogenesis of PTC is influenced by environmental factors, especially dietary iodine, as well as genetic factors.
7 0 0 0 OA 新たな発想による事業事例の研究 : 経済復興計画の策定に向けて
- 著者
- 南相馬市経済復興研究チーム
- 出版者
- 南相馬市
- 巻号頁・発行日
- 2011-07-14
7 0 0 0 OA 若きバタイユとシェストフの教え : 「星の友情」の軌跡
- 著者
- 酒井 健
- 出版者
- 法政大学言語・文化センター
- 雑誌
- 言語と文化 = 言語と文化 (ISSN:13494686)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.29-53, 2018-01-10
比較制度的な研究を通じて明らかになったのは、マスメディアによる人権侵害の救済システムがソフトロー的な性格をもち、それによって適切に機能している部分と限界が存在することである。また、ソフトローとしての機能する条件についてもいくつかの軸が見えてきた。すなわち、まず第一に、イギリスや韓国等において、苦情処理機関が行った仲裁や裁定の措置が、報道機関によって一般によく遵守されていることは注目に値する。この背景には、もし自主規制がうまくいかない場合の規制立法に対する警戒もあるが、報道機関が自己規律に対する意識が明確にあることの反映でもあり、それがこの分野でのソフトローを機能させる条件となっていると見ることが出来る。それと同時に、とくにイギリスで指摘される、和解的な感覚の社会的普及も、ソフトローを機能させる上で重要なファクターとなりうることが示唆されている。第二は、苦情処理機関において適用されるルールには、法規制と重なる内容と、法では規制されていない内容の双方が含まれていることである。この後者の観点から言えば、法規制よりも幅広い対象について、柔軟な調整をソフトローが行いうることを意味する。第三に、上記の前者の観点からすれば、ソフトローは法と同じ対象を規律するため一見リダンダントに見えるが、内容は同じであっても、例えば迅速な処理や軽微な費用など、執行のコストや効果において独自の意味をソフトローが持ちうることがあることを、メディアの救済制度の経験は示唆する。以上のような検討を通じ、マスメディアによる人権侵害の救済システムを素材として、ソフトローが成立・機能しうる条件、またソフトローが一般の法に比して有する固有の意義の一端が示され、人権侵害の救済システムの研究とともに、ソフトローの研究に資する成果が得られた。
7 0 0 0 OA 括要算法 4巻
- 著者
- 関孝和 遺編
- 出版者
- 升屋五郎右衛門[ほか]
- 巻号頁・発行日
- vol.第1冊, 1712
7 0 0 0 OA イタリアにおける震災復興プロセスに関する研究
- 著者
- 野村 直人 佐藤 滋
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.3, pp.387-393, 2015-10-25 (Released:2015-10-25)
- 参考文献数
- 13
巨大災害が引き起こす長期避難生活において、適切な住環境、生活環境の構築は、本格的な復興へと円滑に移行していく上で重要な課題である。2009年に中部イタリアで起きたラクイラ地震においては、復興に膨大な時間がかかることが予想されたことから、「応急建設」という法的枠組みのもと、長期避難生活に耐えうる質の高い住環境を短期間で供給することに成功している。本研究では、第1に適切な緊急時対応及び応急建設を実現させた組織体制を明らかにすること、第2に長期復興プロセスに対する応急建設の有効性を明らかにすることで、災害の規模や被災地の特性に応じた住宅供給のあり方として日本への示唆を得ることを目的とする。本研究により具体的に以下の2点が明らかになった。 1.応急建設物の迅速な建設プロセスや住宅としての質の高さにおいて長期的な復興プロセスに対する有効性が見られた。 2.全国災害防護庁は技術的な蓄積をもとに、被災の規模や被災地の特性に応じて緊急時における住宅供給の戦略を決定し、多様な規制緩和や行政手続きの免除等によって迅速な事業の実施を可能としている。
7 0 0 0 OA サッカー選手の〈パスの知〉の地平分析
- 著者
- 寺田 進志 佐野 淳
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育学会
- 雑誌
- 体育学研究 (ISSN:04846710)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.1, pp.169-186, 2017 (Released:2017-06-22)
- 参考文献数
- 48
In soccer, passing has a decisive influence on the match, and can be said to be one of the game's most important elements. Regardless of playing style, in order to win, soccer players must master the ability to deliver the ball accurately to teammates. Therefore, the training menu of coaches must ensure precise passing of the ball. Even if coaches teach this, the outcome depends on the skills of individual players. If it is possible to reduce the number of failed passes as far as possible, then a better strategy than the opposing team can be achieved. For this purpose, it is necessary to refine the “passing wisdom” of soccer players. As the importance of passing in soccer is widely recognized, a number of studies have addressed this aspect. For example, an attempt has been made to clarify the mechanical structure of the kick from a biomechanics perspective, and to clarify the structure of cognitive perception from a sports psychology perspective. However, to our knowledge, there has been no phenomenological analysis of “passing wisdom” in soccer players to date. In order to analyze this, a phenomenology (Bewegungslehre des Sport) perspective needs to be adopted, and this was done in the present study. This revealed the following 7 abilities: 1) The ability to sense other players' intention. 2) The ability to sense whether the criteria for successful action meet other players' intention. 3) The ability to construct a situation based on one's own analysis. 4) The ability to recognize the criteria for effective passing. 5) The ability to sense the receiver of the pass. 6) The ability to visualize the course of the pass. 7) The ability to apply the technique to a constructed situation based on one's own analysis.
7 0 0 0 OA 将棋における投了局面の識別
- 著者
- 竹内 章 飯田 弘之
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.11, pp.2370-2376, 2014-11-15
柔軟な戦略に基づいた人間らしい思考をコンピュータで実現するため,ゲームにおけるクリティカルな局面の識別は重要である.本研究は,将棋における投了局面の識別に着目する.共謀数や証明数と類似の指標は,投了局面を識別するのに有効である.有利な局面に制限した探索におけるノード数が勝ちの反証数と類似であることから,この探索の有効分岐因子を用いた投了モデルを提案する.提案モデルの妥当性を確認するため,プロ棋士による投了に至る局面を分析する.提案モデルによって,有効分岐因子が減少することをとらえ,プロ特有の投了が説明できる.
7 0 0 0 OA 飼育下のタヌキにおける体重,皮下脂肪厚および摂食量の季節変動
- 著者
- 岸本 真弓
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.2, pp.165-174, 1997 (Released:2008-07-30)
- 被引用文献数
- 3