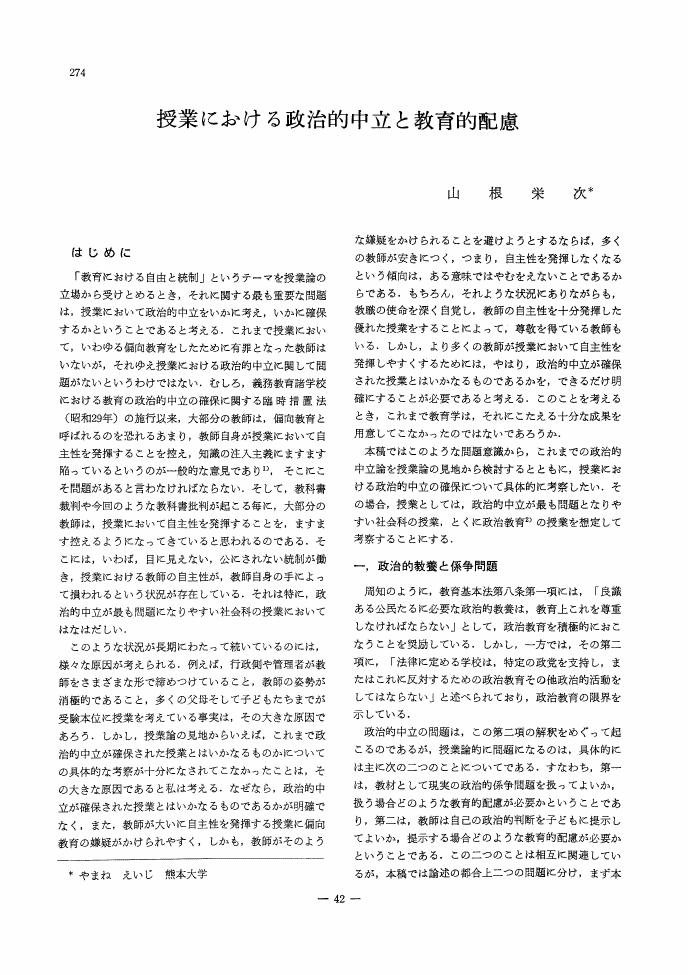1 0 0 0 OA 徐弘祖の地理・地学思想初探 : 地の「脈」の説を中心に<人文・社会科学>
- 著者
- 薄井 俊二
- 出版者
- 埼玉大学教育学部
- 雑誌
- 埼玉大学紀要. 教育学部 = Journal of Saitama University. Faculty of Education (ISSN:18815146)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.2, pp.307-316, 2018
- 著者
- 野間 晴雄 松井 幸一 齋藤 鮎子
- 出版者
- 関西大学大学院東アジア文化研究科
- 雑誌
- 東アジア文化交渉研究 = Journal of East Asian cultural interaction studies (ISSN:18827748)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.461-475, 2013-03-27
The authors discuss the visualization the Chinese travelogue "Jokakaku-yuki" (徐霞客遊記) written by Jokakaku (徐霞客) in the 17th century. Besides an outstanding traveler, he was an excellent geographer, a botanist and a historian. In Japan his name is not so famous, but his views are not simply categorized into sightseeing records and diaries. Every time he tried to observe objects correctly, and to confirm in situ site/place by his minute academic description. We tied to create the Fujian part of "Jokakaku-yuki"database in a geographical viewpoint. As this database contains text information and maps, users can get them easily. Additionally it can be searched from the text information and/or maps. Since text information and maps are integrated by GIS, we can also process this database by GIS. In this paper Remote Sensing and NDVI analysis are implemented. We believe that such a database will make a great contribution to the development of the historical GIS (HGIS).
1 0 0 0 OA クロス・コンプライアンス適用に向けた新たな農業政策設計のための手法開発
EUでは、環境に配慮した農業生産を行うなどの一定要件を満たした農業生産者に補助金等を支払うというクロス・コンプライアンス(CC)を適用した農業政策が実施されている。本研究では、CC受給要件を、農業由来の環境負荷などの外部性効果とみなして評価し、CC受給要件の内容設計に資する手法の開発や適用を試みた。農業生産活動由来の環境負荷に及ぼす環境影響を経営段階のミクロレベルや国全体のマクロレベルで定量評価できる手法の開発と適用を行い、CCを適用した新たな農業政策の設計に資する基礎知見を得ることができた。
- 著者
- 麻生 憲一
- 出版者
- 日本交通学会
- 雑誌
- 交通学研究 (ISSN:03873137)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, pp.113-124, 2001 (Released:2019-05-21)
- 参考文献数
- 17
1 0 0 0 OA クロラール
- 著者
- 中村 公一
- 出版者
- The Society of Synthetic Organic Chemistry, Japan
- 雑誌
- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.2, pp.171-172, 1987-02-01 (Released:2009-11-13)
1 0 0 0 OA 実験的膵炎に関する病理学的研究
- 著者
- 中村 直文
- 出版者
- 昭和大学学士会
- 雑誌
- 昭和医学会雑誌 (ISSN:00374342)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.3, pp.321-334, 1982-06-28 (Released:2010-09-09)
- 参考文献数
- 33
急性膵障害を作製し, その初期像から進転に至る過程を明らかにする目的で実験病理学的研究を行なった.膵障害作製の為に高アミラーゼ血症を来たすことで知られるサソリ毒 (Leiurus quin-questriatus) を家兎に対しては耳静脈より致死量に近い量の2.44×10-4mg/gとその1/2量を3時間, 6時間, 12時間, 24時間間隔で投与した計8群, モルモットに対しては皮下より2.44×10-4mg/g, その1/2量, 1/4量の連日投与および1/2量を隔日にて週3回注射し, 1カ月後に1/4量を増量した計4群, 総計12群に対して投与した.これら投与群に対して, 膵を中心として病理組織学的検索を行なうとともに, 生化学, 電顕的検索, 数種の膵刺激剤を用いた対照実験を加えて行なった.病理組織学的には, 静脈投与では各群において膵における間質の水腫, 毛細血管および導管の拡張, 部分的には腺房細胞の濃縮, 膨化を認め12時間間隔2.44×10-4mg/g投与群, 3時間, 6時間間隔の1/2量投与群では, これらの所見に加えて腺房細胞の空胞形成から崩壊に至る組織像が認められた.皮下投与群では, 恒常的変化は毛細血管網の拡張による目立ちと腺房細胞の変性性障害であり, 長期投与群になるに従いこれら変化が高度になり, 多数の腺房細胞の空胞形成, 脂肪浸潤を認めた.電顕的には耳静脈投与家兎, 皮下投与モルモットの両方に, チモーゲン顆粒の減少, 腺房腟拡大, 粗面小胞体, ミトコンドリアの変性, 空胞形成が種々の程度で認められた.生化学的検索では, 膵腺房細胞の変性性病変が高度の場合には血清および尿アミラーゼ値が漸次上昇する傾向がみられ, 上昇したアミラーゼは3: 8程度で唾液腺型アミラーゼの優位な上昇を示した.以上.サソリ毒投与により, 主に膵においてその腺房細胞に変性性病変を主体とする過分泌を伴う膵障害を起こさしめ得ることを確認した.そしてサソリ毒の短期大量投与群では, 主に水腫を中心とする変性性病変を認め, 長期投与の場合は緩徐な持続分泌による機能亢進の為の細胞疲労, 消耗と思われる変性性変化の過程であり, 両者とも急性膵炎の組織表現と思考する.また当教室における膵障害分類では, 急性障害の内の変性型, すなわち急性実質性膵炎に相当するものである。
1 0 0 0 OA 梅北集
- 巻号頁・発行日
- vol.[3], 1000
- 著者
- 山本 智子
- 出版者
- 日本生命倫理学会
- 雑誌
- 生命倫理 (ISSN:13434063)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.1, pp.4-12, 2009
- 参考文献数
- 36
本稿は、包括的な子どもの権利保障を目的に、「国連子どもの権利委員会(UNCRC)」による「乳幼児の権利(GENERAL COMMENT No.7(2005)Implementing child rights in early childhood)」との関係において、日本の小児医療にInformed Assent(I.A.)を採用するにあたっての課題を提示した。I.A.は、「親の許諾(Parental Permission)」と「患児の賛同(Patient Assent)」という小児医療に特有の2概念から成る。具体的な適用例では、乳幼児は、「親の許諾」のみの適用を奨励されている。さらに、アメリカ合衆国の小児科医によって提示されたI.A.理念には、「子どもの患者の権利」とも「適切なケアの提供」とも異質な、また、法的責任にも対応していない、「医師と親との責任のシェア」(Decision-making involving the health care of young patients should flow from responsibility shared by physicians and parents.)という記述が盛り込まれている。一方、UNCRCによる「乳幼児の権利」は、乳幼児を「社会的主体(Social Actor)」とし、また、乳幼児期を「子どもが条約において保障されたすべての権利を認識する重要な時代」と位置づけている。さらに、乳幼児の力を肯定的に評価すると共に、能力の未熟さ故の乳幼児の権利制限を問題視し、乳幼児の権利の保障を強く求めている。I.A.の採用にあたっては、「子どもの権利」の視点や、臨床経験(実践知)や研究成果に基づいた小児科医による乳幼児の力の評価やその力の独自性を指摘する見解もふまえ、乳幼児観の転換や、乳幼児の未熟さを子どもの権利の支援要素へと転換することが課題になる。また、医療専門職が提示する医療に係る理念の影響についても検討を要する。
1 0 0 0 IR 「気のいい火山弾」論
- 著者
- 高橋 直美
- 出版者
- 東洋大学ライフデザイン学部
- 雑誌
- ライフデザイン学研究 (ISSN:18810276)
- 巻号頁・発行日
- no.10, pp.109-124, 2014
童話「気のいい火山弾」は宮沢賢治が法華文学を志した初期の作品である。この作品の主人公であるベゴ石の特徴を多面的に考察するには、当時の賢治が日蓮の説く『法華経』の文底秘沈である「事の一念三千」(賢治は作品や書簡でこの「事の一念三千」を「妙法蓮華経」と記しているため、以下では「妙法蓮華経」と記し、経典である『法華経』と区別する)をいかに感得したのかとともに、賢治の仏教に対する見識の広さや科学に対する見方も知る必要がある。 火山弾であるベゴ石は火山の産物であり、永遠の生命を象徴する「石」である。その性格のよさは仏教の修行者の姿勢として重要なものであり、また火山信仰の対象である岩手山や、花巻・盛岡の巨石の文化等からも、ベゴ石の重要性を推察することができる。 一方で、ベゴ石は悪口罵詈されることを修行としている点から「クニサレモセズ」を理想とするデクノボーとは異なり、また、化他行である折伏行を行じていない点から、悪口罵詈・杖木瓦石の難を被りながらなお『法華経』を説いた常不軽菩薩とも異なっている。 ベゴ石の「みなさん。ながながお世話でした。苔さん。さよなら。さっきの歌を、あとで一ぺんでも、うたって下さい」というわかれのことばは、「393 昭和6年9月21日 宮沢政次郎・イチあて書簡」に記された「どうかご信仰といふのではなくてもお題目で私をお呼びだしください」に近い「摂受」と考えられる。また、日蓮は「攝受・折伏時によるべし」(「佐渡御書」)と説いているが、賢治も「摂折御文 僧俗御判」に「佐渡御書」の同文をのせ、「開目抄」の「無智悪人ノ国土ニ充満ノ時ハ摂受ヲ前トス。安楽行品ノ如シ。邪智謗法ノ者多キ時ハ折伏ヲ前キトス。常不軽品ノ如シ」等を羅列している。 以上のことからベゴ石の言動は、当時の賢治が考えた摂受と折伏の一つの形であるといえよう。
1 0 0 0 OA 社会的責任と法の支配に関する一考察 -ISO26000に関連して-
- 著者
- 宮守 代利子
- 出版者
- 早稲田大学大学院社会科学研究科
- 雑誌
- 社学研論集 (ISSN:13480790)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.33-48, 2013-03-25
1 0 0 0 OA 授業における政治的中立と教育的配慮
- 著者
- 山根 栄次
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.3, pp.274-283, 1983-09-30 (Released:2009-01-13)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 「初発心時便成正覚」の一考察――中世真言学僧の華厳解釈を中心に――
- 著者
- 鈴木 雄太
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.84-87, 2017-12-20 (Released:2019-01-11)
- 参考文献数
- 2
“The First Inspiration to Set One’s Mind on Seeking Enlightenment” (Shohosshinjibenjōshōkaku) is a key term from the “Kegon Sūtra” concerning the theory of attaining Buddhahood in the Kegon sect. “Shohosshinjibenjōshōkaku” has been the subject of a variety of debates since ancient times.In this paper, I discuss the Kegon interpretations of Shingon priest-scholars (such as Raiyu, Gōhō, Shōken, and Shōdō), who were active during the Middle Ages, from the perspective of “Shohosshinjibenjōshōkaku.” As a result, I am able to clarify differences between the interpretations of Shingi Shingon scholar-priests and those of Kogi Shingon scholar-priests.Furthermore, the method by which each school understands the “ideal world” provides a background for the differences between the two interpretations.
1 0 0 0 OA 膠原病における耳鼻咽喉科領域の実際
- 著者
- 黒坂 大太郎
- 出版者
- 耳鼻咽喉科展望会
- 雑誌
- 耳鼻咽喉科展望 (ISSN:03869687)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.6, pp.304-308, 2015-12-15 (Released:2016-12-15)
1 0 0 0 OA 近年のジカウイルス感染症流行域の拡大
- 著者
- 林 昌宏
- 出版者
- 日本ウイルス学会
- 雑誌
- ウイルス (ISSN:00426857)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.1, pp.1-12, 2018 (Released:2019-05-18)
- 参考文献数
- 101
- 被引用文献数
- 1
ジカウイルスは1947年にウガンダのジカの森で囮動物であるアカゲザルから分離されたフラビウイルス科フラビウイルス属のウイルスであり,主にネッタイシマカやヒトスジシマカ等のシマカ属の蚊によって媒介される.主な症状は発熱,発疹,間接痛であり,その流行域および症状からデング熱およびチクングニア熱の重要な鑑別疾患である.ジカ熱はこれまでにアフリカから東南アジアにかけて散発していたがヒトの症例報告はわずかであった.しかしながら2007年にミクロネシアで再興しその流行は南太平洋諸島から米州に拡大した.近年のジカウイルス感染症の流行ではギラン・バレー症候群との関連および経胎盤感染による先天性ジカウイルス感染症が問題となっており,国内外でジカワクチンの開発が進められている.我が国では2013年末から輸入症例が報告されており,媒介蚊であるヒトスジシマカが本州以南に生息するため,その浸淫の可能性は否定できない.ジカウイルス感染症は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」で4類感染症に指定されており,当該患者を診断した医師はただちに保健所を経由して都道府県知事に届け出ることが求められる.