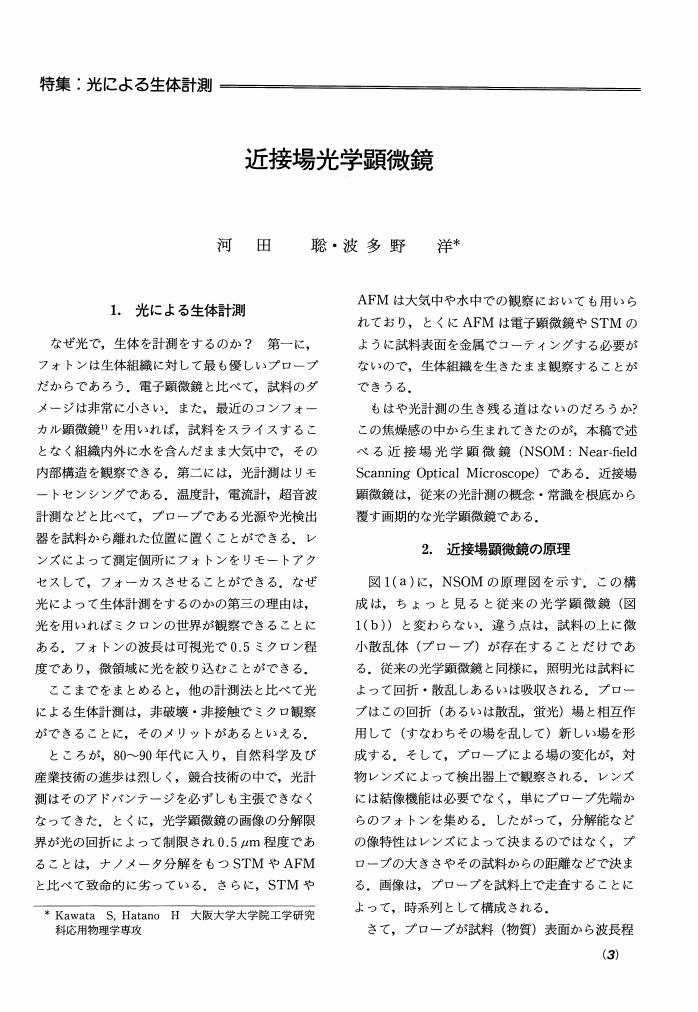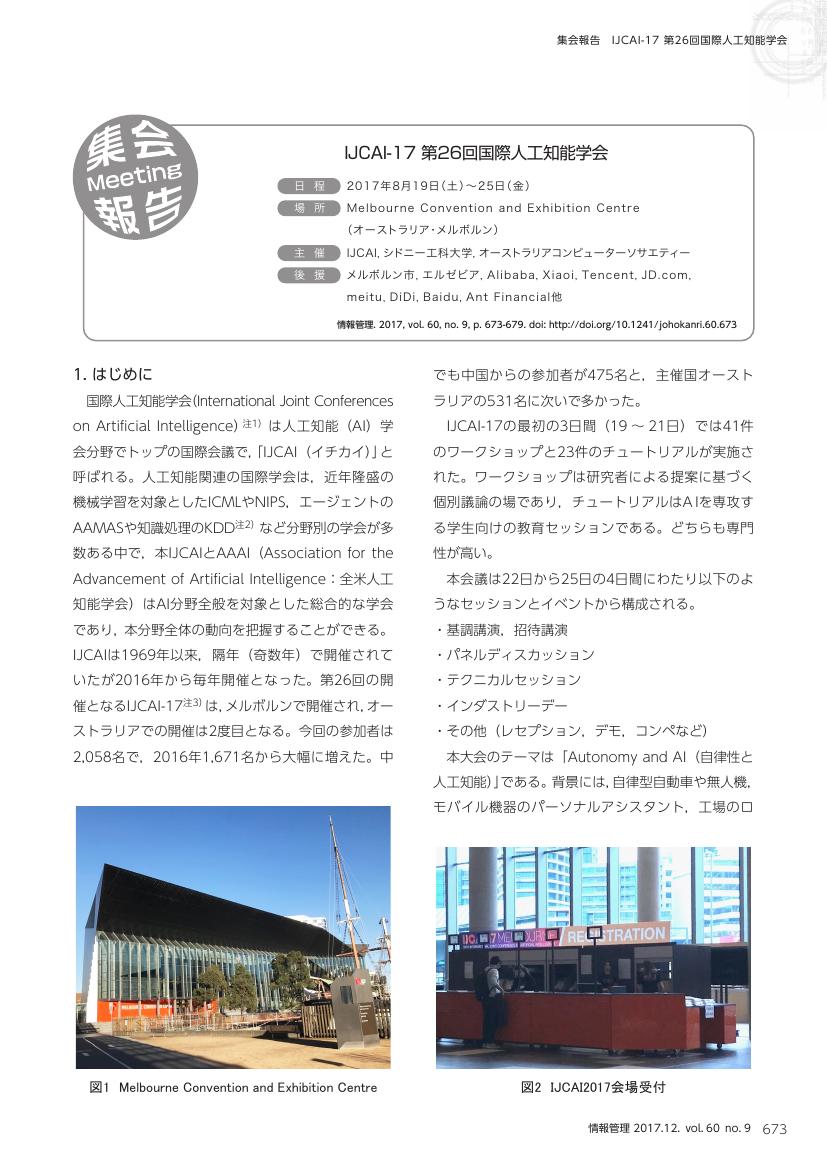3 0 0 0 OA スポーツ現場における野球肘重症度予測のための要因検討
- 著者
- 山野 宏章 和田 哲宏 田坂 精志朗 福本 貴彦
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.43 Suppl. No.2 (第51回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.1264, 2016 (Released:2016-04-28)
【はじめに,目的】野球肘は成長期の野球選手に多く,発見が遅れ重症化すると選手生命に関わることから,予防,早期発見が重要視されている。その発生要因としては投球数や練習量だけでなく,肩関節周囲筋の筋力や柔軟性などの身体的要因も関わっているとの報告がされている。しかし,野球肘を発症する選手の身体的特徴は,一貫した報告がされていない。また,スポーツ現場で野球肘の評価をするにはポータブルエコーを用いて医師が行うのが一般的で,理学療法士や指導者が簡易に評価できる指標はストレステストや痛みの問診等しかなく,十分ではないのが現状である。そこで本研究の目的は,エコー診断や各種身体機能検査を含めた評価をもとに,野球肘の発症あるいは重症度に関係する要因を包括的に検討することとした。【方法】奈良県の少年野球選手436名を対象とした野球肘検診において野球歴・投球時痛などのアンケート調査,医師によるエコー検査とストレステスト,理学療法士による柔軟性検査を実施した。そこで得た結果を基に野球肘の重症度を5段階に分けた。統計解析は,5段階の重症度を従属変数,アンケートの結果,エコー所見,ストレステストの結果,柔軟性検査の結果を独立変数とし,重回帰分析(ステップワイズ法)を行った。統計学的有意水準は5%未満とした。なお,統計解析にはSPSS statistics ver. 22(IBM,Chicago,IL)を使用した。【結果】重回帰分析の結果,外側エコー異常所見,内側エコー異常所見,肘関節伸展での違和感,肩関節水平内転テスト(以下:HFT),投球時痛,肩関節外旋での違和感,肘内外側のしびれ感の7項目が独立した因子として抽出された。標準偏回帰係数は外側エコー異常所見0.684,内側エコー異常所見0.331,肘関節伸展での違和感0.268,HFT0.056,投球時痛0.045,肩関節外旋での違和感0.052,肘内外側のしびれ感-0.037であった。自由度調整済み決定係数は0.882であり,Durbin-Watsonの検定は2.134であった。【結論】柔軟性検査のうち唯一抽出されたHFTの減少については,肩関節後方の軟部組織の柔軟性の低下を示している。これは投球動作時に体幹,肩甲帯から受けるエネルギーを適切に上肢に伝えることを困難にし,肘関節の適切な運動を阻害する。その結果,肘関節に異常なストレスを与え,野球肘の発症に繋がると考えられる。本研究の結果から,エコー検査が重症度予測に有用であると考えられるが,通常医師が行うエコー検査と比較した場合,エコー検査以外の重症度に影響する因子である痛みやしびれ,違和感の聴取,HFTの測定は理学療法士や指導者が簡易的に実施できる。そのため,スポーツ現場でこれらの評価を定期的に実施することにより,野球肘の予防や早期発見に繋がる可能性があると考えられる。
3 0 0 0 OA 地域で生活する成人知的障害者の肥満の実態とその要因
- 著者
- 増田 理恵 田高 悦子 渡部 節子 大重 賢治
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.8, pp.557-565, 2012 (Released:2014-04-24)
- 参考文献数
- 23
目的 肥満は心血管系疾患等のリスク要因となるが,地域で生活する成人知的障害者には肥満が多いことが指摘されてきた。本研究の目的は,地域で生活する成人知的障害者の肥満の実態および肥満をもたらす要因を明らかにすることにより,肥満予防に向けた実践への示唆を得ることである。方法 A 市における 5 つの通所施設•相談施設に通う男女39人を対象に,BMI,食事,活動についての面接調査を行った。対象者の基本属性について,項目別の単純集計を行った。BMI については平成19年版「国民健康•栄養調査」における20~59歳の一般成人の平均値と t 検定を用いて比較した。エネルギー摂取については,対象者の摂取エネルギー,摂取エネルギーと推定必要エネルギーの差,および食品群別摂取量を算出した。またエネルギー消費については,消費エネルギー,身体活動レベル,エクササイズ量を算出し,身体活動レベルについてはカイ 2 乗検定により一般成人と比較した。食習慣については 7 つの質問項目の和(食習慣得点)を算出した。さらに対象者の BMI について,対象者の属性,エネルギー摂取に関連する項目,エネルギー消費に関連する項目,食習慣得点,および食品群別摂取量との相関分析を行った。結果 対象者の BMI の平均値は一般成人と比較すると男女とも有意に高かった(P<0.001)。摂取エネルギーと推定必要エネルギーの差の平均値は男性で396±503 kcal,女性は569±560 kcal であった。BMI との有意な相関(P<0.05)がみられたのは摂取エネルギー,摂取エネルギーと推定必要エネルギーの差,消費エネルギー,穀類摂取量,菓子類摂取量,食事制限の有無であった。対象者の身体活動レベルは,一般成人に比べて低い者の割合が有意に高かった(P<0.001)。結論 対象者の BMI の増大をもたらしている要因は,主には過剰なエネルギー摂取であり,その背景には間食で菓子類を多く摂取するなど不適切な食習慣がある。また,一般成人に比して著しく低い身体活動レベルが対象者の生活上の特徴であることが明らかとなった。成人知的障害者の肥満対策として,過剰なエネルギー摂取,不適切な食習慣,低い身体活動レベルのすべてに対し,包括的に介入する必要がある。
3 0 0 0 OA 近接場光学顕微鏡
- 著者
- 河田 聡 波多野 洋
- 出版者
- 一般社団法人 日本生体医工学会
- 雑誌
- BME (ISSN:09137556)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.5, pp.3-11, 1997-05-10 (Released:2011-09-21)
- 参考文献数
- 25
3 0 0 0 OA 集会報告 IJCAI-17 第26回国際人工知能学会
- 著者
- 茂木 強
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.9, pp.673-679, 2017-12-01 (Released:2017-12-01)
- 参考文献数
- 1
3 0 0 0 OA 鉄道用信号機の着雪防止対策
- 著者
- 五十嵐 勉 平野 徹 佐藤 篤司 本田 雅彦
- 出版者
- 公益社団法人 日本雪氷学会/日本雪工学会
- 雑誌
- 雪氷研究大会講演要旨集 雪氷研究大会(2009・札幌) (ISSN:18830870)
- 巻号頁・発行日
- pp.181, 2009 (Released:2009-12-10)
3 0 0 0 OA 認知心理学に基づいたサイバーセキュリティ研究に関する一考察
- 著者
- 宮本 大輔
- 出版者
- 日本認知心理学会
- 雑誌
- 日本認知心理学会発表論文集 日本認知心理学会第14回大会
- 巻号頁・発行日
- pp.33, 2016 (Released:2016-10-17)
近年、コンピュータシステムではなくコンピュータを利用するエンドユーザを対象としたサイバー脅威が報告されている。とりわけ、金融機関などに似せて作られたウェブサイトを用いてユーザを騙すなどの攻撃の被害は増加している。従来、サイバーセキュリティ分野ではユーザが偽サイトを見分けるためのサポートが研究課題であり、教材の開発やインタフェースの改善、検知して知らせるソフトウェアといった対策が行われている。ここで、サイバー脅威に対するエンドユーザの思考を、コンピュータシステムがエンドユーザから観測される情報から推測できると考える。我々は被験者を集めて実験を行い、ウェブサイトの真贋判定を行う際の眼球運動から被験者がどのような意思決定を行うかを予想する研究を行った。この先行研究を紹介するとともに、認知心理学の知見をサイバーセキュリティ分野に応用できるかを議論する。
- 著者
- 後藤 史彦 西薗 由依
- 出版者
- 国公私立大学図書館協力委員会
- 雑誌
- 大学図書館研究 (ISSN:03860507)
- 巻号頁・発行日
- vol.106, pp.54-62, 2017-05-31 (Released:2017-09-22)
2015年9月16日から19日にかけて,欧州における日本分野資料の専門家によるグループ「日本資料専門家欧州協会(EAJRS)」の第26回年次大会がオランダのライデンにて開催された。今大会では「Breaking Barriers - Unlocking Japanese Resources to the World」をテーマに掲げ,従来あまり知られてこなかった一次資料を普及させるための取り組みに焦点があてられた。筆者らは,今大会において,所属する長崎大学と鹿児島大学がそれぞれ所有する貴重資料について,保存および公開の取り組みを紹介した。その発表内容を含め,今大会の概要を報告する。
3 0 0 0 OA 国際地理オリンピック2015国内3次試験の設計と実践
- 著者
- 香川 貴志 井上 明日香
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- E-journal GEO (ISSN:18808107)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.2, pp.136-144, 2016 (Released:2016-03-15)
- 参考文献数
- 18
国際地理オリンピック(iGeo)は,主に高校生が選手として出場する競技会で,最近では国際地理学会議(IGC)の地域大会の開催地で毎年催されている.日本は長らく苦戦を続けていたが,直近の2015年8月にロシアのトヴェリで開催されたiGeoでは,代表選手の全員がメダルを獲得するという史上初の快挙を成し遂げた.その背後には,日本代表選手の選考にあたっての選抜試験の工夫,代表選手に対する強化研修の取り組みなど,成績の改善に向けた不断の取り組みがある.本稿では,前者に焦点を当てて,2015年における3次試験の内容を紹介し,地理教育を改善していくための一助としたい.
3 0 0 0 OA 非線形Receding Horizon制御の自動操船システムへの適用
- 著者
- 浜松 正典 加賀谷 博昭 河野 行伸
- 出版者
- The Society of Instrument and Control Engineers
- 雑誌
- 計測自動制御学会論文集 (ISSN:04534654)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.8, pp.685-691, 2008-08-31 (Released:2013-02-25)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 6 6
Recently, maritime works, such as ocean observation or cable laying works, become efficient with the dynamic positioning control of the vessels. The conventional PID control is still useful but the performance is not enough for precise positioning or multiple waypoints tracking. In this paper, we present the application of real-time nonlinear Receding Horizon control for route tracking problem and control allocation problem for vessels equipped with azimuth thrusters. The performance and usefulness of the proposed method is verified with the actual cable laying works.
- 著者
- 仲田 勇人 Peter Martin Anuradha Wijesinghe 白井 隼人 松永 彰生 冨永 浩之
- 出版者
- 公益社団法人 計測自動制御学会
- 雑誌
- 計測自動制御学会論文集 (ISSN:04534654)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.2, pp.175-181, 2018 (Released:2018-02-20)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 3
This paper considers an application of a C/GMRES-based model predictive control (MPC) method to a diesel engine air path system. The plant model is derived based on the physical first principle to explicitly take account of plant nonlinearities. Since the plant has unmeasurable states, we employ an extended Kalman filter to estimate them. Then we design a C/GMRES-MPC algorithm and apply it to a real engine. We demonstrate the effectiveness of the present method by showing experimental results using a real vehicle.
3 0 0 0 OA 精神障害者へのハンドケアリング前後の変化
- 著者
- 渡邉 久美 國方 弘子 三好 真琴
- 出版者
- 公益社団法人 日本看護科学学会
- 雑誌
- 日本看護科学会誌 (ISSN:02875330)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, pp.146-154, 2015-10-25 (Released:2015-11-05)
- 参考文献数
- 21
本研究は,独自に開発したソフトタッチの皮膚接触をベースとするハンドケアリングを精神障害者に実施し,その効果を,心拍変動,アミラーゼなどの自律神経活動指標と,不安,リラックス度,疲労度,会話欲求度,親近感の心理的指標を用いて明らかにした.対象は地域で生活する精神障害者10名(平均年齢56.7±14.9歳)であり,内田クレペリンテストによる負荷後,座位対面式にて15分間のハンドケアリングを実施した.各指標を実施前後で比較分析した結果,心拍数は有意に低下し,pNN50は有意に増加した.STAI得点は,特性不安と状態不安ともに実施後に有意に低下し,VASを用いた主観的評価では疲労度のみが有意に低下した.施術者との会話欲求度と親近感は,実施後50%以上増加した.唾液αアミラーゼは,安静時と実施前後で有意差を認めなかった.ハンドケアリングは,副交感神経活動の亢進および,不安や主観的疲労感の軽減とともに,施術者との心理的距離に良好な影響を与えており,患者–看護師関係の形成に向けた活用の可能性が示された.
- 著者
- Hiroki Yoshioka Tsunemasa Nonogaki Yasuro Shinohara Masumi Suzui Yurie Mori Gi-Wook Hwang Katsumi Ohtani Nobuhiko Miura
- 出版者
- The Japanese Society of Toxicology
- 雑誌
- The Journal of Toxicological Sciences (ISSN:03881350)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.2, pp.129-134, 2018 (Released:2018-02-26)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 7
The aim of the present study is to investigate the “chronotoxicity” of seven metal compounds (Hg, Pb, Ni, Cr, Cu, Zn, or Fe) by assessing how their toxicity varies with circadian periodicity. Male ICR mice were injected with each metal compound intraperitoneally at 6 different time points over the course of a day (zeitgeber time [ZT]: ZT2, ZT6, ZT10, ZT14, ZT18 and ZT22). Mortality was then monitored until 14 days after the injection. Our investigation demonstrated that mice were tolerant against Ni toxicity during dark phase, on the other hand, they were tolerant against Cr toxicity during light phase. The chronotoxicity of Hg and Pb seemed to be biphasic. Further, mice were susceptible to toxicities against Cu and Zn in the time zone during which light and dark were reversed. Interestingly, no significant differences were observed for Fe exposure at any time of the day. Our results propose that the chronotoxicology may provide valuable information regarding the importance of injection timing for not only toxicity evaluation tests but also the reproducibility of animal experiments. Furthermore, our data suggests that chronotoxicology may be an important consideration when evaluating the quality of risk assessments for night shift workers who may be exposed to toxic substances at various times of the day.
- 著者
- Kenshi Hayashi Toyonobu Tsuda Akihiro Nomura Noboru Fujino Atsushi Nohara Kenji Sakata Tetsuo Konno Chiaki Nakanishi Hayato Tada Yoji Nagata Ryota Teramoto Yoshihiro Tanaka Masa-aki Kawashiri Masakazu Yamagishi on behalf of the Hokuriku-Plus AF Registry Investigators
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- pp.CJ-17-1085, (Released:2018-03-01)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 30
Background:B-type natriuretic peptide (BNP) may be a predictor of stroke risk in patients with nonvalvular atrial fibrillation (NVAF); because heart failure is associated with the incidence of stroke in AF patients. However, limited data exist regarding the association between BNP at baseline and risks of thromboembolic events (TE) and death in NVAF patients.Methods and Results:We prospectively studied 1,013 NVAF patients (725 men, 72.8±9.7 years old) from the Hokuriku-plus AF Registry to determine the relationship between BNP at baseline and prognosis among Japanese NVAF patients. During the follow-up period (median, 751 days); 31 patients experienced TE and there were 81 cases of TE/all-cause death. For each endpoint we constructed receiver-operating characteristic curves that gave cutoff points of BNP for TE (170 pg/mL) and TE/all-cause death (147 pg/mL). Multivariate analysis with the Cox-proportional hazards model indicated that high BNP was significantly associated with risks of TE (hazard ratio [HR] 3.86; 95% confidence interval [CI] 1.83–8.67; P=0.0003) and TE/all-cause death (HR 2.27; 95% CI 1.45–3.56; P=0.0003). Based on the C-index and net reclassification improvement, the addition of BNP to CHA2DS2-VASc statistically improved the prediction of TE.Conclusions:In a real-world cohort of Japanese NVAF patients, high BNP was significantly associated with TE and death. Plasma BNP might be a useful biomarker for these adverse clinical events.
3 0 0 0 OA 環境と健康を守る発想の転換
- 著者
- 比嘉 照夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本農村医学会
- 雑誌
- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.6, pp.784-789, 1996-03-30 (Released:2011-08-11)
- 参考文献数
- 9
Chemical fertilizers, pesticides and large-size machinery characterize present-day intensive agricultural operations. Technological advances in the application of those chemicals and machinery have made a large contribution toward solving the food problem, to be sure, but with detriment to the earth's environment and endangering man's health. Such untoward consequences were also observable not in agriculture and the manufacturing industry alone but in medicine and many other branches of science as well. In 1972, I was diagnosed with pesticide poisoning. With this as a turning point, I washed my hands of modern agriculture, which had been in my line for many years, and decided to do research in microbiology in earnest with my sights set on establishing farming of the sort that is friendly to the natural environment and compatible with the laws of nature. So far, I have harvested well over 2, 000 varieties of microbes. At least two years would be required for the study of one variety thoroughly if conventional methods were employed. So, I gave up all the old ways and resorted to my own method of eliminating harmful bugs and unpleasant odors using pH values and activated water. As a result, a symbiotic group of colonies made up of more than 80 kinds of “effective microorganisms”(EMs) has been formed.Without reliance on chemical fertilizers and pesticides, it has become possible to produce more than twice as much crops of high quality only by dint of EMs. Not only that, those microscopic organisms have proved to be surprisingly helpful in the improvement as well as conservation of the environment. Agricultural, livestock and fishery products produced through the use of EMs are rated high as healthy foods today. Now that it has been made clear that the favorable effects of EMs are due to the antioxidizing substances synthesized by EMs, the scope of their application is being expanded from the above-mentioned sectors to medicine, manufacturing industry, environmental protection, energy resource development and so on. Thus, the EM technology is hailed as something that will bring about a new industrial revolution.The principle of the technology is very simple: Oxidation breaks down everything on earth, but is prevented by the work of antioxidizing substances formed in EMs. The application of this principle could not have been thought of no matter how much the knowledge of modern science as based on the law of entropy was extended. A good idea occurs when you get your thinking on a different track, see the natural phenomena as they are and study them multidimensionally.
3 0 0 0 OA 現代中国における基督教の発展と国家
- 著者
- 上野 正弥
- 出版者
- 一般財団法人 アジア政経学会
- 雑誌
- アジア研究 (ISSN:00449237)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.1, pp.40-55, 2018-01-31 (Released:2018-03-02)
- 参考文献数
- 57
To control Christians and their religious activities, the Chinese Communist Party (CCP) established the Three-Self Patriotic Movement (TSPM) committees in 1954 and required Protestant churches to register with these committees. However, the number of non-registered house churches has been growing rapidly since the end of the Cultural Revolution. During the first decade of the 21st century, new house churches, whose leading members are students and intellectuals, developed in large cities. This paper studies the Chinese government’s response to the development of Protestant churches. The national government has devolved the mandate to develop religious policies to local government in order to address concerns about Protestant churches. Provincial governments have a mandate to establish regulations for religious affairs, and some have established regulations that allow local churches in their jurisdiction to receive donations from Christian organizations abroad. Local governments adopt these policies in order to encourage Protestant churches to supply welfare and public services to the residents instead of the government. In 2001, the CCP central committee decided to build networks of religious affairs management among governments of counties, townships, and villages to post religious affairs staff to a grassroots community. However, local governments have not been willing to build these networks or strengthen the management of Protestant churches for the following reasons. First, local governments want the churches to provide public services. Second, they emphasize economic development rather than religious affairs management in their jurisdictions. Third, they have been ordered to reduce and simplify government organizations by the central government; hence, it is difficult to increase the number of staff members assigned to religious affairs. On the other hand, some local governments and churches registered with TSPM committees have begun to approach individual house churches directly. TSPM churches provide pastoral work, services, and materials for some house churches. The government is trying to apply this approach across the country, but even some pastors of TSPM churches have doubts about this approach because some house churches fundamentally do not want to involve with the government or TSPM churches. Meanwhile, some local governments scout out house churches and order them to dissolve if they have connections with hostile forces abroad. Through these analyses, this paper reveals that the Chinese government has been confronting challenges in implementing policies for church affairs management because each stakeholder has different priorities.
3 0 0 0 OA 多種の油脂を用いた琉球菓子“ちんすこう”の調製
- 著者
- 成田 亮子 島村 綾 名倉 秀子 峯木 眞知子
- 出版者
- 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会大会研究発表要旨集 平成28年度大会(一社)日本調理科学会
- 巻号頁・発行日
- pp.25, 2016 (Released:2016-08-28)
(目的) 琉球王朝菓子ちんすこうは、豚脂(ラード)を使用し、西洋の焼菓子とは異なった食感と風味に特徴があり、保存性にもすぐれている。ラードの代わりに多種の油脂を用いて調製し、テクスチャーに与える影響を調べた。(方法) ちんすこうはラード(油脂)、薄力小麦粉(日清フーズ㈱)、砂糖(三井製糖㈱)で調製する。油脂は8種(ラード、バター、アボガドオイル、オリーブオイル、キャノーラ油、ココナッツオイル、胡麻油、米油)で、基本配合は予備実験より、小麦粉120g、砂糖90g、油脂58gとした。油脂を60℃に温め、砂糖を加え、みぞれ状態になったら、小麦粉を加えた。それを、Ø3.5㎝の大きさ(各15g)に形成後、150℃で28分焼成した。焼成後の試料は、重量、体積、比体積、水分含有率、表面の焼き色、破断特性を測定し、官能評価を行った。焼成後の伸びを示すスプレッド値は、直径(㎜)/厚さ(㎜)で算出した。製品の水分含有率は赤外線水分計(㈱ケット)で110℃、80分の条件下で測定した。破断特性はレオナーRE2-3305 B-1(山電(株))で測定した。(結果) 8種の油脂を用いた試料では、ラードを用いた試料より、破断応力および破断歪が低く、もろい製品であった。アボガドオイル試料、オリーブオイル試料では、もろさおよびもろさ歪がかなり低かった。キャノーラ油試料ではスプレッド値、比体積、水分含有率がラードに近い値を示した。ココナツオイル試料では、スプレッド値が6.0と最も高く、水分含有率は3.6%で最も高い値を示した。胡麻油試料ではもろさおよびもろさ歪が高く、水分含有率が2.6%で最も低かった。油の種類により、食感の異なるちんすこう製品ができた。
3 0 0 0 OA 脳出血の血圧管理
- 著者
- 佐藤 祥一郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本脳卒中学会
- 雑誌
- 脳卒中 (ISSN:09120726)
- 巻号頁・発行日
- pp.10605, (Released:2018-02-27)
- 参考文献数
- 40
脳出血急性期の血圧上昇は,転帰不良の強力な予測因子である.発症6 時間以内の急性期脳出血に対する積極降圧療法(目標収縮期血圧<140 mmHg)の有効性を検討したThe Intensive Blood Pressure Reduction in Acute Cerebral Haemorrhage Tria(l INTERACT)2試験により,急性期の積極降圧療法が機能的転帰を改善することが示され,国内外のガイドラインの記載が相次いで改訂された.しかし,最近発表されたAntihypertensive Treatment of Acute Cerebral Hemorrhage(ATACH)-II 試験では,発症4.5 時間以内の患者を対象に,より厳格な降圧療法の効果を検討したが,転帰改善効果は証明されなかった.したがって,脳出血急性期における降圧目標の下限や最適な降圧方法に関してはいまだ明らかになっていない.脳卒中再発防止における降圧療法の有用性は証明されており,複数のガイドラインで130/80 mmHg 未満のコントロールを推奨している.しかし,これを直接支持する無作為化比較試験のエビデンスは乏しく,現在,国際共同試験Triple Therapy Prevention of Recurrent Intracerebral Disease EveNts Tria(l TRIDENT)が進行中である.
- 著者
- Doyeon Hwang Hyun Kuk Kim Joo Myung Lee Ki Hong Choi Jihoon Kim Tae-Min Rhee Jonghanne Park Taek Kyu Park Jeong Hoon Yang Young Bin Song Jin-Ho Choi Joo-Yong Hahn Seung-Hyuk Choi Bon-Kwon Koo Young Jo Kim Shung Chull Chae Myeong Chan Cho Chong Jin Kim Hyeon-Cheol Gwon Myung Ho Jeong Hyo-Soo Kim The KAMIR Investigators
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- pp.CJ-17-1221, (Released:2018-02-28)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 14
Background:There has been debate regarding the added benefit of high-intensity statins compared with low-moderate-intensity statins, especially in patients with acute myocardial infarction (AMI).Methods and Results:The Korea Acute Myocardial Infarction Registry-National Institutes of Health consecutively enrolled 13,104 AMI patients. Of these, a total of 12,182 patients, who completed 1-year follow-up, were included in this study, and all patients were classified into 3 groups (no statin; low-moderate-intensity statin; and high-intensity statin). The primary outcome was major adverse cardiac event (MACE) including cardiac death, non-fatal MI, and repeat revascularization at 1 year. Both low-moderate-intensity and high-intensity statin significantly reduced low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C; all P<0.001). Compared with the no statin group, both statin groups had significantly lower risk of MACE (low-moderate intensity: HR, 0.506; 95% CI: 0.413–0.619, P<0.001; high intensity: HR, 0.464; 95% CI: 0.352–0.611, P<0.001). The risk of MACE, however, was similar between the low-moderate- and high-intensity statin groups (HR, 0.917; 95% CI: 0.760–1.107, P=0.368). Multivariable adjustment, propensity score matching, and inverse probability weighted analysis also produced the same results.Conclusions:When adequate LDL-C level is achieved, patients on a low-moderate-intensity statin dose have similar cardiovascular outcomes to those on high-intensity statins.
3 0 0 0 OA 共働き家庭と非共働き家庭の夫妻の疲労自覚症状
- 著者
- 桑田 百代 伊藤 セツ 大竹 美登利
- 出版者
- The Japan Society of Home Economics
- 雑誌
- 家政学雑誌 (ISSN:04499069)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.6, pp.446-449, 1977-09-20 (Released:2010-03-09)
- 参考文献数
- 12
以上, 疲労自覚症状調査を生活時間とのかかわりで検討してきたが, 生活時間の上からみても, 共働き家庭では妻の労働負担によって家庭が維持されており, それは集約的に疲労の自覚症状となって反映されている.特に乳幼児をかかえた共働き妻は平均年齢がいちばん若いにもかかわらずとびぬけて疲労訴え率が高いが, これはその妻の生活時間構造にみあうものである.平日の訴え率は高い順に共働き妻, 夫, 非共働き夫, 妻で, この傾向は1967, 1971, 1975年の3回にわたる調査で同じである.全労働時間においても, 稲葉らの第1回の調査時点から, 共働き妻がいちばん多いことは変わらず, 19年を経過しても, 共働き妻は収入労働に家事労働の時間的負担が加わって, 疲れきった毎日を送っていることがわかる.各群の訴え率は, 平日, 休日とも3回の調査を通じてA>C>B型であるが, 共働き妻のA群の訴え率は回を重ねるごとに朝夕の差が大きくなっている.また, 自律神経失調症状を表わすといわれるC群は, 平日, 休日とも朝夕の訴え率が増加している.
3 0 0 0 OA 日本発・世界に広がる二次元コード:QRコード
- 著者
- 原 昌宏 岩井 誠人 佐波 孝彦 菊間 信良
- 出版者
- 一般社団法人 電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会 通信ソサイエティマガジン (ISSN:21860661)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.2, pp.126-132, 2013-09-01 (Released:2013-12-01)
- 参考文献数
- 1
- 被引用文献数
- 1