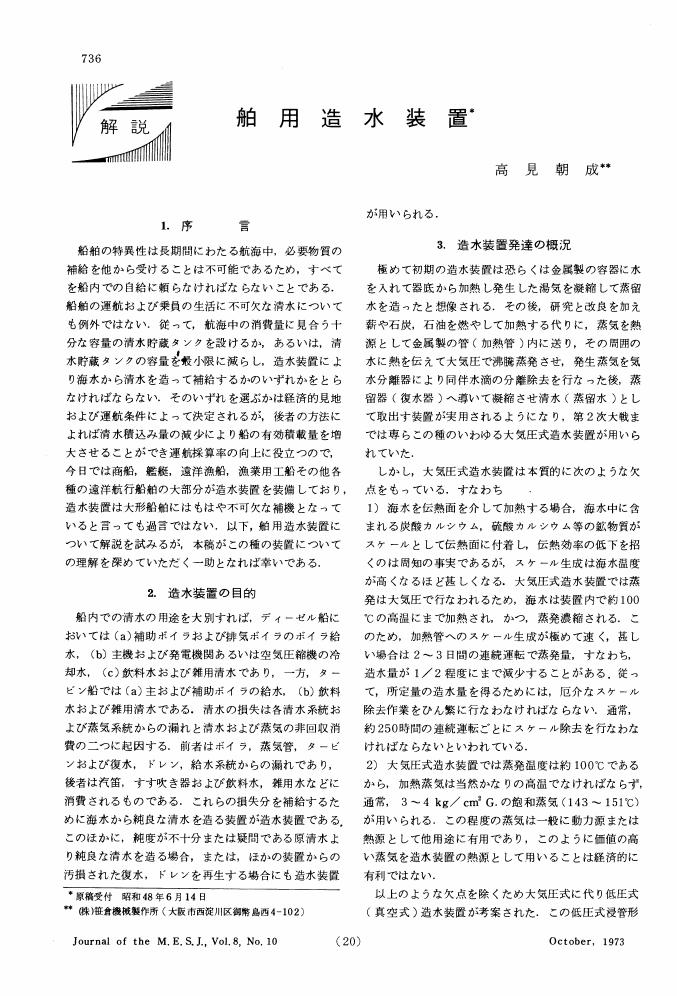6 0 0 0 OA 舶用造水装置
- 著者
- 高見 朝成
- 出版者
- 公益社団法人 日本マリンエンジニアリング学会
- 雑誌
- 日本舶用機関学会誌 (ISSN:03883051)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.10, pp.736-744, 1973 (Released:2010-05-31)
- 参考文献数
- 3
- 著者
- 谷口 泰司
- 出版者
- 近畿医療福祉大学
- 雑誌
- 近畿福祉大学紀要 (ISSN:13461672)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.2, pp.145-158, 2007-12-15
Supporting Independence to Persons with Disabilities Law, wholly implemented in October2006, is exerting a serious influence on daily life of Persons with Disabilities. Especially, two influences must not be neglected. There are "a problem of a supportingterm artificially established by law", and "a problem of a revenue source". And now, allof many problems including there two are more serious for community life of not onlypersons with disabilities, but also all citizens. To solve these problems, informal resources in each community are indispensable inaddition to formal support. But community welfare in Japan is faced with a shortage of innerregulation principle to drive forward. An Independence Support Conference to Persons with Disabilities, althought it is holdingremarkable difference of municipalities' temperature as of today, will be a bridgehead to finda way out of these difficulies. Various approaches by this Conference will be most effecive to break down a feeling of ablockade in welfare for persons with disabilities, and to aim at subimation to communitywelfare in a true meaning.
6 0 0 0 OA サバ類に寄生しているアニサキス亜科線虫幼虫の特性および殺滅条件の検討
6 0 0 0 OA 日本の洞窟並に地下水産巻貝類
- 著者
- 黒田 徳米 波部 忠重
- 出版者
- The Malacological Society of Japan
- 雑誌
- 貝類學雜誌ヴヰナス (ISSN:24330698)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.3-4, pp.183-196, 1958-02-28 (Released:2018-01-31)
6 0 0 0 IR 日本戦闘的無神論者同盟の活動
- 著者
- 田中 真人 Masato Tanaka
- 出版者
- 同志社大学人文科学研究所
- 雑誌
- 社会科学 (ISSN:04196759)
- 巻号頁・発行日
- no.27, pp.p209-243, 1981-02
論説
6 0 0 0 OA 編集委員会ワークショップ 学術書が出版されるまで:
6 0 0 0 OA 非理工系学生のための音響教育(<小特集>大学における音響教育の現状)
- 著者
- 西村 明 亀川 徹 星芝 貴行
- 出版者
- 一般社団法人 日本音響学会
- 雑誌
- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.5, pp.294-299, 2009-05-01 (Released:2017-06-02)
- 参考文献数
- 3
6 0 0 0 OA 糖質制限により血清尿酸値が上昇した一例
- 著者
- 横関 美枝子 大山 博司 田中 万智 大槻 美佳 諸見里 仁 大山 恵子 藤森 新
- 出版者
- 一般社団法人 日本痛風・核酸代謝学会
- 雑誌
- 痛風と核酸代謝 (ISSN:13449796)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.1, pp.132, 2017-07-25 (Released:2017-07-25)
6 0 0 0 OA 織田権力の到達 : 天正十年「上様御礼之儀」をめぐって
- 著者
- 原田 正記 ハラダ マサキ Masaki Harada
- 雑誌
- 史苑
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.1, pp.43-49, 1991-01
6 0 0 0 OA カンディンスキーの色彩理論とその実践
- 著者
- 江藤 光紀 Eto Mitsunori
- 出版者
- 筑波大学人文社会科学研究科現代文化・公共政策専攻
- 雑誌
- 論叢現代文化・公共政策 (ISSN:13499513)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.1-24, 2007-03-13
- 著者
- 柳澤 博紀 杉浦 琢
- 出版者
- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 認知行動療法研究 (ISSN:24339075)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.1, pp.15-23, 2020-01-31 (Released:2020-10-23)
- 参考文献数
- 15
チック症状に対する行動療法として、ハビット・リバーサル(Habit Reversal: HR)の有効性が示されているが、音声チックや重症度の高い症例の蓄積が少ないと国内外で指摘されている。本研究では叫び声様の重度音声チック症状を抱えたクライエント(Cl.)に対してHRを含んだ行動療法を実施し、客観的行動指標を用いたうえで単一症例研究法により効果を検証した。Cl.は40代女性、入院後約1カ月の服薬治療も著効なく行動療法を開始した。ベースラインでは1日5時間の測定を4日行い、叫び声の頻度は1日平均93.5回であった。介入は各回約15分程度心理士と共に咳払いを用いた競合反応訓練を練習すること、および同様の練習を日常的に実施する宿題であった。介入は25日間で10回実施した。介入開始後叫び声の頻度は大幅に減少し、約4週で叫び声は生起しなくなりCl.は退院した。介入実施後3年経過後も症状の再発は見られていない。重度音声チック症状に対するHRの有効性が示唆された。
- 著者
- Hidenobu Takami Mariko Nakamoto Hirokazu Uemura Sakurako Katsuura Miwa Yamaguchi Mineyoshi Hiyoshi Fusakazu Sawachika Tomoya Juta Kokichi Arisawa
- 出版者
- Japan Epidemiological Association
- 雑誌
- Journal of Epidemiology (ISSN:09175040)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.12-20, 2013-01-05 (Released:2013-01-05)
- 参考文献数
- 44
- 被引用文献数
- 58 82
Background: It is unclear whether consumption of coffee and green tea is associated with metabolic syndrome.Methods: This cross-sectional study enrolled 554 adults who had participated in the baseline survey of the Japan Multi-Institutional Collaborative Cohort (J-MICC) Study in Tokushima Prefecture, Japan. Consumption of coffee and green tea was assessed using a questionnaire. Metabolic syndrome was diagnosed using the criteria of the National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III (NCEP ATP III) and the Japan Society for the Study of Obesity (JASSO). Logistic regression analysis was used to examine the association between consumption of coffee and green tea and prevalence of metabolic syndrome and its components.Results: After adjustment for sex, age, and other potential confounders, greater coffee consumption was associated with a significantly lower prevalence of metabolic syndrome, as defined by NCEP ATP III criteria (P for trend = 0.03). Participants who drank more coffee had a lower odds ratio (OR) for high serum triglycerides (P for trend = 0.02), but not for increased waist circumference or high blood pressure. Using JASSO criteria, moderate coffee consumption (1.5 to <3 cups/day) was associated with a significantly lower OR for high plasma glucose (OR = 0.51, 95% CI 0.28–0.93). Green tea consumption was not associated with the prevalence of metabolic syndrome or any of its components.Conclusions: Coffee consumption was inversely correlated with metabolic syndrome diagnosed using NCEP ATP III criteria, mainly because it was associated with lower serum triglyceride levels. This association highlights the need for further prospective studies of the causality of these relationships.
- 著者
- 色川 大吉
- 出版者
- 東京経済大学
- 雑誌
- 東京経大学会誌 (ISSN:04934091)
- 巻号頁・発行日
- no.57, pp.105-132, 1968-03
6 0 0 0 IR 徳川実紀の編纂について (小特集 歴史編纂の比較史)
- 著者
- 藤實 久美子
- 出版者
- 史料館
- 雑誌
- 史料館研究紀要 (ISSN:03869377)
- 巻号頁・発行日
- no.32, pp.199-181, 2001-03
6 0 0 0 OA 北大西洋条約の形成と米国の軍事コミットメントの成立
- 著者
- 太田 歌子
- 出版者
- 北海道大学大学院法学研究科
- 雑誌
- 北大法学研究科ジュニア・リサーチ・ジャーナル
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.303-327, 2001-12
6 0 0 0 IR 幕末期京都情報の流布をめぐって
- 著者
- 後藤 重巳
- 出版者
- 別府大学会
- 雑誌
- 別府大学紀要 (ISSN:02864983)
- 巻号頁・発行日
- no.38, pp.1-12, 1997-01
岡藩と情報収集の機能 幕末江戸・京都事情の概要 豊後筋への京都情報 京都情報の内容と情報源 後藤碩田・龍之進・石友と伊藤樵渓 龍之進の情報源 「別系」情報
6 0 0 0 OA 症例検討「脳症を伴った急性心筋炎の1例」
- 著者
- 猪子 森明 木村 祐樹 舩迫 宴福 辰野 健太郎 小松 研一 松崎 直美 松山 高明
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.104, no.10, pp.2241-2254, 2015-10-10 (Released:2016-10-10)
6 0 0 0 奇抜な名前が社会的評価の印象形成に及ぼす影響
- 著者
- 伊藤 資浩 宮崎 由樹 河原 純一郎
- 出版者
- 日本認知心理学会
- 雑誌
- 日本認知心理学会発表論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2016, 2016
外見や社会的地位だけでなく名前そのものが対人評価に影響することがある。例えば,名前の魅力や流暢性の高さが付加価値となり,社会的な評価場面において好意的な印象が形成される。本研究では,名前の奇抜さが見た目の社会性,特にリーダーシップ性に及ぼす影響を検証した。具体的に,名前の奇抜さ(奇抜な名前・一般的な名前)と元々の見た目のリーダーシップ性の程度(低群・中群・高群)を実験要因として,被験者は呈示される若年者の顔画像と名前から見た目のリーダーシップ性の程度を評価した。その結果,元々の見た目のリーダーシップ性の程度に関わらず,一般的な名前に比べて奇抜な名前が呈示されたとき,リーダーシップ性は低く評価された。またこの効果は,高齢者の顔画像が呈示されたとき強く生じた。これらの結果は,近年のいわゆるキラキラネームは社会性評価において付加価値とならず,外見に関わらず非好意的な印象を生むことを反映している。