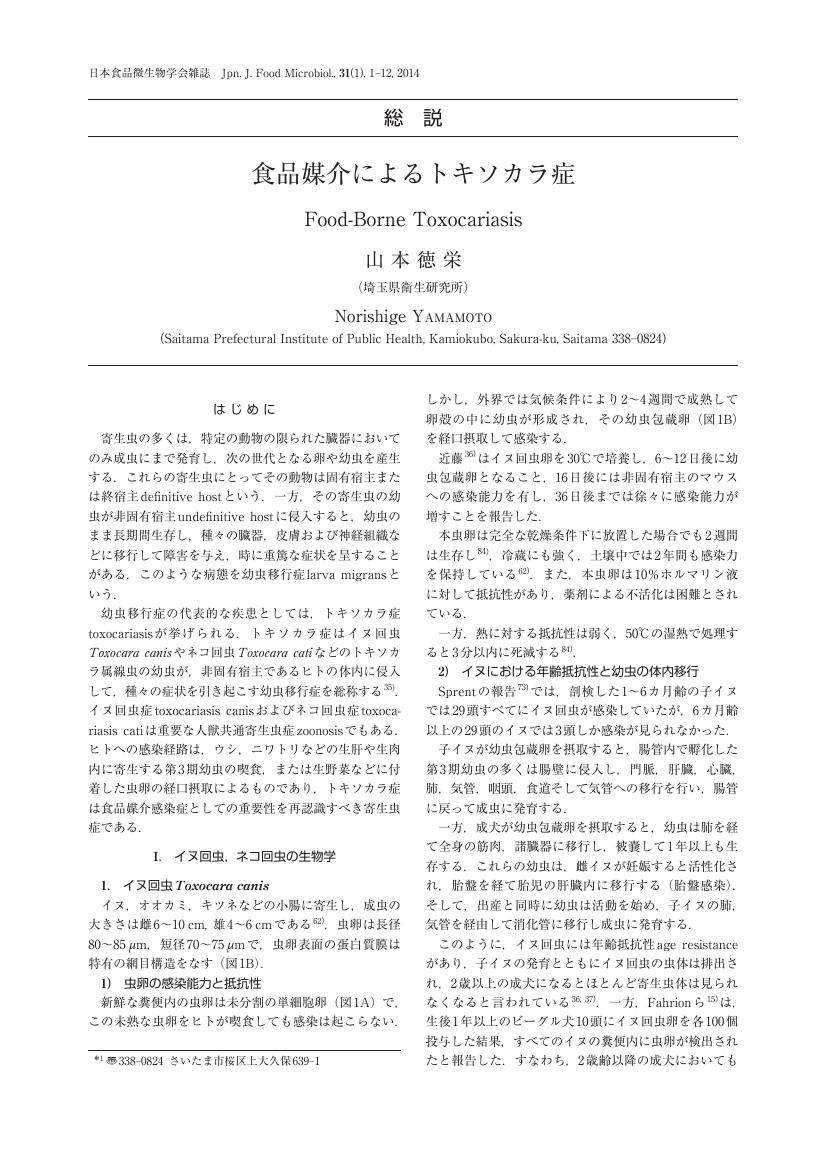5 0 0 0 OA びぶろす
- 著者
- 国立国会図書館総務部
- 出版者
- 国立国会図書館
- 巻号頁・発行日
- no.(94), 2022-08
- 著者
- 坂田 勝彦
- 出版者
- The Kantoh Sociological Society
- 雑誌
- 年報社会学論集 (ISSN:09194363)
- 巻号頁・発行日
- vol.2008, no.21, pp.49-59, 2008
Beginning in the modern era as part of the process of national state formation, the Japanese government adopted an isolation policy for people with Hansen's disease in which sufferers were segregated from the general public and confined to sanatoria. This isolation policy was in effect for a century, ending only recently in 1996.<br>Meanwhile, in post-war Japan, there were some who left the sanatorium. This article examines the experience of Hansen's disease sufferers who left the sanatorium, in order to explore how they constructed plural life-worlds through resisting 'isolation'. 'Return to society' for the sufferers meant that they tried to build several relationships and selves outside the sanatorium.
5 0 0 0 OA 講演 精神病者の絵画
- 著者
- 村上 仁
- 出版者
- 日本美術教育学会
- 雑誌
- 美術教育 (ISSN:13434918)
- 巻号頁・発行日
- vol.1957, no.36, pp.10-16, 1957-09-10 (Released:2011-08-10)
- 著者
- 宮前 良平 藤阪 希海 上總 藍 桂 悠介
- 出版者
- 国立大学法人 大阪大学大学院人間科学研究科附属未来共創センター
- 雑誌
- 未来共創 (ISSN:24358010)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.243-275, 2022-03-31 (Released:2022-07-22)
本稿は共生・共創を考えるうえで重要なテクストである『サバルタンは語ることができるか』(スピヴァク 1998 = Spivak 1988)(以下『サバルタン』)の共読を通して、スピヴァクによる表象(代表/表現)の問題意識を共生学の3つの アスペクト(フィロソフィー、アート、サイエンス)から多角的に捉えなおすことを目的とする。第1章では、『サバルタン』の共読の舞台となった読書会がはじまった経緯を述べ、正しく内容を読み取ることを志向しながらも「読みの差異」が生まれたことに着目する。第2章では、共生のフィロソフィーの視点から『サバルタン』におけるスピヴァクの立ち位置を確認する。その際にスピヴァクによる自己言及に着目し、サバルタン連続体の見方を導入することの重要性を述べる。第3章では、共生のアートの視点からテクスト経験をオートエスノグラフィとして表現することを通して、自らのサバ ルタン性を語り直す。第4章では、共生のサイエンスの視 点から調査研究を行う際のサバルタン性との関わりを反省的に描き出す。最後にこれらの「読みの差異」を、ポジショナリティの差異として環状島モデルに布置し整理することで、「サバルタン」と、語る主体としての私との関係性を考察する。
5 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1923年08月18日, 1923-08-18
5 0 0 0 IR 無力化とエンパワメント -施設的ケアからパーソナル・アシスタンスへの移行に関する研究-
5 0 0 0 OA 父親の育児参加が母親,子ども,父親自身に与える影響に関する文献レビュー
- 著者
- 加藤 承彦 越智 真奈美 可知 悠子 須藤 茉衣子 大塚 美耶子 竹原 健二
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.5, pp.321-337, 2022-05-15 (Released:2022-05-24)
- 参考文献数
- 50
- 被引用文献数
- 1
目的 近年,父親の育児参加に対する社会の関心が高まりつつある。しかし,父親が積極的に育児参加することによってどのような影響があるのかあまり明らかになっていない。本研究では,我が国で主に2010年以降に報告されている父親の育児参加に関する研究の知見についてレビューを行い,日本社会において父親の育児参加が母親,子ども,父親自身に与える影響に関する知見をまとめた。さらに,今後の課題についても検討を行った。方法 医学中央雑誌文献データベース,JSTPlus,JMEDPlusを用いて,「乳幼児関連」,「父関連」,「育児関連」のキーワードで2010年以降に掲載された和文原著論文の検索を行った。また,PubMedを用いて,「father or paternal」,「childcare OR co-parenting OR involvement」で英文原著論文の検索を行った。また,日本国内の研究,乳幼児期がいる家庭を対象,質問紙を用いた量的研究,2010年以降に掲載などの条件を設定した。これらの条件を満たした26編の論文(和文22編,英文4編)について,対象者(母親,父親,両者),育児参加方法の内容,アウトカムの内容,得られた知見などについて検討を行った。結果 父親の育児参加の影響に関する過去10年間の和文論文および過去20年間の英文論文の文献レビューの結果,次の2点の傾向が見られた。第1点目として,母親が父親の積極的な育児参加を認知している場合,母親の育児負担感が低く,幸福度が高い傾向が見られた。また,子どもの成長においても,母親が父親の積極的な育児参加を認知している場合,子どもの健康や発達(怪我や肥満の予防)に良い影響を及ぼしている可能性が示唆された。しかし,第2点目として,父親が自分自身で評価した育児参加の度合いは,母親の負担感などとは直接に関連しない可能性が示唆された。父親の育児参加が父親自身に与える影響(QOL等)は,研究の数が少ないこともあり,一貫した傾向は見られなかった。また,父親の育児参加の評価の方法がそれぞれの研究で異なっていた。結論 今後,父親の育児参加が積極的に推奨されると同時に,その影響についても社会の関心が高まると推測される。今後の課題として,父親の育児参加の量および内容をどのように適切に評価するのかに関する議論を深める必要が示唆された。
- 著者
- 四元 真弓 ヨツモト マユミ Mayumi Yotsumoto
- 出版者
- 鹿児島国際大学
- 巻号頁・発行日
- 2020
5 0 0 0 IR 皇帝を殺す : 中国における至高者を殺害する物語についての予備的研究
- 著者
- 川田 耕 Koh Kawata 京都学園大学経済学部
- 出版者
- 京都学園大学経済学部学会
- 雑誌
- 京都学園大学経済学部論集 = Journal of the faculty of economics Kyoto Gakuen University (ISSN:09167331)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.33-50, 2013-09
近世の中国にあっては支配的な規範や価値を侵犯し逸脱するような、秩序転覆的な物語が多く生まれ各地の民衆に広がっていた。四大奇書と四大伝説のいずれもがそうした秩序転覆性を多かれ少なかれもつが、民話においては皇帝を庶民が殺してしまう大胆不敵なものすら広く伝えられてきた。本稿では、そうした秩序転覆的な物語が近世中国において広く語り継がれ好まれてきた、歴史的・社会学的・心理学的な意味を明らかにするための基礎作業として、皇帝ないし王を殺す物語である、「眉間尺」、「十兄弟」、「百鳥衣」の三つの系統の民話を取り上げて、それらのもつ物語的な特質と精神的な意義を、とくに「英雄神話」型の物語との異同と日本との比較を手がかりとして、考察する。
5 0 0 0 OA 食品媒介によるトキソカラ症
- 著者
- 山本 徳栄
- 出版者
- 日本食品微生物学会
- 雑誌
- 日本食品微生物学会雑誌 (ISSN:13408267)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.1-12, 2014-03-31 (Released:2014-08-13)
- 参考文献数
- 104
- 被引用文献数
- 1 1
5 0 0 0 IR 霊魂をとらえ損ねる : 神の声から考える民衆宗教大本 (特集 日本宗教史像の再構築 : トランスナショナルヒストリーを中心として) -- (神の声を聴く : カオダイ教,道院,大本教の神託比較研究)
- 著者
- 永岡 崇
- 出版者
- 京都大學人文科學研究所
- 雑誌
- 人文学報 = Journal of humanities (ISSN:04490274)
- 巻号頁・発行日
- no.108, pp.143-158, 2015
特集 : 日本宗教史像の再構築 --トランスナショナルヒストリーを中心として-- ≪第III部 :神の声を聴く --カオダイ教, 道院, 大本教の神託比較研究--≫本稿は, 近代日本において「神の声を聴く」という営みがどのような宗教史的・思想史的可能性をもちえたのかを, 大本を事例として検討するものである。大正期大本の思想・実践は, 異端的な神話的世界を語り出しながら, 近代国家が排除した霊魂との直接的交流の道を開くものであった。しかしそれは, 霊魂を統御するという志向性を, 近代天皇制ないし靖国神社などと共有していた部分もあったのではないだろうか。鎮魂帰神法は, 霊魂を発動させて, 鎮静させ, 序列化する試みといえるのだが, それは逆にいえば, 鎮静化させ, 序列化するための発動であり, 高級霊/低級霊, 立替立直/病気治しのヒエラルキーを確認・創出するものでもあったのだ。ただし, 実践のレベルではそのプロセスには不確定領域が広がり, 統御を逃れ出る霊魂の運動を可能にすることになる。出口王仁三郎や浅野和三郎の意図する秩序は越境する霊魂と過剰な欲望によって裏切られてしまうのだ。国家主義的神道の秩序世界を掘り崩す可能性を内包していたのは, じつは王仁三郎の思想・実践そのものではなく, 人びとの野放図な欲望の法‐外さではなかったか。そして, その欲望を賦活する仕掛けとして, 鎮魂帰神法システムは再評価しうるのではないだろうか。近代日本に生きた多くの人びとは, おそらく天皇制国家を下支えする心性と, そこから逸脱しようとする欲望の双方を抱えていたのであり, 鎮魂帰神法の思想と実践は, その両義的なありようを浮かび上がらせ, そこにはらまれる緊張関係を開示してみせるものだったということができる。こうして, 鎮魂帰神法が霊魂をとらえ損ねる営みであったというところにこそ, 近代天皇制国家の論理へと還元されえない民衆宗教としての大正期大本の可能性を読み取ることができるのではないだろうか。This essay reevaluates the significance of the technique of listening to divine speech in the history of religion in modern Japan, examining in particular the case of the Ōmoto sect. The thought and practice of Ōmoto in the Taishō period opened the way to direct communication with the spirits, and their mythical worldview was considered to be heterodox by the modern nation. Yet their practice shared with the modern emperor system and Yasukuni shrine an orientation towards controlling and organizing the spirits. The Ōmoto spirit-listening technique chinkon-kishin invoked, appeased, and assigned a hierarchical ranking to the spirits ; it invoked them in order to appease and assign the ranks of higher/lower and reconstructive/healing. In actual practice, however, indeterminate factors limited this control and let the spirits escape. The order established by Deguchi Onisaburō and Asano Wasaburō was betrayed by uncontrollable spirits and surplus desire. It was the excessive desire of the believers, not Onisaburō's system, that had the potential to undermine the premise of the State Shinto. Chinkon-kishin should be reappraised as a system that activated the desire of the people against the desire of the nation. This practice and theory illuminated the ambiguity of a popular desire that supported the emperor system and deviated from it at the same time, and thereby disclosed the unmitigated tension within the disposition of the people. This failure to capture the spirits illustrates the potential of Taishō period Ōmoto as a popular religion that could not be reduced to the logic of the emperor system.
5 0 0 0 IR トマス・ネーゲル『利他主義の可能性』(第五-六章)
- 著者
- ネーゲル トマス 桜井 直文訳
- 出版者
- 明治大学教養論集刊行会
- 雑誌
- 明治大学教養論集 (ISSN:03896005)
- 巻号頁・発行日
- no.531, pp.117-153, 2017-12
5 0 0 0 IR トマス・ネーゲル『利他主義の可能性』(第九-十章)
- 著者
- ネーゲル トマス 桜井 直文
- 出版者
- 明治大学教養論集刊行会
- 雑誌
- 明治大学教養論集 (ISSN:03896005)
- 巻号頁・発行日
- no.534, pp.1-38, 2018-09
5 0 0 0 OA 高齢者をめぐる生政治 医療費増加の責めを高齢者に帰する言説の分析
- 著者
- 花岡 龍毅
- 出版者
- 科学技術社会論学会
- 雑誌
- 科学技術社会論研究 (ISSN:13475843)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.68-78, 2019-04-20 (Released:2020-04-20)
- 参考文献数
- 19
医療費が増加するのは高齢者が増えるからであるという一般に流布している見解が誤りであることは,医療経済学においては,ごく初歩的な常識である.本稿の課題は,こうした誤った認識の根底にある思想を「高齢者差別主義」と捉えた上で,こうした一種の「生物学主義」が浸透している社会の特質を,フーコーの「生政治」の思想を援用しながら検討することである. 生権力は,もともと一体であるはずの集団を,人種などの生物学的指標によって分断する.年齢などの指標によって高齢者と若年者とに分断する「高齢者差別主義」もまた生権力の機能であるとするならば,そして,もしこうした仮説が正しいなら,フーコーの指摘は現代の日本社会にも当てはまる可能性がある.フーコーが私たちに教えてくれているのは,生権力のテクノロジーである生政治が浸透している社会は,最悪の場合には自滅にまでいたりうる不安定なものであるということである.
5 0 0 0 OA テレビゲーム機の変遷--ファミコン、スーパーファミコン、プレステ、プレステ2、Wiiまで
- 著者
- 小川 純生
- 出版者
- 東洋大学経営学部
- 雑誌
- 経営論集 = Journal of business administration. (ISSN:02866439)
- 巻号頁・発行日
- no.77, pp.1-17, 2011-03
5 0 0 0 OA ストレスによる情動変容の誘導における炎症の役割
- 著者
- 北岡 志保 古屋敷 智之
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.9, pp.922-928, 2017 (Released:2017-09-01)
- 参考文献数
- 21
社会や環境から受けるストレスは内分泌系, 免疫系, 自律神経系を介したストレス応答を惹起する. しかし, これらのストレス応答がいかに統合されて情動変容や精神疾患を促すかには不明な点が多い. 近年ストレスによる情動変容における炎症様反応の重要性が確立され, この炎症様反応における内分泌系, 免疫系, 自律神経系の関与が調べられている. 末梢では, ストレスによる内分泌応答は骨髄系細胞を活性化し血中の炎症性サイトカインを上昇させ, 交感神経の活性化は血中の顆粒球・単球を増加させる. また, ストレスは腸内細菌叢を変化させ免疫系を活性化する. 脳内では, ストレスはミクログリアを活性化し炎症関連分子を介して前頭前皮質のドパミン系を抑制する. これらの知見は, 多様なストレス応答が脳内外の炎症様反応に収斂して情動変容や精神疾患を促すことを示唆しており, ストレスによる炎症様反応を標的とした新規抗うつ薬の開発を期待させる.
5 0 0 0 OA 英国における看護師の職務拡大 : 看護師による医薬品の処方に関する検討
- 著者
- 白瀬 由美香
- 出版者
- 社会政策学会
- 雑誌
- 社会政策 (ISSN:18831850)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.1, pp.102-112, 2011-06-01 (Released:2018-02-01)
本稿は,英国における看護師の職務領域の拡大について,特に医薬品の処方への従事にまつわる問題を中心に検討した。看護師の役割に関しては,現在日本でも活発に議論されていることから,アメリカ型のナース・プラクティショナーの英国への導入経緯,処方などの拡大された業務を担う看護師の現況とその制度的背景に関して考察を行った。職務拡大の要因は様々あるが,養成システムの改革および上級資格の創設,NHS改革による地域包括ケア推進の2つが相互に関連し合い,処方看護師の導入等の多職種機能の再編がもたらされた。処方看護師はいまだ少数であるものの,患者の医薬品へのアクセスの改善が評価されている。一連の改革において重要だったのは,看護助産審議会という国から独立した自主規制機関が教育・資格登録・安全管理に責任をもつ点,業務範囲の設定が法律ではなく雇主との職務記述書に任されている点であり,それらが看護師制度の基盤となっていた。
5 0 0 0 OA ジャック・リゴーに関する覚書
- 著者
- 三好 美千代 Michiyo Miyoshi
- 雑誌
- 年報・フランス研究 (ISSN:09109757)
- 巻号頁・発行日
- no.30, pp.228-240, 1996-12-25
5 0 0 0 OA 喚起的なキス サッカーにおける男らしさとホモソーシャリティ
- 著者
- 岡田 桂
- 出版者
- 日本スポーツ社会学会
- 雑誌
- スポーツ社会学研究 (ISSN:09192751)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.37-48,106, 2004-03-21 (Released:2011-05-30)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 2
英国や欧州におけるサッカー・リーグの試合では、時おり、男性選手同士がキスし合うパフォーマンスが見受けられる。こうした行為は、ゴールを決めた際の感激の表現として理解され、受け入れられてはいるが、通常想定される「男らしさ」の価値観からは逸脱している。近代スポーツは、その制度を整えてゆく過程で、男らしさという徳目に重点を置いた人格陶冶のための教育手段として用いられてきた経緯があり、サッカーを含めたフットボールはその中心的な位置を占めていた。それではなぜ、男らしさの価値観を生みだしてゆくはずのサッカー競技の中で、「男らしくない」と見なされるような行為が行われるのだろうか。この疑問を解く鍵は、近代スポーツという制度に内在するホモソーシャリティにある。男らしさの価値観を担保するホモソーシャリティは、異性愛男性同士の排他的な権利関係であり、女性嫌悪と同性愛嫌悪を内包する。サッカーをはじめとするスポーツ競技は、ジェンダー別の組織編成によって制度上の完全な女性排除を達成しており、もう一方の脅威である同性愛者排除のために、ホモフォビアもより先鋭化された形で実践されている。こうして恣意的に高められたホモソーシャルな絆によって、スポーツ界は通常の男らしさ規範に縛られない自由な表現が許される場となり、キスのような、通常であればホモソーシャリティの脅威となり得るホモセクシュアリティを仄めかすようなパフォーマンスも可能となるのである。つまり、こうした行為は「自分たちは同性愛者ではない」という確固とした前提に基づいた、逆説的な「男らしさ」の表出であるといえる。また、男性同士のキスという全く同一の行為が、プロ・サッカーという特定の文脈では「男らしさ」を表出し、他の文脈では正反対の意味を構成するという事実は、ジェンダーというものが行為によってパフォーマティヴに構築されるものであり、ジェンダーのパフォーマンスとそれが構築する主体 (不動な実体) との間の関係が恣意的なものであること、即ち、行為の実践によってそれが構築する主体をパフォーマティヴに組み替えてゆくことができる可能性を表しているといえる。