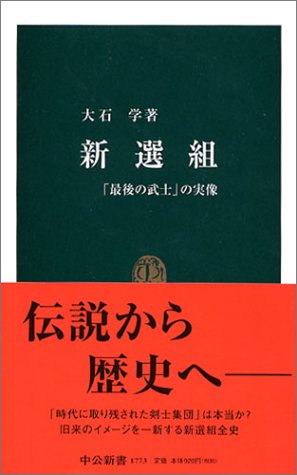- 著者
- Koichi Yoneyama Atsuko Sekiguchi Takashi Matsushima Rieko Kawase Akihito Nakai Hirobumi Asakura Toshiyuki Takeshita
- 出版者
- 日本医科大学医学会
- 雑誌
- Journal of Nippon Medical School (ISSN:13454676)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, no.1, pp.6-14, 2016-01-15 (Released:2016-03-09)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 2
Aim: The aim of the present study was to elucidate the clinical characteristics of pregnancy-associated maternal deaths. Methods: We performed a retrospective analysis with medical records and autopsy reports of cases of pregnancy-associated deaths. We collected information on all maternal deaths related to pregnancy that occurred in 3 hospitals affiliated with Nippon Medical School in Japan from January 1, 1984, to December 31, 2014. Data analyzed were maternal age, past medical history, parity, gestational age, clinical signs and symptoms, cause of death, and maternal autopsy findings. Results: A total of 26 maternal deaths occurred during the 31-year study period. Autopsies were performed for 16 patients (61.5%). The 26 deaths included 19 (73.1%) classified as direct maternal deaths and 7 (26.9%) classified as indirect maternal deaths. The mean maternal age at death was 33.1±4.3 years (range, 26-41 years). The highest percentage of women was aged 35 to 39 years (38.5%). Of the 26 maternal deaths, 69% occurred at 32 to 41 weeks of gestation. In cases of direct maternal death, the leading causes were amniotic fluid embolism (7 cases, 27.0% of all deaths) and hemorrhage (6 cases, 23.1% of all deaths). In cases of indirect obstetric deaths, the causes included cardiovascular disorders, cerebrovascular disorders, sepsis due to group A streptococcal infection, and hepatic failure of unknown etiology. Conclusions: Amniotic fluid embolism was the leading cause of maternal deaths and was followed by obstetric hemorrhage. To prevent and reduce the number of maternal deaths in Japan, further basic and clinical research on amniotic fluid embolism is required.
- 著者
- 杉山 晴康
- 出版者
- 早稲田大学法学会
- 雑誌
- 早稲田法学 (ISSN:03890546)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.1, pp.p1-37, 1983
1 0 0 0 小河滋次郎著作選集
- 著者
- 小河博士遺文刊行會編
- 出版者
- 日本評論社
- 巻号頁・発行日
- 1942
1 0 0 0 IR 竹口喜左衛門信義『横浜の記』の研究 : ミシン初伝をめぐって
- 著者
- 中山 千代
- 出版者
- 文教大学女子短期大学部
- 雑誌
- 研究紀要 (ISSN:03855309)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.1-12, 1977-12
1 0 0 0 OA <論文>『大日向村』という現象 : 満州と文学
- 著者
- 田中 益三
- 出版者
- 法政大学
- 雑誌
- 日本文學誌要 (ISSN:02877872)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, pp.78-89, 1987-12-25
1 0 0 0 伊予灘北東部における中央構造線海底活断層の完新世活動
- 著者
- 小川 光明 岡村 真 島崎 邦彦 中田 高 千田 昇 中村 俊夫 宮武 隆 前杢 英明 堤 浩之
- 出版者
- 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学論集 (ISSN:03858545)
- 巻号頁・発行日
- no.40, pp.75-97, 1992-12-15
- 被引用文献数
- 5
愛媛県伊予郡双海町沖において, 高分解能ソノプローブを用いた詳細な音波探査を実施し, 中央構造線活断層系の正確な分布と形態を記載した。さらに, 断層を挟んだ地点からピストンコア試料を採取し, それらを対比することにより, 断層活動の時期を解読した。この海域に分布する中央構造線は, 左雁行に配列する計4本の断層から構成されており, そのうちの1本には完新世における明瞭な右ずれ運動が認められる。また, この断層は近接する他の断層と同時に活動することにより, 細長い地溝を形成する。その活動時期は, 石灰質化石の^<14>C年代測定から, 約6200年前と約4000年前であると推定された。4000年前以降にも活動があったと思われるが, 残念ながら堆積速度の急減のため, 断層活動が保存されていなかった。本地域での活動性に, 陸上のトレンチ調査から解読された活動性を加味すると, 四国における中央構造線は, 少なくとも3つ以上の領域に分かれ, それぞれが約2000年の間隔で活動を繰り返していると考えられる。
1 0 0 0 OA 市販緑茶の個別カテキン類とカフェインの分析
- 著者
- 後藤 哲久 長嶋 等 吉田 優子 木曽 雅昭
- 出版者
- 日本茶業学会
- 雑誌
- 茶業研究報告 (ISSN:03666190)
- 巻号頁・発行日
- vol.1996, no.83, pp.21-28, 1996-07-31 (Released:2009-07-31)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 6 17
市販録茶試料7茶種85点の8種のカテキン類とカフェインの含有量を測定した。玉露,抹茶は煎茶,玉緑茶と比較してやや多くのカフェインを含む一方総カテキン量は少なかった。同じ茶種の中では,上級茶は一般に下級茶より多くのカフェインを含み総カテキン量は低かった。個々のカテキン類の中では,エピガロカテキンガレート(EGCg)の含有量が最も多く,総カテキン量の50~60%を占め,エピガロカテキン(EGC)と合わせた量は総量の約80%であった。遊離型カテキン(EC,EGC)の含有量は,エステル型カテキン(ECg,EGCg)の,煎茶,玉緑茶では半分以下,玉露,抹茶では1/3以下であった。玉露,抹茶では多くの試料からカテキン(C)が検出されたが,それ以外の微量カテキン類はほとんど検出されなかった。ほうじ茶のカテキン類は,加熱による変化を受けるためか量的にも少なく,その組成も他の茶種と大きく異なっていた。
1 0 0 0 OA 宋代の御筆手詔
- 著者
- 徳永 洋介
- 出版者
- 東洋史研究會
- 雑誌
- 東洋史研究 (ISSN:03869059)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.3, pp.393-426, 1998-12-31
- 著者
- 近藤 智彦
- 出版者
- 東京大学大学院人文社会系研究科哲学研究室
- 雑誌
- 哲学研究論集 (ISSN:18821510)
- 巻号頁・発行日
- no.2, pp.165-175, 2005-03
1 0 0 0 新選組 : 「最後の武士」の実像
1 0 0 0 OA 10.海ホタルルシフェリンの構造
- 著者
- 平田 義正 江口 昇次 下村 脩
- 出版者
- 天然有機化合物討論会
- 雑誌
- 天然有機化合物討論会講演要旨集
- 巻号頁・発行日
- no.3, pp.83-93, 1959-10-17
1 0 0 0 緑色蛍光たんぱく質GFPは天の恵みか?
- 著者
- 下村 脩
- 出版者
- 日本解剖学会
- 雑誌
- 解剖學雜誌 (ISSN:00227722)
- 巻号頁・発行日
- vol.85, no.3, pp.99-106, 2010-09-01
1 0 0 0 IR 無機クロマトグラフィーに関する研究-6-
- 著者
- 安永 峻五 下村 脩
- 出版者
- 日本薬学会
- 雑誌
- 薬学雑誌 (ISSN:00316903)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.7, pp.778-780, 1954-07
In electrochromatography, five kinds of different filter paper holders were used and the velocity of migration, area of colored band, and migration distance of each position on the filter paper were measured under identical conditions so as to examine the separatory ability and equality of rate of each apparatus. It was thereby found that the best separation is effected by placing the paper in a convex form, with the middle higher, while for uniform mobility, the filter paper should be cooled directly by closely adhering the lower surface on a cooling vat.
- 著者
- 益川 敏英
- 出版者
- 素粒子論グループ 素粒子研究編集部
- 雑誌
- 素粒子論研究 (ISSN:03711838)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.1, pp.A42-A43, 1972-03-20
1 0 0 0 OA Chiral対称性について(素粒子の時空記述,研究会報告)
- 著者
- 益川 敏英
- 出版者
- 素粒子論グループ 素粒子研究編集部
- 雑誌
- 素粒子論研究 (ISSN:03711838)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.2, pp.232-236, 1971-04-20
1 0 0 0 OA 複合粒子モデルとchiral symmetry(素粒子の模型と構造,研究会報告)
- 著者
- 益川 敏英
- 出版者
- 素粒子論グループ 素粒子研究編集部
- 雑誌
- 素粒子論研究 (ISSN:03711838)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.4, pp.D44-D49, 1969-12-20
1 0 0 0 OA 高密度核物質の諸相といくつかのコメント(高密度核物質,研究会報告)
- 著者
- 益川 敏英
- 出版者
- 素粒子論グループ 素粒子研究編集部
- 雑誌
- 素粒子論研究 (ISSN:03711838)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.1, 1976-10-20
1 0 0 0 OA Yang-Mills場一元論(基本粒子系の諸模型の検討,研究会報告)
- 著者
- 益川 敏英
- 出版者
- 素粒子論グループ 素粒子研究編集部
- 雑誌
- 素粒子論研究 (ISSN:03711838)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.5, pp.E23-E24, 1976-08-20
- 著者
- 益川 敏英
- 出版者
- 素粒子論グループ 素粒子研究編集部
- 雑誌
- 素粒子論研究 (ISSN:03711838)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.2, pp.H38-H39, 1973-04-20