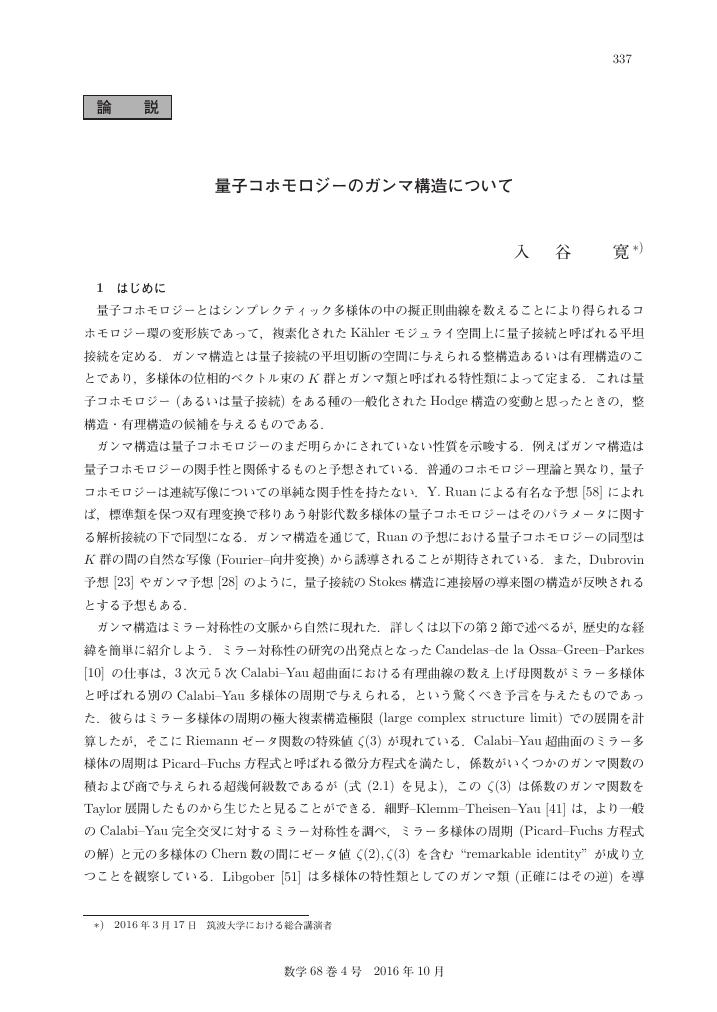5 0 0 0 角層タンパク質のカルボニル化による肌透明感の低下
- 著者
- 岩井 一郎 桑原 智祐 平尾 哲二
- 出版者
- 日本化粧品技術者会
- 雑誌
- 日本化粧品技術者会誌 (ISSN:03875253)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.1, pp.16-21, 2008
- 被引用文献数
- 3
近年, カルボニル化と呼ばれるタンパク質の変性が角層で知られるようになったが, 肌への影響は不明だった。本研究では「角層の透明度」に焦点を当て, 角層タンパク質カルボニル化の影響とその対応法について検討した。まず粘着テープで採取した角層タンパク質のカルボニル基を蛍光標識し, 画像解析により数値化する方法を開発し, 外界の影響を受けやすい露光部 (顔面) 角層, 角層表層部で角層カルボニル化レベルが高いこと, <i>in vitro</i> UV照射により角層タンパク質がカルボニル化することを示した。さらに, 頬部角層カルボニル化レベルの高い女性では, 視感判定による透明感が低いことを示した。これらより, 外界の影響による角層のカルボニル化が透明感低下の一因と考えられた。実際に角層を<i>in vitro</i>でカルボニル化処理すると角層は不透明に白濁した。さらにアミノ酸L-リジンは角層カルボニル化を抑制し, ヒト皮膚においてもカルボニル化による透明感の低下を抑制した。これらより, 外界の悪影響による角層タンパク質のカルボニル化をL-リジンによって防ぐことで, 角層透明度を保ち, 肌の透明感を向上させることができると考えられた。
5 0 0 0 IR 書評 深海菊絵著『ポリアモリー 複数の愛を生きる』
- 著者
- 阪井 裕一郎
- 出版者
- 慶應義塾大学大学院社会学研究科
- 雑誌
- 慶應義塾大学大学院社会学研究科紀要 : 社会学・心理学・教育学 : 人間と社会の探究 (ISSN:0912456X)
- 巻号頁・発行日
- no.81, pp.109-117, 2016
書評1. はじめに2. 論点 2-1. 論点① 「複数愛」とは何か 2-2. 論点② ポリアモリストにとって「所有」とは何か 2-3. 論点③ 愛という言葉について 2-4. 論点④ ポリアモリストになる契機 2-5. 論点⑤ ポリアモリストの属性について 2-6. 論点⑥ ポリアモリーの法制化をめぐって 2-7. 論点⑦ オープン・マリッジをめぐるジェンダー 2-8. 論点⑧ ポリアモリーを通じてモノガミー社会を問いなおす 2-9. 論点⑨ 親密関係における民主主義 2-10. 論点⑩ オープンな関係について3. おわりに
- 著者
- 宮澤 早紀
- 出版者
- 佛教大学総合研究所
- 雑誌
- 佛教大学総合研究所共同研究成果報告論文集 = Supplement to the bulletin of the Research Institute of Bukkyo University (ISSN:21896607)
- 巻号頁・発行日
- no.6, pp.87-94, 2018-03
本稿では,伊豆諸島にある八丈島と青ヶ島の巫者が行う死者の口寄せの事例を報告している。八丈島と青ヶ島ではミコと呼ばれる女性の巫者が,死者の口寄せを行う。これが「ナカヒト」や「ナカシト」と呼ばれた。当該地域には,ミコ以外に男性の巫者が存在する。男性の巫者と女性の巫者が共に巫業を行っていた点が,八丈島と青ヶ島の巫俗の特徴である。巫者は住民の依頼に応じて,病気治しや生業や航海安全などの祈祷,ナカヒトを行った。こうした巫業を通して,近年まで巫者が住民の生活にかかわってきた。八丈島と青ヶ島では近年まで巫者以外の宗教者が日常生活に関与することが少なく,巫者が宗教行為にたいして総合的な役割を果たしたと考えられる。こうした巫者の役割の 1 つとして,ナカヒトがあったと考えられる。巫俗巫女口寄せナカヒト
5 0 0 0 OA 2020年度大学図書館シンポジウム「オンライン授業における図書館の役割」報告
- 著者
- 国公私立大学図書館協力委員会シンポジウム企画・運営委員会
- 出版者
- 国公私立大学図書館協力委員会
- 雑誌
- 大学図書館研究 (ISSN:03860507)
- 巻号頁・発行日
- vol.118, pp.2117, 2021-08-31 (Released:2021-08-17)
5 0 0 0 OA 視界内の植生の配置が人の意識に与える影響について
- 著者
- 仁平 裕太 山田 育穂 関口 達也
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集 2017年度日本地理学会春季学術大会
- 巻号頁・発行日
- pp.100228, 2017 (Released:2017-05-03)
近年の日本では,緑被率に代わり,緑視率が人の意識に与える影響についての注目が高まってきている.特に,建物が密集する都心部において緑を確保することの重要性は高く,実際に,緑の基本計画に緑視率向上の政策が示されている自治体も存在する.また,緑視率が人に与える影響についての研究も複数存在するが,植生の配置が人々の意識に与える影響を充分に評価できているとは言いがたい.そこで本稿では,都市部における植生の量・配置を定量的に指標化し,人々の景観に対する主観的評価に与える影響を分析する.そして、得られた知見を適切な植生配置の一助とすることを目的とする.重回帰分析を用いて植生の量と配置が人々の評価に与える影響について分析した結果,目線上部にある植生は,高評価につながることが示された.つまり,植生を多く配置できない場合,中木や高木を中心に植栽を整備する方が景観上好ましいことが示唆された.
5 0 0 0 OA 量子コホモロジーのガンマ構造について
- 著者
- 入谷 寛
- 出版者
- 一般社団法人 日本数学会
- 雑誌
- 数学 (ISSN:0039470X)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.4, pp.337-360, 2016-10-25 (Released:2018-10-26)
- 参考文献数
- 68
5 0 0 0 OA アトピー性皮膚炎患者における心身の状態と皮膚症状の関連性について
- 著者
- 針谷 毅 平尾 哲二 勝山 雅子 市川 秀之 相原 道子 池澤 善郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本アレルギー学会
- 雑誌
- アレルギー (ISSN:00214884)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.6, pp.463-471, 2000-06-30 (Released:2017-02-10)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 4
アトピー性皮膚炎(AD)は心理的, 身体的ストレスによって皮膚症状が悪化することが臨床の場で知られている.本研究ではAD患者の皮膚症状を2週間毎の外来受診時にスコア化して記録すると共に, 皮膚生理指標や常在菌叢, 心理, 気分指標を患者毎に経時的に測定・検査し, それらの関連性について検討した.心理・気分指標としてはPOMS(profile of mood states)を用い, さらに患者には毎日VAS(visual analogue scale)を用いて疲労やストレス度合い, 主観的な肌の状態などを記録させた.同一患者で2ヶ月以上, 上記について検討可能であった患者18名を対象に各指標間の相関性を中心に解析した結果, POMSの抑うつ-落ち込みや緊張-不安の得点と皮膚症状スコア, 角層水分量, 総菌数との相関性が高い傾向にあり, VASによる患者のストレスの程度とかゆみなどの皮膚症状も相関する傾向を示した.以上の検討からAD患者では抑うつや緊張傾向が高まるなどの心理的なストレスや疲労などの身体的なストレスの有無と皮膚炎の増悪寛解とが互いに関連していることが示された.
- 著者
- Kazuto Takemura Hitoshi Mukougawa
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- SOLA (ISSN:13496476)
- 巻号頁・発行日
- pp.2021-029, (Released:2021-08-20)
- 被引用文献数
- 4
This study presents a possible large-scale factor of tropical cyclogenesis over the western North Pacific, which is triggered by Rossby wave breaking to the east of Japan. More than half of the wave breaking cases is accompanied by the tropical cyclogenesis. Results from a composite analysis for the wave breaking cases indicate that the genesis and development of tropical cyclones are dominant over the southwest quadrant of the wave breaking center, where an intrusion of the upper-level potential vorticity caused by the wave breaking and the consequent enhanced convection are seen. The number of tropical cyclones in the wave breaking cases exponentially increases in time during the developing stage of the wave breaking. The results of composite analysis further indicate that lower-level strong wind convergence and the associated enhanced convection, which are resulting from the wave breaking, is favorable conditions for the tropical cyclogenesis. An enhanced monsoon trough accompanied by the Pacific–Japan pattern resulting from the enhanced convection can regulate tracks of the tropical cyclones. These results show that the Rossby wave breaking can trigger the tropical cyclogenesis over the western North Pacific, through the southwestward intrusion of the upper-level potential vorticity and the consequent enhanced convection.
5 0 0 0 哺乳類学者・進化学者 徳田御稔の足跡
- 著者
- 大舘 智志 金子 之史 岩佐 真宏 本川 雅治 三中 信宏
- 出版者
- The Mammal Society of Japan
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.1, pp.206-211, 2011-06-30
5 0 0 0 IR 日本とドイツの反フェミニズムとナショナリズム (故山口定教授追悼論文集)
- 著者
- 姫岡 とし子
- 出版者
- 立命館大学政策科学会
- 雑誌
- 政策科学 = Policy science (ISSN:09194851)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.3, pp.229-244, 2015-03
5 0 0 0 OA グスコーブドリの伝記 : 童話
5 0 0 0 ミノキシジルの発毛作用について
- 著者
- 小友 進
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.119, no.3, pp.167-174, 2002-03-01
- 参考文献数
- 59
- 被引用文献数
- 4 24
毛髪の長さと太さは主に毛包サイクルの成長期毛包の期間の長さで決まる.成長期はVEGF,FGF-5S,IGF-1,KGF等の細胞成長因子で維持されている.しかし体内時計によって設定された時が満ちれば,FGF-5,thrombospondin,あるいは何らかの未同定の因子により成長期は終了し,毛母細胞にアポトーシスが誘導され退行期へと移行する.男性型脱毛症は遺伝的背景の下に男性ホルモンによって,より早期に成長期が終了する事によっておこる毛包の矮小化である.ミノキシジルの発毛効果はsulfonylurea receptor(SUR)を作動させ,(2)血管平滑筋ATP感受性Kチャネル開放による毛組織血流改善,(3)毛乳頭細胞からのVEGFなど細胞成長因子の産生促進,(4)ミトコンドリアATP感受性Kチャネル開放による毛母細胞アポトーシス抑制,のいずれかを誘起し,成長期期間を延長して,矮小化毛包を改善することによると推察される.<br>
- 著者
- 橋爪 圭司 渡邉 恵介 藤原 亜紀 佐々岡 紀之 古家 仁
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 = The Journal of Japan Society for Clinical Anesthesia (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.141-149, 2011-01-14
- 参考文献数
- 12
髄膜が破れて髄液が漏れると低髄液圧性頭痛が発症する.代表的なものに硬膜穿刺後頭痛がある.特発性低髄液圧性頭痛(特発性脳脊髄液減少症)は頚・胸椎からの特発性漏出が原因で,造影脳MRI,RI脳槽造影,CT脊髄造影などで診断される.自験ではCT脊髄造影での硬膜外貯留が最も確実であった.むちうち症が髄液漏出であるとの意見があり(外傷性脳脊髄液減少症),RI脳槽造影における腰椎集積が漏出と診断される.われわれはRI脳槽造影とCT脊髄造影を43症例で比較したが,腰椎集積はCT脊髄造影では正常神経根鞘であった.CT脊髄造影を診断根拠とした291症例では,1症例の外傷性脳脊髄液減少症も発見できなかった.
5 0 0 0 OA 1950 年代韓国経済の復興と安定化 -合同経済委員会を中心に-
- 著者
- 林 采成
- 出版者
- 政治経済学・経済史学会
- 雑誌
- 歴史と経済 (ISSN:13479660)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.3, pp.28-36, 2016-04-30 (Released:2018-04-30)
- 参考文献数
- 20
This paper focuses on the Korea-U.S. Combined Economic Board (CEB), which developed comprehensive policies for the Korean economy after the Korean War, and reconsiders presuppositions about the “development period” by examining economic recovery and stabilization under the American aid program.Rehabilitation and stabilization in the Korean economy were achieved through cooperation and opposition between Korea and the U.S. The CEB played a central role in this process. Although it is true that significant differences of opinion occurred over the amount and composition of economic aid, the accumulation and use of counterpart funds, and exchange rates, the MSA programs that integrated economic aid and military assistance ultimately caused more friction than did the philosophies of CEB participants. The result was issues over how Korea and the U.S. would share the economic expenses for post-war rehabilitation.Once the exchange rate was adjusted to meet the increase in prices, a system of cooperation between Korea and the U.S. was formulated, including exchanges in manpower, and management of the Korean economy became highly sophisticated. In particular, the Korean government implemented plans that succeeded in stabilizing the economy, enabling long-term maintenance of the exchange rate. In other words, from the mid-1950s on, Korea and the U.S. were able to avoid excessive friction. The introduction of large volumes of aid supplies enabled Korea to implement an array of projects and thereby to return to its prewar production levels, and long-term economic development plans were drawn up with U.S. support with the aim of enhancing Korea’s capacity for economic independence. The Korean government, however, seeking to stay in power, failed to rein in the sharp increase in prices, and was therefore unable to extend exchange-rate adjustments with the U.S. Ultimately, it faced an economic crisis that resulted in the early demise of its long-term economic development plans.The above shows that, contrary to the premise of “collapse” and “delay” presented in existing research, the Korean economy of the 1950s did achieve rehabilitation after the war, as well as economic stabilization, and was able to lay the groundwork for the “development period.” Fluctuations in economic aid are not enough to explain the process. That is, the rehabilitation and stabilization of the Korean economy would be impossible without the accumulation of experience and the resulting maturity of administrative capacity.
- 著者
- Shumpei Iwao Yumi Kato
- 出版者
- Global Business Research Center
- 雑誌
- Annals of Business Administrative Science (ISSN:13474464)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.6, pp.251-262, 2019-12-15 (Released:2019-12-15)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 1 3
The keiretsu, or long-term stable business network that exists between Toyota and its suppliers, seems to demonstrate exceptional resilience in the face of natural disasters. Toyota shares production knowledge among the firms in its keiretsu through long-term kaizen-based inter-company learning activities (jishuken). In this regard, we have confirmed that (A) in times of normal operations, jishuken adopt a flat structure of interpersonal connections among firms that facilitates mutual trust. From case studies, we also found that (B) in times of disaster response, the structure “switches” to a hierarchical one with a clearly delineated leadership to bring knowledge and human resources into play.
5 0 0 0 IR ナチス・ドイツにおける住民の警察化 : 日独比較史の観点から
- 著者
- 矢野 久
- 出版者
- 慶應義塾経済学会
- 雑誌
- 三田学会雑誌 (ISSN:00266760)
- 巻号頁・発行日
- vol.102, no.4, pp.693(59)-717(83), 2010-01
20世紀には世界戦争や民族虐殺のような破局的な暴力が噴出した。この暴力の噴出において広義の警察機構がこの暴力の最先端で機能していた。しかし現代社会においても監視と規律化が最重要な課題の一つとされ, テロル・暴力に対して国家の暴力独占は正当化されているようである。現代における国家の暴力は, 歴史的にみると, ナチスの暴力実践とどのような位置関係にあるといえるのか。比較史の観点から, ナチス・ドイツの警察による住民支配のあり様を20世紀ドイツ史の中に位置づけて考察する。In the 20th century, catastrophic violence such as global wars and ethnic massacres erupted. In the eruption of this violence, police mechanisms, in a broad sense of the meaning, functioned at the cutting-edge of this violence.However, even in modern society, monitoring and discipline are considered among the most important themes as terrorism and violence seem to justify the state monopoly on violence. This study examines how the practice of violence under the Nazis is positioned vis-a-vis contemporary state violence when viewed historically from the viewpoint of comparative history, through the depiction of residents controlled by Nazi Germany police, an event that marked 20th century German history.論説
5 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1910年07月13日, 1910-07-13
- 著者
- 逢坂 巌
- 出版者
- 日本マス・コミュニケーション学会
- 雑誌
- マス・コミュニケーション研究 (ISSN:13411306)
- 巻号頁・発行日
- vol.85, pp.43-61, 2014-07-31 (Released:2017-10-06)
- 参考文献数
- 12
This article discusses the changes in Japanese politics in the age of the Internet, especially in this age of social media. From my point of view I can say that three major changes have been occurring with the spread of the use of social media in these days. The first is that Japanese people are starting to talk, or type, about politics in the new "public sphere" in the Internet and so are building up another type of public opinion. We call it in Japanese netto-yoron ("Internet public opinion"), which both politicians and the mass media cannot avoid taking into account. The second change is that politicians, parties, and candidates have been empowered by social media. Japanese politicians have succeeded in creating or developing new ways of using social media, attacking articles or coverage by the mass media in order that the politicians can influence the mass media. This may change the Japanese politics as well. The third change concerns the Japanese mass media, which is attacked both by politicians using social media and by netto-yoron. This will be a major change in terms of political communication in Japan.