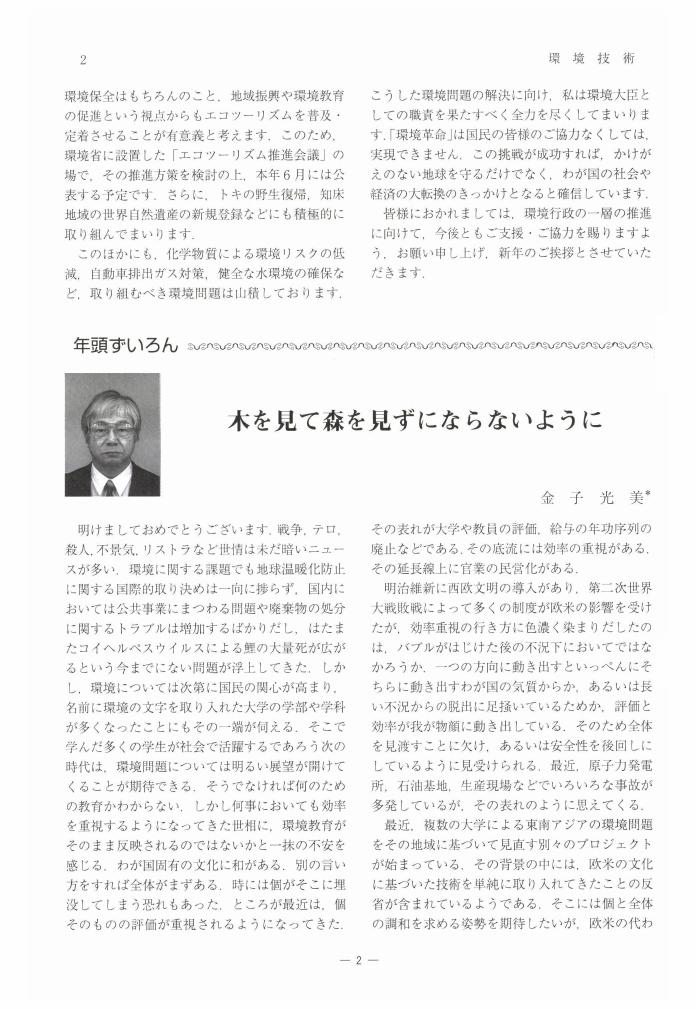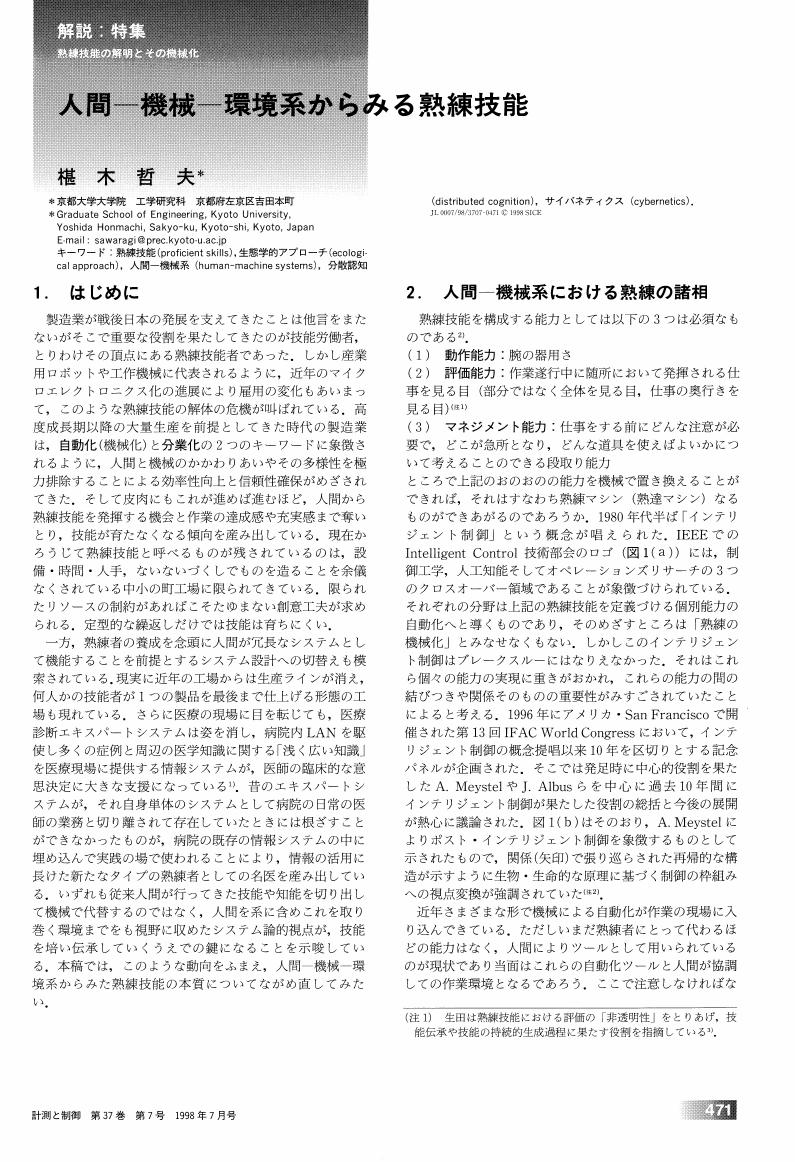1 0 0 0 OA 閾下感情的プライミング効果の検討
- 著者
- 小川 時洋 鈴木 直人
- 出版者
- 日本感情心理学会
- 雑誌
- 感情心理学研究 (ISSN:18828817)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.2, pp.70-77, 1998-03-31 (Released:2009-04-07)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 2 1 1
本研究は,Murphy&Zajonc(1993)の報告する閾下感情的プライミング現象と,その生起に関わる要因を検討することを目的として行った。実験1では先行研究に準じた,プライムの閾下提示群,閾上提示群を形成して実験を行った。その結果,閾上提示群では,ターゲットの評価がプライムの誘意性に左右される強いプライミング効果が見られたが,閾下提示条件では見られなかった。実験2は,実験1の結果を踏まえ,プライムの存在に対する被験者のアウェアネスの役割を検討し,プライムが見えていることが効果の生起に決定的な役割を果たすことを示唆する結果が得られた。実験3および実験4は,閾下刺激の効果に焦点をあて,ターゲット刺激の特性,試行間間隔,プライム刺激提示時の視角,同一ターゲソトの反復提示などの要因を統制した。しかしながら,実験3,および実験4のどちらにおいても閾下プライミング効果は見出されず,先行研究の一般性に疑義を呈する結果となった。
1 0 0 0 比留間賢八の生涯 : 明治西洋音楽揺籃時代の隠れたる先駆者
1 0 0 0 OA 年頭ずいろん
- 著者
- 金子 光美
- 出版者
- 環境技術学会
- 雑誌
- 環境技術 (ISSN:03889459)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.1, pp.2-3, 2004-01-20 (Released:2010-03-18)
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 IR The Momentary and Placeless Community: Constructing a New Community with regards to Otaku Culture
- 著者
- IMAI Nobuharu
- 出版者
- Graduate School of Humanities and Social Sciences, University of Tsukuba
- 雑誌
- Inter Faculty (ISSN:18848575)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, 2010
The aim of this article is to examine how a new community in information societies is constructed by referring to the cultural practices of Otaku and their methods of communication. Today, the realities of internet space are gaining ground. The Otaku are the most acclimatized people, or the most addicted, to the information society, however, when they gather in certain real geographic places that they denominate by religious terms, they affirm the existence of their reference group and strengthen the plausibility of their structures. The practices of Otaku present one of the ways of living in the information society.この論文は、情報社会における新たな共同体の在り方について、オタクと呼ばれる人々による文化的実践とコミュニケーションに言及することによって論じるものである。インターネット空間のリアリティが増進している今日、オタクは情報社会にもっとも適応した人々であり、あるいはそこに耽溺しているとも言える。しかし、彼らが宗教的語彙で呼び表す現実の場に集う時、彼らはそこで準拠集団の確認と信憑性構造の強化を行っている。そうしたオタクの実践は、情報社会における1つの生き方を提供している。
1 0 0 0 MPA(海洋保護区)導入の理論的研究
申請者は申請書内の研究目的・内容[3]にある,社会経済学的な視点を取り入れた海洋保護区(MPA)の効果的な導入方法を明らかにする研究をすすめてきた。この研究において,漁業資源管理をするにあたり,努力や海洋保護区配分の最小単位である管理単位スケールの選択が,経済的便益や資源量などの資源管理の帰結に重大な影響を与えることを明らかにし,資源の生物学的特性に関する情報の他に,管理者らの意思決定も管理の成否に大きく関わる可能性を示唆した。また,伝統的な資源管理モデルを空間明示的なモデルに拡張し,最も重要な漁業資源管理の指標の一つである最大持続生産量(MSY)がどのように影響を受けるかを明らかにする研究を行った。モデルを空間明示的に拡張した場合,得られるMSYの値は必ず伝統的に使われてきたMSYの値より低くなることがわかった。すなわち,現実の空間構造を無視している伝統的なモデルは,MSYを過大に見積もっている可能性があることを示唆する。さらに,申請者は空間構造・齢構造を取り込んだ資源動態モデルを発展させ,MPAの導入が漁獲量を増加させるための理論的条件を初めて導きだした。この条件は,漁獲対象種1個体当たりの再生産数が中庸な値になるとき達成され,同時に漁獲高を増加させるという観点からみると,MPAは必ずしも有効な管理手段では無い事を示唆する。以上の3研究は現在論文にまとめ,審査中である
1 0 0 0 災害時における携帯電話の通話時間規制の検討
- 著者
- 岡田 和則
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. RCS, 無線通信システム (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.100, no.278, pp.81-86, 2000-09-01
- 被引用文献数
- 12 5
地震等の大規模な災害時には、安否確認等のために通話需要が急増する。一般に広く普及した携帯電話への通話需要も急増することが予想される。しかし、携帯電話は、有限である周波数資源を使用するため、容量を余分に大きくすることは難しく、多くの呼損が生じることが予想される。そこで、本報告では、通話時間を規制して多くの通話を実現することを考え、生起呼数に応じて通話規制時間を変化させる制御を提案する。そして、通話時間を規制した場合の効果を簡単なシミュレーションモデルを用いて調べる。その結果、通話規制時間を少なくすると、通話時間は少なくなるが、呼損率やハンドオーバー時の強制切断率を十分少なく出来ることが示された。また、簡易な通話規制時間の見積法の検討も行い、シミュレーション値とよく一致することを示した。
1 0 0 0 OA 新資料に基づく関東地方古人骨の系譜論・生活論の再考
赤星直忠博士を中心とする横須賀考古学会は,1967~1968年に神奈川県三浦市所在の雨崎洞穴遺跡(弥生~古墳期)において発掘調査を行った。本研究で出土人骨の整理を行なった結果,非焼骨について,大腿骨がもっとも残存する部位であり,その最小個体数は19体であった。死亡年齢や性別の構成を見ると,本人骨群には少なくとも成人男性3体,成人女性1体,性別不明成人11体,未成人5体の20体が含まれた。焼成人骨について,各部位の出土点数に基づく個体数の算定と焼成状況の復元を試みた。人骨は少なくとも33体からなり,主体は成人であるものの,未成人骨が複数確認された。
1 0 0 0 OA 「美の芸術家」の一解釈 : オーウェン・ウォーランドと無意識
- 著者
- 大場 厚志
- 出版者
- 東海学園大学
- 雑誌
- 研究紀要 (ISSN:13421514)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.125-136, 2000-03-31
In Hawthorne s "The Artist of the Beautiful, " Owen Warland completes the butterfly which is organic as well as mechanical. The process of creation correlates with the unconscious, the operation of which is inseparable from the creativity of an artist. Owen comes to know that not the product, the butterfly, but the process of creation and the instinctive content matter for him. The narrator describes him as grown spiritually as an artist. Nevertheless Owen does not evoke our keen sympathy. And the unconscious seems to concern one of the causes. The relation between Owen and the antagonists-Peter Hovenden and Robert Danforth-proves to be correlative rather than contrary. In spite of Owen's hostility, Danforth is friendly to Owen though he has little imagination and despises Owen's spirituality and fragility. Hovenden displays his hostility only when he suspects that Owen is engaging himself in an imaginative work. In view of these circumstances, Hovenden and Danforth severally function as the "shadow" in Jungian theory. The "shadow" Is what is denied by the ego, the center of consciousness, in conscious personality. Owen projects his personal "shadow" upon the two antagonists, which, it seems to us, indicates the conflict between an artist and a society. In fact, like Owen, they are also left behind in the society with a new system for mass production. Therefore the conflict between Owen and the antagonists proves to remain the personal one (or the one in an old community) rather than the generalized one between an artist and a society. In addition, Owen's alternate repetitions of artistic desire and lethargy remind us of a puer aeternus (child archetype). Without the betterment of his relation to the "shadow " we cannot expect Owen's true independence and maturity.
1 0 0 0 近世陶磁器の生産・流通・消費に関する考古学的研究
本研究は、まず、第1部「近世陶磁器の研究史」で、近世考古学と近世陶磁器の研究史について略述した。第2部「消費地遺跡における近世陶磁器の研究」では、第1章で江戸遺跡の事例をあげ、陶磁器の出土状況を検討した後、陶磁器の生産年代から遺構の廃絶年代を推定する方法を述べ、産地組成、器種組成から江戸における陶磁器流通とその背景を考察した。第2章では陶磁器の数量把握の方法を論じ、望ましい数量把握の方法を示した。第3章では江戸から京都、大阪にいたる東海道の消費地遺跡を多数取り上げて産地組成を比較し、近世陶磁器の流通には地域差が存在したことを明らかにした。第4章では、消費地で少数ながら出土する茶陶や鍋島藩窯製品などのやや特殊な高級陶磁器の出土状況を検討した。第3部「生産地遺跡出土の陶磁器」では、生産地の窯跡、物原から出土した陶磁器について、多変量解析など統計的な手法を含む型式学的な分析を行った。第1章では肥前広東碗の器形と文様の変化について検討し、量産品が多い近世陶磁器についても、微細ながら器形の形態変化が捉えられることを示した。第2章では有田と瀬戸の磁器端反碗の容量と規格性を論じ、ふたつの産地にみる販売戦略の違いを検討した。第3章では、器形の微細な差異から生産した窯や陶工個人を識別する可能性を論じた。第4部「近世陶磁器と文字資料」では、紀年銘資料、暦を記した陶器碗、関口日記の事例などから、文字記録を考古資料の関係について論じた。以上のような分析から、遺跡から出土する近世陶磁器は編年や年代推定の資料になるばかりではなく、近世の文化や社会を解明する上で有益で重要な遺物であることを示した。
1 0 0 0 OA HIV-1 pol遺伝子のSLSA1構造内1塩基置換による複製制御基盤の解析
HIV-1 Vif とAPOBEC3Gとの拮抗はウイルス複製にとってcriticalである。HIV-1の馴化・適応研究から、SLSA1を含むスプライシングアクセプター1近傍の領域(SA1prox)に自然に存在する1塩基置換によりウイルス複製能が変動することを見出した。本研究では、このようなウイルス複製能の変動が、Vif発現量の増減により起こることを明らかにした。さらに、Vif低発現変異体の馴化実験により、vif mRNA産生に関与するSA1prox以外のゲノム領域が存在すること、また、APOBEC3Gにより強力に複製が抑制される環境下でも、HIV-1が極めて高い適応能力を持つことが示された。
1 0 0 0 OA 製材品流通の地理的変化と製材業大手の供給戦略
- 著者
- 嶋瀬 拓也
- 出版者
- 一般財団法人林業経済研究所
- 雑誌
- 林業經濟 (ISSN:03888614)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.5, pp.1-16, 2005-08-20
- 被引用文献数
- 4 2
国内製材業における製品(製材品)の出荷先地域別出荷量に注目し、その変化と製材業大手の供給戦略との関係について検討した。まず、統計データの分析から、我が国製材業の製品出荷に関する地理的変化として、(a)自県向け・三大都市圏向けの縮小と地方圏向けの拡大、(b)製材生産が活発な県と不活発な県の二極化、(c)出荷シェアを拡大した県における出荷の広域化がみられることを明らかにした。次に、製材品需要が縮小する中で製材業大手が生産規模の拡大に取り組んでいることが、上にみた変化を引き起こす要因となっていることを示した。製材業大手における規模拡大は、これまでのところ専門性(生産品目や素材樹材種の特化)を保ちつつ進められている。製材業大手は、品質に幅のある生産物をより有利に販売できるよう、専門性を保ちつつ生産規模を拡大し、広域な出荷圏や幅広い顧客層の確保に努めている。
- 著者
- 岡崎 宏光
- 出版者
- 公益社団法人日本数学教育学会
- 雑誌
- 数学教育論文発表会論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.517-522, 2006-10-07
1 0 0 0 婚姻から見る源氏物語を中心とした平安朝物語の虚構性に関する研究
今年度の学会発表をもとに執筆し、投稿受理された論文「平安朝物語の婚姻居住形態-『源氏物語』の「据ゑ」をめぐって-」は、国文学の分野においてあまり言及されてこなかった従来の婚姻居住形態に関する議論を、物語の方法として捉え直すことを目的としたものである。本論文では、当時の婚姻居住形態に関する議論について改めて整理を行い、これまで妻としての疵と捉えられるのみであった「据ゑ」の形態について、物語の描かれ方に即して検討を加えた上で、『源氏物語』の独自性とその先駆としての『蜻蛉日記』の存在を指摘した。また、今年度に発表した論文「『源氏物語』の初妻重視-葵の上の「添臥」をめぐって-」では、古記録等の調査により「添臥」についての通説に再検討を加え、さらに『源氏物語』における「添臥」の語の使用方法が、光源氏の両義性を照射する優れた方法となっていたことに着目し、それを手がかりに物語に語られる初妻重視の思想について考察した。さらに、今年度末に予定していた研究会発表(震災の影響により中止)は、物語に散見する婿選びの際の登場人物の発言を取り上げ、このような記述をもとに実際に平安朝の婚姻慣習を炙り出そうとするような方法を退け、その描かれ方をこそ問題にすべきであると主張するものであった。具体的には若菜下巻の蛍宮と真木柱の結婚記事を端緒として、当該場面直後に置かれる代替わり記事と女三の宮物語との繋がりや、光源氏の地位を揺さぶり物語を展開していく当該巻の手法について検討した上で、蛍宮と真木柱の結婚記事と上記のような若菜巻の論理との関連を指摘するものである。以の研究により、婚姻研究という視点を通して、平安朝の各作品相互の交渉や『源氏物語』の独自性の一端を浮かび上がらせることができたと考えている。
1 0 0 0 光による鼻息像のリアルタイム計測
1 0 0 0 イギリスの障害児教育におけるインクルージョン概念の探究
平成19年度は、これまでの訪英で得られた資料を分析の対象として、イギリスの文脈に沿いながら、インクルージョン概念の整理と概念規定を行うことを目的としていた。そこで、インクルージョンについて理解する上で新たな視点を提供するセバらの「プロセスとしてのインクルージョン」というとらえ方に着目して考察を行った。その成果は、平成19年10月に行われたSNE学会で発表した。また、平成20年5月に同学会の研究紀要(SNEジャーナル)に投稿予定である。本年度の研究では、インクルージョンの先進的な実践としてスキッドモアが紹介しているイギリス南西部のダウンランド校の実践例を取り上げ、同校が、学習上の困難をもつ生徒への対応を発展させていく中で、どのようにインクルージョンの実現をめざしていたのかを検討することを通して、「プロセス」としてインクルージョンを理解することの具体像の一端を明らかにした。またその過程が、統合という「状態」の実現をめざしていた従来のインテグレーションと、インクルージョンの相違をあらためて浮き上がらせるものであることを指摘した。「プロセス」としてインクルージョンを理解することにより、障害児を含めた多様なニーズをもつ生徒の存在を前提として、彼らを包摂する「不断の学校づくりの努力のプロセス」としてインクルージョンをとらえることが可能となり、通常学校教育のあり方そのものを問い直す議論としての視座を明確にすることができた。さらに、昨年度に引き続き、京都市立高倉小学校との共同授業研究では、障害児学級を足場に学習する児童について、教師と協働で具体的な支援について考えた。また、日本学術振興会の許可を得て大阪府大東市教育委員会の非常勤巡回発達相談員を勤め、本研究の成果の普及にも努めた。
1.国内におけるアカリンダニの分布調査:昨年度より引き続き、全国から採集したミツバチ358コロニーを用いて、アカリンダニの寄生状況の調査を昨年に引き続き行い、北海道と沖縄をのぞくほぼすべての都府県での発生を確認した。2.ネオニコチノイド系農薬を曝露したミツバチへのアカリンダニ寄生実験:イミダクロプリド、チアメトキサム、クロチアニジンの3種類の農薬をセイヨウミツバチに経口投与し、アカリンダニに対する対抗行動にどのような影響を及ぼすかを評価した。3.アカリンダニの寄生がニホンミツバチに与える影響:アカリンダニ寄生がミツバチの発熱能力と飛翔能力を低下させることを、サーモグラフィーおよびフライトミルを用いて明らかにした。4.アカリンダニの生存時間:従来報告されていたよりも長く、特に低温かつ高湿度条件では9日間生存していることを確認した。
1 0 0 0 OA 人間-機械-環境系からみる熟練技能
- 著者
- 椹木 哲夫
- 出版者
- 公益社団法人 計測自動制御学会
- 雑誌
- 計測と制御 (ISSN:04534662)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.7, pp.471-476, 1998-07-10 (Released:2009-11-26)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 4
- 著者
- 神山 伸弘
- 出版者
- 跡見学園女子大学
- 雑誌
- 跡見学園女子大学人文学フォーラム (ISSN:13481436)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.52-65, 2014-03-15