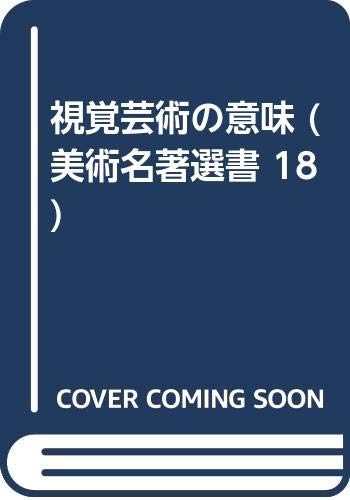1 0 0 0 IR 奄美大島の蚊と日本脳炎ウイルスの越冬について
- 著者
- 和田 義人 茂木 幹義 小田 力 森 章夫 鈴木 博 林 薫 宮城 一郎
- 出版者
- 長崎大学熱帯医学研究所
- 雑誌
- 熱帯医学 Tropical medicine (ISSN:03855643)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.4, pp.187-199, 1976-02-28
奄美大島において1972-1975年に蚊の調査を行なった.成虫は畜舎にかけたライトトラップ及び野外でのドライアイストラップにより,幼虫はその発生場所において,1年を通じて採集を行なった.その結果31種の蚊が得られた.上記の方法による採集の記録と,野外で採集した幼虫の飼育の記録とから,各々の種の,特に冬季における,生態について記載した.また,奄美大島での日本脳炎ウイルスの越冬について,伝搬蚊コガタアカイエカの生態の面から考察を加え,ウイルスの越冬が可能なのは,冬の気温が高く,蚊-豚の感染サイクルが持続する場合においてのみであると結論した.Mosquitoes were investigated on Amami-Oshima Island in 1972-1975. Adults were collected by light traps at animal shelters and by dry ice traps in the field, and larvae at their breeding sites in the whole year. In total, 31 species of mosquitoes were found. From the mosquito catches by the above methods together with the rearing records of some larvae collected in the field, the biology of each mosquito particularly in the winter time was reported. Also, the possibility of the overwintering of Japanese encephalitis virus on Amami-Oshima was discussed on the basis of the biology of the vector mosquito, Culex tritaeniorhynchus. It was considered that the successful overwintering of the virus is attained only by the succession of the pig-mosquito cycle maintained by the continuous feeding activity of the vector mosquitoes in warm winter.
1 0 0 0 デング出血熱の発病機構と伝播に関する研究
- 著者
- 五十嵐 章 WARACHIT Pai CHANYASANHA チャンチュ SUCHARIT Sup 長谷部 太 江下 優樹 CHANYASANHA Charnchudhi SAGWANWONGSE スラン
- 出版者
- 長崎大学
- 雑誌
- 国際学術研究
- 巻号頁・発行日
- 1996
デング出血熱の発病機構と伝播に関する現地調査研究を、デング流行地の1つであるタイ国東北部ナコンパノム市において実施した結果、下記の知見が得られた。(1)デング患者のウイルス学的検査には、ELlSA記録計と抗原、酵素標識抗体などの測定用試薬が入手できればIgM‐ELlSAが適正技術である。それに対して、RT‐PCRは実験条件が整備されていない地方で日常検査に使用するには問題点が多い。但し、ウイルス分離は分離株の詳細な解析を行うために不可欠である。(2)6月に採取した患者血液検体からはデングウイルス1型、2型、3型が分離され、ナコンパノム市は依然としてデングウイルスの超汚染地域の1つであることが確認された。(3)患者プラスマ中のサイトカインに関して、不明熱患者に比べてデング患者ではIFN‐γが上昇しており、臨床的にデング出血熱と診断された患者の半数以上に見られた。(4)乾期に臨床的にデングと診断された患者は、デング以外の感染症の可能性が高い。(5)今回の調査において、乾期・雨期共に多数のネッタイシマカ成虫が採集され、その殆どはabdominal dorsal tergal pattern 1の黒い蚊であった。残念なことにネッタイシマカ雌成虫からデングウイルス遺伝子の検出は陰性であった。従って、当初予定していたabdominal dorsal tergal patternとウイルス感染率との関係、及びウイルス保有蚊の潜伏場所に関する知見は得られなかった。これらの課題は今後検討すべき価値があろう。(6)1〜2月の調査によって推定されたネッタイシマカの屋内潜伏場所にオリセットネツトを選択的に使用した結果、ネッタイシマカに対する防除効果が見られたことは、今後限られた経費と資源を有効に利用してデング媒介蚊防除を実施する上で重要な知見である。
1 0 0 0 東アフリカ諸国のコーヒー産地をめぐる地域経済圏に関する実証的研究
本研究計画では、タンザニア北部高地のキリマンジャロ・コーヒー産地を中心的な調査対象地域とした。国際的・国内的な要因によるコーヒー生産者価格の下落という近年の状況に対して、地域全体を統合するような広域の地域経済圏の形態での対応は発見できなかった。地理的分断、居住する民族集団の相違、行政的区分、農産物流通組織の相違等の要因によって、同地域は4〜5の山地-平地という組み合わせの下位地域に細分され、それぞれが別個にコーヒー価格の下落に対応している。メル山地域においては近隣都市の野菜・乳製品等の需要増大に応じて、中核的なコーヒー栽培地域において作目転換・畜産重視という変化が見られた。キリマンジャロ山地域には複数の下位地域区分が存在するが、コーヒーの差別化・流通改革をめざす地域、平地部でのトウモロコシ・米生産を重視する地域等の対応の差が見られた。また、北パレ山塊においては、建設ブームによって山麓にある都市部で人口増大が著しいのに対して、コーヒー産地である山間部では過疎化が進行しつつあることが明らかになった。比較対照のためにとりあげたルワンダ、エチオピアでは、タンザニア北部高地では見られない対応が行われていた。ルワンダにおいては、コーヒー産地は最も人口稠密であり、また有利な換金作物を栽培できる地域であるために、ルワンダの他地域では見られない分益小作制が発生しつつあった。また、エチオピアにおいては協同組合がフェアトレードやオーガニック・コーヒーという差別化に巧みに対応し、民間業者と互してコーヒー流通を担い続けていた。両国の事例は東アフリカにおけるコーヒー経済の存在形態の違いを浮き彫りにしており、本研究計画のめざした比較研究の必要性が改めて確認された。
- 著者
- 堀欠 和晃 貝島 桃代 志村 真紀 一之瀬 彩 河村 藍
- 出版者
- 一般社団法人日本建築学会
- 雑誌
- 学術講演梗概集. F-2, 建築歴史・意匠 (ISSN:13414542)
- 巻号頁・発行日
- vol.2007, pp.683-684, 2007-07-31
1 0 0 0 都市内緑地のクールアイランド効果とその規模別影響評価
緑地規模や土地被覆構成と緑地内の気温低下量との関係を明らかにするために、2006年夏季に都内11箇所の公園緑地(対象の緑地は皇居、明治神宮と代々木公園、新宿御苑、自然教育園、小石川植物園、小石川後楽園、芝公園、戸山公園、六義園、新宿区立甘泉園公園、港区立有栖川宮記念公園)にて気温の長期連続観測を行った。その結果、以下の成果が得られた。1.都内の主要な緑地における連続的な気温観測記録を得た。それにより、夏季の緑地内外の気温差は最大で5℃に達するほどであることなど、都市内緑地の熱環境緩和効果が明らかになった。2.緑地内外の気温差は、緑地総面積や樹林面積の対数に近似される曲線で近似できることが分かった。このことは、都市内緑地の熱環境緩和効果を論じるうえで近年課題となっているSLOSS(Single large or several small)問題に答えたことになる。また、緑地内の樹林面積と樹林率からなる、公園緑地における気温低下量を説明できる指標を提案した。3.高時間分解能での観測を生かし、時刻ごとに公園の土地被覆構成と気温低下量との関係を表す重回帰式から、どのような土地被覆構成要素がどの時間帯にどの程度の熱的効果(気温低下量への寄与の大きさ)を持っているのかを明らかにした。
- 著者
- 吉田 直隆 難波 良平 片谷 克也
- 出版者
- 社団法人日本造園学会
- 雑誌
- 造園雑誌 (ISSN:03877248)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.2, pp.123-133, 1990-11-26
- 被引用文献数
- 2 2
森林公園の植生の形態を構成する樹種,立木密度,林況,および芝生地等の形態が,その利用状況に直接的に影響することは,一般的に自明のこととされている。そこで,代々木公園の通年にわたる利用実態調査をもとに,植生の形態を類型化し,植生の形態と利用との関係を明らかにするとともに,芝生広場の利用者が最も好む形態と広さについても明らかにした。
1 0 0 0 OA 女子学生の食に関する生活について(第3報) : 地域別による比較
- 著者
- 時枝 久子 福司山 エツ子 徳田 和子
- 出版者
- 九州女子大学・九州女子短期大学
- 雑誌
- 九州女子大学紀要. 自然科学編 (ISSN:0916216X)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.2, pp.11-30, 1998-09
若年単身女性の食生活の実態を把握することを目的として、女子大生の身体および生活状況や食に関する意識について、2地区(A、B地区)別による比較を行い次の結果を得た。(1)最近の身体状況では両地区全体で「体がだるい」「目覚めが悪い」「便秘」を多くの学生が挙げている。生活状況は、平日の睡眠時間は全体で6〜7時間の割合が高く、両地区とも睡眠は概ねとれている。起床時間は全体で7〜8時の割合が高いが、A地区に比べてB地区の方が起床時間が早い。ここ1年間の体重の変化は全体で「変わっていない」と回答した者が多い。また「運動習慣はない」割合がA地区で特に高い。(2)食習慣は、朝食の欠食は全体的に少なく、B地区が特に少ない。また、居住形態別では両地区とも寮生の欠食が少ない。食事摂食回数は「3回」が高い割合を示し、特にB地区の全体と寮生が高い。食事は美味しく食べている者が多く、食事に対する意識は両地区とも高く、A地区は健康とダイエットが配慮され、B地区は健康に対する配慮が強い。(3)食品摂取状況は、肉・魚類の摂取ではやや肉類が多い。特に両地区とも自炊生にその摂取の割合が高い。卵は全体では1日1個の摂取はないが、B地区の自宅生は摂取の割合がやや高い。大豆製品は全体では週に「1〜2回」の割合が高いが、B地区の自宅生に大豆製品の摂取が多い傾向にある。牛乳の摂取量は両地区とも少ない傾向にある。乳製品はヨーグルトが好まれるものの、摂取は隔日が多い。油物の摂取は全体で毎日「2〜3回」の割合が高い。野菜類は緑黄色野菜、淡色野菜とも普通にとっている。飲み物は清涼飲料水を「殆ど飲まない」割合が高く、茶類が飲まれている。A地区はウーロン茶が多く、B地区は緑茶が多く飲まれている。飲酒は全体では低いが、自炊生に時々飲む傾向が見られる。(4)昼食の状況は全体で外食と手作り弁当がほぼ半々であるが、両地区とも寮生に外食の割合が高い。昼食の主食は両地区の自宅生と自炊生に米食が多く、寮生にパン食が多い。昼食の予算は全体で「300〜400円」の割合が高かった。(5)日常食の料理の嗜好は肉類を素材とした料理が好まれ、野菜が中心で特に香味野菜を使用した料理を好まない傾向にある。
- 著者
- [Tōkyō Teikoku Daigaku Fuzoku Toshokan]
- 出版者
- In-house reproduction
- 巻号頁・発行日
- 0000
1 0 0 0 鴎外文庫目録
- 著者
- 東京帝國大學附屬圖書館 [編]
- 出版者
- 私製
- 巻号頁・発行日
- 0000
- 著者
- 車 勤
- 出版者
- 山梨英和大学
- 雑誌
- 山梨英和大学紀要 (ISSN:1348575X)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.A95-A108, 2011
普遍的に実効力のある倫理は、現代社会に固有な形態である「貨幣・商品社会システム」を根拠にしなければならない。そのシステムの原型を描いたアダム・スミスに、「構成関係」から社会をとらえたスピノザを重ね合わせ、取りだしたのが「互恵交換」の倫理である。その構成要素は以下の6つ。1.人々の対等性、2.恵みを構成関係者全体で享受する、3.与え返される程度に与える、4.人を騙さず、期限などの約束を守る、5.説明責任、6.離脱する自由。これらを社会形成原理として徹底的に実現すること。それはまた、理性の平和的な使用〜略奪目的でも飼育目的でもない〜になる。
1 0 0 0 OA Recursive Elastic Netによる大規模遺伝子ネットワークの推定
Statistical modeling based on vector autoregressive model has been considered as a promising tool to reconstruct large-scale gene networks from time course microarray data. However, it remains a challenging problem due to the small sample size and the high-dimensionality of time course microarray data. We present a novel regression-based modeling strategy with a new class of regularization, called recursive elastic net. Numerical simulations and real data analysis show that the proposed method outperforms other traditional methods.
1 0 0 0 沼口 敦会員の急逝を悼む
1 0 0 0 OA 巡視船の上甲板上に生じた撓みについて
- 著者
- 岡田 宏平 石山 一郎
- 出版者
- 公益社団法人日本船舶海洋工学会
- 雑誌
- 造船協會論文集
- 巻号頁・発行日
- no.106, 1960-01
1 0 0 0 OA 学生の看護基本技術経験に関する臨床看護職の認識
- 著者
- 井上 真奈美 田中 愛子 川嶋 麻子 丹 佳子 野口 多恵子
- 出版者
- 山口県立大学
- 雑誌
- 山口県立大学看護学部紀要 (ISSN:13430904)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.7-15, 2005-03
- 被引用文献数
- 1
本研究は、学生の看護基本技術経験に関して臨床の看護師がどのように認識しているかを明らかにし、今後の技術教育を検討する際の一助とする目的で行った。調査は、山口市周辺にある300床以上の医療機関3施設に所属する看護職760名を対象に、看護基本技術103項目毎に、「学内演習での経験」「臨地実習での経験」の必要性の有無、さらに「臨地実習で経験する際の実施条件(水準)」の認識について選択方式で回答を求めた。結果として、669(88%)の有効回答を得た。看護基本技術103項目すべてに対して50%以上の看護職が、学生時に「学内演習」および「実習場」での経験が必要であると考えているこが明らかになった。一方で、学生が看護基本技術を実習の場で展開する際の実施条件(水準)においては、教員や指導者から指導を受け「学生が単独で行ってよい」とする看護基本技術項目は限られており、臨地実習場での指導監督が必要な項目や、見学としての実習参加を求める項目が多くあることがわかった。これらの結果から、今後の学生の看護技術修得に向けて検討すべき課題や臨地における学生指導のあり方について考察した。
1 0 0 0 視覚芸術の意味
- 著者
- アーウィン・パノフスキー著 中森義宗 内藤秀雄 清水忠訳
- 出版者
- 岩崎美術社
- 巻号頁・発行日
- 1971
1 0 0 0 土迦文庫目録 : 岡本信次郎氏寄贈圖書
- 出版者
- 第一高等學校圖書館
- 巻号頁・発行日
- 1943
1 0 0 0 OA チンパンジーとボノボにおける利他性・互恵性・他者理解の検討
- 著者
- 山本 真也
- 出版者
- 京都大学
- 雑誌
- 研究活動スタート支援
- 巻号頁・発行日
- 2010
ギニア共和国ボッソウ村にて野生チンパンジーの調査、コンゴ民主共和国ワンバ村にて野生ボノボの調査をおこなった。同時に、林原生物化学研究所類人猿研究センターおよび京都大学野生動物研究センター熊本サンクチュアリのチンパンジーを対象に実験研究をおこなった。集団協力行動・食物分配・手助け行動に焦点を絞り、進化の隣人であるチンパンジーとボノボでの行動を比較することにより、利他性・互恵性・他者理解の進化、ひいては人類進化について新たな考察をおこなった。
1 0 0 0 OA 歯科治療後知覚神経障害による医事紛争
- 著者
- 福田 謙一 笠原 正貴 西條 みのり 林田 眞和 一戸 達也 金子 譲
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.7, pp.696-701, 2005 (Released:2005-11-29)
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 1
歯科治療行為による知覚神経障害は決して少なくない. 歯科領域の知覚神経障害は, 日常生活で容易に不快感を認識できるため, 患者を長期にわたって苦しめることがあり, 医事紛争に発展するケースもある. ここでは, 東京歯科大学水道橋病院歯科麻酔科・口腔顔面痛みセンターに通院している知覚神経障害患者のうち, 発症が医原性で医事紛争に発展した症例のなかから5症例 (症例1: インプラント埋入, 症例2, 3: 根管充填処置, 症例4, 5: 抜歯処置) を取り上げ, 歯科治療後知覚神経障害による医事紛争の現状と歯科臨床における問題点について報告した. 歯科治療における事前説明や事後対応は, いまだ十分に確立されていないのが現状であった.