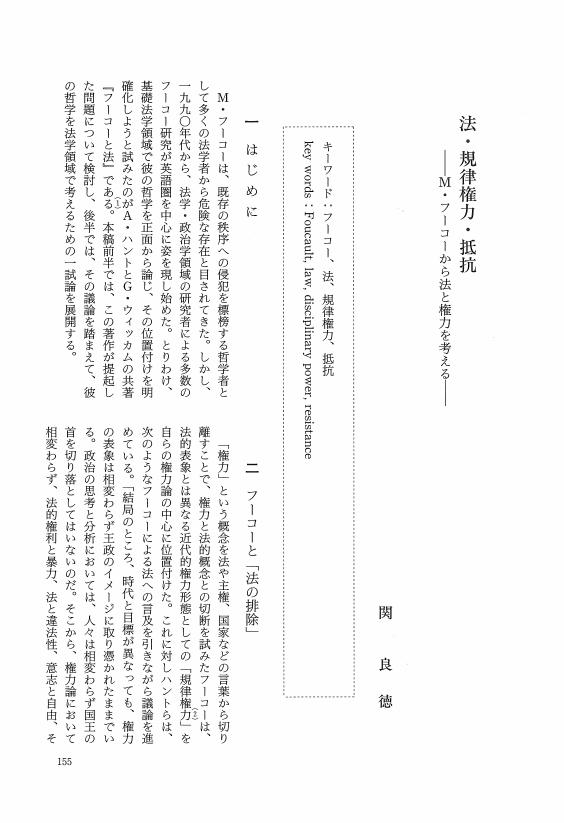2 0 0 0 OA ドイツの市民社会とブンデスリーガ ―共的セクターとしての非営利法人の機能―
- 著者
- 釜崎 太
- 出版者
- 日本スポーツ社会学会
- 雑誌
- スポーツ社会学研究 (ISSN:09192751)
- 巻号頁・発行日
- pp.29.2.1, (Released:2021-08-30)
- 参考文献数
- 31
現代においては、国や自治体だけではなく、企業や地域住民にも公的な課題への貢献が期待されている。ドイツでは、非営利法人が共的セクターとなって、自治体、企業、地域住民と連携し、公的な課題に取り組む事例が見られる。本研究が対象とする非営利法人は、ドイツのVerein(フェアアイン)である。Vereinは、法体系からは「社団」と訳される。しかし、スポーツクラブを運営するVereinが公的優遇を受ける登記法人(eingetragener Verein)であり、特にブンデスリーガの関係者にとっては、市場経済に対抗しつつ公益性を担保する自治的集団として意識されていることを重視する立場から、本研究では「非営利法人」と規定している。 ドイツにおいて非営利法人が運営するスポーツクラブが急増する1960年代以降、非営利法人をひとつのセクターとしながら数多くの社会運動が展開され、対抗文化圏が形成されていく。特に空き屋占拠運動で知られるアウトノーメは、FCザンクトパウリを動かし、反商業主義と反人種主義の運動を象徴するプロサッカークラブ(を一部門とする総合型地域スポーツクラブ)を生み出す。その一方で、90年代後半、プロサッカークラブの企業化が認められたブンデスリーガにおいては、非営利法人の議決権を保護する「50+1ルール」が定められ、プロサッカークラブ(企業)によるファンの獲得が、総合型地域スポーツクラブ(非営利法人)の資金を生み出す仕組みがつくられると同時に、非営利法人を軸とする市民社会のもとで、多様な地域課題への取り組みが実現されてきた。 本研究では、SVヴェルダー・ブレーメン非営利法人理事長、1FC. ケルン合資会社社長と顧問弁護士、FCザンクトパウリ非営利法人理事への聞き取り調査をもとに、ブンデスリーガに見られる市民社会の特徴と非営利法人の機能を明らかにした。
2 0 0 0 OA 一酸化窒素の生化学
- 著者
- 牧野 圭祐 鈴木 利典
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.1, pp.14-19, 2000-01-25 (Released:2009-05-25)
- 参考文献数
- 21
2 0 0 0 OA 緊急提言
- 出版者
- 公益社団法人 日本皮膚科学会
- 雑誌
- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)
- 巻号頁・発行日
- vol.131, no.5, pp.1107, 2021-04-13 (Released:2021-05-15)
2 0 0 0 OA 朝の運動遊びへの参加と子どもの身体活動量との関連性
- 著者
- 塙 佐敏 野井 真吾
- 出版者
- 日本幼少児健康教育学会
- 雑誌
- 日本幼少児健康教育学会誌 (ISSN:21896356)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.2, pp.111-120, 2021 (Released:2021-09-01)
- 参考文献数
- 45
This study aims to clarify the relationship the amount of physical activity between children’s exercise play in the morning and the achievement rate of daily recommended physical activity. We found that the amount of physical activity during morning exercise with the intensity LC3-9 was 9-13 minutes; LC4-9, was 7-10 minutes; LC7-9, 2-4 minutes; and the number of steps were 1,600-2,200 . The target number of steps to achieve the recommended physical activity time of 60 minutes was 12,300 steps in LC3-9, including daily activities, and the achievement rate depended on the frequency of morning exercise (High frequency group (a) > Medium frequency group (b) > Low frequency group (c), p<.001). The target number of steps with medium intensity or higher was 15,300 steps in 60 minutes, the target steps with high intensity was 15,700 steps in 25 minutes. The achievement rate was varid with the frequency of exercise.
2 0 0 0 OA 「あく」の中の無機成分の調理操作による溶出について(第1報) よもぎの場合
- 著者
- 出雲 悦子 大木 和香子
- 出版者
- 一般社団法人 日本調理科学会
- 雑誌
- 調理科学 (ISSN:09105360)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.2, pp.101-104, 1979-07-20 (Released:2013-04-26)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 5
2 0 0 0 OA リース取引における「使用権資産」勘定の特質
- 著者
- 菱山 淳
- 出版者
- 日本簿記学会
- 雑誌
- 簿記研究 (ISSN:24341193)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.2, pp.1-10, 2018-10-31 (Released:2019-04-19)
本稿は,IFRS16 のもとでオンバランスされる使用権資産に焦点をあて,これがどのような性質を持つ資産勘定であるか検討したものである。検討の視座は,リース取引とは何を取得する取引であるかについての二つの視点である。一つは,リース物件という「物」に着目する視点,いま一つは物件の使用権という「権利」に着目する視点である。この二つの視点をよりどころにし,かつ基準で定める借り手と貸し手の会計処理を手掛かりにして検討を行った。検討の結果,使用権資産を認識する前提として特定の資産が存在していなければならないこと,二次測定時には「物」の測定と整合する会計処理が規定されていること,表示では,「物」としての表示が求められていることが確認できた。また,貸し手の会計処理との対応関係の検討から,借り手の使用権資産勘定はリース取引の分類に応じて異なって解釈されることが確認できた。これらの帰結として,「使用権資産」は「権利」としての性質を持ちながらも,「物」として会計処理される面を含む,「物」と「権利」の性質が混在する資産勘定であることを指摘した。
2 0 0 0 OA ポテトチップス中の抗酸化成分について
- 著者
- 三好 隆行 石原 克之 中村 和哉 古賀 秀徳
- 出版者
- 一般社団法人 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会誌 (ISSN:13411535)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.5, pp.277-282, 2006-10-20 (Released:2013-04-26)
- 参考文献数
- 16
A study was conducted to determine how frying slices of potato would enhance the antioxidative activity. The content per unit weight of such antioxidants as L-ascorbic acid and chlorogenic acid in raw potato was nearly doubled when the slices were fried. Ultrafiltration of the water-soluble extract taken from the potato chips revealed the medium moleculare weight fraction of 3,000 to 20,000 to have high anti-oxidative activity, although the amount was small. This medium moleculare weight fraction had a strong brown color, due to melanoidin. There was a large amount of the fraction with a molecular weight of less than 3,000, and this fraction contributed 91% of the total antioxidative activity. It appears that chlorogenic acid and melanoidin were responsible for the antioxidative activity of this low molecular weight fraction.The DPPH radical scavenging activity of 19 kinds of potato snack foods was compared. There was higher activity in the potato chips made from raw potato than in those that had been more highly processed.
2 0 0 0 OA 水産増養殖における染色体操作の現状
- 著者
- 荒井 克俊
- 出版者
- Japanese Society for Aquaculture Science
- 雑誌
- 水産増殖 (ISSN:03714217)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.3, pp.411-416, 1997-09-20 (Released:2010-03-09)
- 参考文献数
- 41
2 0 0 0 OA キャンパス・セクシュアル・ハラスメント 実態・対応・課題
- 著者
- 上野 千鶴子
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.6, pp.16-23, 2000-06-01 (Released:2009-12-21)
- 参考文献数
- 11
2 0 0 0 OA II.近年問題となった新興感染症と現状
- 著者
- 岡部 信彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.105, no.11, pp.2120-2125, 2016-11-10 (Released:2017-11-10)
- 参考文献数
- 11
1980年地球上からの痘そう(天然痘)の根絶が宣言され,これが感染症に対する人類の勝利のように思われたが,その前後から新しい病原体による新しい感染症が次々と発見され,病原体の逆襲ともいえる状況が続いている.それまで未知であった新しい病原体による新しい感染症あるいは新たに感染症であることが解明された疾患は新興感染症,既知の病原体による疾患が改めて問題になる場合には再興感染症と呼ばれ,警戒されている.本稿では,近年問題となったこれらの感染症について概説する.
2 0 0 0 OA 日本人とキリスト教ー山梨英和学院の場合ー
- 著者
- 深津 容伸
- 出版者
- 山梨英和学院 山梨英和大学
- 雑誌
- 山梨英和大学紀要 (ISSN:1348575X)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.A17-A25, 2010 (Released:2020-07-20)
日本にキリスト教プロテスタントによる宣教が開始されてから、150年以上になるが、その特徴の一つとしていえることは、学校、すなわちミッションスクールの設立に力を注いできたことである。現在ミッションスクールは、(沖縄から北海道に至るまで)定着し、根付いている。日本のキリスト教人口が1%に満たない現状を考えると、日本人はキリスト教信仰は退けたが、(そこで行われているキリスト教教育を含めて)教育機関としてのミッションスクールは受け入れたといえるであろう。 山梨英和学院(以下山梨英和)の場合、当時交通の便の悪い内陸の地という悪条件にもかかわらず、山梨の青年キリスト者たちの熱心な働きかけが、カナダメソジスト教会の宣教団体を動かし、設立されるに至った。本稿では、この時の日本の社会状況、日本人側、カナダメソジスト教会の宣教団体側双方の思いを掘り起こすとともに、どのように山梨英和は地域社会に受け入れられてきたか、また、山梨の諸教会との繋がりはいかなるものであったかを探り、ミッションスクールの教育のあり方、とらえ方を論じる。
2 0 0 0 OA 凍結全卵と普通卵の調理特性の比較検討
- 著者
- 林 真愉美 遠藤 陽子 市川 和子 河原 和枝
- 出版者
- 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会大会研究発表要旨集 平成18年度日本調理科学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.88, 2006 (Released:2006-09-07)
【目的】凍結全卵の調理特性については、我々のこれまでの研究で卵豆腐や茶碗蒸しなどの蒸し料理において普通卵と同様の結果が得られ、コスト面では普通卵に劣るものの、ごみや保管スペース、作業効率、衛生管理の面で利用価値が高いと考えられた。しかし、かきたま汁や中華スープなどの汁物では卵が散ってしまい外見が悪いという点から実用化には至っておらず、凍結全卵の汁物への適応が課題として残されていた。今回は液卵の粘度に着目し、汁物における凍結全卵の利用について検討を行った。【方法】凍結全卵はキューピータマゴ(株)の凍結全卵No.3およびNo.12、ツインパックを使用した。常温(15℃)に解凍した各種凍結全卵および普通卵を用いてかきたま汁を作成し官能評価を行った。さらにツインパックを47℃に加温し同様の官能評価を行った。官能評価は普通卵を基準とし、評価項目は散在状態、色、味・食感、総合の4項目とした。さらに凍結全卵No.3、ツインパック、普通卵の各温度帯における粘度についてB形粘度計(東京計器)を用いて測定した。【結果】官能評価の結果、常温で使用した凍結全卵のかきたま汁はいずれも普通卵に劣っており実用化できるものではなかった。しかし、47℃に加温したツインパックは散在状態以外の全ての項目で普通卵よりも良好な結果が得られ、従来汁物以外で使用している凍結全卵No.3でも40℃以上に加温することで普通卵に近い状態が確認され、加温することで汁物にも利用できる可能性が示唆された。液卵の粘度については、ツインパックは普通卵と同様に温度による変化が小さく安定していたが、凍結全卵No.3は温度による影響を受けやすく、不安定であることが明らかとなった。
2 0 0 0 OA 相界面析出現象と最近の実用鉄鋼材料への応用
- 著者
- 船川 義正
- 出版者
- 公益社団法人 日本金属学会
- 雑誌
- 日本金属学会誌 (ISSN:00214876)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.10, pp.447-457, 2017-10-01 (Released:2017-09-25)
- 参考文献数
- 56
- 被引用文献数
- 1 1
The interface-precipitation has been observed as row carbide arrange since 1960’s. Whereas the interface-precipitated carbides in steels were NbC, TiC, VC and Cr23C6 in the early stage, composite TiC containing Mo and W has been also become to observe recently. Several kinds of the mechanism of the interface-precipitation have been suggested and ledge mechanism and bowing mechanism which combined interface barging and carbide precipitation are widely accepted since the mechanisms successfully explained a large amount of the experimental results. Fine interface-precipitates in low carbon steel realize high strength steel sheets, plates, bars and rods which are non-quenched and tempered. Especially, in sheet products, in which fine carbides can be easily generated, ferritic steel of 1180 MPa in tensile strength is successfully obtained by dispersing fine carbides with the diameter of several nano-meters.
2 0 0 0 OA 自動車事故における同乗者の影響
- 著者
- 松浦 常夫
- 出版者
- 日本社会心理学会
- 雑誌
- 社会心理学研究 (ISSN:09161503)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.1, pp.1-10, 2003-08-06 (Released:2017-01-13)
Both field observations of passengers in cars and accident analyse were conducted to clarify the influences of passengers on automobile accidents. Items investigated in both studies included the age and gender of both driver and passenger, and the number of passengers. We used data on accidents occurring in the Tsukuba area (N=957), where observational studies were conducted (N=2682). An accident case study (N=206) was also done to examine the types of passenger-related effects. Log-linear analysis indicated that accident risk was higher when carrying two or more passengers or when driving alone than when carrying only one passenger, and risk was also higher when males or children were passengers. These passenger effects were discussed in terms of communication, distraction, and conformity to passenger norms.
2 0 0 0 OA センサ機能付照明器具について
- 著者
- 前田 哲治
- 出版者
- 一般社団法人 照明学会
- 雑誌
- 照明学会誌 (ISSN:00192341)
- 巻号頁・発行日
- vol.87, no.10, pp.809-817, 2003-10-01 (Released:2011-07-19)
- 被引用文献数
- 1
2 0 0 0 OA 薬剤管理サマリーと患者のイベント抑制に関する調査
- 著者
- 高井 靖 梶間 勇樹
- 出版者
- 一般社団法人日本医療薬学会
- 雑誌
- 医療薬学 (ISSN:1346342X)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.8, pp.446-451, 2020-08-10 (Released:2021-08-10)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 1
This study aims to evaluate the usefulness of the Medication Management Summary, which is a tool of information sharing between hospital pharmacists and pharmacists at insurance pharmacies, based on patient-centered outcomes. Patients whose hospital pharmacists provided the Medication Management Summary to the pharmacists at the insurance pharmacy were assigned to the Medication Management Summary group (Group A), and patients before the introduction of the Medication Management Summary were assigned to the control group (Group B). Each group consisted of 90 patients, among which 30 were cardiac arrest patients, 30 were ischemia heart disease patients, and 30 were arrhythmia patients. The primary endpoint was the number of events, and the secondary endpoints were the presence or absence of readmission, evaluation of medication adherence, and changes in the number of medications in 6 months. The information on the Medication Management Summary in Group A was as follows: medication changes: 20; start of medication: 43; adverse effects: 4; medication management: 29; adjustment of leftover medication: 8; monitoring: 6 (including duplicates). The number of events was significantly lower (P = 0.032) in Group A (2 events) compared to that in Group B (9 events). The number of patients who were readmitted to the hospital was not significantly different between Group A and Group B. The medication adherence was unchanged in Group A but significantly worsened in Group B (P = 0.001). The number of medications did not change significantly in both groups. In conclusion, the provision of the Medication Management Summary by hospital pharmacists to insurance pharmacy pharmacists can help control patient events.
- 著者
- Kazumichi YOSHIDA Susumu MIYAMOTO SMART-K Study Group
- 出版者
- The Japan Neurosurgical Society
- 雑誌
- Neurologia medico-chirurgica (ISSN:04708105)
- 巻号頁・発行日
- pp.st.2019-0188, (Released:2019-11-09)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 1
With recent advances in medical treatments for carotid artery stenosis (CS), indications for carotid surgery should be more carefully considered for asymptomatic CS (ACS). Accurate stratification of ACS should be based on the risk of cerebral infarction, and subgroups of patients more likely to benefit from surgical treatment should be differentiated. Magnetic resonance imaging (MRI) offers a non-invasive, accurate modality for characterizing carotid plaque. Intraplaque hemorrhage (IPH) seems the most promising feature of vulnerable plaque detectable by MRI. Lectin-like oxidized low-density lipoprotein receptor-1 (LOX-1) is a type II membrane protein of the C-type lectin family with an extracellular domain that can be proteolytically cleaved and released as a soluble form (sLOX-1). This sLOX-1 plays a key role in the pathogenesis of atherosclerosis, and elevated sLOX-1 concentrations correlate with thin or ruptured fibrous caps in patients with acute coronary syndrome. This ongoing study aims to clarify the incidence of ischemic stroke in patients with ACS and IPH confirmed by MRI, and to assess whether sLOX-1 could provide a biomarker for risk of future ischemic events. The study population comprises patients with ACS (>60% area stenosis) associated with MRI-diagnosed IPH receiving follow-up under medical treatment. Primary endpoints comprise transient ischemic attack, stroke or amaurosis resulting from concerned CS. Secondary endpoints comprise any stroke or surgical treatment for progressive luminal stenosis. The target number of patients is 120 and the observational period is 36 months. The study results could help identify individuals with ACS who are refractory to medical therapy.
- 著者
- 佐伯 壮一朗 柳澤 沙也子 小笠原 理恵 安田 直史 中村 安秀 関西グローバルヘルスの集い運営委員会
- 出版者
- 日本国際保健医療学会
- 雑誌
- 国際保健医療 (ISSN:09176543)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.2, pp.63-72, 2021 (Released:2021-07-22)
- 参考文献数
- 10
背景 新型コロナウイルス感染症(Novel Coronavirus Disease 2019, COVID-19)の影響を受け、各種イベント開催が自粛され、人が物理的に集まらないオンラインセミナーの開催の需要が高まっている。しかし、オンラインセミナーの開催経験を豊富に有するグローバルヘルス関連の学術団体はまだ少なく、ノウハウの蓄積は不十分である。そのような状況の中、公益社団法人日本WHO協会は一般市民に開かれた公開講座「関西グローバルヘルスの集い」を「COVID-19とSDGs」をテーマに2020年3月から企画し、5月より3回オンラインにて開催した。この経験に基づきオンラインセミナーを開催する際の主催者への注意点をまとめる。開催概要 関西グローバルヘルスの集いを開催するにあたりオンラインで参加者の募集、登録受付を行った。その際Google Formsを利用し、参加者の属性に対するアンケート調査を実施した。本番はオンライン会議ソフトウェアZOOMを使用し、動画サイトYouTubeにて生配信した。視聴者動向の解析はYouTube Analyticsによる自動解析を利用し、セミナー終了後、参加登録者にGoogle Formsを利用したアンケートでフィードバックを依頼した。 3回の参加者はのべ2,083名だった。大半は日本在住であったが、海外在住の参加者はのべ69名で、欧米諸国やチュニジア、ザンビアなどであった。参加者の属性は医療者のみならず大学教員や学生、会社員も参加した。満足度について、5段階評価で4以上を回答した参加者は85.7%であった。記述回答では内容への肯定的な意見の他、開催前から当日にかけての運営の不手際を指摘した意見が寄せられた。教訓 オンラインセミナーでは、講演内容のみならず運営の手際でも満足度が変化することが分かった。運営の不手際は具体的に、セミナー開催前には一部の参加者に対し配信用URLが届かない例があり、セミナー中には画面の切り替えの不手際、画面共有で投影していたスライドの動作不全が生じたこともあった。これらは運営側の取り組み次第では予防あるいは早期発見し修正する余地があり、不具合が生じた際の対応を事前に検討することが重要である。結論 オンラインセミナーを開催することで視聴者のみならず登壇者は世界中から参加可能となったのは大きな利点である。一方、綿密な準備が必要で、運営者の経験を蓄積し円滑な運営を行うことは議論活性化の最低条件である。今後、国際保健医療分野での活用のためにはオンラインセミナーの運営のみならず内容の質も問われることとなるだろう。
2 0 0 0 OA 法・規律権力・抵抗—M・フーコーから法と権力を考える—
- 著者
- 関 良徳
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.2000, pp.155-163, 2001-10-30 (Released:2008-11-17)
- 参考文献数
- 6
2 0 0 0 OA つながる「つる」-茎寄生植物ネナシカズラがつくる植物-植物コネクション-
- 著者
- 青木 考 藤原 大輝 清水 皇稀
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.2, pp.99-107, 2019 (Released:2019-08-08)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 1