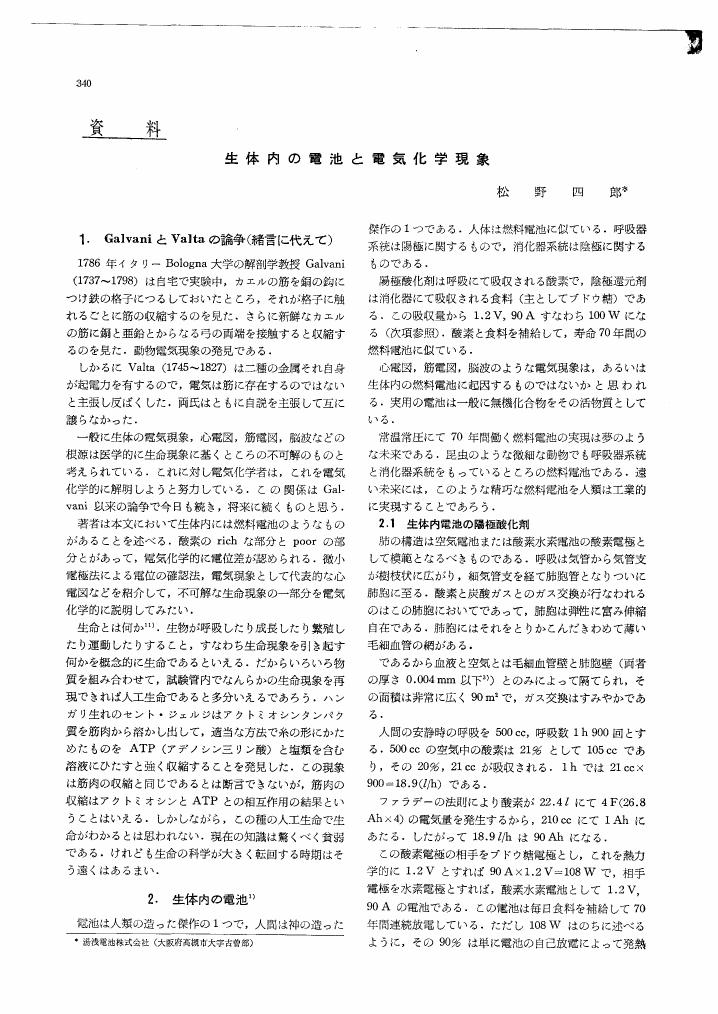2 0 0 0 OA 我が国の航空機による微小重力実験飛行
- 著者
- 景山 大郎
- 出版者
- 日本マイクログラビティ応用学会
- 雑誌
- International Journal of Microgravity Science and Application (ISSN:21889783)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.2, pp.45, 2014-04-30 (Released:2020-05-14)
- 著者
- Takashi Ohrui Hidenori Takahashi Satoru Ebihara Toshifumi Matsui Katsutoshi Nakayama Hidetada Sasaki
- 出版者
- Tohoku University Medical Press
- 雑誌
- The Tohoku Journal of Experimental Medicine (ISSN:00408727)
- 巻号頁・発行日
- vol.192, no.1, pp.81-86, 2000 (Released:2005-04-21)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 16 16
This report presents the cases of two patients with rapidly progressive hypoxemia associated with influenza A(H3N2) virus infection, who were diagnosed with influenza related acute pulmonary microthromboembolism by serum D-dimer, lung perfusion and ventilation scans and computed-tomography scan of the chest, and were successfully treated by anti-coagulant therapy. The present cases suggest that acute onset pulmonary microthromboembolism should be considered in some patients with sudden, unexplained dyspnea during an outbreak of influenza infection and prompt diagnosis is essential to save the patient from acute death associated with influenza.
2 0 0 0 OA Cornelia de Lange症候群に併発した盲腸捻転:臨床および画像の検討
- 著者
- 江口 麻優子 野坂 俊介 植松 悟子 藤野 明浩 金森 豊 岡本 礼子 窪田 満 石黒 精
- 出版者
- 日本小児放射線学会
- 雑誌
- 日本小児放射線学会雑誌 (ISSN:09188487)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.2, pp.107-115, 2019 (Released:2019-11-22)
- 参考文献数
- 18
小児の盲腸捻転は稀であるが,重症心身障害児,特にCornelia de Lange症候群(以下CdLS)での報告が多い.症状は非特異的で,画像診断の役割は大きい.早期診断は腸管壊死を回避する上で重要で,診断や治療の遅れは死亡に繋がる可能性がある.当院で経過観察中のCdLS 13例中4例に盲腸捻転を認めた.いずれも盲腸捻転に特異的な腹部単純撮影所見,もしくは過去と比較して変化を認め,引き続き行った造影CT所見から全例で術前に盲腸捻転を疑うことができた.盲腸捻転併発4例と捻転非併発9例を比較すると,併発例全例が胃瘻造設術・噴門形成術後で,これらの手術が捻転の誘因になると考えられた.また,既報告と比較して死亡率と術後合併症率は,より低率であった.CdLSで,胃瘻造設術・噴門形成術後の児が腹部症状を示す場合,盲腸捻転の併発を念頭に,腹部単純撮影に続く造影CTが早期診断と治療に有用である.
2 0 0 0 OA 高分子磁性体
- 著者
- 蒲池 幹治
- 出版者
- 公益社団法人 高分子学会
- 雑誌
- 高分子 (ISSN:04541138)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.12, pp.832-835, 1987-12-01 (Released:2011-10-14)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 1 1
2 0 0 0 OA 権力理論の説明形式
- 著者
- 志田 基与師
- 出版者
- 数理社会学会
- 雑誌
- 理論と方法 (ISSN:09131442)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.2, pp.299-312, 2000-10-30 (Released:2016-09-30)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 1
権力を主題とする社会理論を権力理論と呼ぼう。権力理論は、理論であるからには現象を説明する能力をもとめられ、与件から被説明項である社会状態を一義的に演繹するものでなければならない。この性能は理論が備える法則的言明あるいはそれらの組から導出される命題が担っている。権力理論は、理論に備わる法則あるいはそこから導出される命題のいくつかが非対称的な決定(ディタミネーション)の形式となる社会理論のことである。この非対称な命題を権力命題と呼ぼう。このことはすべての変数が一般には相互に連関するという社会理論に持ちこまれた特殊な仮説であり、つねに無条件に成立することではない。非対称的な決定形式を持つ法則的言明が理論に含まれるとはどのような場合であるのかまたどのような条件のもとでそれは可能となるのか検討すると、権力は一つの理論体系の中でも多様なものでありうることが明らかになる。またそれらの可能性に応じて権力理論がどのようにして可能になるのかについて、いくつかの権力理論の一般性と特殊性とについて検討する。
- 著者
- 松尾 貴史
- 出版者
- 公益社団法人 有機合成化学協会
- 雑誌
- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.4, pp.311-321, 2021-04-01 (Released:2021-04-07)
- 参考文献数
- 49
Hoveyda-Grubbs-type complexes with a ruthenium center coordinated by an N-heterocyclic carbene (NHC) and a 2-alkoxybenzylidene ligands have gained increased applicative importance as catalysts for olefin metathesis because the complexes have suitable reactivities and stabilities in a wide range of reaction media. Furthermore, this type of catalysts has also been applied for biochemical research projects including the construction of artificial biocatalysts and the regulation of in-cell bioreactions because the ruthenium-olefin interaction, a driving force of olefin metathesis mediated by Hoveyda-Grubbs-type complexes, provides the specificity among functional groups in biomolecules. In this context, we have investigated the structural modification of Hoveyda-Grubbs-type complexes aiming at the application of the complexes to biomolecules. In parallel, we have also studied the mechanism of olefin metathesis in aqueous media. In this article, we firstly describe the construction of an artificial metalloenzyme with olefin metathesis activity using α-chymotrypsin. The artificial metalloenzyme displayed the substrate specificity with the protein surface charge state. Next, we demonstrate the importance of chloride anion in solutions to attain efficient olefin metathesis reactions in aqueous media and the reactivity control of Hoveyda-Grubbs-type complexes through second-coordination sphere effect. Finally, we introduce the ruthenium complex transfer reaction between Hoveyda-Grubbs-type complexes and biomolecules (peptides and proteins) through the ruthenium-olefin specific interaction. The reaction potentially serves a new type of chemical modification strategy toward biomolecules.
2 0 0 0 OA 生体内の電池と電気化学現象
- 著者
- 松野 四郎
- 出版者
- 公益社団法人 電気化学会
- 雑誌
- 電氣化學 (ISSN:03669440)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.5, pp.340-346, 1961-05-05 (Released:2019-09-25)
- 著者
- 堀江 政広 横川 耕二 須永 剛司
- 出版者
- 一般社団法人 日本デザイン学会
- 雑誌
- 日本デザイン学会研究発表大会概要集 日本デザイン学会 第54回研究発表大会
- 巻号頁・発行日
- pp.P16, 2007 (Released:2007-06-09)
高度な専門性をもつソフトウェア技術者等の不足が問題視されている。その不足という状況は、エンジニアだけでなく、ソフトウェア開発に関わるデザイナーにも当てはまる。それを解決するための手段のひとつとして、エンジニアと協調しソフトウェア開発を行えるデザイナーの育成が有効であると考えた。 本稿では、「グループ活動提示ツール」のプロトタイプ・ソフトウェア開発を事例に、「エクストリーム・プログラミング(XP)」というコーディングを中心的活動とする開発手法の実践を報告する。そして6週間(1.5人月)という短期間で行われたエンジニアとデザイナーとの協調について述べる。
2 0 0 0 OA 歯磨剤の研磨性について
- 著者
- 伊豆山 実
- 出版者
- 一般社団法人 色材協会
- 雑誌
- 色材協会誌 (ISSN:0010180X)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.1, pp.26-33, 1969-01-30 (Released:2012-11-20)
- 参考文献数
- 18
2 0 0 0 OA 嚥下時舌運動の経時的発達変化 超音波前額断による舌背面について
- 著者
- 大塚 義顕 渡辺 聡 石田 瞭 向井 美惠 金子 芳洋
- 出版者
- 一般財団法人 日本小児歯科学会
- 雑誌
- 小児歯科学雑誌 (ISSN:05831199)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.5, pp.867-876, 1998-12-25 (Released:2013-01-18)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 4
乳児期に獲得される嚥下機能の発達過程において,舌は中心的役割を果たしている。しかしながら,吸啜時の動きから固形食嚥下時の動きへと移行する舌の動きの経時変化の客観評価についての報告はほとんど見られない。そこで,生後20週から52週までの乳児について,超音波診断装置を用いて顎下部より前額断面で舌背面を描出し,舌の動きの経時的発達変化の定性解析を試みたところ以下の結果を得た。1.生後20週には,嚥下時の舌背部にU字形の窪みが見られ,舌全体が単純に上下する動きが観察された。2.生後26週には,嚥下時の舌背正中部に陥凹を形成する動きがはじめて見られた。3.生後35週には,上顎臼歯部相当の歯槽堤口蓋側部に舌背の左右側縁部が触れたまま正中部を陥凹させる動きが確認できた。4.生後35週から52週までの舌背正中部の陥凹の動きは,ほぼ一定で安定した動きが繰り返し観察できた。5.舌背正中部にできる陥凹の動きの経時変化から安静期,準備期,陥凹形成期,陥凹消失期,口蓋押しつけ期,復位期の6期に分類することができた。以上より,前額断面での舌運動は,舌の側縁を歯槽堤口蓋側部に接触固定し,これを拠点として舌背正中部に向けて食塊形成のための陥凹を形成する発達過程が観察できたことから,食塊形成時の舌の運動動態がかなり明らかとなった。
2 0 0 0 OA 乳児用食品の物性基準の適正評価 第1報 固形物の固さについて
- 著者
- 大河内 昌子 向井 美惠
- 出版者
- 一般財団法人 日本小児歯科学会
- 雑誌
- 小児歯科学雑誌 (ISSN:05831199)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.1, pp.224-231, 2003 (Released:2013-01-18)
- 参考文献数
- 18
乳児を対象にした乳児用食品の固さの基準値についての客観的な検証は行われていない現状である.そこで,乳児に適正な物性基準の資料を得る目的で,離乳期の乳児を対象に摂食時の口腔領域の動きを観察評価して,その発達状態によって4群に分類し,以下の検討を行った.被験食品は,予め調整した固さの異なる4種類の基準食品とし,それらの食品の摂食時の処理方法の適否および顎の運動回数を指標として4群間で比較検討を行い以下の結論を得た.1.被験食品の固さが増加するに伴い,適正処理可能な乳児の割合は減少した.2.乳児は,食品の固さに応じて,顎の運動回数を変化させ食品を処理していることが認められた.3.食品の固さの変化による顎の運動回数は,離乳の時期によって異なることが示唆された.離乳初期~後期の乳児が処理できる固さの目安は得られたが,今後これらの固さの食品に対して適切な顎運動回数の検討などがさらに必要と考えられた.
2 0 0 0 OA デジタル音源のサンプリング周波数が聴取者の心理・生理状態に及ぼす影響
- 著者
- 大湾 麻衣 入戸野 宏
- 出版者
- 日本生理心理学会
- 雑誌
- 生理心理学と精神生理学 (ISSN:02892405)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.3, pp.169-176, 2020-12-31 (Released:2021-03-19)
- 参考文献数
- 25
ハイレゾリューション音源はCDより時間方向あるいは振幅方向の解像度が高く,その高周波成分が生理状態に影響を及ぼすという報告がある。本研究では192 kHz/24 bitで録音された自然環境音(オリジナル音源)にフィルタをかけ,高周波成分(>22 kHz)をカットした2種類の音源(サンプリング周波数192 kHzと44.1 kHz)を作成した。24名の大学生が3種類の音刺激をランダムな順で聴取した。脳波のシータ帯域(4.0―8.0 Hz)とスローアルファ帯域(8.0―10.5 Hz)のトータルパワーは,サンプリング周波数が高い音を聴取しているときの方が高くなった。主観的気分や音質評価には明瞭な条件差が認められなかった。この結果は,CDよりもサンプリング周波数が高い音源は,意識的に違いに気づかなくても生理状態に影響を及ぼすことを示唆している。
2 0 0 0 OA ジェンダー・ステレオタイプと科学教育:社会心理学的研究からの示唆
- 著者
- 森永 康子
- 出版者
- 一般社団法人 日本科学教育学会
- 雑誌
- 日本科学教育学会年会論文集 43 (ISSN:21863628)
- 巻号頁・発行日
- pp.7-8, 2019 (Released:2020-07-31)
- 参考文献数
- 5
STEM分野における女性研究者や女性学生はなぜ少ないのかについて,ジェンダー・ステレオタイプ(GST)に関する社会心理学的研究を取り上げて,1) GSTが他者評価に影響を与え,女性が低く評価される可能性,2) ST脅威の現象に見られるように,GSTが自己成就予言として働く可能性,3) 潜在的STの影響,4) 表面的にポジティブに聞こえる場合でも,GSTがネガティブな結果をもたらしうること,の4点から説明を試みる.これらの研究をもとに科学教育にどのような示唆ができるかを考えてみたい.
2 0 0 0 OA 大元帥明王考
- 著者
- 森田 龍僊
- 出版者
- 密教研究会
- 雑誌
- 密教研究 (ISSN:18843441)
- 巻号頁・発行日
- vol.1942, no.80, pp.1-20, 1942-02-01 (Released:2010-03-12)
- 著者
- Ryota UMEZAWA
- 出版者
- Faculty of Mathematics, Kyushu University
- 雑誌
- Kyushu Journal of Mathematics (ISSN:13406116)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.2, pp.233-254, 2020 (Released:2020-12-15)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1
We introduce an iterated integral version of (generalized) log-sine integrals(iterated log-sine integrals) and prove a relation between a multiple polylogarithm and iterated log-sine integrals. We also give a new method for obtaining relations among multiple zeta values, which uses iterated log-sine integrals, and give alternative proofs of several known results related to multiple zeta values and log-sine integrals.
- 著者
- Masayuki Amano Taro Shimizu
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.2, pp.79-82, 2014 (Released:2014-01-15)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 14 95
Emphysematous cystitis (EC) is a rare form of complicated urinary tract infection, its characteristic feature being gas within the bladder wall and lumen. Patients with EC present with variable clinical manifestations ranging from asymptomatic to severe sepsis. EC is typically observed in elderly women with severe diabetes mellitus. Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae are often isolated from urine cultures. Imaging methods, such as plain conventional abdominal radiography and computed tomography, are pivotal for obtaining a definitive diagnosis of EC. Most cases can be treated with a combination of antibiotics, bladder drainage and glycemic control. EC is potentially life-threatening, with a mortality rate of 7%. Early medical intervention can contribute to achieving a favorable prognosis without the need for surgical intervention. In this review, we provide a comprehensive description of the clinical characteristics of EC.
2 0 0 0 OA 数学に於ける抽象の必然性
- 著者
- 沢口 昭聿
- 出版者
- 科学基礎論学会
- 雑誌
- 科学基礎論研究 (ISSN:00227668)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.4, pp.156-165, 1962-02-28 (Released:2009-09-04)
- 参考文献数
- 10
2 0 0 0 OA 香辛野菜のフレーバー形成
- 著者
- 川岸 舜朗
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.11, pp.741-745, 1993-11-25 (Released:2009-05-25)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1 1
- 著者
- 金田 康秀
- 出版者
- 一般社団法人 日本東洋医学会
- 雑誌
- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.4, pp.278-286, 2014 (Released:2015-03-30)
- 参考文献数
- 60
Vogt-小柳-原田病(原田病)は,本邦では2番目に多いぶどう膜炎である。自己のメラノサイトに対する自己免疫性疾患と考えられており,汎ぶどう膜炎に加え,中枢神経症状,内耳症状,皮膚症状をきたすことが特徴的である。標準治療は全身的なステロイド大量療法である。更に不十分なステロイド剤使用は再燃や遷延化を招く。今回,B 型肝炎ウイルスキャリアに初発した原田病に対し,ステロイド剤を一切使用せずに竜胆瀉肝湯(一貫堂)と五苓散の併用が奏効した一例を経験したので報告する。症例:40歳男性。両)霧視を主訴に近医眼科を受診し,両)黄斑症を認め当科に紹介。原田病と診断し,和漢診療学的に軽度の水滞・瘀血を伴う足厥陰肝経の湿熱と捉え,竜胆瀉肝湯(一貫堂)と五苓散を投与した。結果,翌日から徐々に視力が改善し始め,ステロイド剤を使用することなく治癒した。原田病に漢方単独の治療が選択肢になり得ることが示唆された。
2 0 0 0 OA 認知神経科学よりみた発達障害の脱抑制
- 著者
- 相原 正男
- 出版者
- 認知神経科学会
- 雑誌
- 認知神経科学 (ISSN:13444298)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.3, pp.233-240, 2012 (Released:2017-04-12)
発達障害は神経心理学的に前頭葉の機能障害であることが明らかになるにつれて、行動抑制やワーキングメモリモデルに基づく認知神経科学的研究が近年活発に行われてきている。発達障害の脱抑制が、サッケード、NoGo 電位、情動性自律反応などの神経生理学的手法から明らかとなってきた。さらに、将来に向けた文脈を形成するためには、適切な行動(抑制・促進)を随時意思決定する必要があり、その際情動性自律反応がbiasとして作用している。