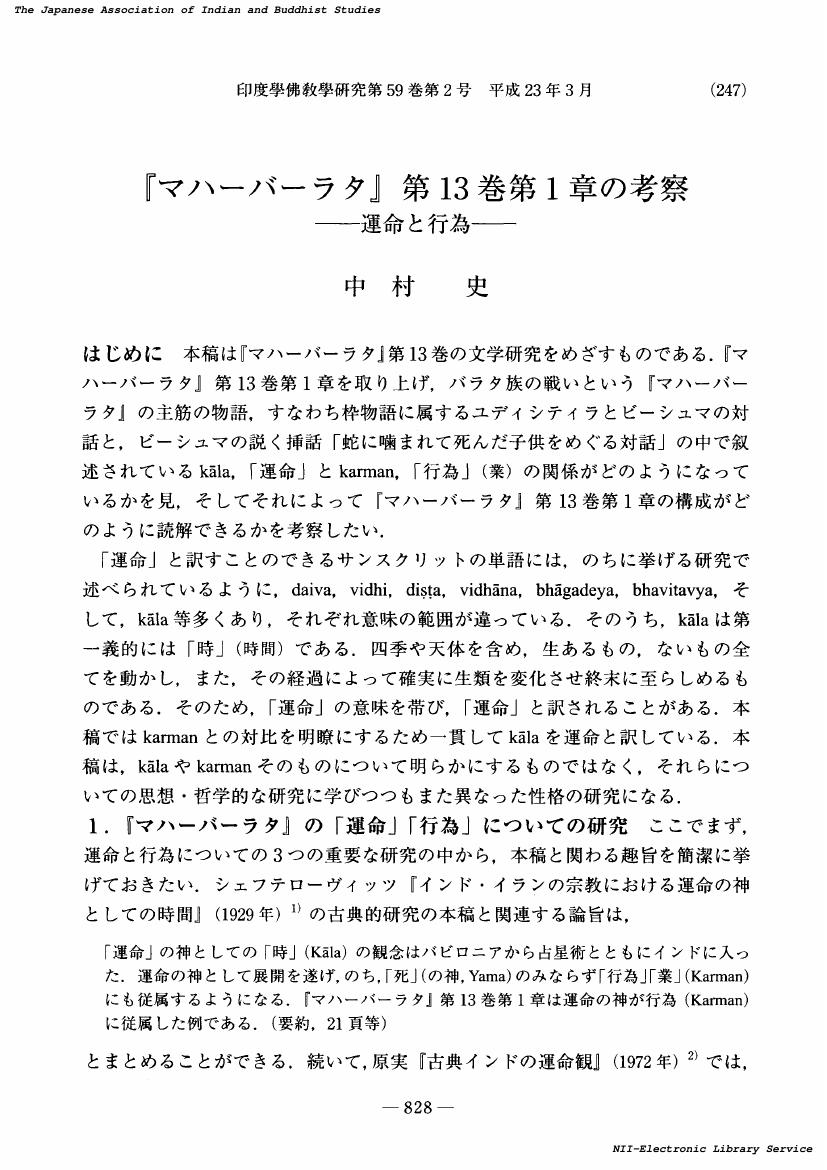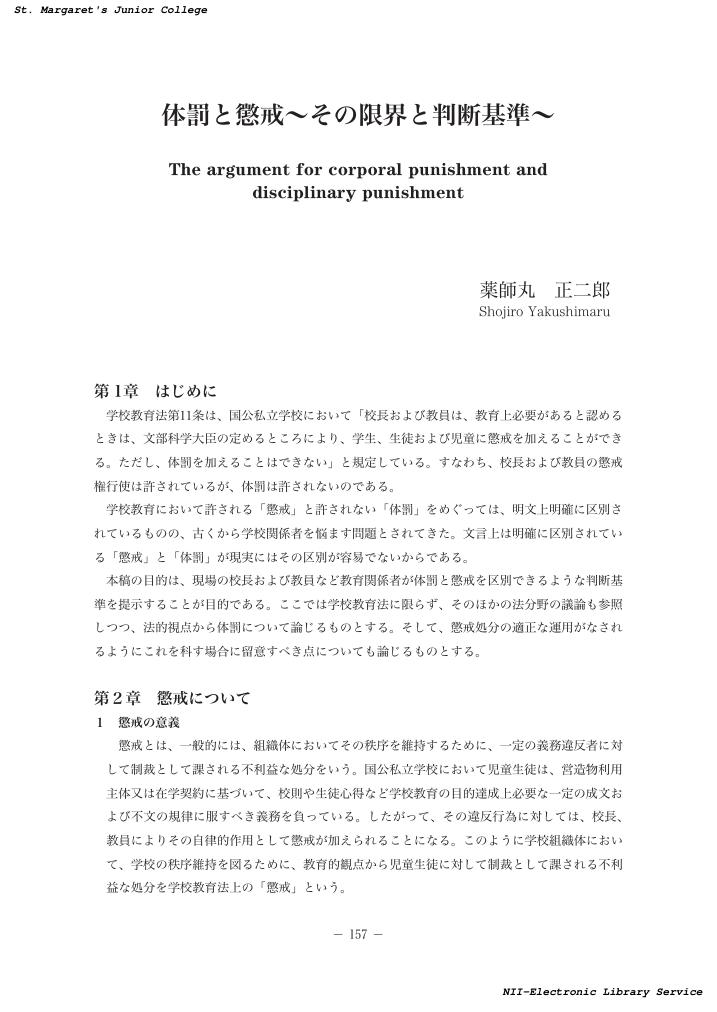2 0 0 0 OA 磁気共鳴画像法(MRI)を用いた閉鎖筋の筋活動分析
- 著者
- 平尾 利行 竹井 仁 佐久間 孝志 妹尾 賢和 近藤 貴揚
- 出版者
- 理学療法科学学会
- 雑誌
- 理学療法科学 (ISSN:13411667)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.2, pp.297-302, 2016 (Released:2016-04-29)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 1
〔目的〕閉鎖筋の筋活動を賦活するのに適した運動負荷を検討すること.〔対象〕腰部および下肢に器質的疾患を持たない成人男性11名とした.〔方法〕高負荷の課題1(60°/sec)と無負荷の課題2(500°/sec)における等速性股関節外旋運動前後で,MRIのT2強調画像から内閉鎖筋,外閉鎖筋,大殿筋,中殿筋,縫工筋のMR信号強度率を抽出し比較した.〔結果〕抽出された課題1において内閉鎖筋,外閉鎖筋,中殿筋,縫工筋で,課題2において内閉鎖筋,外閉鎖筋,縫工筋で,運動前に比べ運動後にMR信号強度率が有意に上昇した.〔結語〕速筋線維を多く含む閉鎖筋に対しては,高負荷のみならず無負荷の運動も筋活動を得ることを可能にすると考える.
2 0 0 0 OA 運動負荷の違いが内外閉鎖筋に及ぼす影響について
- 著者
- 平尾 利行 佐久間 孝志 妹尾 賢和 岡田 亨 竹井 仁
- 出版者
- 社団法人 日本理学療法士協会関東甲信越ブロック協議会
- 巻号頁・発行日
- pp.74, 2011 (Released:2011-08-03)
【目的】 解剖学的観点から股関節深層筋のうち内外閉鎖筋は股関節の衝撃吸収作用という役割を担っていると考えられ、内外閉鎖筋機能を改善させることは股関節機能改善、維持という観点において重要な意味をなすと考える。しかし、どのような負荷のトレーニングをすることで内外閉鎖筋が促通されるかは明らかでない。運動によって活動した筋はMRI信号強度が上昇することが知られており、股関節深層筋機能評価においてMRIを用いることは有用と考えられる。本研究の目的は股関節深層筋である内外閉鎖筋を賦活するのに適した負荷量についてMRIを用いて明らかにすることである。 【方法】 股関節に既往のない成人男性11名(平均年齢23.5±1.5years、平均身長169.4±4.7cm、平均体重62.3±4.6kg)を対象とした。被検者に高負荷外旋運動と低負荷外旋運動を行い、それぞれの運動前後でMRI(1.5T)を施行し股関節周囲筋の信号強度を抽出した。高負荷外旋運動とは角速度60deg/secでの等速性外旋運動と定義し、低負荷外旋運動とは角速度500deg/secでの等速性外旋運動と定義した。運動機器にはBIODEX system3(BIODEX社製)を用い、股関節90°屈曲位(恥骨結合と上前腸骨棘を結ぶ線に大腿骨長軸が垂直になるよう設定した)の端座位にて0°から最大外旋位までの範囲で等速性外旋運動を行った。運動課題は30秒間の等速性外旋運動を5セットとした。セット間の休憩は10秒とした。MRIで抽出する筋は内閉鎖筋、外閉鎖筋、梨状筋、大殿筋、中殿筋、小殿筋、腸腰筋とした。高負荷外旋運動と低負荷外旋運動における各筋の運動前と運動後のMRI信号強度を比較した。統計処理にはSPSS ver.12.0を用い、Wilcoxonの符号付順位検定を行った。有意水準は5%とした。 【結果】 高負荷外旋運動において運動後にMRI信号強度の有意な上昇を認めた筋は内閉鎖筋、外閉鎖筋、中殿筋、腸腰筋であった。低負荷外旋運動において運動後にMRI信号強度の有意な上昇を認めた筋は内閉鎖筋、外閉鎖筋のみであった。 【考察】 低負荷外旋運動後にMRI信号強度の有意な上昇を認めた筋は内閉鎖筋、外閉鎖筋のみであり、高負荷外旋運動よりも選択的に内外閉鎖筋が働いていた。 内閉鎖筋を選択的に促通する際には、高負荷外旋運動よりも低負荷外旋運動の方が有用であると考える。 【倫理委員会の承認】 本研究は船橋整形外科病院倫理委員会の承認を得て行った。
2 0 0 0 OA 『マハーバーラタ』第13巻第1章の考察 ――運命と行為――
- 著者
- 中村 史
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.2, pp.828-822, 2011-03-20 (Released:2017-09-01)
2 0 0 0 OA カビ由来 ラクターゼについて
- 著者
- 後藤 真孝
- 出版者
- 日本酪農科学会
- 雑誌
- ミルクサイエンス (ISSN:13430289)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.3, pp.239-245, 2012 (Released:2014-03-15)
- 参考文献数
- 23
Lactose intolerant people in Asia are about 80% population. People with lactose intolerant do not produce enough of the lactase enzyme to break down lactose contained in milk and milk products. One method for prevention, reduction or improvement is lactase supplementation, and fungal lactase (β-galactosidase) is used generally. Characteristics of fungal lactase is stability at acidic pH. Acidic stability of three lactases produced by Aspergillus oryzae, Penicillium multicolor and Aspergillus niger are different. Lactase from A. niger is most stable among them, but low-reactivity at neutral pH. Amino acid sequence homology among three fungal lactases is more than 70%, but relation between lactase character and structure is unknown. In Japan, lactase for lactose intolerance is regulated as drug and it is hard to purchase generally. A. oryzae is known as ‘Koji’ used for japanese traditional fermented foods such as miso, syoyu and sake. For this reason, lactase produced by A. oryzae is thought to be safe. If lactase can be obtained like U.S. dietary supplement, it is expected that lactase supplementation will be known widely.
2 0 0 0 OA 競争志向型のマーケティング戦略
- 著者
- 中村 世名
- 出版者
- 日本マーケティング学会
- 雑誌
- マーケティングジャーナル (ISSN:03897265)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.1, pp.97-105, 2019-06-28 (Released:2019-06-28)
- 参考文献数
- 37
伝統的にマーケティング研究は競争を回避すべき対象と見なしてきた。しかし,激しく,素早い競争行動によって特徴づけられる今日の環境を踏まえると,競争が不回避であるという前提のもと,競合企業との競争に勝ち続けるために必要な要因を探究する新たなマーケティング研究が求められるであろう。本論は,そのような研究を「競争志向型のマーケティング戦略研究」と呼称し,競争志向型のマーケティング戦略研究が依拠すべきフレームワークを検討した。分野横断的なレビューの結果,オーストリア経済学をルーツとする競争ダイナミクス・ビューが競争志向型のマーケティング戦略論の依拠するフレームワークとしてふさわしいことが特定化された。また,今後の研究の方向性として,競争ダイナミクス・ビューの知見に(1)顧客との関係性,(2)流通業者との関係性,(3)ポートフォリオの視点を加えた研究を行うことによって,新たな示唆を提供できることが指摘された。
2 0 0 0 OA コーヒー豆のカビ汚染に及ぼす含有成分の影響について
- 著者
- 諸角 聖 和宇慶 朝昭 一言 広 小原 哲二郎
- 出版者
- 日本食品微生物学会
- 雑誌
- 食品と微生物 (ISSN:09108637)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.2, pp.80-87, 1985-08-20 (Released:2010-07-12)
- 参考文献数
- 23
生および焙煎コーヒー豆におけるカビの増殖および毒素産生の相違がいかなる原因によるものかを明らかにする目的で, コーヒー豆成分のカビに及ぼす影響を検討し, 以下の結論を得た.1) 蒸留水またはYES培地を用いて水分含量を50%に調整した生および焙煎コーヒー豆粉末にA. flavus, A. ochraeusなど6種のカビを接種し, 発育と毒素産生の有無を調べた. その結果, 生豆粉末においては全菌種が発育し, ochratoxin A産生もみられたのに対し, 焙煎豆粉末においてはYES培地を添加した条件でA. ochraceusの発育が認められたのみで, 他の菌の発育は全くみられなかった.2) 焙煎コーヒー豆成分中には抗カビ物質の存在が示唆されたため, その単離を試み, 活性物質本体としてカフェインを得た.3) カフェインはA. flavusおよびA. versicolorの発育をいずれも2.5mg/mlで, P. glabrumおよびC. cladosporioidesの発育を5.0mg/mlで, F. solaniの発育を10mg/mlで完全に阻止したのに対し, A. ochraceusの発育は10mg/mlの濃度においても阻止しなかった. また, カフェインは生豆中にも存在することから, そのカフェインを単離し焙煎豆由来カフェインと抗菌活性を比較したところ, 両者の活性に差は認められなかった.4) 生および焙煎豆からの温湯抽出画分についてカフェイン含有量および抗菌活性をそれぞれ比較した. その結果, 両画分中のカフェイン含有量に差が認められなかったにもかかわらず, 抗菌作用は焙煎豆由来画分のみに認められ, 生豆由来画分には全くみられなかった.5) この結果から, 生豆由来温湯抽出画分中にカフェインの抗菌作用を不活化する物質の存在が疑がわれたため, その物質の単離を試み, 最終的にクロロゲン酸を得た.6) クロロゲン酸はカフェイン2.5mgに対して15mg, 5.0mgに対して30mgと, カフェインの3倍のモル量で最も顕著にカフェインの抗菌作用を不活化した. このクロロゲン酸は生豆中でカフェインと複合体を形成して存在し, 焙煎によりその含有量が半減することから, カビが生豆において発育可能であるのに対して焙煎豆で発育できない理由が, 主として両者におけるクロロゲン酸含有量の差であることが明らかとなった.
2 0 0 0 OA 誤解しないBiFC法のすゝめ: 蛍光タンパク質を使ったタンパク質間相互作用イメージング
- 著者
- 藤井 雄太 児玉 豊
- 出版者
- 一般社団法人 植物化学調節学会
- 雑誌
- 植物の生長調節 (ISSN:13465406)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.1, pp.48-51, 2016 (Released:2017-02-15)
- 参考文献数
- 25
Protein-protein interaction plays a fundamental role to maintain biological process. Bimolecular fluorescence complementation (BiFC) assay is an imaging technique to visualize protein-protein interaction in living cells. BiFC assay is based on structural complementation between two non-fluorescent N-terminal and C-terminal fragments derived from a fluorescent protein. Over the past decade, BiFC assay has been widely used in plant science fields, due to its technical simplicity. However, designing appropriate control experiment is quite important for BiFC assay, because non-specific self-assembly of the non-fluorescent fragments induces background fluorescence, which may lead to misinterpretation of BiFC results. In this technical note, we describe information regarding fluorescent protein and BiFC assay in plants, and introduce “BiFC competition assay” as a control experiment.
2 0 0 0 OA 体罰と懲戒 ~その限界と判断基準~
- 著者
- 薬師丸 正二郎
- 出版者
- 学校法人立教女学院 立教女学院短期大学
- 雑誌
- 立教女学院短期大学紀要 (ISSN:0285080X)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, pp.157-167, 2009 (Released:2017-09-15)
2 0 0 0 OA 16-18世紀のヨーロッパへ伝わった日本の鍼灸
- 著者
- ミヒェル ヴォルフガング
- 出版者
- 社団法人 全日本鍼灸学会
- 雑誌
- 全日本鍼灸学会雑誌 (ISSN:02859955)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.2, pp.150-163, 2011 (Released:2011-08-11)
- 参考文献数
- 59
- 被引用文献数
- 1
現代では東洋医学と西洋医学を対立するものと見る研究者は少なくないが、 近世に遡ると、 互いに理解しにくいものに対する拒絶反応はあるものの、 有用と判断された医薬品や治療法は選択的に受容されていた。 16世紀中頃から東アジアに進出した西洋勢力に対し、 中国と朝鮮が反発の姿勢を見せる一方で、 日本はいわゆる 「鎖国政策」 以降も一定の交流を保ち続けた。 19世紀初頭まで 「東洋医学」 に関する情報の大半は中国からではなく、 長崎のオランダ商館を通じて西洋に伝わり、 中国の伝統医学のほか、 管鍼法、 打鍼法など日本独特のものも日中共有の治療法として紹介された。 鍼術と灸術の観察と受容は基本的に別々に進められた。 「火のボタン」 として16世紀に紹介された灸は、 1675年に刊行されたバタビアの牧師の著書により足痛風の治療薬Moxaとして注目され、 日本での研究成果も踏まえつつ、 西洋の医学界において本格的に議論されるようになった。 ケンペルが持ち帰った 「灸所鑑」 とその詳細な説明でさらに関心が高まり、 古代ギリシャやエジプトにも類似の治療法があったことから、 医術としての灸は比較的好意的に受容された。 灸術と同様に鍼術に関する最古の記述は日葡交流時代に遡るが、 ヨーロッパでの専門家による議論は、 出島商館医テン・ライネ博士が1682年に発表した論文集から始まる。 テン・ライネは鍼術を 「acupunctura」 と名づけ、 出島の阿蘭陀通詞に説明を受けた資料を紹介したが、 「気」、 「経絡」、 「陰陽」 などの理解に至らず読者を困惑させた。 その後商館医ケンペルが疝気を 「疝痛」 (colica) と見なし、 その治療法を詳細に記したが、 西洋の医学界で 「日本人と中国人は、 胃腸に溜ったガスを抜くために腹部に針を刺す」 という誤った解釈が広まり、 18世紀末までは来日した医師達も西洋の読者も、 鍼術に対する疑問を払拭できず、 有用性を認めることに極めて消極的だった。
2 0 0 0 OA アメリカの公民権法=1世紀にわたる理性の戦い
- 著者
- 久保田 きぬ子
- 出版者
- アメリカ学会
- 雑誌
- アメリカ研究 (ISSN:03872815)
- 巻号頁・発行日
- vol.1968, no.2, pp.161-172, 1968-03-20 (Released:2010-06-11)
- 参考文献数
- 24
2 0 0 0 OA 声かけなどの不審者遭遇情報と性犯罪の時空間的近接性の分析
- 著者
- 菊池 城治 雨宮 護 島田 貴仁 齊藤 知範 原田 豊
- 出版者
- 日本犯罪社会学会
- 雑誌
- 犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, pp.151-163, 2009-10-20 (Released:2017-03-30)
警察や一般市民の間で,声かけなどのいわゆる不審者遭遇情報は,より重篤な性犯罪などの前兆事案として捉えられているものの,実証的な研究はこれまでなされてきていない.本研究では,犯罪学における近接反復被害の分析手法を応用し,声かけなどの不審者遭遇情報とその後の性犯罪発生との時空間的近接性を検証する.A都道府県警察における3年間の不審者遭遇情報(1,396件)と屋外での性犯罪(599件)の認知データを地理情報システム(GIS)とシミュレーション手法を用いて時空間的に解析したところ,声かけなどの不審者遭遇情報と性犯罪は時間的にも空間的にも近接して発生していることが分かった.具体的には,声かけなどの不審者遭遇情報発生後,少なくとも1ヶ月にわたって発生地点から1kmの範囲において性犯罪の発生件数が有意に高いことが示された.この結果に基づいて,本研究の限界を踏まえつつ,実証データに基づく警察活動への考察を行う.
- 著者
- 利根川 佳子
- 出版者
- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- アフリカレポート (ISSN:09115552)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, pp.54-66, 2020-06-20 (Released:2020-06-20)
- 参考文献数
- 46
サハラ以南アフリカでは、NGOに対して規制的な法制度が2000年代以降制定されている。本稿では、エチオピアとケニアの二カ国を事例とし、NGOに関連する法規制の比較検討に基づき、NGOと政府の関係性と現在の市民社会スペースの状況を明らかにすることを目的とする。両国ともに、政権に影響があるような、人権やガバナンスなどに関連する活動を行うNGOの活動領域の縮小化を政府は試みているが、ケニアの場合はそのような活動を行うNGOをおもな対象としているのに対し、エチオピアの場合、2009年の「慈善団体および市民団体に関する布告」のもと、NGO全体が対象となったことが大きく異なる。さらに、エチオピアにおいては、国際NGOを含め国内で活動するNGO全体の活動領域が縮小化された一方で、ケニアにおいては、政府の規制的な対応にもかかわらず、NGOは人権やガバナンスに関連する活動を継続している現状がある。
2 0 0 0 OA Association between Traffic Count and Cardiovascular Mortality: A Prospective Cohort Study in Taiwan
- 著者
- Wen-Chi Pan Szu-Yu Yeh Chih-Da Wu Yen-Tsung Huang Yu-Cheng Chen Chien-Jen Chen Hwai-I Yang
- 出版者
- Japan Epidemiological Association
- 雑誌
- Journal of Epidemiology (ISSN:09175040)
- 巻号頁・発行日
- pp.JE20200082, (Released:2020-06-20)
- 参考文献数
- 45
- 被引用文献数
- 3
Background: Exposure to traffic-related pollution is positively associated with cardiovascular diseases (CVD), but little was known about how different sources of traffic pollution (e.g. gasoline-powered cars, diesel-engine vehicles) contribute to CVD. Therefore, we evaluated the association between exposure to different types of engine exhaust and CVD mortality.Methods: We recruited 12,098 participants from REVEAL-HBV cohort in Taiwan. The CVD mortality in 2000-2014 was ascertained by the Taiwan Death Certificates. Traffic pollution sources (2005-2013) were based on information provided by the Directorate General of Highway in 2005. Exposure to PM2.5 was based on a land-use regression model. We applied Cox proportional hazard models to assess the association of traffic vehicle exposure and CVD mortality. A causal mediation analysis was applied to evaluate the mediation effect of PM2.5 on the relationship between traffic and CVD mortality.Results: A total of 382 CVD mortalities were identified from 2000 to 2014. We found participants exposed to higher volumes of small car and truck exhausts had an increased CVD mortality. The adjusted hazard ratio (HR) was 1.10 for small cars (95% confidence interval [CI], 0.94-1.27; p-value=0.23) and 1.24 for truck (95% CI, 1.03-1.51; p-value=0.03) per one unit increment of the logarithm scale. The findings were still robust with further adjustment for different types of vehicles. A causal mediation analysis revealed PM2.5 had an over 60% mediation effect on traffic-CVD association.Conclusions: Exposure to truck exhaust or gasoline-powered cars is positively associated with CVD mortality, and air pollution may play a role in this association.
2 0 0 0 OA 軽量Rubyを用いた効率的な組込みソフトウェア開発コンポーネントベースフレームワーク
- 著者
- 山本 拓朗 大山 博司 安積 卓也
- 出版者
- 日本ソフトウェア科学会
- 雑誌
- コンピュータ ソフトウェア (ISSN:02896540)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.4, pp.4_3-4_16, 2017-10-25 (Released:2017-12-25)
The complexity and scale of embedded software have increased. To improve the productivity, the mruby on TOPPERS embedded component system (TECS) framework, which employs a scripting language (i.e., lightweight Ruby) and supports component-based development, has been proposed. In the current mruby on TECS framework, mruby programs must be compiled and linked every time they are modified, because mruby bytecode are incorporated in the platform. Moreover, while the framework supports multiple virtual machines (VMs), developers must be familiar with the functions of real-time operating systems to effectively execute multiple mruby programs concurrently or in parallel. This paper proposed an extended mruby on TECS framework that improves development efficiency more than the current framework. We implemented a Bluetooth loader receives an mruby bytecode, and a RiteVM scheduler simplifies multitasking. Synchronization of initializing multiple tasks is also implemented using an Eventflag. Experimental results demonstrate the advantages of the proposed framework.
2 0 0 0 OA 頭痛診療ツールとしての鍼灸技法の応用
- 著者
- 間中 信也
- 出版者
- 日本神経学会
- 雑誌
- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.11, pp.1299-1302, 2012 (Released:2012-11-29)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1 1 1
We use two oriental medical techniques in headache management. One is topological microstimulation, and the other is acupuncture point BL10 (Tianzhu) block. 1. Topological microstimulation The topological microstimulation apparatus delivers programmed fluctuating electrical signals to electrodes placed on the distal portion of the limbs, where meridians are concentrated. Topological microstimulation adjusts "qi-blood-fluid" circulating through meridians. "Qi-blood-fluid" is a virtual concept of oriental medicine that means 3 elements (qi, blood, and colorless body fluid). Topological microstimulation induces natural healing power through the bio-homeostatic function, and reduces chronic intractable pain. 2. Acupuncture point BL10 (Tianzhu) block Tianzhu as a meridian point is located at the intersection of the superior nuchal line of the occipital bone and lateral border of the trapezius. This site is located in the superficial layer of the trunk of the greater occipital nerve. Tianzhu block has therapeutic effects on the trigeminocervical complex. As a result, various types of headache are relieved. Tianzhu block was performed in 50 patients in our clinic, and marked effects were observed in 6 patients, moderate effects in 22, slight effects in 19, and no effects in 3. According to the type of headache, this block was effective in 47% of patients with tension-type headache, 38% of those with migraine, 50% of those with chronic daily headache, and 71% of those with neck and/or shoulder pain. Conclusion Various somatic and mental stresses induce headache and functional somatic syndrome, i.e., Tianzhu syndrome. Acupuncture is useful and can be actively recommended for the management of intractable headache such as complicated headache due to Tianzhu syndrome.
2 0 0 0 OA ラナルド・マクドナルドの「日英語彙集」
- 著者
- 河元 由美子
- 出版者
- 日本英学史学会
- 雑誌
- 英学史研究 (ISSN:03869490)
- 巻号頁・発行日
- vol.1998, no.30, pp.151-168, 1997 (Released:2010-05-07)
- 参考文献数
- 36
The Glossary of English and Japanese Words' written by Ranald MacDonald (1824 -1894) contains a few words peculiar to the dialects of Northeastern Japan and those of Kyushu. About the Kyushu dialect, there have been comments by numbers of scholars, however, about the Northeastern dialect, no one but Dr. Yoshio Yoshimachi, has ever suggested the existence of Northeastern dialect in the MacDonald's 'Glossary'.This paper attempts to find out some phonological regularities in descriptions in the vocabulary of the 'Glossary' and determine the words in questions whether they are dialectal words or not, referring to the phonological characteristics observed in both dialects at present.Regarding the fact that MacDonald had been captured in Ezo, the present Hokkaido, for almost 3 months before being sent to Nagasaki, he must have heard the Japanese language spoken in that area. His first Japanese informant, Tangaro, is likely to be a temporary employee of the guard house in Rishiri Island, then under the control of the Soya Headquaters of the Bakufu. The history of the Northern Japan tells that there were numbers of military people despatched from northern parts of Honshu to Ezo to defend the land and the people from the Russian intrusion; besides them, many fishermen and farmers also crossed the Tsugaru Straits seeking the temporary jobs. Tangaro must have been one of them.This paper includes on the result of the interview check with the native speakers of the two representative cities, Aomori and Nagasaki, in order to check if the people there accept or approve of the words in questions in the MacDonld's 'Glossary' as their dialects. Also, other Word Lists written by foreign scholars such as Thumberg, Curtius, Sansom are refered to, to observe how they describe the Japanese dialectal words in their works.
2 0 0 0 OA 東南アジアにおける陸上競技外国人ハイパフォーマンスコーチの信念
- 著者
- 水島 淳 前田 奎 広瀬 健一 大山卞 圭悟 尾縣 貢
- 出版者
- The Japan Journal of Coaching Studies
- 雑誌
- コーチング学研究 (ISSN:21851646)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.1, pp.71-78, 2018-10-20 (Released:2019-09-02)
- 参考文献数
- 21
The aim of this study was to investigate the coaching beliefs of foreign high-performance track and field coaches in South East Asian countries. Five foreign coaches from Germany, Portugal, and New Zealand who represented Malaysia and Singapore in track and field events at the South East Asian Games in 2017 were asked to participate and were interviewed in this study. For the purposes of this research, the factors believed most important for coaching from the coach’s perspective were asked. The results showed that the coaching beliefs of foreign high-performance track and field coaches in South East Asian countries were divided into 3 categories. These were (a) goal oriented: developing athletes’ competence and developing athletes’ character; (b) coaches’ knowledge oriented: professional knowledge, and interpersonal and intrapersonal knowledge; and (c) coaching context oriented: coaching context.
2 0 0 0 OA 利他性の推論に援助者・被援助者の性別が及ぼす影響
- 著者
- 河村 悠太 楠見 孝
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 巻号頁・発行日
- pp.3EV-018, 2015-09-22 (Released:2020-03-27)
2 0 0 0 OA 電波による地中・水中の探査
- 著者
- 鈴木 務
- 出版者
- 公益社団法人 計測自動制御学会
- 雑誌
- 計測と制御 (ISSN:04534662)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.8, pp.762-772, 1981-08-10 (Released:2009-11-26)
- 参考文献数
- 33
2 0 0 0 OA 紀州藩にみられる徴兵令の先駆
- 著者
- 梅渓 昇
- 出版者
- 日本英学史学会
- 雑誌
- 英学史研究 (ISSN:03869490)
- 巻号頁・発行日
- vol.1970, no.2, pp.28-35, 1970-09-30 (Released:2009-09-16)