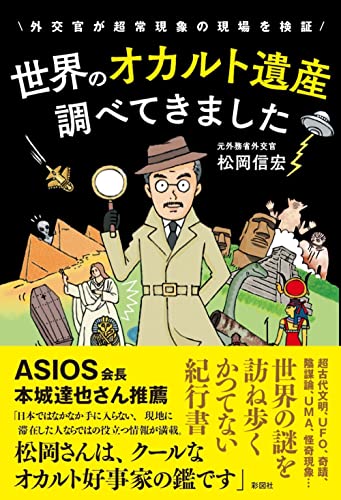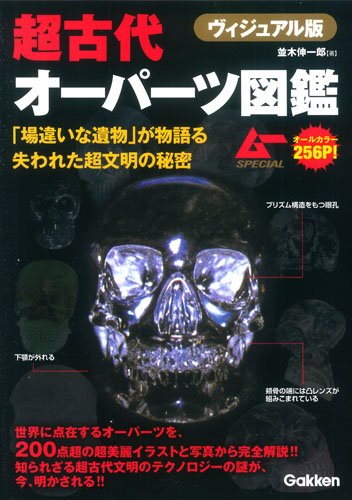- 著者
- 國重 智宏
- 出版者
- 一般社団法人 日本社会福祉学会
- 雑誌
- 社会福祉学 (ISSN:09110232)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.4, pp.30-40, 2019
<p>本研究は,長期入院精神障害者の退院支援場面における相談支援事業所の精神保健福祉士(PSW)の「かかわり」のプロセスについて明らかにすることを目的とする.A圏域の7名のPSWに対するインタビュー調査を実施し,修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチによる分析を行った.分析の結果,三つのカテゴリーからなる「かかわり」のプロセスを明らかにした.まずPSWは,退院支援という自らの業務をいったん横におき,長期入院精神障害者との〈お互いを知るための「つきあい」〉を通して,彼らに「人」として信用してもらう.次に彼らと〈パートナーとして認めあう関係〉を築き,退院という共通の目標に向けて協働する.最後に退院という目標がなくなり,援助関係が終結した後も,彼らと「人」として〈つながり続ける「かかわり」〉を築くに至っていた.</p>
4 0 0 0 OA 〈北陸の民俗・文化〉娼妓からみた近代日本の公娼制度――周旋業者・借金・梅毒
- 著者
- 人見 佐知子
- 出版者
- 近畿大学民俗学研究所
- 雑誌
- 民俗文化 (ISSN:09162461)
- 巻号頁・発行日
- no.34, pp.187-212, 2022-12-21
4 0 0 0 OA 曲水の宴
4 0 0 0 OA 一枚布の民族衣装
- 著者
- 井上 好 Inoue Yoshimi イノウエ ヨシミ
- 出版者
- 東京家政大学博物館
- 雑誌
- 東京家政大学博物館紀要 (ISSN:13433709)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.77-98, 2006
4 0 0 0 IR 江戸時代文献「うつろ船の蛮女」に描かれている「宇宙文字」の正体
- 著者
- 皆神 龍太郎
- 雑誌
- 文化科学研究 = cultural sciences
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.(1)-(8), 2014-03-15
- 著者
- 松倉 聡史 三戸 尚史
- 雑誌
- 名寄市立大学社会福祉学科研究紀要 (ISSN:21869669)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.13-29, 2018-12-28
社会福祉学を学ぶ学生にとって、しかも教職課程で高校公民の免許取得を目指す学生にとって、社会権の意義及び生存権の法的性格を学ぶことは福祉国家における人権思想の基礎を築くことになろう。憲法の生存権規定がどのような性格であるのかが真正面から争われたのが、朝日訴訟と呼ばれる事件である。朝日訴訟最高裁判決では、朝日茂の死亡によって生活保護受給権の一身専属性を理由に訴訟継承しうる余地はなしとし、その後の「なお、念のため・・・当裁判所意見を付加する」とする傍論ではプログラム規程説とされる見解が示されている。最高裁判決50周年を迎え、朝日訴訟の先例的な意義への注目度は薄くなっているかもしれない。しかしながら、朝日訴訟の「人間裁判」としての「人間に値する生存」を朝日茂の手記から考察し、防衛費予算に占める社会保障費の減少、生活保護世帯の増加等、当時と酷似する現代的意義を「朝日訴訟運動史」から考察する。
4 0 0 0 OA 反芻家畜の栄養の特異性
- 著者
- 安保 佳一
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.3, pp.149-158, 1979-03-25 (Released:2009-05-25)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1 1
- 著者
- 新藤 透
- 出版者
- 十六世紀史論叢刊行会
- 雑誌
- 十六世紀史論叢 (ISSN:21878609)
- 巻号頁・発行日
- no.8, pp.59-72, 2017-03
- 著者
- 黒川 京子
- 出版者
- 日本社会事業大学
- 雑誌
- 日本社会事業大学研究紀要 = Study report of Japan College of Social Work : issues in social work (ISSN:0916765X)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, pp.57-65, 2018-03
本学には、日本患者同盟から本学図書館に寄贈され、膨大な時間をかけ手作業で整理・分類され、マイクロフィルムとして保管されている患者同盟の資料(朝日訴訟を含む)がある。また、本学の授業にゲスト講師としてしばしばお越しくださった朝日健二氏(朝日訴訟の原告である朝日茂氏の養子となって訴訟を継承した方。2015 年にご逝去)と親しく交流させていただく中で、朝日訴訟を次世代に伝えたいとの強い思いを知った。氏の思いを引き継いでいくにあたり、朝日訴訟を語りつぐのみならず、本学所蔵の貴重な資料を専門職としての力量形成に活かすことを模索している。そのプロセスとしての報告となる。
4 0 0 0 OA 地下鉄サリン事件被害者の後遺症状について
- 著者
- 石松 伸一
- 出版者
- 日本毒性学会
- 雑誌
- 日本トキシコロジー学会学術年会 第38回日本トキシコロジー学会学術年会
- 巻号頁・発行日
- pp.193, 2011 (Released:2011-08-11)
【はじめに】1995年3月20日朝、発生した地下鉄サリン事件では死者13名、傷病者6000名を超えるテロ事件であった。当院では当日だけで640名、その後1週間で1200名以上の傷病者が来院した。初期に見られた中毒症状も次第に軽減し、消失するものと思われたが、1年以上を経過しても症状の残存する事例を多数経験したので、継続的に症状の追跡調査を開始した。 【方法】事件後5年間は、当院を初診した被害者にアンケート用紙を郵送して記入後返信してもらった。6年以降は同様に被害者のケアを行なっていたNPO法人リカバリーサポートセンター(RSC)とともに調査を行ない、希望者には検診を実施した。症状アンケートは事件後、被害者の訴えの多かった33種類の症状について重症度を1〜5までのリカートスケールを用いた。なお重症度の3〜5と回答したものを「症状あり」とした。 【結果】後遺症と認定されている眼症状、PTSDをはじめとする精神症状以外での身体症状では、「体がだるい」1年後7.3%、5年後16.0%、10年後43.4%、「体が疲れやすい」は1年後11.9%、5年後23.1%、10年後56.3%、「頭痛」は1年後8.6%、5年後12.5%、10年後44.7%、「下痢をしやすい」は1年後1.0%、5年後11.9%、10年後18.6%。なお、アンケート調査開始時には項目になかった症状のうち「手足のしびれ」は13年後の時点で49.8%と実に半数近くが症状を訴えていた。また受傷時未成年であった被害者への小児科による追跡調査では身体症状は遅発的に発生しており、精神健康度、不安尺度ともに正常域であった。 【考察】多くの身体症状で経年的に訴える頻度が増加していたことは、年齢の変化以外にアンケート回答者の特異性などの因子も関連していると思われるが、有機リン系毒物の遅発的障害に関しても否定できない。
4 0 0 0 IR 広義化した「オタク」の整理 : オタクファッションを考察するために
- 著者
- 松下 戦具
- 出版者
- 大阪樟蔭女子大学
- 雑誌
- 大阪樟蔭女子大学研究紀要 = Research Bulletin of Osaka Shoin Women's University (ISSN:24322458)
- 巻号頁・発行日
- no.9, pp.237-242, 2019-01-31
4 0 0 0 超古代オーパーツ図鑑 : ヴィジュアル版
- 著者
- 並木伸一郎著
- 出版者
- 学研マーケティング (発売)
- 巻号頁・発行日
- 2014
4 0 0 0 OA 占領下の歌舞伎弾圧と解除の経緯 ――父繁俊のGHQとの交渉手記――
- 著者
- 河竹 登志夫
- 出版者
- 日本演劇学会
- 雑誌
- 演劇学論集 日本演劇学会紀要 (ISSN:13482815)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, pp.241-254, 2005-10-01 (Released:2018-12-14)
4 0 0 0 OA Tietze症候群:リウマチ性疾患と鑑別が必要な骨格症
- 著者
- 中村 正
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床リウマチ学会
- 雑誌
- 臨床リウマチ (ISSN:09148760)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.4, pp.260-268, 2020 (Released:2021-02-18)
- 参考文献数
- 46
胸痛はありふれた症候で,いわゆるTietze領域に痛みを指で指し示すことができる範囲に腫脹と圧痛を認めればTietze症候群を疑う.一般に,第2・3胸肋関節や肋軟骨あるいは胸鎖関節などの領域に限局した疼痛と腫脹を伴う良性疾患の非化膿性病態で,原因は不明である.同部位の圧痛を来たす疾患の一群に,関節リウマチ,強直性脊椎炎,反応性関節炎,乾癬性関節炎などの脊椎関節炎,SAPHO症候群などのリウマチ性疾患がある.現状ではTietze症候群は独立した疾患とは考えにくく,ある種の全身性疾患や局所性疾患の異質な病態のひとつであるか,または特定の疾患の進行過程の一変化である可能性が高い.従って,リウマチ性疾患に関連したTietze症候群様病態への注意深い検討が望まれる.さらに,これらのリウマチ性疾患の炎症病態における標的分子が明らかになりつつあり,Tietze症候群の治療において分子標的薬の治療選択肢が広がる可能性がある.リウマチ性疾患を鑑別診断する過程でTietze症候群の再認識が求められ,今後の更なる症例集積や病態生理の解明が期待される.
4 0 0 0 イタリアにおける視覚障害教育に関わる触覚教材への対応
4 0 0 0 OA 五島列島の潜伏キリシタン墓の研究 : 旧木の口墓所調査その2
- 著者
- 加藤 久雄 野村 俊之 白濱 聖子 藤本 新之介
- 出版者
- 長崎ウエスレヤン大学
- 雑誌
- 長崎ウエスレヤン大学地域総合研究所研究紀要 (ISSN:13481150)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.71-83, 2015-03-31
- 著者
- 川口 真実 / 行實 志都子
- 出版者
- 日本福祉大学社会福祉学部
- 雑誌
- 日本福祉大学社会福祉論集 = Journal social Welfare, Nihon Fukushi University (ISSN:1345174X)
- 巻号頁・発行日
- no.141, pp.83-94, 2019-09-30
本研究は,神奈川県における医療と介護に携わる福祉専門職がもつ連携に対する意識を明らかにすることを目的とした.また,本研究の仮説は,福祉専門職はそれぞれの職場が違っても,地域共生社会を支えるための連携に関する共通認識があるとした. 医療と介護の連携における具体的な共通課題として,「自分たちに求められる力」,「連携を見据えた研修体制の構築」の2つが明らかとなった.しかし,それぞれの専門職間において,"連携"に対する促え方の違いもみられた.この課題を解決するためにも「連携を見据えた研修体制の構築」が必要である.だが一方では,職場の事情により研修に参加したくても参加できないことや,「支援の縦割りの弊害」から自分の支援範囲以外に対する関心の低さが目立った.ただ連携に関する研修を整備するだけでは解決には至らない.連携には何がいるのか,自分はその中で何をするのかということをしっかりと理解し,行動に移すことができるようになる研修が必要である.
4 0 0 0 OA 党首選出における日英比較 : なぜ英国の首相は若いのか
- 著者
- 山田 真裕 坂本 元来 Masahiro Yamada Genki Sakamoto
- 雑誌
- 法と政治 (ISSN:02880709)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.4, pp.163(761)-204(802), 2011-01-20