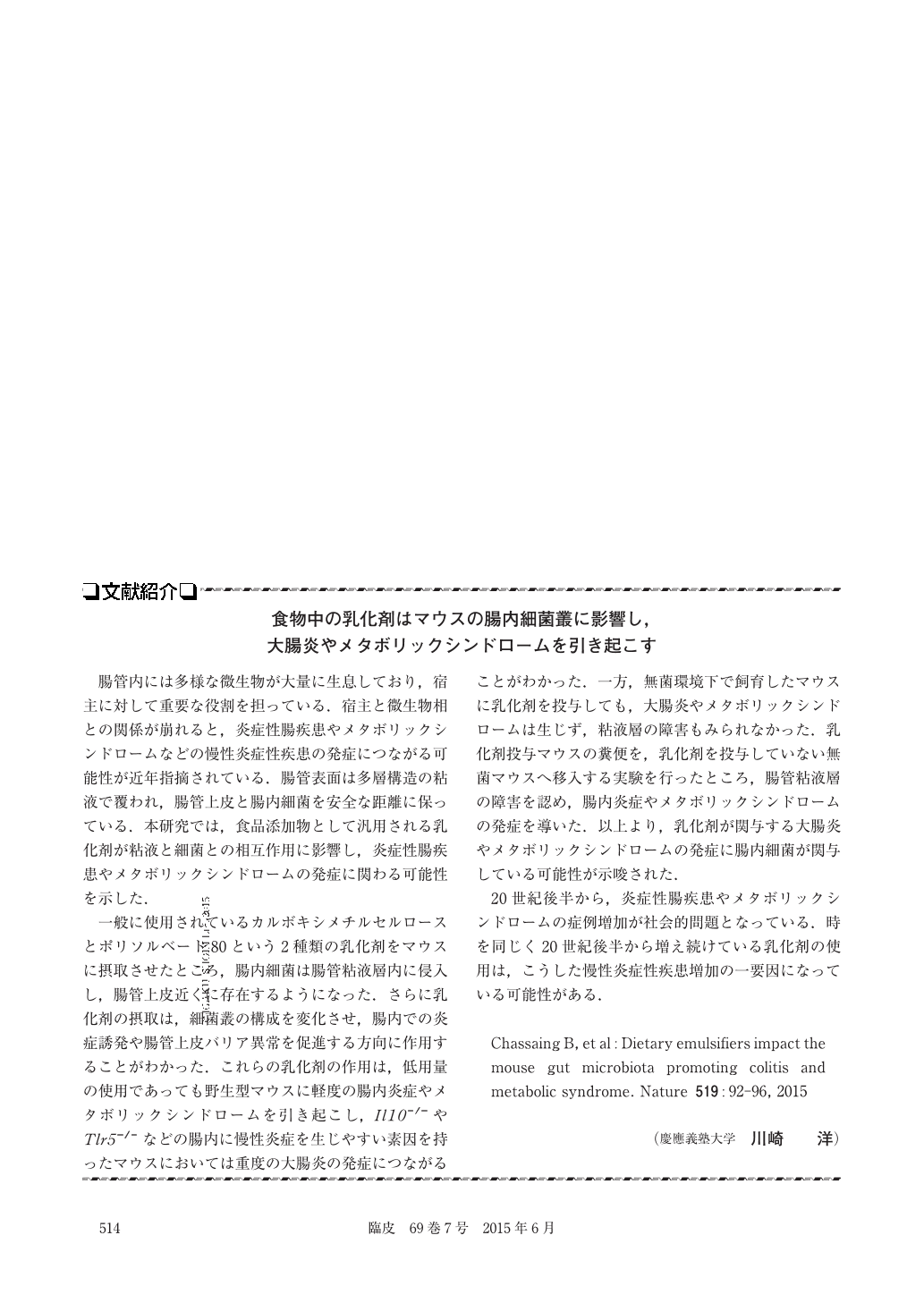腸管内には多様な微生物が大量に生息しており,宿主に対して重要な役割を担っている.宿主と微生物相との関係が崩れると,炎症性腸疾患やメタボリックシンドロームなどの慢性炎症性疾患の発症につながる可能性が近年指摘されている.腸管表面は多層構造の粘液で覆われ,腸管上皮と腸内細菌を安全な距離に保っている.本研究では,食品添加物として汎用される乳化剤が粘液と細菌との相互作用に影響し,炎症性腸疾患やメタボリックシンドロームの発症に関わる可能性を示した. 一般に使用されているカルボキシメチルセルロースとポリソルベート80という2種類の乳化剤をマウスに摂取させたところ,腸内細菌は腸管粘液層内に侵入し,腸管上皮近くに存在するようになった.さらに乳化剤の摂取は,細菌叢の構成を変化させ,腸内での炎症誘発や腸管上皮バリア異常を促進する方向に作用することがわかった.これらの乳化剤の作用は,低用量の使用であっても野生型マウスに軽度の腸内炎症やメタボリックシンドロームを引き起こし,Il10-/-やTlr5-/-などの腸内に慢性炎症を生じやすい素因を持ったマウスにおいては重度の大腸炎の発症につながることがわかった.一方,無菌環境下で飼育したマウスに乳化剤を投与しても,大腸炎やメタボリックシンドロームは生じず,粘液層の障害もみられなかった.乳化剤投与マウスの糞便を,乳化剤を投与していない無菌マウスへ移入する実験を行ったところ,腸管粘液層の障害を認め,腸内炎症やメタボリックシンドロームの発症を導いた.以上より,乳化剤が関与する大腸炎やメタボリックシンドロームの発症に腸内細菌が関与している可能性が示唆された.
4 0 0 0 着氷性降水の気候学的特徴と地域性について
- 著者
- 松下 拓樹 西尾 文彦
- 出版者
- The Japanese Society of Snow and Ice
- 雑誌
- 雪氷 (ISSN:03731006)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.5, pp.541-552, 2004-09-15
- 被引用文献数
- 1 5
過去14冬季間(1989年11月~2003年5月)における気象庁の地上気象観測資料から,着氷性の雨,着氷性の霧雨,凍雨の発生に関する地域分布と,季節変化および経年変化を調べた.日本では,これらの降水種は1月から3月の時期に発生することが多く,毎年10回程度の割合で観測されている.このうち着氷性の雨の発生率は毎年数回程度で,12月~1月に発生する場合が多い.<BR>着氷性の雨と凍雨の発生率が高いのは,中部地方以北の内陸山間部と関東地方以北の太平洋側平野部である.この両地域に着目して,着氷性の雨や凍雨が発生するときの気象条件の形成過程を調べたところ,地上付近の寒気層の形成は,局地的な気象現象や地形の影響を強く受けることがわかった.内陸山間部では盆地地形による冷気湖の形成が関与しており,太平洋側平野部では内陸からの寒気流出によって地上付近の寒気層が形成される.一方,上空暖気層の形成は,総観規模の気圧配置に伴う暖気移流に起因する.
4 0 0 0 OA ハンネス・マイヤーの建築思想と独ソ建築界(1926-1930年)
4 0 0 0 IR 思春期の心性に関する研究 : 親から友人へと変化していく関係性に焦点を当てて
- 著者
- 西尾 祐美子
- 出版者
- 神戸大学
- 雑誌
- 神戸大学発達・臨床心理学研究
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.29-35, 2015-03-31
- 著者
- Hirotoshi Watanabe Takeshi Morimoto Ko Yamamoto Yuki Obayashi Masahiro Natsuaki Kyohei Yamaji Manabu Ogita Satoru Suwa Tsuyoshi Isawa Takenori Domei Kenji Ando Shojiro Tatsushima Hiroki Watanabe Masanobu Oya Kazushige Kadota Hideo Tokuyama Tomohisa Tada Hiroki Sakamoto Hiroyoshi Mori Hiroshi Suzuki Tenjin Nishikura Kohei Wakabayashi Takeshi Kimura for the STOPDAPT-2 ACS Investigators
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- pp.CJ-22-0650, (Released:2022-12-08)
- 参考文献数
- 28
Background: The REAL-CAD trial, reported in 2017, demonstrated a significant reduction in cardiovascular events with high-intensity statins in patients with chronic coronary syndrome. However, data are scarce on the use of high-intensity statins in Japanese patients with acute coronary syndrome (ACS).Methods and Results: In STOPDAPT-2 ACS, which exclusively enrolled ACS patients between March 2018 and June 2020, 1,321 (44.2%) patients received high-intensity statins at discharge, whereas of the remaining 1,667 patients, 96.0% were treated with low-dose statins. High-intensity statins were defined as the maximum approved doses of strong statins in Japan. The incidence of the cardiovascular composite endpoint (cardiovascular death, myocardial infarction, definite stent thrombosis, stroke) was significantly lower in patients with than without high-intensity statins (1.44% vs. 2.69% [log-rank P=0.025]; adjusted hazard ratio [aHR] 0.48, 95% confidence interval [CI] 0.24–0.94, P=0.03) and the effect was evident beyond 60 days after the index percutaneous coronary intervention (log-rank P=0.01; aHR 0.38, 95% CI 0.17–0.86, P=0.02). As for the bleeding endpoint, there was no significant difference between the 2 groups (0.99% vs. 0.73% [log-rank P=0.43]; aHR 0.96, 95% CI 0.35–2.60, P=0.93).Conclusions: The prevalence of high-intensity statins has increased substantially in Japan. The use of the higher doses of statins in ACS patients recommended in the guidelines was associated with a significantly lower risk of the primary cardiovascular composite endpoint compared with lower-dose statins.
4 0 0 0 OA 「英語教育実施状況調査」の経年的研究
- 著者
- 津村 敏雄
- 出版者
- 東洋学園大学
- 雑誌
- 東洋学園大学紀要 = Bulletin of Toyo Gakuen University (ISSN:09196110)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, pp.142-163, 2020-02-28
文部科学省は,平成25年度から全国の公立の小学校・中学校・高等学校(義務教育学校・中等教育学校を含む)を対象として「英語教育実施状況調査」を実施している。調査は毎年12月に行われて結果は翌年度の春に公表されている。平成30年度の主な調査項目は,小学校における英語担当者の現状,生徒(中学生・高校生)の英語力,生徒の英語による言語活動の状況,パフォーマンステストの実施状況,「CAN-DOリスト」による学習到達目標の設定等の状況,英語担当教師の英語使用状況,英語教師の英語力,ALT等及びICT 機器の活用状況,小学校と中学校の連携に関する状況となっているが,過年度の調査項目には,共通しているもの,加減されているもの,単発で行われているものがある。本稿では,ほぼ毎回共通している項目として,生徒(中学生・高校生)の英語力,英語教師の英語力,「CAN-DOリスト」による学習到達目標の設定等の状況,ALT等及びICT機器の活用状況を取り上げて,過去6年間の経年変化の考察を行った。その結果,大半の項目で全国平均においては概ね良好な傾向にあるものの,都道府県や政令指定都市の地方自治体によるばらつきがあることなど,今後さらに改善していく必要性があるということが明らかになった。
4 0 0 0 OA 〈北陸の民俗・文化〉越前国東郷槙山城の歴史と構造
- 著者
- 新谷 和之
- 出版者
- 近畿大学民俗学研究所
- 雑誌
- 民俗文化 (ISSN:09162461)
- 巻号頁・発行日
- no.34, pp.173-186, 2022-12-21
4 0 0 0 OA 石川淳未発表原稿「華厳」「しぐれ歌仙」続稿・翻刻と解説 ― 世田谷文学館所蔵資料より
- 著者
- 小池 智子 山口 俊雄
- 出版者
- 日本女子大学
- 雑誌
- 日本女子大学大学院文学研究科紀要 = Journal of the Graduate School of Humanities (ISSN:13412361)
- 巻号頁・発行日
- no.28, pp.1-16, 2022-03-15
- 著者
- Hayato Tada Hirofumi Okada Atsushi Nohara Ryuji Toh Amane Harada Katsuhiro Murakami Takuya Iino Manabu Nagao Tatsuro Ishida Ken-ichi Hirata Masayuki Takamura Masa-aki Kawashiri
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- pp.CJ-22-0560, (Released:2022-11-26)
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 4
Background: Recently, the function of high-density lipoprotein (HDL), rather than the HDL cholesterol (HDL-C) level, has been attracting more attention in risk prediction for coronary artery disease (CAD).Methods and Results: Patients with clinically diagnosed familial hypercholesterolemia (FH; n=108; male/female, 51/57) were assessed cross-sectionally. Serum cholesterol uptake capacity (CUC) levels were determined using our original cell-free assay. Linear regression was used to determine associations between CUC and clinical variables, including low-density lipoprotein cholesterol and the carotid plaque score. Multivariable logistic regression analysis was used to test factors associated with the presence of CAD. Among the 108 FH patients, 30 had CAD. CUC levels were significantly lower among patients with than without CAD (median [interquartile range] 119 [92–139] vs. 142 [121–165] arbitrary units [AU]; P=0.0004). In addition, CUC was significantly lower in patients with Achilles tendon thickness ≥9.0 mm than in those without Achilles tendon thickening (133 [110–157] vs. 142 [123–174] AU; P=0.047). Serum CUC levels were negatively correlated with the carotid plaque score (Spearman’s r=0.37; P=0.00018). Serum CUC levels were significantly associated with CAD, after adjusting for other clinical variables (odds ratio=0.86, 95% CI=0.76–0.96, P=0.033), whereas HDL-C was not.Conclusions: HDL function, assessed by serum CUC level, rather than HDL-C level, adds risk stratification information among FH patients.
4 0 0 0 OA Faa di Brunoの公式とその応用(1)
- 著者
- 岡野 節 奥戸 雄二 清水 昭信 新倉 保夫 橋本 佳明 山田 浩
- 雑誌
- Annual review (ISSN:13429329)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.35-44, 2001-03
Faa di Brunoの公式を証明し,組み合わせ論とHermite多項式へのその応用を議論する.
4 0 0 0 OA 作業療法の独自性と可能性
- 著者
- 柴田 克之
- 出版者
- 一般社団法人 日本作業療法士協会
- 雑誌
- 作業療法 (ISSN:02894920)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.1, pp.7-12, 2022-02-15 (Released:2022-02-15)
- 参考文献数
- 7
本稿は,筆者が教育と臨床場面の経験から感じていることを踏まえて,以下の4つの事項についてまとめたものである.内容は,1)作業療法の独自性と専門性,2)作業療法の臨床力と技術力の向上,3)作業療法の学術発展,4)最後にこれまで培ってきた作業療法の強みと魅力を医療・福祉領域で発揮するための取り組みと可能性についてである.
4 0 0 0 OA 個体化における他者と世界の問題
- 著者
- 垂谷 茂弘
- 出版者
- 宗教哲学会
- 雑誌
- 宗教哲学研究 (ISSN:02897105)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.78-95, 1988 (Released:2018-03-15)
The “individuation” is the process of breaking away from “participation mystique.” The participation mystique is based on “identity,” an a priori oneness of subject and object, which can be thought of as the ‘unconscious’ itself. The process of individuation is, finally, the separation of subject from object. Then the problem is whether the identity between subject and object disappears when one realizes his whole personality (the self). Jung himself thinks we cannot become conscious of the entire unconsious. So, the identity must remain even in self-realization. We can sublate (aufheben) the inner and outer worlds only through symbolism. Even then we must preserve the distinction between them. However, there ought to be something fundamental that underlies the two worlds. Then the suspicion will arise that symbolism, especially that pertaining to synchronicity, is a movement back to the participation mystique. I try to prove the individuation is not the work of a single individual, but the dialectical cooperative work of the consciousnesses and the unconscious of “I and thou.” The foundation of this work is the identity, which in clinical psychology is treated as the problem of transference. In chapter 2, I investigate the union of the self and the “unus mundus,” following Jung’s final line of thought with regard to the question of the identity. I demonstrate, however, that Jung wouldn’t go beyond the psychological framework. Thus, I find the foundation of Jung’s thought in the concept of “numinous” experience and the “world-creating significance of the consciousness”.
- 著者
- 林 眞帆 織原 保尚 日和 恭世
- 出版者
- 別府大学会
- 雑誌
- 別府大学紀要 = Memoirs of Beppu University (ISSN:02864983)
- 巻号頁・発行日
- no.61, pp.59-74, 2020-02
近年、医療における意思決定支援への議論は活発化している。ただし、判断能力の不十分な人を対象とする意思決定支援の議論は深まっているとは言い難い。とりわけ、実践の根拠となる成年後見制度の抱える課題は医療ソーシャルワーカーにも少なからず影響している。そこで、本稿は医療ソーシャルワーカーへのアンケート調査の結果を踏まえ、成年後見制度から弾かれている医療選択と同意という課題に対する医療ソーシャルワークの役割について検討した。
4 0 0 0 OA 山川の神々(三) : 「山海経」の研究
- 著者
- 伊藤 清司
- 出版者
- 慶應義塾大学
- 雑誌
- 史学 (ISSN:03869334)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.2, pp.163-212, 1969-11
山川の鬼神・妖怪の属性とその棲み処を記述した山経は、山林薮藪沢に立ちいる者にとつて、怪物の害を避けるうえの手引きとなつたであろうし、これはまた、崇り・揃禍いする山川の神々の正体を判別して、それに宥恕を請い、あるいは、それを撃攘しようとする者にとつて、有効なる書でもあつたであろう。しかし、圧倒的な勢威をもつて君臨し、人々の幸不幸を支配したのが岳神であつた。山経はそれら岳神の祭祀方法について具体的に記録した書でもあつた。山経は好んで怪力乱神を語るものでは、もちろんなかつたのである。人倫関係の改善や社会秩序の確立によつて、世の平和と人々の幸福を期待しうると主張する者にとつて、山川に棲む神々は敬して遠ざくべきものであり、あるいは、否定すべきものですらあつた。しかし、山川に出没する妖怪の存在を信じておびえ、去来する鬼神の怒りに恐怖する人々は、変わることなく多かつた。已然として人々は、雲を湧出する峰々に神霊の存在を観じ、「山川ノ神ハ則チ水旱癘疫ノ災」をくだし、おるいはまた、「能ク百里ヲ潤ス」恩沢を賜うものと信じていた。山川の超自然的存在がこの世の禍福を左右するものと信じる社会にとつて、その超自然的存在について誌した山経は、決して、虚誕の書ではなかつたのである。山経は古代中国の邑里にくらす人々の伝来の民間信仰と、それらにかかわる日々のなりわいの苦悩とをふまえ、これに対処せんとする者-おそらくは、巫祝たちの儀礼の書としての一面をもつものである。山経はたしかに一つの実用の書であつた。 「漢書」芸文志によれば、かつて 禎祥変怪 二十一巻 人鬼精物六畜変怪 二十一巻 変怪誥咎 十三巻 執不祥劾鬼物 八巻 請宿除妖祥 十九巻 禳祀天文 十八巻 請〓致福 十九巻 請雨止雨 二十八巻の諸書が存していたという。今日、これらの古書の具体的な内容は知るべくもないが、「禎祥変怪 二十一巻」・「人鬼精物六畜変怪 二十一巻」等は、その名から想像して、山経の記録している百物・怪力乱神の類が含まれていたであろうし、「執不祥劾鬼物 八巻」・「請官除妖祥 十九巻」等には、これらの魑魅罔両・神姦を除祓するための儀礼・呪術が説かれていたとみられ、「請雨止雨 二十八巻」には、「現ワルレバ則チ大雨・現ワルレバ則チ大旱」を致す水神・旱鬼を宥和・祓除する呪術が記されていたとみられる。すなわち、これら一群の佚書の中には、山経の妖怪・百物の神々等に関する記述につながるものがあり、あるいは、その奥義書Upanisad的なものともいうべき書が含まれていると想像されるのである。他方、山経の岳神祭祀に関する記載自体は、どぢらかというと、礼書的体裁を帯びている。これらの点から、山経は「周礼」春官にみられる職掌に該当するもの、おそらくは祝史らの管轄するところではなかつたかと想像されるのであるが、山経と祝史・巫祝との関係については、稿を改めて考えることとする。
- 著者
- ジョン ビョル 大富 潤 本村 浩之
- 出版者
- 一般社団法人 日本魚類学会
- 雑誌
- 魚類学雑誌 (ISSN:00215090)
- 巻号頁・発行日
- pp.22-018, (Released:2023-03-08)
- 参考文献数
- 25
Four specimens (390.5–576.0 mm standard length; SL) of Etelis boweni Andrews, Fernandez-Silva, Randall and Ho, 2021 (Perciformes: Lutjanidae), collected from the Osumi Islands, Kagoshima Prefecture, Japan, were similar to Etelis carbunculus Cuvier, 1828 in sharing the following characters: dorsal fin with a deep notch and lacking scales; maxilla covered with scales; caudal-fin lower lobe whitish; and length of caudal-fin upper lobe greater than 3.3 in SL. However, the specimens differed from E. carbunculus in having the opercular spine posterior end rounded (pointed in the latter), 14 scale rows below the lateral line (vs. 12), and tip of the caudal-fin upper lobe black in both fresh and preserved specimens (vs. reddish in fresh specimens, yellowish in preserved specimens). Furthermore, a sequence analysis of the mitochondrial cytochrome oxidase I gene of the four Osumi Islands’ specimens showed a divergence of only 0.0–0.5% from the holotype of E. boweni, the five specimens comprising a clade separated by 7.5–8.8% sequence divergence from E. carbunculus. Although E. boweni is widely distributed in the IndoWest Pacific (from the Red Sea and Seychelles to Samoa), the Osumi Islands’ specimens (for which the standard Japanese name “Oo-akamutsu” is newly proposed) represent the first specimen-based records of Etelis boweni from Japanese waters as well as from the northwestern Pacific Ocean. Additionally, the apparently sympatric occurrence of E. boweni and E. carbunculus was evidenced by the collection together of the two species (KAUM–I. 160343, 390.5 mm SL and KAUM–I. 160342, 407.9 mm SL, respectively).
4 0 0 0 OA 生き物を殺して食べる マタギの生業と動物の権利
- 著者
- 竹之内 裕文
- 出版者
- 東北哲学会
- 雑誌
- 東北哲学会年報 (ISSN:09139354)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, pp.95-117, 2021 (Released:2022-03-04)
- 著者
- 井面 信行
- 出版者
- 近畿大学文芸学部
- 雑誌
- 文学・芸術・文化 : 近畿大学文芸学部論集 = Bulletin of the School of Literature, Arts and Cultural Studies, Kinki University (ISSN:13445146)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.1, pp.1-29, 2013-09-01
目次 序 一, 模倣理論と図像解釈 1. 模倣理論--指示作用 2. イコノロジー--図像解釈 ニ, イコン的転回--構造分析とイコニック 1. 「イコン的転回」の源泉としてのフィードラーの芸術理論 2. 構造分析--ゼーデルマイヤの「層モデル」 3. 構造分析の「イコン的転回」の意味とその批判 4. イコニック Ikonik --イムダールの「イコン的転回」 結び
4 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1890年07月10日, 1890-07-10
4 0 0 0 OA 植物の発熱現象と植物ホルモン(<特集>植物の環境適応と植物ホルモン)
- 著者
- 伊藤 菊一
- 出版者
- 一般社団法人植物化学調節学会
- 雑誌
- 植物の生長調節 (ISSN:13465406)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.2, pp.167-173, 2004-12-20 (Released:2017-09-29)