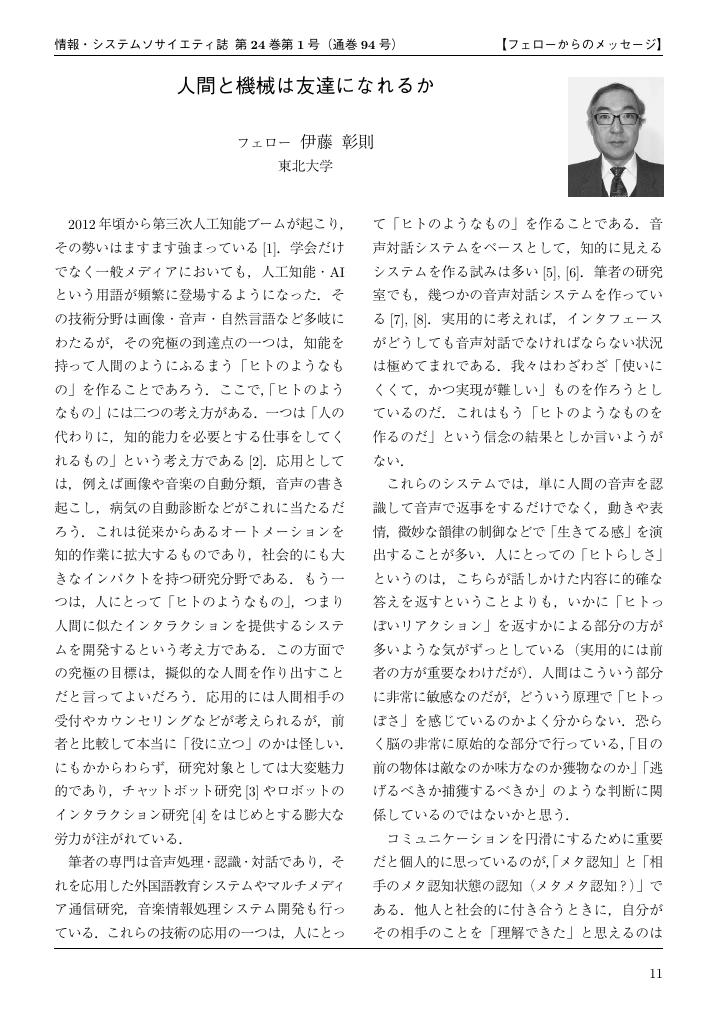4 0 0 0 IR 精神障害者の生活支援支援システム構築に関する試論
- 著者
- 松浦 智和
- 出版者
- 名寄市立大学
- 雑誌
- 地域と住民 : 道北地域研究所年報 (ISSN:02884917)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, pp.1-9, 2016-03-31
4 0 0 0 筋萎縮や筋損傷など骨格筋に対する鍼治療の基礎的研究
- 著者
- 池宗 佐知子 鈴木 茂久 高岡 裕 宮本 俊和
- 出版者
- 文光堂
- 雑誌
- 臨床スポーツ医学 = The journal of clinical sports medicine (ISSN:02893339)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.6, pp.599-605, 2010-06-01
- 被引用文献数
- 1
4 0 0 0 OA マルクス主義文学闘争
本稿は、両大戦間期以降の科学・技術に関する諸言説を文化的・社会的文脈に即して分析する作業を通じて、戦後日本社会におけるナショナル・アイデンティティのあり方について考察することを主な目的としている。日本社会には歴史的にみて、いくつかの特徴的ともいえる科学・技術をめぐる言説が流布されてきた。古くは明治期以来の「和魂洋才」から、近年の「メイド.イン.ジャパン」まで、科学・技術をめぐる言説は時代の推移とともに変遷を遂げてきた。そしてこれらの言説は、ある時は直接的に、またある時は間接的に、「日本文化」や「日本人」の枠組みを描き出してきたと考える。また同様に、日本という国家や「日本人」にとっての他者に対する認識や表象のあり方にも、科学・技術を軸にして揺れ動いてきた面がある。科学・技術をめぐる言説を詳細に検討することを通じて、戦後日本社会においてナショナル・アイデンティティがどのように構成されてきたのかを明らかにしたい。 その際に課題の一つとしたいのが、科学・技術をめぐる言説に戦中期と戦後を通じて保たれている、連続性に焦点を当てることである。科学・技術についての様々な議論が活発化したのは、総力戦体制へと向かうなかで科学・技術振興の重要性が認識されてきた時からだった。この時期には、科学者や技術官僚を中心にして、科学・技術の「日本的性格」をいかに確立するかについて、盛んに意見が戦わされた。これらの議論の多くは、「日本精神」と呼ばれるような精神性や道徳性に依拠していたために、戦後においてはほとんど省みられることがなかった。しかし極端な国粋主義や日本主義が過ぎ去ったはずの戦後においても、科学・技術をめぐる言説には総力戦体制期に見られたものを、そのまま引き継いでいるところがある。このような連続性が見られる以上、戦後日本のナショナル・アイデンティティの構成を問うためには、総力戦体制期の諸言説についても詳細な分析が必要であると考える。 本稿では、ナショナル・アイデンティティは大衆社会の想像力と大きな関わりを有しているとの立場にたっている。そのため科学・技術に関する諸言説を抽出する際に、いわゆる専門家の議論へ偏らず、戦後の考察については大衆社会の科学・技術認識が反映されやすい、新聞広告を主な資料として用いる。また総力戦体制期の考察についても、上述した科学者や技術官僚らによる議論ばかりではなく、同じ時期に大衆メディアにおいて広まりを見せていた「科学戦」ブームについても着目する。 以上の点を踏まえて、本稿の構成は以下のようになっている。まず第1章では、1920年代後半から30年代にかけての、「科学戦」に対する社会的な関心の高まりと大衆メディアにおけるイメージの広がりについて考察を行う。「科学戦」人気は、次の戦争がすぐそこまで近づいており、科学・技術の優劣が戦争の行方を決めてしまうことを強く印象づけた。第1節においては、「科学戦」のイメージが具体的にどのようなものであったのかについて、ラジオドラマ、科学読本、科学雑誌、軍事読本など幅広い分野を横断的に検討することで明らかにする。これらの出版物などは新兵器や空襲などの「科学戦」に関する知識を普及させたのはもちろん、科学振興の重要性についても訴えていた。つづく第2節と第3節では、当時少年達を中心に人気の高かった平田晋策、海野十三という二人の作家の未来戦記物を取りあげる。これらの作品を通して、日本と主に敵国とされたアメリカの科学・技術の比較や、科学・技術が戦争や社会に果たす役割がどのようなものとして考えられていたのかを分析する。 第2章では総力戦体制下における科学・技術をめぐる言説について、主に科学者や技術官僚などの視点から考察する。科学・技術をめぐる言説において、「日本文化」や「日本人像」が語られていたのは戦後的な現象ではなく、総力戦体制期から続く潮流である。この章は戦後のナショナル・アイデンティティを論じるうえでの前史にあたる。第1節では、科学・技術をめぐる言説の背景として、総力戦体制へと向かう科学動員の過程と、科学・技術の必要性や有用性が国家危急の事態においていかに認識されていたのかを概観する。続く第2節では、日本の精神性や道徳性を損なわないようにして、「西洋の所産」である科学・技術の振興を唱える、その訴え方のありようを、「物質文明と精神文化」という基本的な対立軸に基づいて考察する。第3節では、第2節で示した科学・技術を振興する必要性を説く議論からさらに進んだ、「西洋」とは異なる科学・技術の「日本的性格」を確立させようとする言説を分析する。これは「物質文明と精神文化」を単に対立させるのではなく、科学・技術の基底に「日本精神」や民族性を位置づけようとする試みだった。その際にあみだされた論法が、戦後における科学・技術をめぐる言説のひとつの雛型になったと考える。 第3章は、敗戦から1950年代初め頃までの短い時期を取り扱う。この時期は第2章と第4章のちょうど谷間にあたる。第1節では、総力戦体制期にその必要性が叫ばれた科学・技術の欠如が、敗戦直後に保守主義・自由主義・左翼陣営のそれぞれの思惑から「敗因」とされたことを論じる。陣営間の対立を越えて「科学・技術立国」というスローガンが、総力戦体制から引き継がれていった点を指摘する。第2節では、女性と科学・技術の関係性を「主婦」や「化粧品」をとりまく諸言説から考察する。戦前戦時にもう一度遡り、女性と科学・技術を取り巻く環境がどのように変化していったのか、科学・技術の振興一関して女性はとのような役割を求められていたのかについて論じたい。さらにはそのような役割がこの章で取り扱う敗戦とともに、いかに変化を遂げたのかについて考えてみることとする。 第4章では、1950年代から1960年代までの新聞広告を資料に用い、時計やカメラ、家電製品などの広告における科学・技術をめぐる言説について分析する。第1節においては、次節以降で新聞広告の言説分析をおこなう準備として、この時期の科学・技術行政および技術開発状況を概観することと、科学・技術にとって新聞広告という言説空間が持つ意味合いについて考察をおこなう。第2節では、1950年代の新聞広告において外国の技術と日本の技術がいかに比較・対置されていたかについて分析する。欧米諸国との比較を通じて、日本の科学・枝術についてどのような認識がなされていたのかについて考える。つづく第3節では、1960年代を境に頻出するようになった「日本の誇り」という言説を中心に、1960年代の新聞広告を考察する。日本の科学・技術が「日本の誇り」として語られるようになると、次第に「日本文化・日本人・日本民族」と結びつけられるようになった。その際、いかに日本という国家や「日本人」像が新聞広告において表象されていたかを論じる。最後、第4節では、日本製品や日本の科学・技術が「国境」を越えるという現象を、広告がどのように描いていたのかを中心に考察する。他者=世界が日本製品をいかに受け入れ、「愛用」していると広告が伝えていたのか、そしてそのような他者の存在が「日本の誇り」をさらに高めていった点について論じる。 第5章では、前章に続いて1970年代の広告を分析する。またこの章は新聞広告を資料として考察を行う最後の章でもある。1970年代の広告文には、今までには見られなかった変化が現れていた。第1節においては、公害問題を契機にした反科学的思想の興隆が、新聞広告の言説にどのような変化を及ぼしたのかについて考察する。科学・技術の進歩や経済成長の追求に対して批判が高まったことによって、今までの「日本人」や日本という国家のあり方に反省を迫る言説が増えた点に注目する。第2節は、1970年代後半になると、戦後一貫して科学・技術を介して「日本人」像や国家像を描いてきた新聞広告が、ナショナル・アイデンティティ表象の場として機能しなくなったことに着目する。強固な編成を保っていた新聞広告という言説空間に何が起こったのかを、新聞広告の媒体上の変化と、広告言説に起こった変化の二つから論じる。 最後、終章ではまず、新聞広告からは探ることができなくなっていた1980年代の科学・技術に関する言説を他の領域から抽出し、そこへ補足的に考察を加えることから始める。1980年代初頭に、戦後日本の科学・技術行政は従来の民間企業による技術導入や技術開発を主体とする方針から転換し、「科学・技術立国」を明確な国家戦略に位置づけるようになった。そのため80年代には言説の担い手として、政府や国家が急浮上するようになった。また80年代から90年代にかけては、技術開発を扱うルポルタージュが量産されてもいた。ルポルタージュの多くは日本製品や技術者の優秀さを文化的特殊性などと結びつけて論じており、その語り口に第4章で考察した新聞広告における言説の構図がそのまま継承されていた。そして、これら80年代以降の動向も踏まえて、今までの議論をもう一度振り返りながら、現在の私たちの科学・技術に対する認識の枠組は戦争を契機に培われたのであり、戦後日本のナショナル・アイデンティティもその枠組みの上で形成され続けてきた点を論じ、全体のまとめとする。
4 0 0 0 OA 技術戦としての日露戦争 : 日本陸軍による技術革新期への対応
- 著者
- 横山久幸
- 出版者
- 防衛省
- 雑誌
- 戦争史研究国際フォーラム報告書
- 巻号頁・発行日
- vol.第3回, 2005-03-31
4 0 0 0 IR 精神障害者の就労定着および離職に関する研究の動向
- 著者
- 野﨑 智仁 谷口 敬道
- 出版者
- 国際医療福祉大学学会
- 雑誌
- 国際医療福祉大学学会誌 = Journal of the International University of Health and Welfare
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.89-98, 2021-02-20
Various studies have been conducted to investigate the actual conditions and to verify the interventions that have been made to support the employment of individuals with mental disorders since their job retention and job separation appeared to be problematic. With the aim of finding ways to support people with mental disorders in retaining employment, a literature search including both Japanese and foreign language journals was performed in the Ichushi, CiNii and PubMed databases. The keywords used in the search were mental disorder, schizophrenia, depression, manic-depressive illness, job retention, job separation and retirement. The literature search resulted in 25 articles. Our analysis indicated that schizophrenia, depression, sleep disorders, duration of the disease (long-term), age (young generation), attention disorders, social cognitive impairment, full-time employment, absence of a person that they can consult with at work, etc., may increase the risk of job separation. Employees with a mental disorder who have not disclosed their disability to their employer are likely to have long working hours per day and retain their employment only for a short period of time; they are not receiving training and support before and after starting employment; and they do not feel rewarded at work. It was revealed that Individual Placement and Support (IPS) was effective for job retention and for improving their cognitive function. As a trend of studies in Japan, there have been many investigative research studies on individuals with mental disorders in the workforce, whereas few intervention studies have been conducted.
4 0 0 0 OA 自家製・桂枝茯苓丸の臨床効果に関する研究
- 著者
- 寺沢 捷年 松田 治己 今田屋 章 土佐 寛順 三潴 忠道 鳥居塚 和生 本間 精一
- 出版者
- The Japan Society for Oriental Medicine
- 雑誌
- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.2, pp.131-136, 1984-10-20 (Released:2010-09-28)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 4 4
慢性関節リウマチと全身性進行性硬化症の合併症例に対し, 自家製の桂枝茯苓丸を投与したところ, レイノー現象と手指屈曲制限が著しく改善した。この効果が桂枝茯苓丸によるものであることを急性投与実験により明らかにした。この効果は同一生薬を用いた水煎剤では得られず, 丸と丸料との相違を示唆する所見である。今後は剤型の相違による適応病態の差異について慎重に検討すべきものと考える。
4 0 0 0 OA 盛岡藩の罪と罰雑考(四・完)
- 著者
- 吉田 正志
- 出版者
- 東北大学法学会
- 雑誌
- 法学 = HŌGAKU (THE JOURNAL OF LAW AND POLITICAL SCIENCE) (ISSN:03855082)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, no.1, pp.109-148, 2019-06-28
4 0 0 0 OA 盛岡滞の罪と罰雑考(三)
- 著者
- 吉田 正志
- 出版者
- 東北大学法学会
- 雑誌
- 法学 = HŌGAKU (THE JOURNAL OF LAW AND POLITICAL SCIENCE) (ISSN:03855082)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.6, pp.79-116, 2019-02-28
4 0 0 0 IR 盛岡藩の罪と罰雑考(二)
- 著者
- 吉田 正志
- 出版者
- 東北大学法学会
- 雑誌
- 法学 = HŌGAKU (THE JOURNAL OF LAW AND POLITICAL SCIENCE) (ISSN:03855082)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.5, pp.132-101, 2018-12-30
4 0 0 0 IR 盛岡藩の罪と罰雑考(一)
- 著者
- 吉田 正志
- 出版者
- 東北大学法学会
- 雑誌
- 法学 = HŌGAKU (THE JOURNAL OF LAW AND POLITICAL SCIENCE) (ISSN:03855082)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.4, pp.134-98, 2018-10-30
4 0 0 0 IR 精神障害者の家族政策に関する一考察 : 保護者制度の変遷を手がかりに
- 著者
- 塩満 卓
- 出版者
- 佛教大学福祉教育開発センター
- 雑誌
- 福祉教育開発センター紀要 (ISSN:13496646)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.73-89, 2017-03-31
本稿の目的は、精神障害者対策を図るうえで、家族がどのように位置づけられてきたのか。保護者制度の源泉も辿りつつ、今日までの歴史的経緯を明らかにし、精神障害者家族に対する制度上の課題を言及していくことである。研究の結果、江戸時代後期には、「精神病者監護法」の私宅監置や家族の個別責任化という処遇や思想の原形が明文化・制度化されていた。そして、明治後期以降の精神障害者家族は、治安対策上、無償で機能する法の執行者として、さらには疾病管理から日常生活支援に至るまでのケアラーとして位置づけられ続けた。2013年の精神保健福祉法改正で「保護者制度」は廃止されたものの、医療保護入院の契約者は「保護者」が「家族」に変更されたに過ぎず、実態はこれまでと変わっていない。今後の精神障害者対策は、家族介護を前提としない「脱家族」の制度設計を目指し、家族介護に代わる公共的支援を量的にも質的にも拡充していく必要があることを指摘した。保護(義務)者制度精神障害者家族残余的福祉モデル脱家族家族介護
4 0 0 0 OA 人間と機械は友達になれるか
- 著者
- 伊藤 彰則
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 情報・システムソサイエティ誌 (ISSN:21899797)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.1, pp.11-12, 2019-05-01 (Released:2019-05-01)
- 参考文献数
- 9
4 0 0 0 OA 非RTPの学生/選手におけるドーピング防止教育
本研究ではRTP選手ではなくドーピング検査対象になっていない学生/選手(非RTPA)を対象にドーピング問題を検討した。結果として、検査方法などに抜け道があればドーピングに手を染める選手の現状は防止教育の難しさを物語っていた。問題解決に厳罰主義か、緩和主義かがある中、日本の「世間」という個人と社会の媒介を利用した、教育的スポーツを連帯責任システムによって堅持する方法論は検討に値する。伝統や美徳を大切にする共同体主義的傾向が強い日本社会では、教育的スポーツをベースにして、正しいスポーツ教育、スポーツのインティグリティ教育、ドーピング防止教育を推進することが必要と考えられる。
4 0 0 0 OA 伝承を持続させるものとは何か : 比婆荒神神楽の場合
- 著者
- 鈴木 正崇
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.186, pp.1-29, 2014-03-26
伝承という概念は日本民俗学の中核にあって,学問の成立の根拠になってきた。本論文は,広島県の比婆荒神神楽を事例として伝承の在り方を考察し,「伝承を持続させるものとは何か」について検討する。この神楽は,荒神を主神として,数戸から数十戸の「名」を単位として行われ,13年や33年に1度,「大神楽」を奉納する。「大神楽」は古くは4日にわたって行われ,最後に神がかりがあった。外部者を排除して地元の人々の願いを叶えることを目的とする神楽で秘儀性が強かった。本論文は,筆者が1977年から現在に至るまで,断続的に関わってきた東城町と西城町(現在は庄原市)での大神楽の変遷を考察し,長いサイクルの神楽の伝承の持続がなぜ可能になったのかを,連続性と非連続性,変化の過程を追いつつ,伝承の実態に迫る。神楽が大きく変化する契機となったのは,1960年代に始まった文化財指定であった。今まで何気なく演じていた神楽が,外部の評価を受けることで,次第に「見られる」ことを意識し始めるようになり,民俗学者の調査や研究の成果が地域に還元されるようになった。荒神神楽は秘儀性の高いものであったが,ひとたび外部からの拝観を許すと,記念行事,記録作成,保存事業などの外部の介入を容易にさせ,行政や公益財団の主催による記録化や現地公開の動きが加速する。かくして口頭伝承や身体技法が,文字で記録されてテクスト化され,映像にとられて固定化される。資料は「資源」として流用されて新たな解釈を生み出し,映像では新たな作品に変貌し,誤解を生じる事態も起こってきた。特に神楽の場合は,文字記録と写真と映像が意味づけと加工を加えていく傾向が強く,文脈から離れて舞台化され,行政や教育などに利用される頻度も高い。しかし,そのことが伝承を持続させる原動力になる場合もある。伝承をめぐる複雑な動きを,民俗学者の介在と文化財指定,映像の流用に関連付けて検討し理論化を目指す。
4 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1927年10月22日, 1927-10-22
- 著者
- 日比野 幹生 舟橋 弘晃 青柳 健隆 間野 義之
- 出版者
- 日本スポーツ産業学会
- 雑誌
- スポーツ産業学研究 (ISSN:13430688)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.1_13-1_28, 2016 (Released:2016-04-26)
- 参考文献数
- 33
Although studies conducted to understand why athletes do not use Performance Enhancing Drugs (PEDs) are becoming more common, little is known about the problem from the “elite” athlete’s perspective. This study qualitatively identified the factors that had influenced the decisions not to dope of twelve retired Japanese elite athletes (six males and six females) who won Olympic medals after the Athens Games in 2004. Thematic analysis was used to extract meaning from the semi-structured interview data using MAXQDA11. Personal and socio-environmental factors underpinning their decisions not to dope were identified in the accounts. Personal factors included: (1) personal moral stance; (2) judgment from a wide perspective; (3) intrinsic motivation; (4) task orientation; and (5) resilience. Socio-environmental factors were: (1) education from parents; (2) education from coaches; (3) social pressure; (4) fair play culture in Japan; (5) secure elite sport climate; (6) monetary benefit from winning a medal; (7) access to and knowledge of PEDs. The above-mentioned factors might be useful for developing future anti-doping strategies under a situation where there is a growing social need for actively engaging in promoting elite sports as a national strategy in order to generate success in the Tokyo Olympics in 2020, and in view of the fact that the pressure for athletes to engage in doping may be increased.