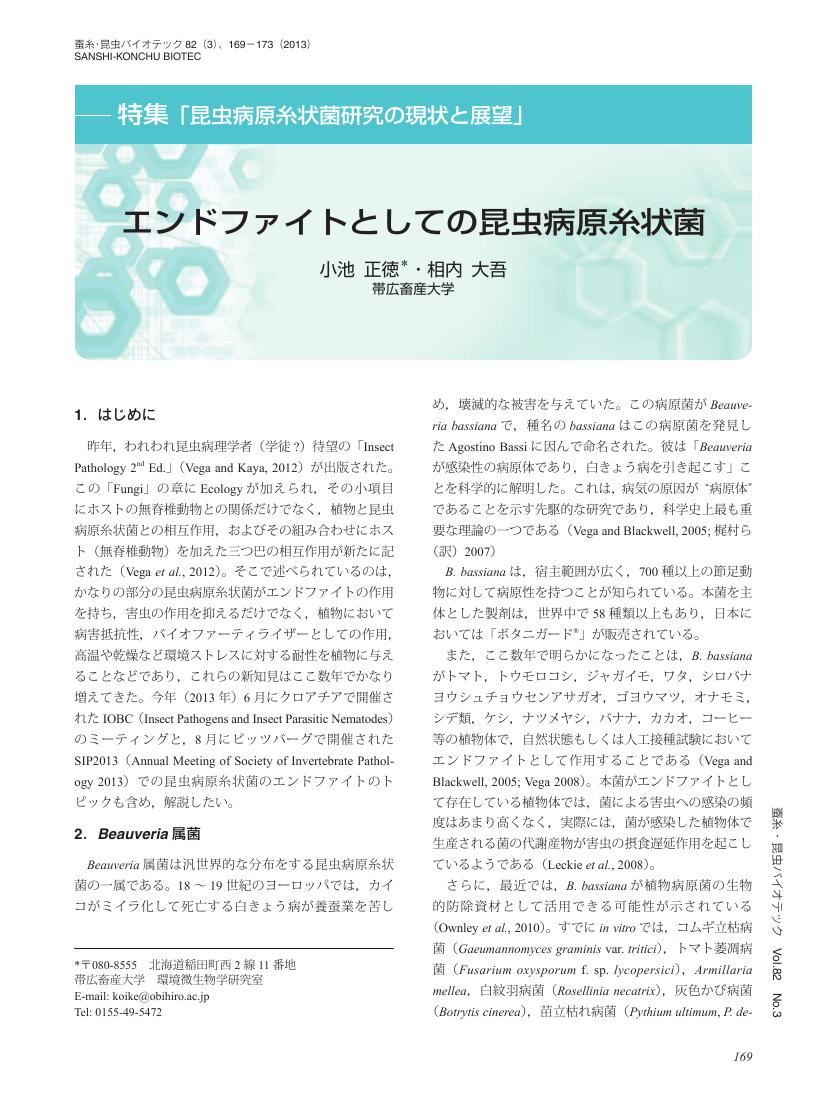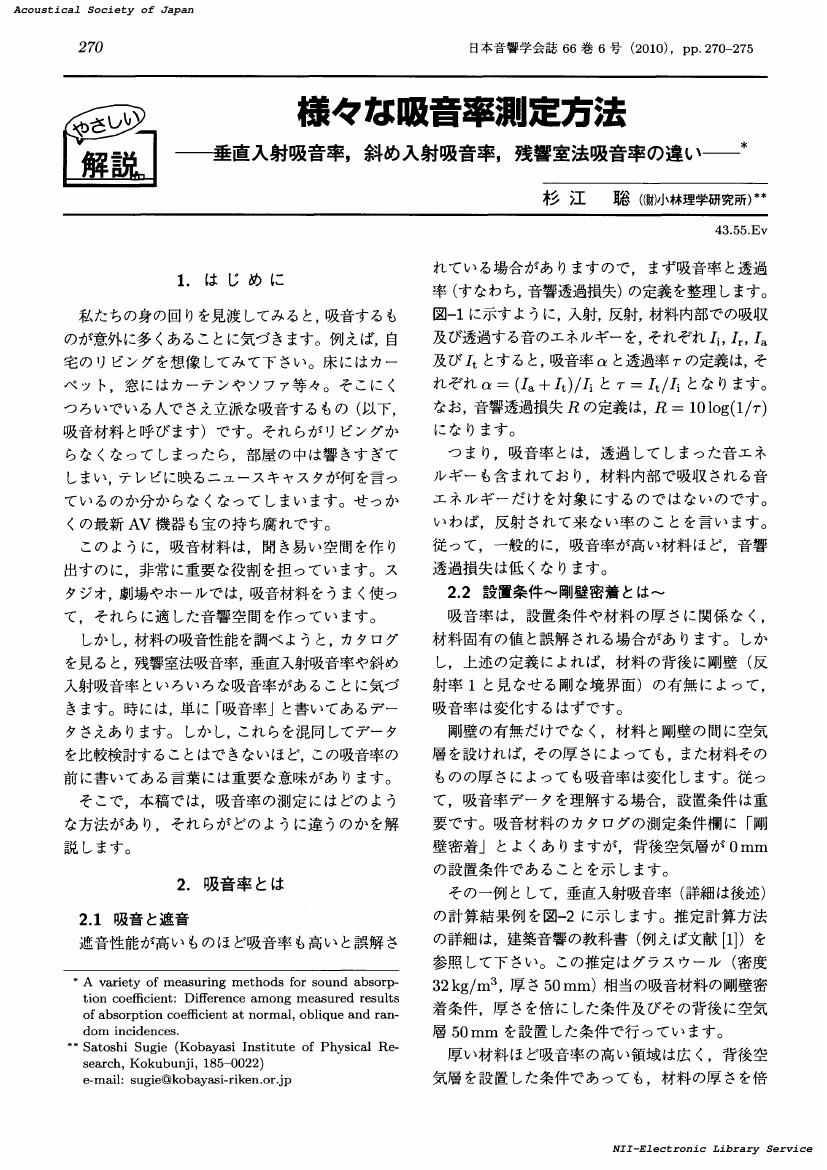3 0 0 0 OA 素裸にした甲州財閥
- 著者
- 萩原為次 著
- 出版者
- 山梨民友新聞社東京特置事務所
- 巻号頁・発行日
- 1932
3 0 0 0 OA 自己愛と他利愛のむすびつきーP.A.ソローキンとE.フロムー
- 著者
- 吉野 浩司 Koji Yoshino
- 雑誌
- 長崎ウエスレヤン大学現代社会学部紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.7-15, 2018-03-31
3 0 0 0 OA なぜナッジで行動を後押しできるのか?—経済学から見たナッジ—
- 著者
- 竹林 正樹 後藤 励
- 出版者
- 日本健康教育学会
- 雑誌
- 日本健康教育学会誌 (ISSN:13402560)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.2, pp.68-74, 2023-05-31 (Released:2023-06-22)
- 参考文献数
- 38
本稿は,健康支援関係者に向け,行動経済学やナッジの原理を概説することを目的とする.経済学は,人・物・金といった限られたリソースをどのように配分すると満足度を高めることができるのかを分析する学問である.伝統的経済学では,目的達成のために手立てを整えてベストを尽くす「合理的経済人」をモデルとする.行動経済学は,健康の大切さを頭でわかっていても認知バイアスの影響で望ましい行動ができないような「ヒューマン」を対象とする.ナッジは行動経済学から派生した行動促進手法で,認知バイアスの特性に沿ってヒューマンを望ましい行動へと促す設計である.ナッジが行動を後押しできるのは,認知バイアスには一定の系統性があり,ヒューマンの反応が一定の確率で予測できるからである.ナッジは他の介入に比べて費用対効果が高く,ナッジの中でも「デフォルト変更」に高い効果が報告されている.一方で,ナッジは行動変容を継続させるほどの効果は期待できないことや,日本での研究が少ないことといった限界がある.ナッジはヒューマンの自動システムに働きかける介入であり,倫理的配慮が求められる.介入設計に当たってはスラッジ(選択的アーキテクチャーの要素のうち,選択をする当人の利益を得にくくする摩擦や障害を含む全ての要素)になる可能性がないかを入念に検討する必要がある.
- 著者
- 村枝 ひろみ 干川 隆
- 出版者
- 一般社団法人 日本特殊教育学会
- 雑誌
- 特殊教育学研究 (ISSN:03873374)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.3, pp.133-143, 2017 (Released:2019-03-19)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 2 1
本調査は、現在の特別支援学校〈病弱〉中学部に在籍する生徒の実態とそこで行われている支援を明らかにすることを目的とし、発達障害を背景にもつ不登校などの適応障害のある生徒への有効な支援について検討した。現在の特別支援学校〈病弱〉中学部に在籍する生徒の発達障害の内訳は自閉症スペクトラム障害が56.5%を占め、また一方では、この10年間で、発達障害などで適応障害のある生徒数はおよそ2倍になっている。通常の学校で不登校などの不適応を起こした生徒が転入学している状況は今も続いている一方で、特別支援学校〈病弱〉での支援を通して、7割近い生徒の登校状況が「ほとんど欠席なし」になり、卒業後も発達障害を有する生徒の約5割が良好な登校状況を維持していた。これらの結果をふまえ、特別支援学校〈病弱〉中学部の現状と生徒の実態、発達障害で適応障害のある生徒への指導上の課題、また、有効な支援のあり方や特別支援学校〈病弱〉中学部の役割について考察した。
3 0 0 0 OA 機能分析に基づいた不登校への行動療法的介入—2症例を通して—
- 著者
- 西村 勇人
- 出版者
- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 行動療法研究 (ISSN:09106529)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.2, pp.257-265, 2016-05-31 (Released:2019-04-27)
- 参考文献数
- 11
近年、不登校の治療において機能分析に基づくアセスメントと介入が注目を浴びており、Kearneyらは不登校行動を四つの機能に大別している。本稿で報告する2事例は、不登校行動がもつ機能に注目してアセスメントを行った結果、否定的感情を喚起する学校関連刺激からの回避、社会的・評価的状況からの回避という機能を共通して持っていると想定された。これに対して共通してエクスポージャーやSSTを行い、事例1に対しては認知的介入も行った結果、学校に対する不安感が減少し、再登校が可能になった。同じ機能をもつ2事例の比較を通して、エクスポージャーやSSTの有用性についてや、どのような事例の差異に注目して技法を選択・運用していくかについて、考察を加えた。
3 0 0 0 OA Motivational Factors Affecting Sports Consumption Behavior of K-league and J-league Spectators
- 著者
- Jung-uk Won Kaoru Kitamura
- 出版者
- Japan Society of Physical Education, Health and Sport Sciences
- 雑誌
- International Journal of Sport and Health Science (ISSN:13481509)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.233-251, 2006 (Released:2008-01-25)
- 参考文献数
- 56
- 被引用文献数
- 14 18
The purpose of this study was to examine motivational factors affecting consumption behavior of K-league and J-league spectators, and their predictability to explain it. We found that 10 motivational factors significantly, but not sufficiently explained the current attendance frequency of the K-league spectators, whereas these factors well predicted their future consumption behavior. It was considered that there is great potential in the K-league spectator market. The results of the J-league spectators indicated that team identification and vicarious achievement were strong predictors to explain the variance in the game attendance frequency of the J-league spectators, and these results were consistent with the results of Mahony, et al., (2002). However, we found a new predictor (social interaction) to explain this variance. Also, we found that escape was a new positive predictor to explain the intention to attend future games of the K-league and J-league spectators, and escape, player, and team identification were related to the future merchandise consumption of both the K-league and J-league spectators.
3 0 0 0 OA 「学ぶ観光」としての修学旅行の意義とその課題 : 福島県立会津高等学校の取り組みから
- 著者
- 須賀 忠芳
- 出版者
- 日本国際観光学会
- 雑誌
- 日本国際観光学会論文集 (ISSN:24332976)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.97-104, 2013 (Released:2019-04-03)
- 被引用文献数
- 1
The school trip in a Japanese school is planned as a thing which recognizes various knowledge on many sides and originally investigates it at the area, and can be positioned as "learning tourism." However, in a school trip in recent years, it carried out without also awaking what awareness of the issues in the travel, teachers also regards a school trip as one of the mere usual school events, and students and teachers has hardly paid concern for the meaning. The school trip to Tohoku district and Hokkaido in Japan which Fukushima Prefectural Aizu High School in this year under the Great East Japan Earthquake succeeded in making a newly think in local situation. Moreover, it visited Mutsu city in Aomori prefecture in connection with the history of Aizu, and succeeded in making a student realize historical relation in this area. In this paper, the subjects in the school trip as "learning tourism" were considered, referring to this example.
- 著者
- 長谷川 秀樹
- 出版者
- 横浜国立大学教育学部
- 雑誌
- 横浜国立大学教育学部紀要. Ⅲ, 社会科学 = Journal of the College of Education, Yokohama National University. The social Sciences (ISSN:24339474)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.57-82, 2023-02-28
- 著者
- 井手口 彰典 イデグチ アキノリ Akinori Ideguchi
- 出版者
- 立教大学社会学部
- 雑誌
- 応用社会学研究 = The journal of applied sociology
- 巻号頁・発行日
- vol.65, pp.1-15, 2023-03-23
- 著者
- 長内 厚 土屋 裕太郎 大野 貴弘
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.3, pp.401-408, 2023 (Released:2023-05-01)
- 参考文献数
- 34
従来のユーザ・イノベーションは,ユーザの情報発信力は限定され,個別のユーザの情報は企業が集約して拾い集めることを前提として,ユーザを巻き込みながらも,製品や製品に関する情報は企業が統制し,市場に提供するという形態であった.しかし,ソーシャルメディアが個人の発信力を強化し,ユーチューバーが職業として成立するように個人の発信が収益化を伴うビジネスになると,製品情報の統制は企業の専有物ではなくなり,企業のコントロールの効かないところで個人が発信し,個人が発信した情報が収益化に結びつく状況になっている.ソーシャルメディアの普及に伴い,ユーザ・イノベーションは必ずしも企業の収益に結びつくとは限らず,ユーザ・イノベーションが企業の利害と対立する状況があるのではないかということが,本研究の大きな問いである.この問いを検討するため,ロバート・インの個別事例研究法を用い,資生堂とアルビオンの化粧品開発事例の定性分析から探索的な問いを求めた.
3 0 0 0 OA 黒川真頼の活用研究と草稿「語学雑図」
- 著者
- 遠藤 佳那子
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.2, pp.67-52, 2016 (Released:2017-03-03)
- 参考文献数
- 12
本稿は、未発表資料である黒川真頼の草稿「語学雑図」を紹介するものである。当該資料はおもに用言やテニヲハの活用表からなり、これによって、用言の活用研究とテニヲハ類の研究が連動して行われていたことなど、真頼の構想過程をうかがい知ることができる。また本稿では、術語「終止言」の使用と、「良行四段一格」の配置を手がかりにして、当該資料の成立時期が明治四年頃までであると推定した。こうしたことから、文部省編輯寮『語彙別記』『語彙活語指掌』の編纂に際して、真頼の文法学説が重要な位置を占めていたことが示唆された。
3 0 0 0 OA 脳波による実用的なBMI研究開発
- 著者
- 神作 憲司
- 出版者
- 認知神経科学会
- 雑誌
- 認知神経科学 (ISSN:13444298)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.3, pp.185-192, 2013 (Released:2017-04-12)
我々は、非侵襲型ブレイン−マシン・インターフェイス(Brain-Machine Interface :BMI)研究を行い、特定の視覚刺激を注視した際に生じるP300様脳波を利用した環境制御システム(Environmental Control System : ECS)を開発している。このBMI-ECSに用いる視覚刺激の強調表示の手法として、これまでの輝度変化に加えて色変化(緑/ 青)を用いることで、使用感および正答率を有意に向上させることに成功した。また、当該課題遂行中のEEG-fMRI 信号を計測したところ、右の頭頂後頭部を中心として、輝度変化に加えて色変化(緑/ 青)を用いたことによる特徴的な脳活動が見いだされた。さらに、これらのBMI 技術と拡張現実(AugmentedReality : AR)技術を統合させ、AR-BMI 技術を開発した。これにより、操作者の環境を脳からの信号で制御するこれまでのBMI に加えて、代理ロボットを介してリモート環境を制御することをも可能とした。我々は、このBMI-ECSの実用化に向けて、着脱容易で長時間使用可能な脳波電極、独自の脳波計およびシステム(ソフトウェア)等を開発し、これらを用いて臨床研究をすすめている。こうしたBMI 技術をさらに研究開発していくことで、脳からの信号で操作できるインテリジェントハウスへと繋げることも可能であり、麻痺を伴う患者・障害者の活動領域拡張へと貢献していくことが期待できる。
3 0 0 0 OA エンドファイトとしての昆虫病原糸状菌
- 著者
- 小池 正徳 相内 大吾
- 出版者
- 社団法人 日本蚕糸学会
- 雑誌
- 蚕糸・昆虫バイオテック (ISSN:18810551)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.3, pp.3_169-3_173, 2013 (Released:2014-02-28)
- 参考文献数
- 18
3 0 0 0 OA 第2次世界大戦中琉球諸島に流行したマラリアに関する再考察―とくに八重山群島を中心として―
- 著者
- 崎原 盛造 西 貴世美 當山 冨士子 宇座 美代子 平良 一彦
- 出版者
- The Japanese Society of Health and Human Ecology
- 雑誌
- 民族衛生 (ISSN:03689395)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.2, pp.67-84, 1994-03-31 (Released:2010-06-28)
- 参考文献数
- 43
- 被引用文献数
- 6 6
This paper focused on malaria epidemic in Ryukyu Islands during World War II with special reference to Yaeyama Islands to prove whether malaria outbreak in Yaeyama in 1945 was unusual, by reanalyzing published data by various researchers and unpublished documents of the U.S. military Government that occupied Ryukyu Islands from 1945 to 1972. The following results were obtained: 1) Outbreak of malaria in the Ryukyu Islands in a period from 1945 to 1947 was caused by great alteration of biologic balances due to military operations by Japanese Army. 2) Compared with those in Miyako and Okinawa Islands, fatality from malaria in Yaeyama in 1945 was extraordinarily high. 3) Forced evacuation of the inhabitants to malaria endemic areas by the Japanese Army caused exceptionally high incidence, mortality and fatality in Yaeyama. 4) Of species of malaria parasites, malignant P, falciparum was predominant in Yeayama. P. vivax was preponderant both in Miyako and Okinawa Islands . 5) In Okinawa Islands, intensive mosquito control measures were initiated by the US Army when they landed the Island in April 1945. But in Miyako and Yaeyama Islands, only partial chemotherapy was administered, not full scale mosquito control activities . In conclusion, unusual outbreak of malaria epidemic in Yaeyama in 1945 was mostly attributed to the forced evacuation of the inhabitants to malaria endemic areas by the Japanese Army.
3 0 0 0 植物由来吸水性ポリマーを用いた砂漠緑化剤の開発
土壌の砂漠化は世界的規模で進行しており、大きな環境問題となってきている。土壌を回復させ緑化を行うための一つの手段として、土壌へ水分保持剤としての吸水性ポリマーを添加することが着目されているが、化学合成されたポリマーは土壌中に蓄積され新たなる環境問題へと発展する恐れがある。本研究では、吸水性ポリマーを植物を素材として作製することを試み、その評価を中性子ラジオグラフィで行った。材料として混合針葉樹材パルプを用い、カルボキシメチル(CM)化することにより得られたポリマーを使用した。ポリマーは、パルプ材の微細繊維を除去し、イロプロパノール中に懸濁した後、モノクロル酢酸を添加しCM化することにより得た。ダイズを用いたポット試験では、土壌中に0.3%このポリマーを添加して植物体の生育状況を検討した。植物体の乾燥重量は、コントロールと同等であり、ポリマーは植物育成に影響を与えないことが確認された。次に、アルミニウム薄箱中でダイズを育成させ、中性子ラジオグラフィにより土壌中の根の生育状況を非破壊状態で調べた。照射は日本原子力研究所原子炉JRR3を用いた。根の片側にポリマーを添加した場合には、側根はポリマーが添加されていない側のみ生育した。また根の真下にポリマーを添加した場合には主根の生育深度がポリマーの上部で止まり、側根が上部で発達した。しかし、根および植物体の乾燥重量はコントロールと同等であり、地上部の生育状況も良かった。これらの実験を通して、本ポリマーは土壌中の水分保持機能のみならず、植物の生育に影響を与えずに植物を浅い土壌で生育させることが可能であることが判った。植物由来の吸水性ポリマーは、根の生育をデザイン出来るばかりでなく、土壌中で分解した後も環境に影響を与えないと予想されることから、砂漠の緑化剤として将来期待されると思われる。
- 著者
- 山口 和紀
- 出版者
- 『遡航』刊行委員会
- 雑誌
- 遡航 (ISSN:27581993)
- 巻号頁・発行日
- vol.2023, no.7, pp.37-58, 2023-04-30 (Released:2023-06-10)
日本で唯一の法的に実施が定められたウェブアーカイブである、国立国会図書館による「ネットワーク系電子出版物の制度的収集事業(通称 WARP)」がどのような議論を経て形成されたのかを論じた。国立国会図書館の納本制度調査会/審議会の議事録から、議論を整理した。第一に、ウェブアーカイブを既存の納本制度の枠組みの中に入れるか/新たな制度を外側に設けるかが議論の中心となり、新たな枠組みを設けることが決まったことを明らかにした。第二に、公的機関/民間を問わない包括的なウェブアーカイブ事業の形成も視野には入っていたが、2000 年代初頭の議論の中で「公的機関」のみを制度的収集の対象とすることが決まったことを明らかにした。
3 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1937年05月28日, 1937-05-28
3 0 0 0 OA 音楽教室における生徒の演奏行為と著作権法 : 物理的・自然的な観察のもとに
- 著者
- 本山 雅弘
- 出版者
- 最先端技術関連法研究所
- 雑誌
- 最先端技術関連法研究 = Studies of Most-Advanced Technology-Related Law (ISSN:13474480)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.1-50, 2021-12-15
Ⅰ.問題の提起 1.世間の耳目を集めた音楽教室事件とその当座の結論 2.教室内での生徒演奏は家庭内での自主的な生徒演奏と同等か : 本稿の問題意識 3.規範的利用主体論とは筋を異にする解釈問題Ⅱ.生徒演奏に関する使用料請求権の可能性 1.生徒演奏と演奏権該当行為 2.生徒演奏には著作権法38条1項の制限規定が適用され得るかⅢ.生徒演奏を根拠とする民事責任のあり方 1.生徒演奏による演奏権侵害 (加害行為) とその効果 2.非営利演奏を行う生徒と責任との関係 3.音楽教室の金銭賠償責任 4.小括Ⅳ.結語 1.これまでの考察の要約 2.控訴審判決の結論との抵触をいかに評価すべきか 3.いずれの結論を妥当と解すべきか
- 著者
- 杉江 聡
- 出版者
- 一般社団法人 日本音響学会
- 雑誌
- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.6, pp.270-275, 2010-06-01 (Released:2017-06-02)
- 参考文献数
- 11