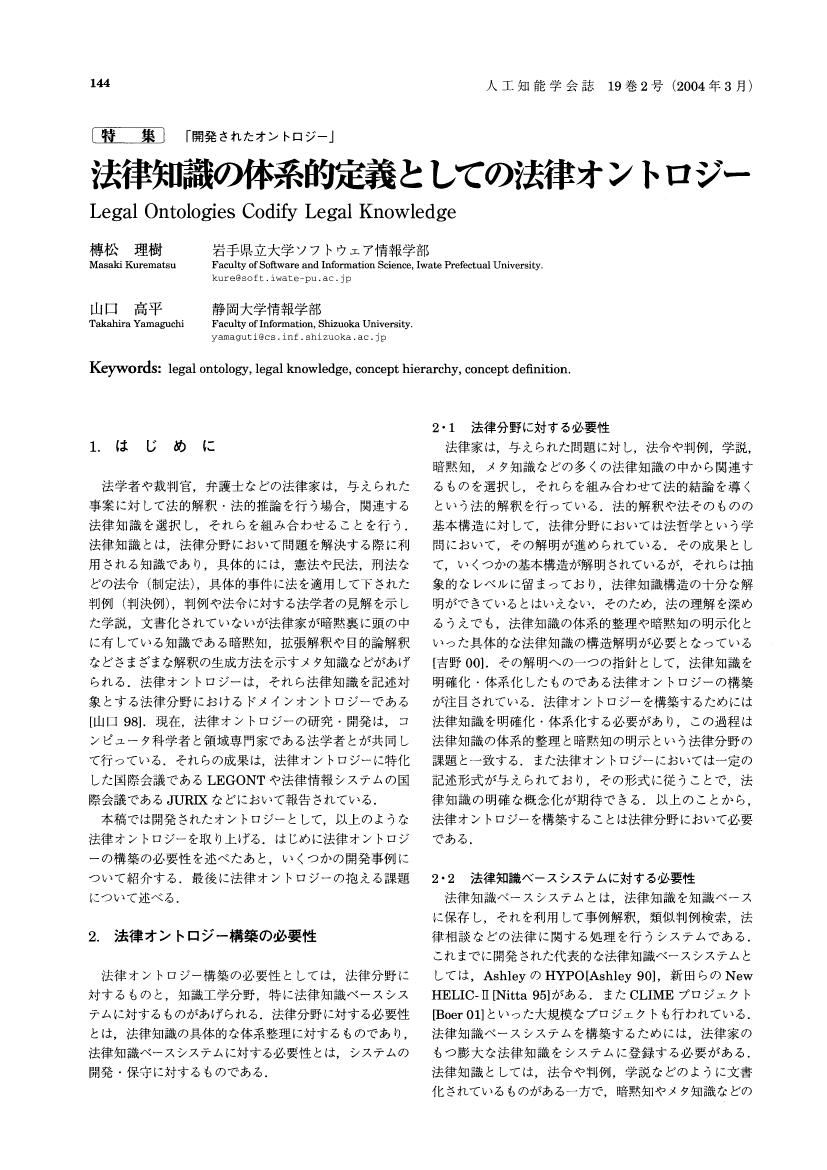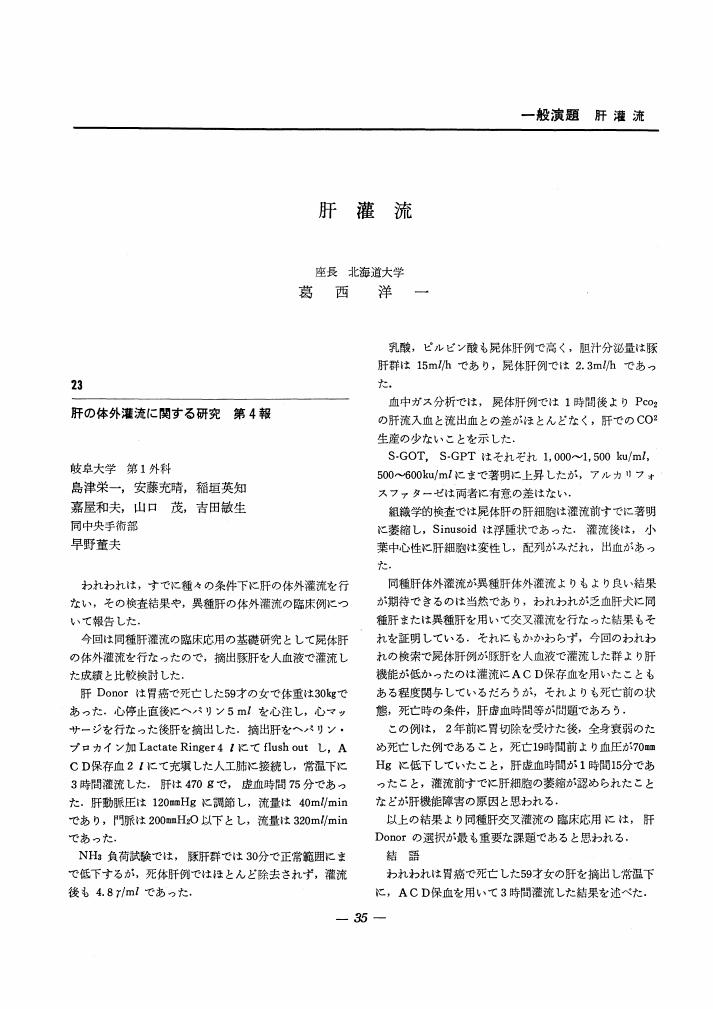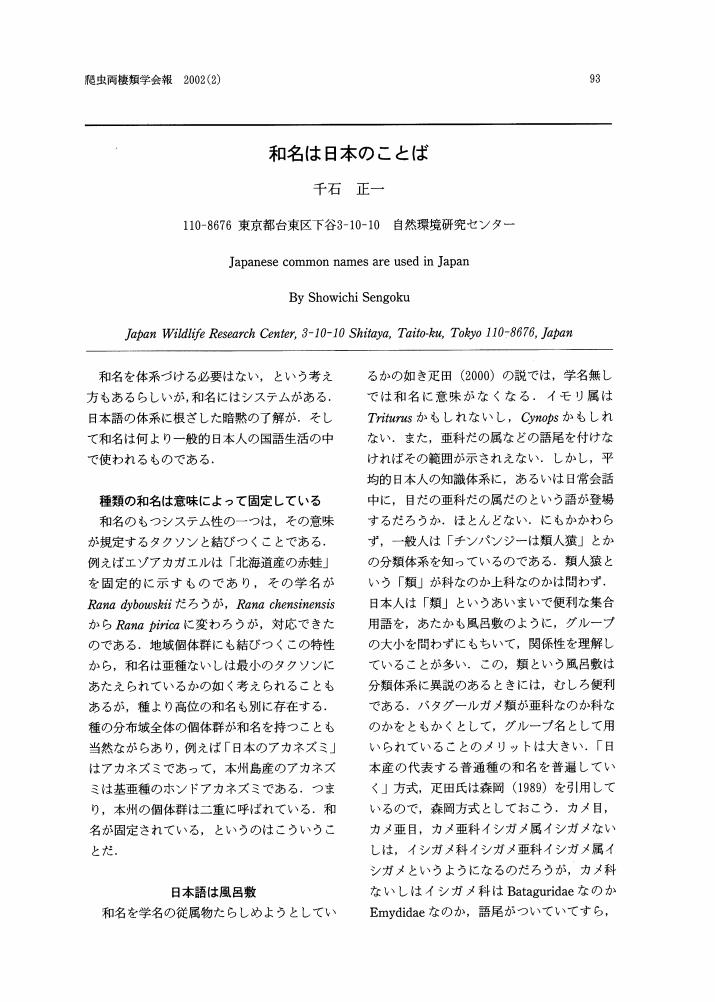2 0 0 0 OA 対人場面における怒りの表出方法の適切性・効果性認知とその実行との関連
- 著者
- 木野 和代
- 出版者
- 日本感情心理学会
- 雑誌
- 感情心理学研究 (ISSN:18828817)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.2, pp.43-55, 2004-01-31 (Released:2009-04-07)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 2 1
The first purpose of this study was to investigate Japanese adults' evaluations of appropriateness and effectiveness of anger expression strategies. The second purpose was to investigate the effects of their evaluations and interpersonal goals (i. e., relationship and communication) on the likelihood of using each anger expression strategy. Two hundred and nineteen undergraduates were asked to read a vignette in which a person displayed anger using various anger expression strategies toward either a superior, an equal, or a subordinate whose behavior evoked the anger. The participants were then asked to evaluate each anger expression strategy for its appropriateness and effectiveness. They were also asked to identify themselves as the angry person in the vignette and to rate the intensity of their own anger, the importance of interpersonal goals, and the likelihood of using each anger expression strategy. Findings suggested that pointing out the target person's faults calmly was reported to be a competent anger expression strategy especially when superiors expressed their anger. Regression analyses revealed that the cognitive evaluation of appropriateness of each expression strategy influenced the likelihood of using the strategy.
- 著者
- 齋田 哲也 中野 行孝 藤戸 博 宮﨑 翼 進 正志
- 出版者
- 一般社団法人日本医療薬学会
- 雑誌
- 医療薬学 (ISSN:1346342X)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.7, pp.423-429, 2013-07-10 (Released:2014-07-10)
- 参考文献数
- 17
Recently, six furanocoumarin derivatives isolated from grapefruit juice were found to be inhibitors of CYP3A4, suggesting that they may be clinically active and useful constituents. We succeeded in developing a sensitive and specific enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for these furanocoumarin derivatives in grapefruit juice.In this study, we examined the correlation between immunoactivity as indicated by ELISA and CYP3A4 inhibitory effects, in order to determine whether ELISA is a useful method for analysis of the CYP3A4-inhibitory activity of furanocoumarin derivatives. Our results show a close correlation between the values. Therefore, our findings strongly indicate that ELISA is a useful method for analysis of these furanocoumarins.Using this ELISA, grapefruit-derived products (grapefruit juice, jam and marmalade) were examined for furanocoumarin derivatives. Immunoactivity analysis was used to determine the amount of 6',7'-dihydroxybergamottin conversion. The amount of 6',7'-dihydroxybergamottin conversion was 13.0 μg/g with grapefruit juice, 40.0 μg/g with grapefruit marmalade and 1.7 μg/g with grapefruit jam. In addition, it was found that the heat treatment of grapefruit juice decreases the immunoactivity as indicated by ELISA and the CYP3A4-inhibitory activity. Moreover, the decreasing rate of the CYP3A4-inhibitory activity was lower than that of the immunoactivity as indicated by ELISA. Therefore, when the heat-treating grapefruit-derived products were analyzed by the ELISA, it was suggested that the CYP3A4-inhibitory activity might be estimated low. These findings will become indexes of the drug interaction of grapefruit-derived products.
2 0 0 0 OA 法律知識の体系的定義としての法律オントロジー(<特集>開発されたオントロジー)
- 著者
- 榑松 理樹 山口 高平
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能 (ISSN:21882266)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.2, pp.144-150, 2004-03-01 (Released:2020-09-29)
- 被引用文献数
- 1
2 0 0 0 OA ジェンダーをめぐる中高生と親の意識 「中学生・高校生の生活と意識調査2022」から②
- 著者
- 村田 ひろ子
- 出版者
- NHK放送文化研究所
- 雑誌
- 放送研究と調査 (ISSN:02880008)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.6, pp.64-75, 2023-06-01 (Released:2023-06-20)
NHKが2022年夏に実施した「中学生・高校生の生活と意識調査」の2回目となる今回の報告では、中高生と父母のジェンダーをめぐる意識に焦点を当てる。 大学まで進学を希望する女子は54%で、40年間で初めて男子(48%)を上回った。父母の結果をみても、10年前は、「大学まで」進学させたい親は、女子よりも男子の父母で多かったのに対し、2022年はこうした差はみられなくなった。 進学意向では男女差が解消されつつある一方で、家庭内に目を向けると、親による子への接し方は、子の性別によって異なる傾向がある。男子に対しては、「勉強が遅れている」「意思が弱い」と考える父母が多い。また、「男らしく、女らしく育てる」という考え方に賛成なのは、男子の父親で7割に上る。 それでも、中高生の多くは、伝統的な男女の役割分担にとらわれることなく、多様性に対しても寛容である。仲のよい友だちから「からだの性とこころの性が一致しない」と打ち明けられたら『理解できる』と回答したのは中学生で7割近く、高校生で8割に上る。父母の子育ての分担は、10年前から変わらず『母親主導』が多いが、中高生が思い描く将来の夫婦の子育て分担は、「父親も母親も同じくらいする」が多く、10年前の5割から7割へ大きく増えている。
2 0 0 0 OA アイガモによる除草作用の解明と環境負荷などの評価に関する研究
- 著者
- 浅野 紘臣
- 出版者
- 日本雑草学会
- 雑誌
- 雑草研究 (ISSN:0372798X)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.3, pp.151-156, 2009 (Released:2009-10-03)
- 参考文献数
- 17
- 著者
- Makoto Tachibana
- 出版者
- The University of Tokushima Faculty of Medicine
- 雑誌
- The Journal of Medical Investigation (ISSN:13431420)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.1.2, pp.19-23, 2015 (Released:2015-03-27)
- 参考文献数
- 47
- 被引用文献数
- 12 14
Epigenetics is the study of changes in gene function that cannot be explained by changes in DNA sequence. A mammalian body contains more than two-hundred different types of cells, all derived from a single fertilized egg. Epigenetic gene regulation mechanisms essentially contribute to various processes of mammalian development. The essence of epigenetic regulation is the modulation of gene activity through changes in chromatin structure. DNA methylation and histone modifications are the major epigenetic mechanisms. Sex determination is the process of establishing a gender. Sry, the sex-determining gene in therian mammals, initiates testis differentiation. Recent studies have provided evidence that epigenetic mechanisms contribute to Sry regulation. J. Med. Invest. 62: 19-23, February, 2015
2 0 0 0 OA 同位体の分離
- 著者
- 千谷 利三
- 出版者
- 公益社団法人 化学工学会
- 雑誌
- 化学工学 (ISSN:03759253)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.2, pp.127-132, 1965-02-05 (Released:2010-10-07)
- 参考文献数
- 5
2 0 0 0 OA 肝灌流
- 著者
- 葛西 洋一
- 出版者
- 一般社団法人 日本人工臓器学会
- 雑誌
- 日本人工臓器学会雑誌 (ISSN:03000826)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.35-38, 1970-11-20 (Released:2011-09-05)
- 著者
- 魏 燕玲 田中 豊穂
- 出版者
- 日本民族衛生学会
- 雑誌
- 民族衛生 (ISSN:03689395)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.2, pp.57-68, 2010 (Released:2010-05-31)
- 参考文献数
- 43
The purpose of this research is to compare two different high altitudes Tibetan group’s physiques, physical strengths and physiological functions.In total 199 Tibetan subjects, 101 subjects (48 males and 53 females) from a 1800 meter highlands (mid-altitude group) and 98 subjects (48 males and 50 females) from a 4000 meter highlands (high altitude group) were examined morphological and physiological characteristics such as height, weight, vital capacity, blood pressure, grip strength and two step exercise test. Subjects for the analyses were extracted from the total subjects by matching the age and sex between the two groups, 53 subjects respectively.Compared to the mid-altitude group, the high altitude group had a smaller body size, lower physical abilities except for endurance performance, lower systolic and diastolic blood pressure and lower vital capacity. The results of vital capacity were different from that of previous researches. Although the blood pressure was remarkably low in high altitude group, it is difficult to attribute the cause only to the difference of altitude, because besides the altitude some differences such as occupations and eating habits existed between the comparison groups.
2 0 0 0 海馬は末梢組織の慢性炎症に伴う疼痛反応を制御する
- 著者
- 鹿山 将
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.9, pp.869, 2023 (Released:2023-09-01)
- 参考文献数
- 2
脳は,末梢神経を介して末梢臓器の活動を感知し,制御している.こうした脳と末梢組織との関連は,近年注目を集めている.例えば,大脳皮質の一部である島皮質は,身体の内部の活動と深く関連する.マウスを用いた知見では,炎症に関連する島皮質の神経細胞を人工的に活性化させることで,腸内の免疫細胞が炎症時と類似した挙動を示すことが報告されている.このことは,島皮質が腸内の炎症状態を記憶し,制御する可能性を示している.一方で,炎症発生時に複数の脳領域の活動が変化することから,こうした機能は島皮質だけでなく,他の脳領域も担っている可能性が考えられてきた.本稿では,海馬の中でも,特に情動記憶と関連する腹側海馬に着目し,末梢組織における炎症性疼痛との関連を明らかにしたShaoらの報告を紹介する.なお,本稿は下記の文献に基づいて,その研究成果を紹介するものである.1) Koren T. et al., Cell, 184, 5902‒5915.e17(2021).2) Shao S. et al., Cell. Rep., 41, 112017(2023).
2 0 0 0 OA 女性の高等教育と無意識のバイアス払拭が次世代の幸福の鍵になる
- 著者
- 大隅 典子
- 巻号頁・発行日
- pp.1-19, 2023-03-31
「転換点を生きる / 東北大学教養教育院編. -- 東北大学出版会, 2023.3. -- (東北大学教養教育院叢書「大学と教養」 / 東北大学教養教育院編 ; 6).」第7章(pp.151-168)の著者版
2 0 0 0 OA 研究論文の書き方(3) 文章構成力も身につける
- 著者
- 山本 澄子
- 出版者
- バイオメカニズム学会
- 雑誌
- バイオメカニズム学会誌 (ISSN:02850885)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.3, pp.219-222, 2014 (Released:2016-04-16)
- 参考文献数
- 2
- 被引用文献数
- 1 1
2 0 0 0 OA ロボトミーの歴史(2):ロボトミー以前
- 著者
- 田中 雄一郎
- 出版者
- 学校法人 聖マリアンナ医科大学医学会
- 雑誌
- 聖マリアンナ医科大学雑誌 (ISSN:03872289)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.3, pp.97-109, 2022 (Released:2022-12-22)
- 参考文献数
- 19
ロボトミー誕生以前の脳科学や精神病の治療について概説する。精神病の治療には精神療法と身体療法がある。身体療法のなかには,電気治療,水治療,持続睡眠療法の他,様々な臓器切除があった。臓器切除の中には女性器切除や,精神病治療を目的とする男性の断種もあった。これまで十分な分析がない領域であったがNgramで光を当てる。1800年代後半,ロボトミーが行われる50年前に,精神病治療のために脳の部分切除を試みたスイスの精神科医がいた。それは世界初の精神外科手術ではあったものの,精神医学の発展に貢献することなく人々から忘れ去られた。1900年代前半には人為的にマラリアを感染させることで,ある種の精神病(進行麻痺)が治療可能となり精神医学発展に大きく寄与する。
2 0 0 0 OA 歯周病細菌プレボテラ・インターメディアのバイオフィルム形成機構の解明
2 0 0 0 OA 植物を「生きている」と思えるには:大学生の生物観から考える生物教育の課題
- 著者
- 水野 暁子 Akiko Mizuno
- 雑誌
- 日本福祉大学子ども発達学論集 = The Journal of child development
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.11-20, 2014-01-31
植物を生物と思えるようになるには, 生物教育として何が重要かを探るため, 昨年度 (水野 2013) と同じように 「命の仲間度アンケート」 と 「食べものと生物アンケート」 を実施した. 今年度は, 約 3 分の 2 の学生たちが, 食べものの原材料である植物を生物と思っていなかった. しかし, それらの学生たちも植物の構造や機能についての知識は, 植物を生物と思った学生たちと違いがみられなかった. また, 小学校から高校までの過程で, 全員, 授業の一環として植物を栽培した経験があった. 植物栽培の体験もあり知識もあるのに, 植物を生物と思えていない学生が多い. 小学校教師を目指す学生たちが受講する 「理科研究」 のレポートから, この現状を打開する方法を探ってみた.
2 0 0 0 OA 日本語入力から見る“PCが使えない大学生問題”
- 著者
- 長澤 直子
- 出版者
- 一般社団法人 CIEC
- 雑誌
- コンピュータ&エデュケーション (ISSN:21862168)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, pp.58-63, 2019-06-01 (Released:2019-12-01)
本稿では“PCが使えない大学生”の問題を文字入力の観点から論じる。大学生を対象としたアンケート調査によると,2,000文字のレポートをPCで作成する際にすべての作業をPCですると回答した人は約80%であった。一方で,約6%が先にスマートフォンで入力すると回答し,手書きまたはスマートフォンで下書きをする人が約13%存在した。また,PC以外のツールを用いて作業をする人は,将来へ向けてのICT利活用に対する自己評価が低いということが明らかになった。この評価を高めるには,初等中等教育からPCを使う頻度を増やし,キーボードにも慣れておくことが必要だと考えられる。
2 0 0 0 OA 羽根尾貝塚の発掘調査成果とその意義
- 著者
- 戸田 哲也 舘 弘子
- 出版者
- 一般社団法人 日本考古学協会
- 雑誌
- 日本考古学 (ISSN:13408488)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.11, pp.133-144, 2001-05-18 (Released:2009-02-16)
- 参考文献数
- 6
羽根尾貝塚と泥炭層遺跡は,神奈川県小田原市羽根尾において発見された縄文時代前期中葉の遺跡であり,1998年から1999年にかけて筆者等により発掘調査が行われた。遺跡はJR東海道線二宮駅西方約2.5kmに位置し,現相模湾より内陸に約1km入った地区にあたる。貝塚及び泥炭質包含層は地表下2~4mという深さに遺存しており,低位の幅狭い丘陵突端部の両側斜面と近接する同一地形の斜面計3カ所から発見されている。これらの斜面部には小規模な貝塚の形成のみならず,往時の汀線ラインに寄り着いたと考えられる多くの樹木類と木製櫂が点在している状況を加え,縄文前期海進により湾入した海水面汀線に沿った地点であったと考えられる。この汀線ラインには多くの人工遺物,自然遺物が廃棄されており,遺跡が埋没する中で低湿地化が進み,厚い堆積土の下に貝塚をも包み込むように泥炭層が形成されたのである。標高22~24mを測る斜面部には当初前期関山II式から黒浜式の古段階にかけて貝塚が形成された。この全く撹乱を受けていない貝層中には,土器・石器類そして多くの獣・魚骨と骨角器が良好な保存状態で遺存しており,当時の相模湾において船を用いたイルカ・カツオ・メカジキ・サメ・イシナギなどの外洋性漁労が活発に行われたことが知られる。さらに貝塚の端部には屈葬と考えられる埋葬人骨1体も遺されていた。貝層形成時及び直後の黒浜期に至ると貝塚こそ形成されなくなるが,貝層下端から斜面下方に残された泥炭質包含層中からは大量な廃棄された遺物類が出土した。多くの遺物が検出されたが,中でもシカ・イノシシの獣骨類とイルカ・カツオの魚骨類は足の踏み場もないほどのおびただしい量が出土しており,水辺の動物解体場を考えさせる状況であった。このように羽根尾貝塚と泥炭層遺跡からは縄文前期の相模湾岸で行われた陸上での動・植物採集活動と海浜での漁労という両面からの生活実態を知ることができる。また,その他の廃棄された漆器類,木製品類の豊かな木工技術を示す遺物を含めた文化遺物とともにまさに縄文前期のタイムカプセルといえる貴重な調査資料を得ることができた。
- 著者
- 渡辺 洋子 行木 麻衣
- 出版者
- NHK放送文化研究所
- 雑誌
- 放送研究と調査 (ISSN:02880008)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.7, pp.2-42, 2023-07-01 (Released:2023-07-20)
本稿は「全国メディア意識世論調査・2022」の結果報告である。テレビ番組(リアルタイム)を「毎日のように」利用する人は7割を超えるが、2020年以降減少が続き、特に16~29歳では63%(2020年)から40%(2022年)と大きく減少した。16~29歳では、テレビよりYouTubeやSNSに毎日接する人の方が多くなった。また、若年層以外にもYouTubeやSNSの日常的な利用が広がった。 メディアの効用では、「世の中の出来事や動きを知る」うえで役に立つメディアとして、全体ではテレビが59%とほかのメディアと比べて圧倒的に高く評価されていた。また、全体では「世の中の出来事や動きを知ること」という効用自体を「とても重要」だと思う人は62%で、ほかの効用と比べてもっとも高いが、16~29歳では42%と半数に満たず、「感動したり、楽しんだりすること」(59%)、「生活や趣味に関する情報を得ること」(51%)の方が上位だった。さらに彼らは、感動したり楽しんだりするのはYouTube、生活や趣味の情報を得たりするのはYouTubeやSNSを評価していた。 メディア利用と意識の関係では、テレビや動画の視聴は若いほど同じようなものに偏る傾向があり、好きなもの・ことに対する積極的な意識が関係していた。また、自分と似たような思考を求める意識も関係していた。利用頻度が高いほどそのメディアが自分に影響を与えていると思う人が多く、「多くの人が賛同している情報は、信頼できる」「同僚や、友人・知人が知っているのに、自分が知らないことがあると、恥ずかしい」という意識の人はそうでない人よりメディアが自分に影響を与えていると思う人が多かった。
- 著者
- 小島 千佳
- 出版者
- 一般社団法人 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理 (ISSN:00187216)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.2, pp.119-141, 2023 (Released:2023-08-22)
- 参考文献数
- 60
本稿は,文学作品の分析を通じて,ジェントリフィケーションにおける立ち退きをめぐる問題について,定性的な考察を試みるものである。英語圏のジェントリフィケーション研究では,聞き取り調査に依拠する定性的研究により,居住者の場所喪失という犠牲の経験が論じられつつある。本稿では,文学作品の表象分析を通じて,立ち退きに伴う登場人物の場所喪失を関係論的な場所論の視座から検討した。具体的にはジェントリフィケーションを描いた,ヤン・ブラントによる小説『街の中のとある住まい』を研究対象とし,主人公をはじめとした登場人物の場所喪失の描かれ方を分析した。その結果,主人公の場所喪失は一時的なものではなく,長期にわたる精神的苦痛を伴う過程として描かれていたことが明らかとなった。他方で,旧東ベルリン居住者やトルコ系住民の場所喪失との関係において,主人公は他者の場所喪失による痛みに無自覚であるばかりか,それをロマンチックな経験へと読み替える加害者としても描かれていた。本小説は,ジェントリフィケーションにより住まいが奪われる痛みを私小説形式で伝えるとともに,個人の経験に含まれる犠牲と加害との両義性を示している。しかし,本小説における主人公と他者の痛みの描写のように,場所喪失の経験を序列化する物語は,現実に起きているジェントリフィケーションに対する想像力を方向付け,立ち退かされる人々のあいだに分断をもたらし得るという問題を内包している。