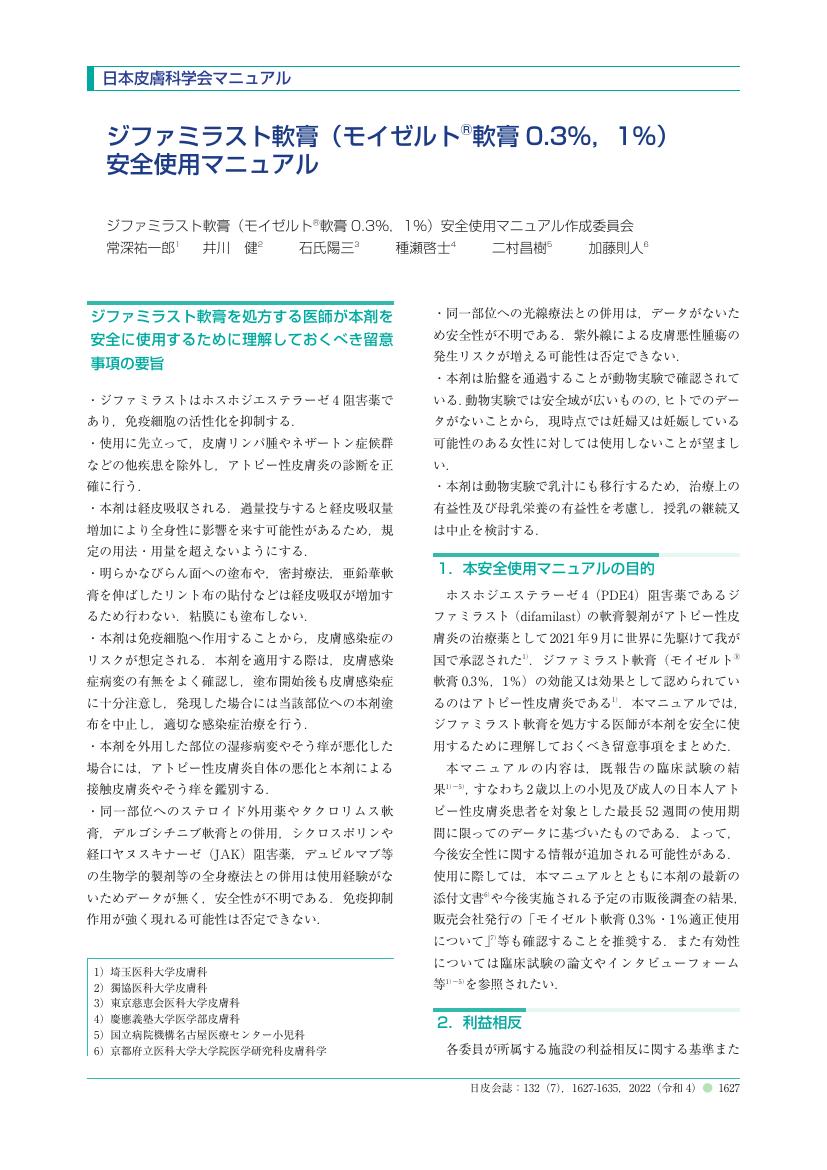- 著者
- 一井 崇
- 出版者
- 立命館大学産業社会学会
- 雑誌
- 立命館産業社会論集 = Ritsumeikan social sciences review (ISSN:02882205)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.2, pp.31-49, 2021-09
- 著者
- Hiroki Tanaka Masato Urushima Shuji Hirano Makoto Takenaga
- 出版者
- The Japanese Society of Internal Medicine
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.2, pp.243-245, 2019-01-15 (Released:2019-01-15)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 7 12
A 78-year-old man with mild coronary arteriosclerosis on coronary CT angiography underwent MRI of the prostate with the administration of Gadolinium-based contrast agent (GBCA) (gadopentetate dimeglumine). He developed acute coronary syndrome immediately after the intravenous injection of GBCA, and recovered after the administration of nitroglycerine, atropine sulfate, and hydrocortisone. He was discharged on the ninth day of hospitalization without recurrent chest symptoms. This is the second reported case of Kounis syndrome caused by GBCA. Kounis syndrome caused by MR contrast media is rare, but we should recognize that all contrast agents have the potential to cause Kounis syndrome.
2 0 0 0 OA 熟達美容師の行為と思考に着目したカウンセリング技能に関する特徴分析とモデル構築
- 著者
- 佐藤 文彦 金今 直子 四方 庸子 松居 辰則
- 出版者
- 日本感性工学会
- 雑誌
- 日本感性工学会論文誌 (ISSN:18845258)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.4, pp.415-424, 2022 (Released:2022-12-26)
- 参考文献数
- 15
In this study, we conducted interview surveys and observational surveys for understanding the characteristics of counseling skills possessed by expert hairdresser, and developed an integrated model of activities and thought processes in counseling. As a result, the following three characteristics were suggested: (1) The counseling process is proposal-based rather than listening-based, (2) The thoughts in the observation phase are based on abstract cognitions about clothing, and (3) The decision-making in the observation phase are more frequently in line with the customer’s wishes. These are expected not only to explain the skills possessed by expert hairdressers but also to provide clues for discussing counseling by novice. Therefore, this study is expected to contribute to the expertise of hairdresser. In constructing the model, we developed a method for integrated visualization of activities and thought processes. This method is considered to be novel and useful in skill analysis.
2 0 0 0 OA 味覚障害患者に対するポラプレジンクの有効性
- 著者
- 任 智美 阪上 雅史
- 出版者
- 日本口腔・咽頭科学会
- 雑誌
- 口腔・咽頭科 (ISSN:09175105)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.1, pp.53-56, 2011 (Released:2011-04-16)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 1
亜鉛欠乏により生じた味覚受容器の機能低下に対して, 亜鉛を補充することで可逆的な回復が期待される.亜鉛含有の胃潰瘍治療剤であるポラプレジンクは, 味覚障害の治療薬として有用であることが報告されている. 今回, ポラプレジンク75mg, 150mg, 300mgまたはプラセボを12週間投与した際の有効性と安全性について検討したので報告する.濾紙ディスク法検査の有効率は, プラセボ群63.0%, ポラプレジンク75mg群51.9%, 150mg群80.0%及び300mg群89.3%であり, 300mg群はプラセボ群に対して統計学的な有意差を認めた. また, 血清亜鉛値の変化量は150mg群と300mg群ではプラセボ群に対して統計学的に有意であった.
2 0 0 0 OA 占い情報に対する態度と人格特性の関連性
- 著者
- 大久保 純一郎
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第78回大会 (ISSN:24337609)
- 巻号頁・発行日
- pp.2PM-1-002, 2014-09-10 (Released:2021-03-30)
- 著者
- 島田 美小妃
- 雑誌
- 流経法學 = Journal of the Faculty of Law, Ryutsu Keizai University
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.2, pp.37-93, 2020-02-10
2 0 0 0 OA 道路交通法改正の経済効果-民間委託導入による路上駐車の削減と最適な駐車政策-
- 著者
- 田邉 勝巳
- 出版者
- 日本交通学会
- 雑誌
- 交通学研究 (ISSN:03873137)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, pp.171-180, 2009 (Released:2019-05-27)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 1
2006年6月に施行された道路交通法改正により、違法駐車の取締り業務の一部が民間委託され、取締りが強化された。東京都で最も早く民間委託が導入された地域の取締りは2年間で5倍以上となり、主要路線の合法駐車を含む路上駐車(二輪車を除く)の台数は58.9%減少した。外部費用の削減額は年間81億円程度と試算され、委託費を十分に上回る成果を得ている。現時点で道路交通法改正の費用対効果は高いが、最適な取締り水準、民間委託導入の程度など、多くの政策課題が残されている。
2 0 0 0 OA 巡検案内書:足尾山地南西部「桐生及足利」地域のジュラ紀付加体
- 著者
- 伊藤 剛
- 出版者
- 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 地質調査総合センター
- 雑誌
- 地質調査研究報告 (ISSN:13464272)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.4, pp.143-192, 2022-11-01 (Released:2022-11-04)
- 参考文献数
- 158
足尾山地南西部「桐生及足利」地域には,足尾帯に属するジュラ紀付加体が広く分布する.同地域内のジュラ紀付加体は,黒保根–桐生コンプレックス,大間々コンプレックス,葛生コンプレックス,行道山コンプレックスの各構造層序単元からなる.また,足利市名草周辺では,後期白亜紀の花崗閃緑岩からなる足利岩体が貫入している.本案内書では,付加体の特徴的な岩相や層序が観察できる露頭やルートとして14地点を紹介する.
2 0 0 0 積雪寒冷地での凍死の法医病態学的研究と診断確立
検屍における凍死事例152例、解剖における凍死事例69例の合計221例について法医病態学研究と診断確立のため以下の研究を行った。1)左右心臓血の色調差総事例数221例中左右心臓血の採取が行われたのは128例であった。その内訳は検屍152例中63例、解剖事例69例中65例である。●色調差がみれらたのは検屍例48/63(76.2%)解剖例62/65(95.4%)であった。2)第1度凍傷(紅斑)175例中84例(男性43例、女性41例)で認められ全体の48%であった。3)胃・十二指腸粘膜下出血(Wischnewski斑)解剖例69例中34例(男性16例、女性18例)、49.3%に認められた。4)矛盾脱衣(Paradoxical undressing)矛盾脱衣は221例中男性33例、女性12例の計45例で認められ、全体の20.4%であった。5)アルコールの関与アルコール濃度測定は検屍例120例中42例で測定が行われ20例で検出された。解剖例50例中38例で測定され19例に検出された。合計170例中39例の22.9%に検出された。6)薬毒物の関与凍死例170例中21例(検屍例4例、解剖例17例)に検出を試み7例に検出された。検出された薬物は、レボメプロマジン(精神神経剤)、フルラゼパム、ブロムワレリル尿素、ブロチゾラム、三環系抗うつ薬であった。7)各臓器の細胞内熱ショック蛋白(ubiquitin蛋白)の動態について剖検例20例について肝臓、腎臓、肺、心臓、膵臓、脾臓、大脳、小脳の各臓器についてubiquitin蛋白の存在を調べたところ、肝臓の胆管上皮、腎臓の尿細管に多くの出現をみた。
- 著者
- 式部 義信 井澤 信三
- 出版者
- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 行動療法研究 (ISSN:09106529)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.3, pp.271-282, 2009-09-30 (Released:2019-04-06)
- 被引用文献数
- 1
本研究では、断続的な不登校状態を呈したアスペルガー障害児の登校行動を促進・維持するための支援の効果について検討した。アセスメントの結果、断続的な不登校に陥った要因として学校場面に対する3つの負荷(「友達関係」「苦手な漢字」「学校行事」)が考えられた。そこで、支援は3つのステップ(「ステップ1:嫌悪的事態の除去・軽減」「ステップ2:3つの負荷に対する本人のスキルの向上」「ステップ3:登校行動の維持のために保護者を支援者にすること」)による段階的なアプローチを行った。支援内容としては、(1)保護者への行動論的カウンセリング、(2)対象児とその兄への社会的スキル訓練、が中心であった。その結果、登校行動を促進・維持することができた。また、本人の特性を理解し、家庭や学校との連携、さらに保護者が主体的な支援者として機能することが、登校行動を促進・維持する要因として重要であると考えられた。
2 0 0 0 OA 介護老人保健施設における薬剤適正化の現状と今後の展望
- 著者
- 丸岡 弘治
- 出版者
- 一般社団法人 日本薬局学会
- 雑誌
- 薬局薬学 (ISSN:18843077)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.2, pp.115-121, 2021 (Released:2021-10-22)
- 参考文献数
- 23
介護老人保健施設(以下,老健)は,医療とケアを受けられるバランスの取れた形態の施設であり,外国では見られない日本が誇るシステムの高齢者施設である.老健は介護保険の様々な制限の中で医療とケアを実施しなければならないため,もともとは処方見直しを行い,薬剤適正化に取り組む傾向にある場所である.さらに,令和 3 年度の介護報酬改定により老健における薬剤適正化が促進され,老健薬剤師の介入について明記され,注目されている施設である.薬局薬剤師は,施設外部からは調剤と配薬セットの委託を受けていることが多いが,その業務だけにとどまらず,老健の特性や性質を理解しながらであれば,薬剤適正化への介入や在宅から施設を行き来する入所者の薬剤情報・処方経緯を管理する役割も十分に担うことができると考える.
2 0 0 0 OA べ平連にみる海外連携のリスク JATECに注目して
- 著者
- 石井 至
- 出版者
- 日本リスクマネジメント学会
- 雑誌
- 危険と管理 (ISSN:09110992)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, pp.64-86, 2020 (Released:2020-05-22)
2 0 0 0 OA 奄美群島におけるソテツ利用
- 著者
- 吉良 今朝芳 三好 亜季
- 出版者
- 鹿児島大学農学部演習林
- 巻号頁・発行日
- no.28, pp.31-37, 2000 (Released:2011-03-05)
2 0 0 0 IR 奄美群島におけるソテツ利用
- 著者
- 吉良 今朝芳 三好 亜季
- 出版者
- 鹿児島大学農学部演習林
- 雑誌
- 鹿児島大学農学部演習林研究報告 (ISSN:13449362)
- 巻号頁・発行日
- no.28, pp.31-37, 2000-12
2 0 0 0 OA ジファミラスト軟膏(モイゼルトⓇ軟膏0.3%,1%)安全使用マニュアル
- 著者
- ジファミラスト軟膏(モイゼルトⓇ軟膏0.3%1%)安全使用マニュアル作成委員会 常深 祐一郎 井川 健 石氏 陽三 種瀬 啓士 二村 昌樹 加藤 則人
- 出版者
- 公益社団法人 日本皮膚科学会
- 雑誌
- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)
- 巻号頁・発行日
- vol.132, no.7, pp.1627-1635, 2022-06-20 (Released:2022-06-20)
- 参考文献数
- 16
- 著者
- 新田 和宏
- 出版者
- 近畿大学
- 雑誌
- Memoirs of the School of Biology-Oriented Science and Technology of Kinki University = 近畿大学生物理工学部紀要 (ISSN:13427202)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.37-54, 2007-09
冷戦終結以降、世紀を跨ぎ、急速に進展しつつあるグローバリゼーションに適応するために選択された新自由主義という政治的アイデアに基づく一連の改革は、日本国内において、従来の政策やレジームからの転換、とりわけポスト「日本型福祉国家」およびポスト「公共事業社会」を政治課題に据えながら、「新しい政治」の展開を導き出した。また、「新しい政治」の展開により、新たな政治的クリーヴッジが引き起こされた。本稿は、小泉構造改革を通じて導き出された「新しい政治」の展開と、その展開により引き起こされた新たな政治的クリーヴィジが指し示す方向性を明らかにし、改めて、ポスト「日本型福祉国家」/ポスト「公共事業社会」の行方について省察することを目的とする。
2 0 0 0 OA 学校における儀式的行事の存在価値
- 著者
- 水口 洋
- 出版者
- 国際基督教大学
- 雑誌
- 国際基督教大学学報. I-A 教育研究 = Educational Studies (ISSN:04523318)
- 巻号頁・発行日
- no.55, pp.43-53, 2013-09-01
学校教育を構成する特別活動の中で,学校行事は生徒の帰属意識を培うために有効な手段となっている。それぞれの学校の特色は行事の中に見られる。しかし,学校行事の一部に位置づけられる儀式的行事は,多くの生徒・卒業生にとって印象の薄いものとなってしまっている。それは式典の意味がきちんと伝えられていないからであろう。歴史的に見ても,式典の形式や内容については,様々な議論が展開されてきた。とりわけ,式典における国旗・国歌の用い方を巡って政治的・社会的問題が繰り返されてきたが,肝心の生徒に対する式典の意義は議論されずに,例年通りに踏襲されているに過ぎないことが多い。本稿は学習指導要領に見られる特別活動の意味を視野に入れつつ,式典等の儀式的行事の持っている教育的意味について考えてみたい。児童・生徒にとっての,「節目体験」になる区切りの行事の大切さについて考察してみたい。School events are an effective means of giving students a sense of belonging. The characteristics of the school are also evident in various school events. Unfortunately “ceremonial” events have, over time, lost significant meaning for students. Historically, the form and content of ceremonies have created various problems. Problems concerning the national flag and the use of the national anthem in the school ceremony have repeatedly created political and social dispute, although there has been no debate in the educational sphere on its meaning. I will consider the meaning of school ceremonies in this paper and consider the meaning of the events that are important in students’ social development.
2 0 0 0 OA 鉄骨造超高層建物の航空機衝突に対する損傷評価(構造)
- 著者
- 福田 隆介 福澤 栄治 小鹿 紀英 森川 博司
- 出版者
- 一般社団法人 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会技術報告集 (ISSN:13419463)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.21, pp.79-84, 2005-06-20 (Released:2017-04-14)
- 参考文献数
- 7
At the September 11, 2001, New York World Trade Center Towers did not collapse immediately after the aircraft impacts, despite the localized damage. Thus, the reserve capacity to the phenomenon besides assumption was called "redundancy", and after the WTC two towers' collapse, when taking the safety of a building into consideration, it had been recognized to be important property. In order that a building structure could not collapse and be secure safety to the load beyond anticipation on its structural design like the impulsive load by a collision, explosion, etc., it is important the building structure possesses structural redundancy. The purpose of this study is to evaluate the overall damage and the local damage and its structural redundancy against the aircraft impact equivalent to that in WTC for the Japanese typical 50 story high-rise steel building.
- 著者
- 山田 志津香 吉村 篤利
- 出版者
- 一般社団法人 日本歯内療法学会
- 雑誌
- 日本歯内療法学会雑誌 (ISSN:13478672)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.3, pp.157-166, 2019 (Released:2019-10-15)
- 参考文献数
- 83