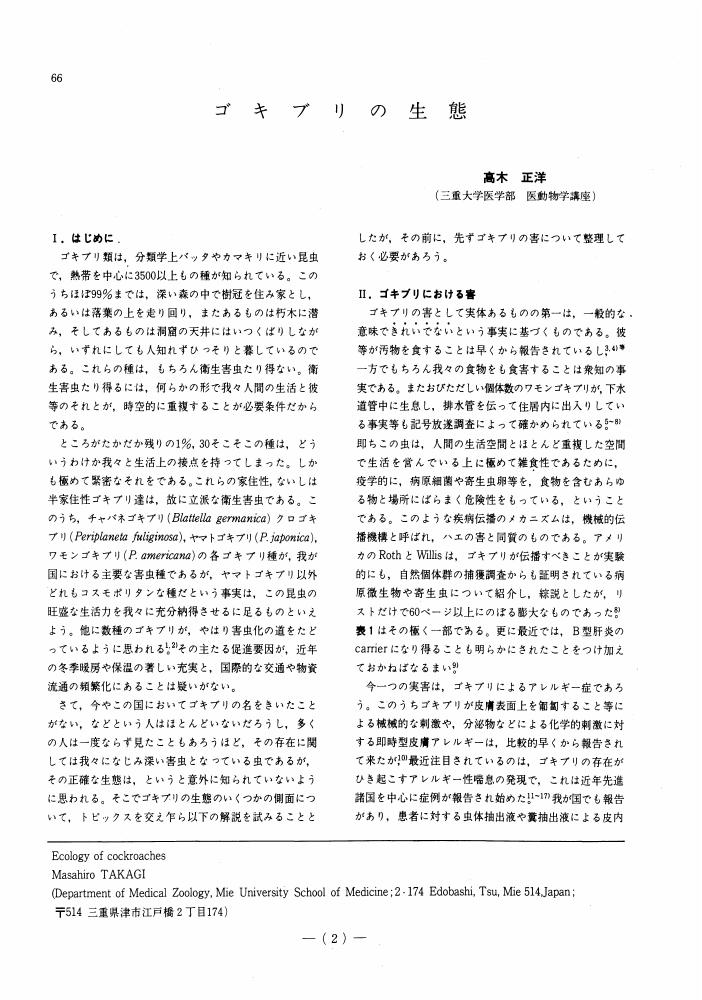2 0 0 0 OA キャリア教育の実践としての「ESD」 : 今後の社会生活を営む上で必要な資質の育成
2 0 0 0 IR キャリア教育における職場体験の意義--正統的周辺参加の視点からの再検討
- 著者
- 吉田 裕典
- 出版者
- 東京大学大学院教育学研究科
- 雑誌
- 東京大学大学院教育学研究科紀要 (ISSN:13421050)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, pp.247-258, 2009
Recently in Japan, most secondary schools are conducting work experience in career education. To clarify its meaning, this study reviews the history of career education in Japan first. On this basis, I review the change of treatment and meaning of work experience in the history of career education. The result shows three essential meanings of work experience; 1. Cultivation of work ethic and work value, 2. Understanding of aptitude and interest, 3. Acquirement of vocational understanding and skill. To ensure their theoretical background, this study adopts Super's career development theory and social learning theory. However, I find these theories are not sufficient to figure out unified meaning of work experience. Thus, this study discusses the viewpoint of Legitimate Peripheral Participation and tries to figure out unified meaning of work experience.
2 0 0 0 OA 歯周病患者における口内法による刷掃指導と位相差顕微鏡を用いての患者教育の効果
- 著者
- 平岩 弘 森田 学 渡邊 達夫
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本歯周病学会
- 雑誌
- 日本歯周病学会会誌 (ISSN:03850110)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.3, pp.602-609, 1985-09-28 (Released:2010-07-16)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 1 1
外来患者40名を対象として刷掃指導を行った。顎模型を用いた群 (コントロール群), 位相差顕微鏡によりプラークの観察を行った後, 顎模型を用いて指導した群 (位相差群), 術者が実際に患者の口腔内を清掃し, 指導する群 (術者群), 位相差顕微鏡によりプラークの観察を行った後, 術者が患者の口腔内を清掃し, 指導する群 (術者+位相差群) の4群に分け, 歯肉炎指数, プラーク指数を4週間にわたって追跡した。その結果, 位相差顕微鏡の効果は, 実験初期においては認められるものの, 持続性に欠けていた。術者+位相差群では, すべての診査項目において著しい改善が認められた。以上のことから, 従来よりの顎模型を用いた刷掃指導に比べ, 術者による刷掃と位相差顕微鏡の併用が刷掃指導を行う際のモチベーションに有効であることが示唆された。
2 0 0 0 OA 身体運動が味覚に与える影響
- 著者
- 佐々木 繁盛 早川 公康 藤井 久雄 Shigemori Sasaki Kimiyasu Hayakawa Hisao Fujii 仙台大学 仙台大学 仙台大学 Sendai University Sendai University Sendai University
- 雑誌
- 仙台大学紀要 = Bulletin of Sendai College (ISSN:03893073)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.1, pp.47-53, 2013-09-30
2 0 0 0 OA 教師のメンタルヘルスに関する研究とその課題
- 著者
- 田上 不二夫 山本 淳子 田中 輝美
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学年報 (ISSN:04529650)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, pp.135-144, 2004-03-30 (Released:2012-12-11)
- 参考文献数
- 77
- 被引用文献数
- 8 5
本論の目的は, 教師のメンタルヘルスに関わる研究を教師のストレスに焦点をあてて概観し, 今後の課題について検討を行うことである。はじめに, 教師のストレスに影響を及ぼす要因を, その職業の特性から3つ (職業の特殊性, 個人特性, 環境の特異性) に分類し, 概観した。そして, 要因間に複雑な関連はあるものの, 教育現場へのより具体的な提言を可能にするために, ある特別で限定された側面に焦点をあてた研究が必要であることや, 教師のストレス反応を引き起こす過程を明らかにするような研究が必要であると論じた。次に, 教師や学校組織によるストレス軽減のための方法について検討している研究を, その取り組みの形式から2側面 (教師のスキル向上と学校組織の再構成) に分類して概観した。最後に, 組織・個人双方向からのアプローチの重要性を指摘するとともに, 地域や学校関連機関との連携に関する研究の必要性について論じた。
2 0 0 0 IR 近世大阪市内における被差別部落の歴史
- 著者
- 牧 英正
- 出版者
- 大阪市立大学同和問題研究室
- 雑誌
- 同和問題研究 : 大阪市立大学同和問題研究室紀要 (ISSN:03860973)
- 巻号頁・発行日
- no.3, pp.53-106, 1979-03
2 0 0 0 OA 中州集 10卷 樂府1卷
- 著者
- (金) 元好問 輯
- 巻号頁・発行日
- vol.[2], 1300
2 0 0 0 OA 単語の持つ感情推定法の提案と単語感情辞書の構築
- 著者
- 武内 達哉 萩原 将文
- 出版者
- 日本感性工学会
- 雑誌
- 日本感性工学会論文誌 (ISSN:18845258)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.4, pp.273-278, 2019 (Released:2019-08-30)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 2 2
In this paper, we propose an emotion estimation method for words and its application to construct a word-emotion dictionary. Since the estimation of more delicate emotions in various natural language processing tasks is a crucial issue, we aim to estimate various emotions to a word. In order to realize it, we employ the distributional hypothesis and assume that an emotional word in a sentence influences the surrounding words. First, we collect more than 2,000 words expressing emotions from an emotion expression dictionary. By using these emotional words and a neural model based on Continuous Bag-of- Words (CBOW), we propose an automatic system to estimate the emotions of many ordinary words. As a result, emotion vectors for 20,000 words could be obtained. We carried out experiments to examine the accuracy of the vectors. It is confirmed that the generated emotion vectors reflect the emotion image for words that humans have.
2 0 0 0 OA 福岡市とその近郊における近代海浜リゾートの成立に関する研究
- 著者
- 麻生 美希
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.3, pp.1196-1203, 2015-10-25 (Released:2015-11-05)
- 参考文献数
- 52
本稿は、福岡市とその近郊を対象とし、近代における海水浴の発展とそれに関連した海浜リゾートの成立について明らかにすることを目的とした研究である。新聞記事を元に福岡における海水浴場成立の変遷とその特徴を捉え、海浜という好環境を生かした施設の立地について分析を行うことで、津屋崎・福間・奈多・西戸崎・箱崎・伊崎浦・百道は海水浴場にとどまらない海浜リゾートとして成立していたことが明らかとなった。特に箱崎と津屋崎は、多様なアクティビティが可能な初期の海浜リゾートであり、箱崎は福岡の都市の発展に寄与した海浜リゾートとして、津屋崎は産炭地域と深く結びついた娯楽と療養の両側面を持つ海浜リゾートとして成立していたという特色が明らかとなった。
2 0 0 0 OA 「組織開発」再考 : 理論的系譜と実践現場のリアルから考える
- 著者
- 中原 淳
- 出版者
- 南山大学人間関係研究センター
- 雑誌
- 人間関係研究 = Human Relations (ISSN:13464620)
- 巻号頁・発行日
- no.16, pp.211-273, 2017-03-31
南山大学人間関係研究センター公開講演会日時:2017年1月7日(土)13:30~17:00場所:南山大学名古屋キャンパス D棟DB1教室講演者:中原淳(東京大学大学総合教育研究センター)対談者:中村和彦(南山大学人間関係研究センター)
2 0 0 0 OA 西田幾多郎と「模倣」の問題 タルドへの小さな言及の波紋
- 著者
- 合田 正人
- 出版者
- 西田哲学会
- 雑誌
- 西田哲学会年報 (ISSN:21881995)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.57-70, 2018 (Released:2020-01-29)
Du moins à ma connaissance, on n’ a jamais mentionné un grand sociologue français Gabriel Tarde(1843‒1904)dans les textes, innombrables d’ailleurs, qu’on a consacrés, jusqu’ à maintenant, à la philosophie de Kitaroh Nishida. Le but de ma communication d’aujourd’hui, consiste, dans une telle situation, à vous montrer l’attention constante que prêtait Nishida à la notion d’“imitation”chez Tarde aussi bien que la profondeur de la compréhension de la part de Nishida à ce sujet. En France, c’est grâce à Gilles Deleuze(1925‒1995)et à son Différence et Répétiton(1968)que Tarde a été tiré du purgatoire, alors qu’au Japon, on lisait beaucoup Tarde dans les années 20‒30. Parmi les lecteurs ardents japonais de Tarde, on peut trouver de grands philosophes tels que Tetsuroh Watsuji(1889‒1960), Jun Tosaka(1900‒1945). En effet ils ont beaucoup apprécié la genie de Tarde ; et pourtant cela sous réserve que la notion d’“imitation”ne soit pas du tout suffisante pour éclaircir la formation de la société. Je ne sais pourquoi, on ne peut trouver le nom de Nishida dans le liste des philosophes ou des écrivains japonais qui s’intéressient à Tarde avant la deuxième guerre mondiale. Malgré cette omission, le fait, indéniable d’ailleurs, est que depuis son texte de 1918 jusqu’ à la fin de sa vie Nishida n’a cessé de mentionner Tarde, même si cela de manière si fragmentaire. A cela s’ajoute un autre fait que depuis 1913 Nishida se liait d’une amitié avec un sociologue japonais Shohtaroh Yoneda(1873‒1945)qui avait assisté réellement aux cours de Tarde à Paris A l’examen des remarques faites par Nishida concernat Tarde, on verra que Nishida a pris la notion d“’ imitation”pour jointure des monades et de la société,et l’acomparée à sa propre notion d“’éveil à soi(”Jikaku).On ne pourrait pas ne pas admirer l’intuition géniale de Nishida. Bref, Nishida était un des philosophes rares ou même le premier dans le monde, qui ait pu s’apercevoir du sens profond de la notion d“’ imitation”chez Tarde
2 0 0 0 レドックス活性を利用した抗体修飾と応用
- 著者
- 金井 求 生長 幸之助 豊邉 萌
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- MEDCHEM NEWS (ISSN:24328618)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.1, pp.33-37, 2023-02-01 (Released:2023-02-01)
- 参考文献数
- 11
アミノ酸選択的修飾反応は、天然アミノ酸のうち1種類のみを選択的に修飾する化学反応である。これまでに、システインやリジン側鎖の求核性を活用した反応は数多くの報告があり、これらの抗体修飾への応用は、医薬品(抗体-薬物複合体)として実用化に至っている。一方で近年の発展により、システインやリジン以外のアミノ酸に対する修飾反応も開発されている。しかし、その対象はペプチドや小さなタンパク質が多く、複数のドメイン・サブユニットの複合体である抗体への応用例は少ない。さらに、修飾抗体の機能までを評価した例は限られている。本稿では、アミノ酸や反応剤のレドックス活性を利用したチロシン、トリプトファン、メチオニン選択的修飾法をとりあげ、それらを抗体修飾法へと応用し、機能評価を行った事例について紹介する。
2 0 0 0 OA ゴキブリの生態
- 著者
- 高木 正洋
- 出版者
- Osaka Urban Living and Health Association
- 雑誌
- 生活衛生 (ISSN:05824176)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.2, pp.66-78, 1985-03-10 (Released:2010-03-11)
- 参考文献数
- 49
- 被引用文献数
- 2
2 0 0 0 OA 中国憲法における「民主集中制」の原則およびその課題
- 著者
- 江 利紅
- 出版者
- 麗澤大学中国研究会
- 雑誌
- 中国研究 (ISSN:09194177)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, pp.1-20, 2017-01-31
2 0 0 0 OA 開校十年誌
- 著者
- 天理外国語学校, 天理女子学院 [編]
- 出版者
- 天理外国語学校
- 巻号頁・発行日
- vol.1, 1935
2 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1934年09月05日, 1934-09-05
- 著者
- 長岡 千賀 内田 由紀子
- 出版者
- 一般社団法人 日本計画行政学会
- 雑誌
- 計画行政 (ISSN:03872513)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.2, pp.33-44, 2015-05-15 (Released:2022-04-18)
- 参考文献数
- 15
Secure management of nuclear power plants requires workers to be of sound mental health. Therefore, the aim of this study was to determine the occupational stressors faced by workers in nuclear power plants in order to propose practical measures to improve their mental health. The target population of this study consisted of nondestructive testing personnel and radiation control personnel (radiation control personnel supervise and coach workers, including nondestructive testing personnel, on radiation protection) in periodic inspections of nuclear power plants. Participants (n = 87) completed a self-administered questionnaire that measured variables such as interpersonal issues on the job, cooperation from coworkers, and the number of vacation days given. The results indicated that “interpersonal issues on the job” (e.g., “there is a possibility that they incur a great danger to a lot of people due to their own misjudgment or lack of instructions”) was a stronger stressor. Moreover, a low level of cooperation from coworkers and an inadequate number of vacation days were found to affect the mental health of radiation control personnel. We therefore provide suggestions for effective management of radiation control personnel in terms of opportunity for long-term training for skill acquisition, number of days off work, and culture in the nuclear power plant.