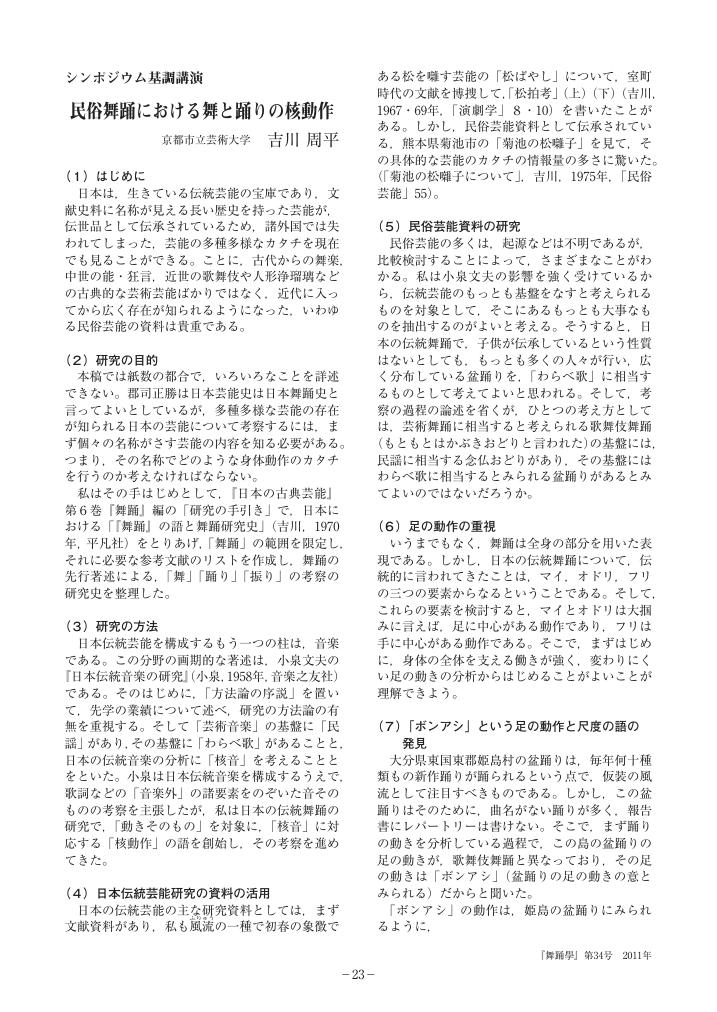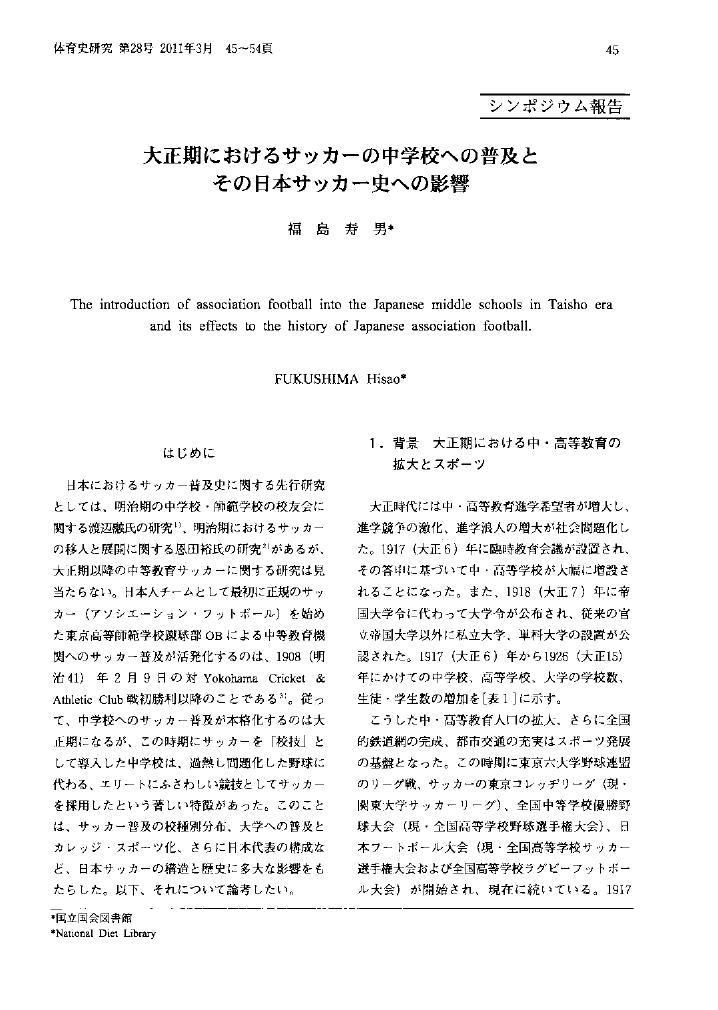2 0 0 0 OA インドにおける新州創設をめぐる人々の運動と政党政治―テランガーナ州創設の事例から
- 著者
- 三輪 博樹
- 出版者
- 一般財団法人 アジア政経学会
- 雑誌
- アジア研究 (ISSN:00449237)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.4, pp.72-89, 2016-10-31 (Released:2016-11-23)
- 参考文献数
- 34
Since the independence in 1947, India has adopted the federal system of government. In India, most of the states are organized along major linguistic lines. Language-based organization of state boundaries started in 1950s and completed in 1987. However, even today there are many demands for the creation of new states. In this paper, I focused on the case of the creation of Telangana state in the Southern India in 2014, and examined three points: (1) Which socio-economic factors contribute to the movements for new states. (2) How the federal and state governments respond to such movements. (3) What are the conditions for the creation of new states. According to the case of the Telangana statehood movement since 2000s, people’s movements for new states in India today are motivated by not only their political and economic interests or so-called identity politics based on caste, religion, etc., but also their demands for the fair distribution of wealth and educational opportunities and for the preservation of their own dignity and self-esteem. A research group led by Kalpana Kannabiran concludes that the Telangana statehood movement is “the emergence of a new politics that is committed to deliberating over the meanings of democracy and direct action.” The existence of such statehood movements is certainly one of the most important factors which contributes to the creation of new states. Nevertheless, whether they are actually created mostly hinges upon the decisions of the federal government and the major political parties. A new state is likely to be created when (1) most of the major political parties in the old undivided state consider that they can get political benefits from the creation of new state, and (2) the ruling party or parties at the center are one of such major political parties in the old undivided state. Although the existence of the statehood movements is important for the creation of new states, it is in fact only a trigger or just cause for the federal government to start the process of the creation of those states. However, if a “new politics” as Kannabiran et al. says is actually emerging in India and the recent movements for new states are one of such “new politics,” it may become more and more difficult for the federal and state governments to deal with such movements in the same old way.
2 0 0 0 IR 市区町村における包括的支援体制構築の課題 : 「共生社会」の実現に向けて
- 著者
- 野村 政子
- 出版者
- 立正大学社会福祉学会
- 雑誌
- 立正社会福祉研究 = Rissho journal of social welfare studies (ISSN:13454609)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.33, pp.45-60, 2018-02
資料
2 0 0 0 OA エクソソームの体内動態
- 著者
- 高橋 有己 西川 元也 高倉 喜信
- 出版者
- 日本DDS学会
- 雑誌
- Drug Delivery System (ISSN:09135006)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.2, pp.116-124, 2014-03-25 (Released:2014-06-25)
- 参考文献数
- 27
細胞から分泌される膜小胞であるエクソソームは、核酸・タンパク質・脂質などの内因性キャリアであることから、エクソソームを用いたDDSの開発が注目されている。エクソソームを用いたDDSの開発にはエクソソーム体内動態の制御法を開発することが必須であるが、それにはまずエクソソームの体内動態に関する情報の蓄積が必要不可欠である。しかしながら、その情報はいまだ乏しく、体系的な理解には至っていないのが現状である。本稿では、これまでに報告されたエクソソームの体内動態の特徴を整理するとともに、エクソソームの体内動態解析を目的とした我々の取り組みを紹介する。
2 0 0 0 OA 「違いが分かる男」はどんな男か
- 著者
- 加藤 由紀子
- 出版者
- 岐阜大学
- 雑誌
- 岐阜大学留学生センター紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.2002, pp.97-109, 2003-03
「基本的な動詞「分かる」は,初級の日本語の教科書にも必ず登場するものでありながら,その説明は教科書の中で十分になされていない。しかし,その語の意味は,和語の例にもれず幅広く,そのふるまいも特殊である。このことが,使用の際に日本語学習者が混乱する原因となっている。本稿では,「分かる」を「知る」と対比させながら,英訳・辞書の意味記述・教科書の取り扱いを通して,その意味特徴を明らかにし,アスペクチュアルな意味における特徴も明らかにすることを試みた。これらの考察から,以下のことが判明した。(1)「分かる」と「知る」の混同の原因のひとつは,辞書や教科書の意味記述において,一つあるいは二つの語で,対象語を置き換えることにある。置き換えられた語と,対象語には微妙な意味のずれがあるのに,それが無視されているのである。(2)「分かる」は,「知る」より意味範囲が広く,従来考えられていた意味に加え,「感覚的に察知する」ことを表す「感覚の動詞」という要素がある。(3)「分かる」は,「分かった」時点に視点を置きながらも,そこに至る過程を視野に入れている「線の動詞」であるのに対して,「知る」は,「知った」瞬間だけが意識される「点の動詞」である。
- 著者
- Zheng ZHANG Ru ZHANG Zhi-Zhen QIN Jia-Ping CHEN Jia-Ying XU Li-Qiang QIN
- 出版者
- Center for Academic Publications Japan
- 雑誌
- Journal of Nutritional Science and Vitaminology (ISSN:03014800)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.2, pp.143-150, 2018 (Released:2018-04-30)
- 参考文献数
- 42
- 被引用文献数
- 7 12
Whey protein is associated with improvement of metabolic syndrome. This study aimed to evaluate effects of whey protein on atherosclerosis in ApoE−/− mice. Male ApoE−/− mice were fed with a high-fat/cholesterol diet (HFCD), or HFCD supplemented with 10% or 20% whey protein for 18 wk. At the end of experiment, serum lipid profiles and inflammatory cytokines were assayed. Livers were examined using HE staining and Oil Red O staining. Aortas were used for en face and cryosection analyses to observe aortic lesions. Western blotting analysis was used to assess relative protein expression of cholesterol metabolism in the liver and aorta. No significant differences were observed in body weight or food intake among the three groups. Liver examination demonstrated decreased lipid droplets and cholesterol content in the whey-protein-supplemented groups. En face lesion of the aorta revealed a 21.51% and 31.78% lesion reduction in the HFCD supplemented with 10% and 20% whey groups, respectively. Decreased lesion was also observed in cryosection analysis. Whey protein significantly increased the serum high-density lipoprotein cholesterol level by 46.43% and 67.86%. The 20% whey protein significantly decreased serum IL-6 (a proinflammatory cytokine) by 70.99% and increased serum IL-10 (an anti-inflammatory cytokine) by 83.35%. Whey protein potently decreased lipogenic enzymes (ACC and FAS) in the liver and NF-κB expression in the liver and aorta. Whey protein significantly increased protein expression of two major cholesterol transporters (ABCA1 and ABCG1) in the liver and aorta. Thus, chronic whey protein supplementation can improve HFCD-induced atherosclerosis in ApoE null mice by regulating circulating lipid and inflammatory cytokines and increasing expressions of ABCA1 and ABCG1.
2 0 0 0 OA 岩手管内県郡立学校入学試験問題答案詳解
- 出版者
- 文明堂
- 巻号頁・発行日
- vol.大正1年度, 1912
2 0 0 0 OA B-55 漆喰の分光放射特性
- 著者
- 秋葉 友利 野部 達夫
- 出版者
- 公益社団法人 空気調和・衛生工学会
- 雑誌
- 空気調和・衛生工学会大会 学術講演論文集 平成15年 (ISSN:18803806)
- 巻号頁・発行日
- pp.1453-1456, 2003-08-20 (Released:2017-08-31)
2 0 0 0 OA 血栓溶解と抗炎症作用を併せ持つ小分子SMTPの脳梗塞治療薬開発
- 著者
- 蓮見 惠司
- 出版者
- 一般社団法人 日本血栓止血学会
- 雑誌
- 日本血栓止血学会誌 (ISSN:09157441)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.3, pp.278-283, 2021 (Released:2021-06-22)
- 参考文献数
- 20
プラスミノゲン・フィブリン結合を促進する化合物の探索において,我々がクロカビから単離した小分子SMTPは,生理的血栓溶解を促進するとともに抗炎症作用,抗酸化作用を併せ持ち,血栓性および塞栓性脳梗塞モデルで再灌流促進,浮腫抑制,出血転換抑制活性を示す.SMTP同族体の一つは脳梗塞治療薬として開発中である(第2相試験の症例組入れを2020年11月に完了).本稿ではSMTPの発見,作用機序,薬理活性,医薬開発について紹介する.
2 0 0 0 OA 大学生の一般的信頼が精神的健康の改善を導くメカニズム─信頼の解き放ち理論に基づく検討─
- 著者
- 吉本 貴博 長谷川 晃
- 出版者
- 日本感情心理学会
- 雑誌
- 感情心理学研究 (ISSN:18828817)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.2, pp.92-100, 2017-02-28 (Released:2017-04-06)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 2
Two studies examined relationships between general trust and improved mental health. Japanese university students participated in Studies 1 (n=325) and 2 (n=402) and they completed self-report measures assessing general trust, committed relationships, tendencies to make acquaintances, which is considered an aspect of extraversion, and negative affect. Consistent with the emancipation theory of trust, both studies indicated that general trust was negatively associated with committed relationships and positively associated with tendencies to make acquaintances. General trust was negatively associated with negative affect and neuroticism, and positively associated with proneness for experiencing positive emotions, which suggested an association between general trust and improved mental health. Study 2 indicated that tendencies to make acquaintances mediated the association between increased general trust and decreased negative affect. These findings suggest that general trust enables people to broaden their interpersonal relationships in daily life, and that the increase in available social support improve mental health. It is suggested that the emancipation theory of trust could be the basis for developing a model that explains mental health.
2 0 0 0 OA 日本の河川のフラクタル次元について
- 著者
- 神谷 茂保 カミヤ シゲヤス Shigeyasu Kamiya
- 雑誌
- 岡山理科大学紀要. A, 自然科学
- 巻号頁・発行日
- vol.28, pp.309-318, 1992
この小論の目的は, 日本の代表的な19の河川(図1に位置を示す)の実験的フラクタル次元, 分岐比を求め河川の様相などとの関連についての調査の結果を報告することである。本調査のためには, 昭文社発行の全日本道路地図を用いた。また私たちが直接得たデータ以外は, 理科年表(1987年版)及び文献中のデータを使用した。
2 0 0 0 OA 明治期における転地療養に相応しい場所の発見 陸軍脚気転地療養地としての軽井沢
- 著者
- 前田 一馬
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集 2018年度日本地理学会春季学術大会
- 巻号頁・発行日
- pp.000322, 2018 (Released:2018-06-27)
Ⅰ.研究の背景と目的 本研究は長野県北佐久郡軽井沢を事例として、明治期における陸軍の脚気転地療養地として当該地が利用されたその実態と経緯を明らかにする試みである。 一般的に転地療養地と見なされてきた場所は、古来温泉地であったが、近代化とともに新たな環境が転地療養に適した場所として見いだされてきた。典型的には、明治期に海水浴場が、大正期に結核サナトリウム治療の適地としての高原が、西洋医学的な環境観の導入とともに、新たな療養地になったものと理解されてきた。 しかし、陸軍脚気療養地の実態を検討すると、早くも明治10年代には「高原」(高地)が陸軍の脚気転地療養地として見出されていた。日本の医学が漢方医学から西洋医学へと転換していくなかでも、脚気の治療法は、日本で知られていた漢方の療法である転地療養が行われていた。また、その後の陸軍(細菌説)と海軍(栄養欠乏説)の対立(脚気論争)は有名である(山下1988)が、細菌説の導入に先んじて、脚気転地療養が陸軍に導入されている。このように陸軍脚気療養地として、「高原」が加えられた経緯は、どのようなものであっただろうか。 本研究では陸軍の脚気治療を取り巻く軍医本部の動向・見解および軽井沢の環境を、陸軍関連文書や新聞記事等から検討することで、医学的見解や環境認識が、「高原」を療養地にふさわしいとする契機となったことを考察する。Ⅱ.陸軍の脚気転地療養地 脚気とはビタミンB1の欠乏による栄養障害性の神経疾患である。近世後期には白米の普及と米食偏重により「江戸煩い」等の名をもって都市的な地域で流行した。脚気の流行は明治期には国民病と言われるほど流行し、徴兵制のもとで組織化が進められていた軍隊、とりわけ兵数の規模が大きい陸軍で患者数は増大した。1875(明治8)年から刊行された『陸軍省年報』によると、脚気は、「天行病及土質病」として捉えられており、陸軍各鎮台の治療実施とその経過の報告は他疾病に比べて詳細である。原因は降雨後の溢水による湿気などによって生じる不衛生な空気や土壌が病根を醸成する一種の風土病と推察されており、空気の流れや汚水の滞留を防止する対策が取られている。治療法は「転地療法奇験ヲ奏スル」と転地療養が効果をあげていることがうかがわれる。1870年代の各鎮台の主な転地療養地は多くの場合、温泉地が選択されている。つまり、患者が発生した場所(兵営)を避けることが重視されており、古来療養の場とみなされた温泉地が転地先として選ばれたと考えられる。Ⅲ.転地療養地の拡大:軽井沢にみる療養に相応しい場所 1880年代以降、陸軍の脚気転地療養地には多気山、榛名山、軽井沢といった温泉地ではない「高原」(高地)が加えられていくことになる。1881年8月、「幽僻且清涼ニシテ最モ適当」な転地先として高崎兵営の脚気患者130名が軽井沢に送られた(『陸軍省日誌』『高崎陸軍病院歴史』)。当時の軽井沢には、まだ外国人避暑地は形成されておらず、温泉を持たない衰退した旧宿場町であったが、残存する旅館が患者を受け入れることができた。後年、日清・日露戦争と多くの脚気患者の転地療養地として利用されていく軽井沢で行われていた治療法は『東京陸軍予備病院衛生業務報告(後)』によると、気候療養と記録されている。このように、高原の気候が陸軍において注目されていたことがわかる。 現代医学からみると脚気の転地療養は対処療法に過ぎず、治療法として正しくなかったかもしれない。しかし、当時の医学的知識が活用され、健康を取り戻すための療養に相応しいとされる「環境」は確かに存在した。この陸軍脚気療養地としての軽井沢は、後年の結核の療養と結びつけられた高原保養地としての軽井沢とは、異なる分脈から見出された療養(癒し)の景観であったと思われる。こうした場所が発見されていく過程に見え隠れする、当時の健康と場所の関係を、転地療養地の実態や近代期の社会的文脈性のなかで考察し、今後検討すべき課題とする。〔参考文献〕山下政三1988. 明治期における脚気の歴史. 東京大学出版会.
2 0 0 0 OA 患者からみた「よい看護師」 : その探求と意義(第17回日本生命倫理学会年次大会報告)
- 著者
- 小西 恵美子 和泉 成子
- 出版者
- 日本生命倫理学会
- 雑誌
- 生命倫理 (ISSN:13434063)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.46-51, 2006-09-25 (Released:2017-04-27)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 5
原則の倫理と徳の倫理は、生命倫理および看護倫理の最も主要なアプローチである。原則の倫理の焦点は行為にあり、徳の倫理は行為する人の特質やふるまいを吟味する。本研究の主題は徳の倫理であり、看護の実践・教育でめざす倫理的理想像、「よい看護師」を韓国、中国、台湾との共同研究として探求している。その一環として、日本の患者がとらえる「よい看護師」の特質を探索した。結果を報告し、あわせて、「よい看護師」探求の意義を述べる。Van Kaamの現象学的手法を用い、病名を知らされている26名のがん患者に半構成的インタビューを行った。結果、対象者らは、「よい看護師」とは、人としての関わりができ、かつ、専門職としての特質を備えた看護師であるとした。また、患者らは、看護師との人と人との関係性に価値をおいていた。「よい看護師」の探求は、東洋における徳の倫理の学問的発展に寄与する。また、ケアを受ける人にとっての「よい」ということの意味を明らかにすることも、「よい看護師」探求の意義である。
2 0 0 0 OA 科学裁判と鑑定
- 著者
- 中野 貞一郎
- 出版者
- 日本学士院
- 雑誌
- 日本學士院紀要 (ISSN:03880036)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.3, pp.181-196, 2009 (Released:2017-04-05)
2 0 0 0 OA 父恩
- 著者
- 市川三升<市川団十郎(2世 1688生)>//〔編〕,英一蜂<英一蜂(1世 1691生)>,小川破笠//〔画〕
- 巻号頁・発行日
- vol.乙, 1830
2 0 0 0 OA 生涯と舞踊-日本の民俗舞踊をめぐって
- 著者
- 吉川 周平
- 出版者
- 舞踊学会
- 雑誌
- 舞踊學 (ISSN:09114017)
- 巻号頁・発行日
- vol.2000, no.2Supplement, pp.18-19, 2000 (Released:2010-04-30)
2 0 0 0 OA シンポジウム基調講演 民俗舞踊における舞と踊りの核動作
- 著者
- 吉川 周平
- 出版者
- 舞踊学会
- 雑誌
- 舞踊學 (ISSN:09114017)
- 巻号頁・発行日
- vol.2011, no.34, pp.23-24, 2011 (Released:2018-07-31)
- 著者
- 斎藤 真己
- 出版者
- 日本森林学会
- 雑誌
- 日本森林学会誌 (ISSN:13498509)
- 巻号頁・発行日
- vol.96, no.6, pp.348-350, 2014-12-01 (Released:2015-04-02)
- 参考文献数
- 12
スギ花粉症対策の一環として,メタセコイア雄花の発育限界温度と有効積算温度を明らかにした。メタセコイアの雄花の発育限界温度はほぼ0°C となりスギと同様の値になったが,開花に要する有効積算温度は,計算上175.4°C・日となり,スギ(184~240°C・日)よりも低い値になった。次に,10°C に設定した人工気象器を用いてメタセコイアとタテヤマスギ,ボカスギで開花試験を行った結果,メタセコイアが最も早く開花した。これらの結果から,メタセコイアの花粉はスギよりも早く飛散が始まっており,その花粉はスギと共通抗原性があることから,居住区の近隣にメタセコイアがある場合,スギ花粉症患者はスギ花粉の飛散予測よりも早く花粉症を発症する可能性があると考えられた。
2 0 0 0 OA (シンポジウム報告)大正期におけるサッカーの中学校への普及とその日本サッカー史への影響
- 著者
- 福島 寿男
- 出版者
- 体育史学会
- 雑誌
- 体育史研究 (ISSN:09144730)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, pp.45-54, 2011 (Released:2022-10-20)
2 0 0 0 秋田県の地質鉱物 : 天然記念物(地質鉱物)緊急調査調査概報
- 著者
- 秋田県教育委員会編集
- 出版者
- 秋田県教育委員会
- 巻号頁・発行日
- 1995
- 著者
- 傅 貴 趙 勇 三宮 信夫
- 出版者
- 一般社団法人 システム制御情報学会
- 雑誌
- システム制御情報学会論文誌 (ISSN:13425668)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.5, pp.234-241, 2003
- 被引用文献数
- 2
A genetic algorithm (GA) is proposed to solve no-buffer jobshop scheduling problems. In the case of applying the standard GA to these problems, no-buffer constraint leads to a deadlock state in the meaning that an operation cannot be processed on the next machine in a pre-defined machine sequence. Because it causes many infeasible solutions, the standard GA cannot perform an efficient search. In this paper, we propose a new semi-active decoding method which avoids the deadlock to generate a feasible solution. Computer experiments on some modified benchmark problems show that the proposed GA performs efficient search and obtains equivalent or better schedules than other algorithms proposed previously.