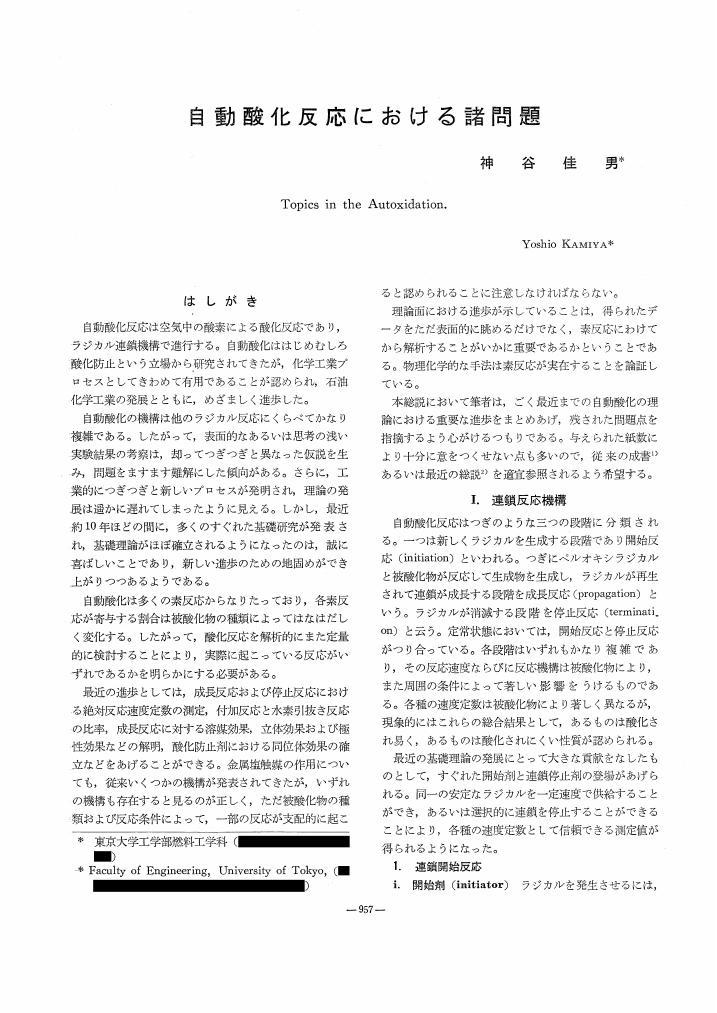2 0 0 0 OA 宇部共同義会五十年誌
- 出版者
- 宇部共同義会
- 巻号頁・発行日
- 1936
2 0 0 0 OA 双参照モデルにおける社会性の創発機構
- 著者
- 塩瀬 隆之 岡田 美智男 椹木 哲夫 片井 修
- 出版者
- 日本認知科学会
- 雑誌
- 認知科学 (ISSN:13417924)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.1, pp.66-76, 1999-03-01 (Released:2008-10-03)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1
According to a study of Situated Cognition, learning for individuals is not valid until they join into practice and acquire their own roles under the social environment. We call such a capability “sociality”, a capability of finding its own role or niche in the social environment through interactions with their restricted neighbors. Our main purpose in this paper is to clarify an emergent mechanism of such “sociality” from the viewpoint of a multiagent study. In this paper, we emphasize that the emergence of “sociality” seems to depend on the dual capabilities of an individual's referencing; self-referential and social-referential abilities. In addition, we present a learning model of an agent having such dual capabilities as a Bi-Referential Model, in which each referencing capability is implemented by an evolutionary computation method of classifier system. Finally we present simulation results obtained by the proposed Bi-Referential Model and discuss the relation between the emergent process of “sociality” and the changes of resources that are commonly available to the agents.
2 0 0 0 OA ハドソン・リヴァー派におけるアカデミズムの痕跡
- 著者
- 出羽 尚
- 出版者
- 宇都宮大学国際学部
- 雑誌
- 宇都宮大学国際学部研究論集 = Journal of the Faculty of International Studies, Utsunomiya University (ISSN:13420364)
- 巻号頁・発行日
- no.43, pp.1-14, 2017-02-01
2 0 0 0 OA 北京官話万物声音 : 附・感投詞及発音須知
2 0 0 0 OA 若年女性における体組成と栄養状態の関係
- 著者
- 今井 祐子 久保 晃
- 出版者
- 理学療法科学学会
- 雑誌
- 理学療法科学 (ISSN:13411667)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.2, pp.259-263, 2019 (Released:2019-04-26)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 2 3
〔目的〕若年女性に対し,体組成と栄養状態の関係を検討した.〔対象と方法〕健常成人女性40名に,体重,BMI,体脂肪率,体脂肪量,全筋肉量,右上肢筋肉量,左上肢筋肉量,体幹筋肉量,右下肢筋肉量,左下肢筋肉量,タンパク質量,ミネラル量,SMI,FFMI,FMIを計測した.計測値および算出値を比較し,相関係数を検討した.〔結果〕全筋肉量と体重,右上肢筋肉量,左上肢筋肉量,体幹筋肉量,右下肢筋肉量,左下肢筋肉量,タンパク質量,ミネラル量,SMI,FFMIに正の強い相関がみられた.〔結語〕全身筋肉量の低下が,タンパク質量の低下,ミネラル量の低下に関係している可能性があること,筋肉量の計測はタンパク質量,ミネラル量の指標になることが示唆された.
2 0 0 0 OA 多孔性無機膜によるナノ濾過
- 著者
- 都留 稔了
- 出版者
- 日本膜学会
- 雑誌
- 膜 (ISSN:03851036)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.2, pp.70-79, 1998-03-01 (Released:2011-03-04)
- 参考文献数
- 56
Nanofiltration by porous inorganic membranes is reviewed from the viewpoint of preparation methods as well as the applications. Sol-gel methods have been widely applied to fabricate porous inorganic membranes, and alumina, titania, zirconia and silica-zirconia have been successfully applied to fabricate inorganic membranes having nanofiltration performance.Summarized are also other preparation techniques including pyrolysis of polymeric membranes, organic/inorganic hybrid membranes, hydrothermal method for zeolite membranes, anodic oxidation, dynamic membranes, clay membranes. Applications of inorganic membranes reviewed are categorized into separation of electrolytes, nanofiltration of organic solutions, electro-ultrafiltration and membrane reactor application.
2 0 0 0 OA 中世漆器の技術転換と社会の動向
- 著者
- 四柳 嘉章
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.210, pp.29-47, 2018-03-30
本稿では中世的漆器生産へ転換する過程を,主に食漆器(椀皿類)製作技術を中心に,社会文化史的背景をふまえながらとりあげる。平安時代後期以降,塗師や木地師などの工人も自立の道を求めて,各地で新たな漆器生産を開始する。新潟県寺前遺跡(12世紀後半~13世紀)のように,製鉄溶解炉壁や食漆器の荒型,製品,漆刷毛,漆パレットなどが出土し,荘官級在地有力者の屋敷内における,鋳物師と木地・塗師の存在が裏付けられる遺跡もある。いっぽう次第に塗師や木地師などによる分業的生産に転換していく。そうしたなかで11~12世紀にかけて材料や工程を大幅に省略し,下地に柿渋と炭粉を混ぜ,漆塗りも1層程度の簡素な「渋下地漆器」が出現する。これに加えて,蒔絵意匠を簡略化した漆絵(うるしえ)が施されるようになり,需要は急速に拡大していった。やがて15世紀には食漆器の樹種も安価な渋下地に対応して,ブナやトチノキなど多様な樹種が選択されるようになっていく。渋下地漆器の普及は土器埦の激減まねき,漆椀をベースに陶磁器や瓦器埦などの相互補完による新しい食膳様式が形成された。漆桶や漆パレットや漆採取法からも変化の様子を取り上げた。禅宗の影響による汁物・雑炊調理法の普及は,摺鉢の量産と食漆器の普及に拍車をかけた。朱(赤色)漆器は古代では身分を表示したものであったが,中世では元や明の堆朱をはじめとする唐物漆器への強い憧れに変わる。16世紀代はそれが都市の商工業者のみならず農村にまで広く普及して行く。都市の台頭や農村の自立を示す大きな画期であり,近世への躍動を感じさせる「色彩感覚の大転換」が漆器の上塗色と絵巻物からも読み解くことができる。古代後期から中世への転換期,及び中世内の画期において,食漆器製作にも大きな変化が見られ,それは社会的変化に連動することを紹介した。
2 0 0 0 サハリンから北東日本海域における古代・中世交流史の考古学的研究
本研究では、ロシア連邦サハリン州を中心として、北東日本海域における古代から中世の交流の実態を考古学的に明らかにすることを目的とした。そのために中世陶器の流通の問題、北東アジアにおける在地土器生産の問題、北海道の中世チャシや東北北部の防御性集落、ロシア沿海州の土城について考古学的な調査を進めた。また関連分野では、建築史学、植生史、言語学、文献史学、炭素同位体年代測定法の各研究者をそろえ、学際的な研究組織を構成した。そして年2回の研究会議を開催し、研究成果の発表と検討を行った。2001年度より3年間にわたって、サハリン白主土城の測量調査および発掘調査を行った。初年度は測量調査を中心に行い、2・3年目に本格的な発掘調査を行った。その結果、土塁と堀に関して、版築を行っていること、金後半から元にかけて使われた1尺=31.6cmの基準尺度が使用されていたことが判明した。これは、在地勢力によって構築されたとは考え難く、大陸からの土木・設計技術である可能性が高いことが明らかとなった。また土城内部から出土したパクロフカ陶器片から成立時期を9〜11世紀頃の年代が想定できるが、版築技術などからは、土城内部の利用時期と土塁・堀の構築時期には、時間差があると考えられた。調査研究の成果を公表するために、最終年度に2月26・27日に北海道大学学術交流会館において北東アジア国際シンポジウムを開催した。シンポジウムは、1・白主土城の諸問題、2・北東アジアの古代から中世の土器様相、3・北東アジアの流通の諸様相の三部構成で、北東アジアにおける古代から中世にかけての交流の実態について発表が行われた。考古学だけではなく、文献史学・建築史学・自然科学など関連諸分野の研究報告が行われ、また国外からも7名の研究者を招聘した。白主土城の歴史的な位置づけのほか、北東アジアにおける土器様相、交易の様相について検討された。
2 0 0 0 OA 白隠禅の武芸への影響
- 著者
- 笠井 哲
- 出版者
- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.1, pp.180-183, 1994-12-20 (Released:2010-03-09)
2 0 0 0 OA アデノイド切除術後に開鼻声を生じ外科的治療を必要とした小児例
- 著者
- 髙尾 なつみ 榎本 浩幸 木谷 有加 田中 恭子 井上 真規 小林 眞司 折舘 伸彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)
- 巻号頁・発行日
- vol.123, no.5, pp.371-376, 2020-05-20 (Released:2020-06-05)
- 参考文献数
- 16
アデノイド切除術後の合併症として鼻咽腔閉鎖不全を来すことがあるが, 多くは保存的加療で消失する. 今回アデノイド切除術後に重度の開鼻声を生じ改善に外科的治療を要した一症例を経験した. 症例は5歳女児. 両側滲出性中耳炎, アデノイド増殖症に対し両側鼓膜チューブ留置術, アデノイド切除術を施行した.術後より聴力は改善したが, 開鼻声を来し発話明瞭度が低下した. 手術4カ月後から言語訓練を開始したが改善せず, 上咽頭ファイバースコピー, X 線所見より先天性鼻咽腔閉鎖不全症と診断し7歳9カ月で自家肋軟骨移植による咽頭後壁増量法を施行し症状は改善した. 術前予見可能性および発症後の対応について検討したので報告する.
2 0 0 0 乳幼児を対象とした乳製品中のアフラトキシンM1含有量調査
- 著者
- 寺谷 清香 紀 雅美 村上 太郎 高取 聡
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品衛生学会
- 雑誌
- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.4, pp.158-162, 2022-08-25 (Released:2022-08-30)
- 参考文献数
- 19
育児用の調製液状乳は,常温で一定期間保存でき,育児負担の軽減や災害時の利便性から平成31年3月に国内での製造・販売が開始された.AFM1は発がん性を有するカビ毒であるアフラトキシンB1 (AFB1)の代謝産物であって,AFB1に汚染した餌を摂食した家畜の乳に含まれる.現在,調製液状乳はもとより乳児用粉ミルク(調製粉乳)では基準値が設定されておらず,乳児では体重あたりの乳製品摂取量が多いため,摂取量には留意が必要である.本研究では,乳幼児の摂取量の多い乳製品についてのAFM1含有量の実態調査を行った.調査の結果,検出された乳製品のAFM1は0.001~0.005 μg/kgとなり,これまでに報告されている乳製品中のAFM1と比較して,極微量であった.乳幼児の栄養は乳製品に依存し,成人より多く摂取する可能性が否めないため,継続して調査を行う必要がある.
2 0 0 0 OA 2003年台風マエミー(0314号)による強風と宮古島での被害について
- 著者
- 奥田 泰雄 林 泰一 横木 研 丸山 敬
- 出版者
- 一般社団法人 日本風工学会
- 雑誌
- 風工学シンポジウム論文集 第18回風工学シンポジウム論文集
- 巻号頁・発行日
- pp.000038, 2005 (Released:2005-07-20)
When Typhoon Maemi passed over the Miyako Island, maximum instantaneous wind speed 74.1 m/s and minimum atmospheric pressure 912 hPa were observed at Miyakojima Local Meteorological Observatory on September 11, 2003. In connection with this high wind, the serious wind damage occurred on the Miyako Island since the 3rd Miyakojima Typhoon in 1968. We already reported on the meteorological situation and the high wind damage in Miyako Islands in some reports. As a result of investigating about the high wind of Typhoon Maemi using meteorological data, such as weather survey data in weather government offices and a weather radar echo charts, it turns out that the high wind were observed under the strong rain band on the west of the ring inside the double eye of the typhoon in this paper. We also classify the damage situation of buildings and structures and compare wind speed records observed at Miyakojima Local Meteorological Observatory with wind loads in Japan Building Code.
2 0 0 0 OA 描画活動における感情表現の発達過程
- 著者
- 古池 若葉
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.4, pp.367-377, 1997-12-30 (Released:2013-02-19)
- 参考文献数
- 39
- 被引用文献数
- 1 2
The purpose of this study was to clarify the kinds of strategies utilized to depict emotions in drawings and their developmental processes. Children aged 5, 6, 7, 9 and 11 (N=187), were asked to create a series of drawings depicting emotions (happy, sad, angry) in trees, and to report on their strategies. Drawings and reports were analyzed in relation to how children operated their knowledge when drawing. Two major findings were as follows.(1) Five kinds of strategies were identified from the reports: facial expressions (e. g., crying face for sad), gestures (e. g., drooping for sad), image scheme (e. g., a small tree for sad), emotion-evoking situations (e. g., a tree injured by a woodcutter for sad), and symbols (e. g., a tree in the rain for sad). These suggested that children utilized their knowledge toward emotions when drawing.(2) Drawings were scored in terms of the reported strategies and combination of the strategies. The results showed that as children grew they added more and more strategies to their repertoire, and depicted emotions while using more and more strategies.
2 0 0 0 OA 一、二年生の急所を掴む植物学
2 0 0 0 OA 戦後における本邦外国為替公認銀行の国際的立地展開
- 著者
- 芳賀 博文
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.2, pp.116-134, 1998-05-31 (Released:2017-05-19)
本稿の目的は, 第二次世界大戦後における邦銀の国際展開の空間的な側面を明らかにすることにある. 1960年代までは, 都市銀行, 特に外国為替専門銀行である東京銀行主体の海外展開がなされ, ニューヨークとロンドンの2大国際金融センターを主要な進出先としていた. 1970年代に入って邦銀の国際業務が拡大するとともに, 進出先は2大国際金融センター以外の都市へも広がっていく. 同時に, ニューヨークとロンドンに香港を加えた3大センターを軸とする, 世界三極体制がこの時期確立される. 1980年代は円高と好景気により, 地方銀行やその他の金融機関も加わって邦銀の海外進出が加速する. 地域的には, 北米や欧州といった先進国の都市やオフショアセンターへの進出が活発化する. そしてバブル経済後の1991年以降には, 店舗配置のリストラが起こるとともに, アジア諸国での急速な経済発展と当地域での規制緩和を受けて, 邦銀の国際展開はアジア指向が強くなった. こうした世界的な三極構造を基底とする邦銀の海外展開は, ニューヨーク・ロンドン・香港の3大国際金融センターをユーロ取引による外貨資金調達の主要な窓口とし, 取り入れた資金を主に日系企業の海外進出に伴う現地貸付として運用することで, それぞれの後背地域の都市間において比較的安定した階層的な関係を有しながら進出がなされて, 店舗ネットワークが形成されてきたと考えられる.
2 0 0 0 OA 自動酸化反応における諸問題
- 著者
- 神谷 佳男
- 出版者
- The Society of Synthetic Organic Chemistry, Japan
- 雑誌
- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.11, pp.957-974, 1968-11-01 (Released:2009-11-13)
- 参考文献数
- 152
- 被引用文献数
- 2 2