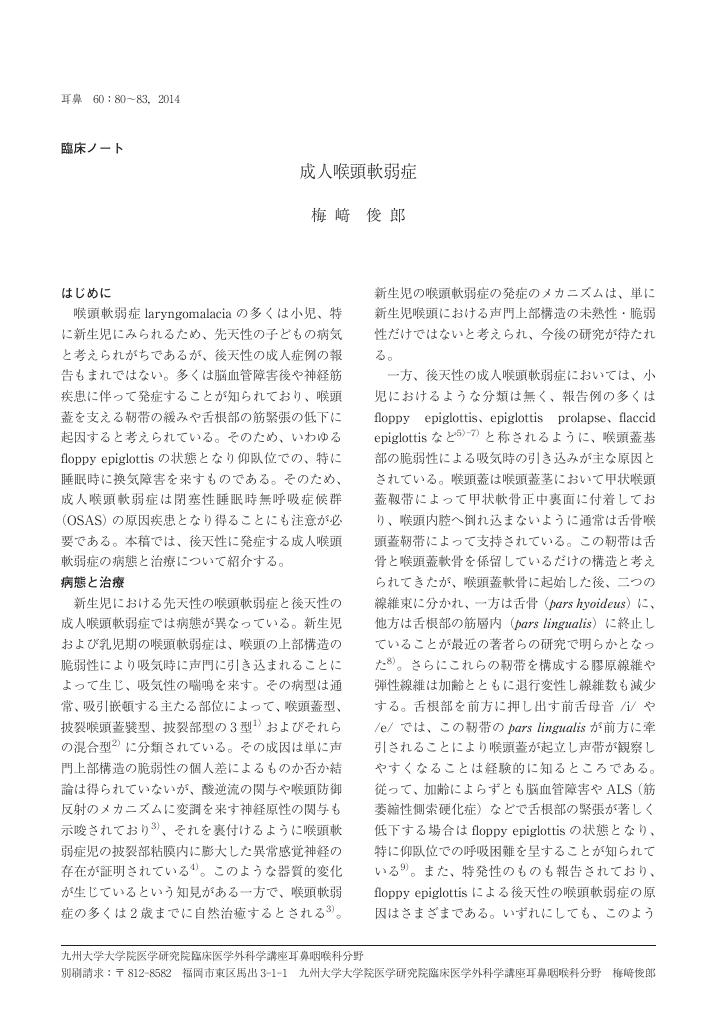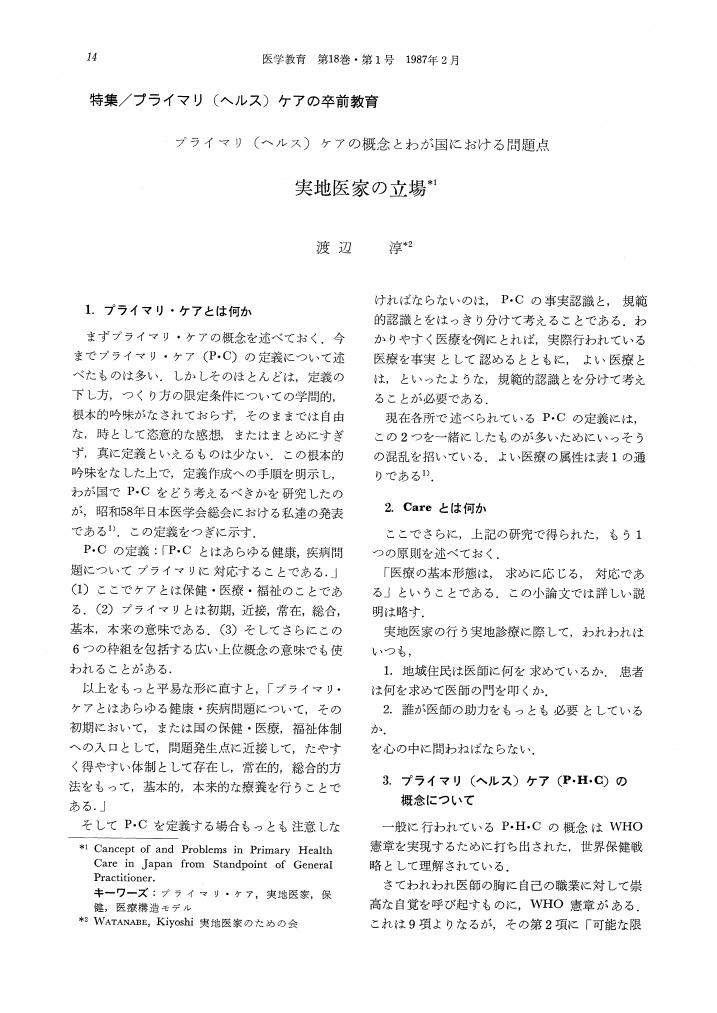2 0 0 0 OA 音楽療法における歌作り(ソングライティング)と オンライン実践への課題と可能性:文献調査
- 著者
- 猪狩 裕史
- 出版者
- 名古屋音楽大学
- 雑誌
- 研究紀要 (ISSN:02894785)
- 巻号頁・発行日
- no.40, pp.1-15, 2021-03
2 0 0 0 OA 郷土料理「たらおさ」の実態調査
- 著者
- 西澤 千惠子 上久保 陽子 阿部 なづき 吉村 悦郎
- 出版者
- 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会大会研究発表要旨集 平成28年度大会(一社)日本調理科学会
- 巻号頁・発行日
- pp.192, 2016 (Released:2016-08-28)
【目的】大分県の日田地方には、真鱈のえらと胃を干した「たらおさ」を甘辛く煮た「たらおさ」という食材と料理名が同じ、盆に食べられている郷土料理がある。しかし近年は料理を作る人も知っている人も減少してきている。今回は「たらおさ」の全容を解明する研究の一環として、「たらおさ」の現状を把握することを目的とした。【方法】別府市内にある大学の学生と大分県の北部に住んでいる人を対象に、認知度についてアンケート調査を行った。またインターネットの書き込みから、食べている地方を調べた。さらに現在「たらおさ」を製造している北海道の業者に、製造方法や歴史などの聞き取り調査を行った。【結果】大分県西部の日田地方、玖珠地方、北部の下毛地方、福岡県の博多市、大宰府市、うきは市、八女市、筑豊地方で食べられていることが判明した。「たらおさ」の他に、こんにゃく、干し竹の子や干ししいたけが入る場合もあった。北前船の積み荷に「干鱈」の記述があったり、明治時代に道南の松前地方で真鱈釣り漁業が始まったりしているので、この頃に「たらおさ」が製造され始めた可能性がある。その後道南の漁獲高が減少するに伴い、製造業者は徐々に北方に移り、現在では稚内市の3業者が、鱈の獲れる冬に棒鱈とともに製造しているに過ぎない。この大部分が北部九州に出荷されている。かつて博多や北九州の問屋に輸送された「たらおさ」は、これらの周辺に広まり、さらに日田街道を通って内陸の日田まで運ばれたので、現在もこの街道沿いで「たらおさ」が食べられているものと推測された。海産物が入手しにくかった内陸地方では最高のご馳走で、盆のもてなし料理として作られていたものと考えられる。
- 著者
- Natsumi SUSAI Tomohiro KUROITA Koji KURONUMA Takeshi YOSHIOKA
- 出版者
- BMFH Press
- 雑誌
- Bioscience of Microbiota, Food and Health (ISSN:21863342)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.2, pp.73-82, 2022 (Released:2022-04-01)
- 参考文献数
- 39
- 被引用文献数
- 4
Pellagra is caused by an abnormal intake and/or use of niacin, but its phenotypes are diverse. The phenotypes of pellagra can also be atypical, such as nausea. We previously reported a mouse model of pellagra-related nausea. However, the mechanism of this model is unclear. In this study, we found that the gut microbiota, which is thought to be a source of niacin, played an important role in the development of pellagra-related nausea in germ-free mice. We also investigated the gut microbiome. We compared urinary niacin metabolite levels and the dermal response between mice fed a normal diet and those fed a low-niacin diet to investigate the putative trigger of pellagra. Epoxyeicosatrienoic and hydroxyeicosatetraenoic acid levels were higher in mice fed a low-niacin diet compared with those fed a normal diet. Furthermore, histological studies indicated a dermatological response to the low-niacin diet. Interestingly, higher levels of oxidised fatty acids in response to the germ-free state were also observed. These findings indicate successful establishment of our newly established mouse model of pellagra via the gut microbiota. We believe that this model could enable the discovery of the putative cause of pellagra and phenotypes of pellagra that have not been recognised yet.
2 0 0 0 OA 鳥雀集 : 拾遺抒情詩
- 著者
- Itsuko Horiguchi Kazuo Koyama Azusa Hirakawa Mieko Shiomi Kaoruko Tachibana Katsuyuki Watanabe
- 出版者
- Food Safety Commission, Cabinet Office, Government of Japan
- 雑誌
- Food Safety (ISSN:21878404)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.2, pp.43-56, 2022 (Released:2022-06-24)
- 参考文献数
- 18
Key topics related to risk communication and food safety were investigated by three different expert groups. In this study, the Delphi method was used to systematically and iteratively aggregate experts’ opinions, and the topics to be communicated to consumers were expressed and prioritized. The opinions of three groups, consisting of 26 members of the expert committee (EC) from the Food Safety Commission of Japan (FSCJ), 29 local government officials (LGOs) from their respective food safety departments, and 25 food safety monitors (FSM) appointed by the FSCJ, were obtained in the period of June through September 2017. “Safety and security concept” was identified and ranked high in all groups. This topic identified “Zero-risk” demand of consumers without understanding risks as the reverse side of safety. The EC group prioritized additional issues, such as “concept of risk” and “safety costs and relevant risk management”. The LGO and FSM groups prioritized specific hazard items for food poisoning and preventive measures. With regard to the so-called “health foods”, the EC and LGO groups indicated insufficient transmission of scientific evidence from the government to consumers, and the FSM group indicated insufficient understanding by consumers of the food labeling system for health and nutrition. Because consumers do not fully understand all concepts of food safety, governments are encouraged to disseminate the probability of risk and the knowledge of risk reduction directly to the consumers by using simple and easy-to-understand terms.
- 著者
- Natsuki SUGIYAMA Hiroshi HASEGAWA Kentaro KUDO Ryo MIYAHARA Rikizo SAITO Chikashi MARUKI Masaru TAKASE Akihide KONDO Hidenori OISHI
- 出版者
- The Japan Neurosurgical Society
- 雑誌
- NMC Case Report Journal (ISSN:21884226)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.225-230, 2022-12-31 (Released:2022-07-27)
- 参考文献数
- 18
There are only a few case reports in which cholesterol crystals were found in the thrombus retrieved by mechanical thrombectomy for cryptogenic stroke, leading to a definitive diagnosis. We herein report a case of aortogenic embolic stroke diagnosed by the presence of rich cholesterol crystals in the retrieved thrombus and review the previously reported cases. A woman in her 80s was transferred as an emergency due to consciousness disturbance, right conjugate deviation, and severe left hemiparesis. Magnetic resonance imaging showed occlusion of the right middle cerebral artery (MCA) and acute infarction in the territory. The MCA was recanalized by thrombectomy using an aspiration catheter and stent retriever, and the symptoms improved. Although the physiological examination did not detect the embolic source during hospitalization, pathological examination of the thrombus revealed atheroma with numerous cholesterol crystal clefts and intermixing of fibrin. Contrast-enhanced computed tomography performed based on the pathological results showed atheromatous lesions in the aortic arch as the embolic source. As a subsequent treatment, medications of a strong statin and an antiplatelet agent were continued, and the patient had no recurrence. The finding that the retrieved thrombus is a simple atheroma containing cholesterol crystals with poor hemocytes suggests embolism due to plaque rupture. Pathological examination of the thrombus obtained by thrombectomy is one of the useful diagnostic approaches for stroke etiology and the determination of its treatment.
2 0 0 0 OA 発泡飲料製造法
- 著者
- 小武山 温之 中井 孝雄
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.5, pp.423-428, 1963-05-15 (Released:2011-11-04)
- 著者
- 大城 道子
- 出版者
- 日本オーラル・ヒストリー学会
- 雑誌
- 日本オーラル・ヒストリー研究 (ISSN:18823033)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.119-136, 2011-09-10 (Released:2018-12-10)
Roughly, the area that the Okinawan people have settled is classified into two, which are due to Pre-War settlement by migrant workers and the post-war repatriation from overseas. In modern Japanese society Okinawan people are newcomers, who have come together to form the "Okinawan" settlement. In doing so they endured the hard life on the mainland. However, they as the workforce have contributed to the development of modern Japan. Housing is a group of strategies, which has emphasized the structure of discrimination. As a consequence, the Okinawan people have pushed the return movement to Japan. Ethnicity was an important point for the organization and establishment of the Okinawan People's Congress.
2 0 0 0 OA クロム酸(6価クロム)中毒に対する治療方針
- 著者
- 山口 均
- 出版者
- 一般社団法人 日本集中治療医学会
- 雑誌
- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.1, pp.14-15, 2015-01-01 (Released:2015-01-19)
- 参考文献数
- 8
2 0 0 0 OA アイヌ-和人の民族関係史に関する文化人類学的再構築
本研究は、アイヌ-和人の民族関係史について文化人類学の観点から再構築を企図したものである。そのため、言論・社会運動、アイヌ文化研究、およびメディアの表象という3つの側面から、近・現代日本においてアイヌ・和人の双方に形作られてきた自己/他者認識の相互作用を主要な焦点と位置付け、それらの歴史的な展開相について批判的に検討するとともに、こうした問題系をアイヌをめぐる〈近代〉に対する実践的アプローチへと接合するために必要な基礎的情報の整備を行った
- 著者
- 堀田 浩貴 熊本 悦明
- 出版者
- 一般社団法人 日本泌尿器科学会
- 雑誌
- 日本泌尿器科学会雑誌 (ISSN:00215287)
- 巻号頁・発行日
- vol.85, no.10, pp.1502-1510, 1994-10-20 (Released:2010-07-23)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 1 2
夜間睡眠時勃起現象 (nocturnal penile tumescence: NPT) は, ほとんどの健康男子に認められる生理現象である. NPTの指標を測定することで性機能評価が可能であることから, NPTは臨床応用されてきているが, その基本となるべき年齢別正常値がこれまで整理されていなかった. そこで健康男子189例を対象にNPTの各指標を測定し, 日本人のNPTの加齢性変化について検討した.NPTの各指標は10歳を過ぎる頃急激な増加を示したが, この増加には思春期前後で劇的な変化を遂げる視床下部, 下垂体そして精巣系の加齢性変化の関与が考えられた. またNPT時間, 一回あたりのNPT持続時間のピーク以後の減少傾向にも androgen の低下の関与が考えられた. 陰茎周最大増加値 (一晩の最大陰茎周変化値), 陰茎周最大増加率 (陰茎周最大増加値の弛緩時の陰茎周値に対する割合) は50歳代後半からその減少傾向が強まったが, これには androgen の低下とともに陰茎血管系および陰茎海綿体の加齢性変化が関与している可能性が考えられた.NPTの各指標は加齢性変化を示すことが明らかとなり, 男性の性成熟あるいはその衰退を表す可能性が示唆された. また本邦におけるNPTの各指標の基準値が形成され, 今後の性機能の臨床において意義深いものと考えられた.
- 著者
- 水藤 昌彦
- 出版者
- 日本犯罪社会学会
- 雑誌
- 犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, pp.47-61, 2016 (Released:2017-10-31)
- 被引用文献数
- 1
本稿の目的は,2000年代半ばから開始され,現在も活発化を続けている刑事司法と福祉の連携によ る非行・犯罪をした人への対応を題材として,福祉機関の側からみたリスクとセキュリティ(安全の 保証策)に関する課題を検討することである.本稿では,まず刑事司法と福祉による連携の現状と特 徴を確認する.次に,このような刑事司法と福祉の連携が開始された契機,ならびに刑事司法と福祉 のそれぞれからみた連携の目的について検討する.続いて,福祉機関の認識するリスクとセキュリティ について考察する.刑事司法と連携する福祉機関によって認識されると考えられるリスクには,①支 援対象者による再犯のリスク,②支援者としての法的責任を問われるリスク,③他の支援機関との関 係が悪化したり,社会的評価が傷つくリスク,④福祉機関の他利用者,利用者家族との関係を悪化さ せるリスクの4つがあると考えられる.これらのリスクに対するセキュリティは,支援対象者の再犯 防止を過度に強調したり,サービスから排除したりすることにつながる可能性がある.福祉が刑事司 法に対して対等性・自立性を確保していくためには,自らの認識するリスクに対するセキュリティが 福祉の司法化という新たなリスクへつながる可能性をはらんだものである点について自覚することが 求められる.
2 0 0 0 OA AI倫理指針の動向とパーソナルAIエージェント
- 著者
- 中川 裕志
- 出版者
- 総務省情報通信政策研究所
- 雑誌
- 情報通信政策研究 (ISSN:24336254)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.2, pp.1-24, 2020-03-30 (Released:2020-03-31)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 1
シンギュラリティによって人間と同じような知的能力を持つAIが出現し、人間への脅威になりかねないという言説が流布した。これによって、AIにも倫理を守らせようという機運が高まったという状況もあってか、2016年ころからAI倫理指針の作成と公開が盛んになった。本論文では、2017年から2019年にかけて国内外で公開された多数のAI倫理指針のうち、影響力の大きな主要な指針に関して、AI制御、人権、公平性、非差別、透明性、アカウンタビリティ、トラスト、悪用、誤用、プライバシー、AIエージェント、安全性、SDGs、教育、独占禁止・協調、政策、軍事利用、法律的位置づけ、幸福などの倫理的テーマを各AI倫理指針がどのように扱ってきたかをまとめた。種々のAI倫理指針の公開の時間順序と合わせてみれば、AI倫理の内容の変遷を探ることができ、同時にAI技術、AI応用システムの開発を行うにあたって留意すべき点が明らかになる。また、これらの指針が誰を対象に起草されているか、すなわち名宛人を考察することによって、AI倫理指針を作成した組織の意図が見えてくる。次に、AI倫理指針のうちIEEE EAD ver2、1eで提案された個人データの収集、管理、保護をおこなう代理ソフトウェア、すなわちパーソナルAIエージェントの概念設計について述べる。これは、データ主体本人の個人データとその利用条件の記述されたデータベースであるので、これをデータ主体の死後に残されたディジタル遺産の管理に適用する場合の検討課題について述べた。
2 0 0 0 OA イギリス地理学における政策論的(再)転回をめぐる議論
- 著者
- 梶田 真
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Series A (ISSN:18834388)
- 巻号頁・発行日
- vol.85, no.4, pp.362-382, 2012-07-01 (Released:2017-11-03)
- 参考文献数
- 54
- 被引用文献数
- 1
本稿では,1990年代末期から2000年代中期にかけて主としてイギリスにおいて展開した政策論的(再)転回をめぐる論争を跡づけ,その内容を考察した.この論争の焦点は,反計量の動きから多様なかたちで展開していった1980年代以降のイギリス地理学の動きが政策的関わりの観点からどのように評価することができ,どのような可能性を持っているのか,ということにあった.この論争では,これらの研究がローカルな地域/政府スケールの政策に関して強みを持っていることが強調される一方で,その他のアプローチとの建設的な補完関係の構築や統合的な活用の重要性も主張された.また,建設的なかたちで公共政策に貢献する地理学を実現するためには,複線的な戦略が必要であることも示唆されている.
2 0 0 0 OA 成人喉頭軟弱症
- 著者
- 梅﨑 俊郎
- 出版者
- 耳鼻と臨床会
- 雑誌
- 耳鼻と臨床 (ISSN:04477227)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.2, pp.80-83, 2014-03-20 (Released:2015-03-01)
- 参考文献数
- 13
2 0 0 0 OA コミュニケーションにおけるビビッドネス効果に関する研究の現状と課題
- 著者
- 張 婷婷
- 出版者
- 日本マーケティング学会
- 雑誌
- マーケティングジャーナル (ISSN:03897265)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.1, pp.90-97, 2021-06-30 (Released:2021-06-30)
- 参考文献数
- 32
企業は消費者にメッセージを発信するとき,消費者の注意を引き付け,さらにメッセージを精緻に処理してもらうために,多彩な言葉,ビデオ,アニメーション,3Dなどの手段を利用している。これらのビビッド手段の利用によって,消費者行動にポジティブな影響を及ぼすと信じられている。しかし,ビビッドメッセージは常に消費者行動にポジティブな影響を及ぼすわけではない。そこで,本稿では,ビビッドネス効果(vividness effect)に関する既存研究を,(1)ビビッドネス効果の定義と分類,(2)ビビッドネス効果の有効性に関する研究,(3)ビビッドネス効果を有効とする媒介変数,(4)ビビッドネス効果の有効性を調整する要因という4つに分けて,レビューを実施する。また,ビビッドネス効果研究の発展のため,今後の研究課題として,(1)多感覚マーケティングにおけるビビッドネス効果に関する研究課題,(2)複数のビビッド要素の組み合わせによるビビッドネス効果に関する研究課題を提示す。
2 0 0 0 OA プライマリ (ヘルス) ケアの概念とわが国における問題点実地医家の立場
- 著者
- 渡辺 淳
- 出版者
- 日本医学教育学会
- 雑誌
- 医学教育 (ISSN:03869644)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1, pp.14-16, 1987-02-25 (Released:2011-08-11)
- 参考文献数
- 3
2 0 0 0 OA 写生論の再検討 : 子規と不折の場合
- 著者
- 柴田 奈美
- 出版者
- 岡山県立大学デザイン学部
- 雑誌
- 岡山県立大学デザイン学部紀要 = The bulletin of the faculty of design Okayama Prefectural University (ISSN:13489674)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.1, pp.13-18, 2008-03-31
2 0 0 0 OA E-Pと人類学的思考の歴史(<特集>人文学としての人類学の再創造に向けて)
- 著者
- 佐々木 重洋
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 文化人類学 (ISSN:13490648)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.2, pp.242-262, 2015-09-30 (Released:2017-04-03)
本稿の目的は、エヴァンズ=プリチャード(以下、E-P)の思考の軌跡と、彼が示していた問題意識と手法をあらためて批判的に再検討し、その知的遺産と検討課題を現在に再接続させることにある。本稿では、民族誌や論考、講義録や書簡から読み取ることができるE-Pの構想のなかでも、人間の知覚と認識、その作用に影響を与えるものとしての社会、それも決して閉じた固定的なシステムではなく、人間関係の動態的な諸関係としてのそれとは何かをモンテスキューにさかのぼりつつ自省し続けた点と、民族誌と人類学の主要な仕事としていち早く解釈という営為を強調した点にとくに注目し、その背景を再検討した。アザンデの妖術やヌアーの宗教を扱った民族誌においては、当時の西欧的思考の枠組みに対する疑義ないし違和感が表明されていたが、E-Pとその後進たちの遺産は、そこに「インテレクチュアル・ヒストリー派」としての省察がともなうかぎり、主知主義批判、表象主義批判や言語中心主義批判、主客二元論批判や心身二元論批判としても、今なお私たちにとって着想の源泉たり得る。さらに、共感や友情を強調したその人文学的経験主義からは、絶えず自己に立ち返り、自らが影響を受けている知的枠組みと社会背景に対する自省を保ちつつ、調査する者と調査される者のあいだの共約不可能性を乗り越えようとする姿勢を継承でき、それはフィールドワークと民族誌を取り巻く思想的、物理的環境が大きく変わりつつある今こそ、あらためて参照に値することを指摘した。今日、E-Pに立ち返って考えることは、モンテスキューを脱構築しつつ、人類学的思考が哲学や社会学はもとより、法学や政治学、経済学などと未分化の状態であった時点に立ち返って考えることにつながるものでもあり、今後の人類学が人文学とどのように関係すべきかという点も含めた人類学の知のあり方を模索するうえで一定の意義があると考える。