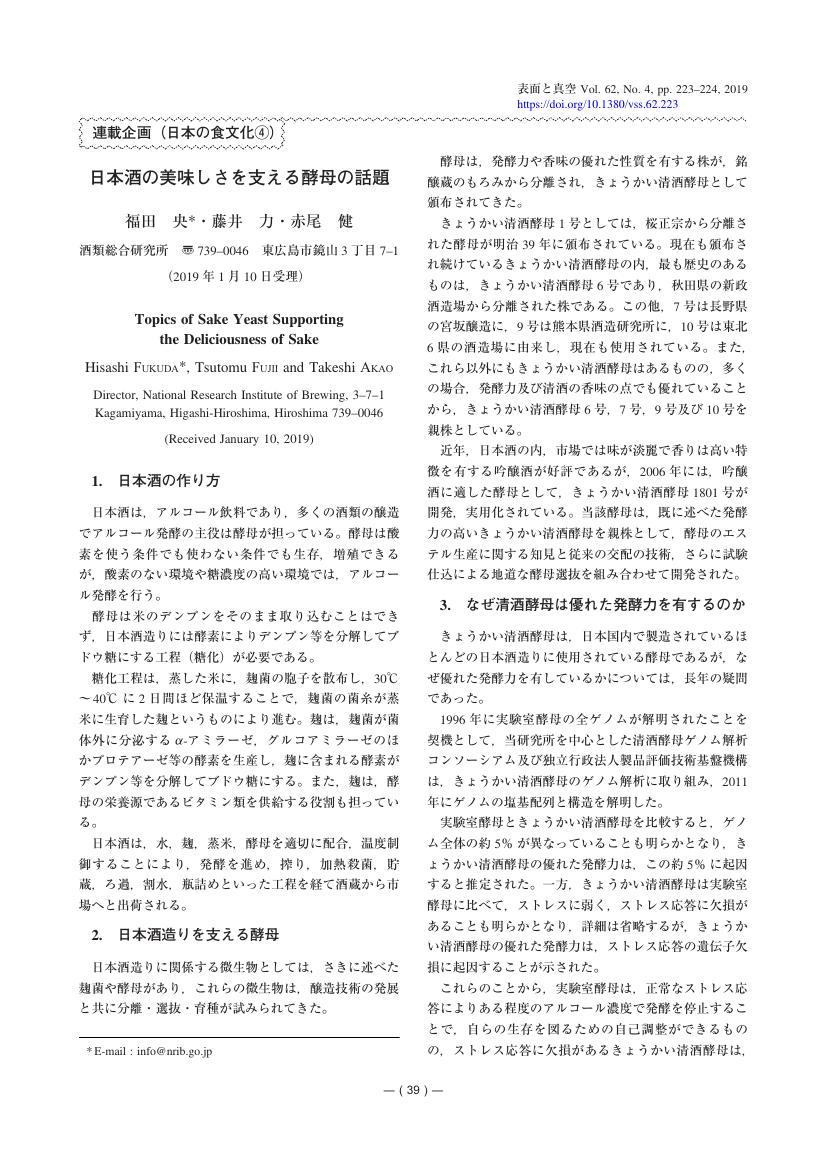2 0 0 0 IR 田畑忍先生に聞く-1-戦時下の同志社と私(法学部史)
2 0 0 0 OA IV.AKIと薬剤
- 著者
- 小林 大介 成田 一衛
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.110, no.5, pp.922-927, 2021-05-10 (Released:2022-05-10)
- 参考文献数
- 10
薬剤性腎障害(drug-induced kidney injury:DKI)とは,「薬剤の投与により,新たに発症した腎障害,あるいは既存の腎障害のさらなる悪化を認める場合」と定義される.臨床現場では,治療目的で投与した薬剤がしばしば腎障害を引き起こす.薬剤により,障害のメカニズムや発症様式にある程度のパターンがあり,そのパターンを把握することは有益である.
2 0 0 0 OA 外国人児童生徒・少数民族の教育的選択肢に関する国際比較 日本とタイ北部の事例より
- 著者
- 奴久妻 駿介 田中 真奈美 馬場 智子
- 出版者
- 多文化関係学会
- 雑誌
- 多文化関係学 (ISSN:13495178)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.3-18, 2016 (Released:2020-09-10)
- 参考文献数
- 24
本研究は、外国人児童・生徒および少数民族の教育を受ける権利を対象とし、多様な教育のアクセスの実態を日本とタイの事例を基にして明らかにした。国際比較の視点を導入することで、日本国内のマイノリティの就学の意味づけを問い直し、新たな研究と実践のアプローチに示唆を与えることを目的としている。日本の事例では、国内外国人学校4校を対象に、教員、児童・生徒を対象とした聞き取り調査を実施した。タイの少数民族の学校3校を対象にした現地調査は、教員・スタッフへのインタビューを実施した。結論として、中央政府が特定民族の草の根的教育場を公的に学校として認可したタイの事例は、日本のノンフォーマル教育としての地方学習室・日本語ボランティア教室の今後の展開や位置づけに重要な示唆を与えてくれるだろう。一方で、マクロ面(国および地方行政両面の社会システム、教育システム)での文化・言語保護や、ミクロ面(現場レベルの多様な教育方法)での人材確保、カリキュラム開発は両国の課題であることがわかった。
2 0 0 0 OA 桂文団治落語集
- 著者
- 三代目桂文団治 講演
- 出版者
- 三芳屋書店
- 巻号頁・発行日
- 1916
2 0 0 0 OA 宮沢賢治サハリン紀行ノート(第一部)
- 著者
- 加藤 多一 カトウ タイチ Taichi KATO
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.29-69, 1990-06
2 0 0 0 OA 神仏習合の歴史展開
- 著者
- 東海林 克也 ショウジ カツヤ Katsuya Shouji
- 雑誌
- 21世紀社会デザイン研究 : Rikkyo journal of social design studies
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.103-108, 2013
2 0 0 0 OA お答えします
- 著者
- 山崎 〓 幸田 清一郎
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 化学と教育 (ISSN:03862151)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.1, pp.103, 1989-02-20 (Released:2017-07-13)
2 0 0 0 OA 生活保護の厳格化を支持するのは誰か ―一般市民の意識調査を用いた実証分析―
- 著者
- 阿部 彩 東 悠介 梶原 豪人 石井 東太 谷川 文菜 松村 智史
- 出版者
- 社会政策学会
- 雑誌
- 社会政策 (ISSN:18831850)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.2, pp.145-158, 2019-11-30 (Released:2021-12-02)
- 参考文献数
- 19
本稿は,2016年に筆者らが行ったインターネット調査のデータを用いて,一般市民が生活保護制度の厳格化を支持する決定要因を分析した。具体的には,貧困の要因に関する自己責任論と,貧困の解決に関する自己責任論に着目し,その二つを峻別した上でそれらが人々の生活保護制度の厳格化に対する意見に影響するかを検証した。 本稿の分析から,まず,従来指摘されてきたようなワーキングプアが生活保護受給者を非難する対立構造についてはそれを裏付ける結果は得られなかった。次に,自己責任論については,貧困者当人に対して要因責任を求めるものと,解決責任を求めるものの二つが混在しており,両者は必ずしも一致しないことがわかった。生活保護制度の厳格化支持に対しては,両者ともに影響力を持っているものの,解決の自己責任論の方が要因の自己責任論よりもその影響力が大きいことがわかった。
2 0 0 0 OA 超越的次元のゆくえ 宗教経験の脳神経科学をふまえて
- 著者
- 冲永 宜司
- 出版者
- 宗教哲学会
- 雑誌
- 宗教哲学研究 (ISSN:02897105)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, pp.13-27, 2018-03-31 (Released:2018-05-11)
Neuroscience is almost able to estimate and control our states of consciousness. It is close to controlling even our spiritual pain or fear of death, which has been addressed by religion. This is almost an attempt to repeat the experience of transcendence by using scientific technology. In this paper, we examine where the transcendent dimension will be, as neuroscience develops.Then, we examine the views of modern science, which finds fundamentally different qualities in consciousness from those of classical science, whose purpose was to control nature regularly and repeatedly. One of the theories of modern science is neurotheology, which examines the possibility of reality affecting not only consciousness but also brain state. Another is quantum brain theory, which finds experience and will in the quantum state of superposition to which the classical laws of physics cannot apply. Both of these views find reality not only in subjectivity, but also in action and spontaneity, instead of finding reality only in objective material.Next, concerning the absence of the transcendent, we examine a religious belief that finds transcendence in our life experiences. As for this thought, the place of transcendence is nothing other than this world presented to us without abstraction, and transcendence to another world is no longer needed. There, spontaneity and purpose acquire their realities again.
2 0 0 0 OA 日本酒の美味しさを支える酵母の話題
- 著者
- 福田 央 藤井 力 赤尾 健
- 出版者
- 公益社団法人 日本表面真空学会
- 雑誌
- 表面と真空 (ISSN:24335835)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.4, pp.223-224, 2019-04-10 (Released:2019-04-10)
- 参考文献数
- 3
2 0 0 0 OA スペイン刑法における性犯罪規定の構造
- 著者
- 江藤 隆之
- 出版者
- 桃山学院大学総合研究所
- 雑誌
- 桃山法学 = St. Andrew's University Law Review (ISSN:13481312)
- 巻号頁・発行日
- no.32, pp.55-92, 2020-03-10
2 0 0 0 OA 増修洋人日本探検年表
- 著者
- 武藤 孝司
- 出版者
- 公益財団法人 産業医学振興財団
- 雑誌
- 産業医学レビュー (ISSN:13436805)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.3, pp.155-178, 2022 (Released:2022-01-13)
健康増進法に基づいた政策「健康日本21(第二次)」では、健康増進の主要な目標である健康寿命の延伸を図るために、生活習慣病の予防と社会生活上必要な機能の維持及び向上などが必要とされている。具体的な取り組みでは地域における活動だけでなく職域での産業保健活動も期待されている。全国民の約半数にあたる約6,000万人の労働者を対象として行われている産業保健活動に関する学術論文を検討した結果、産業保健活動が日本国民の健康寿命延伸に寄与している可能性が示された。
2 0 0 0 OA 理論の発展と完成としての自滅の過程
- 著者
- 唐木田 健一
- 出版者
- 科学基礎論学会
- 雑誌
- 科学基礎論研究 (ISSN:00227668)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.3, pp.17-21, 1983-12-25 (Released:2009-07-23)
- 参考文献数
- 13
我々は主として量子論の発生と展開を対象とし, 理論変化の過程を考察した。我々の結論は次のようにまとめることができる : 自然科学における基本理論の変化とは, (1) 伝統的理論に対抗して新理論が出現し, それが何らかの事情で多数派を形成してゆき旧理論が廃棄されるという過程ではなく, (2) 伝統的理論が《自滅》していく過程であること。イ) ここにおける自滅とは理論内部の矛盾に基づくものであり, ロ) 理論の外から, すなわち競合する理論あるいは伝統的理論を反証する実験事実によって, もたらされたものではないこと。(3) 理論は自滅によって完成される (すなわち限界づけられる) こと。(4) 理論の自滅の過程は同時に新理論の誕生と確立の過程とも呼ばれること。
- 著者
- 菊田 和代 三田村 仰 武藤 崇
- 出版者
- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 行動療法研究 (ISSN:09106529)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.3, pp.331-343, 2016-09-30 (Released:2019-04-27)
- 参考文献数
- 10
本事例では、うつ病と診断され、社会人になってから30年間にわたって抑うつ感や不安感を抱えてきた男性に、臨床心理士がアクセプタンス&コミットメント・セラピー(ACT)を行った。男性は特に出勤のしづらさを訴え、認知行動療法(CBT)を受けることを希望していた。男性の不安・抑うつ症状は軽度残存しており、自分の能力に関する思考や不安を一時的に回避するための行動が日常的に用いられていた。男性は、自身の業務上のパフォーマンスや他者評価をさほど偏りなく認識していたが、それらの認識は男性の行動に影響を与えておらず、活動内容が固定されていた。セラピストはACTの初心者であり、本事例の中でクライエントとともにACTの実際をさらに学ぶことができたので、それを報告し考察する。
2 0 0 0 OA フィールド調査法の窮状を超えて
- 著者
- 松田 素二
- 出版者
- The Japan Sociological Society
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.4, pp.499-515, 2003-03-31 (Released:2009-10-19)
- 参考文献数
- 45
- 被引用文献数
- 1
社会調査のなかでも近年, エスノグラフィーやライフヒストリーなどの手法を用いた研究の進展はめざましいものがある.こうした調査の興隆とは裏腹に, 方法論的にみると, フィールド調査に代表される質的調査は, 一貫して周縁的位置に置かれてきた.さらに1980年代半ばに起こった民族誌への根源的懐疑の思想運動は, フィールドワークとそれにもとづくエスノグラフィーの可能性を基本的に否定する方向に作用した.フィールド調査の未来はあるのだろうか.この問いかけを考えるとき, 1970年代に行われた社会調査をめぐる似田貝-中野「論争」は, 今日的意義を失っていない.調査する者とされる者とのあいだの「共同行為」として調査を再創造しようという似田貝と, そこに調和的で啓蒙的な思潮を読みとり, する者とされる者とのあいだの異質性をそのままにした関係性を強調する中野のあいだの論争は, 時代性を超えて, 2つの重要な問題を提起している.ひとつは, セルフをどのように捉えるかという問題であり, もうひとつは, 立場の異なるセルフ間の理解と交流はいかにして可能かという問題である.前者は, 共同性 (連帯性) をめぐる存在論の議論に連なり, 後者は, ロゴスと感性による対象把握に関わる認識論の議論につながっていく.本論では, フィールド調査における, 実感にもとづく認識と理解の可能性を検討する.
2 0 0 0 OA 教材文読解における操作活動が歴史の誤認識修正に及ぼす効果
- 著者
- 麻柄 啓一 進藤 聡彦
- 出版者
- 日本教授学習心理学会
- 雑誌
- 教授学習心理学研究 (ISSN:18800718)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.2, pp.67-76, 2012-12-18 (Released:2017-10-10)
本研究では「徳川幕府は全国の大名から年貢を取っていた」という誤った認識(麻柄,1993)を取り上げる。高校の教科書では,例外として一定期間「上げ米(大名がその石高の1%を徳川家に差し出す)」が行われたことが記述されている。ここで,「○○の期間には××が行われた」(命題a)に接したとき,これを「○○以外の期間には××は行われなかった」という形(命題b)に論理変換できれば,先の誤りは修正される可能性がある。実験1では大学生62名を対象にこの関連を検討したところ,年貢の行方を問う問題(標的問題)での正答者は誤答者より,命題の変換に優れている傾向が示唆された。実験2では大学生34名を対象に,論理変換を援助することにより誤った認識の修正が図られるか否かを検討した。その結果,援助が誤った認識の修正を促進する効果をもつことが確かめられた。知識表象を変形することは操作と呼ばれるが(工藤, 2010),上記の論理変換も操作の1つであり,操作の成否が誤った認識の修正に関わることを示すものとなった。
- 著者
- 栗本 猛
- 出版者
- 富山大学総合情報基盤センター
- 雑誌
- 富山大学総合情報基盤センター広報 (ISSN:13490796)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.22-23, 2004-03
メールの添付ファイルで問題となる事例を紹介する。