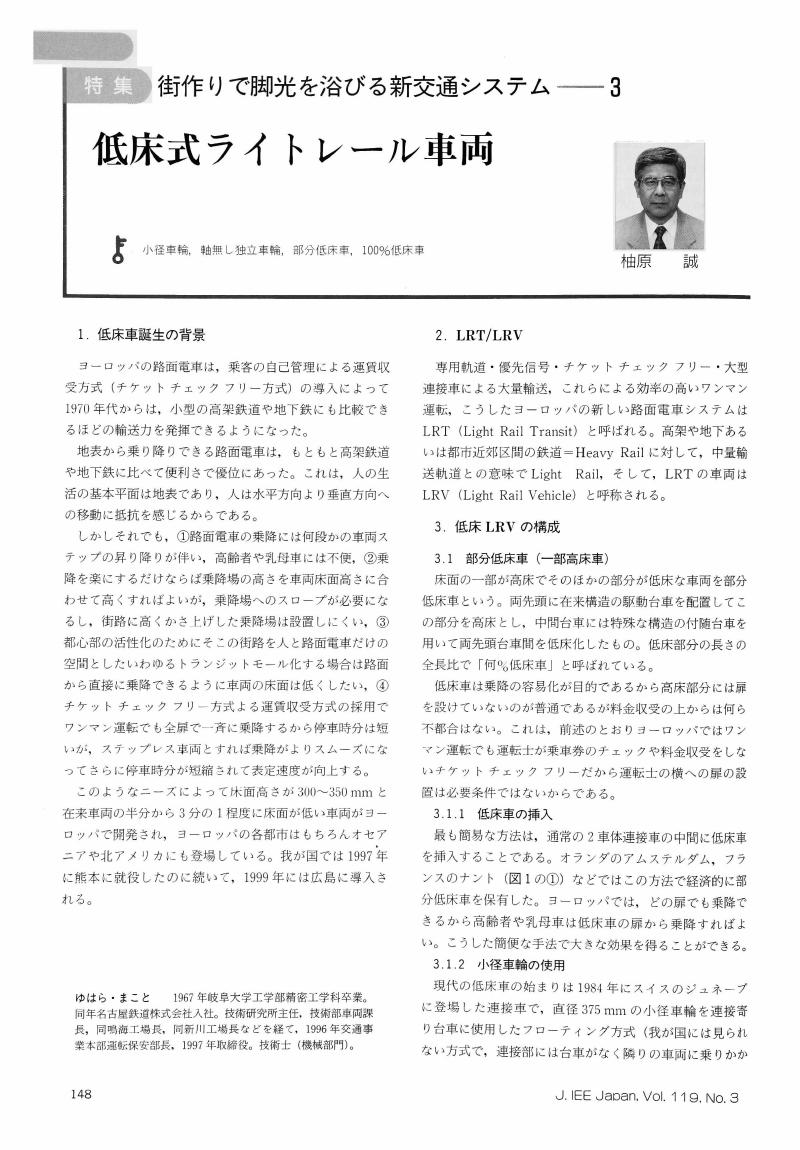2 0 0 0 IR 秋田地方におけるロシア正教の展開
- 著者
- 持田 行雄
- 出版者
- 秋田大学教育文化学部
- 雑誌
- 秋田大学教育文化学部研究紀要 人文科学・社会科学 (ISSN:1348527X)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, pp.23-39, 2003-03
2 0 0 0 OA 明治神宮と靖国神社との御関係
2 0 0 0 OA 『ロリータ』におけるフランス語使用の問題
- 著者
- 秋草 俊一郎
- 出版者
- 一般財団法人 日本英文学会
- 雑誌
- 英文学研究 (ISSN:00393649)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, pp.97-110, 2006-11-20 (Released:2017-04-10)
2 0 0 0 OA 音声認識におけるDeep Learningの活用
2 0 0 0 船井幸雄の聖地論
- 著者
- 寺石 悦章
- 出版者
- 四日市大学
- 雑誌
- 四日市大学総合政策学部論集 (ISSN:1347068X)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.23-39, 2008
2 0 0 0 OA 低床式ライトレール車両
- 著者
- 柚原 誠
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電気学会誌 (ISSN:13405551)
- 巻号頁・発行日
- vol.119, no.3, pp.148-151, 1999-03-01 (Released:2008-04-17)
- 参考文献数
- 4
2 0 0 0 IR 薩長盟約と龍馬伝説
- 著者
- 山岡 悦郎 YAMAOKA Etsuro
- 出版者
- 三重大学人文学部文化学科
- 雑誌
- 人文論叢 (ISSN:02897253)
- 巻号頁・発行日
- no.30, pp.107-122, 2013
慶応2年1月の薩長盟約における龍馬周旋説と龍馬立役者説は共に、それに対する対抗仮説が成立しうる仮説であり、真偽不明の伝説である。しかしこれらの伝説についての考察は歴史学における幾つかの問題に改めて目を開かせてくれるという側面を持つ。
2 0 0 0 明治以降教科書総合目録
2 0 0 0 OA 近世紀聞
- 著者
- 条野伝平, 染崎延房 編
- 出版者
- 金松堂
- 巻号頁・発行日
- 1886
2 0 0 0 OA 現代中国の主権論 ―「一帯一路」 構想の示唆するもの
- 著者
- 石井 知章
- 出版者
- 日本政治学会
- 雑誌
- 年報政治学 (ISSN:05494192)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.1, pp.1_181-1_203, 2019 (Released:2020-06-21)
中華人民共和国の成立 (1949年) とともに、主権理論は共産主義イデオロギーとして、現行憲法においても社会主義 (共産主義) 原理の根幹をなす 「人民主権」 として規定されてきた。だが、1990年代以降、グローバリゼーションの急速な展開にともない、主権理論が再び脚光を浴びると、人権、人道的干渉、途上国への民主化支援、グローバル・ガヴァナンス、経済グローバル化などの展開とともに、国際関係・国際法における 「伝統的主権」 論が大きく動揺していった。こうしたなかで、主権の時代遅れ論、主権の再配分、ウェストファリア体制の終焉といった考え方が登場すると、主権理論をめぐる論争が展開され、新しい主権理論の探究も急速に広がってきた。それらのことを象徴的に示しているのが、現在、習近平体制が精力的に推し進めている中国主導による 「逆グローバリゼーション」 としての経済外交戦略、すなわち 「一帯一路」 構想である。本稿は、一党独裁体制下における 「伝統的主権」 論が、とりわけ現代中国で影響力を強めているC. シュミットの憲法論・政治論との関連で理論的にどのようにとらえられ、かつどのように変化してきたのかについて概観する。
2 0 0 0 OA 台所で発生するヌメリの成分と塩素系洗浄剤による洗浄
- 著者
- 矢島 和美 村田 里美 山岸 弘 杉山 典久 米山 雄二
- 出版者
- 一般社団法人 日本家政学会
- 雑誌
- 一般社団法人日本家政学会研究発表要旨集 59回大会(2007年)
- 巻号頁・発行日
- pp.124, 2007 (Released:2008-02-26)
【目的】 台所の排水口などに発生するヌメリは手で触りたくない汚れであり、次亜塩素酸ナトリウムを主成分とする塩素系洗浄剤による掃除が一般に行われている。しかし、塩素系洗浄剤は特有の臭気を有するため、短時間で掃除を済ませることが望まれている。そこで、ヌメリを発生する原因菌とヌメリの構成成分を把握し、ヌメリの効率的な洗浄について検討した。 【方法】 一般の5家庭の台所排水口からヌメリを採取し、TSA培地で培養し菌種を同定した。アルギン酸ナトリウム水溶液を塩化カルシウム水溶液に滴下して調整したアルギン酸カルシウムゲルをヌメリモデルとし、次亜塩素酸ナトリウムと添加剤をこのヌメリモデルに作用させたときの分解状態を観察し、目視判定により、洗浄試験を実施した。 【結果】 採取したヌメリの菌種を同定した結果、、Pseudomonas属が最も多く存在していることが分かった。この、Pseudomonas属の菌と食品を接触させたところヌメリを発生したことから、ヌメリの原因菌は、Pseudomonas属であると推定した。また、Pseudomonas属は細胞外多糖としてアルギン酸を産出すると報告されている1)ことから、ナフトレゾルシン呈色試験法によるヌメリ中のアルギン酸の同定を試みた結果、ヌメリにアルギン酸が存在することが確認できた。アルギン酸を成分とするヌメリモデルを用いた洗浄試験の結果、次亜塩素酸ナトリウムにアルカリ金属炭酸塩を添加することにより、アルギン酸の分解を促進することが分かり、実際にヌメリに対する洗浄試験においても素早い洗浄効果が確認できた。 文献1)森川正章,科学と生物,vol.41,No.1,(2003)
2 0 0 0 IR 池田政権のヨーロッパ外交と日米欧「三本の柱」論
- 著者
- 池田 慎太郎
- 出版者
- 広島市立大学国際学部 (Hiroshima City University, Faculty of International Studies)
- 雑誌
- 広島国際研究 (ISSN:13413546)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.13-23, 2007
2 0 0 0 IR 池田勇人の対外認識とアジア政策
- 著者
- 李 炯喆 LEE Hyong Cheol
- 出版者
- 県立長崎シーボルト大学
- 雑誌
- 県立長崎シーボルト大学国際情報学部紀要 (ISSN:13466372)
- 巻号頁・発行日
- no.3, 2002-12-20
2 0 0 0 OA 地域交通システムの成立と発展 高知県を事例に
- 著者
- 加藤 浩徳 志摩 憲寿 中川 善典 中西 航
- 出版者
- 社会技術研究会
- 雑誌
- 社会技術研究論文集 (ISSN:13490184)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.70-85, 2012 (Released:2012-10-03)
- 参考文献数
- 20
本論文は,高知県を対象として,交通システム成立の経緯を整理するとともに,その経緯と社会経済的要因や政治的要因との関係を分析するものである.同県の広域交通ネットワークの発展経緯を,古代~中世,近世,明治~戦前,戦後の4つの時代区分にしたがって整理した.その結果,高知県は,険しい四国山地と海に囲まれた地域であったため,古代から現在に至るまで,海路による広域交通ネットワークに頼らざるを得なかったこと,県領域内の閉鎖的な交通政策が広域旅客交通の発展を妨げたこと,高知県の陸路ネットワークの整備は,主に政治的要因によって実施されてきたこと,高知県の海上交通ネットワークは,一貫して関西地方との経済的結びつきのもとに発達してきたこと,四国遍路が高知県内の技術に与えた影響が大きいことなどを明らかにした.
2 0 0 0 OA 現代ロシアの自国史教科書の動向―20世紀史の描写を中心に―
- 著者
- 立石 洋子
- 出版者
- 東北大学東北アジア研究センター
- 雑誌
- 東北アジア研究 (ISSN:13439332)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.133-146, 2016-02-29
2 0 0 0 OA 遺品整理業のエスノグラフィー(1) : 宝塚市と西宮市の事例から
- 著者
- 藤井 亮佑 Ryosuke Fujii
- 雑誌
- 関西学院大学社会学部紀要 (ISSN:04529456)
- 巻号頁・発行日
- no.129, pp.51-61, 2018-10-31
2 0 0 0 OA 「黒地の絵」-松本清張のダイナミズム- 評伝松本清張:昭和33年
- 著者
- 加島 巧
- 出版者
- 長崎外国語大学
- 雑誌
- 長崎外大論叢 = The Journal of Nagasaki University of Foreign Studies (ISSN:13464981)
- 巻号頁・発行日
- no.16, pp.1-36, 2012-12-30