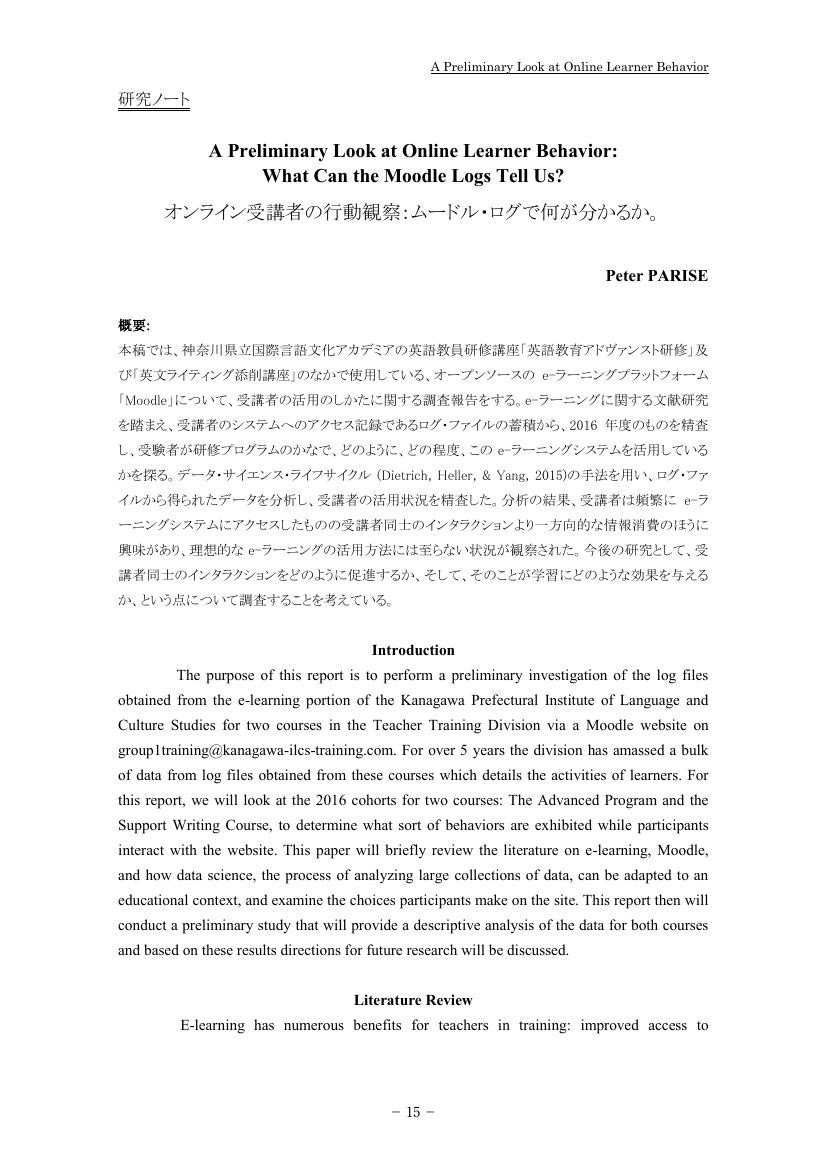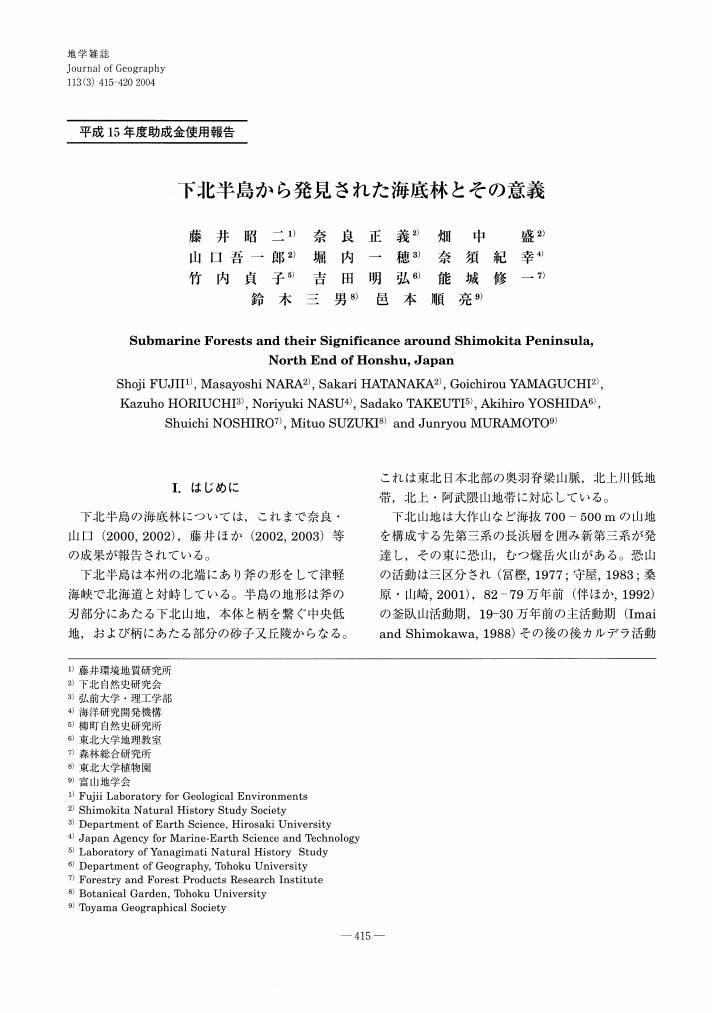1 0 0 0 OA ストロボ光に対するマアジの回避行動
- 著者
- 安 永一 有元 貴文
- 出版者
- 公益社団法人 日本水産学会
- 雑誌
- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.6, pp.713-718, 1994-11-25 (Released:2008-02-29)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 4 6
The avoidance response of the jack mackerel Trachurus japonicus to a strobe light barrier was investigated in the laboratory, by electrocardiogram measurement. The avoidance response varied with the strobe flash frequency (1.7-430 Hz) and strobe light intensity. Avoidance was greatest at flash frequencies of 5 and 10 Hz and clearly decreased as the strobe light intensity (15 Ix•s) was reduced. Heart rate increased when the fish stayed in the dark section of the tank or approached the barrier, but decreased when fish avoided or passed through the barrier or strobe light. Therefore, heart rate change can be used as an index of fish response to the effect of strobe light stimuli.
1 0 0 0 OA 仏教経典にみる洪水の問題について
- 著者
- 春日井 真英
- 出版者
- JAPANESE ASSOCIATION OF INDIAN AND BUDDHIST STUDIES
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.1, pp.172-173, 1983-12-25 (Released:2010-03-09)
1 0 0 0 OA 青年-両親関係におけるコンフリクトの多様性とその背景要因
- 著者
- Nobuhiro Tanaka Masato Nakamura Takashi Akasaka Kazushige Kadota Shirou Uemura Tetsuya Amano Nobuo Shiode Yoshihiro Morino Kenshi Fujii Yutaka Hikichi for the CVIT-DEFER Registry Investigators
- 出版者
- 日本循環器学会
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- pp.CJ-16-1213, (Released:2017-04-26)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 22
Background:Clinical use of fractional flow reserve (FFR) has been rapidly increasing, but outcomes after FFR-based coronary intervention in Japanese daily clinical practice have not been well investigated.Methods and Results:The prospective multicenter cardiovascular intervention therapeutics registry (CVIT)-DEFER enrolled consecutive patients for whom FFR measurement was clinically indicated. This study comprised 3,857 vessels in 3,272 patients. Lesions were categorized into 4 groups according to FFR result and revascularization strategy: group 1: FFR >0.8, and deferral of PCI (n=1992); group 2: FFR >0.8, then PCI (n=230); group 3: FFR ≤0.8, and deferral of PCI (n=506); and group 4: FFR ≤0.8, then PCI (n=1,129). The event rate for deferred lesions was significantly low compared with that for PCI lesions (3.5% vs. 6.6%; P<0.05). Vessel-related events occurred in 62 (3.1%), 11 (4.8%), 25 (4.9%), and 79 (7.0%) patients in groups 1, 2, 3, and 4, respectively. PCI for lesions in which FFR was >0.8 (group 2) showed no improvement in the event rate compared with a defer-strategy. On the other hand, deferred lesions with lower FFR values had a higher risk of vessel-related events.Conclusions:A FFR-based revascularization strategy in daily clinical practice was safe with regard to vessel-related events.
1 0 0 0 OA ハワイ州オアフ島のホノルル火山活動に伴う火山地形
- 著者
- 黒田 圭介 安永 典代 磯 望
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集 2007年度日本地理学会春季学術大会
- 巻号頁・発行日
- pp.181, 2007 (Released:2007-04-29)
I.はじめに Hawaii諸島のOahu島は,Waianae山脈とKoolau山脈の2つの開析された盾状火山から構成されており,ホットスポット上に形成された火山島として知られる.Oahu島西部のWaianae盾状火山は2.2-3.8(Ma),東部のKoolau盾状火山は1.8-2.6(Ma)の放射年代をもつ玄武岩体から構成される(Macdonaldほか,1983).Honolulu火山活動は,これらの大規模盾状火山形成後の浸食期を経て再活動した比較的小規模な火山活動の総称で,Oahu島の景勝地であるDiamond Headなどは,Honolulu火山活動によって形成された火山地形である.本研究では,Honolulu火山活動で形成された火砕丘,特にクレーターの地形を解析した結果を報告し,Honolulu火山活動の特徴等について検討する.本要旨では,クレーターを形成した火山噴火の規模と,クレーターの侵食程度について報告する. 図1:研究対象地域地形区分図とクレーター分布 II.クレーター解析方法 1) U.S GEOLOGICAL SURVEY発行の1/24000地形図を用いて,クレーターの比高,直径等を計測した.この結果から,クレーターの体積を推定した.この結果より,火山爆発指数(VEI)を算出し,オアフ島南東部のクレーターを形成した火山噴火の規模を推定した. 2)クレーターの接峰面図を描いて,侵食前の地形を推定した.また,この接峰面図をデジタルデータ化して,定量的に侵食の程度を試算した. III.火山爆発指数(VEI) 火山爆発指数(以下,VEI)は,噴火の大きさの尺度として用いられる.これは噴出物の総量が体積でわかれば決められる値で,0から8までの整数で示され,噴出物の量をA×10i㎥とするとき,VEI=i-4で算出される.VEIは0から8までの値で示され,0が非爆発的噴火,1が小規模,2が中規模,3がやや大規模,4が大規模,5が非常に大規模である. Oahu島南東部に分布するクレーターのVEIと面積の関係を図2示す.おおむね面積が大きくなるほどVEIも大きくなるという結果が得られた.特にVEIが大規模のクレーターは,いくつかの火口が複合した形状を持つものがほとんどである。 IV.侵食度合い 1)解析方法:まず,クレーターごとに接峰面図を描いた.谷埋めの間隔は100mと1000mとした.このクレーターごとの接峰面図と地形図をスキャンし,Illustratorで等高線ごとにトレースした.トレースした等高線の輪は、ピクセル数を数えるため塗りつぶした.このデータをPhotoshopで開き,等高線毎にピクセル数を数えた.図3を見ると,侵食前の地形(B)から現地形(A)のピクセル数を引いた数(C)が,侵食程度ということになる.Diamond Headの560ftでは,7.8%が侵食されたことになる. 2)結果:クレーターの形成年代と侵食程度を図4に示す.形成年代が古ければ古いほど,侵食が進んでいるという一応の結果は出た.しかしながら,侵食の程度は,立地,地質,気候,風量,風向きなどに左右されると考えられるので,今後はそれらを加味しつつ,クレーターの侵食程度や開析具合を検討したい. V.まとめにかえて 1)Oahu島南東部に分布するクレーターの爆発規模は中~大規模であり,小規模は分布しない.また,面積が大きければ大きいほど,VEIも大きい. 2)クレーターの侵食程度を定量的に表すことができた.その結果,クレーターは,侵食が進んでいれば進んでいるほど形成年代が古い傾向が見られた.今後は,クレーターの侵食を左右する要因を加味して,Oahu島南東部におけるクレーターの侵食様式を検討したい.
1 0 0 0 OA メニエール病の経過と予後に関する研究
- 著者
- 岸 澄子
- 出版者
- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.3, pp.386-400, 1973-03-20 (Released:2008-12-16)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 4
[目的]メニエール病の臨床症状は多種多様で,かつその経過も長短まちまちである.そこでメニエール病の臨床的経過を明らかにすると共に,その臨床症状ならびに検査成績から予後に関係する因子を知る目的から研究を行なつた.[対象]昭和42年1月から45年12月までの4年間に当科を受診したメニエール病78例,および原因不明の耳性眩暈98例の内,外来観察ないしはアンケートによつて受診後少なくとも1年以上の経過を知ることのできたメニエール病67例,耳性眩暈78例をえらんだ.[結果]アンケートの結果,めまいが治癒あるいはほぼ治癒した例は約90%以上あつたが,その罹病期間はメニエール病では平均4年4ヵ月であつた.初発年令はメニエール病,耳性眩暈ともに20代から40代に多く,初発年令が高令化するにつれて罹病期間が短かくなる傾向がみられた.初回眩暈発作時に耳鳴,難聴を加えて3主徴をもつたものは42例(63%),さらに耳閉塞感を加えて4主徴を伴つたものは24例(36%)であった.まためまい発作がcluster groupingを示す傾向は耳性眩暈例には少なく,メニエール病に特徴的であつた.CMI (Cornell Medical Index)検査では,メニエール病が精神身体疾患の傾向をもつことが確かめられた.初診時の純音聴力検査では,平均聴力損失が40dB以内の軽度難聴者と40dB以上の難聴者の2つのグループに分けることができた.患側耳の聴力型は水平型が最も多く,次いで斜昇型,高音急墜および斜降型,山型,正常,聾の順であつた.このうち,水平型は発病よりの期間が長い例に多く認められ,一方斜昇型はその逆に経過の短い例に多かつた.温度刺激検査と発病から初診までの期間との関係はNo Response群が他群に比し,明らかに長い経過を示した.臨床症状のうち予後に関係すると思われた因子は,初発年令,めまい発作におけるcluster groupingの有無であり,若年者に初発した場合,発作にcluster groupingをみとめる場合,初回発作時にすでに難聴を自覚した場合に治癒までの期間が長くなる傾向があった.検査成績と予後との関係をみると,純音聴力検査で平均聴力損失が40dB以上か,あるいは患側耳の聴力型が高音急墜あるいは斜降型の場合に短い予後期間を示した.温度刺激検査成績では正常型か,あるいは著しい半規管機能の低下例に予後期間の短い例を多くみとめた.
1 0 0 0 OA 個別集荷型配送システムの実現に関する基礎検討
- 著者
- 増田 悦夫
- 出版者
- 日本物流学会
- 雑誌
- 日本物流学会誌 (ISSN:13493345)
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, no.14, pp.117-124, 2006-05-28 (Released:2011-08-16)
- 参考文献数
- 12
今後の配送には荷主の要望にきめ細かく対応できる高度なサービスが望まれる。モバイル通信技術の進展を考慮すると、出先の個人荷主が依頼するC2C型の配送へも積極的に対応していくことが望ましい。本論文では、小口配送システムのうち特に地理上に不特定多数が広く分布する個人荷主に対し直接集荷を行う個別集荷型配送を取り上げ、実現性について基礎検討を行った。まず、従来の巡回集荷型配送との比較を通してその特徴を示し、続いて基本的なモデルを対象にシミュレーションを行い基本的特性を明らかにするとともに実用化に向けての課題を抽出した。
1 0 0 0 OA 記録される「個性」
- 著者
- 稲葉 浩一
- 出版者
- 日本教育社会学会
- 雑誌
- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)
- 巻号頁・発行日
- vol.93, pp.91-115, 2013-11-30 (Released:2015-03-25)
- 参考文献数
- 13
本稿は『生徒指導提要』(文部科学省)の記述に見られるように,児童生徒の個性尊重と児童生徒理解の方法が,しばしば多くの「注文」をつけて語られることに着目し,その実践の起源ともいえる個性調査において実際の教師たちはどのように児童らを「理解」していたのかを明らかにするものである。主として大正期から昭和初期にかけて多く発刊された個性調査のテキストは,典型的には教師の個性調査実践を「客観的基礎」に欠けものとし,そこに「失敗」の可能性を想定するものであった。だが一方本稿が見た大正期の個性調査簿の記録は,そのような方法をもって児童の「ありのまま」に接近するようなものではなく,むしろ個性調査簿の様式に則りながらも,前年度までの児童の「個性」をその次の年度の教師が参照し,児童たちの「らしさ」ともいえる「パターン」を再構成するという言説-解釈実践を行うものであった。これはいうなれば教師による児童の「性格づけ」・「語り継ぎ」の実践であったといえるだろう。以上のことからわかるのは,公的な言説が要求する「理解」のあり方と異なったものであっても,教師は日常生活者として十分な理由をもって児童らの個性を理解=解釈していたということである。その意味で「よりよい精確な」理解が教育現場に要請される以上そこには原理的な「困難」が常に潜在し,「注文」が尽きることはないというのが本稿の結論となる。
1 0 0 0 OA C型慢性肝炎治療薬テラプレビル —ガイドラインからみた特徴と注意点—
- 著者
- 北村 正樹
- 出版者
- 耳鼻咽喉科展望会
- 雑誌
- 耳鼻咽喉科展望 (ISSN:03869687)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.4, pp.250-252, 2012 (Released:2013-08-15)
- 参考文献数
- 6
1 0 0 0 OA 「エサルハドン王位継承誓約文書」のタイナト版による新知見と再検討
- 著者
- 渡辺 和子
- 出版者
- 一般社団法人 日本オリエント学会
- 雑誌
- オリエント (ISSN:00305219)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.1, pp.55-70, 2013-09-30 (Released:2016-10-01)
- 参考文献数
- 29
The Tayinat Archaeological Project of Toronto University, in 2009, excavated a large clay tablet along with 10 other tablets at Tell Tayinat, Turkey, which was identified as a copy of the 'Succession Oath Documents' issued by the Assyrian king Esarhaddon in 672 BC. These documents were known through the Nimrud version published by D. J. Wiseman in 1958, and reedited by myself in 1987. As J. Lauinger, who published the Tayinat version in 2012, pointed out, the tablets were excavated in situ at the sacred precinct in the center of the mound, and had been issued to the governor of Kunalia. Through this information, Tell Tayinat was definitely identified with the ancient city Kunalia. The present author considers §30 (ll. 353-359), now restored by the Tayinat version, to be especially important here. The mood of the verb in line 353 of the conditional clause has proven to be indicative, not subjunctive, as I had expected before. Indicative verbs are generally used in conditional clauses led by "if" (šumma). However, the usage of subjunctive verbs in conditional clauses had not yet been elucidated in any Akkadian grammars, which had regarded the subjunctive as an expression of an oath, and in translation, merely gave instructions to omit the word "if" and to render affirmative subjunctive verbs in the negative, and negative subjunctive verbs in the affirmative. However, almost all of the conditional clauses in these documents are in the second person plural, and are in fact, followed by curses as apodoses, mostly placed in the latter part of the documents. Only §57 is an utterance of an oath and consists of a conditional clause (protasis) in the first person plural subjunctive, and a directly following self-curse (apodosis). Sometimes, with verbs in the second person plural indicative and subjunctive are combined in the same conditional clause, as in the case of §30. In my view, the indicative is used to explain certain given conditions and the subjunctive affirmative ('if you should do ...') that follows, indicates something that the speaker assumes that 'you' ought not to do ; the negative subjunctive ('if you should not do ...') expresses something that 'you' ought to do.
- 著者
- 岡田 由紀子 押谷 創 杉山 豊 三村 哲史 浅野 靖之 辻田 誠 渡部 啓子 成瀬 友彦 佐々木 洋光 渡邊 有三
- 出版者
- 一般社団法人 日本糖尿病学会
- 雑誌
- 糖尿病 (ISSN:0021437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.3, pp.249-253, 2009-03-30 (Released:2010-03-01)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 4
症例は58歳,女性.47歳より糖尿病を指摘され,52歳からインスリン(ペンフィル30R®)を使用していた.53歳で血液透析を導入し,57歳で右下肢切断術を行った際,血糖コントロール不良でインスリン抗体68.8%, HbA1c 13.3%であった.インスリンリスプロに変更し,血糖コントロールは改善した.今回,急性腹症で来院し穿孔性腹膜炎の診断で緊急入院手術となったが,術後遷延性低血糖と高血糖を呈した.インスリン製剤の変更,ステロイドの併用,二重膜濾過(DFPP), pioglitazoneの併用などを試みたが血糖コントロールは改善せず.インスリンとは異なる機序の血糖降下作用をもつIGF-1製剤メカセルミン(ソマゾン®)を使用し,コントロールを得た症例を経験したので報告する.
1 0 0 0 OA セラノスティクスの構築に向けた超音波応答性バブルリポソームによる遺伝子・核酸デリバリー
- 著者
- 根岸洋一 高橋 葉子 鈴木 亮 丸山 一雄 新槇 幸彦
- 出版者
- 日本DDS学会
- 雑誌
- Drug Delivery System (ISSN:09135006)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.4, pp.285-293, 2014-09-25 (Released:2014-12-25)
- 参考文献数
- 26
1 0 0 0 OA ナノDDS がもたらす新しいMRイメージングとナノ・セラノスティクス
- 著者
- 青木 伊知男 城 潤一郎 Horacio Cabral Rumiana Bakalova Kevin M. Bennett
- 出版者
- 日本DDS学会
- 雑誌
- Drug Delivery System (ISSN:09135006)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.1, pp.47-53, 2015-01-25 (Released:2015-04-25)
- 参考文献数
- 37
- 被引用文献数
- 1
臨床で幅広く利用される生体イメージングであるMRIに対して、ナノDDSはこれまで、標的化による感度の向上、マルチモダリティ化、環境や外部刺激に応答する反応性の造影剤、そして診断と治療の一体化(セラノスティクス)など多様な応用を前臨床研究にもたらした。また、高分子ポリマー、ナノミセル、炭素素材、PEG化リポソームなど各キャリアの優れた特徴や限界も明らかになりつつある。本稿では、MRIに応用するという視点から、急激な発展を遂げたナノDDSの進歩と問題点を議論し、新しい方向性として注目される反応性造影剤(activatable probe)とセラノスティクスへの応用を中心に最近の動向を俯瞰し、将来を展望したい。
1 0 0 0 OA 金コロイド凝集法を測定原理とする尿中ジアセチルスペルミン試薬の開発
- 著者
- 柳谷 真理 土居 洋介 小坂 美恵子 榎本 昌泰 平松 恭子 高橋 慶一 川喜田 正夫
- 出版者
- 日本分子腫瘍マーカー研究会
- 雑誌
- 日本分子腫瘍マーカー研究会誌
- 巻号頁・発行日
- vol.23, pp.44-45, 2008 (Released:2008-03-10)
- 参考文献数
- 5
- 著者
- Kanji HIMENO
- 出版者
- 日本教育工学会
- 雑誌
- Educational technology research (ISSN:03877434)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.1, pp.5-13, 2017-11-25 (Released:2017-04-18)
- 参考文献数
- 19
This article reports on recent trends in research on classroom instruction and teacher education based on the educational technology approach in Japan. First it was surveyed research on classroom instruction and teacher education during the early period of educational technology. Then it traces the genealogy and background of research based on the educational technology approach, having divided the material into research on classroom instruction and teacher education. The article then shifts its focus to the activities of “SIG-02: teacher education and practical research,” one of the Special Interest Groups founded in 2014, and reports on the achievements and future challenges of five SIG study meetings and SIG sessions at three annual conferences.
1 0 0 0 OA Fe-Cr-Ni系ステンレス鋼のマルテンサイト変態に対する化学組成の影響
- 著者
- 平山 俊成 小切間 正彦
- 出版者
- 公益社団法人 日本金属学会
- 雑誌
- 日本金属学会誌 (ISSN:00214876)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.5, pp.507-510, 1970 (Released:2008-04-04)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 17 74
In order to investigate the martensitic transformation in Fe-Cr-Ni stainless steel, the Ni equivalent has been introduced thermodynamically as a universal quantity which indicates stability of austenite with regard to chemical composition. The relation between the Ni equivalent and the amount of strain-induced martensite or athermal martensite has been studied by means of saturation flux density measurement. Furthermore, the mechanism of the formation of strain-induced martensite has been considered thermodynamically.The results obtained are summarized as follows:(1) The Ni equivalent, (Ni), in Fe-Cr-Ni stainless steel is expressed by\phantom(1)(Ni)=Ni+0.65Cr+0.98Mo+1.05Mn+0.35Si+12.6C\ oindentwhere Ni, Cr, etc. represent weight % of these elements in the stainless steel considered.(2) The relation between the Ni equivalent and the amount of strain-induced or athermal martensite has been obtained.(3) About 75% cold rolling of Fe-Cr-Ni stainless steel has the same effect on martensitic transformation as decreasing the Ni content by 3∼5%. In this case, the difference in the free energy at room temperature between the ferrite phase and the austenite phase increases by about 113∼188 cal/mol.(4) The deduced value of the work done by transformation strain induced by the applied stress due to cold rolling is about 120∼126 cal/mol or about 192 cal/mol by compressive or tensile stress, respectively. These values agree very well with the above mentioned change of the free energy difference calculated from the variation in Ni equivalent. Therefore, under applied stress, the stored free energy required for martensitic transformation can be lowered by this work value, 120∼192 cal/mol.
1 0 0 0 OA オンライン受講者の行動観察
- 著者
- パリセ ピーター
- 出版者
- 神奈川県立国際言語文化アカデミア紀要編集委員会
- 雑誌
- 神奈川県立国際言語文化アカデミア紀要 (ISSN:21867348)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.15-31, 2017 (Released:2017-04-17)
1 0 0 0 OA 下北半島から発見された海底林とその意義
- 著者
- Hiroko Makihara Yuka Koike Masatomi Ohta Emi Horiguchi-Babamoto Masahito Tsubata Kaoru Kinoshita Tomoko Akase Yoshio Goshima Masaki Aburada Tsutomu Shimada
- 出版者
- 公益社団法人日本薬学会
- 雑誌
- Biological and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:09186158)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.7, pp.1137-1143, 2016-07-01 (Released:2016-07-01)
- 参考文献数
- 42
- 被引用文献数
- 19
Visceral obesity induces the onset of metabolic disorders such as insulin resistance and diabetes mellitus. Adipose tissue is considered as a potential pharmacological target for treating metabolic disorders. The fruit of Terminalia bellirica is extensively used in Ayurvedic medicine to treat patients with diseases such as diabetes mellitus. We previously investigated the effects of a hot water extract of T. bellirica fruit (TB) on obesity and insulin resistance in spontaneously obese type 2 diabetic mice. To determine the active ingredients of TB and their molecular mechanisms, we focused on adipocyte differentiation using mouse 3T3-L1 cells, which are widely used to study adipocyte physiology. We show here that TB enhanced the differentiation of 3T3-L1 cells to mature adipocytes and that one of the active main components was identified as gallic acid. Gallic acid (10–30 µM) enhanced the expression and secretion of adiponectin via adipocyte differentiation and also that of fatty acid binding protein-4, which is the target of peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ), although it does not alter the expression of the upstream genes PPARγ and CCAAT enhancer binding protein alpha. In the PPARγ ligand assay, the binding of gallic acid to PPARγ was undetectable. These findings indicate that gallic acid mediates the therapeutic effects of TB on metabolic disorders by regulating adipocyte differentiation. Therefore, TB shows promise as a candidate for preventing and treating patients with metabolic syndrome.
- 著者
- 増井 幸雄 板橋 愛宜 石井 暁 伴 文彦 井上 栄
- 出版者
- 社団法人 日本感染症学会
- 雑誌
- 感染症学雑誌 (ISSN:03875911)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.6, pp.707-713, 2007-11-20 (Released:2011-02-07)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 1 3
Epstein-Barrウイルスのカプシド抗原 (VCA) に対するIgM抗体検査は, 主として伝染性単核症の病原診断に使われている.本論文では, 1999~2006年の8年間に全国の医療機関から1臨床検査会社に間接蛍光抗体法によるVCA-IgM抗体検査の依頼があった約18万件の血清検体の検査結果を集計・解析した. 集計結果は, IgM抗体陽性数の年齢分布は2峰性 (乳幼児期および青年期) を示した. 年齢により男女差があり, 乳幼児では男性が多く, 青年では女性が多かった. IgM抗体陽性数の月別変動を見ると, 青年層で春から秋にかけて増加が認められた. この検査室データは, 国内の青年層において伝染性単核症が発生していることを示唆している. 今後, 乳幼児期より症状が重い青年層での同症発生の実態を知るための疫学調査が必要であろう.