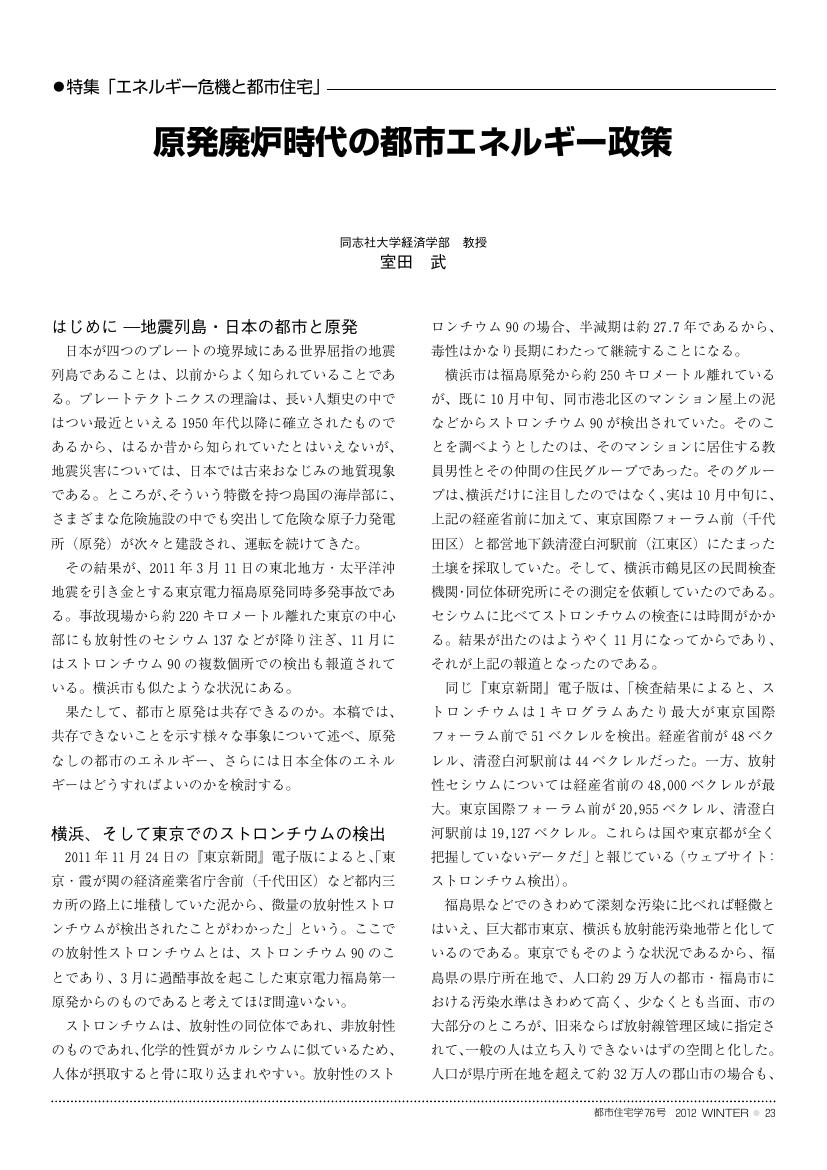2 0 0 0 OA 体脂肪率と体力の関連
- 著者
- 小泉 直子 Naoko KOIZUMI
- 出版者
- 大手前女子短期大学・大手前栄養文化学院・大手前ビジネス学院
- 雑誌
- 大手前女子短期大学・大手前栄養文化学院・大手前ビジネス学院研究集録 = Reseach of Otemae Junior College, Otemae College of Nutrition, Otemae Business College (ISSN:09103767)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.091-106, 1995-12-11
- 著者
- 野中 俊文
- 出版者
- 日本甲殻類学会
- 雑誌
- CANCER (ISSN:09181989)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.101-102, 2012-08-01 (Released:2017-07-05)
- 著者
- 周 菲菲
- 出版者
- 北海道大学大学院文学研究科
- 雑誌
- 北海道大学大学院文学研究科研究論集 (ISSN:13470132)
- 巻号頁・発行日
- no.13, pp.111-135, 2013
この論文は,観光研究におけるアクター・ネットワーク論的なアプローチ の必然性と可能性を探求する。まず,従来の観光研究における全体論的な視 点の欠如とモノについての考察の不足といった問題点を指摘する。観光地対 観光者という二分法や,イメージ論のような表象分析の枠では,観光実践の 複雑性を十分に研究することができない。ここで,関係の生成変化に注目し, 人やモノ等の断片的な諸要素を,諸関係を構成する対称的なアクターと見て, それらのアクターが織り成すネットワークの動態の過程を把握するアク ター・ネットワーク論に注目する。そして,観光におけるモノの物質性と場 所の多元性の存在を論証し,観光者のような特定のアクターが観光ネット ワークの中で他のアクター(地域イメージ,モノ等)を翻訳し,自らの実践 に導く様相を,先行研究に基づいてまとめる。さらに,中国人の北海道観光 を例として,アクター・ネットワーク論に基づき,個的実践の共有化の過程 と,地域イメージのブラックボックス化の過程をまとめた。最後に,観光研 究へのアクター・ネットワーク論的アプローチを,地域の複数性を提示する 研究として提示してみた。
2 0 0 0 OA 怒りと循環器系疾患の関連性の検討
- 著者
- 鈴木 平 春木 豊
- 出版者
- 一般社団法人 日本健康心理学会
- 雑誌
- 健康心理学研究 (ISSN:09173323)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.1-13, 1994 (Released:2015-06-13)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 8 29 25
This study was conducted to examine the structure of factors of STAXI-Japanese-version among the people with circulatory-diseases and normal healthy group, and to compare their scores among three groups with diseases (hypertension / coronary heart disease /both). (STAXI, which were developed by Spielberger et al. has two sub scales. One is State and Trait Anger Scale(STAS), the other is Anger Expression Scale (AX). STAS was desigend to assess the intensity of anger as an emotional state (state anger) and individual differences in anger proneness as a personality trait (trait anger). After examining the research on anger expression, AX scale was developed. This AX has 3 sub-scales for measuring suppressed anger (anger in), anger expressed toward other people or the environment (anger out), and the control of anger (anger control).) As it was proven, STAXl-Japanese-version has an almost equal structure of factors to the American-version. In addition, it has ample reliability. But in two sub scales (anger in & anger control), there exists some validity problems which may come from cultural differences between Japan and U.S. A. And, the scores of 3 sub-scales(state anger, trait anger, anger out) were related to the patients under 60's who are suffering from both hypertension and CHD. As the results, anger should be studied more in relation to circulatory diseases in consideration of cultural differences.
2 0 0 0 OA 小室家の中世文書 : 「屋代典憲氏所蔵古文書之写」について
2 0 0 0 OA 戦前期中国青島市におけるクロマツとサクラの植栽
- 著者
- 江 本硯 藤川 昌樹
- 出版者
- 公益社団法人 日本造園学会
- 雑誌
- ランドスケープ研究 (ISSN:13408984)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.5, pp.393-398, 2014 (Released:2015-05-22)
- 参考文献数
- 52
- 被引用文献数
- 1 1
This paper aims to analyze how Japanese Black Pine and Cherry Blossom were imported and planted in Qingdao. It turns out that they were firstly imported to Qingdao by the German governors from Japan, and planted on the hills, along the coasts and in the parks. As Qingdao was occupied by Japan in 1914, the Black Pine and Cherry Blossom were planted more widely on the hills, parks and even courtyards. What should be emphasized is that they were not merely planted as ornamental trees, but also used to symbolize Japanese culture. The Cherry Blossoms planted along the entrance path of the Qingdao Shrine and the monument built for the dead soldiers were considered as the reproduction of Japan’s traditional landscape in Qingdao. That is why when Japan was beaten in the Second World War, the Cherry Blossoms planted in Qingdao were widely cut down and replaced by Cedar. While compared to Cherry Blossom, most Black Pines were free of cut down disaster and is widely used in Qingdao nowadays.
2 0 0 0 日本の政治学--その歴史と現状
- 著者
- 山川 雄巳
- 出版者
- 関西大学法学会
- 雑誌
- 関西大学法学論集 (ISSN:0437648X)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.2, pp.p477-499, 1987-10
2 0 0 0 ― 護岸改修と外来魚に着目した 10 年前との比較 ―
- 著者
- 藤原 結花 内田 有紀 川西 亮太 井上 幹生
- 出版者
- 応用生態工学会
- 雑誌
- 応用生態工学 (ISSN:13443755)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.2, pp.91-105, 2014
- 被引用文献数
- 2
愛媛県の重信川中流域に点在する灌漑用湧水池の魚類群集を,約 10 年を隔てた 2 時期 (1998-1999 年と 2008 年) 間で比較し,護岸改修工事やオオクチバスの定着が魚類群集にどのような変化をもたらしたかについて検討した.調査地である 11 の湧水池のうち 2 つが 2000 年以降に護岸改修 (素堀りから石積み護岸への改修) が施されたもので (改修湧水池), 別の 1 つは 1999 年においてオオクチバスの定着が確認されていたものである (バス湧水池). 出現種数,種構成,種毎の生息密度,および岸部の状態,底質,カバーといった環境要素を比較した結果,バス湧水池では,オオクチバス以外の種が激減するという大きな変化が認められた.このような顕著な変化はバス湧水池に特有のものであり,また,その 10 年間で環境要素に際立った違いは認められなかったことから,バス湧水池で見られた他魚種の激減は,オオクチバスによるものと考えられた.一方,改修湧水池では,改修工事に伴う大きな環境変化が示されたものの,魚類群集には顕著な違いは認められなかった.1 つの改修湧水池では種数は減少したが,もう一方の改修湧水池では増加していた.また,両改修湧水池で生息種の入れ替わりや生息密度の増減が認められたものの,そのような変動は他の非改修湧水池で見られた変動と同程度であった.それぞれの湧水池における各魚種の増減を総じて見た場合,生息密度が増加した例が 32 に対して減少したのは 56 例であり,全体的には減少傾向にあった.この減少傾向は,2008 年におこった水位低下による一時的な減少を含む可能性があるが,ヤリタナゴとタモロコの減少傾向については注意を払う必要があると思われた.これら 2 種は,以前生息していた湧水池の全て (ヤリタナゴ 6 池,タモロコ 2 池) から消失しており,これらの分布域や個体群サイズの縮小が示唆された.また,このことが氾濫原水域や農業水系網全体の劣化を示唆する可能性があることを指摘した.
2 0 0 0 OA 山崎断層系大原断層のトレンチ調査
- 著者
- 遠田 晋次 宮腰 勝義 井上 大栄 楠 建一郎 鈴木 浩一
- 出版者
- 公益社団法人 日本地震学会
- 雑誌
- 地震 第2輯 (ISSN:00371114)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.1, pp.57-70, 1995-05-25 (Released:2010-03-11)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1 2
The Yamasaki fault system is located from the eastern Okayama to Hyogo Prefectures, southwest Japan, trending in NW-SE direction with a length of 87 kilometers. Earthquake risk evaluation of this fault system is not complete because the past seismic events have not been determined throughout the fault system. This paper reports a comprehensive survey of the Ohara fault, located at the northwestern end of the fault system. High resolution electrical exploration and five drillings at Ohara Town clearly identified the location of the fault underneath the sediment cover. Trench survey was then carried out to determine the past seismic events along the Ohara fault. The following conclusions were derived from these studies. (1) The Ohara fault shows up as a sharp resistivity contrast in the high resolution electrical exploration, reflecting mainly the difference in resistivity between acid tuff and black slate that constitute the northern and southern sides of the fault, respectively. (2) The trench observation in the log and radiocarbon dating of sediments revealed that the latest fault movement along the Ohara fault occurred between 150 and 1200 years B. P. The Harima Earthquake of 868 years AD is most likely to correspond to this fault movement. The timing of the event roughly coincides with the latest event of the Yasutomi fault (Okada et al., 1987) comprising the central part of the Yamasaki fault system. This strongly suggests that the Ohara and Yasutomi faults ruptured simultaneously or as a sequence of events during the Harima Earthquake. (3) The penultimate movement of the Ohara fault was estimated between 1500 and 3000 years B. P. If the latest event corresponds to the Harima Earthquake, then the interval between the last two events is estimated to be 400 to 1900 years. (4) The present trench survey revealed possibly four events along the Ohara fault during the Holocene. Thus the recurrence interval may be about 2500 years. Comparing this result with the interval between the last two events, movement of this fault system is likely to be aperiodic.
2 0 0 0 OA 北海道におけるコシジロウズラシギCalidris fuscicollisの春季の記録
- 著者
- 先崎 理之
- 出版者
- 日本鳥学会
- 雑誌
- 日本鳥学会誌 (ISSN:0913400X)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.1, pp.55-58, 2014 (Released:2014-05-09)
- 参考文献数
- 17
2 0 0 0 海こそなけれ : 諏訪海軍の航跡
- 著者
- 諏訪海軍史刊行会編
- 出版者
- 諏訪海軍史刊行会事務局
- 巻号頁・発行日
- 1994
2 0 0 0 OA 運用業務プロセスのモデリング
- 著者
- 波田野 裕一
- 出版者
- 一般社団法人 経営情報学会
- 雑誌
- 経営情報学会 全国研究発表大会要旨集 2010年春季全国研究発表大会
- 巻号頁・発行日
- pp.23, 2010 (Released:2010-06-14)
運用業務のプロセス分析については、ITILやBPMなどさまざまな分析の提案がなされてきた。 <br/>運用フレームワークfwopでは、運用業務を遂行する組織、個人に着目し、運用組織に求められる 10 の機能を業務機能ユニットとしてモデル化することで、運用業務プロセス全般を表現しようとしている。 <br />本発表では、この「業務機能ユニット」のコンセプトを紹介するとともに、「業務機能ユニット」で表現された運用業務プロセスの、1.標準化による効率化、2. 業務特性に従ったモデル化による展開容易性の実現、3. 運用業務基盤に反映 (実装) するための「運用アーキテクチャ」の3つの展望について述べる。
2 0 0 0 OA 3)食欲調節機序の破綻と肥満の関連を考える
- 著者
- 中里 雅光
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.105, no.3, pp.402-405, 2016-03-10 (Released:2017-03-10)
- 参考文献数
- 8
2 0 0 0 OA 発光素子の色をはかる
- 著者
- 中西 洋一郎
- 出版者
- 一般社団法人 色材協会
- 雑誌
- 色材協会誌 (ISSN:0010180X)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.8, pp.313-318, 2003-08-20 (Released:2012-11-20)
- 参考文献数
- 15
2 0 0 0 OA 高齢者の口腔機能はどのように低下するのか?
- 著者
- 菊谷 武
- 出版者
- 公益社団法人 日本口腔インプラント学会
- 雑誌
- 日本口腔インプラント学会誌 (ISSN:09146695)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.2, pp.102-106, 2019-06-30 (Released:2019-08-10)
- 参考文献数
- 12
口腔機能は加齢とともに低下する.全身の機能の低下に伴い低下する.歯やインプラントの存在は,健康増進やフレイル予防に有効である.一方で身体機能の低下した患者にとってはその効力を相対的に失う.さらに重症の要介護状態では,歯やインプラントの存在が口腔環境や生命のリスクとなる場面もある.歯の存在がリスクとならないように,あらゆるステージにおいても口腔管理が適正に実施されなければならない.自立を失った高齢者に十分な口腔管理が提供できない現状は早期に解決しなければならない歯科の課題である.
2 0 0 0 OA 原発廃炉時代の都市エネルギー政策
- 著者
- 室田 武
- 出版者
- 公益社団法人 都市住宅学会
- 雑誌
- 都市住宅学 (ISSN:13418157)
- 巻号頁・発行日
- vol.2012, no.76, pp.23-29, 2012 (Released:2017-06-29)
- 参考文献数
- 12
- 著者
- 高倉 耕一
- 出版者
- 日本環境動物昆虫学会
- 雑誌
- 環動昆 (ISSN:09154698)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.3, pp.81-87, 2016 (Released:2017-09-02)
2 0 0 0 OA 再帰性に富んだ反射材を貼付した救急車について
- 著者
- 吉沢 彰洋 中村 俊介 山下 智幸 三林 洋介 一杉 正仁 有賀 徹
- 出版者
- 一般社団法人 日本交通科学学会
- 雑誌
- 日本交通科学学会誌 (ISSN:21883874)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.3, pp.79-80, 2016 (Released:2018-03-01)
長野県北アルプス広域消防本部において、2015年11月に実施された既存車両への「再帰性に富んだ反射材」貼付の実証実験とその後のアンケート調査の結果、非常に高い評価を得た。このうち救急車に関しては、実車両の反射具合と国土交通省発出文書に関する松本自動車検査登録事務所の解釈が落ち着いたことを確認して、貼付位置等を若干変更し、2016年3月18日「再帰性に富んだ反射材」を備えた新車の納車を迎えた。