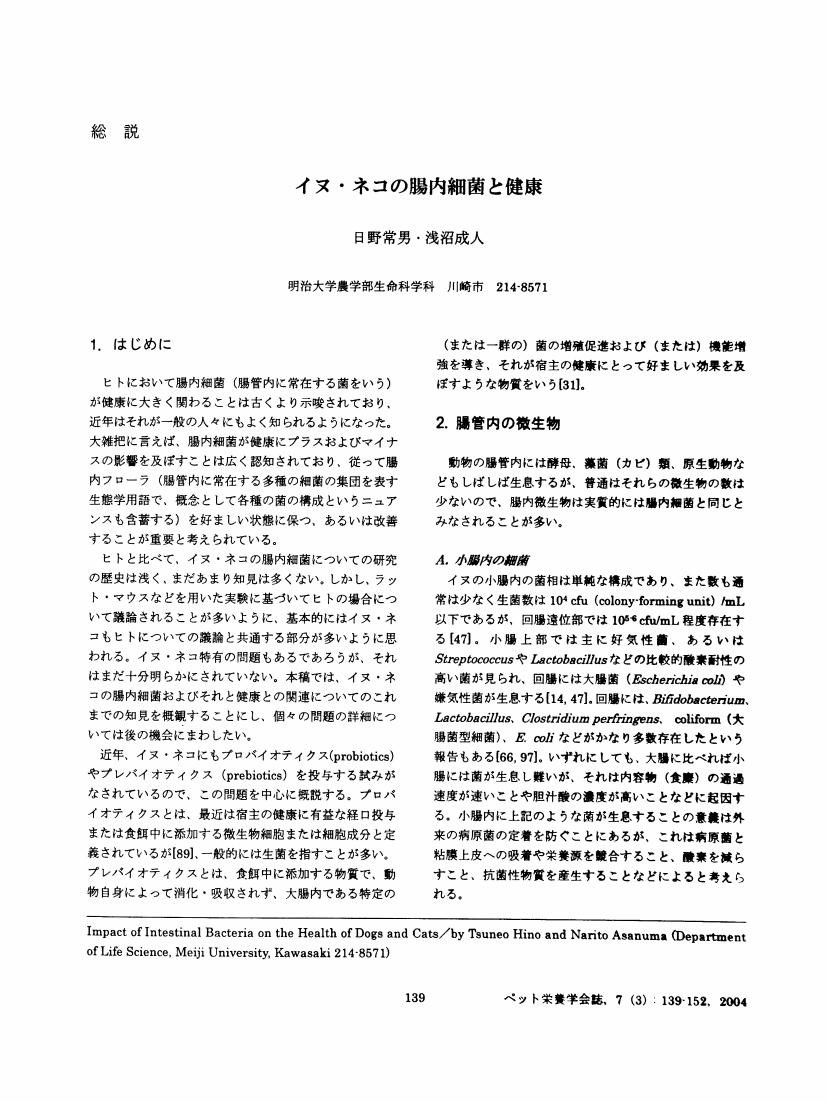1 0 0 0 OA 肺動脈塞栓を合併したヒラメ筋静脈血栓の3例
- 著者
- 長嵜 悦子 佐久田 斉 仲栄真 盛保 比嘉 昇 國吉 幸男 古謝 景春
- 出版者
- 日本臨床外科学会
- 雑誌
- 日本臨床外科学会雑誌 (ISSN:13452843)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.11, pp.2913-2917, 2003-11-25 (Released:2009-03-31)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1
肺塞栓症の塞栓源として下肢深部静脈血栓症が知られている.肺塞栓症を合併した孤立性ヒラメ筋静脈血栓症の3症例を経験したので報告する.症例1: 59歳,女性. Cushing syndromeに対する腹腔鏡下副腎摘出術後3日目に胸部圧迫感,低酸素血症が出現.症例2: 54歳,女性.卵巣癌の既往があり1カ月前より左下腿鈍痛が出現.症例3: 44歳,女性.両下腿に腫脹,鈍痛があり,階段昇降時に息切れを自覚.いずれも下肢超音波検査でヒラメ筋静脈のみに限局した血栓,肺血流シンチで肺血流欠損像,胸部造影CT検査で多発性肺動脈血栓を認めた. 3例中1例にウロキナーゼによる血栓溶解療法,全例に抗凝固療法を行い症状の改善が得られた.ヒラメ筋静脈血栓症は臨床症状が乏しいため見落とされやすい.しかし肺塞栓症の合併,血栓の中枢側進展,再発を繰り返すことがあり,積極的に診断,治療,予防する必要がある.
1 0 0 0 OA “エコノミークラス症候群”から“旅行者血栓症”へ
- 著者
- 一杉 正仁
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本バイオレオロジー学会
- 雑誌
- 日本バイオレオロジー学会誌 (ISSN:09134778)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.32-33, 2002-03-30 (Released:2012-09-24)
- 参考文献数
- 4
1 0 0 0 OA イヌ・ネコの腸内細菌と健康
- 著者
- 鷹木 達
- 出版者
- 一般社団法人 日本口腔衛生学会
- 雑誌
- 口腔衛生学会雑誌 (ISSN:00232831)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.3, pp.306-327, 1986 (Released:2010-10-27)
- 参考文献数
- 42
A previous report has shown the anticariogenic effects of combined topical fluoride application in school dental health programs (Isozaki, 1984). The aim of the present study was to evaluate the cariostatic effects on each tooth surface in school children given topical fluoride treatments by using Cohort analysis.The subjects of this study were 827 school children (437 boys and 390 girls) who were in the 1-6 grade in 1975. Topical fluoride application was given once a year using an acidulated phosphate fluoride solution (0.9% F-, pH 3.6), and fluoride mouthrinsing was practiced 5 times a week after every school lunch with a phosphoric acid-acidfied sodium fluoride solution (0.05% F- pH 5.0). Cohort observations on each tooth surface were carried out for anticariogenic effects from 1976 to 1980 according to the school grade levels of the subjects.Cohort analysis on the DMFS of each tooth type showed a statistically significant anticariogenic effect in the groups which started these programs from the lower grade levels. The results were as follows: The proximal- and lingal-surface of central and lateral incisor, and occlusal surface of first and second premolar of maxilla, and occlusal surface of second premolar of mandibula showed a decrease in the DMFS rate. Especially, the group which started from the first grade showed high anticariogenic effect on the occlusal surface of the maxillar and mandibular first molar.These results study indicate that combined topical fluoride treatments have a high anticariogenic effect on each tooth surface.Regarding the measures of caries prevention applied to school dental health program, it is suggested that combined topical fluoride treatments are usefull, and that it is necessary to start from the lower school grade and to carry out this program continuously through the primary school years.
1 0 0 0 OA フッ化物塗布による露出歯根象牙質面に対するプラーク抑制効果について
- 著者
- 伊藤 公一 荒井 法行 菅野 直之 戸村 真一 金子 和夫 村井 正大
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本歯周病学会
- 雑誌
- 日本歯周病学会会誌 (ISSN:03850110)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.2, pp.642-651, 1990-06-28 (Released:2010-08-25)
- 参考文献数
- 43
- 被引用文献数
- 1 1
健全な歯根を用いルートプ. レーニングを施した象牙質片を作製し, その象牙質片に2%NaF, 2および8% SnF2を塗布したものを口腔内に7および28日間装着させ, これらの薬剤塗布が象牙質面のプラーク形成にどのような影響を与えるか, 併せてブラッシングの影響をも組織学的に観察し, 以下の結論を得た。1. 非ブラッシング試片の7日目において2および8% SnF2群はコントロール群に比べプラーク形成量は小さかった。2. ブラッシング試片では7および28日目いずれにおいても各処理群はコントロール群と比較しプラーク形成量に差は認められなかった。3. 非ブラッシングおよびブラッシング試片を比較するとブラッシング試片が, いずれの条件においてもプラーク形成量は小さかった。4. 露出歯根象牙質面のプラーク抑制にSnF2の局所塗布が有効であることが示唆された。
- 著者
- Naoko Kaida Nguyet Anh Dang
- 出版者
- 日本熱帯生態学会
- 雑誌
- Tropics (ISSN:0917415X)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.4, pp.187-194, 2016 (Released:2016-03-01)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 1 3
This study reports field survey results on current tourist activities and perception regarding marine ecosystem conservation in the Nha Trang Bay Marine Protected Area (NTB-MPA), Vietnam. Structured questionnaire surveys to visitors (n=166) revealed that, comparing Vietnamese and foreign tourists: (1) About half of the Vietnamese respondents were aware of the NTB-MPA while only 9.6% of foreign respondents recognized this, (2) average respondents visited more than two islands out of the total nine islands during their stay and Vietnamese and foreign respondents tended to visit different islands with different marine activities, and (3) of six marine conservation program components presented in the present survey, both groups showed stronger support for physical enhancement of marine ecosystems rather than for sustainable local community development with slight differences in components between the two respondent groups. These results suggest that the NTB-MPA needs to fulfill both the diverse demands of tourists as well as sustainable marine ecosystem management. However, at the same time, NTB-MPA could also offer diverse opportunities to familiarize tourists with different backgrounds in both environmental and socio-economic issues in marine ecosystems and to facilitate their support for the MPA.
1 0 0 0 OA わが国における複数爲替レート制の意義
- 著者
- 波多野 眞
- 出版者
- 日本国際経済学会
- 雑誌
- 国際経済 (ISSN:03873943)
- 巻号頁・発行日
- vol.1952, no.4, pp.88-98, 1952-11-01 (Released:2012-02-09)
1 0 0 0 OA 長野県白馬村八方尾根スキー場周辺地域におけるインバウンドツーリズムの発展
- 著者
- 小室 譲
- 出版者
- The Association of Japanese Geographers
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- pp.100167, 2014 (Released:2014-03-31)
1.序論 2003年の観光立国宣言以降,政府の積極的なインバウンドツーリズム施策に伴い,訪日外国人客数は約521万(2003)から1,036万人(2013)へ増加している(日本政府観光局「JNTO」).しかしながら観光産業が抱える慢性的な課題として,出国日本人数に対する訪日外国人客数の大幅な赤字が指摘でき,更なる訪日外国人客数獲得のためには各観光地における外国人客への受入れ態勢強化が急務である.2000年代に入り,北海道のニセコに端を発した豪州客を中心としたスキーブームは,近年では白馬や野沢,さらに妙高や蔵王といった幾つかの本州のスキー場においてもみられる.本研究では,長野県白馬村の八方尾根スキー場周辺地域におけるインバウンドツーリズムの動向を分析し,ツーリズムの発展に伴う変容と発展の要因を明らかにする事を目的とする.併せてインバウンドツーリズムの発展に伴う新たな地域課題について検討したい. 2.インバウンドツーリズムの動向 村内最大規模を誇る八方尾根スキー場は, JR大糸線白馬駅から西へ2km程度進んだ北アルプス唐松岳の東斜面にあたる.本研究では,この八方尾根スキー場およびスキー場の麓に位置し,60年代からのスキー観光拡大期にスキー場の宿泊地としての性格を強めた和田野,八方,エコーランドの3地区を研究対象地域とする.2002年に0.3万人であった村内外国人客数は,2011年には5.6万にまで急増しており,また世界最大の旅行口コミサイトTrip adviserの「ベストディスティネーション(観光地)トップ10」において国内第6位の人気観光地に選出されるなどインバウンドツーリズムの発展が顕著である. 3.インバウンドツーリズムの発展に伴う変容 泊食分離と長期滞在を嗜好する外国人スキー客の増加に伴い,スキー場や宿泊施設,さらに飲食施設や娯楽施設では受入れ態勢の強化が進められている。特にキッチン完備の長期滞在施設や異文化体験型施設など従来みられなかった新たな形態の施設が拡充する一方で,外国人スキー客の受入れの有無により施設間,地区間において格差が増大している点が課題として明らかとなった. 4.インバウンドツーリズムの発展要因 ツーリズムの発展要因として,(1)外国人客の直接的な来訪動機となるスキー場の規模や雪質に加えて,民宿発祥の地に根付く「もてなしの文化」による宿泊施設の固定客確保や残存する民宿や温泉といった地域観光資源の存在,(2)70年代以降のペンションブーム期に移住した和田野地区の宿泊施設を母体とする民間主導の外客誘致団体による発地国へのプロモーション活動や素泊まり客に対応した外国人のための飲食店ガイドブック作成と二次交通の拡充,(3)ゲストのホスト化により在住外国人が自ら旅行代理店や空港バス,宿泊施設など外国人スキー客に対応したサービス(事業)を創出している点に大きく分けられる. 5.結論 外国人スキー客の急増は受入れ側である観光地の施設や地域に変容をもたらした.同時にインバウンドツーリズムの発展は新たな地域的課題を与え,ゲストの増加に伴う治安悪化や騒音問題,また施設間・地区間格差の増大やゲストのホスト化に伴う不動産投資や景観問題など,外国人客(住民)と既存住民の共存・共生が求められている.
1 0 0 0 OA 自己関係づけと対人恐怖心性·抑うつ·登校拒否傾向との関連
- 著者
- 金子 一史 本城 秀次 高村 咲子
- 出版者
- 日本パーソナリティ心理学会
- 雑誌
- パーソナリティ研究 (ISSN:13488406)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.1, pp.2-13, 2003 (Released:2004-02-27)
- 参考文献数
- 38
- 被引用文献数
- 1 1
本研究の目的は, 一般青年に見られる被害妄想的観念を自己関係づけとしてとらえて, 対人恐怖心性, 抑うつ, 登校拒否傾向との関連を検討することであった. 被調査者は高校生487名(男子257名, 女子225名, 不明5名)であった. 自己関係づけ尺度, 対人恐怖心性尺度, 抑うつ尺度 (Children’s Depression Inventory: CDI), 登校回避感情尺度, 登校拒否関連性格尺度からなる質問紙に回答を求めた. その結果, 一般高校生において妄想的観念は高頻度で体験されていることが明らかになった. 自己関係づけは, 対人恐怖心性および抑うつ感情と正の相関があった. 考察では, 自己関係づけと対人恐怖心性との概念の異同について検討した.
1 0 0 0 OA 腹痛を呈した鉛中毒の2例
1 0 0 0 OA 鉛中毒が発生した農場における哺乳子牛の鉛汚染の実態
- 著者
- 佐藤 慎一 和田 恭則 山口 俊男 勝見 晟 小林 正人
- 出版者
- 公益社団法人 日本獣医師会
- 雑誌
- 日本獣医師会雑誌 (ISSN:04466454)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.1, pp.19-22, 1992-01-20 (Released:2011-06-17)
- 参考文献数
- 12
鉛中毒が子牛に発生した農場の鉛汚染の実態を知る目的で子牛の血液中鉛濃度を中心に調べ, あわせて血液検査も実施した.調査は発生農場およびその周辺の未発生農家の臨床上著変のない10日齢の哺乳子牛 (黒毛和種) をそれぞれ50頭, 14頭供試し, 次の結果が得られた.1) 血液中鉛濃度は発生農場の子牛が51.5±53.1μ9/100mlで, 未発生農家の7.9±3.6μg/100mlに比べて有意に高かった (P<0.01).2) プロトポルフィリン濃度は発生農場の子牛が未発生農家のものに比べて有意に高かった (p<0.05).3) 発生農場の子牛の血液中鉛濃度は1号棟 (1981年製) 12.4±7.9μg/100ml, 2号棟 (1982年製) 48.8±48.9μg/100ml, 3号棟 (1983年製) 81.1±57.3μg/100mlで, 牛舎の建築年次が新しいほど有意に高かった (1vs2: P<0.05, 1vs3: p<0.01, 2vs3: p<0.05)4) 発生農場の牛舎別子牛のδ-アミノレブリン酸脱水素酵素活性は牛舎の建築年次が新しいほど有意に低かった (1vs2: p<0.05, 1vs3: p<0.01)5) 発生農場の牛舎別子牛の赤血球数, ヘマトクリット値は新しい牛舎ほど低い傾向がみられ, γ-グルタミルトランスペプチターゼ活性は高い傾向がみられた.以上の成績から, 発生農場の子牛は鉛に汚染され, しかも新しい牛舎の子牛に鉛汚染の高いことが認められた.
1 0 0 0 OA ジェンツーペンギンにみられた鉛中毒
- 著者
- 藤井 猪一郎 早稲田 万大 鬼塚 伸幸 山本 賢一 向原 要一 永野 博明 楠田 幸雄 竹川 和明
- 出版者
- 公益社団法人 日本獣医師会
- 雑誌
- 日本獣医師会雑誌 (ISSN:04466454)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.11, pp.889-892, 2008-11-20 (Released:2011-06-17)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1
2007年2月に管内ペンギン水族館において, 屋内飼養ジェンツーペンギン18羽中2羽 (ペンギンA, B) が, 元気消失, 食欲不振, 嘔吐および沈鬱の症状を示し, うちペンギンAが死亡. その他のペンギンには異常は認められなかった. X線検査では, ペンギンAの腹腔内に直径2mmの球状物3個が, ペンギンBには20個の球状物が認められた. 死亡ペンギンAの剖検所見では, 胃底部に軽度のびらんと金属粒が2個, 腸管粘膜には充出血が認められた. 原子吸光分光光度計によるペンギンAの肝臓中鉛濃度は13.3±0.21ppmで, ペンギンBの血清中鉛濃度は6.64PPmであった. また, 金属粒はX線定性分析により鉛と判明した. その他の4羽の健康なペンギンの血清中平均鉛濃度は, 0.007±0.003ppmであった. 以上より本症例は鉛による中毒症と診断された.
1 0 0 0 OA 鉛中毒におけるPorphobilinogenについて
- 著者
- 三浦 創 佐野 晴洋
- 出版者
- 社団法人 日本産業衛生学会
- 雑誌
- 産業医学 (ISSN:00471879)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.4, pp.279-285, 1972 (Released:2011-03-04)
- 参考文献数
- 30
Lead poisoning is associated with characteristic urinary increases of δ-aminolevulinic acid and coproporphyrinogen III, elevated erythrocyte protoporphyrin concentration and partial block of δ- aminolevulinic acid dehydratase.In human lead poisoning a very small amount of increase of porphobilinogen and uroporphyrinogen III is reported, while in rabbits porphobilinogen increases but uroporphyrinogen III does not as in the human cases. The small amount of porphobilinogen or uroporphyrinogen III in the human urine may be explained by δ-aminolevulinic acid dehydratase inhibition, but the increase in coproporphyrinogen III is as yet inexplainable.An alternative pathway of coproporphyrinogen III formation from δ-aminolevulinic acid or porphobilinogen has and suggested in lead poisoning. We proposed that an intermediate, 2-amino-methyl-3-methyl-4-carboxyethyl-pyrrole, may be formed in vivo by enzymic condensation of δ-aminolevulinic acid and 1-amino-butane-2-one (β-ketobutylamine) or by prior decarboxylation of acetic acid sidechain of porphobilinogen. To test this hypothesis we made an experiment, the results of which are as follows.The pyrrole compounds were isolated from the urine or the incubation mixture with δ-aminolevulinic acid and tissue homogenates (bone marrow, liver and kidneys) of lead poisoned rabbits by using the column chromatography on Dowex 2. All the pyrrole compounds were further converted to porphyrins by chemical condensation technique, resulting in the formation of the mixture of uroporphyrin isomers, though no coproporphyrin was detected.The results indicate that the pyrrole compounds in lead poisoning are identical with authentic porphobilinogen and the prior decarboxylation of porphobilinogen appears unlikely. It is suggested that the increase of coproporphyrinogen III in lead poisoning may be caused by over-production of δ-aminolevulinic acid. The increased amount ofthe precursor seems to overcome the partial blocking of δ-aminolevulirlic acid dehydratase and thenormal rate of porphyrin synthesis may be formed.
1 0 0 0 OA 四エチール鉛中毒屍2例に於ける各重要臟器鉛含有量
1 0 0 0 OA 航空機用自動操縦装置のすう勢
- 著者
- 服部 正治 藤平 紘司
- 出版者
- 一般社団法人 日本航空宇宙学会
- 雑誌
- 日本航空宇宙学会誌 (ISSN:00214663)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.275, pp.618-625, 1976-12-05 (Released:2009-05-25)
- 参考文献数
- 8
- 著者
- Junichi Wakayama Yoshihiro Yoshikawa Toshihiro Yasuike Takenori Yamada
- 出版者
- 日本細胞生物学会
- 雑誌
- Cell Structure and Function (ISSN:03867196)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.6, pp.361-365, 2000 (Released:2001-03-28)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 6 8
Atomic force microscopic images of single skeletal myofibrils showed periodical broad filamentous bands interspaced with narrow rigid bands corresponding to the sarcomere structures of skeletal muscle (Yoshikawa, Y., Yasuike, T., Yagi, A., and Yamada, T. 1999. Biochem. Biophys. Res. Comm., 256: 13-19). In order to identify the narrow rigid bands, comparative studies were made for intact single myofibrils and those treated with calcium-activated neutral protease by use of atomic force microscopy. It was found that (a) the periodical narrow rigid bands present in intact myofibrils were completely absent in myofibrils treated with calcium-activated neutral protease, and that (b) myofibrils treated with calcium-activated neutral protease were very fragile compared with intact myofibrils. As calcium-activated neutral protease selectively removes Z-bands of myofibrils (Reddy, M. K., Etlinger, J. D., Rabinowitz, M., Fischman, D. A., and Zak, R. 1975. J. Biol. Chem., 250: 4278-4284), these results clearly indicate that (a) the narrow rigid bands are the Z-bands, and that (b) the Z-bands are the essential disc supporting the sarcomere structure of skeletal muscle.
- 著者
- Nao Akiyama Yoshiki Ohnuki Yuki Kunioka Yasutake Saeki Takenori Yamada
- 出版者
- 日本生理学会
- 雑誌
- The Journal of Physiological Sciences (ISSN:18806546)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.2, pp.145-151, 2006 (Released:2006-07-30)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 20 35
The transverse stiffness of single myofibrils of skeletal and cardiac muscles was examined by atomic force microscopy. The microscopic images of both skeletal and cardiac myofibrils in a rigor state showed periodical striation patterns separated by Z-bands, which is characteristic of striated muscle fibers. However, sarcomere patterns were hardly distinguishable in the stiffness distributions of the relaxed myofibrils of skeletal and cardiac muscles. Myofibrils in a rigor state were significantly stiff compared with those in a relaxed state, and in each state, cardiac myofibrils were significantly stiffer compared with skeletal myofibrils. By proteolytic digestions of sarcomere components of myofibrils, it was suggested that cardiac myofibrils are laterally stiffer than skeletal myofibrils because Z-bands, connectin (titin) filament networks, and other components of sarcomere structures for the former myofibrils are stronger than those for the latter.
1 0 0 0 OA 103 生体リズムの季節変動: 睡眠覚醒、直腸温、血中メラトニンリズム
- 著者
- 富永 禎秀 大風 翼 菊本 英紀 白澤 多一 義江 龍一郎 持田 灯
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会技術報告集 (ISSN:13419463)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.51, pp.609-614, 2016 (Released:2016-06-20)
- 参考文献数
- 10
Recently, applications of CFD (Computational Fluid Dynamics) are expanding to various environmental issues such as pollutant/thermal dispersion in urban areas. The outdoor environment sub-committee of the Architectural Institute of Japan have conducted several benchmark tests for obtaining basic information and knowledge in order to provide the extended practical guidelines of CFD, which can be applied to more broad environmental issues than the present ones. This paper reports the results which considered the sensitivity of various computational conditions in the RANS (Reynolds-Averaged Navier-Stokes equations) model to the prediction accuracy of pollutant concentration distributions for two different configurations.