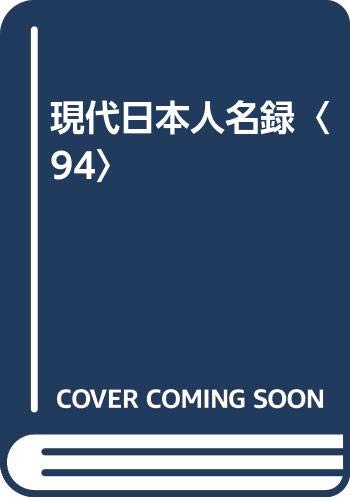2 0 0 0 IR 半透明衣料の色調と下着の色調との関係
- 著者
- 木曽山 かね 雲田 直子
- 出版者
- 東京家政大学
- 雑誌
- 東京家政大学研究紀要. 2, 自然科学 (ISSN:03851214)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.137-144, 1981-03
2 0 0 0 OA 新潟県糸魚川地方のコランダムに伴うプライスワーク雲母とストロンチウムに富む雲母
- 著者
- 宮島 宏 松原 聰 宮脇 律郎
- 出版者
- 一般社団法人日本鉱物科学会
- 雑誌
- 日本鉱物科学会年会講演要旨集 日本鉱物科学会 2007年度年会
- 巻号頁・発行日
- pp.201, 2007 (Released:2008-09-02)
新潟県糸魚川地方の海岸や姫川・小滝川河床から、粗粒なcorundumが転石として発見される(宮島ら, 1999 二鉱学会演旨)。今回、小滝川と青海海岸産のcorundumを含む試料から稀産雲母とSrを含む特異な組成を持つ雲母が発見されたので報告する。 ◆プライスワーク雲母 (Preiswerkite) PreiswerkiteはKeusen and Peters (1980)によりスイスの超苦鉄質複合岩体のrodingiteから発見され、 NaMg2Al[Al2Si2O10](OH)2という組成を持つ。産出例は比較的少なく、本邦では本報告が初産となる。本報告のpreiswerkiteは、糸魚川市小滝川で織田宗男氏が採集した礫に含まれていた。礫には径5~15mmの丸みを帯びた灰紫色ガラス光沢のcorundum, diasporeの集合体が多数存在し、preiswerkiteはその粒間を充填する淡黄色真珠光沢を呈する直径3mmの半自形結晶の集合体をなす。EDSによる分析値(wt. %)は、SiO2 30.75, TiO2 0.34, Al2O3 29.62, FeO 3.64, MgO 18.22, Na2O 4.74, K2O 0.95, Total 88.26となり、実験式は(Na20.7, K0.1) Σ0.8 (Mg2.0, Fe0.3) Σ2.3Al0.8 [Al1.8Si2.2O10](OH) 2となる。 ◆Srに富む雲母 (Sr-rich mica) Sr-rich micaは、糸魚川市青海海岸で小林浩之氏が採集した白地に青色部分が不規則な脈として存在する礫に含まれていた。白色部分は緻密なcelsianと劈開明瞭なmargarite, paragonite, Sr-rich micaからなり、少量のslawsonite, calciteを含む。青色部分は緻密なcorundum, diasporeからなる。margariteとparagoniteからは5 wt.%程度のSrOが検出され、Srに富む部分ではSrO = 15 wt.%を超え、0.75 pfuに達する。実験式は、(Sr0.75, Na0.15, Ca0.05) Σ0.95Al1.98[Al1.98Si2.05O10](OH) 2となり、margariteのSr置換体に相当する。CaとBaを主成分とする雲母は知られているが、Srを主成分とする雲母は知られておらず、公表された分析値でSrを含む例はない。糸魚川地方の蛇紋岩メランジュ中の構造岩塊からは多種のSr鉱物が発見されているが、このような特異な組成の雲母もその一例である。
2 0 0 0 食品安全とHACCP
- 著者
- 藤井 春雄
- 出版者
- Society for Standardization Studies
- 雑誌
- 標準化研究 (ISSN:13481320)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.1, pp.53-65, 2004
雪印事件,BSE(牛海綿状脳症,狂牛病)問題,虚偽表示などなど,近年の食品安全に関する問題は,企業の隠蔽体質も含め,大きな社会問題となった。又,食に関する消費者意識も大きく変化して来た。<BR>この様な中,虚偽表示に対する大幅な罰則強化を盛り込んだJAS法改正も決定し,ISO分野でも,ISO 22000(従来ISO 20543と言われていたもの)が,2004年度末に発行予定である。<BR>そこで,ISOを普及・指導する立場にある者,又食品事業関係者が,どのように食品安全への取り組みを行ったらよいか,について取り纏めた。<BR>その主な内容は,筆者の所属する研究フォーラムで構築した診断プログラムであり,PP診断プログラムおよび6段階評価プログラムの徹底した標準化を推進して来たものである。
2 0 0 0 OA 憲法と髪形の自由 -ハイスクールにおける頭髪規制の合憲性-
- 著者
- 浅利 祐一
- 出版者
- 北海道大学法学部
- 雑誌
- 北大法学論集 (ISSN:03855953)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.5-6, pp.423-455, 1990-08-31
2 0 0 0 IR 戦後の能楽に対する検閲資料 -「能」もしくは伝統演劇-
- 著者
- マートライ ティタニラ
- 雑誌
- 演劇研究センター紀要VIII 早稲田大学21世紀COEプログラム 〈演劇の総合的研究と演劇学の確立〉
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.361-377, 2007-01-31
- 著者
- 矢嶋 美都子
- 出版者
- 亜細亜大学
- 雑誌
- 亜細亜法學 (ISSN:03886611)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.2, pp.125-149, 2007-01
2 0 0 0 現代日本人名録
- 著者
- 日外アソシエーツ編集
- 出版者
- 紀伊國屋書店 (発売)
- 巻号頁・発行日
- 1994
2 0 0 0 IR 二つの書きかた
- 著者
- 今野 真二 Shinji KONNO 清泉女子大学 SEISEN UNIVERSITY
- 雑誌
- 清泉女子大学人文科学研究所紀要 = BULLETIN OF SEISEN UNIVERSITY RESEARCH INSTITUTE FOR CULTURAL SCIENCE (ISSN:09109234)
- 巻号頁・発行日
- 2018-03-31
本稿では十六世紀半ば頃に編纂された「いろは分類」を採る辞書体資料である『運歩色葉集』を採りあげ、「同一と思われる見出しが異なる双つの部に掲げられる」「双掲」という現象に着目した。『運歩色葉集』は「ゐ・え・お」を部としてたてておらず、これらをそれぞれ「い・ゑ・を」部に併せ、全てで四十四部をたてる。したがって、多くの和語は「双掲」されない。「双掲」されている見出しの数は必ずしも多くはないが、拗音、長音が含まれている語がほとんどである。拗音、長音は、室町末期頃までには日本語の音韻として確立していたと考えられており、そうした音韻を含む漢語は、十六世紀半ばにおいても、仮名による「書き方」が揺れていなかった可能性がたかい。漢語は漢字で書くことが標準的であり、漢語の全形を仮名で書くことは必ずしも多くはない。したがって、漢語をどのように仮名で書くかということ自体が、和語と同様に関心事であったとは考えにくい。室町末期頃までに編まれた仮名遣書も、漢語を採りあげることは少ない。そうしたことが、仮名による漢語の書き方が揺れる一因となったことはいえようが、『運歩色葉集』における見出しの「双掲」は「二つの書き方」のどちらからでも求める見出しにたどりつけるための「工夫」といってよい。 In this paper, "Unpoirohashu", title of a dictionary which was edited around 1547, is the focus of analysis. In this dictionary, words that begin with "i" is placed in the "i grouping" just as the entry words are in "iroha" (Japanese alphabetical) order. However, around 1547 the distinction of pronunciation had already disappeared. "I" (い・ゐ) "e" (え・ゑ) "o" (お・を) were grouped in one section, and within that section there were the "i" grouping, "e" grouping, and "o" grouping. In total, there were 44 groupings. Thus, until around 1547 words written with "i" (い~) and (ゐ~) were all in the "i" grouping and those who used the dictionary did not have the problem of finding the words, as one word was not divided into two separate groupings. However, the word "youshou" was found in the "e" (えの部) grouping and "yo" (よの部) grouping. It is assumed that this happened because during those days the same words were written in two different ways "euseu" and "youseu". Such phenomenon is called "soukei". It was pointed out that "soukei" suggests that there were two different ways of writing this word. This writing of one word expressed in two ways can be regarded as "Multi-Expressive Notation System" (Tahyoukisei Hyouki System). Until now the "Multi-Expressive Notation System" was thought to have been administered in the Edo period, but this research highlighted that the previous stage of this system had already been developed before then in the 16th century.
2 0 0 0 OA 新領南洋諸島植物目録
2 0 0 0 IR 『地質学と歴史との境界領域』 : 地質学からみた戦国時代のいくつかの古戦場について
- 著者
- 新関 敦生
- 出版者
- 新潟応用地質研究会
- 雑誌
- 新潟応用地質研究会誌
- 巻号頁・発行日
- vol.59, pp.55-63, 2002-12
2 0 0 0 OA 乃木希典「金州城下作」と唐代詩文 : 付、歌曲「花」・唱歌「仰げば尊し」と古典
- 著者
- 丹羽 博之
- 出版者
- 大手前大学・大手前短期大学
- 雑誌
- 大手前大学人文科学部論集 (ISSN:13462105)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.15-29, 2004
第一章では、乃木希典「金州城下作」と唐代の李華の「弔古戦場」の用語・表現の類似を指摘し、乃木は『古文真宝集』などに収められている名文を参考にして作詩したことを考察。第二章では、武島羽衣作詞「花」の二番の歌詞は『源氏物語』「源重之集」の和歌を利用したものであることを指摘。また、「見ずや〜」の表現は漢詩の楽府体の詩に多く見られる表現を応用したことを指摘。第三章では、「仰げば尊し」の歌詞も『孝経』や『論語』の文章を下敷きにしていることを指摘。
2 0 0 0 OA 戯場仕入楓釣枝 2編6巻
2 0 0 0 OA 高圧固体水素の第一原理計算
- 著者
- 長柄 一誠
- 出版者
- 日本高圧力学会
- 雑誌
- 高圧力の科学と技術 (ISSN:0917639X)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.3, pp.204-211, 2003 (Released:2003-11-05)
- 参考文献数
- 40
Compressed solid hydrogens are introduced with the basic property of the hydrogen molecule. Starting from a brief introduction of old calculations, first-principles calculations of compressed hydrogens and their results are reviewed with some of our results of calculations based on the local density approximation (LDA). The probable structures over 150 GPa and the effects of the zero-point motion of the nuclei on those structures are discussed. The structures are also examined from the view point of electronic band structure. The problems remaining for the future studies of compressed hydrogens are summarized.
- 著者
- 佐藤 安訓 石神 昭人
- 出版者
- 公益社団法人 日本ビタミン学会
- 雑誌
- ビタミン (ISSN:0006386X)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.12, pp.660, 2008-12-25 (Released:2017-10-10)
2 0 0 0 OA 医薬品開発における委受託のポイントと課題
- 著者
- 古田土 真一
- 出版者
- 一般社団法人日本PDA製薬学会
- 雑誌
- 日本PDA学術誌 GMPとバリデーション (ISSN:13444891)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.1, pp.47-61, 2006 (Released:2007-05-10)
- 参考文献数
- 6
医薬品の開発段階における委受託については,委託者の開発戦略と品質ポリシーに基づいて品質リスクマネジメントによる評価を行い,製品ライフサイクルの一環として検討するべきである。委託に際しては,単にスピードや技術に注力するだけでなく,コンフィデンシャリティやパテントについての取り決めも考慮する必要がある。治験薬の製造にあたっては 3 極対応として治験薬 GMP を遵守し,開発過程の情報については変更管理を行い,技術移管時に製品として品質の一貫性を確保する。委託者による承認申請書は,これら全ての情報の最終的な集約でなくてはならない。
2 0 0 0 OA 高齢化社会の生き方と支え方
- 著者
- 長谷川 和夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.5, pp.411-417, 2016 (Released:2016-05-01)
- 参考文献数
- 20
高齢化社会の現在, 高齢者の幸福度は健康, 家族そして収入であろう. ことに高齢になると身体機能の衰退に加えて精神機能が低下し心身医学的な保健, 医療, 福祉の対応が基盤として整備されていることが必要になり, 私たち日本心身医学会に期待されている. 中でも認知症への対応は喫緊の課題であり, 薬物療法や対応するケアそして一般市民への啓発活動を行って, 虚弱高齢者を含めた地域ではぬくもりのある絆を作っていくことが求められる. 認知症ケアの国際的な主流であるパーソンセンタードケアの実施, すなわち個別的な自分史を十分に理解し, その人らしさを尊重する支え方が大切になる. さらに認知症の当事者が自分の体験を語る機会が増えているが, 患者さんや利用者の想いを取り入れていくことや, 介護する家族らを支えていくことなど, 私たち心身医療者へのなすべき責務を痛感する次第である.
2 0 0 0 OA 未刊古文書釈文作成のための協調作業環境の構築
- 著者
- 近藤 成一 海老澤 衷 稲葉 伸道 本多 博之 柳原 敏昭 高橋 敏子 遠藤 基郎 渡邉 正男 神野 潔 野村 朋弘 金子 拓 西田 友広 遠藤 珠紀 山田 太造 岡本 隆明
- 出版者
- 放送大学
- 雑誌
- 基盤研究(A)
- 巻号頁・発行日
- 2013-04-01
未刊古文書釈文作成のための協調作業環境を構築することにより、未刊古文書の釈文を歴史学のコミュニティにおいて協同で行うことを提起し、史料編纂のあり方について新たな可能性を模索するとともに、歴史学のコミュニティの実体形成にも寄与する基礎とした。釈文作成のために外部から自由な書き込みを許す部分と、作成された成果を史料編纂所の管理のもとに公開する部分を構築し、前者から後者にデータを選択して移行するシステムを設けた。
2 0 0 0 臨床実習で学生が感じるハラスメント
- 著者
- 松崎 秀隆 吉村 美香 原口 健三 満留 昭久
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2013, 2014
【はじめに,目的】臨床実習において,臨床実習指導者(以下,SV)が指摘する問題点の多くは,基本的態度など情意領域に関連している。しかし,指導方法や注意の仕方は様々であり,SVの殆どは臨床に従事し,「教育」に関する指導方法が十分でない場合も多い。つまり,社会性や実習態度が未熟な学生に対する,教育的知識が不十分なSVとの間で,実習指導を介したハラスメントが生じる可能性が高くなっている。また,これらのハラスメントは,理学療法学科(以下,PT)の実習形態や作業療法学科(以下,OT)の実習形態の特徴にも関係していると思われる。そこで今回,学科間での違いを把握するとともに,実習でのハラスメントの防止を目的に,臨床実習中に学生が感じたハラスメントに関する調査を行い検討した。【対象および方法】対象は平成25年度,当学院理学療法学科および作業療法学科に在籍し臨床実習を経験した学生64名(男性31名,女性33名)で,平均年齢は23.2±1.4歳(年齢範囲20~44歳)であった。臨床実習終了直後に,自記式の質問用紙を用いて調査を行った。質問内容は,①「ハラスメントを経験した」あるいは「ハラスメントと感じた」かの経験の有無,②経験が有る場合の「ハラスメント内容」である。内容項目は,「言葉による不当な待遇」,「身体へおよぶ不当な待遇」,「学業に関する不当な待遇」,「セクシャルハラスメント」,「性差別の経験」および「他科または他職種との関係」の6つの領域(33項目)である。これらの質問項目は,過去の調査および先行研究の内容を検討して作成した。【倫理的配慮,説明と同意】本研究は当法人倫理審査委員会の承認(FS-46)を受けるとともに,対象者への研究説明と同意を得て実施した。【結果】各学科の属性比較,男女比較において有意差は認めなかった。ハラスメントを感じたという学生の割合は,PTで59.1%,OTで53.3%であった。割合および項目別の内容に学科間の差は認められなかった。領域については,「学業に対する不当な待遇」でハラスメントを感じたとする回答が多かった(PT53.8%,OT47.2%)。内訳は,「忙しいからとあまり指導されない」(PT26.5%,OT20.0%),「将来について否定的な批評をされた」(PT20.4%,OT26.7%),「教える際に不快な態度で接せられる」(PT16.3%,OT13.3%)。一方,セクシャルハラスメント」の領域においては,「言い寄られる,口説かれる」(PT2.0%,OT6.7%)のみであった。ハラスメントを感じた学生のPT82.8%,OT87.5%が抗議していないことも分かった。【考察】昨今の学生教育および指導方法において,体罰をはじめハラスメントに関する報道が多く見られる。今回の調査でも,両学科の臨床実習におけるハラスメントの存在を確認した。PT・OTの臨床実習では伝統的にマンツーマンの指導体制が取られ,徒弟的になる可能性などデメリットも指摘されていた。その対策として症例ごとの指導者と,その指導者を統括する指導者というように複数指導者制が試みられるようになり,それぞれの指導者から多角的な視点で指導を受けることで,学習意欲向上に繋がるなどの有効性も報告されている。しかし,それぞれの指導者の指導方法や実習の到達目標が異なるなど,学生は戸惑い,指導者が2人になったと感じる場面もあった。そこで近年では,クリニカルクラークシップの形態での臨床実習の導入が注目されている。本調査の課題として,学生からの一方的な見解であることを考慮しなければならない。臨床実習中にSVに影響される学生は少なくない。多くの学生が卒業時に臨床実習の思い出を報告することからも,その役割は大きいと考える。今後は,指導者からの意見も取り入れ学生の夢や希望を断つことのない,臨床実習教育方法の構築に向けて努力していきたいと考える。【理学療法学研究としての意義】欧米諸国では指導者に対する批判的評価報告が散見される。一方で,本邦ではPT・OTの実習中のハラスメントに関する調査報告は極めて少なく,実態調査としての意義は大きい。臨床実習教育の手引きで,「良好なコミュニケーションのための鍵は指導者側に委ねられている」との指摘もあり,より良い臨床実習教育方法の構築に向けた調査報告,研究を継続していきたいと考える。
2 0 0 0 IR 銀行取締役の会社に対する責任 : 四国銀行株主代表訴訟事件を中心に
- 著者
- 高橋 紀夫
- 出版者
- 白鴎大学大学院法務研究科
- 雑誌
- 白鴎大学法科大学院紀要 = Hakuoh law review (ISSN:18824277)
- 巻号頁・発行日
- no.5, pp.61-104, 2011-10-01
2 0 0 0 OA マルチエージェントシステムにおける経済学的アプローチ
- 著者
- 松原 繁夫
- 出版者
- 公益社団法人 計測自動制御学会
- 雑誌
- 計測と制御 (ISSN:04534662)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.11, pp.948-953, 2016 (Released:2016-11-23)
- 参考文献数
- 27