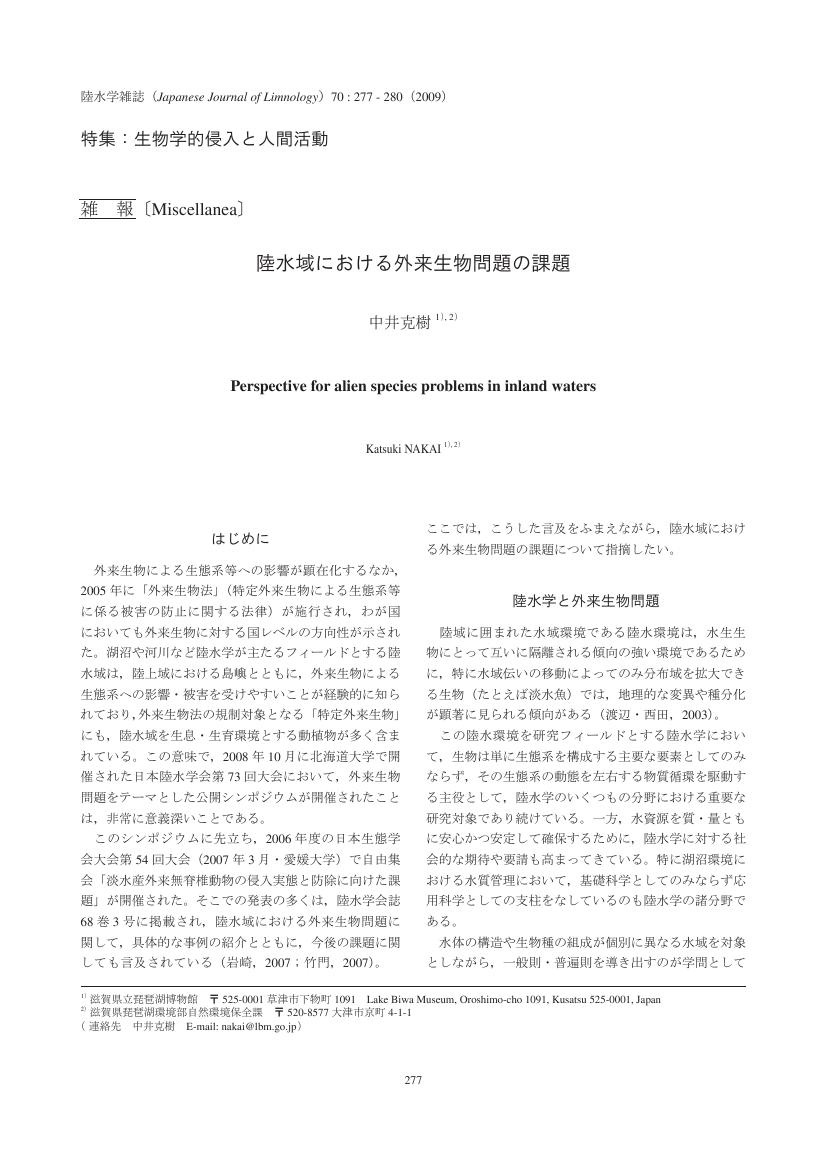1 0 0 0 OA 浅井春夫・松本伊智朗・湯澤直美(編)子どもの貧困 —子ども時代のしあわせ平等のために—
- 著者
- 上野 加代子
- 出版者
- 日本家族社会学会
- 雑誌
- 家族社会学研究 (ISSN:0916328X)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, pp.151, 2009-04-30 (Released:2010-04-30)
1 0 0 0 OA 高齢発症重症筋無力症の標準的神経治療
- 著者
- 本村 政勝
- 出版者
- 日本神経学会
- 雑誌
- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.8, pp.576-582, 2011 (Released:2011-08-29)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 4 6
重症筋無力症(myasthenia gravis,MG)は自己抗体の種類によって,1)アセチルコリン受容体(acetylcholine receptor,AChR)抗体陽性MG,2)筋特異的受容体型チロシンキナーゼ(muscle-specific receptor tyrosine kinase,MuSK)抗体陽性MG,そして,3)前記の抗体が検出されないdouble seronegative MGに分類される.本邦では,MG全体の約80~85%が抗AChR抗体陽性で,残りの5~10%で抗MuSK抗体が検出される.近年,世界中で高齢発症MGの頻度が増加しており,MGはもはや高齢者の病気であるともいわれている.本邦の全国調査2006年では,50歳以上で発症したMG患者が1987年の20%から42%に増加したことが証明された.それにともなって,2010年日本神経治療学会から,高齢発症MGの診断と治療の考え方を示す標準的治療指針が公表された.その内容は,高齢発症MG治療に関してのかぎられたエビデンスと臨床報告や個々の経験から本標準的治療を,高齢発症のMGの疫学的特徴,その臨床症状の特徴,さらに,治療,すなわち胸腺摘出術の適応や副腎皮質ステロイド薬や免疫抑制薬の投与方法などについて記述されている.その要旨は,高齢発症のMG患者では,若年発症MGと比較して,眼筋型の比率が高かった.治療では,胸腺腫を合併しない高齢発症のMG患者では,若年発症MGと比較して胸腺摘除の適応は少なく,ステロイドの副作用をおさえるために少量のステロイドと免疫抑制薬の併用が標準的治療となる.
- 著者
- 實川 幹朗
- 出版者
- 心の諸問題考究会
- 雑誌
- 心の諸問題論叢 (ISSN:13496905)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.35-42, 2004 (Released:2004-09-07)
- 参考文献数
- 3
伊藤幹治「日本文化の構造的理解をめざして」を対象とした批評論文。伊藤は、日常の生活の場が宗教的行事にも用いられるなどの民俗的事実から、「ハレとケとが自由に入れかわる」相互転換を「イレカワリの原理」と名づけた。こんにちでは聖俗のきびしい対立を理論的前提に民俗・宗教の分析の行なわれる場合が多いけれど、伊藤の提唱する原理の方が、世界的に見ても実態に合っている。聖俗の対立を和らげての理論化も考えられるが、そうすると、聖と俗を絶対的に区別してきた西欧のキリスト教社会の建て前に外れることとなる。この建て前それ自身もまた一つの民俗的事実なので、無視することはできない。つまり、聖と俗を基本概念とした分析は、いずれにしても民俗的事実に反するほかない。これに対しハレとケは、もともと相互に転換し、相手の契機を内に含むことが、建て前でも実態でも明らかである。そこで、こちらを基本概念にすえて、聖と俗を分析対象とする体制の方が、一貫性の面で優れている。聖と俗を、人為的に固定されたハレとケとして理解するのである。キリスト教の高度な神学や哲学は、本来は転換する民俗の固定化のための努力と理解することができる。伊藤の論旨は、この方向の可能性を開いたものだが、じゅうぶんに展開することとができなかったのが惜しまれる。
- 著者
- 土屋 智子 谷口 武俊 小杉 素子 小野寺 節雄 竹村 和久 帯刀 治 中村 博文 米澤 理加 盛岡 通
- 出版者
- 社会技術研究会
- 雑誌
- 社会技術研究論文集 (ISSN:13490184)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.16-25, 2009 (Released:2010-05-14)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 3 2
温暖化対策としての原子力の重要性が高まる中で, 信頼回復の切り札のひとつと考えられているのがリスクコミュニケーションの実施であるが, 原子力分野でこれを意図した活動が幅広く行なわれているとはいえない. 本稿では, 東海村を実験地として行われたリスクコミュニケーション活動の設計意図と実施内容を示すとともに, リスクコミュニケーションに対する住民と原子力事業者の評価を分析し, 原子力技術利用に伴うリスクに対する住民の視点を明らかにする. また, これらの住民の視点がどのように原子力施設の安全に関与するかを示し, リスクコミュニケーションにおける課題を論じる.
1 0 0 0 OA 陸水域における外来生物問題の課題
1 0 0 0 OA 外来生物問題の普及啓発の重要性と陸水域で望まれる対策について
1 0 0 0 OA 外来種(移入種)問題と緑化
1 0 0 0 OA 文化進化系進化ゲーム理論による社会的ジレンマ分析
- 著者
- 七條 達弘
- 出版者
- 数理社会学会
- 雑誌
- 理論と方法 (ISSN:09131442)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.2, pp.169-183, 2003-09-30 (Released:2009-01-20)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1
進化ゲーム理論には、「生物系」「経済系」、「文化進化系」の三つの理論体系がある。「文化進化系」は、「経済系」の進化ゲーム理論を発展させたものである。「経済系」の進化ゲーム理論では、利得が高い戦略が広まっていくと仮定するが、「文化進化系」では、この仮定が成立しない場合についても取り扱うことができ、多数派同調の効果や、戦略表明の効果が存在する場合も考慮する。本論文では、それぞれの効果をもちいて、社会的ジレンマ状況における協力の発生を示すモデルを作成する。このモデルにより、繰り返しゲーム特有の戦略を考慮しなくても、協力が進化しえることが示される。
1 0 0 0 OA 大腿骨近位部骨折患者におけるTimed “Up & Go” Testの再検査信頼性
- 著者
- 水澤 一樹
- 出版者
- 社団法人 日本理学療法士協会関東甲信越ブロック協議会
- 雑誌
- 関東甲信越ブロック理学療法士学会 第30回関東甲信越ブロック理学療法士学会 (ISSN:09169946)
- 巻号頁・発行日
- pp.70, 2011 (Released:2011-08-03)
【目的】大腿骨近位部骨折(PFF)は転倒による受傷が大半を占め,再転倒による再受傷も多い.そのためPFF患者において転倒リスクの評価は重要と考えられ,PFF患者においてTimed “Up & Go” Test(TUG)は,6カ月以内の転倒予測に役立つとされる(Kristensenら,2007).なお「測定値=真の値+誤差」であるため,評価を行う際はその評価方法の信頼性が重要となる.これまでTUGの再検査信頼性については,様々な対象において報告されているが,PFF患者における報告は少ない.なお信頼性の指標としてはShroutら(1973)の級内相関係数(ICC)が用いられることは多いが,ICCは相対信頼性であり,測定値が含む誤差の種類や量は不明である.そのため本研究の目的は,PFF患者におけるTUGの再検査信頼性について,相対信頼性のみではなく,絶対信頼性とともに検討することとした. 【方法】対象は歩行が可能なPFF患者17名(男性3名,女性14名)とし,年齢は79.4±9.4歳であった.対象には,あらかじめ研究内容について十分に説明を行い,書面にて同意を得た.TUGはPodsiadloら(1991)の原法に従い,受傷後51.6±20.4日目に初回,初回から1週間後に2回目を実施し,各日3回ずつ1名の理学療法士によって測定された.相対信頼性の指標はICC,絶対信頼性の指標は測定標準誤差(SEM)とし,いずれも95%信頼区間(95%CI)まで求めた.まず本研究における検者内信頼性を検討するため,ICC(1,1)を求め,目標のICC値を0.70として,Spearman-Brownの公式から必要な測定回数(k)を求めた.その後にICC(1,k)を求め,目標値である0.70以上の値が得られていることを確認した.そして最後に両測定日におけるk回の平均からICC(1,1)とSEMによって再検査信頼性を検討した.すべての解析にはR2.8.1(Free software)を使用した. 【結果】本研究における検者内信頼性はICC(1,1)が0.98(95%CI:0.97-0.99),SEMが1.71(95%CI:1.47-2.05)であった.Spearman-Brownの公式からk=0.04となり,必要な測定回数は1回と推定された.そのため,両測定日における1回目,2回目,3回目の測定を対象として再検査信頼性を求めると,ICC(1,1)は1回目が0.92(95%CI:0.81-0.98),2回目が0.98(95%CI:0.94-0.98),3回目が0.98(95%CI:0.94-0.99),SEMは1回目が3.67(95%CI:2.74-5.59),2回目が1.99(95%CI:1.48-3.02),3回目が2.00(95%CI:1.49-3.04)であった. 【考察】PFF患者に対してTUGを実施する場合,ICCの結果から再検査信頼性は十分に高いと考えられた.しかし範囲制約性の問題があるため,他の報告とICCの結果を比較する場合にはSEMを含めて判断しなければならない. 【まとめ】PFF患者17名を対象とし,TUGの再検査信頼性について検討した結果,他疾患者と同様に高い信頼性が確認された.
- 著者
- Kazumi KATSUMATA Kazuo KATSUMATA
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.4, pp.344-345, 2004 (Released:2005-02-04)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 1 1
- 著者
- Takanori Kotera Masahiro Mikuriya
- 出版者
- The Chemical Society of Japan
- 雑誌
- Chemistry Letters (ISSN:03667022)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.7, pp.654-655, 2002 (Released:2002-07-05)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 4
Thiolato-bridged hexanuclear mixed-valence complex, [CuI3CuII3(apampt)3Cl6] (Hapampt=1-[(3-aminopropyl)amino]-2-methylpropane-2-thiol), has been synthesized and characterized by X-ray crystallography. Spectroscopic data as well as structural features support a localized mixed-valence state. Magnetic susceptibility data show that a strong antiferromagnetic interaction is operating between the CuII ions.
- 著者
- 河原 正典 岡部 健
- 出版者
- 日本緩和医療学会
- 雑誌
- Palliative Care Research (ISSN:18805302)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.2, pp.133-142, 2011 (Released:2011-08-08)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 1
アセトアミノフェン(APAP)は, WHO方式がん疼痛治療法の中で非オピオイド鎮痛薬の選択肢の1つに位置づけられているが, わが国において, その有効性や安全性を検討した報告は少ない. われわれは, 当院で非オピオイド鎮痛薬として, 世界標準量のAPAP (1,800~2,400mg/日)を使用した182例(APAP群)と非ステロイド性消炎鎮痛薬(NSAIDs)を使用した86例(NSAIDs群)を比較することで, オピオイドとの併用も含めたがん疼痛管理における世界標準量APAPの有効性と安全性について後ろ向きに検討した. 疼痛管理状況はAPAP群とNSAIDs群で同等であった. オピオイドなどの併用薬剤についての検討が不足しているものの, がん疼痛治療における非オピオイド鎮痛薬としての世界標準量APAPは, 有効性の点でNSAIDsに劣らない結果が得られた. また, 安全性に関するAPAP群とNSAIDs群の比較では, 嘔気の発現頻度はAPAP群が有意に低く(p<0.01), AST・ALTが基準値の2.5倍を超えた患者の割合は両群同等であった. 有効性と安全性に関する以上の結果から, わが国においても世界標準量APAPは, がん疼痛治療における非オピオイド鎮痛薬の有用な選択肢の1つになると考えられた. Palliat Care Res 2011; 6(2): 133-142
1 0 0 0 OA インフォプロってなんだ? 私の仕事,学び,そして考え 第28回
- 著者
- 原田 智子
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.6, pp.351-352, 2011 (Released:2011-09-01)
- 著者
- Chiaki KOBAYASHI Kiyotaka SHIBATA
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)
- 巻号頁・発行日
- vol.89, no.4, pp.363-376, 2011-08-25 (Released:2011-08-31)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 1 4
Dynamical contributions to past long-term changes in the lower stratospheric ozone over the northern mid-latitudes are evaluated using a chemical transport model (CTM) forced by the horizontal wind of the Japanese 25-year Reanalysis (JRA-25). Two simulations (i.e., one is a simulation that prescribes the time-dependent vertical profile of halogens and the other is a simulation which uses the fixed vertical profile of halogens at 1979.) were conducted to estimate chemical and dynamical contributions to the long-term changes in stratospheric ozone during the last three decades. Different from previous similar studies using meteorological data of ECMWF (European Centre for Medium Weather Forecast) 40-year re-analysis (ERA-40), our current simulation does not show a large positive anomaly of simulated total ozone over northern mid-latitudes in the late 1980s, which is consistent with the observation. Because the trend of the fixed halogen simulation amounts to about two-third of that of the time-dependent halogen simulation during 1980–1993 in the northern mid-latitudes, it is evaluated that about two-thirds of the negative trend in total ozone comes from dynamics in the northern mid-latitudes. Since the increasing ozone from 1994 to 1998 is also represented in the fixed halogen simulation, it is considered that the increase of ozone was mainly due to dynamics as pointed out in previous studies. However the dynamical contribution to the trend after 1994 could not be evaluated in our simulation because of simulated ozone gap in 1998. In the same manner, it is evaluated that about two-thirds of the negative ozone trend in the lower stratosphere comes from dynamics in the northern mid-latitudes from 1980 to the mid-1990s. The simulation results indicate that the effect of transport (dynamical influence) is predominant for the negative ozone trend in the lower stratosphere from 1980 to mid-1990s, while the upper stratospheric ozone trend is strongly influenced by long-term changes in halogens (chemical influence).
1 0 0 0 OA 慢性仙腸関節性疼痛に対する仙腸関節前方固定術
- 著者
- 村上 栄一 菅野 晴夫 相澤 俊峰 奥野 洋史 野口 京子
- 出版者
- 日本腰痛学会
- 雑誌
- 日本腰痛学会雑誌 (ISSN:13459074)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1, pp.197-203, 2007 (Released:2008-01-22)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 1
仙腸関節ブロックや骨盤ベルトなどの保存療法の効果が持続せず,日常生活や就労に著しい障害のある仙腸関節性疼痛例に対して仙腸関節前方固定術を行った.男6例,女9例の15例で,年齢は平均49歳(30~86歳),罹病期間は平均3.9年(1~7年),術後経過期間は平均2.3年(6カ月~5年)であった.片側前方固定術を14例に,両側固定術(骨盤輪固定術)を1例に施行した.これらの症例について,関節癒合をCTで,また臨床症状をJOAスコア,VASによる疼痛の変化,Roland-Morris disability questionnaire(RDQ)で評価した.関節癒合は15例全例で得られていた.JOAスコアが術前平均5.6点(4~9点)から術後平均18点(7~24点)に,VASが84(70~93)から40(10~75)に,RDQ得点が21.1(17~23)から6.9(1~14)に改善した.仙腸関節前方固定術の成績は良好であり,保存療法に抵抗する症例には有効な治療法と考えられる.
1 0 0 0 OA 負結合交換ネットワークの権力予測に関する代数理論
- 著者
- フィリップ ボナシーチ 渡部 幹
- 出版者
- 数理社会学会
- 雑誌
- 理論と方法 (ISSN:09131442)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1, pp.33-52, 2003-03-31 (Released:2009-01-20)
- 参考文献数
- 22
個人の意思決定に関する、少数のシンプルかつ妥当な仮定から、負結合の交換ネットワークにおける権力の分布を予測するための構造的・代数的理論を示す。まず、示されたモデルから、複数の式が生成されることを論じる。そして、それらの式の解の特性から、交換ネットワークの類型化を示す。式の解には4つの可能性がある:(1)ネットワーク内のいくつかのポジションがすべての権力を持つような解が1つ存在する場合、(2)全てのポジションが同じ権力を持つような解が1つ存在する場合、(3)解が無限に存在し、構造的な分析では権力の分布を決定できない場合、(4)解がなく、権力が安定しない場合。 次に、通常、実験で検討されるような交換ネットワークよりもさらに多くの種類のネットワークに適用できるように、このモデルの様々な拡張を提唱する。提示されたモデルを、そのまま使用するか、わずかに変えるだけで、ネットワーク内の交換資源の価値が異なっている場合、ポジションによって行える交換の回数が異なる場合、交換が発生するためには3人またはそれ以上の参加者が必要な場合、の3つの状況において、権力の予測が可能となることを示す。
- 著者
- 加藤 尚武
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.11, pp.11_34-11_39, 2010-11-01 (Released:2011-01-20)
1 0 0 0 OA 慢性膵炎診断における超音波内視鏡の役割―特に早期慢性膵炎診断について―
- 著者
- 入澤 篤志 高木 忠之 渋川 悟朗 佐藤 愛 池田 恒彦 鈴木 玲 引地 拓人 佐藤 匡記 渡辺 晃 中村 純 阿部 洋子 二階堂 暁子 宍戸 昌一郎 飯塚 美伸 鈴木 啓二 小原 勝敏 大平 弘正
- 出版者
- 日本膵臓学会
- 雑誌
- 膵臓 (ISSN:09130071)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.29-36, 2011 (Released:2011-03-07)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 2
慢性膵炎の予後は芳しくなく,より早期での慢性膵炎診断の重要性が認識されていた.早期慢性膵炎は微細な膵実質・膵管変化のみが伴うと考えられ,従来の画像診断(体表超音波検査,CT,内視鏡的逆行性胆膵管造影:ERCP,など)では異常を捉えることは困難であった.近年,超音波内視鏡(EUS)による慢性膵炎診断が提唱され,その有用性は高く評価されてきた.EUSは経胃もしくは経十二指腸的に,至近距離から高解像度での観察が可能であり,他の検査では捉えられない異常が描出できる.2009年に慢性膵炎診断基準が改定され早期慢性膵炎診断が可能となり,この診断基準にEUS所見が明記された.より早期からの医療介入のためにも,慢性膵炎診療におけるEUSの役割の理解はきわめて重要である.特に,上腹部痛や背部痛を訴える患者で,明らかな消化管異常が認められず慢性膵炎が疑われる症例においては,積極的なEUS施行が推奨される.