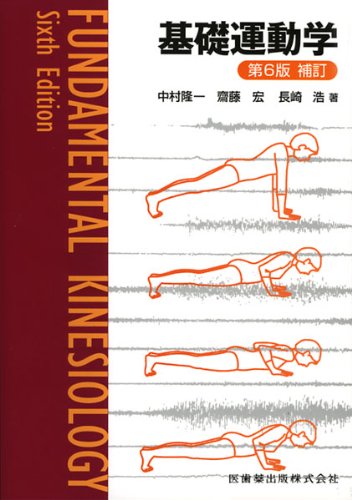1 0 0 0 OA 安全教育としての危険体験の展開
- 著者
- 中村 隆宏
- 出版者
- 安全工学会
- 雑誌
- 安全工学 (ISSN:05704480)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.6, pp.383-390, 2008-12-15 (Released:2016-10-31)
- 参考文献数
- 3
「危険体験」をはじめ「体験型教育」,「体感教育」といった安全教育手法が注目されている.その内容や手法は多岐にわたり,今後ともさまざまに発展する可能性を示している.一方で,今後の普及およびさらなる発展のためには,どのようなコンセプトに基づく教育であるべきかといった議論が不可避であり,危険体験という教育手法についてその成り立ちや経緯,実施上の問題点や課題についても検討・整理する必要がある. 本研究においては,さまざまな展開を示しつつある危険体験教育について,安全教育としての実質的な効果を高め有効な教育手法としての発展の方向性を探る観点から,危険体験教育を実施する教習機関などへの聞き取り調査を実施した.本稿では,調査結果の報告を含め,教育手法開発の背景,教育実施上の課題など,危険体験教育の問題点と今後の展開について検討する.
1 0 0 0 OA 安全教育における疑似的な危険体験の効果と課題
- 著者
- 中村 隆宏
- 出版者
- 安全工学会
- 雑誌
- 安全工学 (ISSN:05704480)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.2, pp.82-88, 2007-04-15 (Released:2016-11-30)
- 参考文献数
- 9
労働安全教育の現場では,「体験型教育」「体感教育」等の疑似的な体験を取り入れた教育手法が展開されている.しかし,その理論的背景について十分な検討がなされないまま「体験すること」のみが重視された結果,労働者の実質的な安全態度の向上につながらず,むしろ労働者の不安全行動を助長する事態が生じることも懸念される. 本稿では,労働安全教育における疑似的な体験の意義と諸課題について検討した.教育効果向上のためには,単なる体験にとどまることなく,実際場面で遭遇する危険とその対処方法について具体的なイメージを形成し,過去経験と結び付けて展開を図ることが重要である.また,危険補償行動に対して適切な対応を図らなければむしろ災害発生率を高める可能性があり,新たな教育手法の普及・展開においてはこうした副作用を十分に考慮する必要がある.
1 0 0 0 前立腺原発カルチノイドの1例
- 著者
- 三木 恒治 黒田 昌男 清原 久和 宇佐美 道之 中村 隆幸 古武 敏彦
- 出版者
- 社団法人 日本泌尿器科学会
- 雑誌
- 日本泌尿器科學會雑誌
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.3, pp.264-272, 1980
61歳男子の前立腺原発カルチノイドの1例を報告した. 主訴は排尿困難と肛門部疼痛であつた. またカルチノイド症候群は示さなかつた. 膀胱尿道造影, 直腸指診より前立腺癌と診断したが, 経直腸的前立腺生検による診断はカルチノイドであつた. しかし, 胸部ならびに胃腸レントゲン検査, 直腸鏡にて異常は認めなかつた. その他血清セロトニン値が345μg/lとやや高値を示した他血液学的検査で異常を認めなかつた. 患者は1976年11月11日直腸膀胱前立腺全摘, 回腸導管造設人工肛門造設術を施行した. また右腸骨リンパ腺に転移を認めた. 摘除標本は肉眼的には充実性腫瘍で前立腺部に相当する位置に存在し, 正常前立腺組織は殆んど認めなかつた.<br>組織学的には, 腫瘍は, 胞巣形成, ロゼット形成を示し, 組織化学的にはグリメリウス染色陽性で, マッソニフォンタナ染色陰性であり, 電子顕微鏡的には特徴的な分泌顆粒を認めた. 以上の所見より前立腺原発カルチノイドと診断した.<br>患者は術後1カ月5-FUの静注を行なつたが, 徐々に全身衰弱, 腰痛を来し, 術後4カ月後に死亡した. 剖検は施行されなかつた.
1 0 0 0 OA 成人鼠径ヘルニア治療時,偶然発見された混合型性腺異常発生症の1例
- 著者
- 安岡 利恵 宮垣 拓也 北尾 善孝 門谷 洋一 中村 隆一
- 出版者
- Japan Surgical Association
- 雑誌
- 日本臨床外科学会雑誌 (ISSN:13452843)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.8, pp.2210-2215, 2004-08-25 (Released:2009-03-31)
- 参考文献数
- 14
混合型性腺異常発生症では,染色体異常が主に45X/46XYなどのmosaicであるために,一側性腺が精巣で他側が線状性腺を持ち,未分化な膣,子宮,卵管などMüller管の遺残を認めることがある.また,混合型性腺異常発生症は様々な身体学的特徴を有する.本症は主に小児科医,小児外科医が関わる疾患であるが,今回われわれは45歳にして成人鼠径ヘルニア治療時に偶然混合型性腺異常発生症を発見し,十分なインフォームドコンセントのもと,線状性腺とMüller管遺残を摘出した興味深い症例を経験したので,これを報告する.
1 0 0 0 OA 腹腔鏡下に完全切除した腹腔内突出型腹壁脂肪腫の1例
- 著者
- 横田 和子 中村 隆俊 佐藤 武郎 樋口 格 山下 継史 渡邊 昌彦
- 出版者
- 日本臨床外科学会
- 雑誌
- 日本臨床外科学会雑誌 (ISSN:13452843)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.3, pp.615-619, 2017 (Released:2017-09-30)
- 参考文献数
- 11
症例は48歳,男性.人間ドックの腹部超音波検査にて,右腎腹側に6cm大の腫瘤を認め,精査目的に当院紹介となった.腹部造影CTでは,右腹横筋に接して6cm大の境界明瞭で内部均一な腫瘤性病変を認め,腹部MRIでは,T1脂肪抑制画像で内部均一な低信号を認めた.注腸造影検査では,横行結腸肝弯曲中心に壁外性の圧排像を認めた.以上より腹横筋脂肪腫が疑われ,悪性腫瘍が否定できないため手術の方針となった.画像上,腫瘍は腹腔内に突出していたため腹腔鏡下手術の方針とした.右肋骨弓下に突出する腫瘍を認め,周囲臓器への浸潤はなく腹膜および腹膜前脂肪織・腹横筋の一部とともに合併切除した.病理組織学的所見は,被膜を有し異型に乏しい脂肪組織の増生を認め,辺縁に全周性に筋組織が付着するintermuscular lipomaと診断した.腹壁由来脂肪腫を腹腔鏡下に切除しえた症例は非常に稀であるため,文献的考察を加えて報告する.
1 0 0 0 OA フィリップ・ペティットの共和主義論ー政治的自律と異議申し立て
- 著者
- 中村 隆志
- 出版者
- 關西大學法學會
- 雑誌
- 關西大學法學論集 (ISSN:0437648X)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.2, pp.59-90, 2011-07-31
1 0 0 0 複数食品による咀嚼の側性の定量的評価に関する研究
- 著者
- 椿本 貴昭 岩崎 正一郎 瑞森 崇弘 中村 隆志 高島 史男
- 出版者
- 社団法人 日本補綴歯科学会
- 雑誌
- 日本補綴歯科學會雜誌 = The journal of the Japan Prosthodontic Society (ISSN:03895386)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.4, pp.494-503, 2001-08-10
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 1 2
目的: 咀嚼の側性を客観的かつ定量的に評価する方法として, 左右側を指定しない自由咀嚼運動の左右側ストローク数より非対称性指数 (Asymmetry Index, 以下AI) を算出する方法を用い, 方法の妥当性, さらには食品による変化, 日間変動について検討することである.<BR>方法: 被験者として健常有歯顎者10名を選択し, チューイング・ガム, カマボコ, グミ・ゼリー, タクアン, スルメ, ピーナッツ, ジャイアント・コーンの計7種類を被験食品に用いた. 被験者に左右側を指定しない20秒間の自由咀嚼運動を行わせ, 左右側のストローク数を視覚的に数え, AIを算出した. 記録は各種食品1日1回, 1週間ごとに計3回行った.<BR>結果:(1) 左右側ストローク数からAIを算出することにより, 咀嚼の側性を定量的に表現できた.(2) 咀嚼の側性を捉える目安として, 3日間のAIの中央値, 範囲から, 各被験者を片側咀嚼型 (U型), 両側咀嚼型 (0型), 不定側咀嚼型 (V型) の3型に分類できた.(3) 軟性食品では0型が, 硬性食品ではU型が多い傾向があったが, 軟性食品内あるいは硬性食品内での性状による差は認められなかった.<BR>結論: 本実験で用いた咀嚼の側性の評価方法は客観的かつ定量的方法であり, 咀嚼の側性は各被験者において特徴的で, 食品の硬性により影響を受ける可能性が示唆された.
- 著者
- 中尾 英雄 荒川 順生 中村 隆洋 福島 正美
- 出版者
- The Pharmaceutical Society of Japan
- 雑誌
- Chemical and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:00092363)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.9, pp.1968-1979, 1972-09-25 (Released:2008-03-31)
- 被引用文献数
- 24 31
A series of 2, 5-bis (1-aziridinyl)-p-benzoquinone derivatives were synthesized and evaluated as antileukemic agents. The most active compounds against lymphoid leukemia L-1210 in BDF1 mice were 2, 5-bis (1-aziridinyl)-3-(2-carbamoyloxyethyl-1-methoxy)-6-methyl-p-benzoquinone, carbazilquinone (7), and related compounds (8, 23 and 24). Structure-activity relationships were discussed.
- 著者
- 白井 喜代子 中村 隆夫 楠原 俊昌 山本 尚武
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. MBE, MEとバイオサイバネティックス (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.104, no.179, pp.1-4, 2004-07-07
- 参考文献数
- 4
簡便な装置により無侵襲的な測定ができるという特長を持つインピーダンス法は,生体情報計測に適しており皮膚インピーダンスを用いた多くの応用計測がある.しかしながら,皮膚インピーダンスには個体差や部位差が存在し,これらは目的因子の変動と重なり評価を困難にしている.今回,応用計測を障害する個体差および部位差を較正するために,一般的なデータをもとに構築する皮膚インピーダンスの標準化モデルを提案した.各パラメータにおいて測定値とモデル皮膚インピーダンス値との相関は高かった.また,規格化皮膚インピーダンス値の変動係数は測定値の変動係数の約60%に減少し,本法の妥当性を確認できた.生体情報計測に標準化モデルを活用することは,測定値そのもので評価する方法と比較し診断精度は高く,今後の応用計測に有用と考えられる.
1 0 0 0 基礎運動学
- 著者
- 中村隆一 齋藤宏 長崎浩著
- 出版者
- 医歯薬出版
- 巻号頁・発行日
- 2003
1 0 0 0 IR ヒューム主義であるとはどのようなことか?
- 著者
- 中村 隆文
- 出版者
- 千葉大学大学院人文社会科学研究科
- 雑誌
- 千葉大学人文社会科学研究 (ISSN:13428403)
- 巻号頁・発行日
- no.17, pp.1-17, 2008-09
現代哲学思想において「ヒューム主義(Humeanism)」というものは、反実在論(anti-realism)、あるいはそれに准ずるような、性質に関する「非.認知主義(non-cognitivism) 」として、一般的には主観主義に近い形で理解される傾向にある1。そのような傾向のもと、或る種の反実在主義者(そして、そのほとんどが非-認知主義者であり、たとえば、A.J. エアーのような表出論者やS. ブラックバーンのような投影論者たち)はヒュームの主張を好意的に取り上げる一方、或る種の実在論者たち(たとえば、J. マクダウェルのような認知主義者)はヒュームの主張それ自体を批判しながら反ヒューム主義を提唱するという対立の図式が出来上がっている。しかし、そもそもそうした反実在論vs. 実在論の対立が、あたかもヒューム思想を認めるかどうかであるように図式化されていることについて、私はそこに違和感を感じる。もちろん、その対立図式のもとで生み出された各種議論はそれぞれ重要な意味をもっているのであるが、そもそもヒューム思想がそのような二分法によって理解されるべきものであるかどうかについて、本論考全体を通じて考えてゆきたい。 本論考で紹介するヒューム主義的思考法とは、簡単にいってしまえば、通常は当たり前とされるような関係(いわゆる「分かっている」)を分析し、それが必然的なものではないこと(しかし、同時にそれが不可欠な形で採用されてしまっていること)を論じる手法である。そうした手法を通じて、我々が通常当たり前のように用いている「私」「われわれ」の概念を分析しながら、ヒューム主義というものが奥深く、かつ非常に哲学的な態度であることを論
1 0 0 0 OA ホンダのスーパーカブのプラットフォーム分析 : 新興国市場での競争優位の要因
- 著者
- 中村 隆
- 出版者
- 国際ビジネス研究学会
- 雑誌
- 国際ビジネス研究 (ISSN:18835074)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.1, pp.33-44, 2014-04-30 (Released:2017-07-04)
新興国市場において、モジュール化が進展すると、日本企業の開発した製品は競争力を失う傾向がある。このような新興国市場における日本企業のジレンマを克服するためには、摺り合せの利点を活かしたプラットフォームを用いて品質と低コストを総合的に備えた製品を開発することが求められる。その具体例として、本稿は本田技研工業株式会社(以下「ホンダ」と略称)が開発したスーパーカブ(現地モデル)のタイ、ベトナム市場での事例を取り上げる。スーパーカブは、二輪車の中ではコモディティに近い製品ながら、新興国市場等で高い競争力を保持している。その背景には、摺り合わせ型のプラットフォームの完成度の高さに依拠する製品の品質の秀逸さと、サプライヤーとの組織間関係の革新による低コスト化の両立を図ったことがある。本稿の目的は、摺り合せ型プラットフォームにより品質等と組織間関係の革新による低コスト化を両立できれば、新興国市場でも競争力を保持できることを示すことにある。
1 0 0 0 OA イミダゾール体の選択的溶解法による光学分割
- 著者
- 中村 隆志 河合 伸高 町谷 晃司 加々良 耕二
- 出版者
- 公益社団法人 化学工学会
- 雑誌
- 化学工学論文集 (ISSN:0386216X)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.5, pp.618-623, 1997-09-10 (Released:2009-11-12)
- 参考文献数
- 6
イミダゾール体をエタノール水溶液中で, L-10-カンファースルホン酸と塩を形成させて光学分割する際に, 最少量の溶媒から両異性体の塩を結晶として充分析出させた後に, 少量の溶媒を徐々に添加して不要の異性体を優先的に溶解させる光学分割法を見い出した. 溶媒の添加方法にはよらず, 溶媒量により光学純度・収率が決定され, 溶解度から推算した値と一致した. 従来の冷却晶析法と比べ, 安定した収率 (50%) ・光学純度 (97%) で (+) イミダゾール体が得られ, 単位体積当たりの撹拌所要動力をスケールアップ因子として, 1,700l晶析槽で実験を行い, 1lスケールでの実験結果が再現できた.
- 著者
- Mwaura Jelvas 梅澤 有 中村 隆志 Kamau Joseph
- 出版者
- 日本地球惑星科学連合
- 雑誌
- JpGU-AGU Joint Meeting 2017
- 巻号頁・発行日
- 2017-03-10
The sources of anthropogenic nutrients and its spatial extent in three fringing reefs with differing human population gradients in Kenya were investigated using stable isotopes approaches. Nutrient concentrations and nitrate δ15N in seepage water clearly indicated that population density in the catchment and tourism along the coast contributed greatly to the extent of nutrient loading through the groundwater to adjacent reefs in Kenya. Although water column nutrient analyses did not show any significant difference among the 3 studied reefs, the chemical contents (i.e., δ15N and N contents) in the macroalgae and complementary use of seagrasses and sedimentary organic matter clearly indicated the different nutrient regime among the sites in higher special resolution. Higher δ15N and N contents in macrophytes showed terrestrial nutrients affected primary producers at onshore areas in Nyali and Mombasa reefs, but were mitigated by offshore water intrusion especially at Nyali. On the offshore reef flat, where the same species of macroalgae were not available, complementary use of δ15N in sedimentary organic matter suggested input of nutrients originated from the urban city of Mombasa. If population increases in future, nutrient conditions in shallower pristine reef, Vipingo, may be dramatically degraded due to its stagnant reef structure. This study represent the first assessment of the Kenyan coast that integrates water column nutrients and macrophyte δ15N analyses, showing direct evidence of the use of terrestrial nutrients by macrophyte and providing basic information for surveying the link between anthropogenic enrichment and ecosystem degradation including macroalgae proliferation in nearshore reefs.
1 0 0 0 OA 生体エネルギー論と熱測定
- 著者
- 中村 隆雄
- 出版者
- Japan Society of Calorimetry and Thermal Analysis
- 雑誌
- 熱測定 (ISSN:03862615)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.2, pp.78-83, 1979-05-25 (Released:2009-09-07)
- 参考文献数
- 14
Since the time of pioneer work of Lavoisier in 18th century, calorimetry have been one of the fundamental approaches in the study of bioenergetics. A review of the historical background of the calorimetric investigations in the field of bioenergetics was briefly described. Our recent construction of a twin-type microcalorimeter equipped with rapid response microthermistors and oxygen electrode, which allows simultaneous recording of heat production and oxygen consumption in a small volume (5cm3) of biochemical reaction systems, was introduced. Performance of the apparatus was tested with acid base neutralization reaction and some enzymatic reactions. Results from the measurements of the energy balance in the energy transducing reactions of rat liver mitochondria under various respiratory states were described with special interest on the mechanism and control of heat production in mitochondria by long chain unsaturated fatty acids.
- 著者
- 中村 隆英 伊藤 修
- 出版者
- 社会経済史学会
- 雑誌
- 社會經濟史學 (ISSN:00380113)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.2, pp.219-223, 1984-07-30
1 0 0 0 OA 総説 慢性肺性心の予後
- 著者
- 中村 隆 香取 瞭
- 出版者
- 公益財団法人 日本心臓財団
- 雑誌
- 心臓 (ISSN:05864488)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.6, pp.575-580, 1969-06-01 (Released:2013-05-24)
- 参考文献数
- 18
1 0 0 0 OA 気体体積の簡易測定とその応用(1)(化学実験虎の巻)
- 著者
- 中村 正信 中村 隆一
- 出版者
- 社団法人日本化学会
- 雑誌
- 化学と教育 (ISSN:03862151)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.6, pp.362-363, 2003-06-20
- 著者
- 中村 元紀 セシル ウェイ 神林 隆 井上 知洋 中村 隆幸 山口 正泰
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会総合大会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2005, no.2, pp."S-26"-"S-27", 2005-03-07
- 被引用文献数
- 1