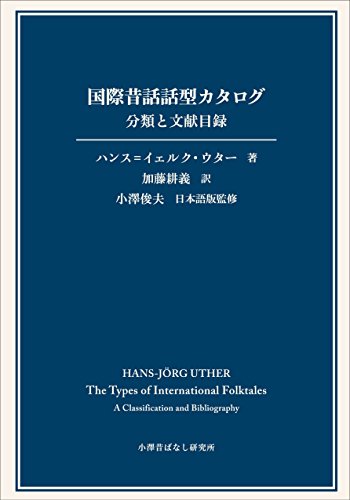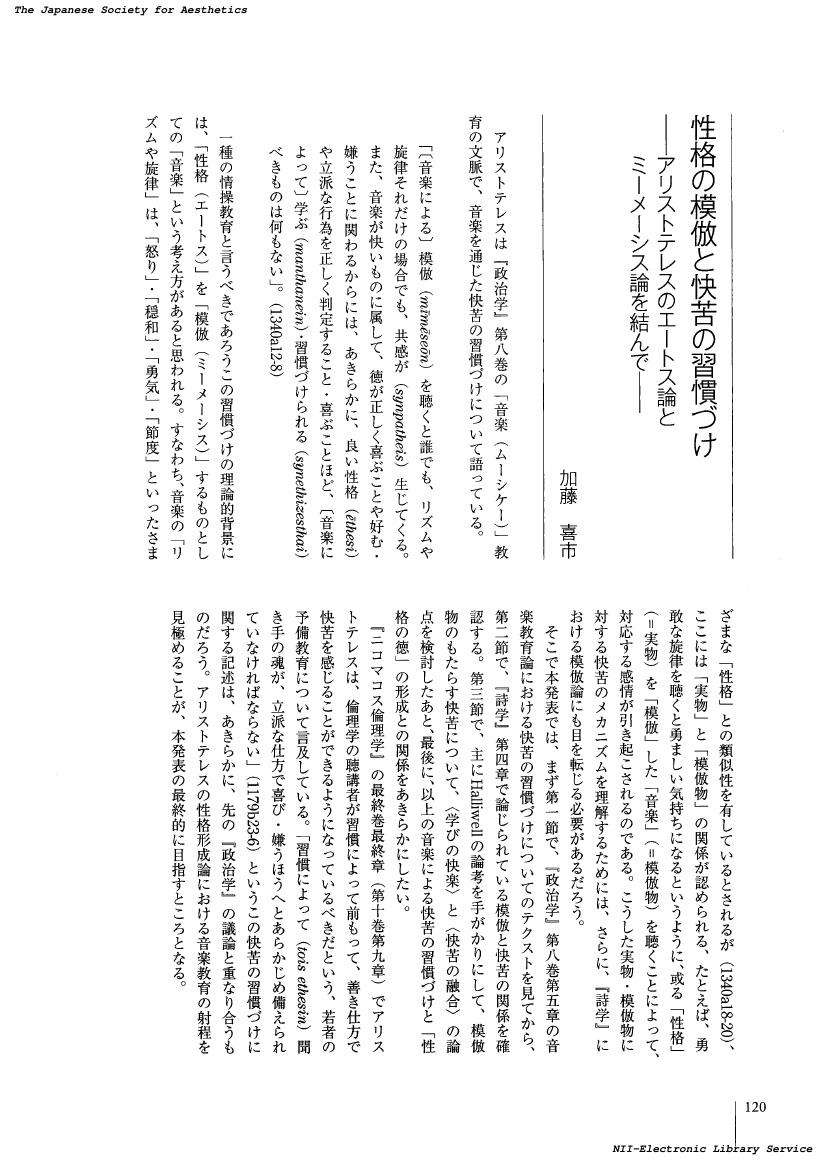9 0 0 0 OA 戦後日本の政治学と先住民問題 : 反省を込めて
- 著者
- 加藤 節
- 出版者
- 北海道大学大学院法学研究科 = Hokkaido University, School of Law
- 雑誌
- 北大法学論集 (ISSN:03855953)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.6, pp.250-245, 2017-03-31
9 0 0 0 OA ネオコグニトロンによる日本語の歴史的典籍におけるくずし字の認識
- 著者
- 早坂 太一 大野 亙 加藤 弓枝
- 出版者
- 豊田工業高等専門学校
- 雑誌
- 豊田工業高等専門学校研究紀要 (ISSN:02862603)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, pp.5-12, 2016-01-29
9 0 0 0 ドイツにおける森林資源利用の一形態としての「森の幼稚園」
- 著者
- 井本 萌 宮川 修一 フォン フラークシュタイン アレクサンドラ 川窪 伸光 加藤 正吾 岩澤 淳
- 出版者
- 日本森林学会
- 雑誌
- 日本森林学会誌 (ISSN:13498509)
- 巻号頁・発行日
- vol.96, no.1, pp.36-42, 2014
ドイツにおける「森の幼稚園」を市民による森林空間と資源の利用という観点から評価する目的で, ヘッセン州ベンスハイム市において2種類のアンケート調査を行った。まず, 幼稚園児の保護者による森の利用状況を調査した。子供が森の幼稚園, 一般の幼稚園のどちらに通っているかに関わらず, 週12回, 家族で, 散歩を目的に森を訪れる保護者が最も多く, 幼稚園児を持つ家族が近隣の森を訪れることは, 日常的な営みの一つと考えられた。次に, 地域と森の幼稚園における森林資源利用を比較した。地域住民が歴史的に食用, 茶・薬用, 工作・装飾, 燃料, 子供時代の遊びなどに用いてきた森林資源の利用は131例あった。自身の子供時代の遊びを除いた112例のうち90が現在も住民に利用されており, 90のうち64は森の幼稚園でも利用されていた。地域で現在利用されない22例のうち7例は森の幼稚園では自然教育を目的に利用されていた。一方, 森の幼稚園における利用例86のうち, 地域での利用履歴がないのは5例のみであった。このことから, 森の幼稚園における森林資源の利用は, 地域の森林資源利用の歴史を反映したものとなっていると考えられた。
9 0 0 0 OA 日本人論と仏教 : 山本七平の鈴木正三論をめぐって
- 著者
- 加藤 均 カトウ ヒトシ Kato Hitoshi
- 出版者
- 大阪外国語大学留学生日本語教育センター
- 雑誌
- 日本語・日本文化 (ISSN:09135359)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, pp.7-18, 2012-03
9 0 0 0 パーティクルフィルタとその実装法
- 著者
- 加藤丈和
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告コンピュータビジョンとイメージメディア(CVIM) (ISSN:09196072)
- 巻号頁・発行日
- vol.2007, no.1, pp.161-168, 2007-01-12
- 被引用文献数
- 37
本稿では,非線形,非ガウス型の時系列フィルタリング法である,パーティクルフィルタについて,特にIsardらのCondensation法に代表されるコンピュータビジョンにおける対象追跡への応用に焦点を当て,理論と実装法を概説する.時系列フィルタリングに関する基本的な考えからから,カルマンフィルタなどの線形,ガウス型のフィルタリング手法,パーティクルフィルタによる非線形,非ガウス型への拡張について説明し,具体的な実装例を紹介する.This article introduces the theory and the implementation of Particle Filter that is one of non-liner and non-gaussian filter. This paper explains the basic idea of Filtering of time series, Kalman-Filter that is liner and gaussian filter and Particle Filter. We introduces the implementation of Paticle filter.
9 0 0 0 拡張現実感システム構築ツールARToolKitの開発
- 著者
- 加藤 博一
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. PRMU, パターン認識・メディア理解 (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.101, no.652, pp.79-86, 2002-02-14
- 被引用文献数
- 58
本報告では,ARToolKitについて紹介し,その構成と動作原理について述べる.ARToolKitは,画像処理に基づく拡張現実感構築ツールで,オープンソースのライブラリとして公開されている.内部に識別用のパターンが描かれた黒色の正方形マーカを使用し,そのカメラ座標系における位置姿勢をリアルタイムに計測する.マーカ座標系を使用した3次元仮想物体描画を行うことで,ユーザの視点位置によらず,仮想物体とマーカの間で幾何学的整合性を維持できる.ARToolKitを用いることで,容易に拡張現実感システムを構築することができ,特にデスクトップ環境における拡張現実感システムの構築に有効である.
8 0 0 0 OA 心不全患者のEnd of Life Discussionに関する現状調査
- 著者
- 大上 耕作 今村 友香 八木 玲佳 井上 直美 門 恵子 加藤 貴雄 白井 由紀
- 出版者
- 日本緩和医療学会
- 雑誌
- Palliative Care Research (ISSN:18805302)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.3, pp.119-126, 2022 (Released:2022-09-30)
- 参考文献数
- 17
【目的】心不全患者と医療者の間で行われる人生の最終段階を意識した対話(EOLd)の現状と関連要因を明らかにする.【方法】京都大学医学部附属病院循環器内科で2015年4月から2020年3月に死亡した患者を対象に診療記録調査を行い,「予後説明」と「人生の最終段階の医療の話し合い」の有無と関連要因を検討した.【結果】109名中,予後説明は40名(36.7%),人生の最終段階の医療の話し合いは25名(22.9%)に実施されていた.予後説明の実施には,年齢(若年)・入院回数の多さ・緩和ケアチームの介入・人生の最終段階の医療の話し合いの実施が関連していた.人生の最終段階の医療の話し合いの実施には,性別(男性)・入院回数の多さ・心不全入院歴があること・緩和ケアチームの介入・予後説明の実施が関連していた.【結論】心不全患者のEOLdは重症および末期心不全患者を中心に行われている現状が示唆された.
8 0 0 0 OA ショック適応のある心電図波形に対してAEDがショック不要と判断した2例
- 著者
- 落合 香苗 齋藤 豊 種田 益造 加藤 啓一
- 出版者
- 一般社団法人 日本救急医学会
- 雑誌
- 日本救急医学会雑誌 (ISSN:0915924X)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.3, pp.125-132, 2011-03-15 (Released:2011-06-02)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 1 1
automated external defibrillator(AED)の普及に伴い,医療機関内で医師がAEDを操作する機会も増加している。我々は医師がショック適応と認識した心電図波形に対してAEDがショック不要と判断した2症例につき事後にデータを検証した。事例1:78歳,男性。前立腺腫瘍精査目的に入院し,病棟で心肺停止となりAEDを用いた心肺蘇生(cardiopulmonary resuscitation; CPR)が実施された。AEDモニター画面で医師が心室性頻拍(ventricular tachycardia; VT)と認識した心電図波形に対し,AEDはショック不要と判断した。事後検証にてこのVTは心拍数が少ないためショック適応外と判断されたことが判明した。事例2:56歳,女性。骨髄腫の化学療法入院中に心肺停止となりAEDを用いたCPRが実施された。AEDモニター上で医師はVTを認識したが,AEDはショック不要と判断した。事後検証にてこのVTはAEDの心電図解析中または充電中に振幅が減衰したためショック適応外と判断されたことが判明した。AEDは AHA(American Heart Association)とAAMI(Association for the Advancement of Medical Instrumentation)の勧告に基づいて,一般市民による誤ったショック実行を避けるため,感度より特異度を重視した設計となっている。医師はAEDの機能や性能限界を認識するとともにAEDの機種特性について精通し,AEDを使用したCPR中でも手動での除細動に切り替える必要性を常に考慮すべきである。
8 0 0 0 OA 天候や気圧変化による頭痛と五苓散の使用に関する調査
- 著者
- 石井 正和 育己 育己 加藤 大貴
- 出版者
- 日本社会薬学会
- 雑誌
- 社会薬学 (ISSN:09110585)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.1, pp.17-25, 2023-06-10 (Released:2023-06-28)
- 参考文献数
- 24
A questionnaire survey was conducted to investigate the use of goreisan for headaches caused by weather and atmospheric pressure changes, and to clarify issues in promoting treatment with goreisan. The subjects were men and women in their 20s to 40s who developed headaches due to changes in weather and atmospheric pressure. Medication was used by 58.0% of the migraine group and 42.5% of the other headaches group. Among them, 27.5% of the migraine group and 15.1% of the other headaches group had used goreisan. Regarding the method of use of goreisan, the most common answer for the migraine group was “used after feeling a sign that headache is likely to occur,” whereas for the other headaches group, the most common response was “used after headache has occurred.” In the migraine group, the most frequent premonitory symptom was “stiffness in the shoulders and neck.” More than 80% of both groups were satisfied with the use of goreisan. In addition, 77.8% of migraine group and 59.5% of the other headaches group of those who had never used goreisan answered that they would like to use goreisan for headaches caused by weather or atmospheric pressure changes in the future. As a reason for not wanting to use goreisan, over half of both groups answered that they did not like the taste of herbal medicines. It is necessary to offer tablets to patients that do not like the taste.
- 著者
- 今中 鏡子 加藤 集子 川野 純子 田方 真由美 畠山 敏慧
- 出版者
- 広島文化学園大学
- 雑誌
- 広島文化短期大学紀要 (ISSN:13483587)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.7-25, 2006-08-07
M施設から「五升炊きガス炊飯器でおいしいご飯が炊けないので,調べて欲しい」という相談をを契機として次の三つの差について実験を行った.加熱過程の差による炊飯米組織形態の比較,品種の差による炊飯米組織形態の比較,釜の差および炊飯量の差による炊飯米組織形態の比較である.(1)実験1 加熱過程の差による炊飯米組織形態の比較では,(1)適正加熱過程(2)早い沸騰加熱過程(3)沸騰遅れ加熱過程(4)早い沸騰熱不足について観察した.その観察結果とM施設炊飯米組織(図3-a)とを照合すると「早い沸騰熱不足」の組織(図3-e)と類似した.M施設の炊飯器は1時間かかって炊きあがるが,実際は浸漬を兼ね低い温度から徐々に加温,その後急激に加熱して4〜7分の間に沸騰し,余熱が無いため98℃以上の適温が保てず温度が下がり,おいしいご飯は炊けない.この組織は膨潤しきれない多角形のデンプン粒(S)や間隙が多い芯状の形態が観察された.(2)実験2 品種の差による炊飯米組織形態の比較では,釜内部をガーゼで仕切り,次の四品種の米を同時炊飯し,実験1と同様に適正加熱過程,早い沸騰加熱過程,沸騰遅れ加熱過程について観察した.試料は(1)新潟県産コシヒカリ(2)岩手県産ひとめぼれ(3)岩手県産あきたこまち(4)広島県産中生新千本(なかてしんせんぼん).1)四品種の比較 比較しやすいので,やや早い加熱後7分沸騰98℃以上20分間経を過した炊飯米組織を900倍で観察した.コシヒカリの細胞内に手まり状のデンプングループ(SG)があり,この中に膨潤したデンプン粒(S)がある.大きなものでは直径8μm前後であるが(図8-a),加熱前の米デンプンでは2〜5μmと小さい.コシヒカリのデンプン粒は,多角形でありデンプン粒と粒との間隙がグループの周辺部まで鮮明であった.ひとめぼれの組織は,コシヒカリに最も似た形態を持っていた(図8-b).あきたこまちは,ややコシヒカリに似ているが,グループ周辺部のデンプンは境界の鮮明さを欠いていた(図8-c).中生新千本はデンプン粒はコシヒカリのように,はっきりした多角形ではなく,グループ周辺部のデンプン粒は密着して観察された(図8-d).同じ釜内部で同じ温度過程を経たにもかかわらず特にデンプン粒に形態の差が見られた.2)コシヒカリの澱粉粒配列コシヒカリでは,グループ内のデンプン粒が直線的に並び二段三段と重なり,あたかも石垣のように見える部分が多い(図3-c,図8-a,図9-a,c,e,図13-a,b,c,f,図,図14-b,c,e).他の品種では,グループの中心から弧または円を描くような粒の配列が観察され,直線的な配列があっても二段三段と重なる構造はみられない.3)単粒の可能性 図12の米デンプンの偏光顕微鏡像は,川上による「形成中心を中心とした黒い十字が認められる」ことや図8-a,図13-bコシヒカリのデンプン粒と粒との鮮明な間隙が,米デンプン粒を覆う膜または隔壁の存在を示唆し,単粒である可能性を示している.一方米デンプンはグループ単位で形成され,これを複粒と言えば複粒であり,残された課題である.4)加熱過程と炊飯米組織形態との関係一覧今回の観察結果をまとめると表1のようになる.炊飯加熱過程ごとに細胞壁,デンプングループ,デンプン粒,加熱が進むと現れる動向性,沸騰が遅れると大量に生じるねばについて整理した.炊飯米の組織形態は部分によって様々な形態があり個体差もある.すなわち本実験結果として掲載した図(写真)はその平均的な部分を選んでいるが,米粒中心部分の写真を得れば表1から炊飯過程の推察はほぼ可能である.また熱による組織形態変化の速度が米により微妙に異なるので,厳密な表を完成するにはさらに品種別の観察が必要である.例えば適正加熱過程コシヒカリ図9-cに動向性は見られないが,図9-dの中生新千本ではところどころに出現しているなど中生新千本の方が熱の影響を早く受けやすい.(3)実験3 炊飯量および釜の差による炊飯米組織 形態の比較 1)適正炊飯過程による各種炊飯組織形態の類似釜の種類や少量大量の炊飯量にかかわらず適正加熱した場合であれば,米粒の組織形態は類似しているのではないかと予測し,(1)家庭用R社五合炊きガス炊飯器により米420gを適正加熱した米粒(図13-a,b)(2)病院給食A社縦型炊飯器内釜で米3kgを適正加熱した米粒(図13-c)(3)工場給食ライスボイラーで大量の米28〜40kgを適正加熱した米粒(図13-e)(4)市販の適正加熱された包装米飯Sb社280g入り米飯を表示通り高周波出力500W電子レンジ3分加熱した米粒(図13-f)(5)冷凍保存米「実験3(1)420gを適正加熱」した試料の一部200gを冷凍保存後(6)電子レンジで高周波出力600W4分間解凍し内部温度80℃になった米粒を観察した.いずれの場合も適正加熱過程を経過しているので,米粒組織は崩壊が少なく,規則性のある好ましい状態の組織形態を維持していた.2)その他の米(1)適正炊飯米蒸らし過ぎ(図13-d)の組織(2)塩飯(3)バターライス(4)粥などの組織形態を観察した.(4)炊飯に必要な必須条件と沸騰時間の範囲 炊飯過程で最も重安な必須条件は「米デンプンの糊化に必要な沸騰後98℃以上蒸らしを含めた20分間の熱量」であり,次に大切な条件は「適正な沸騰時間の範囲」である.1970年代から組織学的に追求してきた局限は,この範囲を求める実験でもあった.今回早い沸騰熱不足を加えて沸騰時間の差,四品種の差,炊飯量の差の実験を通して加熱後8〜15分の沸騰が安全な範囲であることを再確認した.この間の組織はいずれも規則性を保ち細胞やデンプングループの崩壊が少なくデンプン粒は良く膨潤していた.反対に沸騰時間の範囲や米デンプン糊化の時間をおろそかにすると芯の組織が残ったり,デンプングループが崩壊するなど良い状態は得られない.適正な沸騰範囲であっても11分を過ぎる頃から,部分的に動向性が現れるなど微妙な変化が起こり,ご飯の味や食感などに影響する.米デンプン糊化の必須条件を満たす釜であれば,加熱始めの水温を加減することで,主体的に適正範囲で沸騰時間を選び,好みのご飯を得ることができる.以上のことは家庭の炊飯,病院や工場給食の大量炊飯さらに市販の包装米飯の炊飯など,大量少量にかかわらず共通した過程であり「一粒一粒の米が良く炊き上がるために受ける加熱条件」として大切にしたい基本である.本研究にあたり,長年にわたって,食品形態観察のご指導をいただきました理学・医学博士川上いつゑ先生,当時プレパラート作成についてお力添えいただきました田村咲江先生,故和泉公美子先生,また当初から長年にわたり試料と情報をご提供くださいました橋本萬亀雄様,および試料提供と専門的なご助言をくださいました食協株式会社井尻哲様,恵南悦明様,さらに炊飯米試料を提供くださいました穐山宏子様,工場の炊飯実験に熱心にご協力くださいました当時の国鉄広島工場の皆様,その実験過程を克明に記録された頼實由紀子様に心より深く感謝申し上げます.
8 0 0 0 OA 分類群ごとにみた飼育動物の体重と摂取エネルギー量の関係
- 著者
- 三好 智子 袖山 修史 加藤 元海
- 出版者
- 日本家畜管理学会
- 雑誌
- 日本家畜管理学会誌・応用動物行動学会誌 (ISSN:18802133)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.2, pp.98-105, 2016-06-25 (Released:2016-12-27)
- 参考文献数
- 34
本研究では、高知県内と大阪府にある5ヶ所の動物園と水族館において、飼育動物の体重と給餌内容から、1日あたりの摂餌量とエネルギー量の推定を行なった。対象生物は、体の大きさではトビからジンベエザメまでを網羅し、分類群では哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類、頭足類の全35種191個体を対象とした。摂取する餌の重量やエネルギー量と体重の関係について、分類群ごとに特徴がみられるかを検証した。体重に対する餌重量の比の平均値は哺乳類で7.5%、鳥類で12.9%であったのに対して、爬虫両生類、魚類および頭足類は1%未満であった。単位体重あたりの摂取エネルギー量の平均値は哺乳類と鳥類は約100kcal/kgと高く、その他の分類群では15kcal/kg未満の低い値となった。単位体重あたりの餌摂取量に関しては恒温動物と変温動物との間に違いがみられたものの、1日あたりの摂取エネルギー量は体重の増大に比例して増加していたことから、飼育動物の摂取エネルギー量は分類群ごとに体重から推定できる可能性が示唆された。
- 著者
- ハンス=イェルク・ウター著 加藤耕義訳
- 出版者
- 小澤昔ばなし研究所
- 巻号頁・発行日
- 2016
8 0 0 0 OA 天安門事件 : 30 年後に浮かび上がる真相と謀略
- 著者
- 加藤 青延
- 出版者
- 武蔵野大学政治経済研究所
- 雑誌
- 武蔵野大学政治経済研究所年報 = Annual report of the Institute of Political Science & Economics, Musashino University (ISSN:21852170)
- 巻号頁・発行日
- no.19, pp.103-135, 2020-02-29
- 著者
- 田中 雄太 加藤 茜 伊藤 香 五十嵐 佑子 木下 里美 木澤 義之 宮下 光令
- 出版者
- 日本緩和医療学会
- 雑誌
- Palliative Care Research (ISSN:18805302)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.2, pp.129-136, 2023 (Released:2023-05-10)
- 参考文献数
- 24
【目的】緩和ケアの実践には,現場の医療者の認識や受容性などを考慮することが重要である.本研究の目的は,救急・集中治療領域の医師の緩和ケアに対する認識や緩和ケア実践の障壁を明らかにすることである.【方法】集中治療室および救命救急センターに勤務する医師を対象に緩和ケアに関する質問紙調査を実施し,自由記述データを質的に分析した.【結果】873名に質問紙を送付し,436名から回答を得た(回収率50%).そのうち,自由記述欄に回答した95名(11%)を分析対象とした.【結論】本研究の結果から,わが国における救急・集中治療領域の医師は緩和ケアを自らの役割と捉え,日常的なケアの一部と考えて実践している一方で,緩和ケア実践の難しさや不十分さを感じていることが推察された.実践の障壁として,緩和ケアチームのマンパワー不足と利用可能性,救急・集中治療領域における緩和ケアに対する認識が統一されていないことなどが存在していた.
8 0 0 0 OA 人工靭帯を用いた内側膝蓋大腿靱帯再建術症例における等尺性膝伸展筋力の特徴
- 著者
- 大場 健裕 小野 良輔 榊 善成 加藤 拓也 太田 萌香 藤岡 祥平 佐々木 和広 倉 秀治
- 出版者
- 一般社団法人 日本スポーツ理学療法学会
- 雑誌
- スポーツ理学療法学 (ISSN:27584356)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.13-20, 2023-03-23 (Released:2023-03-23)
- 参考文献数
- 34
【目的】人工靭帯による内側膝蓋大腿靭帯再建術(以下MPFLR)および脛骨粗面移行術(TTO)を併用した症例(以下MPFLR+TTO)における膝伸展筋力の特徴を明らかにすること。【方法】MPFLR群15名,MPFLR+TTO群11名を対象に,最終フォローアップ時(MPFL群22.8±15.6ヶ月;MPFL+TTO群22.8±9.6ヶ月)の等尺性膝伸展筋力を,膝関節90度及び30度で測定し,健患差および健患比を検証した。【結果】MPFLR群では,術側と非術側の間に等尺性膝伸展筋力の有意差はみられなかった。MPFLR+TTO群では,術側が非術側と比較して,有意に低い等尺性膝伸展筋力を示した。健患比は,MPFLR+TTO群がMPFLR群と比較して有意に低値を示した。【結論】人工靭帯によるMPFLRは,良好な膝伸展筋力の回復が得られる。一方で,TTOを併用した場合,膝伸展筋力の健患差が残存し,単独MPFLRと比較して術後の筋力回復が得られにくいことが示唆された。
8 0 0 0 ジェンダー論の練習問題(第46回)やおい/BL入門のために(1)
8 0 0 0 OA 理科教育で用いられる距離に関する大森係数について
- 著者
- 加藤 護 岡本 義雄
- 出版者
- 公益社団法人 日本地震学会
- 雑誌
- 地震 第2輯 (ISSN:00371114)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, pp.35-39, 2016-11-10 (Released:2017-01-07)
- 参考文献数
- 40
8 0 0 0 OA 目と眉の間隔の違いが顔の印象に及ぼす影響
- 著者
- 加藤 徹也 青木 滉一郎 菅原 徹 村上 智加 宮崎 正己
- 出版者
- 日本感性工学会
- 雑誌
- 日本感性工学会論文誌 (ISSN:18840833)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.3, pp.419-424, 2015 (Released:2015-08-28)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 2
We produced the average face by combining forty-one facial images of female college students in order to investigate how the facial impression changes depending on distance between eyes and eyebrows. Furthermore, we produced ten experiment samples by shortening or widening distance between them of the average face in five steps respectively. These images were presented individually to ninety college students, and they were asked to evaluate them using twenty adjective pairs. Consequently, the average face received high evaluations about likability-related impressions, while the faces with shorter distance between eyes and eyebrow got high evaluations about activity-related impressions. Moreover, two principal component (“degree of refinement” and “femininity”) were extracted as a result of principal component analysis to evaluation scores. It was found that degree of refinement was likely to be affected by the perceived size of the eyes, and femininity was defined by distance between eyes and eyebrow.
- 著者
- 加藤 喜市
- 出版者
- 美学会
- 雑誌
- 美学 (ISSN:05200962)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.2, pp.120, 2015-12-31 (Released:2017-05-22)