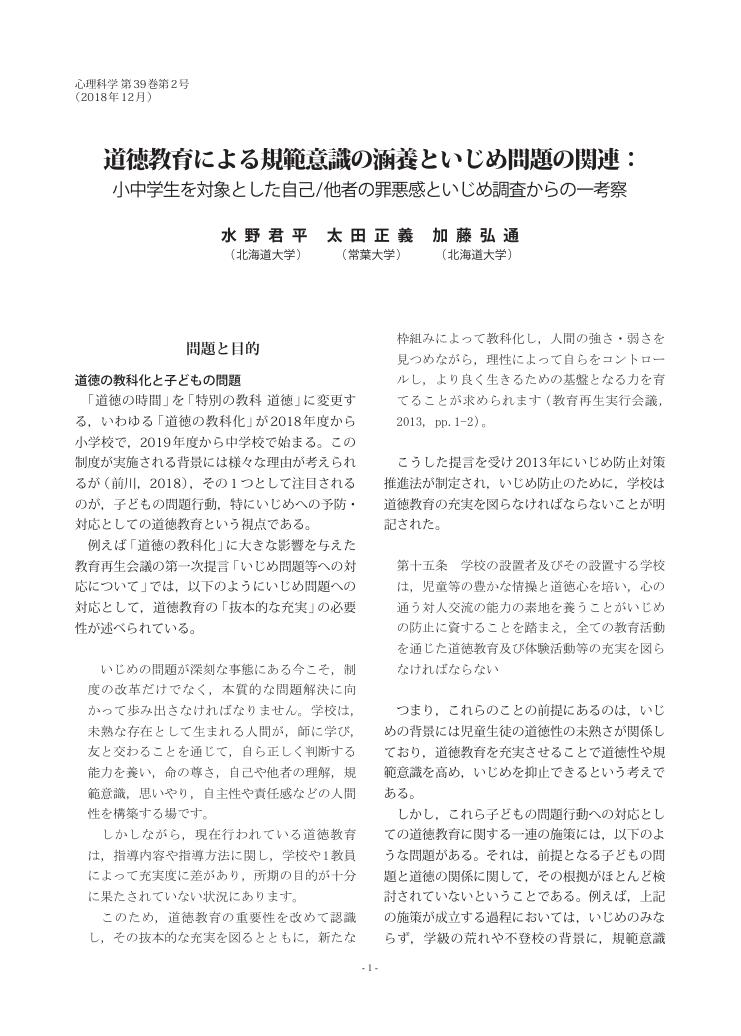12 0 0 0 OA C-H Borylation of Arenes: Steric-controlled Para-selectivity and Application to Molecular Nanocarbons
- 著者
- 瀬川 泰知 長瀬 真依 齋藤 雄太朗 加藤 健太 伊丹 健一郎
- 出版者
- The Society of Synthetic Organic Chemistry, Japan
- 雑誌
- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.11, pp.994-999, 2022-11-01 (Released:2022-11-05)
- 参考文献数
- 42
The selective and predictable C-H functionalization of arenes is a valuable method for the synthesis and modification of organic molecules in which regioisomer formation is often controlled by electronic factors or the presence of coordinating groups. On the other hand, the iridium-catalyzed C-H borylation of arenes can achieve unique steric-controlled regioselectivity. In this account, we describe our recent studies on the iridium-catalyzed C-H borylation of arenes: the development of novel catalytic systems that exhibit steric-controlled para-selectivity for mono- and unsymmetrically 1,2-disubstituted benzenes; and their application to the functionalization of large polycyclic aromatic hydrocarbons (molecular nanocarbons).
12 0 0 0 OA 京料理における一番だしのグルタミン酸含有量と香気成分について
- 著者
- 成瀬 宇平 角田 文 加藤 真理 秋田 正治 村松 啓義 Uhei NARUSE Aya TSUNODA Mari KATO Masaharu AKITA Takayoshi MURAMATSU
- 雑誌
- 鎌倉女子大学紀要 = The journal of Kamakura Women's University (ISSN:09199780)
- 巻号頁・発行日
- no.10, pp.141-145, 2003-03-31
京料理の手法を参考に昆布だし汁のグルタミン酸量とだしの調製条件との関連について検討し,さらに昆布だしにかつお節を加えた「一番だし」の香気成分についてガスクロマトグラフィーマススペクトロメトリー(GC-MS)を用いて検討し,次の結果を得た。1)だし汁を調製する水の温度は60℃,昆布の浸漬時間が60分間のだし汁のグルタミン酸量は他の条件に比べて多かったため,京料理のだしを調製する方法は本実験と一致した。2)京料理では昆布に利尻昆布を使用するのは,濃度の薄いだしをとるためと考えられる。3)一番だしの主な香気成分はかつお節由来の成分であった。
12 0 0 0 OA 幼児に対するネオニコチノイド系殺虫剤の曝露評価
- 著者
- 池中 良徳 宮原 裕一 一瀬 貴大 八木橋 美緒 中山 翔太 水川 葉月 平 久美子 有薗 幸司 高橋 圭介 加藤 恵介 遠山 千春 石塚 真由美
- 出版者
- 日本毒性学会
- 雑誌
- 日本毒性学会学術年会 第44回日本毒性学会学術年会
- 巻号頁・発行日
- pp.O-20, 2017 (Released:2018-03-29)
ネオニコチノイド系殺虫剤は、哺乳類における体内蓄積性は短く、昆虫とヒトのニコチン受容体に対する親和性の違いから、ヒトに対する毒性は相対的に低いため、一定の基準以下であれば、日常生活においてその毒性は無視できると考えられている。しかし、日本では諸外国と比べ数倍~数十倍と果物や野菜、茶葉における食品残留基準値が高く設定されていること、また、記憶・学習などの脳機能に及ぼす影響をはじめ、発達神経毒性には不明な点が多いことなどから、健康に及ぼす懸念が払拭できていない。とりわけ、感受性が高いこどもたちや化学物質に過敏な人々の健康へのリスクを評価するためには、ネオニコチノイドが体内にどの程度取り込まれているかを把握することがまず必要である。そこで本調査では、長野県上田市の松くい虫防除が行われている地域の住民のうち、感受性が高いと考えられる小児(3歳~6歳)から尿を採取し、尿中のネオニコチノイドおよびその代謝物を測定することで、曝露評価を行う事を目的とした。当該調査では、松枯れ防止事業に用いる薬剤(エコワン3フロワブル、主要成分:Thiacloprid)の散布時期の前後に、46人の幼児から提供された尿試料中のネオニコチノイドとその代謝産物を測定した。また、同時に大気サンプルもエアーサンプラーを用いて採取し、分析に供した。分析した結果、Thiaclopridは検出頻度が30%程度であり、濃度は<LOD ~ 0.13 µg/Lであった。この頻度と濃度は、Dinotefuran(頻度、48~56%;濃度、<LOD ~ 72 µg/L)やN-dm-Acetamiprid(頻度、83~94%;濃度<LOD~18.7 µg/L)など今回検出された他のネオニコチノイドに比べて低い値であった。次に、尿中濃度からThiaclopridの曝露量を推定した結果、幼児一人当たり最大で1720 ng/日(平均160 ng/日)と計算された。また、分析対象とした全ネオニコチノイドの曝露量は最大640 µg/日であり、中でもDinotefuranの曝露量は最大450 µg/dayに達した。一方、これらの曝露量はADIに比べThiaclopridで1%未満(ADI;180 µg/日)、Dinotefuranで10%程度(ADI;3300 µg/日)であった。
12 0 0 0 CHI勉強会2017:ネットワーク連携した勉強会とその支援システム
- 著者
- 松村 耕平 尾形 正泰 小野 哲雄 加藤 淳 阪口 紗季 坂本 大介 杉本 雅則 角 康之 中村 裕美 西田 健志 樋口 啓太 安尾 萌 渡邉 拓貴
- 雑誌
- 研究報告ヒューマンコンピュータインタラクション(HCI) (ISSN:21888760)
- 巻号頁・発行日
- vol.2017-HCI-174, no.13, pp.1-8, 2017-08-16
ACM CHI に採録された論文を読み合う勉強会,CHI 勉強会 2017 を開催した.勉強会では ACM CHI2017 に採録された 599 件の論文を参加者が分担して読み合う.これによって,参加者は先端の HCI 研究を概観することができる.本年度は,勉強会をスムースに実施し,また,参加者の支援を行うために支援システムを導入した.システムの分析から,CHI 勉強会がどのような特徴を持っているのか,そして今後どのようにデザインされていくべきなのか議論する.
12 0 0 0 OA グルタミン酸受容体 (GluR) 抗体が陽性であった髄膜脳炎の16歳男児例
- 著者
- 冨岡 志保 下野 昌幸 加藤 絢子 高野 健一 塩田 直樹 高橋 幸利
- 出版者
- 一般社団法人 日本小児神経学会
- 雑誌
- 脳と発達 (ISSN:00290831)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.1, pp.42-46, 2008-01-01 (Released:2011-12-12)
- 参考文献数
- 9
全般性けいれんの後に発熱, 頭痛, 項部硬直が持続した16歳男児.ごく軽度の意識低下, 脳波で前頭葉に連続性棘徐波および髄液細胞数上昇, IgG indexの上昇とoligoclonal IgG band陽性を認めた.頭部MRIのFLAIR像で両側半球に散在する部分的灰白質の信号亢進が疑われた.髄膜脳炎と判断し, methylprednisolone pulse療法を実施したところ, 臨床症状と脳波異常は軽快した.髄液中の抗グルタミン酸受容体 (以下GluR) は入院時ε2・δ2に対するIgG・IgM抗体がともに陽性であり, 軽快時は両抗体がともに陰性となった.抗GluR抗体が陽性になる髄膜脳炎の中に, Rasmussen脳炎とは明らかに異なる経過をとり, 治療に反応する予後良好な一群が存在する可能性が強く示唆された.
12 0 0 0 マイクロブログから抽出したユーザの習慣に基づく行動推定に関する研究
- 著者
- 田中 成典 中村 健二 寺口 敏生 中本 聖也 加藤 諒
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌データベース(TOD) (ISSN:18827799)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.3, pp.73-89, 2013-06-28
携帯端末の普及にともない,ユーザの状況に応じて様々な情報をリアルタイムに提供するサービスに注目が集まっている.そのため,GPSから取得した位置情報や,マイクロブログの投稿内容からユーザの行動を推定する研究が行われている.著者らは,これらに加えて,新たにユーザの習慣的な行動に着目した推定手法について検討を行った.本研究では,マイクロブログにおけるユーザの投稿内容と投稿数の変化から行動のパターンを抽出し,指定した時間帯における習慣的な行動を推定する手法を提案する.この手法により,マイクロブログの投稿内容には行動に関する記述がない場合でも,指定した時間帯におけるユーザの行動を推定できる.実証実験では,投稿内容のみを用いた手法と習慣行動もあわせて考慮する本手法とを比較し,提案手法の有用性について検証した.Services to provide variety of information in real time with reference to users' situations are receiving attention, as portable terminals have become widespread. Accordingly, some studies are being made to estimate the users' activities from their location information obtained by GPS or from the contents of their microblog posts. In addition to these, the author and his colleagues examined a new estimation approach focused on the habitual behavior of users. The present study proposes an estimation method of users' habitual behavior within designated periods of time by extracting behavioral patterns from the changes in contents and numbers of their posts in microblogs. This method enables estimation of users' behavior within designated time periods without any behavioral description provided in their microblog posts. Our demonstration experiments compare a method of merely using posted contents with this method that also considers habitual behavior as well, and verify its usability.
- 著者
- 加藤 まり 門間 晶子 山口 知香枝
- 出版者
- 一般社団法人 日本看護研究学会
- 雑誌
- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)
- 巻号頁・発行日
- pp.20191125077, (Released:2020-05-01)
- 参考文献数
- 34
本研究は,知的障害を伴わないASDがある母親が経験している子育てを,母親の視点から明らかにすることを目的とし,研究協力者6名に半構造化面接を行い,修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチを用いて分析した。その結果,母親の子育ては,ASDとの診断を受けておらず子どもが乳幼児の頃は【“世間並み”との隔たりにもがき,我が子より自分のことで精一杯】であった。しかし,【自らの診断を揺れながら受け入れ,折り合うことを獲得する】ことで,〈我が子と自分のありのままを尊ぶ〉子育てへと転換した。そして,我が子やASDの人々が世の中に受け入れられるよう【ASDと付き合いながら親子で自分らしく生き,社会に発信しようとする】に至っていた。ASDの母親への子育て支援は,母親のペースや子育ての具体的な見通しを大切にし,自らのユニークさや自分らしい子どもとの関係の結び方に気づけるような関わり方が求められている。
11 0 0 0 OA 外向性および内向性の自己呈示が呈示者の顕在的・潜在的外向性に与える影響
- 著者
- 上田 皐介 稲垣 勉 山形 伸二 加藤 弘通
- 出版者
- 日本パーソナリティ心理学会
- 雑誌
- パーソナリティ研究 (ISSN:13488406)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.2, pp.57-68, 2023-07-18 (Released:2023-07-18)
- 参考文献数
- 16
本研究は,外向性・内向性を印象づける自己呈示の前後で呈示者の顕在的・潜在的外向性に変化が生じるか,および公的状況(隣室に他者がいて,その人に個人情報を伝えたうえで自己呈示する)と私的状況(録音のみで個人情報も明かさずに自己呈示する)でその変化の大きさが異なるかを検討した。62名の参加者を2(呈示特性:外向性・内向性)×2(状況:公的・私的)の4条件に無作為に割り当てた。顕在的・潜在的外向性のそれぞれについて,測定時点(自己呈示前・後)を個人内要因とする3要因の分散分析を行った。その結果,潜在的外向性についての測定時点の主効果のみが有意であり,自己呈示は呈示特性,状況にかかわらず潜在的外向性を高める一方,顕在的外向性には影響しないことが示された。潜在的外向性に変化が生じたメカニズムや先行研究との結果の不一致が生じた理由,特に直前の測定が顕在的外向性の変化を抑制した可能性について考察した。
11 0 0 0 OA 名古屋城大天守宝暦大修理における本体上げ起し修理について
- 著者
- 麓 和善 加藤 由香
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.651, pp.1231-1239, 2010-05-30 (Released:2010-07-26)
The Principal Tower of Nagoya Castle was repaired on a large scale from 1752 to 1755. This paper evaluates and analyzes the Principal Tower based on historical drawings and specifications, which explain the repair of the main body of castle tower. The northern and the western parts of the first and the second layers on the top of the stone wall of the Principal Tower were dismantled before the stone wall was dismantled. Also, the builders cleverly applied a system of levers. Then the subsidence and the inclination of the Principal Tower were fixed logically and systematically using the system.
11 0 0 0 OA うつ病の責任脳回路の系統的同定とニューロン・グリア傷害の実像解明
うつ病の神経炎症仮説に基づき、動物実験としては、グラム陰性菌内毒素をマウスに投与して、行動および脳内の組織化学的変化について研究した。広範囲に及ぶミクログリアの一過性の活性化は見られたが、それを通じたアストログリア、オリゴデンドログリアへの影響は検出できなかった。ミクログリア活性化阻害物質であるミノサイクリンの投与は、内毒素投与の有無にかかわらず、抑うつ様行動を惹起した。培養細胞系では、ヒト末梢血中の単球から、ミクログリア様細胞を誘導することに成功し、気分障害罹患者を対象とする画像研究でも、拡散テンソル画像を集積した。これらの研究を通じ、うつ病と神経炎症の関連についてさらに知見を深めた。
11 0 0 0 OA アルミニウム-クエン酸キレートの結合比と安定度定数
- 著者
- 加藤 正義
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 工業化学雑誌 (ISSN:00232734)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.2, pp.182-187, 1966-02-05 (Released:2011-09-02)
- 参考文献数
- 16
「アルミニウムの腐食に関する研究」の一環として,クエン酸のようなアルミニウムに対するキレート化剤が,アルミニウムの腐食に対していかなる影響を及ぼすかを知るための基礎的知見を得るために表題のような研究を行なった。測定は滴定法によった。すなわち硝酸カリウムによってイオン強度を0.1に保った,クエン酸単独液,クエン酸とアルミニウムイオンとを1 : 1 モル比に混合した液および2 : 1 モル比に混合した液を標準濃度の水酸化カリウム溶液で滴定し, その滴定曲線からキレートの結合比と安定度定数を求めた。その結果pH = 3.7 ~ 4.5 の範囲内では, アルミニウムはクエン酸と1 : 1 のモル比で結合し, クエン酸のもつ水酸基も配位に与かることを知った。またその安定度定数K= [AlCit-] / [Al3+] [Cit4-] は1014±0.1であると計算された。3.7よりも低いpH域では酸性キレートがAlCit-と共存すると考えられ,また4.5よりも高いpH域ではアルミニウムイオンが加水分解する反応と, AlCit- にさらに水酸基が配位して(OH) AlCit2- という塩基性キレートが生ずる反応とが併発するものと推定された。加水分解生成物をBrosset に従いAl6(OH)153+ と考えて, この(OH) AlCit2-の安定度定数K' = [(OH)AlCit2-] /[AlCit-][OH-]は106.6±0.3と計算された。
11 0 0 0 OA 第24回図学教育研究会報告
- 著者
- 久保田 祐貴 加藤 昂英 一柳 里樹
- 出版者
- 北海道大学 高等教育推進機構 オープンエデュケーションセンター 科学技術コミュニケーション教育研究部門(CoSTEP)
- 雑誌
- 科学技術コミュニケーション (ISSN:18818390)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, pp.61-74, 2021-03
近年,参加者それぞれが,新たな視点や科学との関わり方を見いだすことのできる,対話を伴う科学技術コミュニケーションが注目されている.その実践では,科学技術に対する参加者の意見や知識を説明者や他の参加者が把握するとともに,参加者と説明者が共同で新たなアイデアや視点を生み出すことが重要な目的となる.本報告では,著者らのUTaTané における一連の活動から2つの実践例を紹介する.これらの実践では,当事者性・受容可能性・柔軟性の3点に配慮した実践設計を行った.さらに,参加者の創作活動を対話の起点とすることで,参加者と説明者の双方が新たなアイデアや視点を見出すことを目指した.結果として,知己の者同士の直接的な対話だけでなく,初対面の者同士の対話や掲示された創作物を通した間接的な対話など,多様な形態の対話が実現した.特に,参加者が自発的に話題を提供することで,他の参加者や説明者が新たな視点を得る場面もあった.加えて,「きっかけから探究への一気通貫のデザイン」が対話を伴う科学技術コミュニケーションを行う上で重要であることが示唆された.これらの実践と考察は,参加者の相互交流や参画を促す実践を行う上での試金石となり,実践を組み立てる際の一助となることが期待される.
11 0 0 0 OA 戦前の鉄道における駅等級制度とその運用
- 著者
- 平野 勝也 加藤 優平
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集D2(土木史) (ISSN:21856532)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.1, pp.1-12, 2019 (Released:2019-02-20)
- 参考文献数
- 88
標準設計は短期間に社会基盤整備をする上で有用であるが,画一的な景観が形成されるという大きな課題がある.画一的な社会基盤整備を避けるためには,選択と集中による差別化が必要であろう.本論文はそうした社会基盤整備制度の基礎資料とするために,戦前の駅等級制度を調査した.その結果,一等駅もしくは二等駅に指定することで,特別設計を行い,重要な駅についてはコストをかけた駅建築が実現していることが明らかとなった一方,それ以外の駅においては,標準設計により迅速な整備が行われていた.
11 0 0 0 OA 幕末維新期の商品流通と貨幣の使用実態について : 東讃岐地方の事例から
- 著者
- 加藤 慶一郎 鎮目 雅人
- 出版者
- 社会経済史学会
- 雑誌
- 社会経済史学 (ISSN:00380113)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.4, pp.545-561, 2014-02-25 (Released:2017-05-17)
本稿では,幕末維新期における貨幣の使用実態について検討する。具体的には,幕末において主に匁建ての藩札が使用されていた東讃岐地方の商家の帳簿に記載された個々の取引の分析をもとに,同地方において匁建ての藩札から円貨による取引に移行する過程を明らかにする。分析の結果,新貨条例が公布され,円という通貨単位が導入された明治4年時点では,東讃岐地方では主に匁建ての藩札が使用されていたと考えられること,明治4年から明治9年頃までの間,東讃岐地方では,円単位の紙幣のほか,匁単位の藩札,銭貨などの各種貨幣が混合流通していた可能性が高いこと,明治9年の秋口以降,支払いにおける円貨の比率が急速に高まり,地域内における貨幣の流通状況に変化が生じていたことが示される。本稿の方法論を,各地に残された帳簿の分析に応用することで,同時期における貨幣使用の実態を,より厳密なかたちで検証することができると考えられる。
11 0 0 0 OA こころのミクログリア仮説解明に向けたトランスレーショナル研究
- 著者
- 加藤 隆弘 扇谷 昌宏 渡部 幹 神庭 重信
- 出版者
- 日本生物学的精神医学会
- 雑誌
- 日本生物学的精神医学会誌 (ISSN:21866619)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.2-7, 2016 (Released:2017-09-26)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 1
脳内の主要な免疫細胞であるミクログリアは,さまざまな脳内環境変化に応答して活動性が高まると,炎症性サイトカインやフリーラジカルといった神経傷害因子を産生し,脳内の炎症免疫機構を司っている。ストレスがミクログリアの活動性を変容させるという知見も齧歯類モデルにより明らかになりつつある。近年の死後脳研究や PET を用いた生体脳研究において,さまざまな精神疾患患者の脳内でミクログリアの過剰活性化が報告されている。精神疾患の病態機構にストレスの寄与は大きく,ストレス→ミクログリア活性化→精神病理(こころの病)というパスウェイが想定されるがほとんど解明されていない。 筆者らの研究室では,心理社会的ストレスがミクログリア活動性を介してヒトの心理社会的行動を変容させるという仮説(こころのミクログリア仮説)を提唱し,その解明に向けて,動物とヒトとの知見を繋ぐための双方向性の研究を推進している。健常成人男性においてミクログリア活性化抑制作用を有する抗生物質ミノサイクリン内服により,強いストレス下で性格(特に協調性)にもとづく意思決定が変容することを以前報告しており,最近筆者らが行った急性ストレスモデルマウス実験では,海馬ミクログリア由来 TNF-α産生を伴うワーキングメモリー障害が TNF-α阻害薬により軽減させることを見出した。本稿では,こうしたトランスレーショナル研究の一端を紹介する。
11 0 0 0 OA 2.小児と思春期の鉄欠乏性貧血
- 著者
- 加藤 陽子
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.99, no.6, pp.1201-1206, 2010 (Released:2013-04-10)
- 参考文献数
- 25
小児の鉄欠乏性貧血は,急激な発育による鉄の需要が増大する離乳期と思春期が好発年齢である.頻度の高さ,発達や精神神経活動に及ぼす影響の大きさ,日々の栄養/食育の観点からも,多角的に捉え医学的に対応する必要がある.
11 0 0 0 OA 新型コロナウイルス感染症に関する壮年パネル調査 ―概要と記述統計分析―
- 著者
- 飯田 高 石田 賢示 伊藤 亜聖 勝又 裕斗 加藤 晋 庄司 匡宏 ケネス・盛・マッケルウェイン
- 出版者
- 国立大学法人 東京大学社会科学研究所
- 雑誌
- 社会科学研究 (ISSN:03873307)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.2, pp.95-125, 2022-03-08 (Released:2022-04-28)