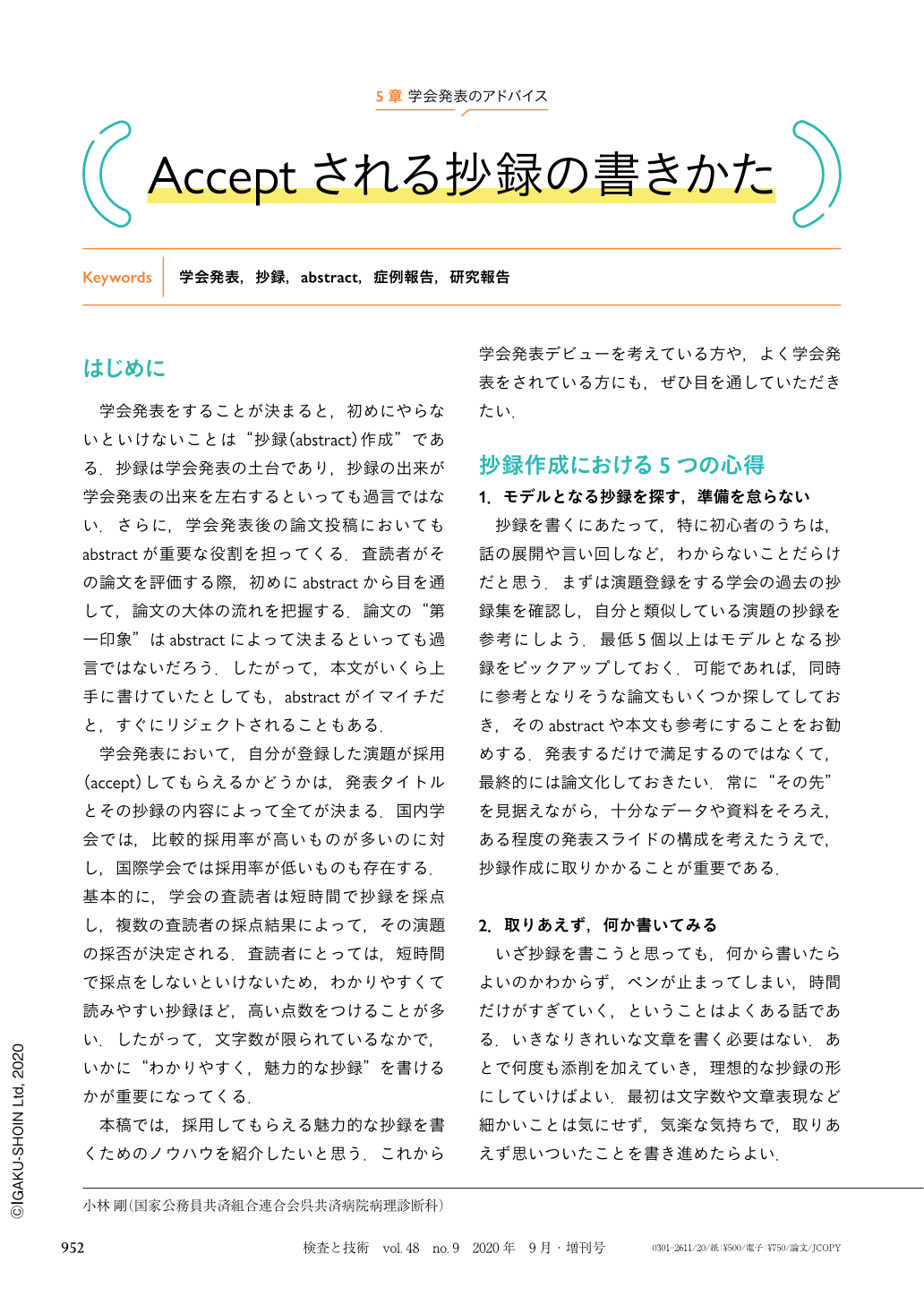1 0 0 0 IR 固体物理とバンド計算と計算機 (第44回物性若手夏の学校(1999年度))
- 著者
- 小林 一昭
- 出版者
- 物性研究刊行会
- 雑誌
- 物性研究 (ISSN:05252997)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.2, pp.393-412, 1999-11
この論文は国立情報学研究所の電子図書館事業により電子化されました。サブゼミ
1 0 0 0 OA 固体物理とバンド計算と計算機(第44回 物性若手夏の学校(1999年度),講義ノート)
- 著者
- 小林 一昭
- 出版者
- 物性研究刊行会
- 雑誌
- 物性研究 (ISSN:05252997)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.2, pp.393-412, 1999-11-20
この論文は国立情報学研究所の電子図書館事業により電子化されました。
1 0 0 0 IR 感化教育・教護教育史における留岡幸助と家庭学校の意義
- 著者
- 小林 仁美
- 出版者
- 教育史学会
- 雑誌
- 日本の教育史学 (ISSN:03868982)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, pp.53-69, 1990
1 0 0 0 54〕 拡大断層撮影法について
- 著者
- 菅原 努 中村 実 林 太郎 深津 久治 小野 伸雄 田口 武雄
- 出版者
- 公益社団法人 日本放射線技術学会
- 雑誌
- 日本放射線技術学会雑誌 (ISSN:03694305)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.1, 1958
1 0 0 0 OA バイオテレメトリーによるヒラメの沿岸来遊行動解析
- 著者
- 林 陽子
- 出版者
- 神奈川県水産総合研究所
- 巻号頁・発行日
- no.3, pp.31-37, 1998 (Released:2011-03-05)
1 0 0 0 書評
1 0 0 0 Acceptされる抄録の書きかた
はじめに 学会発表をすることが決まると,初めにやらないといけないことは“抄録(abstract)作成”である.抄録は学会発表の土台であり,抄録の出来が学会発表の出来を左右するといっても過言ではない.さらに,学会発表後の論文投稿においてもabstractが重要な役割を担ってくる.査読者がその論文を評価する際,初めにabstractから目を通して,論文の大体の流れを把握する.論文の“第一印象”はabstractによって決まるといっても過言ではないだろう.したがって,本文がいくら上手に書けていたとしても,abstractがイマイチだと,すぐにリジェクトされることもある. 学会発表において,自分が登録した演題が採用(accept)してもらえるかどうかは,発表タイトルとその抄録の内容によって全てが決まる.国内学会では,比較的採用率が高いものが多いのに対し,国際学会では採用率が低いものも存在する.基本的に,学会の査読者は短時間で抄録を採点し,複数の査読者の採点結果によって,その演題の採否が決定される.査読者にとっては,短時間で採点をしないといけないため,わかりやすくて読みやすい抄録ほど,高い点数をつけることが多い.したがって,文字数が限られているなかで,いかに“わかりやすく,魅力的な抄録”を書けるかが重要になってくる. 本稿では,採用してもらえる魅力的な抄録を書くためのノウハウを紹介したいと思う.これから学会発表デビューを考えている方や,よく学会発表をされている方にも,ぜひ目を通していただきたい.
1 0 0 0 OA 酸性雨によるコンクリート構造物の劣化機構に関する基礎的研究
- 著者
- 小林 一輔 宇野 祐一 森 弥広
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 土木学会論文集 (ISSN:02897806)
- 巻号頁・発行日
- vol.1997, no.564, pp.243-251, 1997-05-20 (Released:2010-08-24)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 2 3
酸性雨がコンクリート構造物に及ぼす影響を評価する場合には, コンクリートの特性を考慮した方法によって行う必要があることを指摘した. 次に, 著者らが考案した方法によって実験を行い, 酸性雨によるコンクリートの劣化機構についての知見を得た. 酸性雨の影響を受けたコンクリート構造物から採取したコアの分析を通じて上記の知見を立証した.
1 0 0 0 OA ストーリー展開と一貫性を同時に考慮した歌詞生成モデル
- 著者
- 渡邉 研斗 松林 優一郎 乾 健太郎 深山 覚 中野 倫靖 後藤 真孝
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第30回全国大会(2016)
- 巻号頁・発行日
- pp.2K31, 2016 (Released:2018-07-30)
1 0 0 0 立位重心と坐位重心の左右差比較と日常生活時の姿勢の関与(第1報)
- 著者
- 小林 伸二 雲居 秀城 宮下 修 赤尾 幸治 黒澤 つかさ 熊谷 修平 雨宮 雷太 西村 陽介
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, pp.C0323, 2007
【はじめに】<BR>人間は重力下で姿勢を維持し、安定した動作を遂行するために身体各分節を力学的、機能解剖学的に制御している。これらのバランスが崩れ、ある局所に歪みが生じた場合、病態が発生するといわれる。整形外科疾患理学療法の臨床においては、局所の評価や治療のみではなく、姿勢や動作にアウトカムを設定し、それらを調節することで症状が軽減する症例を経験できることがある。<BR>【目的】<BR>重力下で姿勢を安定させることは、身体各固有受容器からの探索情報を処理、統合した結果である。間違った情報入力の有無を確認し補正するために、臨床において立位や坐位姿勢を観察、評価する場面は多い。しかし、その情報を単なる逃避や関節可動域制限、筋力低下として単純に捉えてしまうことが往々にして行われている。今回われわれは、立位と坐位の重心位置が、既往歴や、日常生活時の特徴的な姿勢(以下日常姿勢)にどのような関係があるか、また左右差についてはどうか、を調査し、これらが姿勢制御に及ぼす影響について検討を行なった。<BR>【対象および方法】<BR>対象は、関節の変形や拘縮が認められず、重心に変化を及ぼすような疾患をもたない当院外来患者、入院患者および職員、31例(男性16例、女性15例)平均年齢47.4歳であった。重心位置の測定は、重心動揺計(MEDICAPTEURS社製 Win-pod)を用い、前方注視で30秒間の静止端坐位と静止立位にて行い、同時に後方からデジタルカメラで撮影を行った。これを、個人の既往歴、日常姿勢と比較検討した。<BR>【結果】<BR>既往歴については、症例ごとに関連がある傾向はあったが、局所の評価や三次元的な姿勢、動作分析を必要とし、全体として明らかな関連性を見ることはできなかった。坐位では、日常姿勢と坐位重心で明らかに同一方向にあったものが20名(64.5%)であり、左右での同一性が認められ、立位では8名(25.8%)であった。重心位置の左右差は左に優位であり、立位23名(74.2%)、坐位23名(74.2%)であった。また、坐位重心での左右の偏りが、体重換算し10%以上のものは15例であり、そのうち立位では重心位置が10%以内に入ったものは13例(86.7%)であった。<BR>【考察】<BR>理学療法によって日常の姿勢をより良い方向へ変化させ、疼痛の除去や予防が可能となる。これには日常生活における習慣が大きく関与しており、特に坐位では重心位置との関係に強い傾向が認められた。重心位置は坐位、立位ともに左側が優位であった。また、坐位で偏りが強いものも立位では補正されている傾向が強く、足、膝、股関節における姿勢制御の重要性が示唆された。今後、前後や回旋との関連性、身体各部位との影響、また疾患や症状別の違いなどもより詳しく調査、検討していきたい。<BR>
- 著者
- 小林 義寛
- 出版者
- 日本マス・コミュニケーション学会
- 雑誌
- マス・コミュニケーション研究 (ISSN:13411306)
- 巻号頁・発行日
- vol.87, pp.3-15, 2015-07-31 (Released:2017-10-06)
- 参考文献数
- 26
In our daily lives we are surrounded by many "things." Therefore, for us the phenomena of the media and communications have been presented and represented in our everyday lives by the media itself or by "things" related to the media. However, while there has been much media research concerning "things" or "materiality," most of it did not analyze or consider in a manner that focused on the relationship between humans and non-humans. It means, in other words, this research did not consider "things" and "materials" as conditioned in specific situations. Recently, however, some research has concentrated its interest on both human and non-humans in the same situation and has been taking a variety of approaches that share three common characteristics among them. It takes de-human centrism, de-language centrism or de-text centrism and thirdly it equally presumes humans and non-humans as agencies or actors relative to these situations. In all five papers we attempted to show some approaches on "things" or "materiality" of the media. I have discussed that people will become an audience or fans by themselves in some specific situations. Not only have audiences never lived as a social existence by themselves but neither have fans. Humans become an audience or fans in the conditions where he or she and "things" exist. In other words he or she will become an audience or a fan with a variety of "things" in the conditions where he or she exists.
1 0 0 0 待つ
- 著者
- 小林 仲治
- 出版者
- 渋沢栄一記念財団
- 雑誌
- 青淵 (ISSN:09123210)
- 巻号頁・発行日
- no.856, pp.7-9, 2020-07
1 0 0 0 哺乳類も送粉者―アジアにおける非飛翔性哺乳類媒植物―
- 著者
- 小林 峻
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.2, pp.385-389, 2020
1 0 0 0 表面励起子ポラリトン
- 著者
- 国府田 隆夫 平林 泉 十倉 好紀
- 出版者
- 公益社団法人 応用物理学会
- 雑誌
- 応用物理 (ISSN:03698009)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.11, pp.1069-1073, 1976
1 0 0 0 [Co/Pd]磁性細線における磁区の形成・駆動・検出
- 著者
- 奥田 光伸 宮本 泰敬 川那 真弓 宮下 英一 斎藤 信雄 林 直人 中川 茂樹
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会年次大会講演予稿集 (ISSN:13431846)
- 巻号頁・発行日
- vol.2015, pp.31A-1, 2015
1 0 0 0 IR 日本で自動車はどう乗られたのか (林華生教授追悼号)
- 著者
- 小林 英夫
- 出版者
- 早稲田大学アジア太平洋研究センター
- 雑誌
- アジア太平洋討究 (ISSN:1347149X)
- 巻号頁・発行日
- no.25, pp.29-48, 2015-12
1 0 0 0 日本における水稲うるち米品種の普及 -近年の良食味米の事例-
- 著者
- 林 秀司
- 出版者
- 東北地理学会
- 雑誌
- 季刊地理学 = Quarterly journal of geography (ISSN:09167889)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.2, pp.126-138, 1998-06-15
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 1 3
近年育成されたいくつかの水稲うるち米の良食味品種の普及を, GISソフトの Arc/Info を使って作成した作付比率の分布図を用いて, 地域的普及の視点から明らかにした。<br>多くの品種の普及地域は育成道府県に限定されているが, あきたこまち, キヌヒカリ, ヒノヒカリ, ひとめぼれは比較的広範囲に普及した。あきたこまち, ヒノヒカリ, ひとめぼれには育成県とその周辺で高い普及率を示す距離減衰的な普及パターンを示すと同時に, 飛地的な普及パターンが認められた。一方, キヌヒカリは明確な普及の中心がみられず, 分散的に普及した。このような水稲品種の普及には, 奨励品種の指定等の政策的要因が影響していることが考えられる。
- 著者
- 鹿内 健志 南 孝幸 官 森林 上野 正実
- 出版者
- 日本農作業学会
- 雑誌
- 農作業研究 (ISSN:03891763)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.1, pp.29-36, 2007-03-15
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 1 6
沖縄県におけるサトウキビ生産の担い手として設立が推進されたサトウキビ生産法人は,圃場分散と土地生産性の低さの問題を抱えている.サトウキビ生産法人の圃場は広域に分散しており,作業効率が低下し適期作業に大幅な遅れが生じている.また,単収は県の平均単収を下回っているのが現状である.本研究では集積された農地の分散を示す地理的な指標をGISにより解析し,これらの指標と単収との関係を調査し,圃場分散が生産性に及ぼす影響を検討した.分散を表す地理的な指標として周囲圃場面積,事務所からの距離,圃場面積の3つの指標を提案したが,周囲圃場面積と単収については正の相関があり,事務所からの距離と単収については,負の相関があることが示され,圃場分散がサトウキビ収量に影響を及ぼしている可能性があると示唆された.