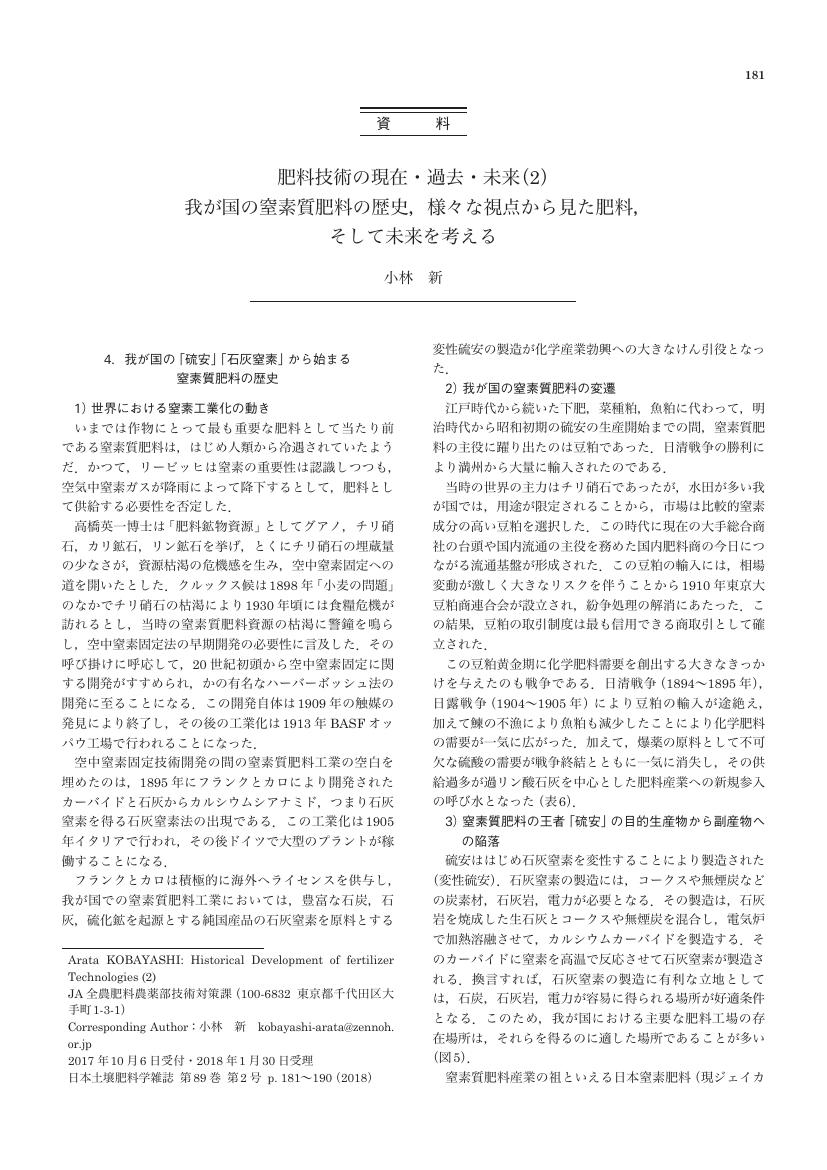1 0 0 0 OA 木製文化財の非破壊材質評価とデジタルアーカイブ作成
- 著者
- 杉山 淳司 今津 節生 小林 加代子 黄 盛煜 毛笠 貴博 金井 いづみ 田鶴 寿弥子 反町 始 鳥越 俊行 赤田 昌倫
- 出版者
- 京都大学
- 雑誌
- 基盤研究(A)
- 巻号頁・発行日
- 2013-04-01
画像情報に基づく樹種識別を、観察者の目を人工知能に置き換えることで、これまで不可能であった解剖学的な近類種の識別を可能にした。同時に、識別技術の他分野への学際的な展開を可能とした。即ち、人の設計する特徴抽出と判別器の組み合わせに加え、特徴抽出から知的判断までの全てを多層のニューラルネットに委ねる深層学習を木材識別に実装した。応用面では、文化財木製品の非破壊診断に利用できるCT画像による識別モデルを構築した。
1 0 0 0 OA 学校内のICT活用を推進するリーダーの現状と課題意識の調査
- 著者
- 小林 祐紀 中川 一史 村井 万寿夫 河岸 美穂 松能 誠仁 下田 昌嗣
- 出版者
- 日本教育メディア学会
- 雑誌
- 教育メディア研究 (ISSN:13409352)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.1, pp.49-57, 2007-10-31 (Released:2017-07-18)
学校教育におけるICT教育の推進に関わる現状の把握と推進のための課題を整理するために、ICT活用に関する研究助成に応募し、採択された学校のICT活用を推進するリーダー(以下ICT推進リーダー)を対象に、「研修」「働きかけ」「カリキュラム」についてアンケート調査を行った。その結果、ICT機器の整理、管理(保守点検)、校内ネットワークの整備・管理を中心とする働きかけをおこなっていることが明らかになった。その一方で、校内の他の教師の求める支援との間に齪飴が生じている現状が明らかになった。また、今後の校内におけるICT活用推進の課題として、教員のICT活用スキルの格差への対応、ICT推進リーダーがICT機器の維持・管理のために費やす時間や負担の軽滅、ICT活用が学校全体の教育活動に位置つくためのカリキュラムの充実、ICT活用推進を支える校内体制の確立の4点に整理することができた。
1 0 0 0 OA ミカン農業における農協共販体制の歴史的展開過程 : 戦前における静岡県と愛媛県の比較
- 著者
- 林 芙俊
- 出版者
- 北海道大学大学院農学研究院
- 雑誌
- 北海道大学農經論叢 (ISSN:03855961)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, pp.73-86, 2009-03-31
The cooperative shipping system receives regulations from the historical development process. This becomes important for understanding the form and the function of the cooperative shipping system. In this study, the distinctiveness of the cooperative shipping system of Satsuma Mandarin in Ehime is analyzed by a comparison with Shizuoka. Characteristics of Cooperative shipping systems in both prefectures that succeeded prewar days are the following three points. The first point, whether it is a single-purpose cooperative or a multi-purpose cooperative depends on the development at prewar days. The second point, the base of shipping system is farmer's small-scale co-fruit sorting group. The third point, technical guidance to those farmers has been enhanced since prewar days.
1 0 0 0 OA 当院における膿瘍形成性虫垂炎に対する治療の現況
- 著者
- 小林 慎二郎 瀬上 航平 三浦 和裕 四万村 司 櫻井 丈 小泉 哲 牧角 良二 月川 賢 宮島 伸宜 大坪 毅人
- 出版者
- 日本腹部救急医学会
- 雑誌
- 日本腹部救急医学会雑誌 (ISSN:13402242)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.4, pp.595-598, 2011-05-31 (Released:2011-07-12)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 5
膿瘍形成性虫垂炎に対する緊急手術では拡大手術移行の可能性や合併症発生率が高い。当院では2008年から膿瘍形成性虫垂炎に対して保存的治療で膿瘍を沈静化させ手術希望があれば約3ヵ月後に虫垂切除を行うinterval appendectomy(以下,IA)を行っている。膿瘍形成性虫垂炎32例について検討した。32例中29例(91%)が平均17.2日の入院期間で保存的治療に成功した。29例のうち,手術希望のあった16例に対してIAを施行した。16例のうち14例(87.5%)が腹腔鏡下虫垂切除術を完遂した。手術症例16例における平均手術時間は96分で,手術時平均入院期間は9.4日であった。また手術症例において合併症の発生は1例も認めなかった。総入院日数が長いことが課題であるが,拡大手術移行が少なく,合併症もない本治療方針は膿瘍形成性虫垂炎に対して有効であると考えられた。
1 0 0 0 OA カツオ由来ナイアシン高濃度含有パウダーのナイアシンとしての生物有効性
- 著者
- 福渡 努 江畑 恵 佐々木 隆造 保苅 義則 紅林 毅久 橋詰 昌幸 柴田 克己
- 出版者
- The Japan Society of Home Economics
- 雑誌
- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.4, pp.265-272, 2005-04-15 (Released:2010-03-10)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 1
(1) ヒトを用いて, カツオ由来ナイアシン高濃度含有パウダー(カツオパウダー)中のナイアシンの生物有効性について検討した.21~23歳の健康な女子経生8名を対象として, 食事摂取基準を満たす食事を2日間与えた後, ナイアシン51mgを含むカツオパウダー15gを摂取させた.カツオパウダーを摂取した日に, 摂取カツオパウダー中のナイアシンの52%がニコチンアミド代謝産物として尿中に排泄された.カツオパウダー中のナイアシンはニコチンアミド標品に近い, 高い生物有効性を持つことが示唆された.(2) カツオパウダーがストレプトゾトシン(STZ)誘発性糖尿病の予防・改善効果を有するか検討した.5週齢のWistar系雄ラットにカツオパウダー添加食を8日間与えた後, STZ20mg/kg body weightを腹腔内注射し, さらにカツオパウダー添加食を21日間与えた.カツオパウダー摂取によるSTZ誘発性の糖尿病の予防・改善は見られなかった.しかし, STZ誘発性糖尿病によるナイアシン栄養状態の悪化を防止した.
1 0 0 0 OA マンザミンアルカロイドの特異な環構造と生合成経路
- 著者
- 小林 淳一 津田 正史
- 出版者
- The Society of Synthetic Organic Chemistry, Japan
- 雑誌
- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.12, pp.1114-1123, 1997-12-01 (Released:2009-11-16)
- 参考文献数
- 37
- 被引用文献数
- 4 7
Manzamines, β-carboline alkaloids having unique heterocyclic systems from marine sponges, are of considerable current interest as compounds generated through unprecedented biosynthetic path or as a challenging target for total synthesis. Recently many manzamine-related alkaloids have been isolated from marine sponges, indicating the unique biogenetic path of manzamines.
1 0 0 0 OA 世界における終末期の意思決定に関する原理・法・文献の批判的研究とガイドライン作成
- 著者
- 盛永 審一郎 加藤 尚武 秋葉 悦子 浅見 昇吾 甲斐 克則 香川 知晶 忽那 敬三 久保田 顕二 蔵田 伸雄 小出 泰士 児玉 聡 小林 真紀 品川 哲彦 本田 まり 松田 純 飯田 亘之 水野 俊誠
- 出版者
- 富山大学
- 雑誌
- 基盤研究(B)
- 巻号頁・発行日
- 2011-11-18
終末期の意思決定に関する法制度・ガイドライン等を批判的に検討した結果、以下のことが明らかとなった。①医師ー患者関係に信頼性があり、透明性が担保されていれば、すべり坂の仮説はおこらないこと、②緩和ケアと安楽死は、相互に排他的なものではなくて、よき生の終結ケアの不可欠の要素であること、③それにもかかわらず、「すべり坂の仮説」を完全に払拭しえないのは、通常の医療である治療の差し控えや中止、緩和医療を施行するとき、患者の同意を医師が必ずしもとらないことにあること。したがって、通常の治療を含むすべての終末期ケアを透明にする仕組みの構築こそが『死の質の良さを』を保証する最上の道であると、我々は結論した。
1 0 0 0 OA 可変正則化パラメータを用いた phase-field 延性破壊モデル
- 著者
- 韓 霽珂 西 紳之介 高田 賢治 村松 眞由 大宮 正毅 小川 賢介 生出 佳 小林 卓哉 村田 真伸 森口 周二 寺田 賢二郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本計算工学会
- 雑誌
- 日本計算工学会論文集 (ISSN:13478826)
- 巻号頁・発行日
- vol.2020, pp.20200005, 2020-04-15 (Released:2020-04-15)
- 参考文献数
- 36
近年,亀裂・進展の解析手法の一つとして,phase-field破壊モデルが注目を集めている.phase-field脆性破壊モデルは既に多くの実績が報告されている一方で,延性材料を適切に表現するphase-field破壊モデルは発展途上である.phase-field破壊モデルにおいて,拡散き裂の幅を表す正則化パラメータは破壊開始の制御に用いられ,これが大きいほど破壊開始が早くなる.これは正則化パラメータが大きい場合には,その分だけき裂近似領域も大きくなるため,1に近いphase-fieldパラメータの分布も拡大し,それに応じて荷重--変位関係のピーク値が小さくなることが原因として考えられる.本研究では,正則化パラメータの性質を考慮し,通常は定数として扱われる正則化パラメータの代わりに,蓄積塑性ひずみの大きさに応じて変化する可変正則化パラメータを提案する.これにより,塑性域と正則化パラメータによって規定されるき裂周辺の損傷域が関連づけられ,塑性変形の影響を考慮した損傷の計算が可能となる.提案モデルの表現性能を調査するためにいくつかの解析を行った.可変正則化パラメータの導入により,塑性変形の進行とともにき裂周辺の損傷域が大きくなる傾向が捉えられ,弾性域から塑性域を経てき裂に発展するといった遷移過程に特徴づけられる延性破壊を表現できることを確認した.ベンチマーク問題の解析等の数値解析を通して,き裂の進展方向を適切に予測できること,および可変正則化パラメータを介して延性の制御が可能になることを例示した.また,金属供試体を用いた実験の再現解析では,実験結果と整合する結果が得られることも確認した.
- 著者
- 小林 新
- 出版者
- 一般社団法人 日本土壌肥料学会
- 雑誌
- 日本土壌肥料学雑誌 (ISSN:00290610)
- 巻号頁・発行日
- vol.89, no.2, pp.181-190, 2018-04-05 (Released:2018-06-08)
- 参考文献数
- 16
1 0 0 0 IR 山の上の藥師像--日本の礼拝対象と同一視されたバーイシャジヤグル
- 著者
- 小林 信彦 Nobuhiko KOBAYASHI 桃山学院大学文学部
- 出版者
- 桃山学院大学総合研究所
- 雑誌
- 桃山学院大学人間科学 (ISSN:09170227)
- 巻号頁・発行日
- no.20, pp.55-79, 2000-12
In Japan there are many mountains on which images of Yakusi 藥師 are found. Bhaisajyaguru, the Indian counterpart of Yakusi, however, has nothing to do with mountains, which are favourate places of Japanese kamis 神. Yakusi has been worshipped by the Japanese as one of kamis, as is suggested by a verse in the Bussokusekika 佛足石歌.
1 0 0 0 よくわかるファミリーソーシャルワーク
- 著者
- 喜多祐荘 小林理編著
- 出版者
- ミネルヴァ書房
- 巻号頁・発行日
- 2005
1 0 0 0 OA 字形を大切にする漢字指導-漢字書き取り調査を行って-
- 著者
- 林 輝夫
- 出版者
- 奈良教育大学国文学会
- 雑誌
- 奈良教育大学国文 : 研究と教育 (ISSN:03863824)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.65-78, 1978-08-06
1 0 0 0 OA Alloy : 自動解析可能なモデル規範形式仕様言語
- 著者
- 中島 震 鵜林 尚靖
- 出版者
- 日本ソフトウェア科学会
- 雑誌
- コンピュータ ソフトウェア (ISSN:02896540)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.3, pp.3_78-3_83, 2009-07-28 (Released:2009-10-05)
1 0 0 0 OA グローバル経営に国民文化が与える影響力の解析
- 著者
- 宮林 隆吉
- 出版者
- 日本マーケティング学会
- 雑誌
- マーケティングレビュー (ISSN:24350443)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.12-22, 2020-03-04 (Released:2020-03-04)
- 参考文献数
- 18
グローバル経営において国や文化の異なる従業員同士の融和は重要な課題であり,国境や文化を超えて組織アイデンティティを構築するためにも,人々を束ねる経営理念が重要な役割を果たすと考えられる。しかし,多くの日本企業の人材面・制度面での現地化は遅れており,安易に翻訳された理念やビジョンがそのまま輸出されて形骸化しているケースが見られる。本研究では,まず経営理念が組織アイデンティティの重要な基盤であり,戦略や組織のあり方に大きな影響を与える要素であることを先行研究より考察した。次に,異なる文化圏(アメリカ,中国,日本,ドイツ)の企業計121社の経営理念をコンテンツ分析・比較し,国民文化が経営理念に与える文化の影響度を検証した。その結果,権力格差(PDI)と不確実性の回避(UAI)が社内外のステークホルダーとの関係構築姿勢に影響を与えていることが認められた。今後,経営理念を核とした企業ブランディングや組織運営を行う上でも,グローバル企業にとって異文化文脈の理解は欠かせない。
1 0 0 0 死後変化に伴う microRNA (miRNA) の経時的挙動
- 著者
- 橋谷田 真樹 臼井 聖尊 大久保 愉一 林崎 義映 境 純 舟山 眞人 TAKAHASHI Shirushi
- 雑誌
- DNA多型 = DNA polymorphism
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.259-262, 2011-05-30
- 参考文献数
- 8
1 0 0 0 OA 電子コミュニティにおけるコミュニケーション構造の類型化
- 著者
- 平本 一雄 林 玲 望月 香菜子
- 出版者
- 日本社会情報学会
- 雑誌
- 日本社会情報学会全国大会研究発表論文集 日本社会情報学会 第20回全国大会
- 巻号頁・発行日
- pp.117-120, 2005 (Released:2006-02-23)
藤沢市民電子会議室の参加者数・発言数の多い会議室を対象としてコミュニケーション活動の構造を分析し、その類型化を試みた。発言回数と会話の長さから4つのタイプを摘出するとともに、これらのタイプがどのようなパターンの会話構造の組み合わせを有するのかを分析した。この分析の結果が今後の電子コミュニティの運営にとって有効な情報となることを確認できた。
1 0 0 0 宿主と寄生体の共進化における普遍則を実験と理論の両面から探求する
本研究の目的は、生命の起源で想定されるような単純な自己複製系においても避けがたく発生してしまう寄生性分子(ウイルスのようなもの)が宿主との生存競争を通じて複製系に及ぼす進化的影響を、実験と理論の両面から追求することであった。理論では、区画化された単純な宿主・寄生体複製系の数理モデルの構築と解析を行った。広いパラメータ空間上での網羅的な計算機シミュレーションの結果、原始地球でも実現可能であろう単純な区画ダイナミクスのみによって複製系が安定に持続可能な条件を見出した。また、複製系が安定に持続可能となるためには区画が多数あること、区画の融合分裂頻度が大きいこと、栄養量が適度な範囲にあることなどが重要な要件であることが明らかになった。これらの知見を用いれば、宿主と寄生体の相互作用の程度を段階的に変化させた新しい進化実験の条件設定を行うことができると考えられる。この成果は、平成29年度内に論文化した。実験では、自己複製能力を持つ宿主RNAと寄生体RNAの長期的な実験進化を実施し、その進化ダイナミクスを次世代シーケンサと生化学的なアッセイにより解析した。配列解析の結果、宿主RNAは多系統に分岐進化を起こしていたこと、寄生体の側では新たな分子種が進化途中で発生していたことが判明した。生化学アッセイにより宿主と寄生体の関係がいかに発展したかを解析した結果、宿主RNA側での寄生体RNAの複製を防ぐ適応進化と、寄生体RNA側での進化後宿主への新たな寄生能力の適応進化が繰り返し起こっており、寄生体が宿主の継続進化と多様化に貢献していることを示唆していた。これらの結果は、単純な複製子集団がダーウィン進化を通じて自発的に宿主・寄生体の関係がダイナミックに変動する複雑な生態系へと発展したことを示しており、生命の初期進化について重要な知見が得られたと言える。この成果は、平成31年度に出版予定である。
1 0 0 0 OA とろろ昆布を用いた,生体関連物質に関する実験(定番!化学実験(高校版)60:生命と物質)
- 著者
- 小林 邦佳
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 化学と教育 (ISSN:03862151)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.2, pp.96-97, 2009-02-20 (Released:2017-06-30)
- 参考文献数
- 5
1 0 0 0 第49回国連統計委員会出張報告
- 著者
- 小林 秀子 伊藤 慧
- 出版者
- メディアランド
- 雑誌
- 季刊国民経済計算 (ISSN:04534735)
- 巻号頁・発行日
- no.163, pp.77-86, 2018-08