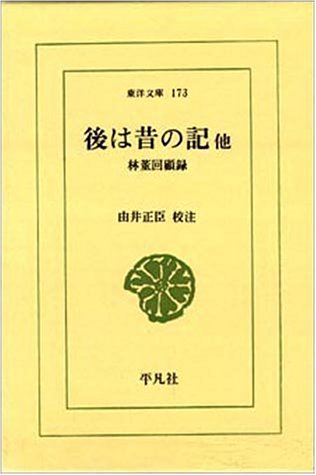- 著者
- 林 葉子
- 出版者
- ジェンダー史学会
- 雑誌
- ジェンダー史学 (ISSN:18804357)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.35-49, 2009
The purpose of this study is to analyze the relationship between Isoo Abe's pacifism and his recommendation that 'weak' men be sterilized. We are here concerned with the problem of manliness in Isoo Abe.<BR>Little attention has been given to Abe's argument in the 1920s about the necessity for sterilization of the weak. However, it is important to note that Abe was a pacifist and recommender of sterilization in 1920's. In his view, sterilization and 'peace' were inseparably related; American society as 'civilization' was the model for Abe's image of a 'peaceful' society.<BR>Abe was influenced by the American birth control movement of Margaret Sanger, and by the American eugenic movement of Paul Popenoe and Eugene Gosney. Abe insisted that the nation should exclude immigration and 'improve the race (jinsyu-kairyo),' in order to maintain homogeneity of the 'race.' That is to say, he attached importance to the 'race' problem in order to obtain 'world peace.' To solve the 'race' problem, he introduced 'birth control' to the Japanese people, and sterilization was one of the most important means for his theory of 'birth control.'<BR>Abe promoted the sterilization of weak men, because he attached importance to manliness. He believed that it was possible to create an 'ideal' society which was based, like an army, on strong people who have 'strong bodies' and 'masculine spirit.'<BR>This issue of Abe's image of manliness is surely not irrelevant to the issue of manliness in America which was examined in the studies about American history. For example, Gail Bederman has argued that there is a strong connection between ideas of 'civilization' and 'race' and the construction of manliness in America, and therefore it is not at all strange that one of the Japanese intellectuals who had been influenced by American culture also drew a connection between the notion of manliness and 'civilization' and 'race.' Further we can identify intellectual influences of this stream of thought on the international eugenic movement that includes the problem of eugenics of Nazism.
- 著者
- 崔 舜翔 亀井 勉 小林 洋子
- 出版者
- 国際生命情報科学会
- 雑誌
- 国際生命情報科学会誌 (ISSN:13419226)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.82-83, 2013
【目的】薬物を一切使わずに、気功入静法、刺絡療法と催眠療法の三者の同時導入により、摂食障害の諸症状の著しい改善が見られた一症例を報告する。【材料と方法】35歳、女性、幼児ごろより周りからのいじめ、未成年時の家出により、14歳から現在まで21年間摂食障害を患う。主な症状として、食事に対する恐怖心と罪悪感、人との外食や出勤時の食事ができず、仕事から帰宅すると暴食し、その自覚もなく、過食と嘔吐を繰り返す。また、20年以上の不眠症、左腹部の鈍痛感、呼吸困難に陥いたりする。鍼灸、整体、マッサージ、催眠療法、瞑想等各種治療法を試みたが、改善は得られなかった。2012年11月から、当院で気功入静法、刺絡療法と催眠療法と3つの組合せ治療を受ける。気功入静法は、徐々に時間を初回の15分から最長150分まで延ばし、呼吸法を行わずに、「人天合一、物我両忘」の虚無境界に入る方法を指導した。気功入静法のみを通じて摂食障害の要因ときっかけを探ることにした。刺絡療法は3回目以降から12正経の井穴に、自宅で週2~3回程度に行うように指導した。催眠療法は、3回目から1回約20分行い、気功入静法を実践するにつれて健康意識が自然に高まるという一般的な暗示を入れた。【結果】治療開始から今までの2ヶ月間計9回の治療(1回治療3時間)を経って、現在嘔吐はまだ多少あるものの、食事量が過食時の三分の一まで減り、上記の諸症状すべてが消え、著しい改善が認められた。【考察及び結論】中医理論では、喜・怒・思・憂・悲・恐・驚などの感情が行き過ぎると、陰陽のバランスの崩れ、気血の運行の乱れと臓腑の機能失調をもたらし、疾病を起こすとされる。本人が5回の指導と治療によって気功入静法をマスターできたために、気功入静による心理的障害の除去と健康増進の効果が現れたと考えられる。また、全身12経絡への刺絡療法によって自律神経と体性神経の異常亢進を抑制でき、そして、催眠療法によって健康意識が高まった。この三つの療法の相乗効果によって行き過ぎた感情が調整されたことが陰陽と気血及び臓腑の機能の改善につながり、結果的に摂食障害の諸症状の顕著な改善につながったと考えられる。
1 0 0 0 IR 与論方言の可能表現形式 : 動作主体の人称による形式の使い分けを中心に
- 著者
- 林 優花
- 出版者
- 鹿児島国際大学大学院
- 雑誌
- 鹿児島国際大学大学院学術論集 (ISSN:18838987)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.41-53, 2014-11
The dialect of Yoronisland in Kagoshima prefecturehas complicated expressions for the potential form. It is a rare feature and can't be found in other dialects. Forms of expression in Yoron can change depending on the grammatical personof performingsubject. However, there have been fewstudies on the dialect,of Yoron, the detailed expressionfor the potential form hasn't been understood sufficiently. Therefore, in this paper I report the result of investigationon dialect in Yoron island and its analysis. Furthermore, I explore the system of the potential form in order to understand the division of dialectal use. As the result of the analysis, I propose that Yoron people might regard the grammatical person of performing subject as important when the form of use for dialect is decided. In the case of first person, Yoron people use the"Nayun" series in the affirmative form for the potential form of the kind of passionand ability. And they use the "Ryun" series in the potential form for inner and outer conditions. In the negative form, they all use the "Raji" series regardless of the kind of potential form. On the other hand, except for the first person as subject, in the affirmative form they all use the "Nayun" series, in the negative form they use the "Naraji" series regardless of the kind ofpotentiality.
1 0 0 0 OA 踏切衝突事故時の各因子が列車乗員の被害度に及ぼす影響評価
- 著者
- 沖野 友洋 永田 恵輔 佐藤 裕之 堀川 敬太郎 小林 秀敏
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学会論文集 (ISSN:21879761)
- 巻号頁・発行日
- vol.85, no.869, pp.18-00270, 2019 (Released:2019-01-25)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 2 4
The crash safety structure of the railway vehicles is effective as one of the safety measures against the train crews and the passengers in the event of a collision accident. However there is no standard for crash safety in Japan. In order to discuss guidelines for the crash safety design of the vehicle structure, it is important to grasp the actual situation of collision accidents in Japan. Therefore, firstly the authors performed the statistical analysis of serious level-crossing accidents for the past 30 years. Secondly, we carried out finite element analyses of a level crossing accident with a dump-truck under various conditions (collision position, collision angle, collision speed and mass of the load on the dump-truck) based on the result of the statistical analysis. We also evaluated their results in terms of the contact force, the deformation energy of the rail vehicle, the deformation amount of the cabin, the mean deceleration of passenger’s area (conformable to European standard), the maximum deceleration of the passenger’s area and the secondary impact velocity of the passenger (American standard). The degree of correlation among these results was discussed. The analyses showed that the horizontal collision position of the dump-truck and the collision speed had a comparatively large effect on the safety of passengers, and further that the mass of the load on the dump-truck also affected it when the secondary impact velocity was used as an evaluation index.
1 0 0 0 後は昔の記他 : 林董回顧録
- 著者
- 林 義人
- 出版者
- 朝日新聞社
- 雑誌
- メディカル朝日 (ISSN:09197818)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.2, pp.66-68, 2015-02
- 著者
- Ballmer Steven A. 小林 収
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネス (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.1063, pp.84-88, 2000-10-23
問 マイクロソフトと言えばビル・ゲイツの会社、というイメージが強い。バルマーさんが最高経営責任者(CEO)に就任して半年、ゲイツCEO時代とは何が変わったのでしょう。 答 ビル・ゲイツと私はマイクロソフトの経営を通じてともに成長してきました。ですから、変わった部分よりも変わっていない部分の方が多いでしょう。もっとも、私はビルほど頭が良くない。
- 著者
- 萩原 葉子 栗林 大輔 澤野 久弥
- 出版者
- 水文・水資源学会
- 雑誌
- 水文・水資源学会研究発表会要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.28, 2015
2011年のタイ国チャオプラヤ川の洪水は死者815名、経済被害約400億ドルという大きな被害をもたらした。日本はこれまでタイへの最大の投資国であり、特に浸水被害が大きかった中~下流域の7つの工業団地では被災企業804社のうち日系企業が半数以上の451社を占めた。本稿の目的は、2011年の洪水後、在タイ日系企業の工場がどのように洪水対策を強化したかを調査し、今後の企業防災や地域防災のための課題を明らかにすることである。2015年2月~3月に、バンコク日本人商工会議所会員企業1,605社のうち、製造業の会員企業735社を対象に実施したアンケート調査の結果を2011年の洪水前後の洪水対策の実施率に焦点をあてて、浸水のあった工場と浸水のなかった工場それぞれについて分析した。<br> アンケートについて、コンピュータ・電子製品・光学製品、電気機器、金属製品、その他輸送用機械器具等の業種に属する28工場から回答を得た。そのうち12工場が2011年の洪水で浸水し、平均床上浸水深は約1.7mであった。浸水した工場は中~下流のアユタヤ県あるいはパトムタニ県に位置していた。浸水しなかった残りの16工場は下流のバンコク都、サムトプラカン県、バンコク南西のサムサコン県、東部のプラチンブリ県、南東部のチャチェンサオ県、チョンブリ県、ラヨン県に位置していた。<br> 分析の結果、企業防災・地域防災を強化していくうえでの今後の課題が明らかになった。2011年に浸水したアユタヤ県、パトムタニ県に位置する12工場は従業員の安全確保や浸水を防ぐ構造物の築造、洪水関連情報の入手、操業の早期復旧、防災計画や防災を管轄する部署の設置等の対策を強化した事がわかった。しかし、自社の生産拠点の多角化、事務所・工場等の生産拠点の確保、取引先との災害時の協力体制の構築、といった事業継続に必要な社内外との協力を伴う対策については、実施率が低いことがわかった。一方、2011年に浸水しなかった工場も非常時の連絡網の整備や指揮命令系統明確化については洪水後に6割以上の工場が実施し、敷地の盛土・防水壁の築造等や基幹業務システムのバックアップ対策の実施率も上がったが、他の対策の実施率は未だ低く、ほとんどの対策について5割以下であることがわかった。今後さらに業種、事業規模、取引先との関係等によって洪水対策実施率に違いがあるかを分析する。
1 0 0 0 OA ビタミンD3のフッ素による化学修飾
- 著者
- 小林 義郎 田口 武夫
- 出版者
- The Society of Synthetic Organic Chemistry, Japan
- 雑誌
- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.11, pp.1073-1082, 1985-11-01 (Released:2009-11-13)
- 参考文献数
- 70
- 被引用文献数
- 12 13
Studies on fluorine-modified vitamin D3 analogs : the design, synthesis and biological activity are reviewed. On the basis of the metabolism of vitamin D3 and the characteristic features of fluorine and fluorinated compounds, fluorine-modified vitamin D3 analogs were designed, synthesized and their biological activity was investigated to clarify the physiological significance of the metabolic hydroxylation of vitamin D3.
1 0 0 0 OA 旧外地の学校に関する研究―1945年を境とする連続・非連続―
戦前の日本国は、台湾・朝鮮・樺太・関東州・満洲国・南洋群島・南方占領地に、地域によって初等教育機関のみの所もあるが、台湾と朝鮮には帝国大学も設置した。今回、それらの学校所在を明らかにした。また、校舎施設や一部教科の指導内容が戦後に引き継がれたことを台湾に於いて確認した。当地からの日本人引き揚げ後も、戦後復興のために残った日本人の大学教員や技術者がいた。その子弟たちが通った日僑学校や日籍学校と呼ばれた日本人学校が台湾・北朝鮮・満洲の主要都市にあり、教育内容等について明らかにした。
1 0 0 0 OA 高度な歪み構造を有したフタロシアニンの合成と性質
- 著者
- 本間 茂継 福田 貴光 小林 長夫
- 出版者
- 基礎有機化学会(基礎有機化学連合討論会)
- 雑誌
- 基礎有機化学討論会要旨集(基礎有機化学連合討論会予稿集) 第17回基礎有機化学連合討論会
- 巻号頁・発行日
- pp.105, 2004 (Released:2005-03-31)
フタロシアニン(Pc)は高い平面性を有した巨大π共役系分子で、650_から_700nmにかけてQ帯と呼ばれる大きな吸収を持ち、主に感光体・光記録媒体などの機能性色素材料として利用されている。近年我々はPcの周辺にフェニル基のような嵩高い置換基を導入することによって骨格に大きな歪みを有したPcを合成したが、その構造および物性に関する知見は十分ではなかった。そこで本研究ではPcの性質的変化を見積もるために、Pcのα位に段階的にフェニル基を導入した6種類のZnPcシリーズを合成し、結晶構造解析からシリーズの歪み具合を定量化し、最終的に吸収スペクトル等の測定から電子状態の変化について検討を行った。
1 0 0 0 OA 説話文学の新研究 : 国語教材
- 著者
- 杉田 収 中川 泉 飯吉 令枝 斎藤 智子 小林 恵子 佐々木 美佐子 室岡 耕次 坂本 ちか子 杉田 靖子 曽田 耕一 濁川 明男
- 出版者
- 新潟県立看護大学
- 雑誌
- 看護研究交流センター年報
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.6-13, 2006-07
化学物質過敏症(CS)発症者の発症原因になった化学物質と,発症者が反応する空気中化学物質との関連性を,空気中の化学物質56項目を分析することで検証した.その結果,発症原因化学物質と思われる一般名テブコナゾール,化学名a-[2-(4-クロロフェニル)エチルトa-(1,1-ジメチルエチルト1H-1,2,4-トリアゾールートエタノールにはヒドロキシル基(-OH)と塩素(C1)が存在した.一方発症者が「入れる建物」と「入れない建物」のそれぞれの空気中化学物質の分析比較から,発症者が反応する空気中の化学物質は,ヒドロキシル基を有するブタノールと塩素を有するトリクロロエチレンであることが推定された.上越市立小学校全児童12,045名のCSに関連する症状について,無記名アンケートによる実態調査を行った.回収数は10,348名分(回収率85.9%)であった.CS診断基準では主症状5項目,副症状9項目,さらに眼球運動や化学物質の微量負荷試験などの検査が取り入れられているが,ここでは一般市民向けアンケート用であることから「検査」を省略し,診断基準に準じた症状の13項目について,それぞれ「大いにある」「ある」「少しある」「全くない」の選択肢で調査した.各項目について「大いにある」「ある」を「症状あり」とした場合は,主症状2項目・副症状4項目以上,及び主症状1項目・副症状6項目以上の児童は21名(0.2%)であった.一方「少しある」を加えて「症状あり」とした場合は618名(6.0%)であった.
1 0 0 0 全身性強皮症に併存し小腸が脱出腸管壁内に陥入した直腸脱の1例
- 著者
- 朝蔭 直樹 原口 美明 鈴木 貴久 塚田 健次 山本 哲朗 小林 滋
- 出版者
- 日本臨床外科学会
- 雑誌
- 日本臨床外科学会雑誌 (ISSN:13452843)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.8, pp.2416-2420, 2009
症例は69歳,女性.24年前より全身性強皮症と診断されている.1年ほど前から直腸脱が出現し早急に増悪,立っているだけで超手拳大の腸管が脱出し当科を受診した.身長149cm,体重34kgと小柄痩せ型で顔面,手指に茶褐色の光沢を持った皮膚硬化を認めた.怒責診では約10cmの直腸が脱出し,脱出腸管は浮腫状であたかもソフトボール状に緊満していた.怒責時腹部CT検査を施行すると,脱出腸管壁内にガス像が認められ脱出腸管反転部内への小腸陥入を伴う直腸脱と診断した.手術は会陰式直腸S状結腸切除術(Altemeier手術)に肛門挙筋形成術を併施した.術後経過は順調で,現在術後1年半経過したが脱出はなく特に排便機能にも問題はない.全身性強皮症は結合組織の線維性硬化性病変を伴い,直腸脱の発症要因の一つと考えられた.本症例のような基礎疾患を有する場合,侵襲が少なく肛門挙筋形成も行えるAltemeier手術は有効であると思われた.
1 0 0 0 OA Brugada症候群と不整脈源性右室心筋症(ARVD)における心電図QRS波の周波数特性
- 著者
- 淀川 顕司 森田 典成 小林 義典 小原 俊彦 村田 広茂 高山 英男 清野 精彦 加藤 貴雄 水野 杏一
- 出版者
- 公益財団法人 日本心臓財団
- 雑誌
- 心臓 (ISSN:05864488)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.SUPPL.1, pp.S1_19, 2012 (Released:2013-08-23)
[背景・目的] Brugada症候群と不整脈源性右室心筋症(ARVD)はともに加算平均心電図における心室遅延電位(LP)が高率に検出されるが,そのLPの形態に着目すると,ARVDでは高周波成分で形成されるのに対し,Brugada症候群では比較的低周波成分で形成されることが多い.そこで,われわれは,QRS波の周波数解析を行うことにより両者の周波数特性を検討した.[対象と方法] 特発性右室流出路起源心室頻拍(RVOT-VT)20例,Brugada症候群10例,ARVD 10例.全例で心電図Z誘導QRS波をガボール関数を用いてウェーブレット変換し,各周波数帯でのピークのパワー値,および総パワー値を比較.[結果] Brugada症候群では80Hzを中心に,ARVDでは150Hzを中心にQRS内部に高周波成分が発達していた.高周波帯の中で最大パワーを有する周波数はBrugada症候群に比し,ARVDで有意に高かった(81.7± 19.9Hz vs 145.4± 27.9 Hz,p[結論] 心電図QRS波の周波数解析において,周波数特性は,Brugada症候群とARVDで明らかに異なる.
1 0 0 0 OA 医療関係職種および事務職員等による処方オーダリングシステムの代行入力の現状
- 著者
- 瀬戸 僚馬 若林 進 石神 久美子 瀬戸 加奈子 池田 俊也 武藤 正樹 開原 成允
- 出版者
- 一般社団法人 日本医療情報学会
- 雑誌
- 医療情報学 (ISSN:02898055)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.1, pp.31-36, 2009 (Released:2015-03-06)
- 参考文献数
- 6
医師と医療関係職種等との役割分担を推進するための処方オーダリングシステムの代行入力について現状を概観するため,質問紙調査を行った.調査票は,2009年4月1日時点でDPCが適用されている1,052病院の薬剤部長あてに送付した.回答が得られた457病院のうち,処方オーダを導入率している404病院を分析対象とした. 医師が入力する処方オーダに関して,代行入力は一切行っていないと回答したのは260病院(64.6%)であり,何らかの方法で代行入力を行っている病院が144病院(35.4%)にのぼった.代行入力者は,薬剤師・看護師のような医療関係職種の場合も,事務職員の場合もみられた.代行入力には,口頭や書面による医師の指示をそのまま入力するものと,医療関係職種の臨床判断を必要とする事例がみられた. これらの代行入力内容は事務職員と医療関係職種とで混在しており,役割分担通知の趣旨を踏まえて再整理する必要性が示唆された.
1 0 0 0 OA 6.広島県府中市上下町における「まちづくり」事業の取り組み
1 0 0 0 OA 胡文忠公遺集86卷首1卷
1 0 0 0 OA 莊子鬳齋口義 10卷
1 0 0 0 OA 大腸穿孔の予後因子とエンドトキシン吸着療法の適用についての検討
- 著者
- 鹿股 宏之 小林 健二 加瀬 建一 篠崎 浩治
- 出版者
- 日本腹部救急医学会
- 雑誌
- 日本腹部救急医学会雑誌 (ISSN:13402242)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.7, pp.957-963, 2009-11-30 (Released:2010-01-13)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 1
【目的】大腸穿孔の予後因子を検討し,エンドトキシン吸着療法(以下,PMX─DHP)の適用について考察した。【対象と方法】対象は2003年4月から2008年3月までの5年間に,当院で経験した大腸穿孔54例である。術前因子9項目,術後因子6項目を選択し,予後についてそれぞれ統計学的検討を行った。【結果】多変量解析で,(1)術前ショック指数1.1以上の症例,(2)手術直後の収縮期血圧80mmHg以下の症例,(3)術後ノルアドレナリンを使用せざるを得なかった症例,(4)術後第1病日の血小板数低下率40%以上の症例,の4項目が独立した予後不良因子として観察された。さらに,死亡例は全例この4項目中2項目以上満たしていた。【考察】われわれはPMX-DHPを大腸穿孔の中でも最重症例に行うものと考えており,検討した予後不良因子~の中で2項目以上満たす症例は,最重症例としてPMX-DHP開始の一つの基準になり得るものと考える。