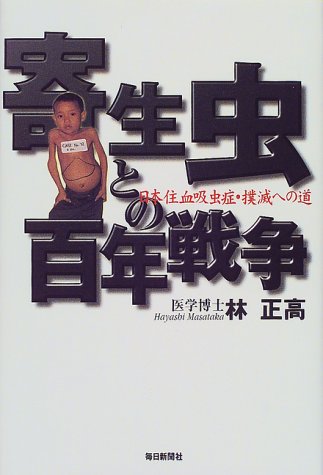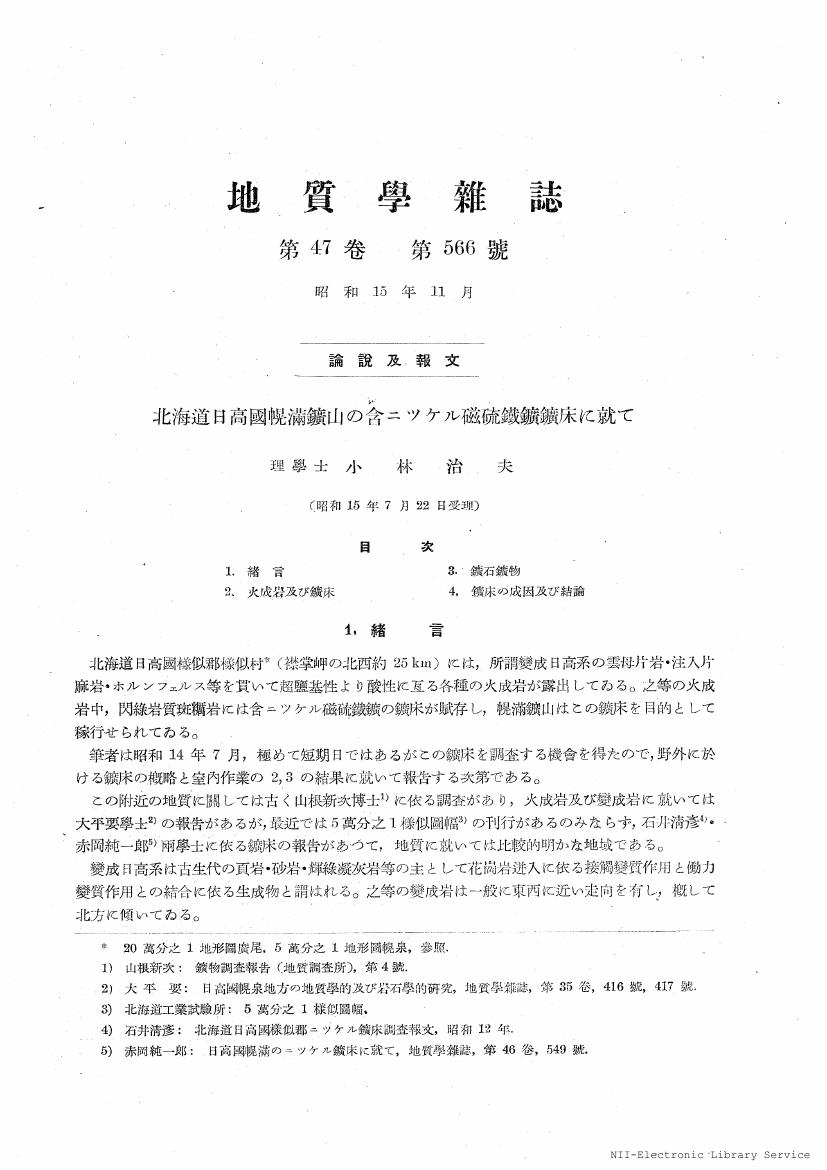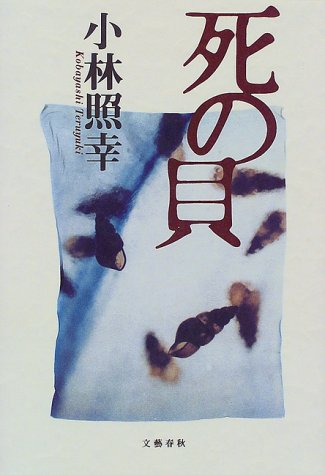- 著者
- 小林 文明 松井 正宏 吉田 昭仁 岡田 玲
- 出版者
- 一般社団法人 日本風工学会
- 雑誌
- 風工学シンポジウム論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.24, pp.115-120, 2016
2015年2月13日15時すぎに神奈川県厚木市内で発生した突風被害は,極めて局所的に被害が集中し,推定風速は20 m/sと推定され,F0(JEF0)スケールに相当した。今回の渦は,メソスケールのシアーライン上で形成された積乱雲前面におけるガストフロントで発生し,上空の積雲(アーク)と連なり,親渦が存在するという構造を有していた。ガストフロントに伴い複数発生した渦の一つであり,渦の接線風速もそれほど大きくなく,明瞭な漏斗雲は形成されず,地上の飛散物によって渦は可視化された。ガストフロントにおける上昇流が寄与した"2次的な竜巻"すなわちガストネード(gustnado)と考えられた。
- 著者
- 中臺 文 黒木 俊郎 加藤 行男 鈴木 理恵子 山井 志朗 柳沼 千春 塩谷 亮 山内 昭 林谷 秀樹
- 出版者
- 社団法人日本獣医学会
- 雑誌
- The journal of veterinary medical science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.1, pp.97-101, 2005-01-25
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 2 54
2000年11月から2002年7月の間に,ペットショップの爬虫類112頭におけるサルモネラの保有状況を調査したところ,74.1%(83/112)と高率に本菌が分離された.分離された112株は5生物群に型別され,I群の割合(62.5%)が最も高かった.また,112株中54株は28血清型に型別可能であった.これらの成績から,ペットの爬虫類は人のサルモネラ症の感染源となる可能性が示唆された.
1 0 0 0 IR エンブレムと鏡 : セーヴ、ロンサール、ベローにおける鏡のモチーフ
- 著者
- 林 千宏 Hayashi Chihiro ハヤシ チヒロ
- 出版者
- 大阪大学大学院言語文化研究科
- 雑誌
- 言語文化共同研究プロジェクト
- 巻号頁・発行日
- vol.2017, pp.9-20, 2018-05-30
表象と文化 (15)
1 0 0 0 OA ミシェル・フーコーのカント受容 : 批判の一つの系譜
- 著者
- 大林 信治
- 出版者
- 名古屋学院大学総合研究所
- 雑誌
- 名古屋学院大学論集 社会科学篇 = THE NAGOYA GAKUIN DAIGAKU RONSHU; Journal of Nagoya Gakuin University; SOCIAL SCIENCES (ISSN:03850048)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.2, pp.1-49, 2018-10-31
フーコーは若いときからニーチェを読み,戦後のフランスで支配的であった現象学や実存主義の意味付与的な主体の哲学の行き詰まりを打開するために,近代的主体の成立の出発点に遡り,ニーチェやハイデガーの目で「カントの人間学」を解読した。そこから「知の考古学」が展開されたが,1968年の「五月革命」を機に権力と直面したことから,改めてニーチェの系譜学を読み,「知と権力」の系譜学を展開した。さらに1978年フランス哲学協会で「批判とは何か」という講演を行ったとき,カントの「啓蒙とは何か」を取り上げ,ヨーロッパにおける「批判的態度」の成立を「統治」と「司牧的権力」の系譜の中に位置づけた。カントにおける「啓蒙」と「批判」の「ずれ」の問題は,フランクフルト学派によって「啓蒙批判」とか「理性批判」という形で展開されたが,フーコーはその問題を独自の仕方で「現在の存在論」ないし「われわれ自身の歴史的存在論」という形で「西欧近代の系譜学」を展開する。
1 0 0 0 OA ロボット間協調を容易に実現する並列論理型プログラミング言語の設計
- 著者
- 西山 裕之 大林 真人 大和田 勇人 溝口 文雄
- 出版者
- The Robotics Society of Japan
- 雑誌
- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.5, pp.620-631, 2001-07-15 (Released:2010-08-25)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1 2
This paper describes a concurrent logic programming language MRL for use in developing programs to cooper-atively control multiple robots. MRL describes actions of each robot and sensor as sets of logical formula. MRL enable us to easily implement complex tasks such as concurrency control, cooperation and negotiation between pro-cesses, and emergent event handling for multiple robots. We conducted an experiment on program development for paper delivery task by cooperation with mobile robots, manipulators and cameras to demonstrate the advantages of MRL programming framework. The results indicated that the MRL programs were more abstract and natural than conventional procedure-oriented programs, resulting in realization of flexible cooperation. Since MRL programs are compiled into C programs with little overhead, NIRL is useful as a multiple robot programming language efficient in both program execution and development.
- 著者
- 林 創 今中 菜七子
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 日本教育心理学会総会発表論文集 (ISSN:21895538)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, 2010
1 0 0 0 寄生虫との百年戦争 : 日本住血吸虫症・撲滅への道
1 0 0 0 ラウンド前に準備しておこう : 地域連携相互チェック (特集 自施設も他施設もどんとこい! ラウンドの精度と効果を高めるスキル総集編) -- (くまなく見よう! ここで差が出るスキルアップ)
- 著者
- 林 真樹
- 出版者
- メディカ出版
- 雑誌
- Infection control : The Japanese journal of infection control (ISSN:09191011)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.26-30, 2014-01
1 0 0 0 OA 結核病床をもたない一般病院環境における職員の結核菌曝露リスク
- 著者
- 阿部 達也 橋本 貴尚 小林 隆夫 人見 秀昭 海老名 雅仁 藤盛 寿一 阿見 由梨 早川 幸子 藤村 茂
- 出版者
- 一般社団法人 日本結核病学会
- 雑誌
- 結核 (ISSN:00229776)
- 巻号頁・発行日
- vol.90, no.9, pp.625-630, 2015 (Released:2016-09-16)
- 参考文献数
- 19
〔目的〕病院職員に対する結核曝露のリスクを,インターフェロンγ遊離試験(IGRA)の陽性率を指標として後ろ向きに比較した。その際,「病院環境曝露」を結核曝露のリスクとして仮定した。〔対象〕2010年12月から2012年4月の間にIGRAを行った職員870人を,病院環境曝露の有無により以下の群に分けて解析した。非曝露群は雇用時に測定を行った新入職者161人,曝露群は接触者健診受診者を含む既職者709人であった。〔方法〕IGRAはクォンティフェロンTBゴールド®3Gを用い,非曝露群を対照として,曝露群における陽性オッズ比(OR)をロジスティック回帰分析で求めた。〔結果〕全体として陽性率は6.7%で,2群間の陽性率(1.9% vs 7.8%)には有意差を認めた(P=0.005)。さらに,非曝露群を対照とし,性別,勤続年数,喫煙歴,および飲酒歴で調整した曝露群の陽性OR(95%信頼区間)は4.1(1.4-17.6)(P=0.007)であった。〔結論〕病院の職場環境ヘの曝露はその年数にかかわらず結核感染の潜在的なリスクとなっている可能性が示唆された。
1 0 0 0 災害対応業務標準化に向けた「防災基本計画」の業務分析
- 著者
- 岩佐 佑一 林 春男 近藤 民代
- 出版者
- 地域安全学会事務局
- 雑誌
- 地域安全学会論文集 = Journal of social safety science (ISSN:13452088)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.193-202, 2003-11-01
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 4
If the Tokai, Tonankai, and Nankai earthquakes occur simultaneously in the first half of the 21^<st> century, the damage would spread over many prefectures. It is indispensable for the prefecture governments in the impacted area, as well as the national government, to establish a standardized emergency response operation system, in order to mobilize the limited resources effectively. "The Basic plan for Disaster Prevention" compiled by the national government serves as the emergency disaster plan for the national government level, as well as the basic requirements to be complied by the emergency response plan compiled by prefecture governments and municipality governments. By employing Flow-chart system as the tool for describing the plan, this paper examined the emergency management section of Basic Plan for Disaster Prevention to identify operational models to be used as the basis for a standardized emergency management system.
- 著者
- 相田 潤 田浦 勝彦 荒川 浩久 小林 清吾 飯島 洋一 磯崎 篤則 井下 英二 八木 稔 眞木 吉信
- 出版者
- 一般社団法人 口腔衛生学会
- 雑誌
- 口腔衛生学会雑誌 (ISSN:00232831)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.4, pp.362-369, 2015-07-30 (Released:2018-04-13)
- 参考文献数
- 13
歯科医師法では公衆衛生の向上および増進が明記されており,予防歯科学・口腔衛生学は歯科分野で公衆衛生教育の中心を担う.またう蝕は減少しているが,現在でも有病率や健康格差が大きく公衆衛生的対応が求められ,近年の政策や条例にフッ化物応用が明記されつつある.根面う蝕対策としてフッ化物塗布が保険収載されるなど利用が広がる一方で非科学的な反対論も存在するため,適切な知識を有する歯科医師の養成が求められる.そこで各大学の予防歯科学・口腔衛生学,フッ化物に関する教育の実態を把握するために,日本口腔衛生学会フッ化物応用委員会は,1998年に引き続き2011年9月に全国の29歯科大学・歯学部を対象に質問票調査を行った.結果,予防歯科学・口腔衛生学の教育時間の大学間の最大差は,講義で8,340分,基礎実習で2,580分,臨床実習で5,400分となっていた.フッ化物に関する教育の時間も大学間によって講義で最大540分,基礎実習で280分,臨床実習は510分の差異があり臨床実習は実施していない大学も存在した.さらに1998年調査と比較して,教育時間や実習実施大学が減少しており,特に予防歯科学・口腔衛生学の臨床実習は1,319分も減少していた.また非科学的なフッ化物への反対論への対応など実践的な教育を行っている大学は少なかった.予防歯科学・口腔衛生学およびフッ化物応用に関する講義や実習の減少が認められたことから,これらの時間および内容の拡充が望まれる.
1 0 0 0 OA 指尖容積脈波解析を用いた情動ストレス刺激時における自律神経機能評価
- 著者
- 吉田 直浩 浅川 徹也 林 拓世 水野 (松本) 由子
- 出版者
- 公益社団法人 日本生体医工学会
- 雑誌
- 生体医工学 (ISSN:1347443X)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.1, pp.91-99, 2011-02-10 (Released:2011-12-13)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 4
The aim of this research was to evaluate the autonomic nervous reaction using photoploethysmography under the emotional stimuli. Twenty healthy adults (11 males and 9 females) with a mean age of 25.0±5.0 were assessed for their psychosomatic states using Cornell Medical Index (CMI) and classified into two groups: group I (healthy) and II-IV (neurotic tendency). The photoplethysmography under emotional stimuli using the audiovisual video footages for 40 seconds and during recalling the contents of the footages soon after the stimuli for 180 seconds was measured. These series were repeated three times. The emotional stimuli consisted of "positive stimuli" and "negative stimuli". The "positive stimuli" such as relaxed and pleasant stimuli could evoke a positive feeling, while the "negative stimuli" such as unpleasants #1 (human-relation problem) and #2 (fear) stimuli could evoke a negative feeling. Pulse waves from photoplethysmography were analyzed for estimating the pulse wave amplitude, reflection index (RI). and pulse wave length, and these values of two groups were compared using analysis of variance (ANOVA). The results showed that the pulse wave amplitudes of group I under and after the positive simuli were significantly larger than the amplitudes under and after the negative stimuli, respectively. On the other hand, there was no obvious difference of the pulse wave amplitudes of group II-IV between the positive and negative stimuli. RI of group I during and before the stimuli was smaller than the base line, and RI under the unpleasant #2 stimuli was smallest in all the stimuli. However, RI of group II-IV under the unpleasant #2 stimuli was largest in all the stimuli. The pulse wave length under the unpleasant #1 stimuli was significantly larger than the other stimuli, and the pulse wave length after the stimuli was significantly smaller than the base line. These results suggested that the autonomic nervous reaction under emotional stimuli would be regulated based on the psychosomatic states.
1 0 0 0 観光鉄道としての大井川鐵道の課題
- 著者
- 土`谷 敏治 高原 純 平林 航
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.2014, 2014
Ⅰ.はじめに<br> 本来鉄道は,通勤・通学,買い物,通院,観光,用務などの諸目的を実現するため,その目的地に到達する移動手段の1つであり,鉄道に乗車すること自体が目的ではない.しかし,諸目的のうち観光については,鉄道が単なる移動手段だけではない場合が考えられ,鉄道そのもの,あるいは鉄道に乗車することが観光の目的となりうる.新納(2013)によると,鉄道をはじめとする乗り物は,①観光地への移動手段,②観光資源をみるための移動手段,③それ自体が観光資源となるものの3つの位置づけが可能であるとしている.すなわち,①は他の目的達成のための派生需要に過ぎないが,②と③は鉄道自体が目的の本源的需要であるとする.<br> 静岡県の大井川鐵道は,旧国鉄の蒸気機関車が全廃された後,SL列車の運行を最初に復活させ,さらに定期的に運行していることで知られる.収支面や技術面などさまざまな側面からの検討がなされた結果,1976年にSL列車の大井川本線での運行が開始され(白井,2013),明らかにSL列車自体を観光資源と位置づけた経営をしている.しかし,これまで利用者に対して,その属性や観光利用の特色について調査したことがないという.これを踏まえて,本研究では大井川鐵道のSL列車利用者について,その諸属性,旅行目的とその特色を調査・分析し,利用者の側面から大井川鐵道の観光利用の特色と今後の課題について検討することを目的とする. <br><br> Ⅱ.調査方法<br> 今回の調査は,大井川鐵道のSL列車利用者,すなわち,観光目的での大井川鐵道利用者を対象としている.このため,調査は2013年10月19日(土)と20日(日)の2日間にわたって実施した.両日は,いわゆる秋の観光シーズンの週末,土曜日と日曜日に相当する.また,大井川鐵道でもこの日から11月末までを観光シーズンの重点期間と位置づけており,19日に観光シーズンに向けての列車ダイヤ改正を実施した.<br> アンケート調査は,2日間3往復6列車の車内で,利用者に調査票を配布し,利用者自身が記入する方式で回答を求めた.主な質問項目は,年齢・性別・居住地等の利用者の属性,個人・家族・団体等の同行者構成,旅行日数,大井川鐵道乗車回数,観光の目的などである.また,SL列車の利用パターンを明らかにするため,SL列車の停車駅間で,乗車中の旅客数を数え,輸送断面を作成した.<br><br> Ⅲ.調査結果の概要<br> 2日間の調査によって,SL列車の旅客輸送断面とその特色が明らかになるとともに,アンケート調査の結果,503人から有効回答がえられた.<br> 1.SL列車の利用は,往路の下り千頭行きが中心で,上り新金谷行きは往路の半分程度以下の利用である.また,ツアー客を中心に,新金谷・家山間の区間利用がみられ,上り列車利用促進,全区間乗車促進策が求められる.<br> 2.SL列車の利用者は,いわゆる中高年の女性中心という観光客の一般的特色に比べ,広い年齢層にわたっていることが明らかになった.また,鉄道が対象ということもあり,比較的男性の利用者が多い.その居住地は,愛知県,三重県,岐阜県など中部地方が多く,距離的に大きな差がない東京都,神奈川県など南関東からの誘客が課題である.<br> 3.SL列車利用者の旅行目的は,SL列車に乗車することに集中しており,SL列車以外の観光目的への誘導が必要である.<br> 4.SL列車利用者は,一人旅をはじめ,夫婦旅行・家族旅行・友人同士などの個人旅行と,旅行会社のツアーやグループ旅行などの団体旅行に2分される.前者は,大井川鐵道までの交通手段として,家族旅行を中心に自家用車の利用が多い.ただし,夫婦旅行や一人旅のように同行者人数が少ないとJR線利用が増加する.後者は,ツアーバス利用が基本である.また,団体旅行に比べ個人旅行では,SL列車乗車以外の旅行目的の割合が高まる.<br> 5.SL列車利用者は約1/4が再訪者で,比較的リピーター率が高い.さらに,再訪者ほどSL列車乗車以外の旅行目的をもつ場合が多い.<br> 以上の結果から考えられる今後の課題としては,区間利用の対策として,蒸気機関車はもちろん,旧型客車,駅や検修設備を含めた大井川鐵道全体の特色・魅力をこれまで以上に利用者に伝え,車内・駅での見学の機会を増やすことが求められる.SL列車乗車に偏重した旅行目的,片道乗車への対策として,沿線・沿線以外の静岡県内の観光地・観光施設の活用・連携と広報,ツアーを企画する旅行会社への働きかけ,JR各社との協調,各種マスメディアの活用も重要である. 参考文献<br>白井昭 2013.保存鉄道とは技術と文化の継承である。(インタビュー).みんてつ44:20-23.<br>丁野朗 2013.観光資源としての地域鉄道.運輸と経済73(1):10-17.<br>新納克広 2013.鉄道経営と観光 ―派生需要と本源需要―.運輸と経済73(1):4-9.
1 0 0 0 OA 嗅覚障害・味覚障害の診断と治療
- 著者
- 司会:西﨑 和則 演者:小林 正佳 任 智美
- 出版者
- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)
- 巻号頁・発行日
- vol.121, no.4, pp.460-461, 2018-04-20 (Released:2018-05-16)
1 0 0 0 OA APP-067 ヒト下部尿路閉塞膀胱上皮における受容体サブタイプ(EP1,EP2,EP3,EP4)の発現 : 非閉塞膀胱との比較(排尿障害/臨床,総会賞応募ポスター,第96回日本泌尿器科学会総会)
- 著者
- 姜 元軍 荒木 勇雄 小林 英樹 座光寺 秀典 芳山 充晴 澤田 智史 望月 勉 武田 正之
- 出版者
- 一般社団法人 日本泌尿器科学会
- 雑誌
- 日本泌尿器科学会雑誌 (ISSN:00215287)
- 巻号頁・発行日
- vol.99, no.2, pp.243, 2008-02-20 (Released:2017-04-08)
1 0 0 0 OA 自己免疫性てんかんにおける診断アルゴリズムの提唱とその有用性の予備的検討
- 著者
- 坂本 光弘 松本 理器 十川 純平 端 祐一郎 武山 博文 小林 勝哉 下竹 昭寛 近藤 誉之 髙橋 良輔 池田 昭夫
- 出版者
- 日本神経学会
- 雑誌
- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)
- 巻号頁・発行日
- pp.cn-001180, (Released:2018-09-29)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 4 2
自己免疫性てんかんが近年注目されているが,抗神経抗体以外の特異的な診断法は確立していない.今回我々は最初に病歴・臨床症候,次に検査成績と2段階で自己免疫性てんかんを診断するアルゴリズムを作成し,臨床的有用性を予備的に検討した.自己免疫性てんかんが疑われた70名に後方視的にアルゴリズムを適応した.MRI,髄液,FDG-PET検査のうち,2項目以上異常所見があれば診断に近づく可能性が示された.一方で抗体陽性13名のうち2名は,第一段階の臨床症候で自己免疫性てんかんの可能性は低いと判断された.包括的抗体検査のもと診断アルゴリズムの更なる検証,改訂が望まれる.
1 0 0 0 IR 反応動作時における自発的『掛け声』の影響
- 著者
- 林 和哉 脇田 裕久
- 出版者
- 三重大学
- 雑誌
- 三重大学教育学部研究紀要. 自然科学 (ISSN:03899225)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, pp.75-84, 2004-03-31
本研究は、動作前の自発的掛け声が局所および全身反応時間に及ぼす影響を観察し、自発的掛け声が神経・筋機能に与える影響について検討することを目的とした。局所反応動作におけるS反応動作およびF反応動作のEMG-RTは、absence試行に比較してpresence試行が有意に短縮した。IEMGについては、absence試行に比較してpresence試行が有意に増大した。全身反応時間については、EMG-RTは、absence試行に比較してpresence試行が有意に短縮した。EMD・動作時間・力積については、両条件間に有意な差が認められなかったが、平均発揮筋力はabsence試行に比較してpresence試行が有意に増大した値を示した。以上のことから、自発的掛け声は局所および全身の反応動作におけるEMG-RTを有意に短縮させるとともに、その後に続く筋力発揮にも作用をもつことが示唆され、このことについては自発的掛け声が網様体賦活系や大脳の運動準備電位の活動水準を上昇させる可能性のあることが考えられる。
1 0 0 0 現代の潜水艦(第29回)
1 0 0 0 OA 北海道日高國幌滿鑛山の含ニッケル磁硫鐵鑛鑛床に就て
- 著者
- 小林 治夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.566, pp.429-436, 1940-11-20 (Released:2008-04-11)