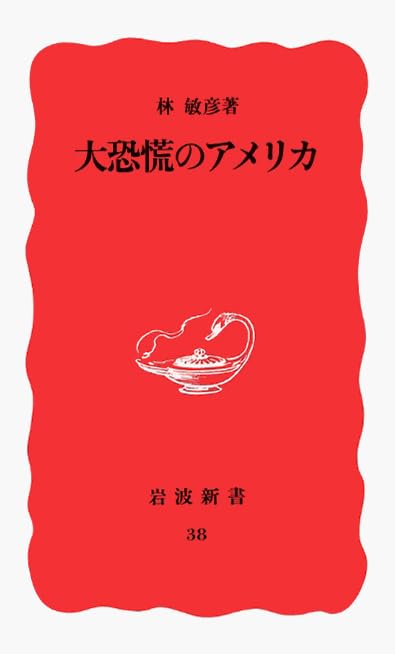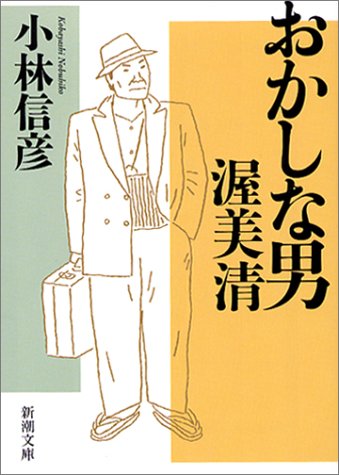- 著者
- 西嶋 力 井村 保 大嶽 昇弘 千鳥 司浩 林 典雄 濱岸 利夫 笠野 由布子
- 出版者
- 中部学院大学教育学部
- 雑誌
- 中部学院大学・中部学院大学短期大学部教育実践研究 = Chubu Gakuin University and Chubu Gakuin College Journal of Educational Research and Practice (ISSN:24241105)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.141-149, 2016-03
- 著者
- 福田 聡史 喜屋武 龍介 林 敏彦 溝田 康司
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.44 Suppl. No.2 (第52回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.1722, 2017 (Released:2017-04-24)
【はじめに,目的】理学療法士の(以下,PT)の臨床実習では,学生は学内で学習した知識や技術を臨床時現場で活かすための体験ができる貴重な機会である。一方で,学生の指導を担当する指導者(SV)は臨床業務も多く,また,指導のための手間は多岐に渡る。さらに学生のレディネスが不十分な場合には実習を十分に遂行できないこともあり,教員のサポートが必要な場合も多い。今回,長期臨床実習において教員が毎週施設に訪問し,実習の進捗状況や学生の生活状況,指導者と教員の情報共有ツールとしてのプログレスノートを用い,即時性のある対応を試みた。その内容をテキストマイニング手法を用いて分析したので報告する。【方法】事前に今回の取り組みを説明し,同意の得られた施設の指導者とその責任者,当該施設で実習を行う実習生9名と当学院の教員3名を対象とした。各施設に当学院の教員を1名割り当て,毎週1回各施設を訪問した。訪問時の共有ツールとして「実習計画及び経過記録表(以下,プログレスノート)」を作成し,「生活状況」「実習進捗状況」「実習計画」「その他・連絡事項」の4項目について教員と指導者が自由に記入し,併せて面談を行い経過を追った。プログレスノートの記録結果を,上記4カテゴリーに分類し,記載内容を実習の進捗にポジティブに働く要素や言葉(以下,ポジティブ),ネガティブな要素や言葉(以下,ネガティブ),その他の項目に分け,実習経過に沿った変化を概観的に検討した。また,立命館大学樋口耕一氏が開発したフリーウェアKH Coderを用い,プログレスノートに記載された内容についてテキストデータマイニング分析を行った。【結果】テキストマイニングの分析結果を基に共起ネットワークの結果をまとめた。すべての項目の中心となったワードは,1~2週目は「コミュニケーション」「生活状況」,3~5週目は「1症例目」「初期評価」「発表」,6~8週目は「2症例目」「中間評価」9週目は「発表終了」「レジュメ作成」「修正」「まとめ」,10週目は,「アドバイス」であった。ネガティブ要素のみを抽出した結果,実習の前半においては,「知識」「状況」と「不十分」「低い」がネットワークを形成し,中盤からは,前半のワードに「指導」「検査」が加わった。後半においても同様の傾向を示し,その頻度は増加した。【結論】これらのことから実習前半では学生と指導者間での実習状況や生活状況についてネガティブなワードが多く見られ,ストレスにつながりやすい状況にあると考えられる。実習前半での学生の環境への適応や現場で学びに関する支援やサポートが必要であると考えられる。ネガティブ要素についてテキストマイニング手法を用いて分析する事で,指導者と学生間のストレスにつながりやすい状況について経時的変化を可視化し捉える事が出来ると考える。
1 0 0 0 OA 脳波計測における瞬目に関連したアーティファクトの局所的な除去法
- 著者
- 川口 浩和 小林 哲生
- 出版者
- 公益社団法人 日本生体医工学会
- 雑誌
- 生体医工学 (ISSN:1347443X)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.4, pp.551-557, 2011-08-10 (Released:2012-01-18)
- 参考文献数
- 10
Eye-blink activities are major artifacts for electroencephalogram (EEG) measurements. Various methods have been reported for removing eye-blink artifacts from EEGs. Almost all previous methods focus on how much eye-blink artifacts are removed. However, they concurrently remove a part of EEGs together with eye-blink artifacts. Instead, we focus on how much true EEGs remains, and proposed a localized removal method for eye-blink artifacts. The proposed method is based on the combinations of independent component analysis (ICA). empirical mode decomposition (EMD) and Kalman filter. In addition, we proposed a novel simulation model to test performances of the proposed and previous methods. This simulation model indicates that the proposed method shows the best performance and reduces information loss of EEGs than previous methods.
- 著者
- 小林 和子 中村 宗亥 藤原 耕三
- 出版者
- 大阪夕陽丘学園短期大学
- 雑誌
- 大阪女子学園短期大学紀要 (ISSN:02860570)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.32-48, 1964-07-01
調理した食物6種(煮タコ,椀種用塩茹でハモ,塩茹でレバー,塩茹でエビ,茹で卵,チキンカレー)を電気冷蔵庫(品温3±2℃)とフリーザー(品温-23±2℃)に8週間貯蔵してその味の変化を検討した。得られた結果を要約すると次の通りである。1. 6種食物を冷蔵車内に貯蔵した場合は,貯蔵可能日数は7日位であったが,フリーザー内で貯蔵した場合は8週間に亘る実験期間を通じて食べられる状態に貯蔵できた。2. フリーザーに貯蔵した場合,味の変化の起る程度は各食物により異り,6種食物中煮タコ,塩茹でハモ,塩茹でエビ,塩茹でレバーは貯蔵中味の変化の少いものであった。これに反して,茹で卵は特に白身が変化して,冷凍貯蔵では味が劣化した。良好な状態で保ち得た4種食物は,温度降下が速かであった事により,冷凍貯蔵では,貯蔵中に於けるよりも凍結時に於ける変化が重要である事が示唆された。3. フリーザーに貯蔵した場合の味必変化は,冷蔵庫に貯蔵した場合に較べて緩慢であったが,中でも特に香の変化が少いのが特徴であった。
- 著者
- 尾西 輝昭 小林 宏至
- 出版者
- 日本農業市場学会
- 雑誌
- 農業市場研究 (ISSN:1341934X)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.2, pp.76-77, 1998-03-31
1 0 0 0 秘められた昭和史 : 戦雲の中の東奔西走記
1 0 0 0 OA 高等学校の世界史教育と大学の歴史学 : 歴史教育の接続の観点から
- 著者
- 徳橋 曜 小林 真
- 出版者
- 富山大学人間発達科学部附属人間発達科学研究実践総合センター
- 雑誌
- 教育実践研究 : 富山大学人間発達科学研究実践総合センター紀要 (ISSN:18815227)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.143-157, 2016-12
この10年ほどの間、高校の現場や大学の教員の間で、世界史教育の在り方がしきりに議論されるようになっている。その中で、高校の世界史教育がどうあるべきか、あるいは大学で世界史をどう教えるべきかという議論や研究は少なくないが、高校の世界史教育と大学の歴史学・歴史教育をどうつなぐかという点については、必ずしも十分な検討がなされていない。本稿では学生へのアンケートから、世界史教育の意義や高校と大学の歴史教育の関連性をめぐる彼らの意識を検討し、高校の世界史教育と大学の歴史教育の接続の在り方を考察する一助とする。
1 0 0 0 OA 走行安定性と曲線通過性能を両立する傾斜軸EEF台車の提案と運動解析
- 著者
- 道辻 洋平 志賀 亮介 須田 義大 林 世彬 牧島 信吾
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学会論文集 (ISSN:21879761)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, no.851, pp.17-00068-17-00068, 2017 (Released:2017-07-25)
- 参考文献数
- 17
It is important for railway bogies to get compatibility between curving performance and running stability. Utilizing independently rotating wheels may be an effective solution. The EEF bogie proposed by Dr.Frederich in late 1980th shows good curving performance making use of the gravity restoring force generated by the tread gradient of independently rotating wheels. However, the bogie gives rise to a kind of hunting motion as the vehicle running velocity increases. In this paper, an effective modification of the EEF bogie which solves the hunting motion is mentioned. The solution is to incline both wheel-axles while adjusting the tread shape of each wheel. In this paper, the EEF bogie with inclined wheel-axles is firstly proposed and analytically evaluated by the MBD simulation. Since the newly proposed bogie has complicated structures, a precise modeling of the bogie is mentioned in detail. From the result of eigenvalue analysis, proposed bogie can dramatically improve the hunting stability as compared to the conventional EEF bogie. In addition, the proposed bogie has excellent curving performance in tight curve section equivalent to the conventional EEF bogie. As those results, it is possible to achieve both high speed hunting stability and curving performance utilizing the proposed bogie unit in the vehicle.
1 0 0 0 OA 数式処理:多変数連立代数方程式の解法
1 0 0 0 OA 新幹線の台車部から発生する空力音の実験的推定法
- 著者
- 山崎 展博 北川 敏樹 宇田 東樹 栗田 健 若林 雄介 西浦 敬信
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学会論文集 (ISSN:21879761)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, no.851, pp.17-00146-17-00146, 2017 (Released:2017-07-25)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 4
A method has been developed for predicting the aerodynamic noise from the bogie of a high-speed train using a two-dimensional microphone array in a low-noise wind tunnel. First, the mean velocity distribution of flow was simulated precisely in the low-noise wind tunnel. Next, aerodynamic noise generated by the bogie, hereinafter referred to as aerodynamic bogie noise, was estimated from the noise source distribution measured with the two-dimensional microphone array. Finally, based on the experimental results, the predicted noise generated from the lower part of the car (i.e. the total of the aerodynamic noise estimated through the proposed method and the rolling and machinery noise estimated in a previous study) was compared with the measurement data obtained near the track in the field test. It was found that the predicted sound pressure level showed good agreement with those measured in the field test. This suggests that the proposed method is appropriate to estimate the aerodynamic bogie noise quantitatively. It was also shown that the contribution of the aerodynamic bogie noise to the total noise generated from the lower part of the car is greater than that of rolling and machinery noise, especially below 500 Hz.
1 0 0 0 『囲碁式』の文化史的意義
- 著者
- 林 道義
- 出版者
- 東京女子大学
- 雑誌
- 東京女子大学比較文化研究所紀要 (ISSN:05638186)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, pp.1-16, 1995
1 0 0 0 インターネット森林観察ウェブサイトの構築
- 著者
- 斎藤 馨 中村 和彦 渡辺 隆一 藤原 章雄 岩岡 正博 中山 雅哉 大辻 永 小林 博樹
- 出版者
- 日本森林学会
- 雑誌
- 日本森林学会大会発表データベース
- 巻号頁・発行日
- vol.124, 2013
「インターネット森林観察サイト」は、森林の現在の様子、過去の様子をインターネットから提供するサイトで、誰もが、遠隔の森林情報に容易に接しながら、森林の季節や経年変化に気づき、興味を持って森林の観察ができ、しかも観察継続がしやすくなるサイトを目的に開発した。対象の森林は遠隔の天然林で、 かつ長期映像記録のある東京大学秩父演習林(埼玉県奥秩父:過去15 年間記録)と信州大学志賀 自然教育園(長野県志賀高原:過去20 年間記録)とした。森林の様子を映像と音によりリアルタ イム(ライブ)でインターネット上に配信し、同時に配信データを録画・録音・公開し、配信後 にも観察できる森林観察サイトを開発し、継続的な運用試験を可能にした。例えば、フェノロジーに着目すると過去の映像と同じショットの画像が毎日配信されることで、日々や季節の変化を見ることが出来、ふと気づいたときに数年から十数年を遡って確認することが出来る。しかもインターネット上で共有されているため、SNSとの親和性も高いことを確認した。
1 0 0 0 情報活用の実践力尺度の作成と信頼性および妥当性の検討
1 0 0 0 OA Tracheostomy positive pressure ventilation(TPPV)を導入したALS患者のtotally locked-in state(TLS)の全国実態調査
- 著者
- 川田 明広 溝口 功一 林 秀明
- 出版者
- 日本神経学会
- 雑誌
- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.7, pp.476-480, 2008 (Released:2008-08-21)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 6 11
TPPVを導入したALS(TPPV・ALS)患者のtotally locked-in state(TLS)について全国調査をおこなった.調査時点709名のTPPV・ALS患者中89名(13%)がTLSであった.臨床経過が確認されたTLS患者41名は,ALSの神経病院分類で,29名(70%)が6カ月間内に四肢,橋・延髄(球),呼吸および外眼運動系の4つの随意運動系のうち2つ以上が麻痺した複数同時麻痺型で,28名(70%)はTPPV開始後5年以内にTLSになった.また最後に麻痺した随意運動系は,37名(90%)が外眼運動系であった.神経病院TLS例の臨床経過の特徴は、全国調査の結果に合致していた。
1 0 0 0 OA イカの精子嚢による口腔内刺傷の一例
- 著者
- 浜田 篤郎 渡辺 直煕 山崎 洋次 吉葉 繁雄 小林 昭夫
- 出版者
- 日本衛生動物学会
- 雑誌
- 衛生動物 (ISSN:04247086)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.3, pp.279-280, 1990-09-15 (Released:2016-08-26)
- 被引用文献数
- 3 3
A 57-year-old woman experienced pain from foreign bodies in her oral cavity after eating raw squid. Examination of her oral cavity revealed 20-30 small foreign bodies embedded in the mucous membrane. After all the foreign bodies were pulled out, the pain was allayed and the wounds eventually healed. The foreign bodies, 5mm in length, were white and of elongated conical shape. Under microscopy, a large number of sperms was observed in the bodies. These foreign bodies were determined to be sperm-bags of the squid. It is supposed that this woman ate squid with spermatophores, thereafter sperm-bags were discharged from the spermatophores into her oral cavity. Although only a few similar cases heretofore have been found, it might increase among the Japanese who frequently eat raw squid.
1 0 0 0 OA 首都圏ベッドタウンにおける世帯構成別にみた孤立高齢者の発現率と特徴
- 著者
- 斉藤 雅茂 藤原 佳典 小林 江里香 深谷 太郎 西 真理子 新開 省二
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.9, pp.785-795, 2010 (Released:2014-06-12)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 2
目的 本研究では,首都圏ベッドタウンで行った調査に基づいて,独居高齢者と同居者のいる高齢者のなかで,孤立した高齢者の発現率とその特徴,および,孤立に関する設問に無回答であった孤立状況不明者の特徴を明らかにすることを目的にした。方法 使用したデータは,埼玉県和光市において,独居の在宅高齢者978人,同居者のいる在宅高齢者1,529人から得られた。社会的孤立の操作的定義には,同居家族以外との接触頻度を用い,別居家族・親戚,および,友人・近所の人との対面接触と非対面接触のいずれもが月に 2, 3 回以下を「孤立」,それ以上を「非孤立」,それらの設問に無回答を「孤立状況不明」に分類した。世帯構成別に孤立・非孤立を従属変数,性別,年齢,婚姻経験,近居子の有無,移動能力,経済状態を独立変数に投入したロジスティック回帰分析,および,それらの諸変数について孤立状況不明と孤立・非孤立間での比率の差の多重比較を行った。結果 分析の結果,1)上記の定義で捉えた場合,孤立者は,独居者では24.1%(独居型孤立),同居者のいる高齢者では28.7%(同居型孤立)であること,2)独居・同居に関わらず,男性,子どもがいない人および近居子がいない人,より所得が低い人の方が孤立に該当しやすいこと,他方で,3)離別者と未婚者の方が独居型孤立に該当しやすく,より高齢の人,日常の移動能力に障害がある人の方が同居型孤立に該当しやすいという相違があること,4)独居・同居にかかわらず,孤立状況不明者はこれらの諸変数において孤立高齢者と類似していることが確認された。結論 高齢者の社会的孤立は独居者だけの問題ではなく,独居型孤立と同居型孤立の特徴の相違点に対応したアプローチを検討する必要があること,また,孤立高齢者をスクリーニングする際には,孤立関連の設問への無回答者を孤立に近い状態と捉えるべきことが示唆された。
- 著者
- 小林 江里香 藤原 佳典 深谷 太郎 西 真理子 斉藤 雅茂 新開 省二
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.6, pp.446-456, 2011 (Released:2014-06-06)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 2
目的 本研究は,高齢者の社会的孤立を同居家族以外との接触頻度の低さから定義し,孤立者が抱える生活•心理面での課題と,そのような課題が同居者の有無や性別によってどのように異なるかを明らかにすることを目的とした。方法 65歳以上の在宅高齢者を対象とした調査より,独居群948人,同居群1,426人のデータを分析した。社会的孤立状況は,別居親族または友人•近所の人との接触が週 1 回以上あるかで,「対面接触あり」,「非対面接触のみ」,「接触なし(孤立)」に分けた。私的サポートの利用可能性(6 項目),公的サポートの利用可能性(2 項目),抑うつと将来への不安を従属変数とするロジスティック回帰分析を行い,年齢,IADL,社会経済的地位を調整後の社会的孤立状況,独居,性別の主効果と交互作用効果を調べた。結果 独居男性では42%が孤立に該当し,独居女性(17%)と大きな差があった。私的サポート入手不能,サービス相談先なし,地域包括支援センターの非認知,抑うつ傾向あり,将来への不安の高さのいずれについても,「対面接触あり」に対する孤立者のオッズ比は有意に高かった。また,私的サポートについては,孤立状況と同居者の有無の交互作用があり,孤立と独居が重なることでサポートを得られないリスクが一層高まっていたが,独居が独立した効果を示したのは,一部のサポート項目や抑うつ傾向に限られた。結論 孤立高齢者は,同居者の有無にかかわらず,私的•公的なサポートを得にくく,抑うつ傾向や将来への不安も高いなど,多くの課題を抱えていることが明らかになった。