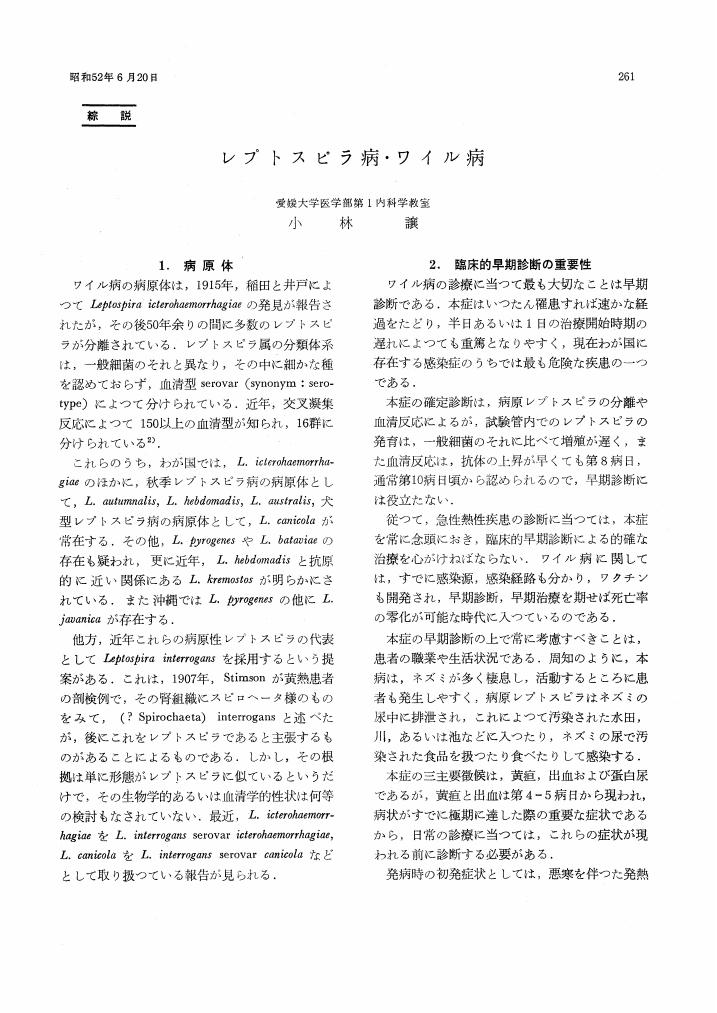1 0 0 0 OA 6.方言の20世紀(日本語の20世紀,日本語学会2007年度春季大会シンポジウム報告)
1 0 0 0 OA 影の表現を利用したインタラクティブコンテンツ
- 著者
- 佐藤 美穂 若林 尚樹
- 出版者
- Japanese Society for the Science of Design
- 雑誌
- 日本デザイン学会研究発表大会概要集
- 巻号頁・発行日
- pp.216, 2006 (Released:2006-08-10)
“影”は、我々の身の回に起こる物理現象である。また映画やアニメーションの表現手法の1つとして、影の非物理的な動きを利用した視覚的表現が、時刻や環境などの状況説明や、感情などの心理表現に多用されている。そこで本研究では、物理現象である影がアニメーションなどで利用される映像的表現を、再度実世界のインタラクティブコンテンツ上で表現するという試みを行い、従来の視覚的表現手法では困難であった、背景や状況を説明する上での、新たな表現手法としての影の表現の効果と役割について明らかにすることを目的とした。そこで映画・アニメーションなどを参考に、影の非物理的表現の調査と分類を試みた。さらにその分類結果を元に、インタラクティブインスタレーション作品を制作し、実際にユーザに体験してもらうことによって影の表現を利用したインタラクティブコンテンツの効果や特性の検討を行った。その結果、影のように日常にある何気ないものが変化することを利用した表現によって、今までにない情報を読み取り、考えることが可能となり、新たな情報伝達手法としての可能性が広がったのではないかと考えられる。
1 0 0 0 IR 自律的学習の領域横断的研究の試み : 学習メディアの視点から
- 著者
- 高林 友美 佐々木 輝美
- 出版者
- 国際基督教大学
- 雑誌
- 教育研究 (ISSN:04523318)
- 巻号頁・発行日
- no.57, pp.137-146, 2015-03
現在のICT社会においてますます注目をあびる自律的学習の研究は,教育心理学,言語教育,成人教育,など,いくつかの領域に分かれて行われている。本研究はこれらの研究を領域横断的にまとめることで自律的学習に重要な要素を明らかにしようとした。各領域の代表的な特徴としてモチベーション,対人コミュニケーションの積極性,自己理解といった要素を発見し,それらに関係する新しい要素として学習のためのメディアという視点が導かれた。更に,この視点に関して関東圏の大学生300人を対象とした調査を行ったところ,メディアリテラシーやイノベーティブネスといった学習メディアの利用の傾向と自律的学習の間にある程度の相関が認められた。Studies of autonomous learning are attracting increasing attention in current ICT society, and are spreading into various disciplines and domains such as educational psychology, language education, and adult education. Summarizing the results of autonomous learning studies in these disciplines, this study explores the elements of autonomous learning. The results indicate the positive attitudes toward personal communication, self-understanding, and motivation constituting the representative characteristics of each discipline; in addition, a new viewpoint emerges called 'learning media.' This new viewpoint was researched in a survey of 300 university students in the Kanto area. The results revealed a moderate positive correlation between autonomous learning and learning media usage, measuring with media literacy and innovativeness.
- 著者
- 原田 謙 杉澤 秀博 小林 江里香 Jersey Liang
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.3, pp.382-397, 2001
- 被引用文献数
- 1
本研究は, 全国高齢者に対する3年間の縦断調査データ (1987-1990) を用いて, 高齢者の所得変動の実態を明らかにし, 貧困への転落, 貧困からの脱出という所得変動の関連要因を検証することを目的とした.本人と配偶者の年間所得の合計が120万円未満の高齢者を貧困層と操作的に定義し, 関連要因として社会経済的地位およびライフイベント指標を分析に投入した. 分析の結果, 以下のような知見が得られた.<BR>(1) 各時点の貧困層の出現割合は 34.7% (1987), 31.7% (1990) であったが, 追跡期間中に全体の8.8%が貧困転落, 11.8%が貧困脱出を経験していた.<BR>(2) 社会経済的地位に関して, 学歴が高い者の方が貧困転落の確率が低く, 最長職の職種によって貧困転落・貧困脱出の確率が異なった.<BR>(3) 高齢期のライフイベントに関して, 追跡期間中における配偶者との死別は, 女性にとってのみ貧困転落のリスク要因であった.追跡期間中における失職は貧困転落のリスク要因であり, 就労継続は貧困脱出の促進要因であった.<BR>(4) 社会経済的地位, ライフイベントの影響をコントロールしても, 性別, 年齢, 生活機能といった要因が, 高齢者の所得変動に有意に関連していることが明らかになった.具体的には男性の方が女性より貧困脱出の確率が高く, 高齢である者, 初回調査時点の生活機能が低い者の方が貧困脱出の確率が低かった.
1 0 0 0 OA 老朽化する都市インフラの選択集中整備に関する理論・実証研究
- 著者
- 大澤 義明 鈴木 勉 秋山 英三 吉瀬 章子 宮川 雅至 小市 俊悟 渡辺 俊 堤 盛人 藤井 さやか 竹原 浩太 有田 智一 田中 健一 小林 佑輔 櫻井 一宏
- 出版者
- 筑波大学
- 雑誌
- 基盤研究(A)
- 巻号頁・発行日
- 2013-04-01
本研究課題は,老朽化する都市インフラ整備の選択集中に関して,独自にデータ収集し,実証分析を実行し,同時に理論的知見を導くことを通じ,施設整備に関する具体の政策を提言することを目的としている.最初に研究基盤を構築した上で,逐次廃止手法の効率性評価,リスク分析における効率性と冗長性とのトレードオフ構造等に関する理論研究・実証研究を展開した.様々な自治体と意見交換・情報収集することから,実装対象を北海道網走郡津別町,茨城県土浦市,茨城県常総市に絞り,研究・理論の自治体への実装を進めた.
1 0 0 0 OA 公共施設配置における住民投票の意義-投票制度は経済効率をどの程度悪化させるのか
公共施設立地を巡る投票に参加する住民の影響を考察するため, 空間を取り込んだ基礎理論を構築した.住民アクセスという距離空間を明示的に取り込んだ単純な公共施設配置モデルを構築し,施設建設について各人の負担する費用(個別合理性)と行政が負担する全住民分の費用(全体合理性)についての比較を数式により明示し投票結果が経済的に最適となる必要十分条件を導出した。庁舎問題に関しては現地建て替えが有利となる2/3以上の同意要件(現在の地方自治法)の非効率性について明らかにした.加えて,実際の関東地域自治体庁舎建設に関して,GISを用いて可視化しながら投票結果の移動効率性の大きさや空間分布に関して分析した.
1 0 0 0 OA 2足歩行ロボット教材を用いた計測・制御学習の提案
- 著者
- 紅林 秀治 樋口 大輔 菱田 亘 大村 基将 兼宗 進
- 雑誌
- 研究報告コンピュータと教育(CE)
- 巻号頁・発行日
- vol.2010-CE-105, no.6, pp.1-8, 2010-07-03
中学校技術・家庭科 (技術分野) における計測・制御学習用教材として 2 足歩行ロボット用いた学習指導を提案する.2 足歩行ロボットは教材用として独自に開発したものを用いる.開発した 2 足歩行ロボットは,16 個のサーボモータを使用した.また,中学生でも製作できるように,工作用アルミ金属や自在金具を利用してロボットのフレームが製作できるようにした.さらに,2 足歩行ロボットを制御する基板も開発した.開発した制御基板を用いることで,16 個のサーボモータの制御と 3 軸加速度センサーによる計測を可能にした.開発した 2 足歩行ロボットおよびそれを用いた学習計画と期待する教育効果について述べる.
1 0 0 0 OA 全マントルP波トモグラフィーの地質学的解釈
- 著者
- 深尾 良夫 丸山 茂徳 大林 政行 井上 公
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.100, no.1, pp.4-23, 1994-01-15 (Released:2008-04-11)
- 参考文献数
- 88
- 被引用文献数
- 67 79
1 0 0 0 OA レプトスピラ病・ワイル病
- 著者
- 小林 譲
- 出版者
- 社団法人 日本感染症学会
- 雑誌
- 感染症学雑誌 (ISSN:03875911)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.6, pp.261-263, 1977-06-20 (Released:2011-09-07)
- 参考文献数
- 5
1 0 0 0 食品業界における企業不祥事の発生メカニズムに関する研究
- 著者
- 西岡 久充 小林 猛久 小林 稔
- 出版者
- 和光大学社会経済研究所
- 雑誌
- 和光経済 (ISSN:02865866)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.3, pp.37-50, 2012-03
- 著者
- 宮崎 佳典 林 佳樹
- 出版者
- 京都大学
- 雑誌
- 数理解析研究所講究録 (ISSN:18802818)
- 巻号頁・発行日
- vol.1780, pp.130-140, 2012-03
1 0 0 0 IR サードプレイスにおける経験がもたらす地域愛着と協力意向の形成
- 著者
- 小林 重人 山田 広明
- 出版者
- 地域活性学会
- 雑誌
- 地域活性研究 (ISSN:21850623)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.1-10, 2015
本稿の目的は、非常設型カフェの利用者の地域愛着を高めることで、利用者の地域に対する協力意向を形成する過程が効果的に機能するカフェの経験と利用者の属性を明らかにすることである。そのため、非常設型カフェの利用者に対してアンケート調査を実施した。分析結果から、地域外に居住する利用者の協力意向の形成には、地域の魅力となるメニューの提供と知らない他者とのコミュニケーションが寄与することを示した。また、これらの二要素に対する肯定的評価と地域愛着には有意な相関があることを示した。以上の結果から、地域愛着が中立である利用者の協力意向の形成には、カフェにおいて二要素を経験させることが効果的であると結論付ける。
1 0 0 0 OA 討議理論と公的討論の規範的評価
- 著者
- 羽鳥 剛史 小林 潔司 鄭 蝦榮
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集D3(土木計画学) (ISSN:21856540)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.2, pp.101-120, 2013 (Released:2013-05-20)
- 参考文献数
- 92
- 被引用文献数
- 4 3
社会基盤整備事業に関わる合意形成を行う上で,パブリック・インボルブメントをはじめとする公的討論が重要な役割を担っている.本研究では,社会基盤整備における公的討議の意義と課題について整理し,社会的意思決定における正統性を様々な討論過程を通じて担保するための理論的枠組みについて考察する.その際,討論システムの概念を導入し,公的討論が特定の公的討論を対象としたミクロ討論,討論システム全体を対象としたマクロ討論で構成されており,パブリック・インボルブメント等が,ミクロ討論とマクロ討論を接合させる役割を果たすことを指摘する.その上で,討論システムを構成する公的討論の基本原理や望ましい討論を実現するための課題や問題点,討論の望ましさを評価するための基本的な考え方について考察する.
1 0 0 0 OA Web Workersを用いた多変数公開鍵暗号Rainbowの並列実装
- 著者
- 鷲見 拓哉 石黒 司 清本 晋作 三宅 優 小林 透 高木 剛
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.9, pp.2061-2071, 2014-09-15
W3Cは,HTML5およびJavaScript上で並列計算を行うための規格であるWeb Workersの勧告候補を2012年に公開した.JavaScriptおよびWeb Workersはプラットフォーム非依存である.JavaScriptで書かれたウェブアプリケーションは広く普及しており,インターネット選挙運動やブロードキャスティングサービス等を行うウェブアプリケーションの中には安全な通信を必要とするものが存在する.そのようなウェブアプリケーションにディジタル署名を組み込むことにより,安全な通信を実現することができる.Rainbow署名は,DingとSchmidtにより2005年に提案された多変数公開鍵暗号方式のディジタル署名である.Rainbow署名は有限体上の多変数2次多項式の連立方程式に対する求解問題がNP困難であることを安全性の根拠とし,ポスト量子暗号の1つとして期待されている.本稿では,Web Workersを用いたRainbow署名の並列実装手法を提案し,その応用例を述べる.また,マルチコアCPUを搭載する汎用PCおよびAndroidタブレット端末を用いて提案方式の実行時間を計測した.その結果,汎用PC上においては0.62ミリ秒,Androidタブレット端末上においては4.54ミリ秒で署名検証を行うことができた.
- 著者
- 小林 文男
- 出版者
- 谷沢書房
- 雑誌
- 月刊状況と主体 (ISSN:03882063)
- 巻号頁・発行日
- no.272, pp.41-54, 1998-08
1 0 0 0 日本古代における山林修行の資糧(1)乞食・蔬食
- 著者
- 小林 崇仁
- 出版者
- 蓮花寺佛教研究所
- 雑誌
- 紀要 (ISSN:18828175)
- 巻号頁・発行日
- no.3, pp.15-61, 2010
- 著者
- 林 麻由 市井 雅哉 宅 香菜子
- 出版者
- 日本トラウマティック・ストレス学会 ; 2003-
- 雑誌
- トラウマティック・ストレス : 日本トラウマティック・ストレス学会誌 = Japanese journal of traumatic stress : official journal of the Japanese Society for Traumatic Stress Studies (ISSN:13480944)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1, pp.51-59, 2015
1 0 0 0 本学の学生の援助要請行動について
- 著者
- 中林 恭子 後藤 和史
- 出版者
- 愛知みずほ大学
- 雑誌
- 瀬木学園紀要 (ISSN:18817181)
- 巻号頁・発行日
- no.9, pp.82-87, 2015