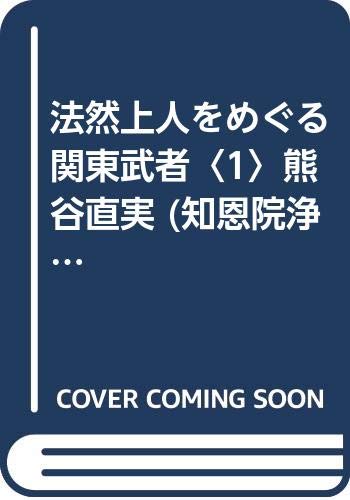1 0 0 0 OA 散乱型近接場顕微鏡によるテラヘルツ自然放出光の超解像イメージング
- 著者
- 梶原 優介 小坂 圭史 小宮山 進
- 出版者
- 公益社団法人 精密工学会
- 雑誌
- 精密工学会学術講演会講演論文集 2010年度精密工学会春季大会
- 巻号頁・発行日
- pp.385-386, 2010 (Released:2010-09-01)
あらゆる物質は分子振動やフォノンに起因する電磁波(主にTHz波)を自然放出しており,それらを高感度・高分解能で捕えることは物質自身のダイナミクスを映し出すことと等価である.我々は以前,世界最高感度のTHz検出器(CSIP)を導入して顕微鏡を開発し,分解能25ミクロンを達成した.本報では散乱型近接場顕微鏡を構築し,照射光源を使わずにTHz自然放出光の超解像イメージングに成功したので報告する.
1 0 0 0 OA 超音波定在波による液中気泡の制御とその応用
- 著者
- 梶山 智晴 富田 裕之 宮原 裕二
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電気学会論文誌E(センサ・マイクロマシン部門誌) (ISSN:13418939)
- 巻号頁・発行日
- vol.119, no.10, pp.464-469, 1999-10-01 (Released:2008-12-19)
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 1 1
We have developed a new method for cleaning flow-through cells by using microbubbles and ultrasonic (US) standing waves. A standing wave generated by US transducers at 1 MHz was used to trap microbubbles at node positions of the sound pressure. We were also able to control the microbubbles' positions spatially through frequency modulation. We found that these microbubbles were very effective for washing microbeads out of flow-through cells, particularly when frequency-modulated US irradiation was used. The proposed method promises to be very useful for cleaning the flow-through cells in small analytical instruments.
1 0 0 0 消えてゆく森について : 詩集
1 0 0 0 生と死のうた : 詩集
- 著者
- 白井 亮久 近藤 高貴 梶田 忠
- 出版者
- 日本貝類学会
- 雑誌
- Venus (Journal of the Malacological Society of Japan) (ISSN:13482955)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.3, pp.151-163, 2010
琵琶湖固有の絶滅危惧種イケチョウガイと中国からの移入種ヒレイケチョウガイの交雑の実態を探るため,分子マーカーを用いて解析を行った。ミトコンドリアのCox遺伝子と核rRNA遺伝子のITS1領域の塩基配列を用いた系統解析の結果,両種はいずれの分子マーカーでも区別されることが分かった。遺伝的組成を調べたところ,琵琶湖と霞ヶ浦の淡水真珠養殖場では両種の交雑に由来すると考えられる個体がみつかった。琵琶湖の養殖場は自然環境とは完全には隔離されていないため,逸出した養殖個体とイケチョウガイの野生個体との交雑が懸念される。姉沼の野生集団は移植された養殖個体の逸出に由来するものの,唯一交雑の影響を受けていない純粋なイケチョウガイの集団であると考えられるため,保全上非常に重要である。
- 著者
- 吉田 泉 駒田 敬則 森 穂波 安藤 勝信 安藤 康宏 草野 英二 大河原 晋 鈴木 正幸 古谷 裕章 飯村 修 小原 功裕 高田 大輔 梶谷 雅春 田部井 薫 NIKKNAVI研究会
- 出版者
- The Japanese Society for Dialysis Therapy
- 雑誌
- 日本透析医学会雑誌 = Journal of Japanese Society for Dialysis Therapy (ISSN:13403451)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.11, pp.909-917, 2010-11-28
- 被引用文献数
- 1
われわれは,透析患者の除水による循環血液量の変化をモニターする機器(Blood Volume Monitoring system:BVM)を日機装社(静岡)と共同開発し,多施設共同研究において臨床的にドライウエイト(DW)が適正と判断された患者の循環血液量の変化(BV%)の予想範囲を設定し,すでに報告した(Ther. Apher. Dial. in press).本論文では,その予想範囲が適正な除水量設定に有用か否かを検討した.維持透析を行っている9施設の144名を対象とし,採血日を含む3回の透析日に,BVM搭載装置を用いて透析を行った.DWが適正と判断された患者のBV%予想範囲は,上限ライン:BV%/BW%後=-0.437t-0.005 下限ライン:BV%/BW%後=-0.245ln(t)-0.645t-0.810.BV%は循環血液量変化率,BW%後は透析による除水量の前体重に対する比率,tは透析時間(h).今回の検討では,DW適正の可否を問わずに144例を抽出し,430データを集積した.プロトコール違反の94データを除外した336データを解析対象症例とした.各施設の判断によりDW適正と判断された230データで,BVMでも適正と判断された適正合致率は167データ(72.6%)であった.臨床的にDWを上げる必要があると判断された45データで,BVMでもDWを上げる必要があると判断されたのは10データ,逆に臨床的にDWを下げる必要があると判断された61データで,BVMでも下げる必要があると判断されたのは37データであった.その結果,BVMによる判定と臨床的判定の適合率は63.7%であった.不適合の原因としては,バスキュラーアクセスの再循環率(VARR),体位変換,体重増加量が1.0kg以下などであった.PWI(Plasma water index)による判定との適正合致率は71.6%で,適合率は58.0%であった.hANPによる判定との適正合致率は68.8%で,適合率は48.7%であった.循環血液量のモニターは,透析患者の除水設定管理の一助になり,われわれが設定したBV%予想範囲は臨床的にも妥当性が高いと考えられた.
1 0 0 0 OA 走査型トンネル顕微鏡
1 0 0 0 OA マウスモデルを用いた大腸がん転移機構の解明
本研究では、マウス生体での機能に基づいた探索により大腸がんの転移制御因子の同定を試み、HNRNPLLというRNA結合タンパクを見出した。大腸がん細胞でHNRNPLLの発現を低下させると転移能や浸潤能が亢進した。さらにHNRNPLLは、(1) CD44というタンパクをコードするpre-mRNAの選択的スプライシングを調節して大腸がん細胞の浸潤を抑制すること、(2) 大腸がん細胞の上皮間葉転換の際に発現が低下すること、(3) DNA複製因子をコードするmRNAの安定性を高めて大腸がん細胞の増殖を促進することを明らかにした。
1 0 0 0 IR スポ-ツ選手の人格構造-1-全日本体操競技選手の事例
- 著者
- 後藤 清志 清水 正典 梶谷 信之
- 出版者
- 岡山県立短期大学
- 雑誌
- 岡山県立短期大学研究紀要 (ISSN:02871130)
- 巻号頁・発行日
- no.34, pp.p113-119, 1991
- 著者
- 南澤 孝太 深町 聡一郎 梶本 裕之 川上 直樹 舘 〓
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本バーチャルリアリティ学会
- 雑誌
- 日本バーチャルリアリティ学会論文誌 (ISSN:1344011X)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1, pp.15-23, 2008
- 被引用文献数
- 17 9
We propose a wearable haptic display to present the sensation of weight and inertial force of virtual objects, which is based on our novel insight that the deformation on fingerpads makes a reliable sensation of weight even when the proprioceptive sensations on wrist and arm are absent. The goal of this project is to meet the increasing demand for realistic haptic feedback with a simple haptic display that delivers realistic existence of virtual objects in entertainment, augmented reality or telexistence systems.
1 0 0 0 蛋白漏出性胃腸症を伴った全身性エリテマトーデスの1例
- 著者
- 松村 みなこ 田中 信治 玉木 憲治 隅井 雅晴 三重野 寛 吉原 正治 春間 賢 隅井 浩治 梶山 悟朗 井上 正規
- 出版者
- The Japanese Society of Internal Medicine
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.85, no.7, pp.1150-1153, 1996-07-10
- 被引用文献数
- 4 2
症例は34歳,女性.主訴は上腹部不快感.胸腹水貯留,低アルブミン血症を認め, α<sub>1</sub>-アンチトリプシンクリアランステスト, <sup>99m</sup>Tcアルブミンシンチにより蛋白漏出性胃腸症と診断した。また,抗核抗体陽性,浸出性胸腹水,関節炎,汎血球減少を伴い,活動性の全身性エリテマトーデス(SLE)の併存を認めた.ステロイドパルス療法により血清アルブミン値の上昇,蛋白漏出の改善を認め,本症例はSLEを基礎疾患とし蛋白漏出性胃腸症を呈したものと考えられた.
1 0 0 0 バス車内における高速無線伝搬特性(研究速報)
- 著者
- 中畑 洋一朗 梶原 昭博
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会論文誌. B, 通信 (ISSN:13444697)
- 巻号頁・発行日
- vol.92, no.10, pp.1716-1720, 2009-10-01
- 被引用文献数
- 1
バスや自動車の車内での高速インターネット接続や動画配信など乗客の快適性や利便性向上のために近距離高速大容量無線伝送が注目されている.しかしながら車内は金属板とガラス窓から構成された閉空間であり,また直接波が座席や乗客により遮断されるため100Mbit/s以上の高速広帯域伝送を実現することは難しいと考えられる.そこで本研究では長距離バス車内での超広帯域インパルス無線を想定し,遅延特性や伝搬損などについて実験を行った.その結果,遅延スプレッドは6〜16nsでバスの車内後方ほど小さく,また乗客によるシャドーイングによって直接波電力は4〜7dB減衰することを確認している.
- 著者
- 清水 渉 唐川 真二 永田 健二 向井 順子 本藤 達也 渡辺 光政 重本 英司 山形 東吾 土岡 由紀子 松浦 秀夫 梶山 梧朗
- 出版者
- The Japanese Society of Electrocardiology
- 雑誌
- 心電図 (ISSN:02851660)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.4, pp.455-461, 1992
A型顕性WPW症候群に合併したリエントリー性心房頻拍 (AT) で, 頻拍中および頻拍時に行った右房ペーシング中にdouble potential (DP) が記録された症例を経験した, 症例は頻拍発作を主訴とした42歳女性で, 電気生理学的検査により洞調律時とほぼ同じQRS波形の頻拍はAT (CL 490mseG) によるものと診断した.洞調律時の心房マッピングでは, 高位右房側壁 (HRAlat) で心房波の持続時間の延長を認めた.ATはHRAlatからの早期刺激法で誘発, 停止が可能であり, 早期刺激間隔とAT誘発時のエコー間隔との関係は逆相関であった.AT中の心房マツピングでは, 高中位右房側壁の興奮が最早期で, 中位右房側壁にDPを認めた.DPはAT時にHFAlatから行ったペーシング中 (entrainment, CL 470, 450msec) にも記録されたが, 洞調律時および洞調律時の心房ペーシング中には記録されず, 機能性のDPと考えられた.
1 0 0 0 OA 臨床実習学生に質問行動の増加を促したことが能動的な行動変容へ与えた影響について
- 著者
- 由谷 仁 梶原 秀明 宮原 正文 中根 博
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.38 Suppl. No.2 (第46回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.GaOI2055, 2011 (Released:2011-05-26)
【目的】 情意領域の低下、特に「自発性のなさ」が問題となる臨床実習学生(以下、学生とする)の指導は、臨床実習指導者(以下、指導者とする)の心的負担を著しく増加させる。そこで、臨床実習を円滑に遂行するため、指導者にとって負担の少ない指導方法を確立させることは急務であるが、現状は各病院や各指導者の裁量次第で明確な方法は示されていない。当院では臨床実習の位置付けとして、平成21年より「受動的教育」から「能動的教育」へ行動変容させることを最重要課題とし、続いて国家試験の知識を習得することを目的として掲げている。辻下は、行動分析学的アプローチは有効な行動変容法であると述べており、学生に行動変容を促しつつ指導者に負担の少ない指導方法を模索してきた。 今回は、情意領域に問題があると指摘された学生に対し、行動分析学的アプローチを用いた「質問行動の増加」という介入を行い、その効果をシングルケースデザインにより検討し報告する。【方法】 対象は当院での臨床実習にて情意領域の低下が指摘された理学療法士学科最終学年、30代、男性、1名。方法は畑山らの報告を参考にし、実習期間をベースライン期(2週間)、介入期(4週間)、非介入期(2週間)に分け、まずベースライン期終了時にターゲット行動の明確化を図るため中間評価を行った。その際、特に低下がみられ問題とした「自発性のなさ」に対し、「質問行動の増加」をターゲット行動と設定した。 介入期は「質問行動の増加」のため、学生に自ら質問を行い、その内容を質問行動記録表に記載するよう指導した。また、質問のルールとして自分の考えを可能な限り述べることとした。先行刺激は、質問数に応じて臨床実習総合評価の情意領域に関して15回/週以上で「可」、30回/週以上で「良」にすること、質問に関して否定的なコメントはしないこと、必要以上に課題を出さないことを約束した。後続刺激は、質問行動が見られた直後に指導者側から賞賛することを徹底し、週末に学生と1週間分の質問内容を確認した。 非介入期では質問行動記録表への記載は継続させたが、後続刺激は与えなかった。調査内容は質問行動数(自分の考えを述べた質問数/全体の質問数)、臨床実習評価(当院独自、各項目4点満点で良好4点、普通3点、やや劣る2点、劣る1点)とした。なおベースライン期の質問行動数はデイリーノートより作成した。加えて最終週は3日間のみのデータ収集となった。【説明と同意】 学生には本報告の主旨、本データを報告以外に使用しないこと、未同意でも不利益を受けないことなどを実習終了時に説明し、紙面にて同意を得た。【結果】 1週間の平均質問行動数はベースライン期で0/0.5(0%)回、介入期で16.3/32.3(50.4%)回、非介入期で16.3/31.3(52.0%)回であり、介入期で増えた回数を非介入期でも維持できた。臨床実習評価による全領域の平均は、2週後2.6点、4週後2.4点、6週後2.5点、最終2.5点と若干の変化であった。そのうち、情意領域だけの平均は、2週後2.5点、4週後2.6点、6週後2.7点、最終2.8点と改善傾向はみられたが大幅な変化ではなかった。【考察】 ベースライン期ではほとんどなかった質問行動自体は、介入期より増加し非介入期でも継続してみられたため、質問行動自体の定着は図れたと考えられる。しかし、臨床実習評価の平均点数に大幅な変化がなかったことを考慮すると、当院で目的とした能動的な行動変容までは至らなかったと考えられる。これは質問行動数の結果より、先行刺激で与えた30回/週以上で「良」との質問数を若干超えた値が多く、質問行動数自体が目的となっていたためと考えた。臨床実習教育の手引き-第5版-によれば内発的動機づけには知的好奇心が必要で、その知的好奇心は環境に変化を起こせたという有能感あるいは達成感が動機づけに重要となると述べられている。今回、知的好奇心を促せなかったことが、能動的な行動変容まで至らなかった原因ではないかと思われた。今後は、知的好奇心を促すために、人の役に立つという視点で指導方法を模索し、能動的な行動変容を促す方法の確立に取り組んでゆきたい。【理学療法学研究としての意義】 臨床実習教育において自発性のなさが問題となる学生に対し、受動的から能動的への行動変容を起こさせる簡便かつ、有効な指導方法が確立出来れば大変有意義なことである。
- 著者
- 蒔野 充裕 梶山 朋子 大内 紀知
- 出版者
- FIT(電子情報通信学会・情報処理学会)運営委員会
- 雑誌
- 情報科学技術フォーラム講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.3, pp.623-624, 2013-08-20