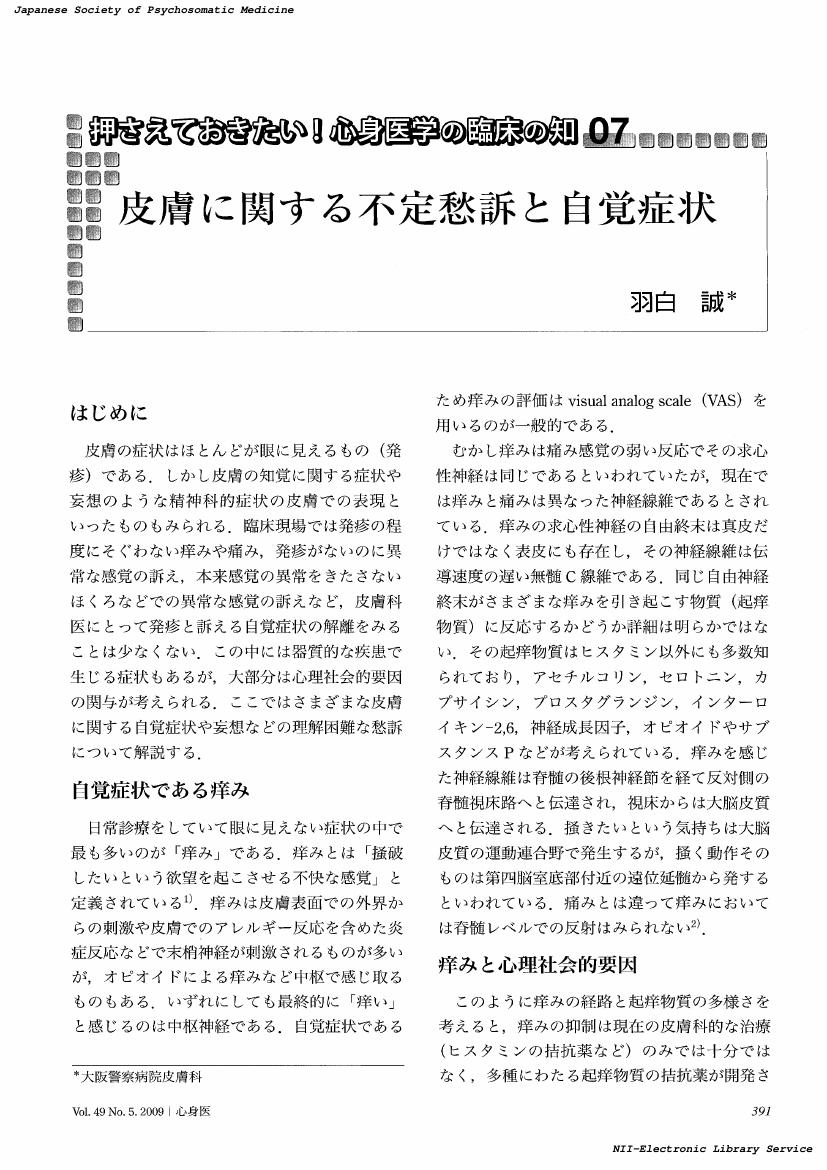2 0 0 0 OA キウイフルーツ及び近縁種の染色体数
- 著者
- 渡辺 慶一 高橋 文次郎 白戸 一士
- 出版者
- 園芸学会
- 雑誌
- 園芸学会雑誌 (ISSN:00137626)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.4, pp.835-840, 1990 (Released:2007-07-05)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 9 26
キウイフルーツ (A. deliciosa) の雄性品種‘マチュア’, 雌性品種‘アボット’, ‘ブルーノ’及びマタタビ(A. polygama), サルナシ(A. arguta) を用いて体細胞染色体, 減数分裂について観察調査を行った. キウイフルーツの3品種の体細胞染色体数は2n=174であり, マタタビの2種では2n=58, サルナシの4種では2n=58, 2n=116, 2n=ca. 174と算定された.これらの染色体数から, Actinidia においてはx=29が基本数であることが認められた.サルナシにおいては, 2仁を有する2n=58, 4仁を有する2n=116と仁数は不明確であったが2n=ca. 174の2x, 4x, 6xの倍数関係が示された. 本報のマタタビは2n=58の2倍性であったが, これまでに報告された2n=116の存在を考えると両者の間には, 2xと4xの同質倍数性関係があるのかもしれない. 本研究の2n=174のキウイフルーツの3品種‘マチュア’, ‘アボット’, 及び‘ブルーノ’は体細胞核に6仁または小胞子核で3仁を有し, いずれも基本数x=29の6倍性を示している.
2 0 0 0 OA 生徒の頭髪と生徒指導に関する一考察
- 著者
- 白石 淳
- 出版者
- 浅井学園北方圏生活福祉研究所
- 雑誌
- 北方圏生活福祉研究所年報 = Bulletin of Northern Regions Research Center for Human Service Studies (ISSN:1342761X)
- 巻号頁・発行日
- no.2, pp.23-29, 1996
今日,中学生,高校生が頭髪を茶色に染める,ピアスをつけることの是非が問われている。学校でこれらのことは,校則により禁止されているところが多い。しかしながら,頭髪の問題は学校生活ばかりではなく家庭生活上のことも考慮されなければならない。頭髪の問題については,憲法にもかかわる問題でもあり基本的人権から考えると子どもとその親の意思が尊重されなければならず,基本的には自己決定権にゆだねられるべき問題であると結論づけた。さらに,これらの問題については,憲法とのかかわりがあるとの認識が低く,意識の改革が必要であると指摘した。
2 0 0 0 OA 福島の原子力事故の経験から 『牛ふんの汚染を例に基準値の課題を考える』
- 著者
- 白井 真
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.12, pp.758-759, 2015 (Released:2020-02-19)
2 0 0 0 OA 今金・インマヌエル移住団体におけるキリスト教的開拓者精神
- 著者
- 白井 暢明
- 出版者
- 日本基督教学会北海道支部/北海道基督学会 = The Hokkaido Society of Christian Studies
- 雑誌
- 基督教学 (ISSN:02871580)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.1-25, 2004-06-25
2 0 0 0 OA 地域づくり型ミニ独立国のいま―4つの事例から―
- 著者
- 白石 太良
2 0 0 0 IR モナルコマキと統治契約(資料) (故木下広居教授追悼号)
- 著者
- 白石 正樹
- 出版者
- 創価大学法学会
- 雑誌
- 創価法学 (ISSN:03883019)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.3, pp.p95-111, 1982-03
- 著者
- 白石 裕子 舟越 和代 中添 和代
- 出版者
- 一般社団法人 日本看護研究学会
- 雑誌
- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.5, pp.5_47-5_58, 2002
3歳児を持つ母親51名を対象に虐待傾向の項目を含んだ育児意識調査と,P-Fスタディを用いて欲求不満場面の言語的特徴から母親の虐待傾向とその関連要因を検討した。 虐待傾向と母親役割否定意識には正の相関が,サポート意識とは負の相関があった。 虐待傾向高群・低群間では,P-Fスタディに見る言語的特徴に有意な差異はなかった。 しかし,母親役割否定意識が高い母親に,欲求不満の原因を他人や環境のせいにし,素朴な攻撃性を示す傾向があった。 母親役割否定意識が低い母親は欲求不満解消のために自己反省から問題の解決に向かう傾向があった。 また,サポート意識が高い母親は,不満場面においてストレスを解消するために素直な言動を示し,自我を強調する傾向があることが示唆された。 本研究では,質問紙と投影法を併用する事により,質問紙調査のみでは測定できなかった無意識の不満や自己欺瞞などの傾向が見出された。
2 0 0 0 IR 地域における近代日本の「戦没者慰霊」行事--招魂祭と戦死者葬儀の比較研究
- 著者
- 白川 哲夫
- 出版者
- 史学研究会 (京都大学文学部内)
- 雑誌
- 史林 (ISSN:03869369)
- 巻号頁・発行日
- vol.87, no.6, pp.812-842, 2004-11
「戦没者慰霊」の研究は近年急速な進展を見せているが、時期的変遷や、事例間の関連性が十分に整理されていないと思われる。本稿では、地域の招魂祭と戦死者葬儀の実態を論じ、それぞれの行事がどのような役割を近代日本社会の中で担っていたのかについて考察した。戦死者を集団として祭祀する招魂祭と、個人として弔う戦死者葬儀は、それぞれが平時と戦時の「戦没者慰霊」を担った。いずれも地域が一体となった行事であり、時代が下るにつれその公的性の度合いは強まった。また二つの行事は神道と仏教の果たす役割の違いを反映しており、前者は主として死者への顕彰と称賛、後者は死者への哀悼と弔いを受け持っていた。その役割は互いに自覚的に選び取ったものではなく、互いの領域を奪い合おうとする紛争が通時代的に起こり続けていたのである。
2 0 0 0 OA 植物増生病を引き起こすタフリナ属菌のインドール酢酸生合成
- 著者
- 山田 哲治 塚本 浩史 白石 友紀 野村 哲也 奥 八郎
- 出版者
- The Phytopathological Society of Japan
- 雑誌
- 日本植物病理学会報 (ISSN:00319473)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.4, pp.532-540, 1990-10-25 (Released:2009-02-19)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 17 22
サクラてんぐ巣病菌(Taphrina wiesneri),モモ縮葉病菌(Taphrina deformans),スモモふくろみ病菌(Taphrina pruni)など,植物に増生病を引き起こすタフリナ属病原糸状菌はインドールピルビン酸(IPyA),インドールアセトアルデヒド(IAAld)を中間代謝物としてトリプトファン(Trp)からインドール酢酸(IAA)を合成する。これらの糸状菌はまた,インドールアセトニトリル(IAN)をIAAに転換する能力をもつ。IANをIAAに転換する酵素,IANニトリレースは基質誘導を受ける適応酵素であるが,TrpをIPyAに転換する酵素,Trpアミノトランスフェラーゼは基質によって誘導を受けない。
2 0 0 0 戦後初期における旧軍関係教育機関出身者への施策
- 著者
- 白岩 伸也
- 出版者
- 教育史学会
- 雑誌
- 日本の教育史学 (ISSN:03868982)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, pp.45-57, 2017
<p>After the Potsdam Declaration, the Japanese government had to decide on the treatment of former military educational institution graduates (hereinafter referred to graduates), while attempting to transform the country's self-image from "Imperial Japan" to "Democratic Japan". The Ministry of Education tried to transfer many graduates to other schools. However, various discussions over the measure developed. This paper clarifies the formation of the measures for graduates in early postwar Japan by focusing on the trend of "demilitarization" and "democratization" and its scope.</p><p>In August 1945, the Ministry of Army and Navy began to negotiate with the Ministry of Education to transfer graduates to other schools. As a result, the Cabinet decided upon "preferential transfers" for graduates. However, when students started to criticize and CIE (Civil Information and Education Section) started to intervene, preferential transfers were abolished in November. "Restrictive transfers" that limited the number of graduates to ten percent of a school's capacity was determined in February 1946. Nevertheless, opinions criticizing restrictive transfers or insisting upon the necessity of re-education appeared. In addition, the discrepancy between the text of the Constitution of Japan and the Fundamental Law of Education and the measures was pointed out.</p><p>As described above, the measures were formed through "consultation" and "crossbreeding" with the Ministry of Army and Navy, the Ministry of Education, and CIE. The scope of "demilitarization" was interpreted differently by each organization, so that "demilitarization" and "democratization" developed a relationship of mutual conflict and reliance. It may be considered that the achievement of "demilitarization" and "democratization" was hindered, thus affecting later historical developments.</p>
2 0 0 0 IR イタリア中世宗教史研究の基本的枠組 : 宗教運動論の成果と課題
- 著者
- 白川 太郎
- 出版者
- 早稲田大学大学院文学研究科
- 雑誌
- 早稲田大学大学院文学研究科紀要 (ISSN:24327344)
- 巻号頁・発行日
- no.65, pp.499-513, 2020-03-15
2 0 0 0 OA 心肺蘇生術のスキル保持に必要な学習頻度と関係因子の検討
- 著者
- 中木村 和彦 佐伯 仁 佐伯 真理子 白澤 由美子 中野 智子
- 出版者
- 日本蘇生学会
- 雑誌
- 蘇生 (ISSN:02884348)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.1, pp.1-6, 2021-04-26 (Released:2021-05-10)
- 参考文献数
- 10
36名を,4,6,12ヶ月の3群に分け,一次救命処置(BLS)講習受講後,傷病者の虚脱発見から心肺蘇生とAEDによるショックまでの時間(BLS時間)と50回連続の胸骨圧迫の質の適切性を調べた。初回講習後,4,6ヶ月群は,それぞれ4,6ヶ月間隔で,スキル保持の評価と簡単な講習を行い,12ヶ月後に全群スキル保持の程度を調べた。 12ヶ月後の胸骨圧迫の質に群間差はなかったが,BLS時間は,12ヶ月群が他の2群よりも有意に長かった。4ヶ月群ではBLS時間に有意な経時変化を認めなかったが,6と12ヶ月群のBLS時間は1年後有意に延長した。 BLSのスキル保持には4ヶ月ごとに講習を受ける必要がある。キーワード:心肺蘇生術,一次救命処置,反復講習,スキル保持,胸骨圧迫
2 0 0 0 ウォッカの大量飲酒により腐食性食道狭窄を生じた1例
- 著者
- 津福 達二 田中 寿明 末吉 晋 田中 優一 森 直樹 藤田 博正 白水 和雄
- 出版者
- The Japanese Society of Gastroenterological Surgery
- 雑誌
- 日本消化器外科学会雑誌 (ISSN:03869768)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.10, pp.1661-1665, 2007
- 被引用文献数
- 1
症例は39歳の男性で, 2004年1月, うつ病があり自殺企図にてウォッカを大量に飲用し, 高度の胸焼け, 嚥下障害を生じたため当院へ紹介となった. 食道潰瘍および食道狭窄を認め, 腐食性食道炎と診断した. 希死念慮が強かったため精神科に入院となり, 精神面の治療を行った. 2月, 狭窄症状が強くなったため, 空腸瘻を造設し, 全身状態の改善および精神状態の安定を待って, 7月, 非開胸食道抜去術, 胸骨後食道胃吻合術を行った. 経口摂取可能となり術後32日目に退院した. 高濃度のアルコール(ウォッカ)飲用による腐食性食道狭窄を経験したので報告する.
2 0 0 0 OA 救荒書の思想史的研究
- 著者
- 白杉 悦雄
- 出版者
- 京都大学 (Kyoto University)
- 巻号頁・発行日
- 1997-03-24
新制・課程博士
2 0 0 0 IR 救荒書の思想史的研究
2 0 0 0 OA 先天性難聴児への対応 —本邦での課題克服へ向けて—
2 0 0 0 OA 6.医療資源配分とQALYに関する倫理的側面からの考察
2 0 0 0 OA 皮膚に関する不定愁訴と自覚症状(押さえておきたい!心身医学の臨床の知07)
- 著者
- 羽白 誠
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.5, pp.391-395, 2009-05-01 (Released:2017-08-01)
- 参考文献数
- 7