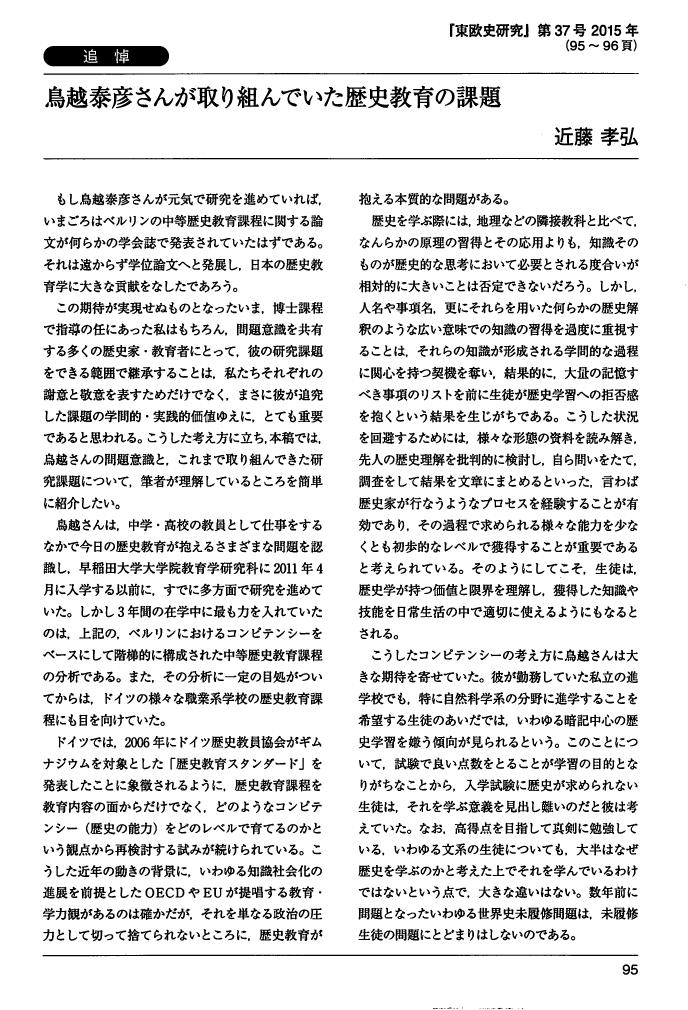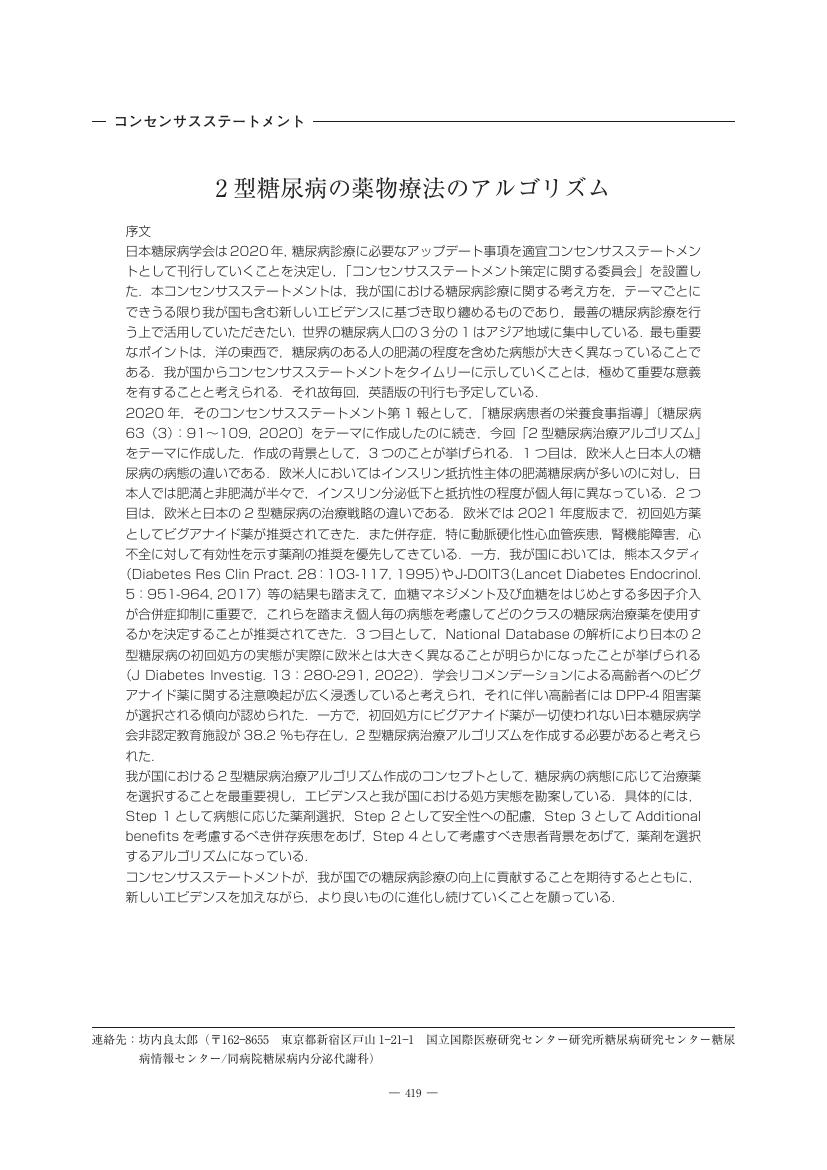- 著者
- 林元 みづき 庭田 祐一郎 伊藤 哲史 植木 進 内田 雄吾 関 洋平 西川 智章 岸本 早江子 神山 和彦 高杉 和弘 近藤 充弘
- 出版者
- 科学技術社会論学会
- 雑誌
- 科学技術社会論研究 (ISSN:13475843)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.119-127, 2020-04-30 (Released:2021-04-30)
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 1
Patient Centricityとは「患者中心」を意味する概念であり,患者・市民参画(Patient and Public Involvement:PPI),Patient Involvement,Patient Engagementといった言葉と同義語である.近年,製薬企業が患者の意見や要望を直接入手し,患者の実体験を医薬品開発に活かすことの重要性が認識されつつあり,製薬企業での医薬品開発におけるPatient Centricityに基づく活動(本活動)が開始されている.本活動により,患者には「より参加しやすい治験が計画される」,「自分の意見が活かされた医薬品が開発される可能性がある」といったことが期待される.また,製薬企業には医薬品開発に新たな視点と価値が加わり,「より価値の高い医薬品の開発につながること」が期待される.本稿では,日本の製薬企業で実施されている本活動の事例の一部を紹介する.今後,日本の各製薬企業が本活動を推進することに期待したい.
1 0 0 0 OA 会計システムと信頼性 ルーマン理論を視座として
- 著者
- 近藤 汐美
- 出版者
- 経済社会学会
- 雑誌
- 経済社会学会年報 (ISSN:09183116)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.92-100, 2017 (Released:2021-04-01)
In response to the globalization of business circumstances, expansion of corporate information is an urgent issue in the international accounting area. In 2013, The International Integrated Reporting Council (IIRC) proposed an integrated reporting framework, which includes the various elements such as strategy, business model, value creation and corporate governance. In this report, stakeholder relationships is also one of the most critical information. It is advocated that the report should provide insight into the nature and quality of the organization's relationships with its key stakeholders, including how and to what extent the organization understands, takes into account and responds to their legitimate needs and interests. In this study, in order to understand the accounting issue, we attempt to propose a new view and perception from the other interdisciplinary viewpoint. We apply the Luhmann's theory of social systems to this study. In particular, we would like to discuss two aspects; first, we attempt to recognize the accounting system as one of the “systems” and describe its special quality; second, we analyze the problem on IIRC's integrated reporting from the viewpoint of stakeholder relationships.
1 0 0 0 OA アクシデントとインフラストラクチャー
- 著者
- 近藤 和都
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.106, pp.8-17, 2021-07-25 (Released:2021-08-25)
- 参考文献数
- 19
1 0 0 0 OA 兄たちの東西 美濃における在原行平とオオウスノミコト
- 著者
- 近藤 さやか
- 出版者
- 古代文学研究会
- 雑誌
- 古代文学研究 第二次 (ISSN:24361062)
- 巻号頁・発行日
- vol.2021, no.30, pp.3001, 2021 (Released:2021-11-13)
- 著者
- 近藤 宏
- 出版者
- 現代文化人類学会
- 雑誌
- 文化人類学研究 (ISSN:1346132X)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, pp.54-79, 2021 (Released:2022-01-29)
- 参考文献数
- 32
本稿では、「存在論的転回」の「真剣に受け取ること」という知的な態度に倣い、「『自然』を/に抗して書くwriting (against) nature」という課題を、パナマに暮らす先住民エンベラの人びとによる「自然を書く」取り組みから考える。具体的には、溺死という出来事をめぐる叙述である。それは文字を使用しない語りによる叙述で、正確には書くことではないかもしれないが、ここでは先住民の考え方を引き受けることを優先させるため、「自然を書く」ことを「自然を叙述する」こととして緩く捉え、人類学者にとっての問いに対応する先住民的な考えを検討する。 その溺死の出来事の叙述は、被害者の身体の様相を詳しく伝えることで、水流の不可解な力に曝された被動作主としての性格を際立たせる。一見すると空白のままとなる溺死を引き起こした力は、不可視の身体を持つ精霊の行為主体性として受け止められている。不幸な出来事の原因を精霊に帰するような語りを、「驚くべき事実Cが観察される、しかしもしHが真であれば、Cは当然の事柄であろう、よって、Hが真であると考えるべき理由がある」[米盛 2007: 54]という形式を取るアブダクションと受け止める。「推論的仮説内容H=精霊が食べた」ことが、溺死の原因としてなぜふさわしいのかを、その仮説内容のかたちづくる際にはたらく「創造的想像力による推測の飛躍」を分析し、検討することから、自然の諸力(水流の力)を自然の要素(ナマケモノという動物)によって叙述するという、自然の叙述の様式が浮かび上がる。 こうした自然の叙述の様式に組み込まれている動物の名前の使用や、動物のイメージを別の自然現象に投影する民族誌的事象の分析や、別の先住民グループの民族誌的記述を手掛かりにしながら、エンベラによる自然の叙述の様式を考察すると、別の「イメージ平面」となる、自然の様態がそこには垣間見える。エンベラによる「自然の叙述」は、自然の事物のイメージが、別の自然の諸力のイメージとして照り返される独特な「イメージ平面」を含みこむ自然の様態が浮かび上がる。
1 0 0 0 OA 電位依存性カリウムチャネルKv1.2の変異体における不活性化の分子機構の解析
- 著者
- 近藤 寛子 吉田 紀生 城田 松之
- 出版者
- 分子シミュレーション学会
- 雑誌
- アンサンブル (ISSN:18846750)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.4, pp.283-289, 2019-10-31 (Released:2020-10-31)
- 参考文献数
- 21
電位依存性カリウムチャネルは細胞膜の脱分極により活性化されカリウムイオンを選択的に透過する.C型不活性化はチャネルの不活性化機構の1種であり,脱分極状態が続くことにより引き起こされるが,その分子機構はわかっていない.そこで,脱分極直後にC型不活性化が起こるためにイオン透過が殆ど見られないKv1.2のW366F変異体を対象とし,分子動力学(MD)シミュレーションにより電場中での動態を解析した.本稿では,MDシミュレーションおよび3D-RISM理論による解析結果から電位依存的な不活性化の機構を考察する.
1 0 0 0 OA 史学会公開シンポジウム「天皇像の歴史を考える」コメント
- 著者
- 近藤 和彦
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.129, no.10, pp.76-84, 2020 (Released:2021-12-01)
天皇像の歴史を君主(monarch)の歴史の共通性において、また特異性において理解したい。ちなみに西洋史で、両大戦間の諸学問をふまえて君主制の研究が進展したのは1970年代からである。2つの面からコメントする。 A 広く君主制(monarchy)の正当性の要件を考えると、①凱旋将軍、紛議を裁く立法者、神を仲立ちする預言者・司祭といったカリスマ、②そうしたカリスマの継承・相続、③神意を証す聖職者集団による塗油・戴冠の式にある。このうち②の実際は、有力者の推挙・合意によるか(→ 選挙君主)、血統によるか(→ 世襲君主)の両極の中間にあるのが普通である。イギリス近現代史においても1688~89年の名誉革命戦争、1936年エドワード8世の王位継承危機のいずれにおいても、血統原則に選挙(群臣の選み)が接ぎ木された。天皇の継承史にも抗争や廃位があったが、万世一系というフィクションに男子の継体という male chauvinism が加わったのは近代の造作である。 B 近世・近代日本の主権者が欧語でどう表現されたかも大きな問題である。1613年、イギリス国王ジェイムズが the high and mightie Monarch, the Emperour of Japan に宛てた親書を、日本側では将軍(大御所)が処理し、ときの公式外交作法により「源家康」名で返書した。幕末維新期にはミカド、大君などの欧語訳には混迷があり、明治初期の模索と折衝をへて、ようやく1873~75年に外交文書における主権者名が「天皇」、His Majesty the Emperor of Japan と定まった。NED(のちのOED)をふくむすべての影響力ある辞書はこの明治政府の定訳に従順である。じつは emperor / imperator は主権者にふさわしい名称かもしれないが、そもそも血統という含意はないので、万世一系をとなえる天皇の訳語としては違和感がぬぐえない。とはいえ、世界的に19世紀は多数の「皇帝」が造作された権威主義の時代でもあった。
1 0 0 0 OA 鳥越泰彦さんが取り組んでいた歴史教育の課題
- 著者
- 近藤 孝弘
- 出版者
- 東欧史研究会
- 雑誌
- 東欧史研究 (ISSN:03866904)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, pp.95-96, 2015 (Released:2020-01-16)
1 0 0 0 OA 2001年度シンポジウム 歴史教育の中の「東欧」
1 0 0 0 OA サライェヴォ事件の背景に関する一考察 ―「青年ボスニア」、「民族防衛団」と「黒手組」―
- 著者
- 近藤 信市
- 出版者
- 東欧史研究会
- 雑誌
- 東欧史研究 (ISSN:03866904)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.26-54, 1987 (Released:2017-09-28)
1 0 0 0 OA 日本語「迷惑」と中国語「麻 」の意味・用法の対照的考察
- 著者
- 近藤 明 邢 叶青
- 出版者
- 金沢大学教育学部
- 雑誌
- 金沢大学教育学部紀要人文科学社会科学編 (ISSN:02882531)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, pp.31-40, 2008-02-29
1 0 0 0 OA 科学衛星「はるか」のアンテナ展開実験
- 著者
- 廣澤 春任 名取 通弘 紀伊 恒男 高野 忠 橋本 樹明 大西 晃 井上 浩三郎 村田 泰宏 三好 一雄 井上 登志夫 野田 隆彦 栗林 豊 田嶋 隆範 近藤 久美子 佐々木 崇志 箭内 英雄 萩野 慎二 小倉 直人 岡本 章 杉山 祥太郎 HIROSAWA Haruto NATORI Michihiro KII Tsuneo TAKANO Tadashi HASHIMOTO Tatsuaki OHNISHI Akira INOUE Kouzaburo MURATA Yasuhiro MIYOSHI Kazuo INOUE Toshio NODA Takahiko KURIBAYASHI Yutaka TAJIMA Takanori KONDOH Kumiko SASAKI Takashi YANAI Hideo HAGINO Shinji OGURA Naoto OKAMOTO Akira SUGIYAMA Shohtaro 中川 栄治 NAKAGAWA Eiji
- 出版者
- 宇宙科学研究所
- 雑誌
- 宇宙科学研究所報告 (ISSN:02852853)
- 巻号頁・発行日
- vol.101, pp.1-27, 1998-06
科学衛星「はるか」は, スポース VLBI に必要な工学諸技術の実験ならびにスペース VLBI による電波天文観測を行うことを目的として, 1997年2月12日, 宇宙科学研究所の新型ロケット M-V の初号機により打ち上げられた。「はるか」では数々の工学的課題への取り組みがなされたが, それらの中で, ケーブルとメッシュからなる, 有効開口径8cmのパラボラアンテナの軌道上での展開が, 最大の工学的課題であった。打ち上げ約2週間後の2月24日から28日にかけてアンテナ展開実験を行い, 展開に成功した。本稿は「はるか」のアンテナ展開実験を, 衛星システム全体としてのオペレーションの観点から詳述するものである。
- 著者
- 近藤 祉秋
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 文化人類学 (ISSN:13490648)
- 巻号頁・発行日
- vol.86, no.1, pp.096-114, 2021-06-30 (Released:2021-09-23)
- 参考文献数
- 63
本稿では、渡り損ねた夏鳥の「残り鳥」や遡上するサケをめぐるディチナニクの実践について報告し、彼らが他種との間に築く「刹那的な絡まりあい」について論じる。北方アサバスカン民族誌学の先行研究では、「人間と動物」の二者関係が記述の枠組みとなってきたが、本稿では「人間-動物-ドムス」の三者関係から考察することを試みる。「刹那的な絡まりあい」は、ディチナニクが他種の生存に対する配慮を怠らない一方で、その関係性が束縛と支配に変わることを未然に防止しようとするせめぎ合いの中で生じるあり方である。ハラウェイは、人間と他種の「絡まりあい」を論じる際に、「自然と絡まりあう先住民」のイメージを前提として、「自然から独立する白人男性=人間」観を批判した。本稿の結論はハラウェイの前提には再検討の余地があることを示している。マルチスピーシーズ民族誌は人間と他種の絡まりあいに関する微細な記述を通して、生態学や生物学の視点からは扱われてこなかった側面を描くことができる。マルチスピーシーズ民族誌家は、人類学者独自の視点を通して、生態学者や生物学者の「人新世」論とより積極的な対話を図るべきである。本稿では、マルチスピーシーズ民族誌がとりうるそのような方向性の一例として、北米の生態学者によって提起された人新世論である「ハイパーキーストーン種」について民族誌事例を通じて検討する。
1 0 0 0 OA 会員の声へのお答え
1 0 0 0 OA 翻刻「琵琶秘曲泣幽霊」 -富山大学蔵本『臥遊奇談』より、ハーン「耳なし芳一」原話-
- 著者
- 近藤 清兄
- 出版者
- 聖霊女子短期大学
- 雑誌
- 聖霊女子短期大学 紀要 (ISSN:0286844X)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, pp.49-55, 2020 (Released:2020-12-01)
1 0 0 0 2型糖尿病の薬物療法のアルゴリズム
1 0 0 0 地域とつくる「どこでもドア」型ハイブリッド・ケアネットワーク
- 著者
- 近藤 尚己
- 出版者
- 京都大学
- 雑誌
- 戦略的な研究開発の推進 戦略的創造研究推進事業 RISTEX(社会技術研究開発)
- 巻号頁・発行日
- 2021
長引くコロナ禍が子どもや若者、女性へ及ぼす影響のメカニズムは十分明らかになっておらず、支援ニーズの増加と支援者間の情報共有や連携の困難により相談支援の現場負荷が高まっている。支援対象者の特徴の把握や支援プラン策定は、支援者の経験とスキルに大部分が委ねられており、経験の浅い支援者などへの支援と地域ぐるみの支え合いを可能にする環境整備が急務となっている。 本プロジェクトでは、①3万人の縦断インターネット調査データを活用して、コロナ禍が子どもや若者、女性に及ぼす社会的孤立・孤独や健康・生活への影響を分析する。②分析で得た知見を踏まえ、これまでに開発してきた支援者の支援データシステムの「子ども・若者・女性版」をつくる。③別途開発してきた「住民主体の共生型地域づくり普及支援ガイド」および「地域住民を含む顔が見える社会資源マップ」などのツールをアップデートして、同システムに接続する。このシステムには対象者のタイプ(ペルソナ像)情報や支援記録の分析に基づく優れた支援者のナレッジを盛り込む。支援対象者のタイプとタイプ別の効果的な支援プランを提示し、これを現場とオンラインの両面(ハイブリッド)のネットワーク上で運用する。地域の人々の誰もが支援の入口(ドア)となり、どこから入ってもケアの輪に包摂され、互いに支え・学び合い、豊かなケアが継続する「どこでもドア型」のケアネットワークを構築する。
1 0 0 0 Gタンパク質共役型受容体を標的としたコバレント創薬
- 著者
- 近藤 萌 西山 和宏 西村 明幸 加藤 百合 西田 基宏
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.157, no.5, pp.356-360, 2022 (Released:2022-09-01)
- 参考文献数
- 14
Gタンパク質共役型受容体(GPCRs)は,細胞内環境の変化(物理化学的刺激)を細胞内情報に変換し,伝達する上で極めて重要な役割を果たしている.リガンド刺激後,多くのGPCRはリン酸化され,β-アレスチン依存性の内在化によって再利用または分解される.このプロセスは,GPCRタンパク質の品質管理を維持するための重要な機構である.一方で,β-アレスチン感受性の低いGPCRがどのように品質管理されるかは不明であった.我々は,β-アレスチン低感受性のプリン作動性P2Y6受容体(P2Y6R)に着目し,リン酸化に依存しないGPCR内在化経路(Redox-dependent Alternative Internalization:REDAI)の存在を新たに見出した.P2Y6Rはマクロファージに高発現しており,大腸炎の発症・進展に深くかかわっている.我々は,食品中に含まれる親電子物質がP2Y6RのREDAIを誘導し,抗炎症効果をもたらす一方で,REDAIの抑制が大腸炎の悪化をもたらすことをマウスで実証した.これらの結果は,GPCRのREDAIを標的にする創薬が,炎症性疾患の画期的な治療戦略となることを強く示唆している.
1 0 0 0 OA 1200年の思いを今に : がんばろう日本
- 著者
- 近藤本淳
- 出版者
- 和歌山社会経済研究所
- 雑誌
- 21世紀Wakayama
- 巻号頁・発行日
- no.66, 2011-07-25