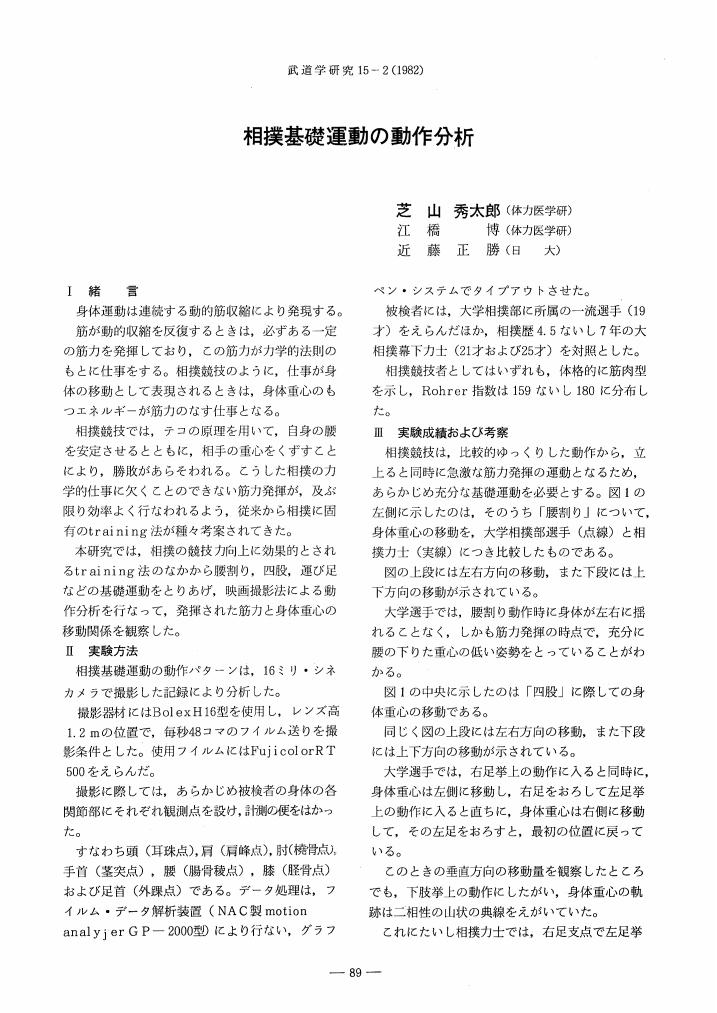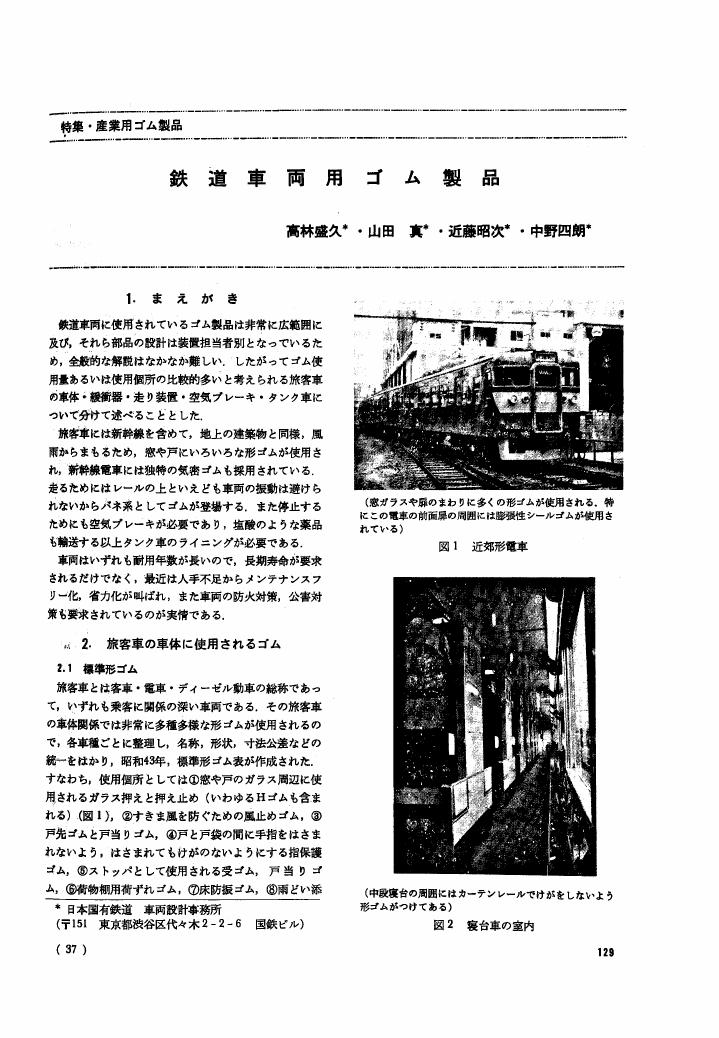1 0 0 0 OA 列状間伐が森林環境に与える影響(<特集>列状間伐)
1 0 0 0 OA ジスチグミン臭化物による低コリンエステラーゼ血症を来たした下顎歯肉癌患者の1例
- 著者
- 鎌谷 宇明 池田 幸 朽名 智彦 飯島 毅彦 吉濱 泰斗 近藤 誠二 代田 達夫 新谷 悟
- 出版者
- 日本歯科薬物療法学会
- 雑誌
- 歯科薬物療法 (ISSN:02881012)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.3, pp.96-100, 2012-12-01 (Released:2013-02-25)
- 参考文献数
- 9
Distigmine bromide is an anticholinesterase used to treat urinary retention. We describe a case of decreased serum cholinesterase caused by a usual oral dose of distigmine bromide for urinary retention. An 84-year-old man, who had been received chemotherapy for carcinoma of the lower gingiva, suddenly decreased serum cholinesterase to 21 IU/L in 7 days of administration of distigmine bromide 5mg without clinical symptoms. Serum cholinesterase improved after stopping the administration of distigmine bromide. This case shows that oral surgeons should be aware of the possibility of decreased serum cholinesterase in patients taking distigmine bromide.
1 0 0 0 OA 相撲基礎運動の動作分析
1 0 0 0 OA 鉄道車両用ゴム製品
- 著者
- 高林 盛久 山田 真 近藤 昭次 中野 四朗
- 出版者
- 一般社団法人 日本ゴム協会
- 雑誌
- 日本ゴム協会誌 (ISSN:0029022X)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.3, pp.129-137, 1975 (Released:2008-04-16)
- 参考文献数
- 3
1 0 0 0 OA グリーンランド北西部カナック村における 氷河流出河川の洪水
- 著者
- 杉山 慎 近藤 研
- 出版者
- 公益社団法人 日本雪氷学会
- 雑誌
- 雪氷 (ISSN:03731006)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, no.2, pp.193-204, 2021 (Released:2021-09-29)
- 参考文献数
- 48
北極域では,温暖化に伴う環境変化が人間社会に影響を与えつつある.本稿ではその事例として,グリーンランドで発生した氷河流出河川の洪水災害を紹介し,数値モデルを用いた氷河融解と流出量解析について解説する.2015 年7 月21 日と2016 年8 月2 日に,グリーンランド北西部カナック氷河の流出河川が増水し,村と空港を結ぶ道路が破壊された.これらの事象を詳しく解析するために,2017-2019 年に氷河と河川で実施した観測に基づいて,氷河融解・流出モデルを構築した.この数値モデルによって2015年と2016年の流出量を再現したところ,両年の洪水時における流出量は,一時間値で9.1 および19.9m3 s−1 と示された.2015 年の洪水は,氷河全域平均で51mm w.e. d−1に及ぶ雪氷融解によるもので,2015-2019年では2 番目に顕著な融解イベントであった.一方で2016年の洪水は,2015-2019 年で2 番目の規模を持つ豪雨(90mm d−1)によるものであった.数値実験の結果は,気温上昇,強風・降雨の頻度増加,裸氷域の拡大などの環境変化が,氷河流出量の増加傾向をもたらすことを示している.
1 0 0 0 OA ブタ脳カルモデュリンの界面活性剤によって誘起されたコンホメーション変化
- 著者
- 近藤 慶之 直井 正俊 小山 勝宏 藤井 敏弘 大木 幸介
- 出版者
- 公益社団法人 高分子学会
- 雑誌
- 高分子論文集 (ISSN:03862186)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.7, pp.467-471, 1985-07-25 (Released:2010-02-26)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1 1
ブタ脳カルモデュリン (CaM) の種々の界面活性剤によって誘起されるコンホメーション変化について, 螢光スペクトル, 円偏光二色性 (CD) の測定により検討した. Tween系, TritonX100などの非イオン性界面活性剤は, CaMのコンホメーション変化に影響をおよぼさなかった. 陰イオン性界面活性剤のドデシル硫酸ナトリウム (SDS) やドデシルベンゼンスルフォン酸ナトリウム (SDBS) を加えた場合, 大きな構造の変化が観察された. Ca2+存在下および非存在下において, 1mMSDSはα-helix含量の増加を引き起こし, Ca2+存在下ではα-helix含量は42%であった. SDBSの場合, その濃度が増すとα-helix含量は減少し, 12mMではCa2+の存在, 非存在にかかわらずCDはランダムコイルの曲線を示した. 陽イオン性の塩化ベンザルコニウムは弱い変性作用を伴ってCaMの規則構造の破壌を促進する. これらの事は, 螢光スペクトルの測定によっても裏づけられた.
1 0 0 0 OA 腸管出血性大腸菌が産生するベロ毒素の検査法
- 著者
- 近藤 文雄 鈴木 匡弘
- 出版者
- 一般社団法人 日本質量分析学会
- 雑誌
- Journal of the Mass Spectrometry Society of Japan (ISSN:13408097)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.1, pp.114-118, 2003 (Released:2007-10-16)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 5 3
During the past 20 years, outbreaks of enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC) have been increasing worldwide and have been recognized as a potential health concern. Vero toxins produced by EHEC seem to be the most common cause of hemolytic uremic syndrome. Rapid diagnosis of EHEC infection is important to prevent the expansion of infection. Diagnosis is carried out by both isolation of EHEC and detection of Vero toxins in fecal extracts or fecal cultures. This review describes briefly about the current knowledge of the EHEC and Vero toxins, and about the determination methods for Vero toxins. The attempt to identify Vero toxins by electrospray ionization-liquid chromatography/mass spectrometry is also discussed.
1 0 0 0 OA 日本列島のリアス海岸における中期更新世海成段丘の高分解能地形面編年
日本列島のリアス海岸周辺における海成段丘は,離水年代が不明な場合が多い.そこで本研究では,リアス海岸などの海成段丘を対象にpIRIR年代測定法を適用し,中期更新世以降に形成された海成段丘の高分解能な地形面編年をおこなうことを目的とする.本研究では,リアス海岸の周辺の海成段丘が発達する複数地域を研究対象地域とした.野外調査と年代測定の結果,調査対象地域においてはMIS 9からMIS 5aまでのpIRIR年代値が得られ,中期更新世以降の海成段丘の離水年代が明らかとなった.
1 0 0 0 OA プロゲステロン膣坐剤の有効性と日内変動を考慮した投与設計
- 著者
- 中山 アヤコ 冨田 史子 齋木 このみ 近藤 東臣 砂田 久一 岡本 浩一
- 出版者
- 一般社団法人日本医療薬学会
- 雑誌
- 医療薬学 (ISSN:1346342X)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.5, pp.375-382, 2006-05-10 (Released:2007-11-09)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 4 3
We examined various pharmacokinetic parameters of progesterone (P) after its administration in a vaginal suppository to healthy females and compared these parameters with those after injection of P at different sites, in order to evaluate the effectiveness of the P vaginal suppository. The increase in the blood P concentration after administering it in the vaginal suppository was similar to that for injecting P (25 mg) into the gluteal region. Since the P vaginal suppository is a useful P preparation and can be readily used, it can be the dosage form of first choice in P replacement therapy. In addition, since our basic experiment suggested that there was a circadian rhythm in the blood P concentration, it may be possible to determine the optimum administration time for maintaining the blood P concentration based on this rhythm.
1 0 0 0 OA 太宰治「如是我聞」注釈(一)
- 著者
- 尾﨑 めぐみ 片木 晶子 近藤 史織 堀 万佑子 李 娜娜 山口 俊雄
- 出版者
- 日本女子大学
- 雑誌
- 日本女子大学大学院文学研究科紀要 = Journal of the Graduate School of Humanities (ISSN:13412361)
- 巻号頁・発行日
- no.28, pp.25-51, 2022-03-15
1 0 0 0 OA 造血幹細胞移植患者の運動耐容能と下肢伸展筋力の関連性について
- 著者
- 八並 光信 渡辺 進 上迫 道代 小宮山 一樹 高橋 友理子 石川 愛子 里宇 明元 森 毅彦 近藤 咲子
- 出版者
- 理学療法科学学会
- 雑誌
- 理学療法科学 (ISSN:13411667)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.4, pp.267-272, 2005 (Released:2006-02-14)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1
本研究の目的は,無菌室という閉鎖環境で治療を要する造血幹細胞移植患者に対して,運動耐容能と移植前後の下肢伸展筋力(変化率)の関連性について検討することである。対象は,造血幹細胞移植を受け,移植前後で運動負荷テストを施行できた40名である。なお,無菌室内の訓練は,主に柔軟体操と立位での筋力強化を行った。移植前の運動負荷テストの完遂率は100%であったが,移植後は57.5%へ低下した。移植後の負荷テストの結果から,対象を完遂群と非完遂群に分け従属変数とし,年齢・性別・体重変化率・前処置のTBIの有無・無菌室滞在期間・下肢筋力変化率を独立変数として判別分析を行った。その結果,下肢伸展筋力の貢献度が最も大きかった。したがって,有酸素運動が困難な無菌室内において,下肢筋力を維持することによって,運動耐容能の低下を遅延させることが示唆された。
1 0 0 0 OA DNAの八重らせん構造およびその開裂四重鎖構造とそれらの生物学的意義
- 著者
- 近藤 次郎 竹中 章郎
- 出版者
- The Crystallographic Society of Japan
- 雑誌
- 日本結晶学会誌 (ISSN:03694585)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.5, pp.345-351, 2004-10-29 (Released:2010-09-30)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 1
Recent human genome projects have revealed that exons encoding proteins count only a few percents, whereas many kinds of repetitive sequences occupy more than 50 % of genome. Some of the latter are related to genetic diseases, but their biological functions and structures are still unknown. Two X-ray structures of a short DNA fragment of d (gcGA [G] 1Agc) show that four base-intercalated duplexes are assembled to form an octaplex at a low K+ concentration, in which the eight G5 residues form a stacked double G-quartet in the central part. At a higher K+ concentration, however, the octaplex is split into just two halves. These structural features suggest a folding process according to a double Greek-key motif for eight tandem repeats of d (ccGA [G] 4Agg) found in Variable number of tandem repeat (VNTR) immediately adjacent to the human pseudoautosomal telomere. Such a packaging of the repeats could facilitate slippage of a certain VNTR sequence during DNA replication, to induce length polymorphism by increasing or decreasing of the repeats.
1 0 0 0 OA 貴金属合金に対するSn電析処理法の接着強さと耐久性ならびに臨床応用について
- 著者
- 山下 敦 近藤 康弘 藤田 元英
- 出版者
- 一般社団法人 日本接着歯学会
- 雑誌
- 接着歯学 (ISSN:09131655)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.1, pp.55-66, 1985-05-15 (Released:2011-06-07)
- 参考文献数
- 9
- 著者
- 田村 元樹 服部 真治 辻 大士 近藤 克則 花里 真道 坂巻 弘之
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- pp.21-014, (Released:2021-10-22)
- 参考文献数
- 38
目的 本研究は,うつ発症リスク予防に効果が期待される65歳以上の高齢者のボランティアグループ参加頻度の最適な閾値を傾向スコアマッチング法を用いて明らかにすることを目的とした。方法 日本老年学的評価研究(JAGES)が24市町村に在住する要介護認定を受けていない65歳以上を対象に実施した,2013年と2016年の2時点の縦断データを用いた。また,2013年にうつ(Geriatric Depression Scale(GDS-15)で5点以上)でない人を3年間追跡し2013年のボランティアグループに年1回以上,月1回以上もしくは週1回以上の参加頻度別に,2016年に新たなうつ発症のオッズ比(OR)を,傾向スコアマッチング法とt検定などを用いて求めた。結果 参加群は,年1回以上で9,722人(25.0%),月1回以上で6,026人(15.5%),週1回以上で2,735人(7.0%)であった。3年間のうつの新規発症は4,043人(10.5%)であった。傾向スコアを用いたマッチングでボランティアグループ参加群と非参加群の属性のバランスを取って比較した結果,月1回以上の頻度では参加群は非参加群に比べて,Odds比[OR]0.82(95%信頼区間:0.72, 0.93)と,うつ発症リスクは有意に低かった。年1回以上の参加群ではORが0.92(0.83, 1.02),および週1回以上では0.82(0.68, 1.00)であった。結論 高齢者のボランティアグループ参加は,月1回以上の頻度で3年後のうつ発症リスクを抑制する効果があることが示唆された。高齢者が月1回でもボランティアとして関わることができる機会や場所を地域に増やすことが,うつ発症予防対策となる可能性が示唆された。
1 0 0 0 OA 市民調査から市民計画へ(<特集>市民調査の可能性と課題)
参加型と称される計画づくりの現場では,「ワークショップ=正当な参加」という暗黙の了解があるため,ワークショップそのものが目的化してしまう危うさや,結果として,生活感と乖離した抽象的なビジョンが決められていく傾向がある。形式的な参加に行政も市民もが妥協しているとも言える。市民が何らかのかたちで継続的に「かかわる」ことができる計画が必要である。そのためには,決定と所有が必須となる。末石冨太郎が言うように,何をさせられているかがわからない=何が可能かがあいまいなことにも問題がある。その絡み合いを紐解くことが市民調査の必要性でもある。また,現場へのかかわり(実践)をいかに共有していくかが鍵となる。抽象的な指針を超えて,そこに具体的なかかわり方を導き,体験していかねばならない。そこで,身体的参加を提起したい。身体が地域にどうかかわるかを捉えたい。正統的周辺参加として,「身体で覚える」学習プロセスを重視したい。身体パタンのデータベース化と,計画に基づく新しい身体パタンとがどう関係するか,どう体得されていくかによって,計画の実効性が左右される。民俗学や社会学が蓄積してきた,ライフヒストリー的あるいは文化生態学的な蓄積もあらためて身体パタンとして解釈すれば,この身体的参加データベースに寄与することができる。ここで専門家に求められる役割は,(1)いかに現在のシステムが絡み合っているかをひもとく役割,(2)身体のパタン・ランゲージを見いだす役割,(3)創発する場をコーディネート/メディエートする役割,である。
1 0 0 0 OA アミオダロンによって発症したと考えられた薬剤性肺障害の1例
- 著者
- 小林 花神 堀口 高彦 近藤 りえ子 志賀 守 廣瀬 正裕 伊藤 友博 鳥越 寛史 林 信行 大平 大介
- 出版者
- 一般社団法人 日本アレルギー学会
- 雑誌
- アレルギー (ISSN:00214884)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.12, pp.1551-1555, 2006-12-30 (Released:2017-02-10)
- 参考文献数
- 15
80歳,男性.平成16年10月より慢性心房細動に対して抗不整脈薬アミオグロンを内服していた.内服7カ月後の平成17年6月,呼吸困難,発熱を来たし入院となった.胸部レントゲン写真,CT写真にて全肺野にスリガラス影を認め,動脈血液ガス分析にて低酸素血症がみられ,acute respiratory distress syndrome (ARDS)と診断した.アミオグロン内服の中止,ステロイドパルス療法を施行するも病態の急速の進行により入院第4日目に死亡した.剖検にてdiffuse alveolar damage (DAD),肺胞腔内に水腫液の貯留,foamy macrophageを認め,アミオグロンによる薬剤性肺障害と診断した.
- 著者
- 上田 三穂 小林 裕 吉森 邦彰 高橋 由布子 近山 達 池田 元美 魚嶋 伸彦 木村 晋也 田中 耕治 和田 勝也 小沢 勝 近藤 元治 河 敬世 井上 雅美
- 出版者
- 一般社団法人 日本血液学会
- 雑誌
- 臨床血液 (ISSN:04851439)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.8, pp.657-662, 1997 (Released:2009-04-28)
- 参考文献数
- 15
Chronic active Epstein-Barr virus infection(以下CAEBV)の経過中にEBV感染T細胞の腫瘍化を起こした1例を経験した。症例は20歳女性で発熱,陰部潰瘍,口腔内潰瘍などのベーチェット病様症状で来院した。頚部リンパ節腫脹を認め,生検では炎症性変化であった。EBV抗体価よりCAEBVと診断し,PSL, acyclovirの投与をおこなった。一旦症状は改善したが,発症約10カ月後に汎血球減少を呈し,骨髄にて異常細胞を35%認めた。TCR-β遺伝子の再構成を認めT細胞腫瘍と診断した。化学療法にて骨髄は寛解となったが,全身のリンパ節の再腫脹を認め,約3カ月の経過で治療抵抗性のため死亡した。骨髄中の腫瘍細胞でのEBVのterminal probeを用いたSouthern blottingにてsingle bandが検出され,単クローン性が証明されたことより,EBV感染T細胞の腫瘍化と考えられた。本邦の成人例では稀であり,報告した。
1 0 0 0 OA 新羅・真平王代後期の対倭外交 : 真平王の対倭政策と関連して
- 著者
- 近藤 浩一
- 出版者
- 京都産業大学
- 雑誌
- 京都産業大学論集. 人文科学系列 (ISSN:02879727)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, pp.237-260, 2019-03-30
本稿は,『日本書紀』にみられる新羅の真平王代後期に展開された対倭外交について,既往の研究と異なり新羅史の観点から検討した。これを通して,真平王代後期の対倭外交は,従来の指摘のように百済・高句麗との対立から倭の支援を引き出そうとした従属的な態度で始まったのではなく,対隋・唐外交の進展と国内の官制整備を達成した自信をバックに,積極的な外交政策のもと実行されたことを明らかにした。 真平王代(579~632)に展開された対倭外交の特徴をみれば,真平王は在位後半に至るまで倭に対しほとんど外交活動を実施しなかったが,真平王32年(610)を契機に態度を大きく変化させた。これ以後,真平王は立て続けに使者を派遣し倭と活発な外交活動を推進している。 こうした背景としては,即位直後から着手した真平王の国内外政策の成功が原動力となったと考えられる。真平王は,国内の官制整備が一段落する真平王16年(594)に,隋に使者を派遣して対中国外交を始動した。さらに唐が建国されると,領客典を設置するなどその動きを一層加速化させている。こうした関係をもとに高句麗・百済に対抗できるまでの外交能力を獲得したが,真平王はそれらをもとに一層王権強化を実現し,後期には対外意識が大きな高まりをみせたのである。 それゆえ,当該期の対倭外交は,積極的な外交政策のもと展開したとみられる。新羅側の新たな動向は,日本側の記録であるが『日本書紀』の内容にみられる通りであり,まず真平王代後期から倭に多くの仏教文物を送り始めている。特に真平王44年(622)は,新羅使節が仏像及び仏舎利・幡など多くの仏具を持参する様子が鮮明に確かめられる。さらにこのときは,百済や高句麗の僧侶たちが集まる飛鳥寺に代わり四天王寺が新たに登場し,新羅が送った仏舎利などの仏教文物はそこに施入されている。 この要因を考える上では,真平王代の新羅国内での仏教の役割が注目される。新羅では,前代の真興王以降国王を転輪聖王・釈迦仏に比定し貴族を弥勒菩薩とすることで,王権と貴族勢力が一定の秩序を形成していた。新羅仏教は王権を象徴する思想的基盤であったといえ,新羅が貢納した仏像・仏具も同じく新羅王権の象徴物であったことが窺い知られる。したがって真平王は,このような仏教文物を倭に送り新羅の王即仏思想を伝えることで,倭王を真平王の仏国土に引き込もうとしたと考えられる。 さらに同じ622年には,新羅使節が新羅経由で在唐倭人留学生を倭に送り届けている。この時から新羅と倭の間では,留学生を通じた外交関係が真平王に続く善徳王代まで継承されたのである。こうした留学生は,帰国直後に新たな外交政策を提言した恵日らの言動からわかるように,倭の外交活動に直接影響を及ぼす存在であった。真平王は,622年を契機に在唐倭人留学生とも関係を築きながら,倭に新羅の思想・制度などを伝播させようとし,それらを通じて倭国内でいわゆる「新羅化」を模索した可能性までが推察される。