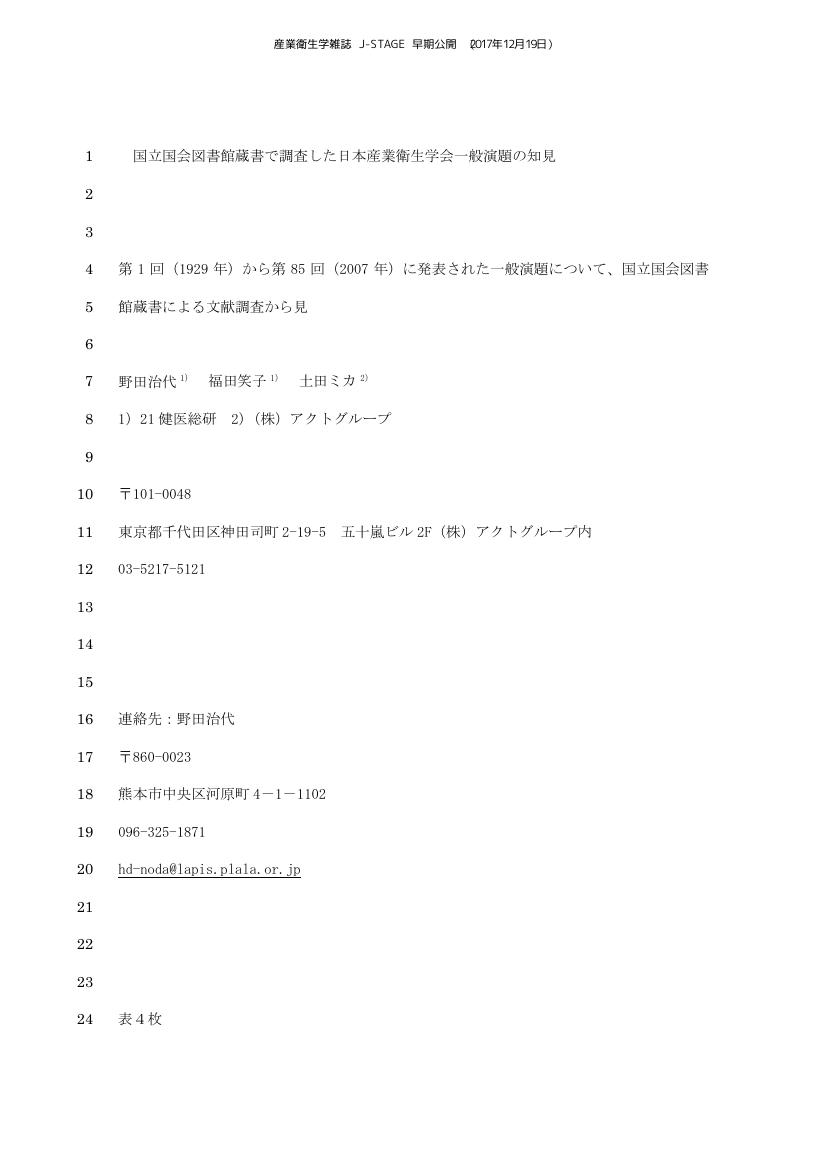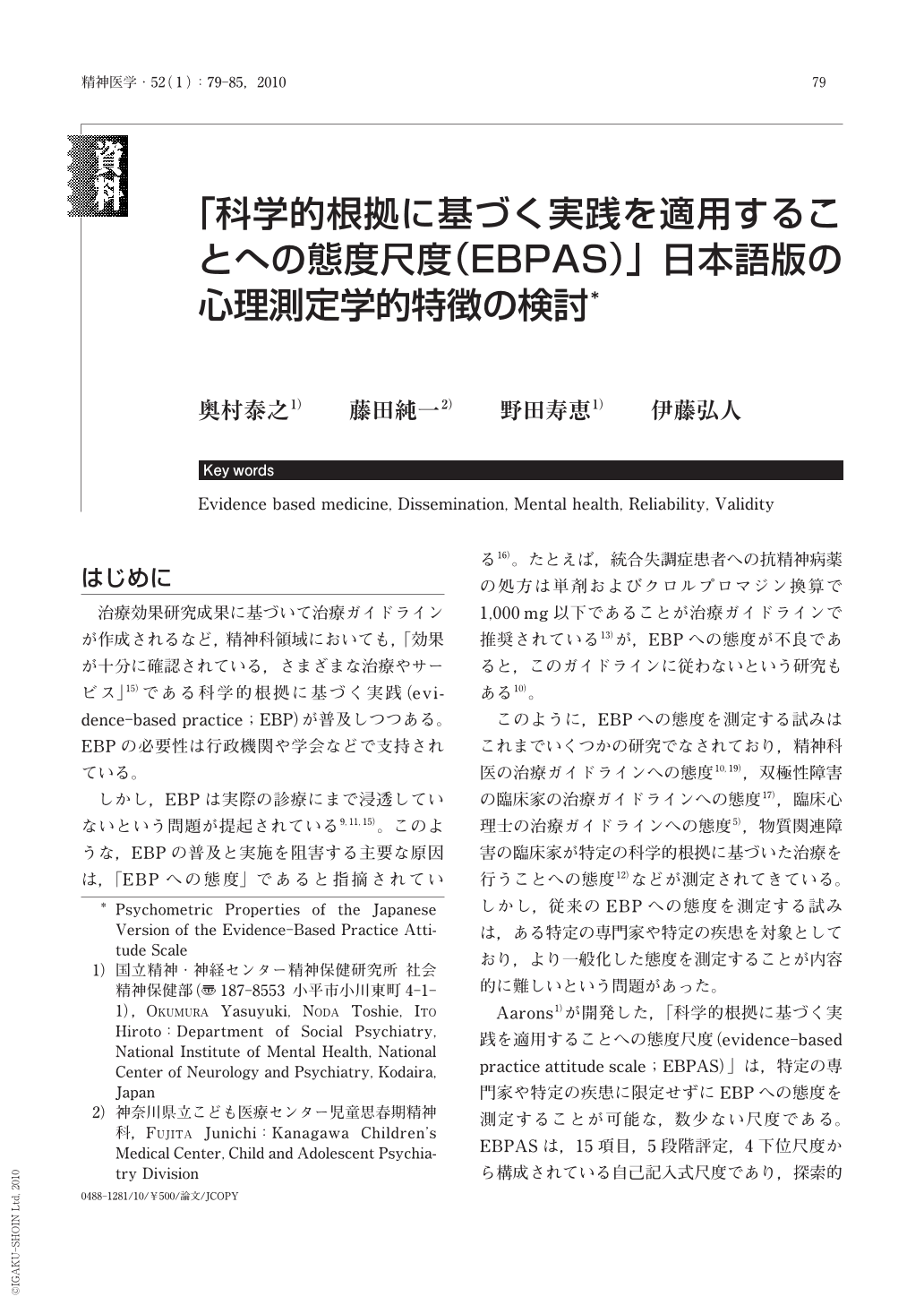4 0 0 0 <原著論文>女子学生の月経の経験と楽観性・悲観性との関連性
- 著者
- 野田 洋子
- 出版者
- 順天堂大学
- 雑誌
- 順天堂医療短期大学紀要 (ISSN:09156933)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.55-65, 2001-03-29
- 被引用文献数
- 1
月経の経験は女性の生涯における健康,QOLを考える上で重要な要因である。本研究は若年女性(18-22歳の女子短大生)の月経の経験と関連要因,ことに楽観性・悲観性との関連を明らかにするものである。記名式自己記入式質問紙法による配表調査を行った結果,2,391名の有効標本が得られた。分析の結果,月経周辺期の変化,月経観,月経のセルフケア行動に楽観性・悲観性が関連していることが明らかとなった。1.オプティミストは月経周辺期の変化を低く捉える傾向にある。2.オプティミストは月経をポジティブに捉える傾向にある。3.オプティミストは自尊感情,自己の性に対する満足度が高く,ストレスを感じることが低い傾向にある。4.オプティミストは月経痛に対し積極的セルフケア行動をとる傾向にある。5.ペシミストは月経をネガティブに捉える傾向にある。以上の結果は,今後月経周辺期変化の強い者への看護面接を行っていく上での考慮すべき要件となる。
4 0 0 0 OA 女子学生の月経の経験 : 第2報 月経の経験の関連要因
- 著者
- 野田 洋子
- 出版者
- 一般社団法人 日本女性心身医学会
- 雑誌
- 女性心身医学 (ISSN:13452894)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.1, pp.64-78, 2003-03-31 (Released:2017-01-26)
女子学生の月経の経験の実態と関連要因を明らかにすることを目的として縦断的調査研究を行った.第2報では月経の経験に関連する身体的要因,心理社会的要因の分析結果を報告する.対象はA女子短大生で2回の調査に連続して有効であった1,045名である.質問紙は回顧的,自己記入式記名式で,月経の経験と関連要因(自尊感情,楽観性・悲観性,ジェンダー満足度,ストレスとストレス発散,自覚的健康観,ライフスタイル)に関する調査項目で構成される.各要因について2群に分割した平均値の差の検定結果及び先行研究の結果を参考に変数を選択,パスモデルを作成し,共分散構造分析を行なった.結果は以下のとおりである.女子学生の月経周辺期の変化,月経痛,月経観,セルフケア行動の関連要因として身体的要因(経血量,女性年齢)だけではなく,ストレス,ストレス発散や自覚的健康観,楽観性,自尊感情,ライフスタイルという心理社会的要因が重要な関連を持つこと,また月経痛・月経周辺期の変化には月経観が影響することが認められた.月経教育は月経痛・月経周辺期の変化を軽減するセルフケア教育が重要であると共に,ストレスマネージメントや健康的なライフスタイルの奨励,月経観をポジティブにリフレーミングすることの重要性が示唆された.
4 0 0 0 AIDMを用いたデマ情報拡散再現への試みと検討
- 著者
- 池田 圭佑 岡田 佳之 榊 剛史 鳥海 不二夫 風間 一洋 野田 五十樹 諏訪 博彦 篠田 孝祐 栗原 聡
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 研究報告知能システム(ICS) (ISSN:09196072)
- 巻号頁・発行日
- vol.2015, no.14, pp.1-6, 2015-02-23
2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災において,Twitter を利用して避難情報や被災地の情報が発信され,重要な情報源となった.しかし,Twitter で発信された情報は,急速に不特定多数の人に広まることから,誤った情報が発信されると瞬時に広がるというデメリットも存在する.そのため,デマ情報を早期収束させる方法を確立する必要がある.そこで,我々は Twitter における情報拡散メカニズムを探るため,新たな情報拡散モデルを提案する.提案モデルは,Twitter ユーザを趣味嗜好の概念を持つエージェントとして定義するさらに,同一ユーザが複数回つぶやくことと,情報経路の多重性を考慮する.提案モデルを用い,東日本大震災時に確認されたデマ情報拡散の再現実験をし,実際のデマ拡散の再現性について検討を行う.
4 0 0 0 OA 国立国会図書館蔵書で調査した日本産業衛生学会一般演題の知見
- 著者
- 野田 治代 福田 笑子 土田 ミカ
- 出版者
- 公益社団法人 日本産業衛生学会
- 雑誌
- 産業衛生学雑誌 (ISSN:13410725)
- 巻号頁・発行日
- pp.17-017-W, (Released:2017-12-19)
4 0 0 0 IR 米国のシティ・カウンティ統合政府と都構想への示唆
- 著者
- 野田 遊
- 出版者
- 地域政策学ジャーナル編集委員会
- 雑誌
- 地域政策学ジャーナル = Aichi University journal of regional policy studies (ISSN:21868166)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.1, pp.25-42, 2014-07
4 0 0 0 OA 高等教育政策に関する一考察 : 新設される大学に着目して
- 著者
- 大橋 充典 野田 耕 行實 鉄平 奥野 真由 浦上 萌 Mitsunori Ohhashi Koh Noda Teppei Yukizane Mayu Okuno Moe Uragami
- 出版者
- 久留米大学人間健康学部
- 雑誌
- 久留米大学人間健康学部紀要 = Bulletin , Faculty of Human Health , Kurume University (ISSN:24350036)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.1, pp.53-65, 2020-09-01
本稿の目的は,日本における高等教育の現状について,主に文部科学省の政策を中心に整理し,今後の高等教育のあり方について検討することであった。具体的には,高等教育における「マス化」および「ユニバーサル化」について,マーチン・トロウの高等教育論を参考として大学進学率の推移からこれまでの日本における高等教育がどのように変容してきたのかについて整理し,その上で,過去10年において設置が認められた新たな大学の特徴から日本における今後の高等教育政策について提言を行った。戦後の日本における高等教育の歴史は,1947年の学校教育法の成立による1949年の新制大学の発足が始まりとされる。その後,2010年代まで徐々に増加傾向をたどってきたが,2009年には進学率が50%を超えることになり,高等教育が「ユニバーサル化」する時期に差し掛かっている。2009年以降に新たに開設された大学における設置組織について概観してみると,特に看護や医療系の学部や学科,また理学療法や作業療法の専攻が半数程度を占めている。こうした状況を見ると,日本における高等教育は文部科学省主導で量的な拡大が行われてきたと言えるが,一方で,質の向上を含めた「計画的な整備」が進められてきたのかについては,今後も議論する余地が残されている。
4 0 0 0 OA 低学年児童を対象とした意見文産出指導
- 著者
- 小野田 亮介 松村 英治
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.3, pp.407-422, 2016-09-30 (Released:2016-10-31)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 3 4
本研究の目的は, 低学年児童の意見文産出活動を対象として (1) マイサイドバイアスの克服におけるつまずきの特徴を解明し, (2) マイサイドバイアスを克服するための指導方法を提案することの2点である。2年生の1学級32名を対象とし, 1単元計5回の実験授業を行った。その結果, マイサイドバイアスの克服におけるつまずきとして, 反論を理由なしに否定する「理由の省略」と, 反論と再反論の理由が対応しないという「対応づけの欠如」が確認された。一方, 他者の意見文を評価する活動においては, 児童は反論想定とそれに対応した再反論を行っている意見文を高く評価していた。そこで, 児童は「良い意見文の型」を理解してはいるが, その産出方法が分からないためにマイサイドバイアスを克服できないのだと想定し, 児童が暗に有している「良い意見文の型」を児童の言葉から可視化する指導を行った。その結果, 児童は教師と協働で「良い意見文の型」を構築・共有することができ, その型を基に独力でマイサイドバイアスを克服した意見文産出ができるようになることが示された。
4 0 0 0 OA グラファイトの多軸破壊則および非破壊検査
- 著者
- 佐藤 英一 小野田 淳次郎
- 出版者
- 公益社団法人 日本金属学会
- 雑誌
- まてりあ (ISSN:13402625)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.8, pp.723-730, 2001-08-20 (Released:2011-08-11)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 4 3
4 0 0 0 OA 「単位制度の実質化」と大学機関別認証評価
- 著者
- 野田 文香 渋井 進
- 出版者
- 独立行政法人 大学評価・学位授与機構
- 雑誌
- 大学評価・学位研究 (ISSN:18800343)
- 巻号頁・発行日
- no.17, pp.20-33, 2016-03
- 著者
- 白井 嵩士 榊 剛史 鳥海 不二夫 篠田 孝祐 風間 一洋 野田 五十樹 沼尾 正行 栗原 聡
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- JSAI大会論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2012, pp.1C3OS121, 2018-07-30
<p>ソーシャルメディアでは多くのユーザーが活発な情報交換を行っており、情報が短時間で拡散するという特徴がある。しかし、これらの中にはデマ情報も含まれており、デマ情報の拡散が問題視されている。本研究ではTwitterにおけるデマ情報およびデマ訂正情報の拡散に焦点を当て、これらの拡散の様子を解析するとともに、感染症の伝播モデルを応用した拡散モデルを提案し、早急なデマ拡散の収束を目的とする方策を検討する。</p>
- 著者
- 奥村 泰之 藤田 純一 野田 寿恵 伊藤 弘人
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 精神医学 (ISSN:04881281)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.1, pp.79-85, 2010-01-15
はじめに 治療効果研究成果に基づいて治療ガイドラインが作成されるなど,精神科領域においても,「効果が十分に確認されている,さまざまな治療やサービス」15)である科学的根拠に基づく実践(evidence-based practice;EBP)が普及しつつある。EBPの必要性は行政機関や学会などで支持されている。 しかし,EBPは実際の診療にまで浸透していないという問題が提起されている9,11,15)。このような,EBPの普及と実施を阻害する主要な原因は,「EBPへの態度」であると指摘されている16)。たとえば,統合失調症患者への抗精神病薬の処方は単剤およびクロルプロマジン換算で1,000mg以下であることが治療ガイドラインで推奨されている13)が,EBPへの態度が不良であると,このガイドラインに従わないという研究もある10)。 このように,EBPへの態度を測定する試みはこれまでいくつかの研究でなされており,精神科医の治療ガイドラインへの態度10,19),双極性障害の臨床家の治療ガイドラインへの態度17),臨床心理士の治療ガイドラインへの態度5),物質関連障害の臨床家が特定の科学的根拠に基づいた治療を行うことへの態度12)などが測定されてきている。しかし,従来のEBPへの態度を測定する試みは,ある特定の専門家や特定の疾患を対象としており,より一般化した態度を測定することが内容的に難しいという問題があった。 Aarons1)が開発した,「科学的根拠に基づく実践を適用することへの態度尺度(evidence-based practice attitude scale;EBPAS)」は,特定の専門家や特定の疾患に限定せずにEBPへの態度を測定することが可能な,数少ない尺度である。EBPASは,15項目,5段階評定,4下位尺度から構成されている自己記入式尺度であり,探索的因子分析1)と確認的因子分析1,3)により,EBPASの下位尺度は以下の4つから構成されていることが明らかにされている。 (1) 要請(requirements):EBPを実施する要請がある時に,EBPを適用する可能性(例:あなたにとって初めての治療や介入の訓練を受けたとして,その治療や介入を上司から命じられた場合に,その治療や介入を利用する可能性を答えてください)。 (2) 魅力(appeal):EBPへの直感的な魅力(例:あなたにとって初めての治療や介入の訓練を受けたとして,その治療や介入が直観的に魅力的だと感じた場合に,その治療や介入を利用する可能性を答えてください)。 (3) 開放性(openness):新しい実践への開放性(例:クライエントを援助するために,新しいタイプの治療や介入を用いてみたい)。 (4) かい離性(divergence):研究者が開発した介入と現状の実践との間の認知のかい離(例:研究に基づいた治療や介入は,臨床的に用をなさない)。 2004年に開発されたEBPASは,2008年末までに,筆者らの知る限り,9つの論文で利用されており1~4,6~8,20,21),その応用可能性の広さのため,徐々に普及が進むことが考えられる。そこで,本研究では,EBPAS日本語版を開発し,その心理測定学的特徴を検討することを目的とした。
4 0 0 0 OA 男子新体操研究の概観と人文社会科学領域における研究の展望
- 著者
- 野田 光太郎 秦 美香子
- 雑誌
- 花園大学文学部研究紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.47, pp.95-113, 2015-03
4 0 0 0 OA 亜鉛異常における小腸粘膜病変に対する漢方薬の作用
- 著者
- 唐 方 野田 裕司 吉村 昌雄 久保 道徳 阿部 博子
- 出版者
- The Japan Society for Oriental Medicine
- 雑誌
- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.4, pp.833-839, 1995-04-20 (Released:2010-03-12)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1
亜鉛欠乏マウスに大量の硫酸亜鉛を投与すると, 投与1時間後の血清亜鉛濃度は正常対照マウスに比べて著しく増加し, 小腸粘膜病変も増悪するが, 漢方薬 (〓香, 紫蘇, 木香, 陳皮, 知母, 鶏内金) 投与した亜鉛欠乏マウスでは血清亜鉛濃度の上昇が抑制されると共に小腸粘膜の障害も軽減されることが見出された。
4 0 0 0 OA 平成を振り返って(平成21年~平成31年)
- 著者
- 野田 英明 白石 啓 中村 美里 南山 泰之
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.7, pp.327-334, 2019-07-01 (Released:2019-07-01)
4 0 0 0 材質判別装置のための赤外線吸光フィルタ自動設計
- 著者
- 野田 陽
- 出版者
- 人工知能学会
- 雑誌
- 2019年度 人工知能学会全国大会(第33回)
- 巻号頁・発行日
- 2019-04-08
ニューラルネットで最適化されたスペクトルフィルタを用いて、赤外線反射光から材質を判別する手法を提案する。通常はフィルタとして特定の波長に着目したバンドパスフィルタを用いる。しかしながらバンドパスフィルタは高価である。そこで本論文では複雑な吸収スペクトルを持つ有機材料をフィルタとして利用した。この有機材料フィルタの配合比をニューラルネットで最適化する事により、非常に安価で軽量な材質判別装置を自動で設計できる。不純物を含むプラスチック片がPP(ポリプロピレン)であるか非PPであるかを判別するタスクにおいて、赤外線分光スペクトルを用いるニューラルネットと同等の精度(99.6%)が得られた。
4 0 0 0 読みのプロセスを「見る」 (特集 "読む"--知的営為の原点)
- 著者
- 三宅 なほみ 野田 耕平
- 出版者
- 学術雑誌目次速報データベース由来
- 雑誌
- 月刊言語 (ISSN:02871696)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.2, pp.26-35, 1998
- 被引用文献数
- 1
4 0 0 0 OA 明治期における鉄道跨線橋の沿革に関する研究
- 著者
- 三浦 彩子 小野田 滋
- 出版者
- 一般社団法人 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会技術報告集 (ISSN:13419463)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.30, pp.577-580, 2009-06-20 (Released:2009-06-19)
- 参考文献数
- 7
Railway foot bridge at stations is one of the station structures for use of passengers. Although it is a universal railway structure in Japan, its historical development is poorly understood until now. This paper describes the history of railway foot bridges on the Tokaido Line based on historical records and drawings in the Meiji era. As the results of this survey, the diffusion process from large stations to local stations, and the standardization process in the end of the Meiji era have become clear.