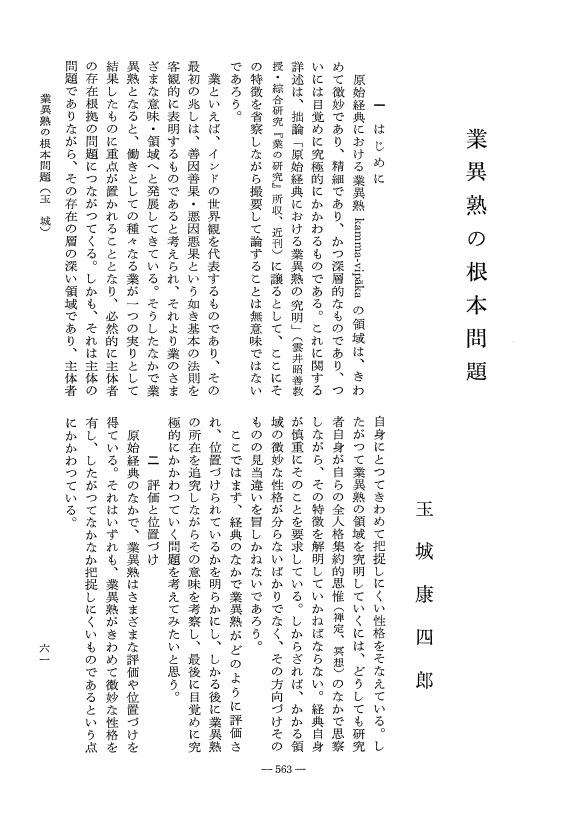1 0 0 0 OA 業異熟の根本問題
- 著者
- 玉城 康四郎
- 出版者
- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.2, pp.563-571, 1979-03-31 (Released:2010-03-09)
1 0 0 0 OA かつお・まぐろ漁船の台風対策 : マリアナ海難の教訓(日本航海学会第35回講演会)
- 著者
- 中島 保司 城戸 卓夫
- 出版者
- 公益社団法人 日本航海学会
- 雑誌
- 日本航海学会誌 (ISSN:24330116)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.29-38, 1967-01-25 (Released:2017-09-26)
The Fishing vessels casualty occured by Typhoon 29th in Mariana, at eary morning, 7th October, 1965. According the TYPHOON WARNING, 10 Bonits fishing vessels anchored to refuge the typhoon at Agrihan Is. It was reported that the typhoon 29th increased in violence with the barometer 914mb. and wind velocity 70m/s. Unfortunately, 7 vessels of them sunk and 209 crews died. We had search the accident and obtained some lessons from the casualty as follows: -(1) Security of water tightness on fishing vessels. (2) Study for a weather reports and a course of typhoon at low latitude. (3) Improvement of a bait hold. (4) Handling of the main engine under the heavy weather, particularly on a variable pitch propeller. (5) Leadership and labor management.
1 0 0 0 OA マリアナ海難の遭難船の調査
- 著者
- 前田 至孝
- 出版者
- 公益社団法人 日本船舶海洋工学会
- 雑誌
- 造船協会誌 (ISSN:03861503)
- 巻号頁・発行日
- vol.449, pp.506-512, 1966-12-25 (Released:2018-04-21)
1 0 0 0 トマト収穫ロボットのための三次元カメラを用いた果実・果柄認識手法
- 著者
- 矢口 裕明 長谷川 貴巨 稲葉 雅幸
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- ロボティクス・メカトロニクス講演会講演概要集
- 巻号頁・発行日
- vol.2017, pp.1A1-C01, 2017
<p>In this paper, we propose the method of tomato fruit and pedicel recognition method using 3D camera for tomato harvesting robot. Recognition method is constructed by 2 parts; tomato fruits detection and tomato pedicel detection. To avoid detecting stem and pedicel of neighbor fruit, we propose a robust estimation method in pedicel direction calculation. We evaluated the proposed method in the greenhouse with real tomato trees, experimental result shows its robustness.</p>
1 0 0 0 OA 明治零年代後半における洋行官僚に関する一考察
- 著者
- 柏原 宏紀
- 出版者
- 關西大学經済學會
- 雑誌
- 關西大學經済論集 (ISSN:04497554)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.4, pp.695-710, 2018-03-10
本論文は、日本の近代化が速やかに達成された理由を探るべく、明治初年の洋行官僚について検討したものである。具体的には、明治零年代後半に時期を限定し、政府内各組織における洋行官僚を抽出して表として掲げ、それらを集計して、人数や割合の変化について考察した。結果として、当該期に洋行官僚は政府で高い価値を帯び、政府内に占める彼らの割合が、全体としても各組織単位でも増加していたことが判明し、西洋を念頭に置いた近代化政策を進める人材が確保されていたことが明らかになった。
1 0 0 0 OA 明治維新における「公議」と「指導」 : 横井小楠と大久保利通
- 著者
- 三谷 博
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- Leaders of Modernization in East Asia
- 巻号頁・発行日
- pp.107-116, 1997-03-31
東アジアにおける近代化の指導者たち, 北京大学, 1995年12月4日-7日
1 0 0 0 母親の食品添加物への意識と行動:--出産・育児による変化--
目的: 次代の子供の健康を担う母親の食品添加物等への意識と, 食品表示の確認行動の妊娠期と育児期の比較から, 母親に向けた食品選択に関する効果的な保健指導を検討するための資料を得ることを目的とした.対象: 妊娠期間中の調査 (以下『妊娠期』と略) の回答者で, 育児期間中の調査 (以下『育児期』と略) へ回答した366人中の, 妊娠期調査時点の胎児を第1子として出産した母親327人を, 今回の解析の対象とした.方法: 食品添加物関連17項目を含む39項目から成る質問紙を, 妊娠期は手渡し, 育児期は郵送で配付した. 回収は両時期とも郵送とした.集計・分析は統計パッケージSPSSにより, 同一人物の妊娠期と育児期のデータを用いて, 両時期間の食品添加物に対する意識と行動と各項目との相関関係・因子分析 (バリマックス回転を行った最尤法) の結果を比較した. そして共分散構造分析により, 育児期の食品添加物等『表示の確認』行動に対する主要項目の影響関係を把握した.結果: 全項目において妊娠期と育児期の回答間には強い相関関係が認められ, 妊娠期の意識や行動の傾向が育児期に反映することが確認された. 9割の人が「食品添加物のことを詳しく知りたい」と関心が高いが, 食品添加物を『気にする』『表示の確認』をする人は5割に留まった. 意識・行動項目の因子分析から両時期とも第一因子『購入品』を得たが, 第二・三因子は時期による相違が見られた. 育児期の『表示の確認』は妊娠期よりやや減少しており, 育児期の『表示の確認』に対する項目間の関係構造は, 『表示の確認』が『気にする』から強い影響を受けていた. 一方, 『気にする』は「食品添加物について詳しく知りたい」からの影響を受けていた.考察: 食品添加物等の表示を確認する行動を促進するには, 食品添加物に関する正しい知識を母親が持つことにより, 母親が食品添加物を気にする意識が強化されることが, 大切なポイントであることが明らかになったと考える.
1 0 0 0 OA 抵抗戦略としての戦後の台湾鉄道
- 著者
- 蔡 正倫
- 出版者
- 立命館大学大学院先端総合学術研究科
- 雑誌
- Core Ethics : コア・エシックス = Core Ethics : コア・エシックス (ISSN:18800467)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.135-147, 2012
- 著者
- 掛谷 佳昭 山本 洋司 渡辺 広希 惠飛須 俊彦
- 出版者
- 一般社団法人 大阪府理学療法士会生涯学習センター
- 雑誌
- 総合理学療法学 (ISSN:24363871)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.9-16, 2021 (Released:2021-06-30)
- 参考文献数
- 34
【目的】レンズ核線条体動脈(lenticulostriate artery:以下,LSA)領域のBranch Atheromatous Disease(BAD)患者に対する発症24時間以内の離床が運動機能および進行性脳梗塞に及ぼす影響について後方視的に検討すること。【方法】対象は2014年から2018年に当院へ入院したLSA領域のBAD患者とし,早期群と通常群の2群に分けた。年齢,性別,BMI,脳卒中危険因子,脳卒中既往歴,発症前modified Rankin Scale(mRS),入院時National Institute of Health Stroke Scale(NIHSS),発症から立位開始までの時間,入院時および転帰時の下肢Fugl-Meyer Assessment(FMA),転帰時Barthel Index(BI),転帰時Functional Ambulation Categories(FAC),進行性脳梗塞の有無,進行性脳梗塞例の離床前後の収縮期血圧,リハビリ実施時間,実施回数について調査した。【結果】早期群17名,通常群13名であった。転帰時の下肢FMAは入院時と比較して両群共に有意に高値であった。BIは両群間に有意差を認めなかったが,自力歩行獲得例は通常群と比較し早期群で有意に多かった。進行性脳梗塞は両群間で有意差を認めなかった。【結論】LSA領域のBAD患者に対する発症24時間以内の離床は,安全かつ運動機能,歩行能力向上に繋がる可能性が示唆された。今後は研究デザインやサンプルサイズを考慮したさらなる研究の実施が必要になる。
1 0 0 0 OA 林業経営と太陽光発電パネル設置の比較
- 著者
- 伊高 静 吉本 敦
- 出版者
- 日本森林学会
- 雑誌
- 日本森林学会大会発表データベース 第128回日本森林学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.71, 2017-05-26 (Released:2017-06-20)
太陽パネル設置による発電は、二酸化炭素の排出量が非常に少ない自然エネルギーとして注目を集めている。一方、山林を伐採して太陽パネルを設置する地上型メガソーラーの急増については、景観の損失や、森林喪失による生態系への悪影響・土砂流出等が懸念されている。本研究は、山間地における太陽パネル設置の総合的な評価を可能にする判断材料を提供するため、それぞれの炭素量収支を明らかにする事を目的とした。具体的には、太陽パネル生産・運搬・設置・メンテナンス・パネル解体・廃棄にまつわる炭素収支を先行研究とメーカーからの聞き取り調査から明らかにした。さらに、太陽光発電に相当する電力を、化石燃料による発電に置き換え、その炭素量を明らかにした。また、仮想林分における施業による炭素収支を、数理最適化の手法を用いて算出した。収穫量・収穫頻度を制約条件に、樹齢に応じた炭素収支が、最小~最大になる解を、様々な施業パターンを想定して算出した。現実には、山間地利用における森林経営とソーラーパネル設置を総合的に判断することの難しさは、比較のための「物差し」が1つではないことにある。発表では、「炭素収支」という見地から議論したい。
1 0 0 0 OA イオン交換樹脂の電子材料精製への応用
- 著者
- 高橋 一重 伊藤 美和
- 出版者
- 日本イオン交換学会
- 雑誌
- 日本イオン交換学会誌 (ISSN:0915860X)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.2, pp.26-30, 2014 (Released:2014-05-20)
- 被引用文献数
- 1
超純水製造で培ったイオン交換樹脂のクリーン化技術や分析技術の応用展開として,電子材料精製向けイオン交換樹脂の開発に取り組んできた。これまでに開発したイオン交換樹脂として,非水系対応品である乾燥樹脂「アンバーリストTM DRY」シリーズ,また超低溶出品であるクリーン樹脂「オルライトTM DS」シリーズについてその特徴を紹介し,またいくつかの利用例について報告する。
1 0 0 0 OA 入試改革が私学学校経営に与える効果 : 私立女子中高一貫校の改革事例から
- 著者
- 石井 豊彦
- 出版者
- 関西国際大学教育総合研究所
- 雑誌
- 教育総合研究叢書 = Studies on education (ISSN:18829937)
- 巻号頁・発行日
- no.13, pp.161-175, 2020-03-31
品川女子学院(東京都,私立女子校,6年制一貫)は,グローバル化への対応として入試改革を成功させた。結果,多様な学力を持つ入学者を受け入れるとともに,少子化の中で出願数をふやすことができた。また,入試改革により,受験生と保護者へ教育方針(「28project」と名付けている)の理解が促進された。これらのことから,学校経営の安定化に貢献した事例として入試改革を報告する。品川女子学院は,2015年度入試まで知識と理解能力を測る4教科型入試を3回行っていた。2016年度入試からそのうち1回の入試の出題内容を,習ったことをいかに表現するかを測る出題とし,異なった学力の合格者を出す入試に変更した。この新しい試験導入で,4教科型入試の不合格者が,表現する力を測る試験で合格するケースが倍増したことは,この変更による成功と言える。2つ目の改革は2018年度入試から行われた算数のみを測る入学試験である。これは受験機会を1回多くし,算数に優れている入学者を受け入れることを目的とした。
1 0 0 0 IR 瀬戸内海漁民の西海地域への移動--海を旅する人たち(4)
- 著者
- 立平 進
- 出版者
- 長崎国際大学
- 雑誌
- 長崎国際大学論叢 (ISSN:13464094)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.37-44, 2005
筆者は、「海を旅する人たち」のテーマで、いくつかの論考を記してきた。海を旅する人たちとは、決して楽な旅ではなく、旅の経緯が比較的不明なものが多く、名も無き人々や、記録に残らないような人たちの旅を記してきたつもりである。漁民は、その中心的な存在であるといえる。本稿では、瀬戸内海漁民の移動について、山口県熊毛郡平尾町佐合島の漁民が、対馬の峰町志多賀に出漁してきていたことを記したものであるが、これを聞き取り調査で明らかにすることができたため、漁民の移動の軌跡として記録したものである。近代になって、瀬戸内海漁民が長崎県の近海に出漁してくる経緯について、江戸時代からの歴史的な経緯もあったが、対馬に「各地ノ漁夫群来シテ種々ノ漁業ヲ営メリ」(下啓介、本文注2)と記されるように、遠くから好漁場であった西海地域に各地の漁師が出漁してくる背景についても考察したものである。また、長崎県の漁民が離島へ出漁していく経緯について、民俗学的な調査により明らかにされたものを、旅の歴史・庶民の交流の歴史として提示したものである。
- 著者
- 池松 由香
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ベンチャ- (ISSN:02896516)
- 巻号頁・発行日
- no.247, pp.66-71, 2005-04
——山田先生が、最初に多摩川精機の指導に入ったのは、2004年8月の初旬でした。その時の皆さんの印象はどうでしたか?梱包作業者・実原 「なんだこりゃ?」って感じですよね。エライ先生だとは聞いてたけど、現場の人間じゃないわけでしょ。現場を知りもしないのに、いきなり来て、「あれどかせ、これどかせ」って言うもんだから、抵抗はあった。
1 0 0 0 OA 視線行動の変容に着目したトレーニング方法の可能性
- 著者
- 水﨑 佑毅 中本 浩揮
- 出版者
- 日本バスケットボール学会
- 雑誌
- バスケットボール研究 (ISSN:21896461)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.3-9, 2019 (Released:2020-12-09)
- 著者
- 賀川 真理 かがわ まり
- 雑誌
- 阪南論集. 社会科学編
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.2, pp.77-96, 2012-03
1 0 0 0 食肉製品中の亜硝酸根分析における醤油や魚醤の影響
- 著者
- 松阪 綾子 伊藤 暁生 粟野 由梨佳 殿原 真生子 横溝 香
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品衛生学会
- 雑誌
- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.3, pp.105-111, 2021-06-25 (Released:2021-07-02)
- 参考文献数
- 23
食肉製品中の亜硝酸根含量は,ジアゾ化法による定量法が用いられる.この測定法は,試料中にアスコルビン酸,システインなどの還元物質が存在すると,それらが定量妨害となり亜硝酸根の測定値が低くなることが知られている.一方,食肉製品に原材料として使用される,醤油,魚醤やみりんが有している抗酸化作用が,この還元物質に該当するのではないかと推測し,これらを使用している食肉製品について検討を実施した.検討の結果,原材料として醤油や魚醤が使用されている食肉製品中における亜硝酸根分析において,定量妨害が認められる場合があった.ただし,醤油や魚醤はその製法により抗酸化力に差があることから,これらを含んだ食肉製品において,亜硝酸根の定量妨害が一律に生じるとは言及できない.しかしながら,醤油や魚醤を含んだ食肉製品中の亜硝酸根含量を測定する場合は,亜硝酸根の定量妨害が生じることを考慮し,異なる試料量を用いて同時に定量を実施し,定量値に差が生じていないかを確認する必要があると考えられる.
- 著者
- 大八木 伸 盛田 隆行 小西 良子
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品衛生学会
- 雑誌
- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.3, pp.79-84, 2021-06-25 (Released:2021-07-02)
- 参考文献数
- 21
ゆでめん類は水分含量が多く,水分活性が高いために腐敗しやすい食品の1つとなっている.そのため製めん業ではHACCPマニュアルを参考とした衛生管理を行うことが推奨されている.しかし,中小企業のゆでめん工場で包装後の製品から一般生菌数が自主基準より高く出る事例が数例あった.その微生物汚染源を特定するために, PDCAサイクルを基本として検討を行った.その結果,汚染原因は環境由来菌であり,殺菌後の冷却工程で二次汚染されたこと,水洗冷却工程の強い水流により環境浮遊菌および酸素が水洗冷却槽に取り込まれ冷却水中の微生物の増殖を招き,最終製品を汚染することが示唆された.このような現象が起こることは,HACCPマニュアルでは提示されておらず新しい知見であり,本知見が今後のHACCPプラン構築に貢献することが期待できる.
- 著者
- 上野 健一 細川 葵 橋本 諭 及川 寛 柴原 裕亮 松嶋 良次 渡邊 龍一 内田 肇 鈴木敏 之
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品衛生学会
- 雑誌
- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.3, pp.85-93, 2021-06-25 (Released:2021-07-02)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 1
二枚貝の麻痺性貝毒(PSTs)はマウス毒性試験(MBA)で検査されているが,動物愛護に対する社会的関心の高まりとともに高感度・高精度なPSTs分析法も開発され,動物実験代替法の利用が可能となった.本研究では,PSTsのモノクローナル抗体を利用したイムノクロマトキットによるスクリーニング法の開発を試みた.食品衛生法規制値(4 MU/g)を下回る2 MU/gをスクリーニング基準として試験液の希釈倍率を80倍とした条件で試験した.目視に加え,画像解析判定も併せて検証した.MBA 2 MU/g以上の20試験品はすべて本キットで陽性を示し,偽陰性はなかった.また,2 MU/g未満の327試験品のうち偽陽性は3%であった.以上のように,本法は高い正確度を示し,迅速・簡便なPSTsスクリーニング法として有用であることが示された.