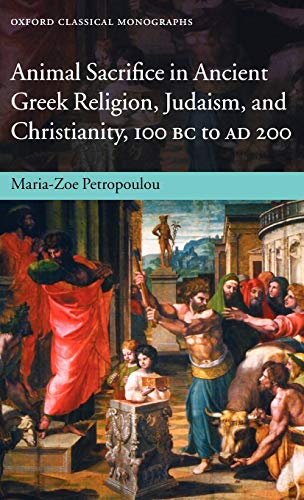2 0 0 0 OA D-13 輻射・気流複合空調システムの快適性評価
- 著者
- 柴田 悦雄 八尾 健治 増田 雅昭
- 出版者
- 社団法人空気調和・衛生工学会
- 雑誌
- 学術講演会論文集
- 巻号頁・発行日
- no.3, pp.797-800, 1991-10-31
- 著者
- Maria-Zoe Petropoulou
- 出版者
- Oxford University Press
- 巻号頁・発行日
- 2008
2 0 0 0 OA 無限級數の一般的總和法
- 著者
- 笠原 芳郎
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電氣學會雜誌 (ISSN:00202878)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.674-677, pp.269a-270, 1945-08-20 (Released:2010-05-19)
- 参考文献数
- 1
2 0 0 0 :第1部データ解析
- 著者
- 川辺 正樹
- 出版者
- 日本海洋学会
- 雑誌
- 日本海洋学会誌 (ISSN:00298131)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.2, pp.95-107, 1982
- 被引用文献数
- 100
対馬海流は日本海中央部において複雑な蛇行路をとるのに対し, 対馬海峡付近では比較的整然とした流路をとり, しばしば3本の分枝流が見出されてきた. しかし, その構造や変動についてはほとんどわかっていない. そこで, 水温・塩分・潮位データを使って, おもに対馬海峡付近での対馬海流の性質を調べ, 次のような結果を得た.<BR>第1分枝 (日本沿岸分枝) の存在は, 塩分分布によって少なくとも3月から8月に認められる. 第3分枝 (東鮮暖流) は常に存在している. 一方, 第2分枝 (沖合分枝) は6月から8月にかけての夏季のみ存在する.<BR>主密度躍層は, 深さ150mから200mで日本側の陸棚上のゆるやかな海底斜面に交叉している. 第1分枝は, おおよそこの交叉位置より岸側を占めており, 第2分枝は交叉位置付近から沖側に位置している.<BR>釜山・厳原間, 厳原・博多間の潮位差によると, 表面流速・流量の季節変化は, 対馬海峡東水道では非常に小さく, 西水道では大きい. しかも, 西水道で表面流速・流量の増大する期間は, 第2分枝の存在する期間とよく一致している.<BR>以上の結果は, 海底地形や密度成層, および対馬海峡西水道での流入流速・流量の季節変化が, 第2分枝の形成に重要な役割を果たしていることを示唆している.
2 0 0 0 IR 源氏物語「ね--なく」考
- 著者
- 鈴木 浩一
- 出版者
- 研究と資料の会
- 雑誌
- 研究と資料 (ISSN:03898121)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, pp.1-13, 2016-07
2 0 0 0 自然なふるまいを利用したユーザーインターフェースの研究
- 著者
- 井上 正太 若林 尚樹
- 出版者
- 日本デザイン学会
- 雑誌
- 日本デザイン学会研究発表大会概要集
- 巻号頁・発行日
- vol.52, pp.116-116, 2005
本研究では、mp3プレイヤーの曲の検索という操作に着目し、この操作を短期間で習熟することが可能なデザインの提案を目的としている。その手法として、経験・体験で既に行ったことのあるふるまいを利用し操作することのできるユーザーインターフェースを用意し、そこからユーザーが操作方法を推測することにより、新たに操作を覚える必要のない道具を提供する。ここで曲の検索ということから、音に関わるものを探す場面を5つ想定した。CD屋でCDを探す場面/レコード屋でレコードを探す場面/レコード内のひとつの音を探す場面/ギターのチューニングで調律のあった音を探す場面/聴診器で体の中の音を探す場面といったものである。この場面において、音を探している最中に行うナゾル・ズラス・マワスといったふるまいに着目した。それらのふるまいにより実際に操作できるように、タッチパネルなどユーザーの動きに依存した操作を取り入れたモデルを構想し、研究の効果を期待する。モデル実験の結果、本研究の手法は、ユーザーの経験・体験によって斑が生じてしまうため、より多くのユーザーへの対応を考えるためには、新たな工夫が必要だと考えられた。
- 著者
- 大内 茂人 矢野 浩司
- 出版者
- The Institute of Electrical Engineers of Japan
- 雑誌
- 電気学会論文誌D(産業応用部門誌) (ISSN:09136339)
- 巻号頁・発行日
- vol.110, no.4, pp.410-417, 1990
- 被引用文献数
- 2 3
On a variable speed control of motors used in industrial plants and industrial robots, a shaft torsional oscillation is often generated when a motor and a load are elastically coupled with a shaft. Such an oscillation may result in damage to the machine.<br>This paper is intended to theoretically explain the fact that a shaft torsional oscillation can be suppressed by using the digital observer regardless of the presense of the gear.<br>In this paper, we conducted tests on two shafts with resonant frequencies at 10.5 Hz and 16 Hz using a full-digital control equipment for controlling DC motors with the digital observer in order to confirm the oscillation control effects.
2 0 0 0 カテゴリ-連続判断法による自動車交通騒音の評価
- 著者
- 難波 精一郎 桑野 園子 中村 敏枝
- 出版者
- 一般社団法人日本音響学会
- 雑誌
- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.1, pp.p29-34, 1978-01
- 被引用文献数
- 47
The present experiments were made to establish a relation between the overall judgment and the instantaneous judgment of the sound which continues over a long period. We have an impression of loudness of sound every moment, at the same time we may judge the overall loudness after some period passed. The overall loudness may be said to be a kind of summation of the loudness at each moment. To find the relation between them is very useful to expect the overall loudness. For this purpose, we have developed a new method, continuous judgment by category. Five subjects with normal hearing ability judged the impression of the sound of each moment using 7 categories from very noisy to very calm by touching one of the 7 micro-switches on the response box corresponding to each category. The stimuli used were nine kinds of road traffic noise with 1 minute duration recorded on a magnetic tape. They were reproduced by a tape recorder and presented to each subject through amplifier and loudspeaker. The responses of the subject were continuously recorded on the recorder. To obtain the overall judgment, two methods were used, semantic differential and the method of adjustment. In the experiment using semantic differential, the subjects were asked to judge the overall impression of the stimuli using 7 categories of three adjective scales, "noisy-calm", "clear-hazy" and "bass-treble", after listening to 1 minute stimulus. As for the method of adjustment, the result of our previous experiment was referred. The findings are as follows : (1) The coefficient of correlation between trials of each subject was so high that method of continuous judgment by category can be said to be reliable. Moreover, the subjective interval between categories was confirmed to be equal by Torgerson's law of categorical judgment. (2) High correlation was found between the sound level and the category scale of continuous judgment of the subjects at every one second (r=. 968). (3) The effect of the preceding stimulus was examined by calculating Leq averaging over 1 sec to 5 sec preceding to the judgment. 2 sec-averaged Leq showed the highest correlation with judgment. This fact suggests that the instantaneous judgment may be affected by the preceding stimulus and determined by averaging the sound level during 2 sec preceding to the judgment. (4) Though the overall judgment showed a high correlation with the average of instantaneous judgment of each changing stimulus, the latter showed a trend to be underestimated in the stimuli composed of 1 or 2 vehicles. This difference could be modified by excluding the judgment of the background noise from averaging. This fact suggests that the overall loudness is mainly determined by the prominent part of signals, and supports our previous finding that the overall loudness of level-fluctuating sound shows a high correlation with L_<10> or Leq, which are affected by the upper level of the sound. (5) From the findings of these experiments it was found that the overall loudness can be estimated by the instantaneous judgment or the instantaneous sound level. Our new method, continuous judgment by category, can be applied to any stimulus with longer duration. We would like to try it in the future.
2 0 0 0 OA 青年のアタッチメントスタイルと不安喚起場面における行動との関連
- 著者
- 若尾 良徳
- 出版者
- 日本パーソナリティ心理学会
- 雑誌
- パーソナリティ研究 (ISSN:13488406)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.2, pp.47-58, 2004-03-24
- 被引用文献数
- 2
本研究の目的は,青年期の自己報告型のアタッチメントスタイルが不安喚起場面での親密な他者との行動に現れるのかを検討することである。自由な相互作用が可能な場面でなく,パートナーの有効性が疑われる分離再会状況において,行動はアタッチメントに関連した組織化がなされ,アタッチメントスタイルとの関連が見られる可能性を検討した。恋愛関係または友人関係にある18組(恋愛関係9組,友人関係9組,男性13名,女性23名)が実験に参加した。参加者の平均年齢は,22.03歳であった。参加者は,不安やストレスを感じた状態で,待合室と称した実験室において,パートナーとの相互交渉および短い分離と再会を経験した.その後,アタッチメントの個人差測定尺度を含むいくつかの質問紙に回答した.彼らの実験室での行動はVTRで撮影され,2名の評定者により評定された.その結果,自由な相互交渉が可能な場面からはアタッチメントに関わる行動の組織化は見られなかった。それに対して,分離再会場面においては,アタッチメントに関連した行動の組織化がなされており,自己報告との関連が見られた。青年のアタッチメントの個人差は,乳幼児と同様に,親密な他者との分離再会における行動に現れることが示された.
- 著者
- 鈴木 健二 木村 充 武田 綾 松下 幸生
- 雑誌
- 日本アルコール・薬物医学会雑誌 = Japanese journal of alcohol studies & drug dependence (ISSN:13418963)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.1, pp.44-53, 2008-02-28
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 1
2 0 0 0 OA 電文体発話を呈した右利き左中前頭回後部の小出血の1例
- 著者
- 斉田 比左子 藤原 百合 山本 徹 松田 実 水田 秀子
- 出版者
- 日本失語症学会 (現 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会)
- 雑誌
- 失語症研究 (ISSN:02859513)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.4, pp.230-239, 1994 (Released:2006-06-06)
- 参考文献数
- 15
電文体発話を呈した左中前頭回後部の小出血の1例を報告した。典型的な電文体発話は我が国の Broca 失語ではまれといわれている。本症例は54歳,右利き男性で,発症時はBroca失語に相当する状態を呈し,その回復過程で,自発話のみに選択的に電文体発話が明確となった。特に,発話意欲の亢進した自発話に著明であった。書字には,電文体は認められなかった。理解力や喚語力は保たれ,文法処理能力も良好であった。本症例では,迅速かつ効率よく多くの情報を伝えようとする場合には助詞が省略され,その背景には文を構成し発話する過程で助詞の使用に関する何らかの機能不全が推察された。本症例は,文の構成に関与するといわれる左中前頭回後部に限局病変を有したことから同部位が文の構成過程に関与する可能性を示唆する1症例と考えられた。
- 著者
- 赤田 信一
- 出版者
- 静岡大学
- 雑誌
- 静岡大学教育学部研究報告. 教科教育学篇 (ISSN:0286732X)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, pp.181-192, 2014
2 0 0 0 OA 立原道造における時空の意識(一) : ジンメルをめぐる一側面
- 雑誌
- 調布日本文化 = The Chofu's Japanese culture
- 巻号頁・発行日
- pp.四九-六四, 1991-03-25
2 0 0 0 IR 経済戦争の時代の経済思想:序説
- 著者
- 中山 智香子 ナカヤマ チカコ NAKAYAMA Chikako
- 出版者
- 東京外国語大学
- 雑誌
- 東京外国語大学論集 (ISSN:04934342)
- 巻号頁・発行日
- no.74, pp.81-102, 2007
2 0 0 0 OA 駐日フランス大使ポール・クローデルと中国(1921-1927)
- 著者
- 学谷 亮
- 出版者
- 東京大学大学院総合文化研究科・教養学部アジア地域文化研究会
- 雑誌
- アジア地域文化研究 (ISSN:18800602)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.74-94, 2016-03-31
論文/Articles
2 0 0 0 IR 微分トポロジーと経済学 (位相幾何学と経済学)
- 著者
- 西村 和雄
- 出版者
- 京都大学
- 雑誌
- 数理解析研究所講究録 (ISSN:18802818)
- 巻号頁・発行日
- vol.407, pp.50-63, 1980-12
2 0 0 0 OA 韓国 たばこ規制の動向
- 著者
- 藤原夏人
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説 (ISSN:13492071)
- 巻号頁・発行日
- vol.(月刊版. 261-2), 2014-11
2 0 0 0 IR 鉄道線と銀幕の風景 : ゴジラの足跡を辿る東京1954年
- 著者
- 猪俣 賢司
- 出版者
- 新潟大学人文学部
- 雑誌
- 人文科学研究 (ISSN:04477332)
- 巻号頁・発行日
- vol.132, pp.19-39, 2013-03
2 0 0 0 OA 植民地期の「朝鮮玩具」
- 著者
- 権 錫永
- 出版者
- 北海道大学大学院文学研究科
- 雑誌
- 北海道大学文学研究科紀要 (ISSN:13460277)
- 巻号頁・発行日
- vol.139, pp.1-23, 2013-03-21