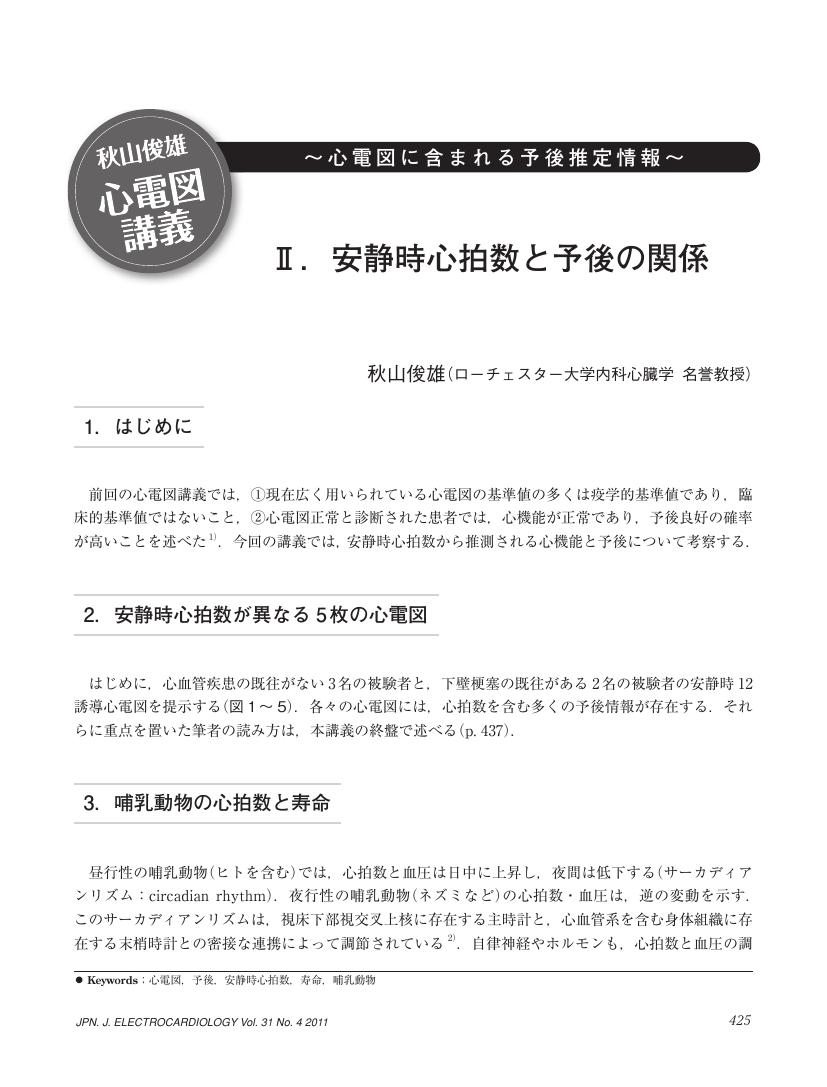2 0 0 0 OA 批判の学としての「国文学」
- 著者
- 空井 伸一
- 出版者
- 愛知大学人文社会学研究所
- 雑誌
- 人文知の再生に向けて
- 巻号頁・発行日
- pp.63-103, 2016-03-20
2 0 0 0 IR 一次元模型実験によるベントナイト系緩衝材の自己シール性評価
- 著者
- 小峯 秀雄 緒方 信英 中島 晃 高尾 肇 植田 浩義 木元 崇宏
- 出版者
- 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集 = Proceedings of JSCE (ISSN:02897806)
- 巻号頁・発行日
- no.757, pp.101-112, 2004-03-21
- 参考文献数
- 27
2 0 0 0 OA 心電図に含まれる予後推定情報
- 著者
- 秋山 俊雄
- 出版者
- 一般社団法人 日本不整脈心電学会
- 雑誌
- 心電図 (ISSN:02851660)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.4, pp.425-441, 2011 (Released:2012-02-10)
- 参考文献数
- 37
- 被引用文献数
- 5 2 8
2 0 0 0 IR 学部消息
- 著者
- 岡河 貢 足立 真 坂本 一成
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.564, pp.363-369, 2003
- 被引用文献数
- 3 1
The purpose of this study is to analyze the character of the architectural space as information in the 'complete works of Le Corbusier'. Extract the types on the view point of the sequential organization of the architectural photographs of the work. Show the character of the architectural space as information to analyze the relation between the types and the method of the continuation of the architectural photos and the montage theory of the films.
2 0 0 0 OA 日隆上人の法華経及び日本国土観
2 0 0 0 OA 日隆聖人全集 : 原文対訳
- 著者
- 日隆聖人全集御聖教刊行会 編
- 出版者
- 御聖教刊行会
- 巻号頁・発行日
- vol.第3巻 法華宗本門弘経抄, 1926
- 著者
- 鈴木健二
- 雑誌
- アルコール研究と薬物依存
- 巻号頁・発行日
- vol.29, pp.168-178, 1994
- 被引用文献数
- 9
2 0 0 0 沖縄県久米島住民の前眼部生体計測
- 著者
- 牧野 憲一
- 出版者
- 旭川医科大学
- 雑誌
- 旭川医科大学研究フォーラム (ISSN:13460102)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.5-10, 2006
出版社版旭川医科大学は1974年の開学以来、北海道の医療に貢献してきた。多くの医師を養成し地域に送り出した。これにより、北海道の人口あたりの医師数は全国平均を上回るようになった。しかし、医師の多くは旭川や札幌などの都市部に集中し、僻地の医師不足は解消していない。医師の派遣体制が問題となるが、今後は今までの医局単位での派遣にかわって大学が窓口となった派遣体制を構築する必要がある。一方、大学病院は各病院の機能分化が進む中、高度先進医療を主体とした医療を提供することが求められる。
2 0 0 0 学童の齲蝕罹患の地域差に関する疫学的研究
- 著者
- 谷 宏
- 出版者
- 一般社団法人 口腔衛生学会
- 雑誌
- 口腔衛生学会雑誌 (ISSN:00232831)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.4, pp.411-435, 1980
- 被引用文献数
- 4
近年の学童の齲蝕罹患の地域差を明らかにすることを目的として本研究を行なった。昭和52年から53年にかけ, 北海道4地区, 沖縄県2地区, 東京都世田谷区内の1地区に居住する小学校1年生から中学3年生まで, 8,672名について歯科検診を行なった。東京の小学校6年生と北海道の小学校6年生, および北海道の中学生については質問紙により, 清涼飲料の摂取頻度と歯ぶらしによる刷掃頻度についても調査した。その結果, 東京の学童は北海道や沖縄の学童に比べ, 歯科保健状態ははるかに良好であり, 北海道辺地の学童が最も悪かった。北海道の学童は齲歯数が多いばかりではなく, 東京や沖縄の学童に比べ, 前歯部に齲歯を持つ者の率がはるかに高く, 比較的齲蝕罹患性の低い前歯部の唇面齲蝕も多く, 中学2年生で約20%の生徒に唇面齲蝕がみられた。前歯唇面齲蝕は隣接面や舌面齲蝕とは異なり, 前歯部に齲蝕を持つ者の率が約20%程度蔓延すると, その地区で唇面齲蝕が発生するようになることが示唆された。<BR>北海道の学童では毎日清涼飲料を摂取する者が多く, 清涼飲料を毎日摂取する者は齲歯数も多く, 前歯に齲蝕を持つ者が多い傾向がみられた。北海道の学童では毎日歯をみがく者の率は全国平均に比べて高いが, 日常の刷掃頻度と齲蝕罹患性との間に明瞭な関係はみられなかった。<BR>市販の清涼飲料10種について糖量を分析した結果, sucrose量は8.3~14.1g/dl, glucose量は0.13~3.429/dl含まれていた。pHは2.5~3.5であった。また清涼飲料を毎日摂取している者とほとんど摂取しない者各々20名の歯垢を調べた結果, 前者は後者に比べ歯垢中の総生菌数に対するStr. mutansの存在比は極めて高かった。<BR>国民栄養調査の結果からも, 北海道の人々は他地域の人々に比べ清涼飲料をよく飲むようであり, 北海道の学童における齲歯の多発, 前歯の齲蝕発生は清涼飲料の摂取頻度の高いことと関連があると考えられた。
2 0 0 0 消防用放水の二次元簡易計算モデルと放水特性評価
- 著者
- 宮下 達也 須川 修身 和田 義孝 石川 亮 川口 靖夫
- 出版者
- Japan Association for Fire Science and Engineering
- 雑誌
- 日本火災学会論文集 (ISSN:05460794)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.1, pp.13-19, 2012
火災を早期消火するためには, 棒状放水された水の軌跡や挙動を予測し, 火災源に効率良く消火水を供給する必要がある。本研究は, 二次元の簡易計算モデルを構築し, 放水シミュレーションによる放水特性の解析を行った。モデルの構築にはM P S 法を基盤として用い, 粒子径にRosin-Rammler 分布を適用することで, 水塊が飛行中に分裂する挙動を再現することができた。また, モデルの妥当性を定量的に評価するため, 放射流量3.7 L/min(圧力0.05 MPa)の小規模放水実験を実施した。最大射程・最大射高(放水軌跡)及び着水域(Footprint あるいはLanding Zone)に落下した水の分散分布を実験とシミュレーションで比較した結果, 4% 以下の誤差で良く一致した。
2 0 0 0 OA 寛政期の学政改革と臣僚養成
- 著者
- 鈴木 博雄
- 出版者
- 横浜国立大学
- 雑誌
- 横浜国立大学教育紀要 (ISSN:05135656)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.23-51, 1963-11-15
In the above thesis the author has investigated the methods by which samurai were educated in the feudal period, with especial reference to educational reform in the Kansei era (1787~1798), a time when the education carried out by 'Hanko', clan conducted schools, was playing an important role in making samurai into feudalistic bureaucrats. In the feudal period, the samurai, whose job was mainly that of a soldier, came to become gradually more involved in the duties of official administration due mainly to the fact the country was in a state of peace and his servies as a fighter were unnecessary. In the beginning of the feudal period the structure of the government was very simple but as it and it's accompanying feudal bureaucracy became more complicated so there acrose the need for samurai able to read and write rather than fight. In order to meet this need the 'Hanko' were developed. In the first chapter the author inquired into the political ideas of Matsudaira Sada-nobu, the man in charge of political reform. The purpose of his reform lay in the training of feudal bureaucrats. His image of them was essentially feudal in that he required them to be persons of great integrity especially obedient to their feudal lord. on the other hand, like modern bureaucrats, they had to be skilled in administration. In the second chapter the author comments on the rules and plans of studies which were part of the reform, such as 'Gakumon Ginmi', (Intellectual examinations in the upper classes) and 'Sodoku Ginmi', (Intellectual examinations in the lower classes), and the construction of government schools. In the last chapter the author discusses how the contradiction of feudal and modern ideas caused the failure of overall education as far as feudal bureaucrats were concerned and the educational reforms which were actually put into practice.
2 0 0 0 OA 英語教師としての佐々木邦
- 著者
- 藤井 哲 Fujii Tetsu
- 出版者
- 福岡大学研究推進部
- 雑誌
- 福岡大学人文論叢 = Fukuoka University Review of Literature & Humanities (ISSN:02852764)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.4, pp.1179-1259, 2016-03
- 著者
- 佐藤 裕久 遠山 敏之
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経レストラン (ISSN:09147845)
- 巻号頁・発行日
- no.399, pp.50-52, 2008-06
1961年京都府で、おかき屋の長男として生まれる。1985年神戸市外国語大学中退、アパレル会社を立ち上げるが、失敗。1991年バルニバービ総合研究所設立。1998年現在の会社に組織変更。98年に大阪・南船場に「カフェガーブ」を出店、全国に広がったカフェブームの先駆者の1人となった。
2 0 0 0 鉄道工場
- 著者
- 交通資料社
- 出版者
- レールウエー・システム・リサーチ
- 巻号頁・発行日
- vol.S26, no.6, 1951-06
2 0 0 0 OA ダイナマイト水雷気砲試験報告
- 出版者
- 参謀本部海軍部
- 巻号頁・発行日
- 1888
2 0 0 0 OA 郷土料理・行事食における煮物の分類
- 著者
- 高橋 ユリア 下村 道子 長野 美根 吉松 藤子
- 出版者
- 一般社団法人日本調理科学会
- 雑誌
- 調理科学 (ISSN:09105360)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.111-120, 1990-02-20
- 被引用文献数
- 1
文献から抽出した郷土料理,行事食の煮物254種において,主な材料,調理終了時の煮汁の量,材料の種類の数,主な調味料,主な材料の状態およびだしの使用の有無について分類し,全国の各地域で作られている煮物の特徴を知ろうとした。分析には,数量化分析II類,III類およびクラスター分析を用いた。1.地域による煮物の特徴に,最も寄与しているのは主な材料で,クラスター〔北海道・東北,北陸〕,〔関東,関西〕,〔中国〕,〔四国〕,〔中部,九州〕,〔沖縄〕に類型化できた。〔北海道・東北,北陸〕では魚類が最も多く,ついで野菜類,エビ・カニ・イカ・貝類であり,これらが全材料の89%を占めていた。〔関東,関西〕では,魚類と野菜類が多く,次に豆類が多かった。〔中国〕では,魚類,野菜類,エビ・カニ・イカ・貝類に獣鳥肉類が加わっていた。〔四国〕では,野菜類が最も多く,ついでいも類,魚類であった。〔中部,九州〕では,魚類,獣鳥肉類が多く,野菜類が少なかった。〔沖縄〕では,獣鳥肉類が非常に多く,また海藻類,特に昆布の煮物が多かった。2.調理終了時の煮汁の多少によるクラスターは,〔北海道・東北,関西,関東,中国,九州,四国〕,〔北陸,沖縄〕,〔中部〕に類型化できた。〔北陸,沖縄〕では,煮汁のある鍋物類が少なかった。〔中部〕では,煮汁の少ない佃煮,甘露煮類が全国のなかでも最も多い地域であった。3.材料の種類の数では,クラスター〔北海道・東北,四国,中国,沖縄,九州〕,〔北陸,関東〕,〔中部〕,〔関西〕に類型化できた。〔中部〕,〔関西〕では,材料の数が少なく,これらの地域から南の方と北の方に向かって,いずれも材料の数は,増加する傾向であった。4.主な調味料については,各地域ともしょうゆで味つけした煮物が最も多かった。クラスターは〔北海道・東北,北陸,中部,九州〕,〔中国,沖縄〕,〔関東〕,〔関西,四国〕に類型化できた。〔北海道・東北,北陸,中部,九州〕と〔中国,沖縄〕はともにしょうゆの次にみその煮物の多い地域であるが,〔中国,沖縄〕の方が塩の煮物の割合が高い。〔関東〕,〔関西,四国〕は,みその煮物が非常に少ない地域である。〔関東〕はしょうゆの次に塩の煮物が多いが,〔関西,四国〕には塩の煮物はほとんどなかった。5.主な材料が加工食品か生鮮食品かの分類では,クラスター〔北海道・東北〕,〔北陸,関東,中部〕,〔関西,九州,中国,沖縄,四国〕の3つに類型化できた〔北海道・東北〕は加工食品の使用が最も多く,これより南の地域へ向かうにつれ,加工食品の使用が減少し,生鮮食品が増加する傾向であった。6.だしの使用の有無と地域との偏相関係数は非常に低かった。だしの使用の有無と主な材料との関連についての相関は高く,魚介類を使用した煮物では,だしを使用しない傾向であり,植物性の材料を使用した煮物ではだしを使用する傾向にあった。
2 0 0 0 OA ??? : 珍妙小説
2 0 0 0 OA 免疫学と分子生物学の交差点 : 利根川進博士の研究方法論(<特集>やさしい免疫の科学)
- 著者
- 黒沢 良和
- 出版者
- 社団法人日本化学会
- 雑誌
- 化学と教育 (ISSN:03862151)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.5, pp.464-466, 1988-10-20