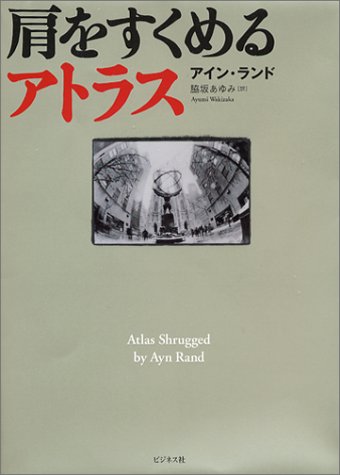1 0 0 0 OA 戦後日本の地域的不均等発展と地域社会類型の諸相:標題紙
- 出版者
- 北海道大学大学院教育学研究院教育社会学研究室
- 雑誌
- 『調査と社会理論』・研究報告書
- 巻号頁・発行日
- vol.36, 2020-03-25
1 0 0 0 OA 長期不登校児への認知行動療法的介入
- 著者
- 西村 勇人
- 出版者
- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 行動療法研究 (ISSN:09106529)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.1, pp.45-54, 2013-01-31 (Released:2019-04-06)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1
本研究では、母親と分離することや担任・クラスメイトに会うことに対して不安や恐怖感を抱き、5年間母親同伴で登校をしていた小6男児に対して認知行動療法的な介入を行った。本児の行動は母親からの分離行動の形成が不十分であること、母親からの注目獲得、担任やクラスメイトへの不安の回避という要因によって影響を受けていると考えられた。そのため、母親からの分離行動のシェイピングや学校関連刺激への段階的エクスポージャーを行った。その結果、小学校在学中に単独で授業に出席できるようになり、中学進学後は学校への全面復帰が可能となった。その後も病欠以外で連続欠席することなく2年生に進級することができた。この事例を通して、不登校の治療におけるエクスポージャーの有用性やさまざまな技法を組み合わせて介入することの必要性について論じた。
- 著者
- 名和 弘幸 山内 香代子 栁瀬 博 岡本 卓真 松野 智子 荒木 麻美 堀部 森崇 藤井 美樹 外山 敬久 藤原 琢也 後藤 滋巳 福田 理
- 出版者
- 一般社団法人 日本障害者歯科学会
- 雑誌
- 日本障害者歯科学会雑誌 (ISSN:09131663)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.4, pp.426-431, 2016 (Released:2017-06-30)
- 参考文献数
- 14
上顎第二乳臼歯の晩期残存と上顎第二小臼歯の異所萌出,上顎前突を呈する11歳9カ月の自閉スペクトラム症男児の治療について報告する.患者の発達指数は,遠城寺式・乳幼児分析発達検査においてDQ:59で,歯科治療に対する協力性は比較的良好であった.患児は5歳11カ月から医療福祉センターの歯科にて,歯科治療への適応向上のために定期的な口腔衛生管理を受けていた.最初の治療計画として,口腔衛生管理のため上顎第二小臼歯を正しい位置へ移動することとした.初期治療が問題なく完了し,患者が矯正歯科治療を希望した場合,上顎前突の治療のために矯正歯科を紹介する予定とした.スプリントを作製し,患者が口腔内に装置を装着できるかどうか確認するため,自宅で装着するように指示した.3カ月後,スプリントの着用時間が長くなったので,固定式矯正装置を作製し口腔内に装着した.7カ月後,上顎第二小臼歯は歯列に移動して,口腔衛生管理が行いやすくなったので,装置を取り外した.咬合誘導は良好な結果であり,患者と両親は上顎前突の改善も希望したので,矯正歯科へ依頼をした.矯正歯科受診時の患者の暦年齢および精神年齢は13歳0カ月と7歳8カ月であった.この症例報告より歯科治療への適応向上ができた自閉スペクトラム症児は,矯正歯科治療を始められる可能性が示唆された.
1 0 0 0 OA 学歴社会論再考 伝統的アプローチと制度論的アプローチ
- 著者
- 竹内 洋
- 出版者
- 北海道社会学会
- 雑誌
- 現代社会学研究 (ISSN:09151214)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.1-32, 1994-04-15 (Released:2010-07-27)
- 参考文献数
- 63
近代社会は雇用や地位達成において学歴が大きな規定力を持つ学歴社会である。では、なぜ学歴が地位達成におおきな比重を占めるのか。この問については技術機能主義や人的資本論、スクリーニング理論、訓練費用理論、葛藤理論など様々な説明がなされてきた。しかし、本論はこれらの伝統的アプローチに大きな欠陥があり、むしろジョン・マイヤー(John Meyer)をパイオニアとし、代表者とする制度論派の「教育論」(制度としての教育論)と「組織論」(制度的同型化論)を学歴主義の説明理論として読み直すことが重要という指摘をおこなっている。そこでまず複数の伝統的アプローチを整理するためにふたつの前提(メタ理論)から考察している。ひとつは学校効果についての前提(学歴の供給の理論)であり、それを社会化と配分に分類している。もうひとつは、雇用についての前提(学歴の需要の理論)であり、それを効率と統制に分類している。このふたつの前提を組み合わせることによって複数の伝統的な説明理論を整理するとともに、その欠陥が明らかにされる。そのあとに、学校効果と雇用の理論について異なった前提をおく制度論的アプローチの新しさと有効性を示している。最後にこうした制度論的アプローチを導きの糸としながら、日本社会における学歴主義の誕生と展開についての経験的研究の方向と可能性について若干の提言をおこなっている。
1 0 0 0 OA バーンスティンの教育ディスコース論の展開
1 0 0 0 OA 日本型選抜の探究 御破算型選抜規範
1 0 0 0 OA 教育改革と教育変動
- 著者
- 菊池 城司
- 出版者
- 日本教育社会学会
- 雑誌
- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, pp.38-49, 1986-10-15 (Released:2011-03-18)
1 0 0 0 OA 学歴の社会学 その理論的検討
- 著者
- 潮木 守一
- 出版者
- 日本教育社会学会
- 雑誌
- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, pp.5-14,en261, 1983-10-20 (Released:2011-03-18)
Sociology of Educational Credentials can be divided into two parts; the analysis of the educational attainment process and that of the status attainment process. Most previous researches have mainly focused on analyzing the effect of educational credentials on the process of individuals' status attainment. However, the process of educational attainment should not be neglected, because, without it, the sociology of educational credentials can not be perfect. As for the analysis of educational attainment, there are two main approach, the functional approach and the moral socialization approach. The functional approach takesthe educational attainment process as a process for an individual to acquire knowledge andskills which are needed in the industrialized society.Against that, the moral socialization approach takes the same process as an internalization process of value orientation which is prerequisite to maintain and reproduce the already established class system. It isan important contribution of radicals that they set up, not educational credentials which individuals have attained, but value orientation which individuals have internalized as a crucial product in the educational attainment process. However, radicals have not succeeded to analyze the dynamic process of moral socialization, and they are trapped by a simplistic and mechanic logic. They depend on the simple logic of one-to-one correspondence in exlaining the causal relationships among the social class system, the formation of sub-culture, the value internarization by the family as a socialization agent, the reinforcement bythe school system and the reproduction of the social class system. But More dynamic approach is needed for the more comprehensive understanding of the educational attainment process.
1 0 0 0 OA 「新しい教育社会学」その後 解釈的アプローチの再評価
- 著者
- 志水 宏吉
- 出版者
- 日本教育社会学会
- 雑誌
- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, pp.193-207,en285, 1985-09-30 (Released:2011-03-18)
- 被引用文献数
- 3
The aim of this paper is to re-evaluate the “New sociology of education.” In the 1970s, an academic movement called “New sociology of education” arose in England. What made the moment was Young's readings, Knowledge and Control. Young criticized the “traditional” sociology of education on two points:(1) It takes for granted the reality of schooling and the presuppositions which make it existing;(2) It devotes itself to extract the relationships between inputs and outputs, so that it sees the “process” of schooling as a blackbox. Then, grasping the school as a culture-transmitting agency, he asserted that we have to call the organizing principles of the school (not only on knowledge but also on students) in question.We can say that the main character of the “New sociology of education” is its application of the “interpretive approach” for schooling. Its origins exist in Schutz's phenomenological sociology and Mead's symbolic interactionism, and it sees schooling as the negotiation process between teachers and students. One uses participant observations, interviews, video-cameras to understand the reality of schooling.Criticisms against the “New sociology of education” are as follows: it overemphasizes the discontinuity with its tradition; it stands on super-relativism which puts values nowhere; it lacks the contact with the “structural” factors; its tecnique of data-analysis is unestablished and its findings are not suitable for generalization. Responding to these criticisms, the “New sociology of education” has been unfolding itself towards two directions: one direction that focuses on the micro process of schooling from the standpoint of symbolic interactionism and another direction that focuses on the macro constraint to the micro process from the standpoint of Marxism.In these circumstances, Willis's “Cultural reproduction theory” attracts our attention. Using the interpretive approach, it tries to reveal the interrelations between structural factors and interactional practices in a particular social setting. His study implies theoretical and methodological potentialities contained in the “New sociology of education” and its substance, that is, the interpretive approach.
1 0 0 0 OA 「マルクス主義教育社会学」の展望
- 著者
- 橋本 健二
- 出版者
- 日本教育社会学会
- 雑誌
- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.127-139,en308, 1984-09-30 (Released:2011-03-18)
The purposes of this paper are to outline Marxist approaches in the sociological study of education taken initiative by S. Bowles in 1971, to point out problems to be solved in them, and to find direction to overcome them.There are three major question in the theory of Bowles and H. Gintis:(1) Instrumentalist view of public educational institutions, (2) Underestimation of economic functions of them, (3) Overestimation of reproductive functions of them. They dealt with the problems of reproduction of capitalist mode of production as far as public educational institutions took part there, and failed to locate them in the whole processes of the reproduction. Furthermore, they regarded public educational institutions as instruments of ruling classes which they could operate arbitrarily. And they concentrated on only noneconomic, political and ideological functions of them.There have been many critiques of their theory. And some have been proposed attempts to overcome them in two directions:(1) integration of “micro” and “macro” sociology, (2) investigation of structural mechanisms and contradictions.Relative to the second direction, I try to locate “Marxist sociology of education” as a branch of the theory of the capitalist state. That is, “Marxist sociology of education” must, based on more general theories of the state and social classes, (1) analyse functions of public educational institutions as a part of the state, (2) investigate factors influencing these functions, (3) locate these functions in the whole processes of reproduction of capitalist mode of production including both economic and non-economic.
1 0 0 0 OA 産業化と学歴社会 その研究課題
- 著者
- 今田 高俊
- 出版者
- 日本教育社会学会
- 雑誌
- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, pp.21-26, 1983-10-20 (Released:2011-03-18)
- 参考文献数
- 6
1 0 0 0 OA 日本型「新しい」教育社会学の課題
- 著者
- 菊池 城司
- 出版者
- 日本教育社会学会
- 雑誌
- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, pp.57-66,en236, 1982-09-20 (Released:2011-03-18)
- 被引用文献数
- 1
With an attempt to typify in a rather sketchy fashion the recent trends of the sociology of education in Japan, the paper argues:(a) that the sociology of education in Japan has been in a state of transition, because, under the influence of the British “new” sociology of education, curriculaum, pedagogy and the forms of assessment have been brought into focus;(b) that, in spite of the preoccupation with the “new” sociology of education, the major technique of enquiry has been and still is the social survey, based upon a large population and using the closed questionaire;(c) that, as a result, there is neither drawing of the sharp line between “old” and “new” sociology of education, nor bold attack on the “conventional paradigm” that could hardly be ignored;(d) that the future development of the sociology of education may require widening the focus of the sociology of education, and less dependence on data processing and more dedication to data collection.
1 0 0 0 OA 知識配分と組織的社会化 「カリキュラムの社会学」を中心に
- 著者
- 柴野 昌山
- 出版者
- 日本教育社会学会
- 雑誌
- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, pp.5-19,en233, 1982-09-20 (Released:2011-03-18)
- 被引用文献数
- 4 2
The author presents a conceptual framework for the analysis of distribution forms of knowledge and “negotiation” processes between teachers and students in the school instead of a “black-box” view of schooling.The analysis based on the interpretative paradigm has several implications for the direction along which researchers should proceed. First, educational knowledge is, as B. Bernstein says, a major regulator of the structure of schooling experiences. Second, the hidden curriculum determines the mode of the transmission of educational knowledge and the forms of knowledge by which students are socialized in terms of the legitimation of symbolic control. Third, major implication of this idea is that this framework would give us a possibility of articulating micro- and macro-levels of analysis, if researchers concerned with sociology of schooling pay more attention to the organizational socialization processes regulated by the hidden curriculum, despite the relative lack of empirical studies under existing circumstances.
1 0 0 0 OA 海底鉱物資源開発に関わる環境調査と影響評価の現状と展開
- 著者
- 山本 啓之
- 出版者
- 資源地質学会
- 雑誌
- 資源地質 (ISSN:09182454)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.2, pp.79-95, 2019-12-16 (Released:2022-08-27)
- 参考文献数
- 108
- 被引用文献数
- 3
Deep-sea environments are faced with cumulative effects of many human activities, e.g. accumulation of plastics, overwhelming fishing and resource exploitation, heavy maritime transportation, and effects from climate change. Recently, growing interest in deep-sea mining enhances the activities of engineering development on seabed mining and environmental monitoring, and exploration of mining sites within States Exclusive Economic Zones (EEZ) or in areas beyond the limits of national jurisdiction. Since 2010, attention paid to potential environmental impacts caused by deep-sea mining has been increased, and many workshops and research conferences have been held. In the Western Pacific Ocean, the Nautilus Minerals Ltd. has announced that the sea mound located in Papua New Guinea will be a first site likely to be commercially exploited polymetallic sulfide deposit. The Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC) conducts a feasibility project for seabed mining in the Okinawa Trough. In 2015, the leaders’ declaration from the G7 summit in Germany identified the conducting of Environmental Impact Assessment (EIA) and scientific research as a priority issue for sustainable development of deep-sea mining. The EIA protocol developed for deep-sea mining is recognized that it will be a practical component for ensuring effective management and protection of ocean ecosystems. The development of EIA protocols is started in Japan as a national project. This paper describes the current situation of technologies concerning deep-sea environmental assessment and monitoring on seabed mining, and technical background of multidisciplinary approaches for deep-sea environmental survey.
1 0 0 0 OA 意向把握義務と推奨販売における顧客の意向 —顧客のニーズに合った商品が販売されるために—
- 著者
- 山本 啓太
- 出版者
- 公益財団法人 損害保険事業総合研究所
- 雑誌
- 損害保険研究 (ISSN:02876337)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.3, pp.81-109, 2016-11-25 (Released:2019-04-09)
- 参考文献数
- 3
平成26年の保険業法改正によって意向把握義務及び乗合代理店等に対する推奨販売ルールが導入された。これは来店型保険ショップ等の増加といった保険募集チャネルの多様化や大型化など,保険募集を巡る環境の変化に対応できるようにするための見直しとのことである。確かに,適合性原則の具体化を論ずる中で導入された意向確認書面はその本来の機能を果たしておらず,また,来店型の大規模乗合代理店の中には,「公平・中立」を標榜しながら,実際には手数料の高い商品を顧客に勧めるという現状は改善の必要がある。この点,今回導入された意向把握義務及び推奨販売ルールは,いずれも顧客の意向に焦点を当てたものであるが,そこでいう意向,言い換えれば,顧客のニーズがどのようなものをいうのかについて,十分な議論がなされていないように思われる。 保険業法上,「意向」という用語は,意向確認書面において初めて使われたものであるので,まずは意向確認書面導入時に「意向」というものがどのように議論されていたのか,意向確認書面において確認すべき「意向」と意向把握義務において把握すべき「意向」が同一でよいのか,更に,意向把握義務でいう「意向」と推奨販売ルールにおける「顧客の意向に沿った商品選別・推奨」でいうところの「意向」との関係はどのように整理されるべきなのか,について分析することとしたい。 最後に,施行されたばかりではあるものの,意向把握・確認義務及び推奨販売ルールの再整理の方向性についても考えてみることとしたい。
1 0 0 0 肩をすくめるアトラス
1 0 0 0 小胞体関連タンパク質によるミトコンドリア分解の制御機構
1 0 0 0 OA 紅葉おろしのビタミンC
- 著者
- 林 宏子
- 出版者
- 一般社団法人 日本調理科学会
- 雑誌
- 調理科学 (ISSN:09105360)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.4, pp.361-366, 1990-11-20 (Released:2013-04-26)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 3
1 0 0 0 OA 埼玉県秩父市荒川白久地区における天狗祭りの再生と中断
- 著者
- 貝沼 良風
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集 2017年度日本地理学会秋季学術大会
- 巻号頁・発行日
- pp.100143, 2017 (Released:2017-10-26)
<はじめに>地域では様々な祭りが執り行われているが,そうした祭りの多くは,地域社会との強い結びつきのもとにあるといえよう.これまで祭りと地域社会との関係に関しては豊富な研究蓄積がみられる.中でも地理学の研究に目を向けると,たとえば,古田(1990)は,新住民の流入により,祭りの意味が伝統的な行事から子どものための行事へと変容したことを明らかにしている.また,平(1990)は,地域社会において祭りの担い手が不足する中,祭りを執り行うスケールを広域化することで,祭りが維持されることを示唆した.こうした祭りと地域社会との関係をめぐる研究では,主として存続している祭りに焦点があてられてきた.しかし,地域社会が変容する中,そうした変容に適応し,存続する祭りがある一方で,中断や消滅に至った祭りも多く存在する.そのため,今日における祭りと地域社会の関係をより詳細に理解するためには,そうした祭りにも目を向ける必要があるだろう.<BR> そこで本研究は,地域社会の変容により中断したものの,再生され,再度中断に至った祭りを事例とし,従来と再生後の祭りの比較を通じ,祭りと地域社会の関係を考察することを目的とする.具体的には,秩父市荒川白久地区の天狗祭りを対象とする.<BR> 本研究で使用するデータは,実行委員長をはじめとする天狗祭りの中心人物や,荒川白久地区の住民10名に対して実施したインタビュー調査により収集した.また,従来の天狗祭りの郷土資料やフィールド調査で得られた情報も分析に使用する.なお,本研究では,荒川白久地区の中でも,天狗祭りの再生において中心的な役割を担った後述の上白久町会に特に注目する.<BR><対象地域と地域住民組織の概要>本研究の対象地域である荒川白久地区は,2005年に秩父市に編入された旧荒川村の一部で,中山間地域として特徴付けられる.2015年の国勢調査によると,人口は846人で,高齢化率は41.1%と,高齢化の進んだ地域といえる.荒川白久地区では,40から70世帯ごとに集落区という地域住民組織が編成されている.同地区にはこの集落区が7つ存在する.他方で,上述の編入合併の際に,2から3の集落区をまとめた,町会という地域住民組織が新たに設けられた.<BR><天狗祭りの再生と中断>天狗祭りは,山の神をやぐらに迎え入れ,やぐらを燃やすことで山へと返すという儀礼的な意味を持つ民俗行事で,小・中学生の男子が中心となって,毎年11月に開催されていた.従来,同祭りは旧荒川村の集落区ごとに執り行われてきたが,中でも原区という集落区のものは,埼玉県の無形民俗文化財に登録されている. 1960年代頃になると,同祭りは夜遊びや火遊びとして捉えられるようになり行われなくなっていった.1970年代以降は上述の原区でのみ継続されていたが,同区でも2011年を最後に休止となった.<BR> そうした中,2015年に地域住民の呼びかけにより天狗祭りが再生された.その際,従来の集落区ではなく,より広域な地域住民組織である町会において祭りが執り行われた.しかし,住民の一部から祭りに対する異論が投げかけられ,翌年,天狗祭りは再度中断となった.<BR> 再生された天狗祭りは,祭りの意味や活動内容が従来のものとは異なる点が多くみられた.従来は,主に子どもたちを中心に集落区を単位に行われていた.また,祭りに必要な諸経費は住民からの灯明料によって賄われていた.しかし,再生された天狗祭りは,60から70歳代の住民を中心に,町会を単位に実施された.そして,諸経費は,灯明料ではなく,有志の住民からの協賛金というかたちの寄付で賄われた.また,従来の天狗祭りでは,祠への参拝をはじめ,神事に関わる活動が重視されたが,再生された天狗祭りでは宗教色が極力排除され,地域内外の人々の交流が重視された.その重視する点の違いから,開催場所も人家から離れた場所から,住宅地付近へと変更された.天狗祭りの再生において,祭りを執り行う単位が集落区からより広域な町会となったことは,結果として祭りの再生に賛同し活動に参加する地域住民を集めやすくなったといえる.地域住民からは,再生された天狗祭りに対して懐かしいという声がきかれた一方で,内容や開催場所が従来とは異なることや,火を炊くことに対して否定的な声もきかれた.<BR><まとめ>天狗祭りは,祭りを執り行う単位の広域化や子どもが不在でも実施可能なものへと内容が変更されたことで,一度中断したものの,再生まで至ることができた.しかし,神事であることや子どもが主体といった従来,住民が重視していた点が失われたことで,当時の様子を知る住民が少なくない中,地域社会が一枚岩となって祭りを支えることはできず,新しいかたちの天狗祭りは継続することはできなかったと考えられる.