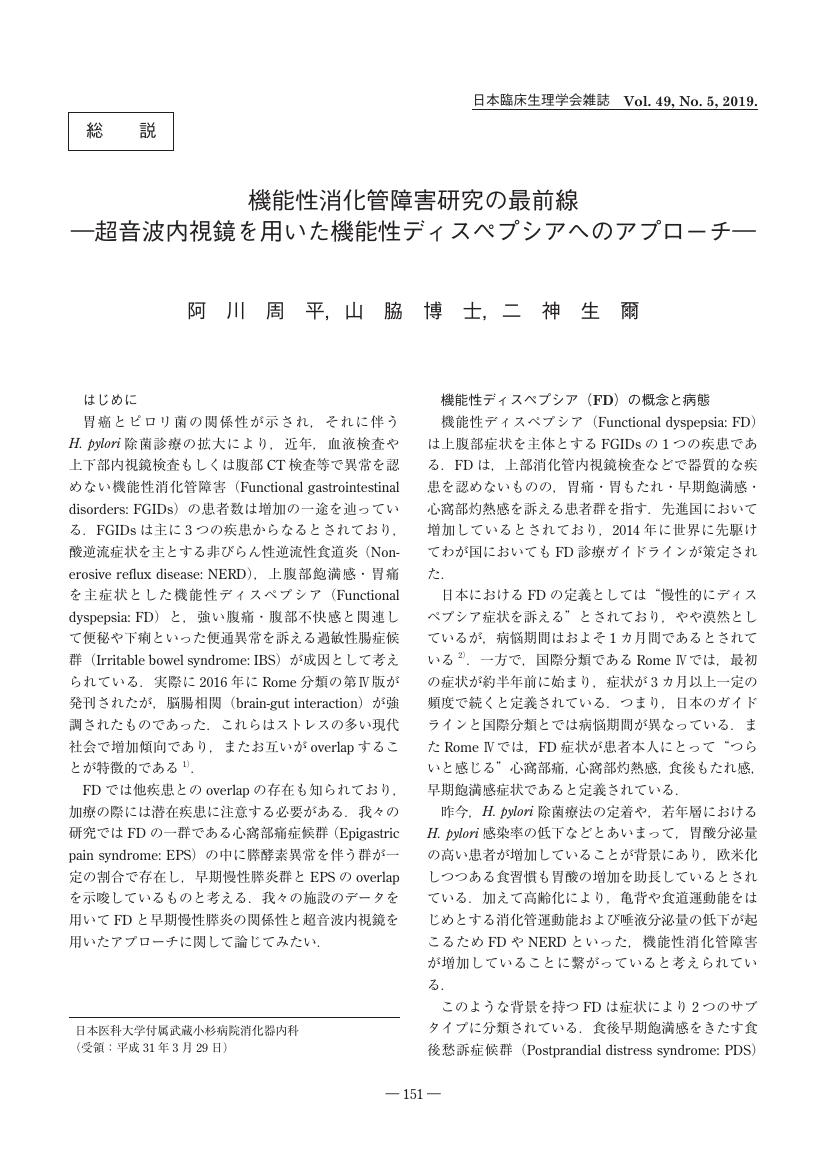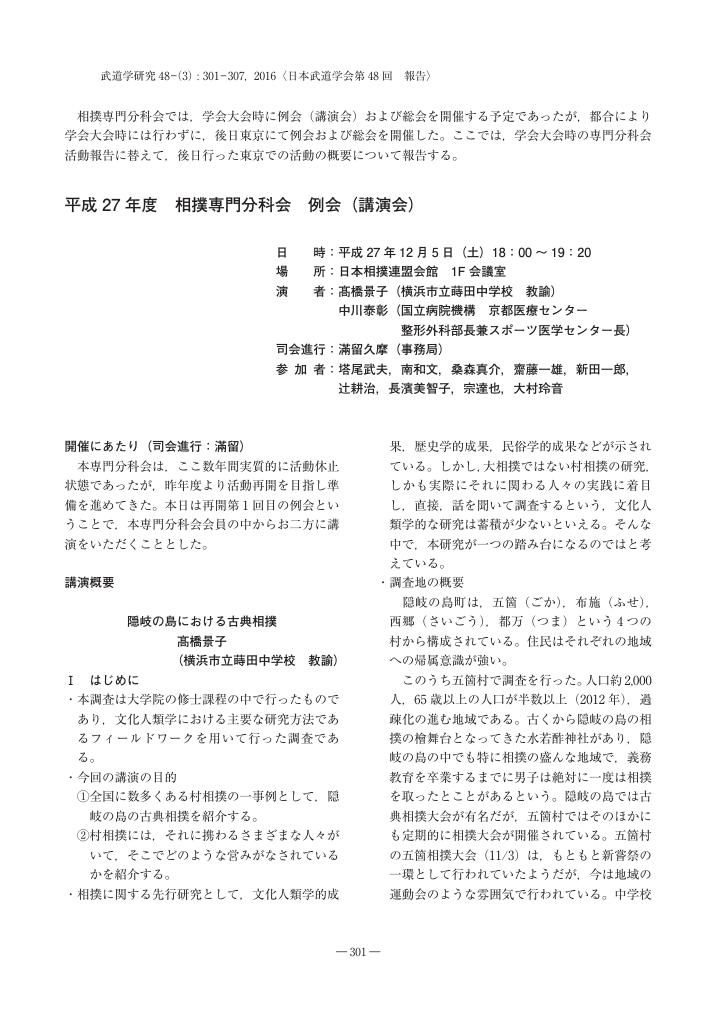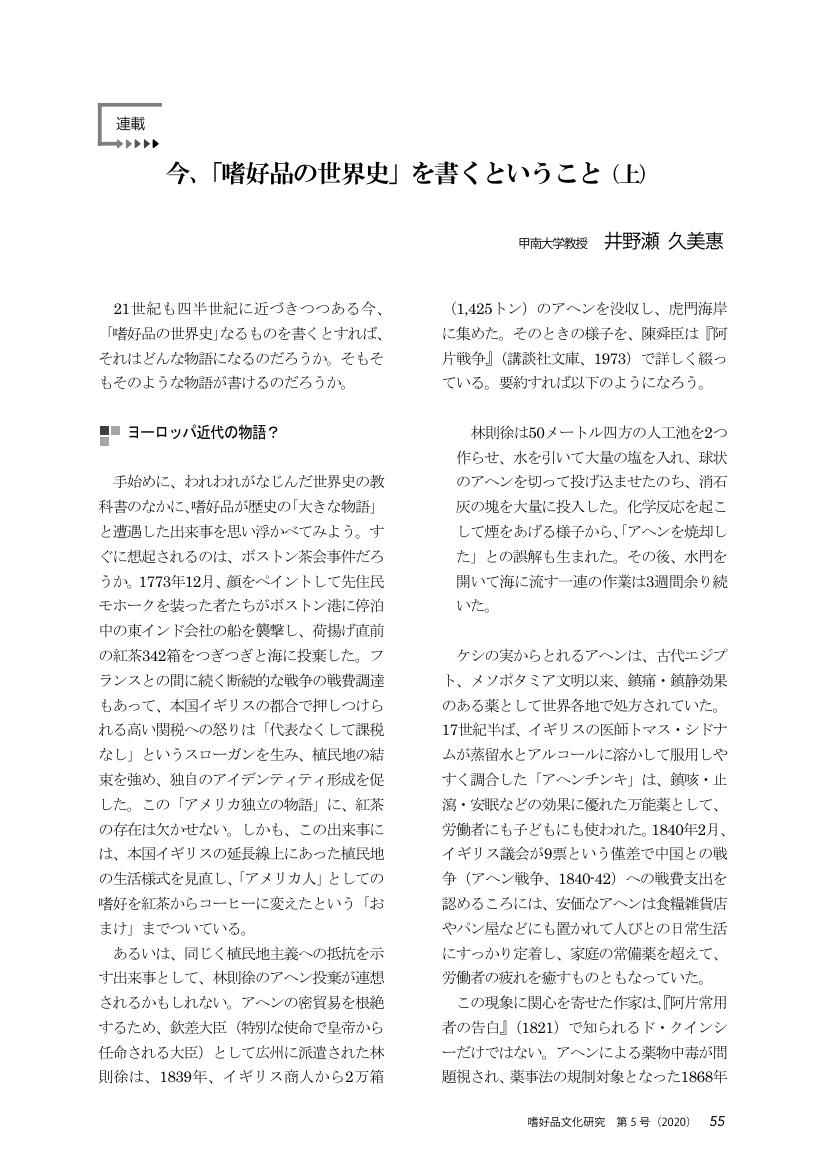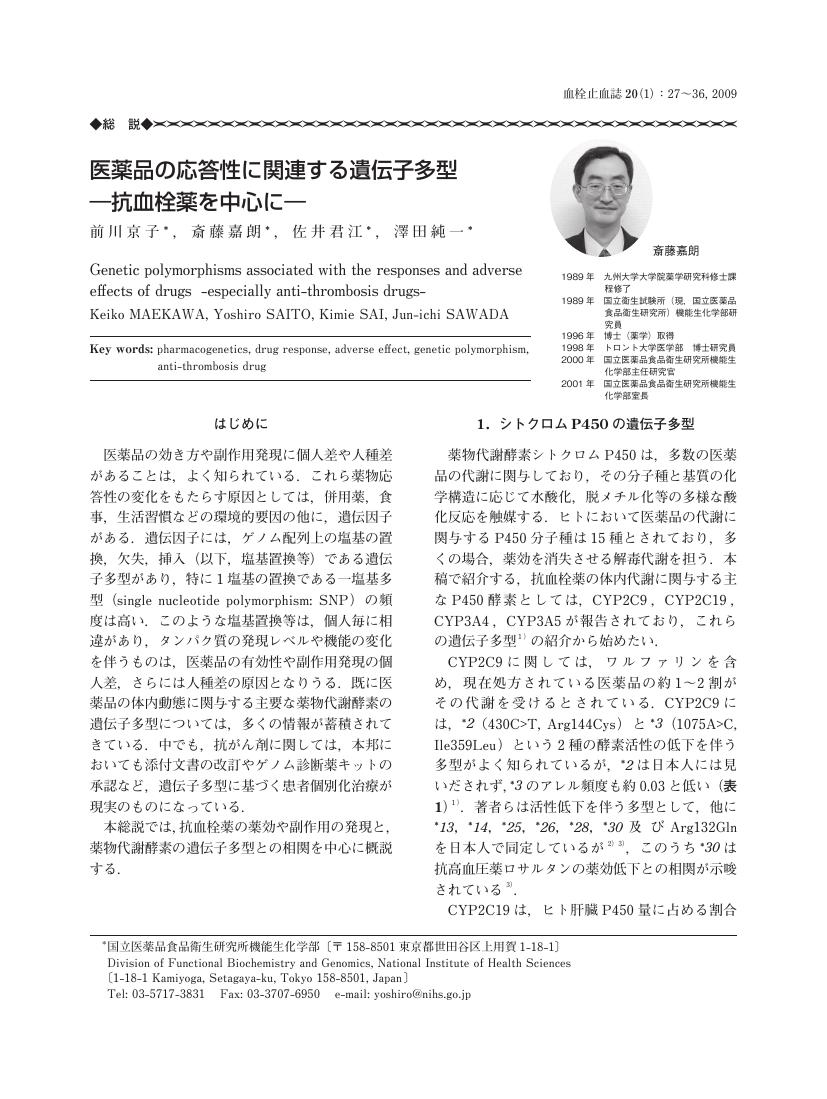1 0 0 0 OA 戦後日本における保育者のライフヒストリーに関する研究
1 0 0 0 幼児教育学研究
- 著者
- 日本幼児教育学会 [編]
- 出版者
- 日本幼児教育学会
- 巻号頁・発行日
- 1994
1 0 0 0 東京体育学研究
- 著者
- 日本体育学会東京支部 [編]
- 出版者
- 日本体育学会東京支部
- 巻号頁・発行日
- 1974
- 著者
- 佐々木 睦史 石川 善美 内海 康雄 小林 仁
- 出版者
- 公益社団法人 空気調和・衛生工学会
- 雑誌
- 空気調和・衛生工学会大会 学術講演論文集 平成12年 (ISSN:18803806)
- 巻号頁・発行日
- pp.629-632, 2000-08-10 (Released:2017-08-31)
- 参考文献数
- 4
1 0 0 0 OA スプリンターネットを巡る議論
- 著者
- 実積 寿也 前村 昌紀 白畑 真 堀越 功 小宮山 功一朗 水越 一郎
- 出版者
- 一般財団法人 情報法制研究所
- 雑誌
- 情報法制レポート (ISSN:24356123)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.52-71, 2023-03-31 (Released:2023-08-29)
1 0 0 0 OA 機能性消化管障害研究の最前線 ―超音波内視鏡を用いた機能性ディスペプシアへのアプローチ―
- 著者
- 阿川 周平 山脇 博士 二神 生爾
- 出版者
- 日本臨床生理学会
- 雑誌
- 日本臨床生理学会雑誌 (ISSN:02867052)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.5, pp.151-154, 2019-12-01 (Released:2020-03-06)
- 参考文献数
- 14
- 著者
- 井濃内 歩 井出 里咲子
- 出版者
- 言語文化教育研究学会:ALCE
- 雑誌
- 言語文化教育研究 (ISSN:21889600)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.61-81, 2020-12-28 (Released:2021-04-14)
- 被引用文献数
- 1
本研究は,国内で急増する留学生とその家族が地域社会で参入する「公共空間」の一つ,保育園をフィールドに,保育園と外国人保護者とのコミュニケーション課題の実態を報告するものである。社会的文脈と不可分の動的実践として「ことば」をまなざす言語人類学の立場から,外国人保護者と園の対話を阻むものとして語られる「ことばの壁」が,相互理解には「英語」か「日本語」という共通「言語」が不可欠だとする言語イデオロギーや,わかってほしい事柄のすれ違いにより,双方に「わかりあえない」という観念が形成されている状態であることを論じる。課題解決の糸口として,現場の「ことば観」を解きほぐし,多様なコミュニケーション資源を柔軟に駆使した対話とかかわりあいの仕掛けづくりへの提案を行う。さらに,課題を抱える公共空間に調査者が「入る」こと,呼びかけに応答し,人々の声を聴くことそのものが,フィールドの変容とその協働的な再創造に繋がる可能性について考察する。
1 0 0 0 OA 反芻家畜における卵巣嚢腫の発生機構
- 著者
- 川手 憲俊
- 出版者
- 公益社団法人 日本獣医師会
- 雑誌
- 日本獣医師会雑誌 (ISSN:04466454)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.2, pp.79-84, 2001-02-20 (Released:2011-06-17)
- 参考文献数
- 49
- 被引用文献数
- 4 3
1 0 0 0 ハンナ・アーレントの「難民」論の現代的受容と可能性
- 著者
- 二井 彬緒
- 出版者
- 東京大学
- 雑誌
- 研究活動スタート支援
- 巻号頁・発行日
- 2023-08-31
1 0 0 0 OA 保育学研究の現状と展望(連載企画:専門分野の最前線と研究動向)
- 著者
- 無藤 隆
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.3, pp.393-400, 2003-09-30 (Released:2007-12-27)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1
本論では,幼稚園・保育所(以下,「幼稚園」と総称する)における実践と,保育・幼児教育(以下,「保育」と総称する)の研究を巡って,その特質と現状を整理したい.ただし,第一に,日本の保育のあり方に即すること,第二に,その保育の実態と改善に資するということ,第三に,保育の研究の詳細ではなく,日本の保育を律しているであろう「原則」の抽出を目指すことを行いたい.
1 0 0 0 OA 平成27年度 相撲専門分科会 例会(講演会)
1 0 0 0 OA 謎の中華料理 油淋鶏
- 著者
- 増子 保志
- 出版者
- 日本国際情報学会
- 雑誌
- Kokusai-joho (ISSN:24364401)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.1, pp.3-9, 2017-07-02 (Released:2023-07-24)
Chinese food in our country has Chinese food Japanese style which was uniquely arranged, notauthentic Chinese, including “Hatupousai” and “Chyukadon”. One of them is ”Yurinchi”. This is servedas one of the Chinese cuisine very commonly, such as a Chinese restaurant in the street and a pub.Because of its convenience, it receives the impression that it is cook arranged in a Japanese style.Also, many home-cooked recipes exist that are arranged in a Japanese style, and have become popular ingeneral, and ”Yurinchi” are recognized as one of the Chinese cuisines for most Japanese.However, in the media, there are many discourses that are regarded as a cuisine originating in China.However, in China, which is said to be home-grown, it is almost impossible to see restaurants andrecipes for home-cooked dishes at all. Even asking the chef of Cantonese cuisine, only ambiguousanswers such as whether it is Taiwanese food rather than Cantonese cuisine can only be obtained. Alsoin books of household dishes published in Hong Kong and Taiwan, there is no descriptionabout ”Yurinchi”, and that description is not found in special cookbooks.However, naming and pronunciation are in Chinese. If so, when and where was the ”Yurinchi”, how wasit brought to Japan? Is it really a dish derived from China?
1 0 0 0 OA 脳室内血腫に対する神経内視鏡下血腫除去術と脳室ドレナージ術の比較
- 著者
- 高砂 浩史 小野 元 伊藤 英道 大塩 恒太郎 田中 雄一郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本脳卒中学会
- 雑誌
- 脳卒中 (ISSN:09120726)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.5, pp.313-318, 2016 (Released:2016-09-23)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 6
【目的】水頭症を伴う脳室内血腫に対する治療として脳室ドレナージ(EVD)が一般的であるが,神経内視鏡を用いた脳室内血腫除去術の有用性と安全性をEVD 単独治療との比較により検討する.【方法】2010 年から2014 年までの水頭症を伴う脳室内出血28 例中,EVD 単独治療の9 例と神経内視鏡下血腫除去とEVD を行った9 例を対象とした.年齢,GCS,脳室内血腫量,EVD 留置期間,離床でのリハビリテーションまでの期間,在院日数,シャント術の必要性,合併症,退院時予後について検討した.【結果】EVD 留置期間と離床でのリハビリテーション導入までの期間は神経内視鏡治療群で有意に短かった.内視鏡治療はより重症例に適用されていたが,退院時の転帰に有意差がなかった.【結論】内視鏡下脳室内血腫除去術はEVD 留置期間を短縮もしくは不要にし,本格的なリハビリの導入期間も早まる.そこで神経学的予後の改善が期待される.
1 0 0 0 OA 物理量や単位の表記について(教科書の記述を考える 14)
- 著者
- 佐藤 直樹
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 化学と教育 (ISSN:03862151)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.9, pp.569-573, 1998-09-20 (Released:2017-07-11)
- 参考文献数
- 2
- 被引用文献数
- 1
自然科学では量の関係を重んじる。その自然科学の柱の一本をなす化学でも, 物理量や単位などの表記はけっして枝葉末節の問題ではなく, ときには理解の本質に深く関わってくる。おもに「化学IB」の教科書をそんな目で見ると, どんどん使っていくべき国際単位系(SI)への対応が実質的にはほとんど図られていないように思える。ここはぜひ, 単位系の技術的な側面だけにとらわれることなく, むしろその思想や基礎概念について勘案しながら手直しを始める必要があろう。このように考える立場から広い議論が湧くことを期待して, 教科書中で目にとまった気になる表記や記述について, その具体例のいくつかを指摘したい。
- 著者
- John Coleman
- 出版者
- Bridger House Publishers Inc
- 巻号頁・発行日
- 1992
1 0 0 0 OA 今、「嗜好品の世界史」を書くということ(上)
- 著者
- 井野瀬 久美惠
- 出版者
- 嗜好品文化研究会
- 雑誌
- 嗜好品文化研究 (ISSN:24320862)
- 巻号頁・発行日
- vol.2020, no.5, pp.55-65, 2020 (Released:2022-07-29)
- 著者
- Jin-Ho Park
- 出版者
- ARCHITECTURAL INSTITUTE OF JAPAN (AIJ), ARCHITECTURAL INSTITUTE OF KOREA (AIK), ARCHITECTURAL SOCIETY OF CHINA (ASC)
- 雑誌
- Journal of Asian Architecture and Building Engineering (ISSN:13467581)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.1, pp.25-30, 2005 (Released:2005-07-30)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 4
This paper first discusses the fundamental notion of shape morphing and morphing techniques. Then it sets out to introduce early applications of the notion in architecture. Antoni Gaudi′s Sagrada Familia Cathedral in Spain and Le Corbusier′s Firminy Chapel in France are examined with regard to shape morphing. The examination seeks to cast new light on the significance of the two designs whose morphing method has become the legacy of an innovative characteristic of considerable contemporary architecture.
1 0 0 0 OA 非可換確率論における独立性と無限分解可能分布
- 著者
- 長谷部 高広
- 出版者
- 一般社団法人 日本数学会
- 雑誌
- 数学 (ISSN:0039470X)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.3, pp.296-320, 2018-07-25 (Released:2020-07-26)
- 参考文献数
- 82
1 0 0 0 OA 医薬品の応答性に関連する遺伝子多型 ―抗血栓薬を中心に―
- 著者
- 前川 京子 斎藤 嘉朗 佐井 君江 澤田 純一
- 出版者
- 一般社団法人 日本血栓止血学会
- 雑誌
- 日本血栓止血学会誌 (ISSN:09157441)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.1, pp.27-36, 2009 (Released:2009-05-13)
- 参考文献数
- 35